解説記事2007年09月10日 【巻頭特集】 本年6月総会の動向と今後の株主総会への影響(2007年9月10日号・№226)
株主提案の増加等にいかに対処するか
本年6月総会の動向と今後の株主総会への影響
日本シェアホルダーサービス取締役会長
三菱UFJ信託銀行(証券代行部門)理事 中西敏和
本年6月総会は、3月期決算会社においては会社法が全面的に適用された最初の定時株主総会となった。また、買収防衛策や配当に係る議案について、投資ファンド等の株主から修正提案や増配提案がなされる動きが顕著にみられるなど、その様相は昨年と比較しても一変した。本稿では、本年6月総会の概況、近時の環境変化が及ぼす影響とともに次期総会への対応をまとめていただいた。(編集部)
Ⅰ はじめに
会社法が昨年5月1日に施行されたが、計算書類の作成・監査等の手続については、施行後に決算期が到来するものから順次会社法を適用することとしたため、3月期決算会社にとっては、本年6月総会が会社法適用のもとでの最初の定時株主総会となった。
また、前年6月総会については、招集決定の取締役会との関係で総会手続が旧商法に基づいて行われた会社があるなど対応が分かれたが、このような会社も含めて3月期決算会社すべての株主総会が会社法全面適用という同一条件のもとで行われることになった。
その結果、会社法の全面適用にいかに対応するかということが、担当者にとって最大の関心事であったということができる。
これに加えて、前年6月総会では、15社において会社提案議案が機関投資家等の反対にあって否決または撤回されるということが関心を集めたが、本年6月総会に先立って、東京鋼鐵で会社が提案した株式交換契約承認議案が投資ファンドの反対にあって否決されたり、投資ファンドを中心に株主提案の動きが続発することにより(表1参照)、本年6月総会に向けて、株主対応の重要性に対する認識が一層高まり、総会準備に大きな影響を及ぼすことになった。その典型的なものは、会社が行おうとした敵対的買収防衛策を巡って訴訟にまで発展したブルドックソースの事例であろう。
以下、会社法全面適用のもとでの最初の6月総会について、以上のような背景を踏まえて振り返りながら、来年総会に向けた対応を提示することとする。
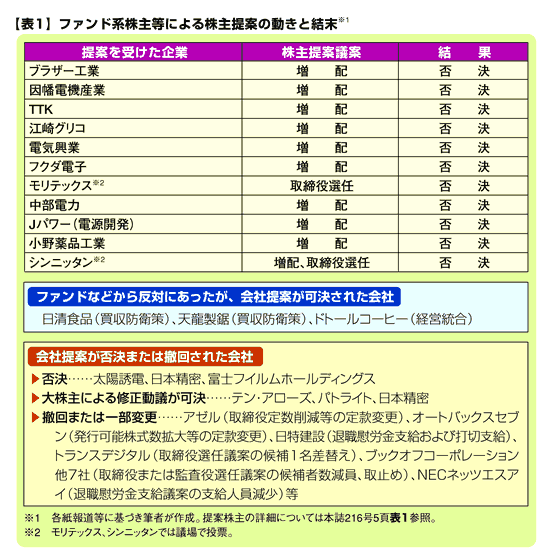
Ⅱ 会社法の全面適用による総会への影響
1 会社法全面適用下の総会準備手続 会社法は、計算書類について、利益処分(または損失処理)案を廃止し代わって株主資本等変動計算書等を加えるとともに、従前の営業報告書を事業報告に改め、計算書類から外し、記載事項を大幅に拡充させた。
事業報告については、新しく記載事項として追加された社外役員や内部統制システム、すべての会社に記載が求められることになった役員報酬の記載の仕方をめぐって議論がなされた。
とりわけ社外役員に関する記載事項については、参考書類の追加記載事項でもあるところから、主要活動状況の記載、兼務先における不当・不正な業務執行があった場合における予防措置、事後対応に関する記載については、社外役員が高名な方であればあるほど該当する機会が多くなりやすいところから、記載にあたっては、兼務先との調整を含め、頭を悩ませたものと思われる。
招集通知添付書類の見直しや記載事項の充実は、招集通知の膨大化を招くことになり、印刷・製本から郵送に付すための封入作業といった事務手続にも大きな問題を投げかけた。これまで招集通知については、郵便料金等との関係から、定形郵便物を意識したサイズにほぼ統一されていたが、記載事項の大幅な増加は、これを維持することに対して限界を感じさせることになったからである。
ダイナシティ等一部の会社にみられたが、今後は、会社法で認められたホームページへの掲載(WEB開示)による一部事項の招集通知への記載の省略が、改めて議論されよう。大半の会社がこれに必要な定款変更手続を昨年6月総会で済ませていたが、本年6月総会においては判明しているところで3社が実施するにとどまっている。
他方、招集通知の開示書類としての重要性を踏まえ、エーザイのように、これまでの郵送料金を意識した定形郵便物という制約から脱却し、サイズを大きくして開示書類としての機能を充実させる例もみられた。招集通知の開示機能という役割をどう考えるかという開示全体を含めた問題であり、今後検討が必要と思われる。
2 会社法全面適用下の総会運営 招集通知添付書類の見直しや記載事項の充実は、総会シナリオや想定問答にも大きな影響を及ぼした。
膨大化した事業報告や計算書類をこれまでの延長線上で考えると、総会冒頭の報告事項のところでいたずらに時間を費やすことになる。また、説明義務という観点からも範囲が広がることが予想され、そのぶん想定問答も分厚くなることになる。
総会シナリオについては、株主資本等変動計算書を省略したり、事業報告を一部割愛するといった見直しが行われたようであるが、長時間化の一因となったことは事実である。
他方、説明義務については、後述するとおり、出席株主の増加(表2参照)と変化を踏まえ、従来のような法律を厳格に運用するという考え方から、株主の満足度を重視し、説明することが適切でないと判断される事項を除き、できるだけ回答するという方針をとる会社が増加している。
表3のとおり、総会全体の長時間化の傾向が今年も顕著であるが、この傾向は避けられないとしても、株主への満足度という観点からは、質疑応答に時間を割く方が望ましい。今後は、総会のナレーション化ということも含めて、思い切った見直しが引き続き望まれるところである。
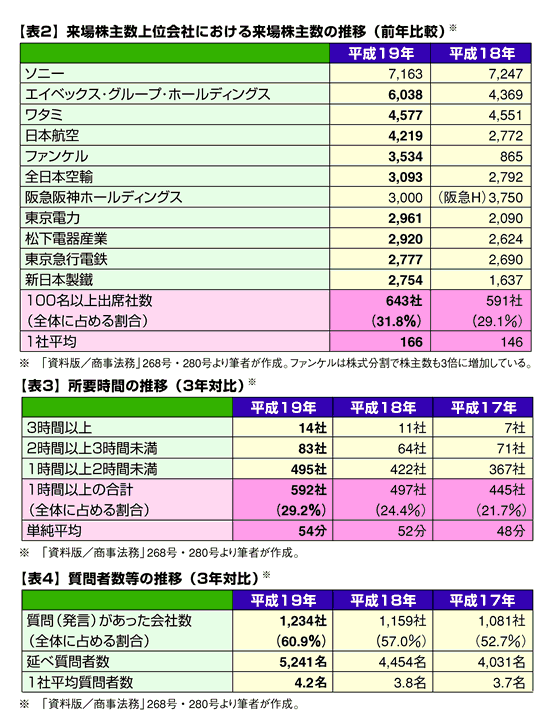
3 総会電子化の進捗状況 会社法は、従来からある招集通知の電子化、議決権行使の電子化に加え、WEB開示を利用した招集通知の一部記載事項の省略や、招集通知記載事項の修正の通知を認めている。
招集通知の電子化については、メリットが不明確であるところから、いまだ進展はみられないが、議決権行使の電子化については、インターネットを利用する方法が確立されており、徐々にではあるが増加傾向がみられる。
さらに、機関投資家の議決権行使の促進という観点から、ICJのプラットフォームを利用する会社が増加している。その前提としてインターネットを利用した議決権行使を認めていることが必要であるところから、これと歩調を合わせる形で今後も着実に増加するものと思われる。
他方、WEB開示の利用については、既に述べたとおり、招集通知の記載事項の省略という点ではわずかな利用にとどまったが、招集通知に誤植等の修正事項が生じた場合の通知手段としてのWEBの利用については、これに備えた招集通知への記載はほぼ全社が行っている点で十分定着したとみることができる。
Ⅲ 総会を巡る近時の環境変化と総会への影響
1 株主構成の変化に伴う総会運営への影響 株主総会への個人株主の参加意識はここ数年、引き続き高まる傾向にある。
来場株主という点からみても、いろいろな意味で知名度を高めた会社を中心に、来場株主数を増加させている。また、発言株主という観点からみても、発言があった会社の6月総会会社全体に占める割合は、引き続き増加傾向にある(表4参照)。
このような、総会への出席・発言を中心とした個人株主の活発な動きに対し、機関投資家の動きは引き続き会社提案に対する反対票という形で行われており、その基準は、原則として自ら示した議決権行使基準をもとに行われる。
本年はこれに加えて、前掲・表1のとおり、投資ファンドを中心に株主提案という形で自らの考えを示し、場合によっては委任状勧誘により賛成票を集める動きすら出始めた。
現在のところ、増配提案が中心となっているが、その背景には会社法による配当に対する考え方の変化が感じられるところである。
すなわち、配当についての株主への示し方が、これまでの利益の処分という見せ方から、剰余金の処理という見せ方に変更されており、会社としてはこれを意識して配当政策の決定に関する方針を明確に打ち出すことが今後望まれるところであろう。
2 会社法による付議議案への影響 ここ数年、役員報酬体系の見直しが盛んに行われている。
その中心は、役員退職慰労金の廃止または打切りとなって現れているが、会社法の施行に伴い、役員賞与の取扱いについても議論が活発化した。その引き金となったのは利益処分案の廃止であり、これに伴い役員賞与は独立した議案として付議することが必要となるからである。
ただし、役員退職慰労金および役員賞与を廃止すると、その代替手段として定例報酬の増額を行うとすれば、定例報酬枠の増額の要否が問題となってくる。このような対応を行った会社は少なくないが、役員賞与や退職慰労金の廃止に伴い、ストック・オプションも含めた報酬体系全体の見直しを行う会社が少なくないのも本年総会の大きな特徴である。
付議議案という点で、今年大きな変化がみられたのは、敵対的買収に対する防衛策を総会に付議する動きである。
最近の事例にみられるごとく、敵対的買収が仕掛けられる会社の範囲が広がっており、関心が高まっている。また、会社法では、事業報告の記載事項として、会社の「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を定めている場合にその記載を、さらに支配に関する方針を侵す者が現れた場合の対応策を定めている場合にその記載を求めているが、これに触発されて、対応策の実施を含め検討を行ったところも少なくない。しかし、一部の会社では、支配に関する方針とそれに対する取組みについてだけ記載するところもあり、こういった考え方を積極的に示していくところから始めても遅くはない。
3 個人株主を意識した総会運営 既に述べたとおり、個人株主の総会への出席は年々増加傾向をたどっている。もちろんすべての会社に共通する現象ではないが、従来から比較的出席株主数が多いとされている会社ほど増加率は高く、全体的には二極化の傾向が強まっている。
ただし、最近の総会に出席する層を注意深くみると、団塊の世代といわれるリタイア組を中心に、会社経営に関して一定の知識水準に達した株主の出席が目立つ。このような株主は、質問もさることながら、議長や答弁担当役員の説明にも熱心に耳を傾ける光景がみられ、総会全体の雰囲気を盛り上げるのにも大きく寄与している。
ここ数年、このような株主に対してわかりやすい説明が試みられており、その手段としてビジュアル化も進んでいる。今後は、このような出席株主を長期安定的な株主とするための工夫が試みられるものと思われる。総会開催日の分散化とともに、会場の選択という面でも株主の利便性向上が試みられるのも、その現れであろう。
Ⅳ 来年総会に向けての課題
本年総会は、会社法全面適用への対応が重要課題となったが、逆にこれをもって一応の定着をみたものと思われる。そして、本年の事例分析を来年総会に向けて活用することによって、本年問題とされた事項も終息を迎えるものと思われる。
他方、一層その必要性を意識させたのは、活発化する株主の把握という問題である。特に株主構成は各社各様であるため、会社法への対応のように他社事例をうのみにするわけにはいかず、きめ細かな対応が必要となる。
まず、機関投資家について必要なのは、議決権行使に及ぼす影響度合の早い時期での読みとそれに応じた対応策の立案である。
ただ単に議決権行使比率の向上を図り、議決権の空洞化を回避するということだけを目的とするのであれば、個々の機関投資家の把握ということまでは必要ないものと思われる。WEBを利用した早期の招集通知等の開示とICJが開設するプラットフォームの利用でも相応の成果は得られる。
しかし、機関投資家の議決権の行方が決議の成否に影響を及ぼす程度にまで達すると、企業年金連合会といった機関投資家や主要な運用機関、外国人投資家へのアドバイスを行うISSといった助言機関への個別説明等の実施が必要となる。
そして、決議の成否の行方が極めて不透明な段階にまで至ると、名義の背後にある個々の機関投資家を明らかにし、直接コンタクトをとることも考えるべきであろう。そのためには専門の調査機関を利用して判明調査を実施する必要がある。いずれの方法をとるにせよ、早い時期に状況を把握する必要がある。
会社法の全面適用とともに、実務で問題となったのは、株主総会そのものに対する考え方であろう。
ここ数年、総会における発言株主の増加とともに、機関投資家の反対票という形での積極的な議決権行使は、招集通知作成といった事務レベルの問題とは別の意味で重要性を増しているが、昨年15社で会社提案が否決されたことは、本年総会に向けて大きな問題を投げかけることになった。併せて、本年5月1日から可能となったいわゆる三角合併は、昨今活発化したTOBを中心とする企業買収に拍車をかけることが予想されるところから、敵対的な企業買収に対する防衛策に大きな関心を集めた。そして、これにさらなる追打ちをかけるような、投資ファンドを中心とする増配提案の増加である。
会社法は総会実務に大きな影響を及ぼしたが、それとともにそこで導入された市場主義という考え方は、総会のあり方そのものにも大きな影響を及ぼしている。
投資ファンドが会社に突きつけた増配提案は、利益処分案という期間損益をベースにした配当の考え方から、過去の社内留保を含めた剰余金の処分という形での配当の考え方への移行なしには考えにくい問題であり、さらに、活性化されていない資本をどう取り扱うかという問題にも及ぶ。これにより、会社は、買収防衛とともに増配提案に対する対策という点でも、今後ますます企業価値向上策の具体的開示が求められるものと思われる。
また、今年も引き続き、総会に出席する株主の増加と出席した株主の発言の増加が新聞報道等で伝えられているが、会社もこれを前向きにとらえる傾向がより顕著なものとなった。ここ数年みられる総会開催日分散化の動きは今年もさらに進展したが、本年総会では、土日開催に加え、月曜日開催が増えている。
これまで月曜日開催は、議決権行使書の行使期限等の関係から避けられる傾向が強かったが、会社法による議決権行使期限の明確化に加え、株主の利便性向上に向けた会場の選択という観点も月曜日開催を増加させた。ここ数年、株主の利便性を考慮して、足の便のよい都心のホテル等で開催する会社が増加する傾向がみられるが、当然のことながら数に制限がある。利便性を重視するには、曜日に固執するわけにもいかないという事情もあるものと思われる。
プロ株主が総会からほとんど姿を消してから久しいが、この間、総会での株主の発言が目立つといわれる割には総会自体は依然としてセレモニーという要素が強かったように思われる。しかし、機関投資家の積極的な議決権行使とともに、個人株主が有する議決権も無視できない状況になりつつある。(なかにし・としかず)
本年6月総会の動向と今後の株主総会への影響
日本シェアホルダーサービス取締役会長
三菱UFJ信託銀行(証券代行部門)理事 中西敏和
本年6月総会は、3月期決算会社においては会社法が全面的に適用された最初の定時株主総会となった。また、買収防衛策や配当に係る議案について、投資ファンド等の株主から修正提案や増配提案がなされる動きが顕著にみられるなど、その様相は昨年と比較しても一変した。本稿では、本年6月総会の概況、近時の環境変化が及ぼす影響とともに次期総会への対応をまとめていただいた。(編集部)
Ⅰ はじめに
会社法が昨年5月1日に施行されたが、計算書類の作成・監査等の手続については、施行後に決算期が到来するものから順次会社法を適用することとしたため、3月期決算会社にとっては、本年6月総会が会社法適用のもとでの最初の定時株主総会となった。
また、前年6月総会については、招集決定の取締役会との関係で総会手続が旧商法に基づいて行われた会社があるなど対応が分かれたが、このような会社も含めて3月期決算会社すべての株主総会が会社法全面適用という同一条件のもとで行われることになった。
その結果、会社法の全面適用にいかに対応するかということが、担当者にとって最大の関心事であったということができる。
これに加えて、前年6月総会では、15社において会社提案議案が機関投資家等の反対にあって否決または撤回されるということが関心を集めたが、本年6月総会に先立って、東京鋼鐵で会社が提案した株式交換契約承認議案が投資ファンドの反対にあって否決されたり、投資ファンドを中心に株主提案の動きが続発することにより(表1参照)、本年6月総会に向けて、株主対応の重要性に対する認識が一層高まり、総会準備に大きな影響を及ぼすことになった。その典型的なものは、会社が行おうとした敵対的買収防衛策を巡って訴訟にまで発展したブルドックソースの事例であろう。
以下、会社法全面適用のもとでの最初の6月総会について、以上のような背景を踏まえて振り返りながら、来年総会に向けた対応を提示することとする。
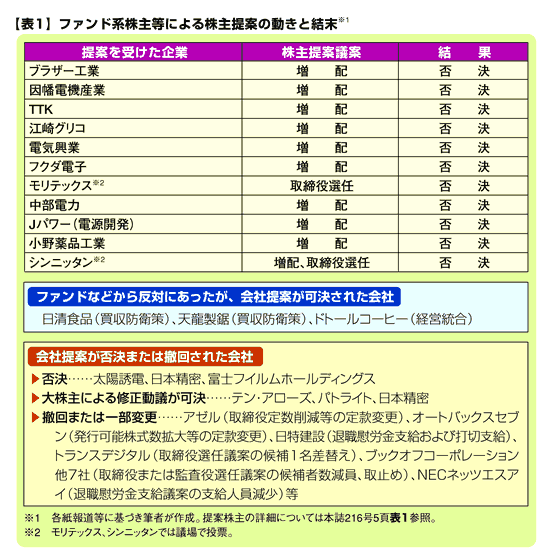
Ⅱ 会社法の全面適用による総会への影響
1 会社法全面適用下の総会準備手続 会社法は、計算書類について、利益処分(または損失処理)案を廃止し代わって株主資本等変動計算書等を加えるとともに、従前の営業報告書を事業報告に改め、計算書類から外し、記載事項を大幅に拡充させた。
事業報告については、新しく記載事項として追加された社外役員や内部統制システム、すべての会社に記載が求められることになった役員報酬の記載の仕方をめぐって議論がなされた。
とりわけ社外役員に関する記載事項については、参考書類の追加記載事項でもあるところから、主要活動状況の記載、兼務先における不当・不正な業務執行があった場合における予防措置、事後対応に関する記載については、社外役員が高名な方であればあるほど該当する機会が多くなりやすいところから、記載にあたっては、兼務先との調整を含め、頭を悩ませたものと思われる。
招集通知添付書類の見直しや記載事項の充実は、招集通知の膨大化を招くことになり、印刷・製本から郵送に付すための封入作業といった事務手続にも大きな問題を投げかけた。これまで招集通知については、郵便料金等との関係から、定形郵便物を意識したサイズにほぼ統一されていたが、記載事項の大幅な増加は、これを維持することに対して限界を感じさせることになったからである。
ダイナシティ等一部の会社にみられたが、今後は、会社法で認められたホームページへの掲載(WEB開示)による一部事項の招集通知への記載の省略が、改めて議論されよう。大半の会社がこれに必要な定款変更手続を昨年6月総会で済ませていたが、本年6月総会においては判明しているところで3社が実施するにとどまっている。
他方、招集通知の開示書類としての重要性を踏まえ、エーザイのように、これまでの郵送料金を意識した定形郵便物という制約から脱却し、サイズを大きくして開示書類としての機能を充実させる例もみられた。招集通知の開示機能という役割をどう考えるかという開示全体を含めた問題であり、今後検討が必要と思われる。
2 会社法全面適用下の総会運営 招集通知添付書類の見直しや記載事項の充実は、総会シナリオや想定問答にも大きな影響を及ぼした。
膨大化した事業報告や計算書類をこれまでの延長線上で考えると、総会冒頭の報告事項のところでいたずらに時間を費やすことになる。また、説明義務という観点からも範囲が広がることが予想され、そのぶん想定問答も分厚くなることになる。
総会シナリオについては、株主資本等変動計算書を省略したり、事業報告を一部割愛するといった見直しが行われたようであるが、長時間化の一因となったことは事実である。
他方、説明義務については、後述するとおり、出席株主の増加(表2参照)と変化を踏まえ、従来のような法律を厳格に運用するという考え方から、株主の満足度を重視し、説明することが適切でないと判断される事項を除き、できるだけ回答するという方針をとる会社が増加している。
表3のとおり、総会全体の長時間化の傾向が今年も顕著であるが、この傾向は避けられないとしても、株主への満足度という観点からは、質疑応答に時間を割く方が望ましい。今後は、総会のナレーション化ということも含めて、思い切った見直しが引き続き望まれるところである。
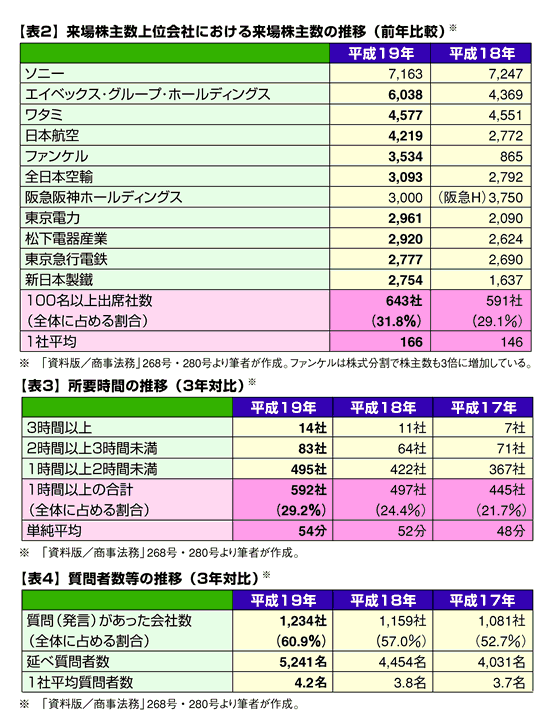
3 総会電子化の進捗状況 会社法は、従来からある招集通知の電子化、議決権行使の電子化に加え、WEB開示を利用した招集通知の一部記載事項の省略や、招集通知記載事項の修正の通知を認めている。
招集通知の電子化については、メリットが不明確であるところから、いまだ進展はみられないが、議決権行使の電子化については、インターネットを利用する方法が確立されており、徐々にではあるが増加傾向がみられる。
さらに、機関投資家の議決権行使の促進という観点から、ICJのプラットフォームを利用する会社が増加している。その前提としてインターネットを利用した議決権行使を認めていることが必要であるところから、これと歩調を合わせる形で今後も着実に増加するものと思われる。
他方、WEB開示の利用については、既に述べたとおり、招集通知の記載事項の省略という点ではわずかな利用にとどまったが、招集通知に誤植等の修正事項が生じた場合の通知手段としてのWEBの利用については、これに備えた招集通知への記載はほぼ全社が行っている点で十分定着したとみることができる。
Ⅲ 総会を巡る近時の環境変化と総会への影響
1 株主構成の変化に伴う総会運営への影響 株主総会への個人株主の参加意識はここ数年、引き続き高まる傾向にある。
来場株主という点からみても、いろいろな意味で知名度を高めた会社を中心に、来場株主数を増加させている。また、発言株主という観点からみても、発言があった会社の6月総会会社全体に占める割合は、引き続き増加傾向にある(表4参照)。
このような、総会への出席・発言を中心とした個人株主の活発な動きに対し、機関投資家の動きは引き続き会社提案に対する反対票という形で行われており、その基準は、原則として自ら示した議決権行使基準をもとに行われる。
本年はこれに加えて、前掲・表1のとおり、投資ファンドを中心に株主提案という形で自らの考えを示し、場合によっては委任状勧誘により賛成票を集める動きすら出始めた。
現在のところ、増配提案が中心となっているが、その背景には会社法による配当に対する考え方の変化が感じられるところである。
すなわち、配当についての株主への示し方が、これまでの利益の処分という見せ方から、剰余金の処理という見せ方に変更されており、会社としてはこれを意識して配当政策の決定に関する方針を明確に打ち出すことが今後望まれるところであろう。
2 会社法による付議議案への影響 ここ数年、役員報酬体系の見直しが盛んに行われている。
その中心は、役員退職慰労金の廃止または打切りとなって現れているが、会社法の施行に伴い、役員賞与の取扱いについても議論が活発化した。その引き金となったのは利益処分案の廃止であり、これに伴い役員賞与は独立した議案として付議することが必要となるからである。
ただし、役員退職慰労金および役員賞与を廃止すると、その代替手段として定例報酬の増額を行うとすれば、定例報酬枠の増額の要否が問題となってくる。このような対応を行った会社は少なくないが、役員賞与や退職慰労金の廃止に伴い、ストック・オプションも含めた報酬体系全体の見直しを行う会社が少なくないのも本年総会の大きな特徴である。
付議議案という点で、今年大きな変化がみられたのは、敵対的買収に対する防衛策を総会に付議する動きである。
最近の事例にみられるごとく、敵対的買収が仕掛けられる会社の範囲が広がっており、関心が高まっている。また、会社法では、事業報告の記載事項として、会社の「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を定めている場合にその記載を、さらに支配に関する方針を侵す者が現れた場合の対応策を定めている場合にその記載を求めているが、これに触発されて、対応策の実施を含め検討を行ったところも少なくない。しかし、一部の会社では、支配に関する方針とそれに対する取組みについてだけ記載するところもあり、こういった考え方を積極的に示していくところから始めても遅くはない。
3 個人株主を意識した総会運営 既に述べたとおり、個人株主の総会への出席は年々増加傾向をたどっている。もちろんすべての会社に共通する現象ではないが、従来から比較的出席株主数が多いとされている会社ほど増加率は高く、全体的には二極化の傾向が強まっている。
ただし、最近の総会に出席する層を注意深くみると、団塊の世代といわれるリタイア組を中心に、会社経営に関して一定の知識水準に達した株主の出席が目立つ。このような株主は、質問もさることながら、議長や答弁担当役員の説明にも熱心に耳を傾ける光景がみられ、総会全体の雰囲気を盛り上げるのにも大きく寄与している。
ここ数年、このような株主に対してわかりやすい説明が試みられており、その手段としてビジュアル化も進んでいる。今後は、このような出席株主を長期安定的な株主とするための工夫が試みられるものと思われる。総会開催日の分散化とともに、会場の選択という面でも株主の利便性向上が試みられるのも、その現れであろう。
Ⅳ 来年総会に向けての課題
本年総会は、会社法全面適用への対応が重要課題となったが、逆にこれをもって一応の定着をみたものと思われる。そして、本年の事例分析を来年総会に向けて活用することによって、本年問題とされた事項も終息を迎えるものと思われる。
他方、一層その必要性を意識させたのは、活発化する株主の把握という問題である。特に株主構成は各社各様であるため、会社法への対応のように他社事例をうのみにするわけにはいかず、きめ細かな対応が必要となる。
まず、機関投資家について必要なのは、議決権行使に及ぼす影響度合の早い時期での読みとそれに応じた対応策の立案である。
ただ単に議決権行使比率の向上を図り、議決権の空洞化を回避するということだけを目的とするのであれば、個々の機関投資家の把握ということまでは必要ないものと思われる。WEBを利用した早期の招集通知等の開示とICJが開設するプラットフォームの利用でも相応の成果は得られる。
しかし、機関投資家の議決権の行方が決議の成否に影響を及ぼす程度にまで達すると、企業年金連合会といった機関投資家や主要な運用機関、外国人投資家へのアドバイスを行うISSといった助言機関への個別説明等の実施が必要となる。
そして、決議の成否の行方が極めて不透明な段階にまで至ると、名義の背後にある個々の機関投資家を明らかにし、直接コンタクトをとることも考えるべきであろう。そのためには専門の調査機関を利用して判明調査を実施する必要がある。いずれの方法をとるにせよ、早い時期に状況を把握する必要がある。
会社法の全面適用とともに、実務で問題となったのは、株主総会そのものに対する考え方であろう。
ここ数年、総会における発言株主の増加とともに、機関投資家の反対票という形での積極的な議決権行使は、招集通知作成といった事務レベルの問題とは別の意味で重要性を増しているが、昨年15社で会社提案が否決されたことは、本年総会に向けて大きな問題を投げかけることになった。併せて、本年5月1日から可能となったいわゆる三角合併は、昨今活発化したTOBを中心とする企業買収に拍車をかけることが予想されるところから、敵対的な企業買収に対する防衛策に大きな関心を集めた。そして、これにさらなる追打ちをかけるような、投資ファンドを中心とする増配提案の増加である。
会社法は総会実務に大きな影響を及ぼしたが、それとともにそこで導入された市場主義という考え方は、総会のあり方そのものにも大きな影響を及ぼしている。
投資ファンドが会社に突きつけた増配提案は、利益処分案という期間損益をベースにした配当の考え方から、過去の社内留保を含めた剰余金の処分という形での配当の考え方への移行なしには考えにくい問題であり、さらに、活性化されていない資本をどう取り扱うかという問題にも及ぶ。これにより、会社は、買収防衛とともに増配提案に対する対策という点でも、今後ますます企業価値向上策の具体的開示が求められるものと思われる。
また、今年も引き続き、総会に出席する株主の増加と出席した株主の発言の増加が新聞報道等で伝えられているが、会社もこれを前向きにとらえる傾向がより顕著なものとなった。ここ数年みられる総会開催日分散化の動きは今年もさらに進展したが、本年総会では、土日開催に加え、月曜日開催が増えている。
これまで月曜日開催は、議決権行使書の行使期限等の関係から避けられる傾向が強かったが、会社法による議決権行使期限の明確化に加え、株主の利便性向上に向けた会場の選択という観点も月曜日開催を増加させた。ここ数年、株主の利便性を考慮して、足の便のよい都心のホテル等で開催する会社が増加する傾向がみられるが、当然のことながら数に制限がある。利便性を重視するには、曜日に固執するわけにもいかないという事情もあるものと思われる。
プロ株主が総会からほとんど姿を消してから久しいが、この間、総会での株主の発言が目立つといわれる割には総会自体は依然としてセレモニーという要素が強かったように思われる。しかし、機関投資家の積極的な議決権行使とともに、個人株主が有する議決権も無視できない状況になりつつある。(なかにし・としかず)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















