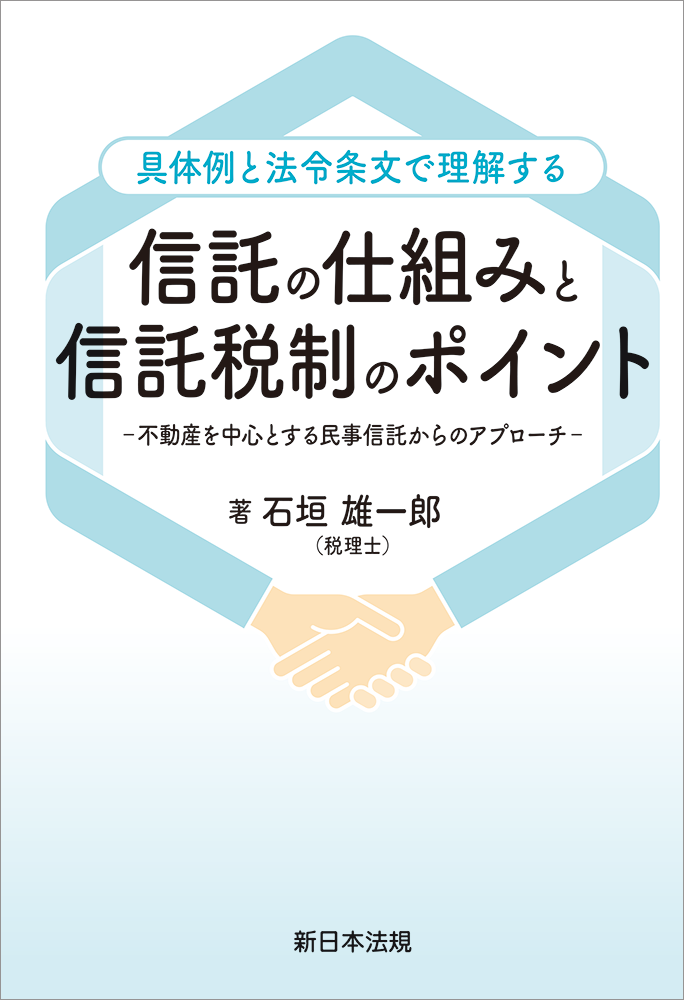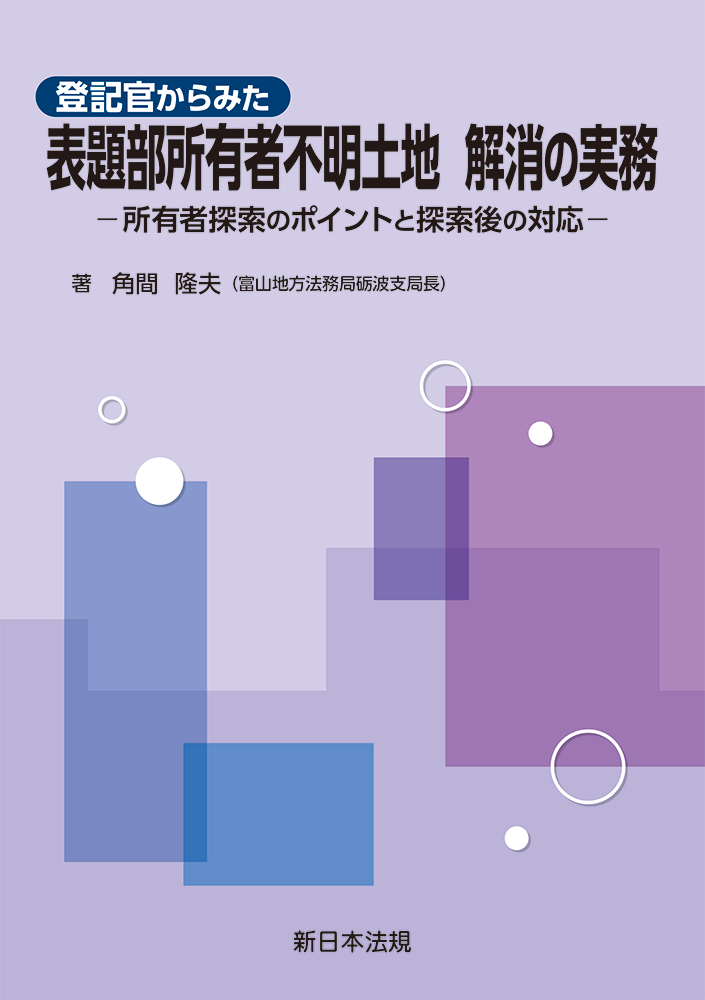解説記事2007年09月17日 【編集部解説】 ブルドックソース買収防衛策に係る裁判所決定を読み解く(4)(2007年9月17日号・№227)
ブルドックソース買収防衛策に係る裁判所決定を読み解く(4)
「著しく不公正な方法」への該当性の判断は?
text 編集部
ブルドックソース(ブル社)による買収防衛策としての新株無償割当てが「『著しく不公正な方法により行われる場合』に該当するか」についての東京地裁・東京高裁・最高裁の各決定を紹介するにあたり、前回(本誌226号23頁参照)は、新株・新株予約権の発行等に関する過去の裁判所の判断を振り返ったところである。具体的に判断規範を掲げたニッポン放送事件、ニレコ事件、日本技術開発事件は、いずれも会社法施行前の事案ではあるが、各決定における判断を最大公約数的にまとめると、(1)経営支配権の争奪を巡る局面においても、(2)会社側の採った手法を「正当化する特段の事情」や一定の条件があればその手法の必要性は肯定され、(3)その手法が株主に「不測の損害」「いわれのない不利益」を与えるものでなく、また、このような損害・不利益も程度により、その相当性が認められるという規範が打ち立てられてきたものといえる。「その手法の採用にあたって株主(総会)の判断が不可欠である」ことは、共通要素としては挙げることができない点にも注目しておきたい。
本件割当てに相当性が認められるか 今回の買収防衛策について、本件割当ておよび一連の裁判所決定における最大の争点といえるのが、「著しく不公正な方法により行われる場合」に該当するか否かである。
以下では、東京地裁決定からみていくこととするが、本レポート第2回と同様に、東京地裁決定においてSPJSF(側)を「債権者(等)(関係者)」と、ブル社を「債務者」といい、東京高裁・最高裁決定においてはSPJSF(側)を「抗告人(等)(関係者)」と、ブル社を「相手方」ということがある(本誌225号20頁表1参照)。
東京地裁においては、まず(1)「公開買付けに対する対抗手段が許容される基準について」述べ、次いで、本件総会における(2)「対抗手段の必要性に関する株主総会の判断の合理性について」を、最後に、(3)「本件新株予約権無償割当ての対抗手段としての相当性について」を判断する構成が採られている。
上記(1)について、決定原文の冒頭では、ニッポン放送事件の地裁決定・高裁決定で述べられたように(本誌226号27頁参照。なお、地裁決定の裁判長は同一である)、(ア)経営支配権が現に争われている局面において特定株主の持株比率を低下させ、現経営陣の支配権を維持・確保することを主要な目的として新株予約権の発行をした場合には、権限の濫用として「原則として不公正な発行として差止請求が認められる」べきところ、(イ)「株主全体の利益保護の観点から当該新株予約権の発行を正当化する特段の事情のある場合」、すなわち、「敵対的買収者が真摯に合理的な経営を目指すものではなく、敵対的買収者による経営支配権の取得が会社に回復し難い損害をもたらす事情がある場合」は、取締役会は一種の緊急避難的行為として相当な対抗手段を講ずることが許容され、(ウ)このような事情を会社が主張・疎明した場合には例外的に、手段の相当性が認められる限り、株主構成を変更すること自体を主要な目的とする発行をも差し止めることはできないことを注意的に述べたうえ、本件割当ては株主総会の権限に基づきなされているとし、「上記の法理は、本件について妥当するものではない」とする。
さらに、本件割当ての「目的が債権者関係者による経営支配権の取得を防止することにあることをもって、直ちに株主総会がその権限を濫用したものと認めることもできない」こと、「公開買付けに応ずるか否かという形での株主の選択権行使の機会とは別に、株主総会における議決権の行使という形での株主の選択権行使の機会を設けることが、証券取引法の趣旨に反するということはできない」ことを指摘。
そのうえで、表1-1のように述べ、
(i)株主総会としては相当な対抗手段を採れる
(ii)その対抗手段の必要性の判断は株主総会に委ねられ、当該判断が明らかに合理性を欠く場合に限り、対抗手段の必要性が否定される
(iii)特別決議による対抗手段であっても、その相当性については、経緯、不利益の有無・程度、阻害効果等を総合判断すべきであることを明らかにした。
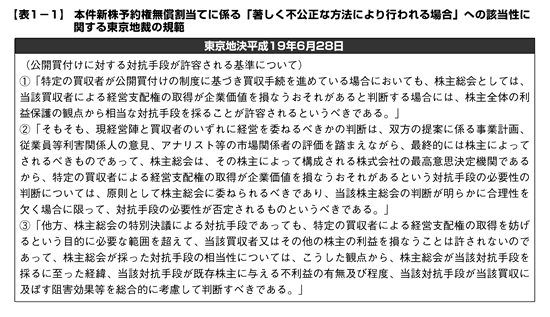
上記(2)は、(ii)の「必要性の判断の合理性」を検討するもので、決定は、「明らかに合理性を欠くものということはできない」としている(表1-2上段参照)。
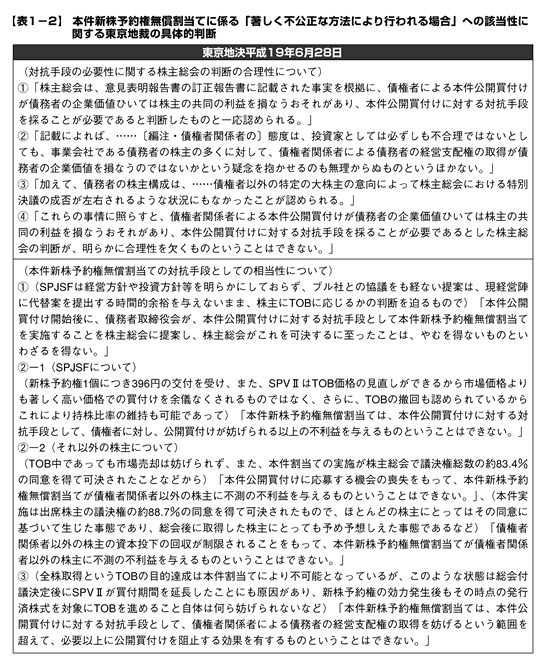
なお、(2)の検討においては、その末尾で、SPJSFが自らを「グリーンメーラーではな」いとし、このため、「債権者関係者には、『真摯に合理的な経営を目指すものではなく、敵対的買収による支配権取得が会社に回復し難い損害をもたらす事情』は存在しないから、本件新株予約権無償割当てには必要性及び相当性が欠如している」とする主張について、東京地裁は、「債権者関係者が上記〔編注・略〕の定義に係るグリーンメーラーであると認めるには足りない」「債権者関係者が……グリーンメーラーであるか否かは当裁判所の判断を左右するものではない」とし、斥けている。
上記(3)では(iii)を検討、いよいよ本件割当ての相当性が判断される。
東京地裁は、(ア)本件割当てに至る経緯、(イ)既存株主に与える不利益の有無および程度(SPJSF側に対するもの、それ以外の株主に対するものを分けて検討)、(ウ)本件割当てが本件TOBに及ぼす効果について仔細に検討を行い、さらに、(エ)SPJSFの「本件新株予約権無償割当ては、投資を抑止して債務者の企業価値を毀損し、債務者の株主も債務者株式を売却するかどうかの適切な判断ができず、株主の財産権に重大な脅威を与える」との主張についても検討を加えた。
その結果、(ア)~(ウ)について、それぞれ表1-2下段のような判断を示し、対抗手段としての相当性をも肯定したものである。
「本件については濫用的買収者」 東京高裁決定の判断枠組は、表2のとおりとなっている。
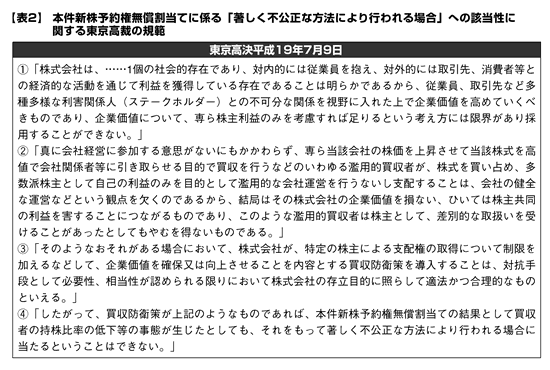
決定では、本件がこのような場合に当たるかどうかについて検討を加えるとし、ブル社の属性等、SPJSF関係者の属性等、これまでの企業買収行為等、両者がここに至る経緯等を仔細に認定した後、「前記認定事実に基づき考察する」として検討を加える。
この検討において、「抗告人関係者がした前記の経緯、態様による本件公開買付け等は、前記の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するものとして信義誠実の原則に抵触する不当なものであり、これを行う抗告人関係者は本件については濫用的買収者であると認めるのが相当というべきである」とした。
その後、本件割当ての必要性を検討し、(ア)「前記認定のとおりの属性を有し濫用的買収者と認められる抗告人が、日本国内で創業以来100年余の歴史を有し、堅調にソースの販売製造事業を行っている相手方を本件公開買付けによって買収しようという」行為により、ブル社が「場合によって解体にまで追い込まれなければならない理由はないのであって、このような事態に直面した相手方が自らの企業価値ひいては株主共同の利益を守るために自己防衛手段を採ることは理由のあることである」とし、(イ)会社法・証券取引法も防衛手段を禁じてはいないことから、買収防衛策としての手段としての本件割当ては「これを導入すべき必要性(目的の正当性)が認められる」とする。
さらに、本件割当ての相当性についても、「相当性を検討するに当たっては、買収防衛策を導入するに至った経緯及び手続、濫用的買収者あるいはその他の株主に与える不利益の程度、当該買収に及ぼす効果等に買収行為の不当性の程度等を総合的に考慮すべき」とし、「前記認定のとおり、前記認定に係る抗告人関係者による本件公開買付けは容認し難い不当なものと評価すべき」ことをまず述べたうえで、(ア)対抗手段としてやむを得ず、(イ)手続的には少なくとも株主総会の特別決議を経て導入されたこと、(ウ)SPJSF関係者に対し「その不当性の程度との相関関係からすると過度の財産的損害を与えるものとはいえないこと」、(エ)その他の株主の利益という観点からも、同株主がこれを受忍することを了承したと解され、同株主に本件割当てを違法とするような不利益を与えるものではないことから、「相当性を有する対抗策である」と述べた。
最高裁はどのように判断したか 最高裁決定の判断は、表3の①のように、まず「株主平等の原則」から判断して著しく不公正な方法ではないとするものである。
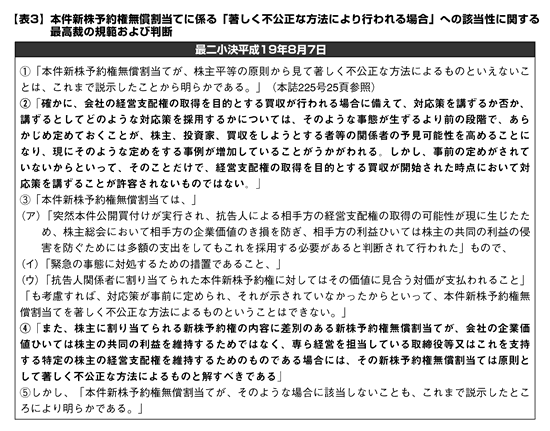
株主平等原則に係る最高裁決定の詳細は本誌225号25頁を参照されたいが、簡単に振り返ると、「企業価値がき損され、会社の利益ひいては株主の利益が害されるような場合」には、衡平の理念に反し相当性を欠くものでない限り特定株主の差別的取扱いが許容される、企業価値がき損されるかどうかは最終的には株主自身により判断され、その判断は「判断の正当性を失わせるような重大な瑕疵が存在しない限り」尊重されるというものであった。
決定原文は、①の後、(i)経営支配権を取得しようとする行為に対してブル社が本件のような対応策を採用することをあらかじめ定めていなかった点、(ii)当該対応策を採用した目的の点からみても、「これを著しく不公正な方法によるものということはできない」と述べて、その理由を挙げていく構成を採っている(最高裁決定における両者の主張がつまびらかではなく、最高裁の判断が(i)に及んだ経緯は不明)。
上記(i)については、表中②のように述べたうえで、本件割当てを検討。③における(ア)~(ウ)のような経緯・目的・手法からは、「対応策が事前に定められ、それが示されていなかった」としても、本件割当てを著しく不公正な方法とはいえないとする。
いわゆる「有事導入型」の買収防衛策であっても、一定の経緯・要件のもとではそれが有効とされる初判断となった。
この文脈においては、株主平等原則に反するかを判断した際の決定文と同様(本誌225号25頁参照)、「株主総会において……採用する必要があると判断されて行われた」ことは認定されているものの、導入に必要な決議要件(特別決議の必要性等)には触れられていない。
また、ここでのSPJSF側の経済的不利益等の取上げ方は、「前記のとおり、……価値に見合う対価が支払われる」ことを述べるのみであって、むしろ株主平等原則に反するかを判断した際の認定の方が細かなものとなっている(この争点に関する判断の冒頭で表中①のように述べられるゆえんであろう)。
上記(ii)についても、表中④のような規範のもと、本件割当ては「そのような場合に該当しない」(⑤参照)とだけ述べた。
規範の枠組としては、本稿冒頭で述べた本件地裁決定や、ニッポン放送事件地裁決定(「現経営陣の支配権を維持することを主要な目的としてされたものであるときは、……正当化する特段の事情がない限り、不当な目的を達成する手段として新株予約権発行が利用される場合にあたる」)・高裁決定(「現経営者又はこれを支持し事実上の影響力を及ぼしている特定の株主の経営支配権を維持・確保することを主要な目的として新株予約権の発行がされた場合には、原則として、……『著シク不公正ナル方法』による新株予約権の発行に該当する」)と同様のものと評価できるが、当該決定のいわゆる「射程」については、学界での検討や実務における事例集積が待たれるところである。
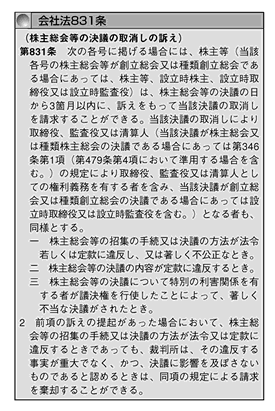
本件割当ての定款違反該当性 SPJSFは、「本件新株予約権無償割当ては定款により株主総会の特別決議を要するところ、本件新株予約権無償割当ては債権者関係者の持株比率を著しく低下させ、経済的損害をも与えるものであるから、これを承認した本件総会の特別決議(第7号議案)は『著しく不当な決議』(会社法831条1項3号)として取り消されるべき」(東京地裁決定文より引用)旨なども主張していた(本誌224号21頁以下参照。この段階における厳密な意味でのSPJSFの主張は、(1)「著しく不当な決議」(831条1項3号)に該当、(2)一般株主が「特別利害関係者」に該当、(3)「多数決の濫用」(831条1項3号類推)に該当するために、株主総会決議に無効または取り消し得べき事由があり、定款に違反する(247条1号)というもの)。
このような主張に関しては、「本件新株予約権無償割当てが定款に違反する場合に該当するか否かについて」と題した項目において、東京地裁決定のみが独自の判断を行っているところであるが(表4参照。東京高裁決定は、同じ見出しを立てて引用)、表中①のように、適正対価の交付による経済的利益の確保((ア)参照)、対抗手段としての必要性・相当性が確保されていること((イ)参照)が述べられたうえ、「当該特別決議について議決権を行使した債権者関係者以外の株主が『特別の利害関係を有する者』に該当するか否かを判断するまでもなく、当該特別決議が、会社法831条1項3号に該当し、取り消されるべきものであるという債権者の主張は採用することができない」といった判断を示し、会社法831条に基づく取消しの主張をまず斥けている。
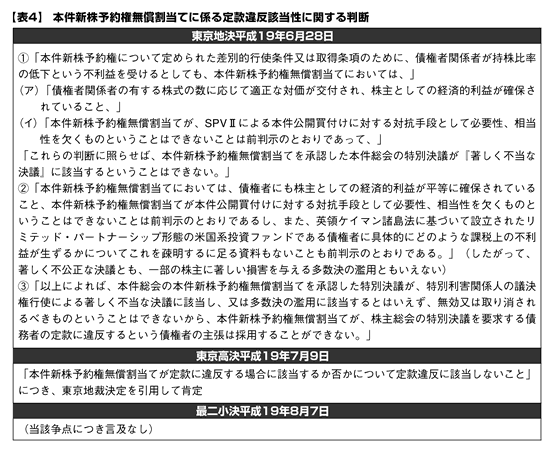
決定では、さらに仔細に検討を加え、
○ 債権者の持株比率を著しく低下させ、経済的損害をも与える
○ 債権者関係者以外の株主の税負担が生じないように配慮する一方、債権者側の税負担についてはまったく配慮されていない
ことを理由とする、当該特別決議が著しく不公正で、一部の株主のみに著しい損害を与える「多数決の濫用」に該当することによる無効または取消しの主張を、表中②のように判断して斥けている。(了)
「著しく不公正な方法」への該当性の判断は?
text 編集部
ブルドックソース(ブル社)による買収防衛策としての新株無償割当てが「『著しく不公正な方法により行われる場合』に該当するか」についての東京地裁・東京高裁・最高裁の各決定を紹介するにあたり、前回(本誌226号23頁参照)は、新株・新株予約権の発行等に関する過去の裁判所の判断を振り返ったところである。具体的に判断規範を掲げたニッポン放送事件、ニレコ事件、日本技術開発事件は、いずれも会社法施行前の事案ではあるが、各決定における判断を最大公約数的にまとめると、(1)経営支配権の争奪を巡る局面においても、(2)会社側の採った手法を「正当化する特段の事情」や一定の条件があればその手法の必要性は肯定され、(3)その手法が株主に「不測の損害」「いわれのない不利益」を与えるものでなく、また、このような損害・不利益も程度により、その相当性が認められるという規範が打ち立てられてきたものといえる。「その手法の採用にあたって株主(総会)の判断が不可欠である」ことは、共通要素としては挙げることができない点にも注目しておきたい。
本件割当てに相当性が認められるか 今回の買収防衛策について、本件割当ておよび一連の裁判所決定における最大の争点といえるのが、「著しく不公正な方法により行われる場合」に該当するか否かである。
以下では、東京地裁決定からみていくこととするが、本レポート第2回と同様に、東京地裁決定においてSPJSF(側)を「債権者(等)(関係者)」と、ブル社を「債務者」といい、東京高裁・最高裁決定においてはSPJSF(側)を「抗告人(等)(関係者)」と、ブル社を「相手方」ということがある(本誌225号20頁表1参照)。
東京地裁においては、まず(1)「公開買付けに対する対抗手段が許容される基準について」述べ、次いで、本件総会における(2)「対抗手段の必要性に関する株主総会の判断の合理性について」を、最後に、(3)「本件新株予約権無償割当ての対抗手段としての相当性について」を判断する構成が採られている。
上記(1)について、決定原文の冒頭では、ニッポン放送事件の地裁決定・高裁決定で述べられたように(本誌226号27頁参照。なお、地裁決定の裁判長は同一である)、(ア)経営支配権が現に争われている局面において特定株主の持株比率を低下させ、現経営陣の支配権を維持・確保することを主要な目的として新株予約権の発行をした場合には、権限の濫用として「原則として不公正な発行として差止請求が認められる」べきところ、(イ)「株主全体の利益保護の観点から当該新株予約権の発行を正当化する特段の事情のある場合」、すなわち、「敵対的買収者が真摯に合理的な経営を目指すものではなく、敵対的買収者による経営支配権の取得が会社に回復し難い損害をもたらす事情がある場合」は、取締役会は一種の緊急避難的行為として相当な対抗手段を講ずることが許容され、(ウ)このような事情を会社が主張・疎明した場合には例外的に、手段の相当性が認められる限り、株主構成を変更すること自体を主要な目的とする発行をも差し止めることはできないことを注意的に述べたうえ、本件割当ては株主総会の権限に基づきなされているとし、「上記の法理は、本件について妥当するものではない」とする。
さらに、本件割当ての「目的が債権者関係者による経営支配権の取得を防止することにあることをもって、直ちに株主総会がその権限を濫用したものと認めることもできない」こと、「公開買付けに応ずるか否かという形での株主の選択権行使の機会とは別に、株主総会における議決権の行使という形での株主の選択権行使の機会を設けることが、証券取引法の趣旨に反するということはできない」ことを指摘。
そのうえで、表1-1のように述べ、
(i)株主総会としては相当な対抗手段を採れる
(ii)その対抗手段の必要性の判断は株主総会に委ねられ、当該判断が明らかに合理性を欠く場合に限り、対抗手段の必要性が否定される
(iii)特別決議による対抗手段であっても、その相当性については、経緯、不利益の有無・程度、阻害効果等を総合判断すべきであることを明らかにした。
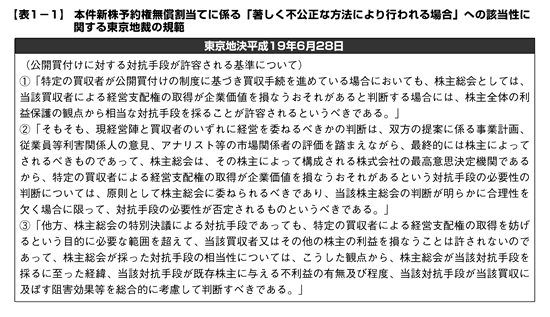
上記(2)は、(ii)の「必要性の判断の合理性」を検討するもので、決定は、「明らかに合理性を欠くものということはできない」としている(表1-2上段参照)。
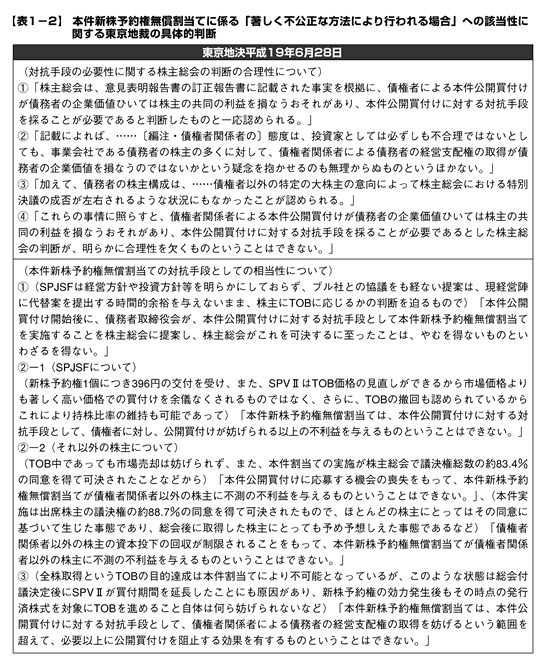
なお、(2)の検討においては、その末尾で、SPJSFが自らを「グリーンメーラーではな」いとし、このため、「債権者関係者には、『真摯に合理的な経営を目指すものではなく、敵対的買収による支配権取得が会社に回復し難い損害をもたらす事情』は存在しないから、本件新株予約権無償割当てには必要性及び相当性が欠如している」とする主張について、東京地裁は、「債権者関係者が上記〔編注・略〕の定義に係るグリーンメーラーであると認めるには足りない」「債権者関係者が……グリーンメーラーであるか否かは当裁判所の判断を左右するものではない」とし、斥けている。
上記(3)では(iii)を検討、いよいよ本件割当ての相当性が判断される。
東京地裁は、(ア)本件割当てに至る経緯、(イ)既存株主に与える不利益の有無および程度(SPJSF側に対するもの、それ以外の株主に対するものを分けて検討)、(ウ)本件割当てが本件TOBに及ぼす効果について仔細に検討を行い、さらに、(エ)SPJSFの「本件新株予約権無償割当ては、投資を抑止して債務者の企業価値を毀損し、債務者の株主も債務者株式を売却するかどうかの適切な判断ができず、株主の財産権に重大な脅威を与える」との主張についても検討を加えた。
その結果、(ア)~(ウ)について、それぞれ表1-2下段のような判断を示し、対抗手段としての相当性をも肯定したものである。
「本件については濫用的買収者」 東京高裁決定の判断枠組は、表2のとおりとなっている。
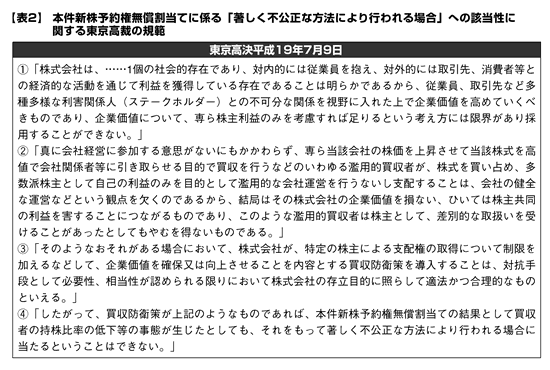
決定では、本件がこのような場合に当たるかどうかについて検討を加えるとし、ブル社の属性等、SPJSF関係者の属性等、これまでの企業買収行為等、両者がここに至る経緯等を仔細に認定した後、「前記認定事実に基づき考察する」として検討を加える。
この検討において、「抗告人関係者がした前記の経緯、態様による本件公開買付け等は、前記の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するものとして信義誠実の原則に抵触する不当なものであり、これを行う抗告人関係者は本件については濫用的買収者であると認めるのが相当というべきである」とした。
その後、本件割当ての必要性を検討し、(ア)「前記認定のとおりの属性を有し濫用的買収者と認められる抗告人が、日本国内で創業以来100年余の歴史を有し、堅調にソースの販売製造事業を行っている相手方を本件公開買付けによって買収しようという」行為により、ブル社が「場合によって解体にまで追い込まれなければならない理由はないのであって、このような事態に直面した相手方が自らの企業価値ひいては株主共同の利益を守るために自己防衛手段を採ることは理由のあることである」とし、(イ)会社法・証券取引法も防衛手段を禁じてはいないことから、買収防衛策としての手段としての本件割当ては「これを導入すべき必要性(目的の正当性)が認められる」とする。
さらに、本件割当ての相当性についても、「相当性を検討するに当たっては、買収防衛策を導入するに至った経緯及び手続、濫用的買収者あるいはその他の株主に与える不利益の程度、当該買収に及ぼす効果等に買収行為の不当性の程度等を総合的に考慮すべき」とし、「前記認定のとおり、前記認定に係る抗告人関係者による本件公開買付けは容認し難い不当なものと評価すべき」ことをまず述べたうえで、(ア)対抗手段としてやむを得ず、(イ)手続的には少なくとも株主総会の特別決議を経て導入されたこと、(ウ)SPJSF関係者に対し「その不当性の程度との相関関係からすると過度の財産的損害を与えるものとはいえないこと」、(エ)その他の株主の利益という観点からも、同株主がこれを受忍することを了承したと解され、同株主に本件割当てを違法とするような不利益を与えるものではないことから、「相当性を有する対抗策である」と述べた。
最高裁はどのように判断したか 最高裁決定の判断は、表3の①のように、まず「株主平等の原則」から判断して著しく不公正な方法ではないとするものである。
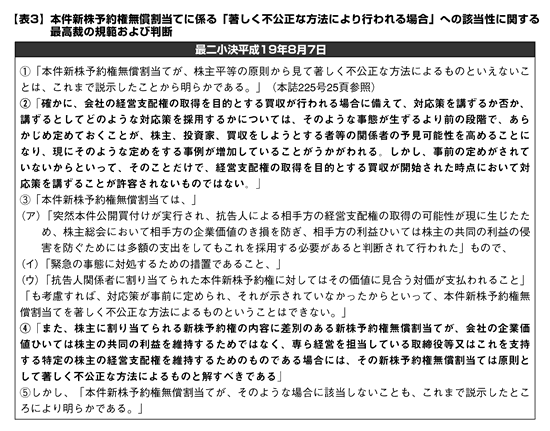
株主平等原則に係る最高裁決定の詳細は本誌225号25頁を参照されたいが、簡単に振り返ると、「企業価値がき損され、会社の利益ひいては株主の利益が害されるような場合」には、衡平の理念に反し相当性を欠くものでない限り特定株主の差別的取扱いが許容される、企業価値がき損されるかどうかは最終的には株主自身により判断され、その判断は「判断の正当性を失わせるような重大な瑕疵が存在しない限り」尊重されるというものであった。
決定原文は、①の後、(i)経営支配権を取得しようとする行為に対してブル社が本件のような対応策を採用することをあらかじめ定めていなかった点、(ii)当該対応策を採用した目的の点からみても、「これを著しく不公正な方法によるものということはできない」と述べて、その理由を挙げていく構成を採っている(最高裁決定における両者の主張がつまびらかではなく、最高裁の判断が(i)に及んだ経緯は不明)。
上記(i)については、表中②のように述べたうえで、本件割当てを検討。③における(ア)~(ウ)のような経緯・目的・手法からは、「対応策が事前に定められ、それが示されていなかった」としても、本件割当てを著しく不公正な方法とはいえないとする。
いわゆる「有事導入型」の買収防衛策であっても、一定の経緯・要件のもとではそれが有効とされる初判断となった。
この文脈においては、株主平等原則に反するかを判断した際の決定文と同様(本誌225号25頁参照)、「株主総会において……採用する必要があると判断されて行われた」ことは認定されているものの、導入に必要な決議要件(特別決議の必要性等)には触れられていない。
また、ここでのSPJSF側の経済的不利益等の取上げ方は、「前記のとおり、……価値に見合う対価が支払われる」ことを述べるのみであって、むしろ株主平等原則に反するかを判断した際の認定の方が細かなものとなっている(この争点に関する判断の冒頭で表中①のように述べられるゆえんであろう)。
上記(ii)についても、表中④のような規範のもと、本件割当ては「そのような場合に該当しない」(⑤参照)とだけ述べた。
規範の枠組としては、本稿冒頭で述べた本件地裁決定や、ニッポン放送事件地裁決定(「現経営陣の支配権を維持することを主要な目的としてされたものであるときは、……正当化する特段の事情がない限り、不当な目的を達成する手段として新株予約権発行が利用される場合にあたる」)・高裁決定(「現経営者又はこれを支持し事実上の影響力を及ぼしている特定の株主の経営支配権を維持・確保することを主要な目的として新株予約権の発行がされた場合には、原則として、……『著シク不公正ナル方法』による新株予約権の発行に該当する」)と同様のものと評価できるが、当該決定のいわゆる「射程」については、学界での検討や実務における事例集積が待たれるところである。
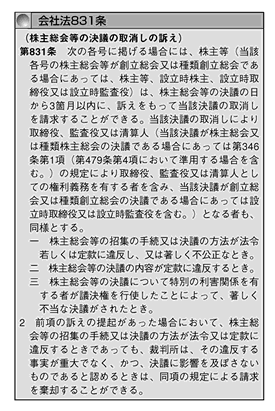
本件割当ての定款違反該当性 SPJSFは、「本件新株予約権無償割当ては定款により株主総会の特別決議を要するところ、本件新株予約権無償割当ては債権者関係者の持株比率を著しく低下させ、経済的損害をも与えるものであるから、これを承認した本件総会の特別決議(第7号議案)は『著しく不当な決議』(会社法831条1項3号)として取り消されるべき」(東京地裁決定文より引用)旨なども主張していた(本誌224号21頁以下参照。この段階における厳密な意味でのSPJSFの主張は、(1)「著しく不当な決議」(831条1項3号)に該当、(2)一般株主が「特別利害関係者」に該当、(3)「多数決の濫用」(831条1項3号類推)に該当するために、株主総会決議に無効または取り消し得べき事由があり、定款に違反する(247条1号)というもの)。
このような主張に関しては、「本件新株予約権無償割当てが定款に違反する場合に該当するか否かについて」と題した項目において、東京地裁決定のみが独自の判断を行っているところであるが(表4参照。東京高裁決定は、同じ見出しを立てて引用)、表中①のように、適正対価の交付による経済的利益の確保((ア)参照)、対抗手段としての必要性・相当性が確保されていること((イ)参照)が述べられたうえ、「当該特別決議について議決権を行使した債権者関係者以外の株主が『特別の利害関係を有する者』に該当するか否かを判断するまでもなく、当該特別決議が、会社法831条1項3号に該当し、取り消されるべきものであるという債権者の主張は採用することができない」といった判断を示し、会社法831条に基づく取消しの主張をまず斥けている。
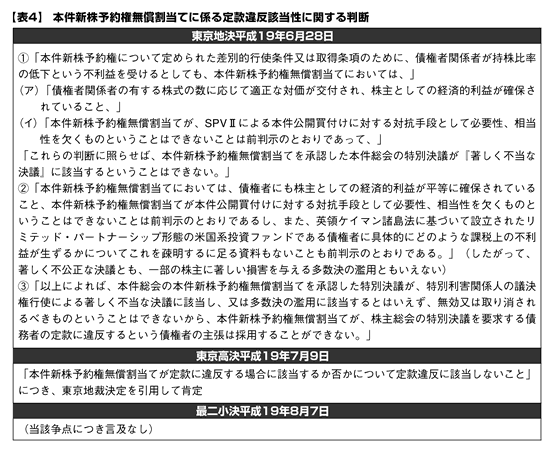
決定では、さらに仔細に検討を加え、
○ 債権者の持株比率を著しく低下させ、経済的損害をも与える
○ 債権者関係者以外の株主の税負担が生じないように配慮する一方、債権者側の税負担についてはまったく配慮されていない
ことを理由とする、当該特別決議が著しく不公正で、一部の株主のみに著しい損害を与える「多数決の濫用」に該当することによる無効または取消しの主張を、表中②のように判断して斥けている。(了)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -