解説記事2007年12月10日 【巻頭特集】 ディスクロージャー制度における見落としがちな規制環境の変化(2007年12月10日号・№238)
金融商品取引法制下における実務上の留意点①
ディスクロージャー制度における見落としがちな規制環境の変化
森・濱田松本法律事務所 弁護士 中村 聡/弁護士 峯岸健太郎
金融商品取引法が今年9月30日から施行されている。施行に伴う改正により、販売勧誘規制を始めとする金融商品取引業等の規制や、平成20年4月以後に開始する事業年度から適用される内部統制報告制度、四半期報告制度などに注目が集まりがちであるが、本稿は、情報開示に関する制度改正のうち見落とされがちなポイントについて取り上げるものである。
Ⅰ 第一項有価証券と開示規制
金融商品取引法では、開示規制の基礎となる有価証券の募集・私募・売出しの概念が、流通性の差に応じ、法2条1項各号に掲げられる私法上の有価証券およびそれに表示される権利である「第一項有価証券」と、「第二項有価証券」とに分けて定義されている。第一項有価証券に係る定義については、基本的に従来の枠組みが維持されつつも、いくつか注意すべき変更がなされている(第二項有価証券に係る定義については、Ⅱで後述する)。
1 適格機関投資家を相手方とする取得勧誘 適格機関投資家を相手方とする第一項有価証券の取得勧誘については、適格機関投資家のみを相手方とする場合(法2条3項1号第2括弧書)には、プロ私募の要件(同項2号イ)を満たすか否かにより、募集ではなく私募に該当するか否かが判定されることとなる。
これに対して、適格機関投資家以外の者が取得勧誘の相手方に含まれる場合には、一定の要件を満たす場合における適格機関投資家が相手方の人数計算から除かれることとなり(法2条3項1号第1括弧書)、そのうえで取得勧誘の人数が50名以上の場合には募集となるが(同号・令1条の5)、49名以下の場合には6か月の期間通算のうえ少人数私募の要件(法2条3項2号ロ)を満たすか否かにより、募集ではなく私募に該当するか否かが判定されることとなる。なお、期間通算においては、同種の新規発行証券に係る取得勧誘の相手方に同じ者が含まれる場合には延べ人数により計算されることとなるが(令1条の6、開示ガイドライン2-2)、これは同種であっても追加投資の判断が別の機会に行われるという考え方によるものと思われる。
取得勧誘の相手方の人数計算から除かれることとなる適格機関投資家に係る要件は、プロ私募の要件と同じものとされており(令1条の4、定義府令11条)、人数についても無制限となっている。また、人数計算から除かれる適格機関投資家を相手方とする取得勧誘については、プロ私募に係る告知義務と共通の告知義務が課せられることとなっている(法23条の13第1項・2項)。これにより、適格機関投資家を相手方とする取得勧誘については、プロ私募に該当するか否かを問わず、適格機関投資家向け勧誘(プロ向け発行勧誘)として規制の共通化が図られている。
以上を踏まえた第一項有価証券に係る募集・私募の概念は、図表1のとおり整理することができる(なお、第二項有価証券との主な相違について、図表2参照)。
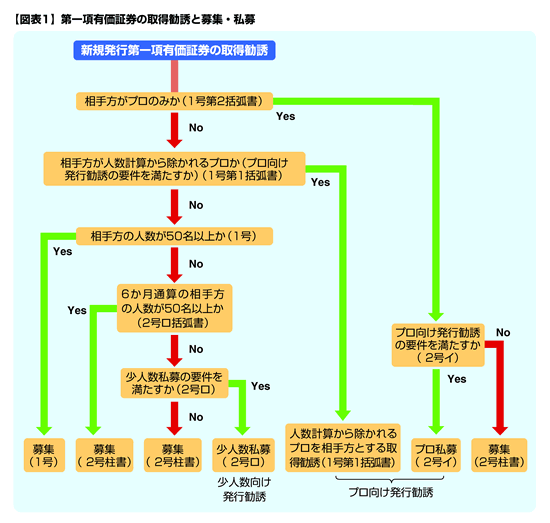
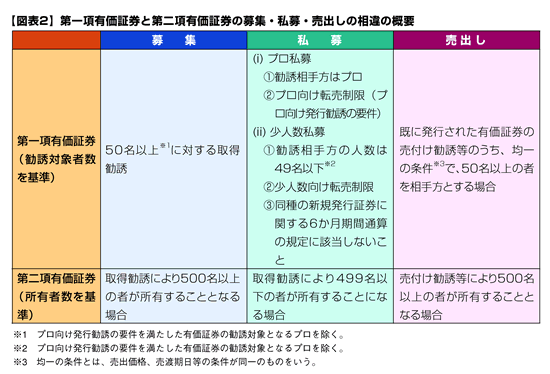
適格機関投資家を含む投資者を相手方とする第一項有価証券の取得勧誘全体が私募を構成するために、たとえば新株予約権付社債の場合には、適格機関投資家を人数計算から除くためのプロ向け発行勧誘の要件として、適格機関投資家以外への譲渡禁止の転売制限を付す必要があり(令1条の4第2号ロ、定義府令11条1項)、また少人数私募の要件を遵守するために、一括譲渡以外の譲渡禁止の転売制限を付すのが通常である(令1条の7第2号ロ、定義府令13条1項・2項ロ)。かかる場合、法令の文言上、転売制限ごとに有価証券を区分発行することは(もちろん可能であるが)必ずしも要求されていないため、同一の有価証券に2つの転売制限を付することが可能と解される。
このような場合、有価証券の取得者は、当該有価証券の内容のみによってはいずれの転売制限が適用されるかが判然としない。ただ、適格機関投資家向け勧誘または少人数向け勧誘に係る有価証券については、それぞれ、発行者から有価証券を原始取得する者に対しても、また法4条1項本文または2項本文による届出が行われない有価証券の交付勧誘等に応じて転売取得する者に対しても、告知義務が課せられているから(法23条の13)、これによっていずれの転売制限が付されているかを取得者は判別することができることとなる。
したがって、同一の有価証券に2つの転売制限が付されている場合には、かかる告知が明瞭に行われることが投資者の保護にとって重要な意味を有することに留意が必要である。
2 適格機関投資家と開示規制 適格機関投資家の範囲は大幅に拡大されており(定義府令10条1項)、たとえば、一般の事業法人投資家については、有価証券報告書提出会社である必要がなくなり、直近日の保有有価証券残高が10億円以上の法人であれば、届出を行うことにより適格機関投資家となることができる(同項23号イ)。また、直近日の保有有価証券残高が10億円以上で、金融商品取引業者等に口座を開設してから1年を経過した個人も、適格機関投資家となる届出を行うことができる(同項24号イ)。なお、金融商品取引業者に対する行為規制(契約締結前書面の交付義務など)が原則として免除される特定投資家の概念との関係においては、適格機関投資家は必ず特定投資家に含まれ(法2条31項1号)、一般投資家には移行できないため(法34条の2第1項参照)、適格機関投資家として届出可能な要件を満たすものの、行為規制による保護を受けたい場合もあると考える者は、適格機関投資家となる届出を行わないこととなろう。
また、組合型集団投資スキームについては、投資事業有限責任組合は組合自体が適格機関投資家であるが(同項18号)、任意組合、匿名組合もしくは有限責任事業組合または外国の法令に基づくこれらに類するもの(投資事業有限責任組合に類するリミテッド・パートナーシップも該当すると解すべきであろう)の場合は、直近日の保有有価証券残高が10億円以上のときに、すべての組合員の同意を得ている業務執行組合員等である法人あるいは個人において、適格機関投資家の届出を行うことができる(同項23号ロ・24号ロ)。ただし、適格機関投資家以外の組合員に現物配当(現物分配も含むと解すべきであろう)することを目的として、特定の有価証券の取得のみのために組成されたターゲット型ファンドである場合には、適格機関投資家に該当しない取扱いとされている(開示ガイドライン2-6④・⑤)。
したがって、かかるターゲット型ファンドはプロ向け発行勧誘の相手方にはなれないため、その取得することとなる第一項有価証券の取得勧誘については少人数私募の要件を満たすかが問題となるが、当該人数計算にあたっては、当該ファンド出資者が当該第一項有価証券の取得勧誘の事実上の対象者であって投資判断を行う者であることを勘案すると、実務上は慎重に、当該ファンド出資者の人数も含めて計算するのが適切であろう(パブコメ回答129頁49番参照)。
これに対して、業務執行組合員等の投資判断により分散投資を行う一般のポートフォリオ型ファンドの場合には、適格機関投資家性は維持されることとなるが、その後適格機関投資家以外の組合員に現物で配当または分配されるときは、法4条2項の有価証券交付勧誘等に該当して届出義務が生じるのではないかという問題がある(パブコメ回答19頁3番参照)2。
3 ストック・オプションに係る取得勧誘・売付け勧誘等 発行会社またはその完全子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役または使用人のみを相手方として譲渡が禁止される新株予約権証券の取得勧誘または売付け勧誘等が行われる(ストック・オプションが付与される)場合、当該役員および使用人も勧誘の相手方の人数計算に含めたうえで募集または売出しに該当するかが判定されることとなる(旧令1条の4第3項・1条の8第2項等の削除)。完全子会社の範囲については、孫会社は含まれないとされ(パブコメ回答122頁4番)、外国会社が発行会社である場合には本邦において設立されたものに限らないものとされている(旧定義府令3条の3第2項2号括弧書の削除)。
ただ、発行会社が上場会社であるとか、継続開示義務を負わない未上場会社でも勧誘対象者が50名以上であるなどにより、募集または売出しに該当した場合であっても、発行会社またはその完全子会社の役員および使用人のみを相手方とするときは、届出義務が免除されることとされている(法4条1項1号、令2条の12、開示府令2条1項・2項、開示ガイドライン4-2)。かかる場合、使用人に対して直近の定時株主総会に係る計算書類および事業報告などの会社情報を記載した書面の交付は要求されていない(旧令1条の4第3項2号ロ・旧定義府令3条の3第3項から9項までの削除)。
なお、届出義務が免除される場合には、発行会社が継続開示会社である場合には、ストック・オプションの発行内容について臨時報告書の提出が必要となる(開示府令19条2項2号の2)。
4 募集概念と有価証券通知書制度 従来、合併、株式交換、株式移転または会社分割(組織再編成)により株式を発行する場合は、「有価証券の募集」すなわち勧誘に該当しないと理解されてきた(削除された旧開示ガイドライン2-4④・⑤)。これに対し、金融商品取引法においては、有価証券の募集の定義自体に組織再編成発行手続は含まれないものの(法2条3項)、情報開示制度の適用上、特定組織再編成発行手続は募集の概念に含まれ、他方、これに該当しない組織再編成発行手続は募集に該当しないこととされている(法4条1項本文)。
この制度変更は、特定組織再編成発行手続について募集と同様の開示規制を新たに課すこととした(パブコメ回答118頁2番参照)だけにとどまらず、合併等についても投資者保護の観点から有価証券の募集に該当する場合があるという考え方(Gパブコメ回答36頁29番参照)に法令立案担当者の見解が変更されたことを意味するようである。たとえば、外国会社による外国法に基づく組織再編成行為であっても有価証券がわが国において発行される場合には、有価証券の取得の申込みの勧誘に該当しうるものとされている(同前)。
また、従来、少人数私募による場合、上記の組織再編成による場合などにおける「募集によらないで取得される株券」の総額1億円以上の発行については、有価証券通知書の提出が必要とされていたが(削除された旧開示府令6条、旧開示府令ガイドライン4-19から4-21まで)、金融商品取引法では、特定募集等(法4条4項)に該当する場合のみ、有価証券通知書の提出が必要となる。
Ⅱ 第二項有価証券と開示規制
1 みなし有価証券に開示規制が適用される場合 第一項有価証券と異なり、法2条2項各号に掲げる信託の受益権、合同会社などの社員権、集団投資スキーム持分などの有価証券とみなされる権利である第二項有価証券については、それぞれ、信託財産に属する資産の価額の総額、出資総額、集団投資スキーム持分に係る権利を有する者が出資または拠出した財産の価額の合計額などの50%を超える額を有価証券に対する投資に充てるもの(有価証券投資事業権利等)のみが、開示規制の対象となる(法3条3号)。
有価証券投資事業権利等に係る具体的な開示内容は、特定有価証券開示府令により定められている(令2条の13第7号)。ただし、令1条の3の4に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権については、学校法人等の財務内容が投資者に有用な情報であることから、開示府令により具体的な開示内容が定められている(令2条の13第7号)。
なお、次の権利を含む一定の権利は、有価証券投資事業権利等から除外されており、開示規制の適用除外とされている。
① いわゆる商品ファンドのうち、一の法人への出資を通じて商品投資を行うもの(令2条の9第1項1号・2項、令2条の10第1項1号ヌ・3項など)
② 年金関係の信託の受益権(令2条の10第1項1号イからトまで)
2 有価証券の募集と売出しの概念 (1)第一項有価証券との相違点 第一項有価証券と異なり、第二項有価証券については、有価証券の所有者を基準とした新たな有価証券の募集および売出しの概念が設けられている。
具体的には、第二項有価証券に関して、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得勧誘のうち、その取得勧誘に応じることにより500名以上の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合をいい(法2条3項3号・令1条の7の2)、「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付け勧誘等のうち、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を500名以上の者が所有することとなる場合をいう(法2条4項2号・令1条の8の2)。
図表2に記載したとおりであるが、大要、第二項有価証券の募集または売出しにおいては、次の点が第一項有価証券と異なる。
① 有価証券の所有者の数が募集または売出しに該当するか否かの基準となっていること
② プロ私募の概念が存在しないこと(したがって、プロも含めて有価証券の所有者として計算されること)
③ 私募とする場合に法律上は転売制限の要件が要求されないこと
④ 同種の新規発行証券に関する6か月の期間通算(令1条の6)に相当する規定がないこと
⑤ 売出しにおいては「均一の条件」が要件とはなっていないこと
その結果、相当に大きな違いが生じる。たとえば、1,000人に第二項有価証券の取得勧誘を行った場合であっても、当該取得勧誘に係る有価証券の所有者が499名以下となる場合には、第二項有価証券の私募として届出義務は発生しない(法4条1項参照)。したがって、499個以下に限定された第二項有価証券の取得勧誘を行う場合には、基本的には有価証券届出書を提出することは不要となる。
また、500個以上の第二項有価証券の取得勧誘を行うような場合であっても、取得者が499名となった時点において取得勧誘を停止すれば、第二項有価証券の募集には該当しないこととなる。
(2)当初意図と異なる販売結果となった場合の対応 募集または売出しの判断は、取得勧誘または売付け勧誘等を開始しようとする時点においてなされるため、当該時点において500名以上の者が第二項有価証券を所有することとなる見込みがある場合には募集または売出しに該当する(パブコメ回答30頁55番参照)。
当初500名以上の者に第二項有価証券を所有させる意図を有していたことから有価証券届出書を提出していたものの、結果として499名以下の者に対してしか第二項有価証券を販売できなかった場合には、有価証券届出書を提出した者は、遅滞なく、当該有価証券届出書を取り下げる旨を記載した「届出の取下げ願い」を関東財務局に提出するものとされている(特定有価証券開示ガイドライン4-2)。この結果、同日において有価証券通知書の提出があったものとみなされ、当該有価証券は、法24条5項の規定により準用される同条1項3号に規定する有価証券には該当せず、有価証券報告書の提出などの継続開示義務が発生しないこととなる(特定有価証券開示ガイドライン4-3)。
一方、取得勧誘または売付け勧誘等を開始しようとする時点においては499名以下の者に第二項有価証券を所有させる意図を有していたところ、その販売が好調であったため、500名以上の者に販売したい場合には、届出がなされていないことから、取得者が499名となったところで一旦販売を停止するほかない。停止せずに取得勧誘または売付け勧誘等を続け、有価証券の所有者が500名以上となってしまった場合には、無届け勧誘に該当し、勧誘者は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処せられ、または併科される(法197条の2第1号)。また、法人の両罰規定では、5億円以下の罰金とされている(法207条1項2号)。
それでは、当該有価証券をさらに販売したい場合には、どのようにすべきか。
第二項有価証券の募集については、前述のとおり、令1条の6の規定のような6か月以内の同種の新規発行証券の取得勧誘についての人数通算の規定がないこと、「その取得勧誘」または「その売付け勧誘等」に関して有価証券の所有者の人数を数えるものとされていることから、所有者の人数は一連の取得勧誘または売付け勧誘等ごとに判断すればよいと解される。
したがって、以前の取得勧誘または売付け勧誘等と異なるものと評価されるような形態で取得勧誘または売付け勧誘等を開始すれば、後の取得勧誘または売付け勧誘等の取得者の人数は別に計算される。ここで重要なのは、後から追加で行われる取得勧誘または売付け勧誘等が、以前のものと異なるものと評価されるような形態で行われることが必要なことである。
たとえば、以前の勧誘を中止した上で別の払込期日を定めて別途勧誘を開始するなどの適切な措置をとらない場合には、当初の取得勧誘または売付け勧誘等を開始しようとする時点から500名以上に有価証券を所有させる意図があったものとして、これについて無届け勧誘として前述の刑事罰の対象となる可能性がある点に注意が必要である(パブコメ回答30頁55番参照)。
また、たとえば、第二項有価証券の取得勧誘の結果として300名の者が有価証券の所有者となり、これと同時に売付け勧誘等の結果として300名の者に有価証券を所有させた場合には、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断されるべきであるが、基本的にはそれぞれ有価証券の募集と売出しには該当しないものされている(パブコメ回答29頁54番参照)。
なお、開示規制との関係においては、前述のとおり私募要件として第二項有価証券に転売制限を付すことは求められていないものの、集団投資スキーム持分の自己勧誘に関して、第二種金融商品取引業の登録を行わず、届出業務である適格機関投資家等特例業務として私募を行うためには、一定の者を相手方としてはならないとされるとともに、次の転売制限などの要件を満たす必要がある(法63条1項1号、令17条の12第3項)。
① 取得者が適格機関投資家である場合には、適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡禁止の転売制限が付されていること
② 取得者が適格機関投資家以外の一般投資家である場合には、一括譲渡以外の譲渡禁止の転売制限が付されていることおよび当該一般投資家の人数と6か月以内に発行された同種の新規発行権利の取得者である一般投資家の人数との合計が49名以下となること
この49名の数え方については、前述の開示規制における少人数私募の場合とは異なり、同一の投資家が複数回出資していたとしても1名と数えればよいとされている(パブコメ回答544頁29番参照)。
3 継続開示義務 第二項有価証券の募集または売出しに際して届出が行われた場合には、当該有価証券に係る特定期間(信託の計算期間または発行者の事業年度)の末日から3か月以内に有価証券報告書を提出することなどの継続開示義務が生ずる(法24条5項・1項3号)。
一方、届出が行われなかった場合においても、その第二項有価証券(法2条2項1号、3号および5号に掲げる権利に限る)の所有者が当該第二項有価証券に係るある特定期間の末日において500名以上となる場合には、継続開示義務が生ずる(法24条5項・1項4号、令4条の2第4項・5項)。したがって、私募を複数回行う場合であっても、継続開示義務の発生を避けたいときには注意を要する。
また、前述のとおり、第二項有価証券の私募として転売制限は開示規制上の要件とはなっていないものの、第二項有価証券の転売や分割が可能であると所有者が500名以上となってしまうことがあることから、継続開示義務の発生を避けるためには第二項有価証券の私募においても、実務上は499個以下としたうえで分割禁止とするか、499名以上が所有することとならないような転売制限を設ける必要がある。
Ⅲ 組織再編成と開示規制
1 組織再編成における届出義務 金融商品取引法は、一定の組織再編成(合併、会社分割、株式交換および株式移転をいう)に関して有価証券の発行者に当該有価証券やその発行者に関する情報の開示を義務付けている。
その概要は、図表3記載のとおりであるが、具体的には、次のいずれにも該当する場合、当該組織再編成に関して、「特定組織再編成発行手続」(法2条の2第4項)または「特定組織再編成交付手続」(法2条の2第5項)として、原則として届出が義務付けられる(法4条1項2号)。
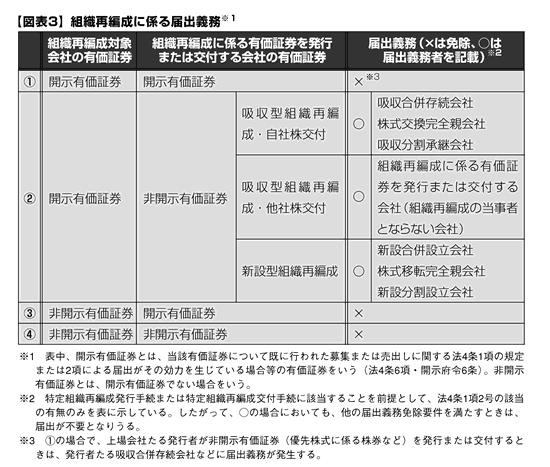
① 組織再編成対象会社(吸収合併消滅会社、新設合併消滅会社、吸収分割会社、新設分割会社、株式交換完全子会社および株式移転完全子会社をいう)の株券、新株予約権証券もしくは新株予約権付社債券またはこれらのいずれかを原券とする預託証券もしくは受託有価証券とする有価証券信託受益証券(令2条の3第3号)(以下「株券等」という)に関して、「開示が行われている場合」
② 組織再編成により発行または交付される有価証券に関して、開示が行われない場合
特定組織再編成発行手続または特定組織再編成交付手続に該当するか否かは、組織再編成対象会社株主等(法2条の2第4項1号)の人数により判断される。
具体的には、組織再編成発行手続または組織再編成交付手続に関して第一項有価証券が50名以上(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く)に発行または交付される場合、第二項有価証券が500名以上に発行または交付される場合には、特定組織再編成発行手続または特定組織再編成交付手続に該当する。この組織再編成対象会社株主等の人数は、前述の組織再編成対象会社が発行する株券等の所有者(実所有者の数)を合算して計算される。
なお、特定組織再編成手続または特定組織再編成交付手続に係る届出については、目論見書の交付は不要とされているが(法4条1項本文第1括弧書・3項本文第1括弧書参照)、これは組織再編成自体に関する組織再編成対象会社株主等の保護は会社法上の手続で足りるという考え方によるものと思われる。
2 届出義務が発生しない場合 届出義務が発生する場合については図表3のとおりであるが、表において原則として届出義務が発生する場合であっても、発行価額または売出価額の総額が1億円未満である募集または売出しで内閣府令で定めるもの(法4条1項5号、開示府令2条3項)に該当する場合には届出義務が免除される。
組織再編成においては、発行価額または売出価額の総額は、新設型組織再編成であれば、新設会社の株主資本または承継純資産により計算されるようであるから、当該金額が1億円未満である募集または売出しで、開示府令2条3項各号に該当するもの以外の募集または売出しである場合には、新設型組織再編成であっても、届出義務が免除される場合がありうるものと思われる4。
注意を要するのは、組織再編成対象会社株主等が当該有価証券の交付を受けない場合であっても、上場会社が①新設分割を行うときや②吸収分割を行い(非継続開示会社の)承継会社の株式の交付を受けるときは、組織再編成対象会社株主等の数が50名以上であるため「特定組織再編成」の定義に該当し(法2条の2第4項1号、令2条の4)、組織再編成に係る届出義務の免除要件にも該当しないため(法4条1項2号)、承継純資産額が1億円未満である場合(同項5号)を除き、届出義務が発生することである。
新設会社や承継会社について届出義務が発生すると継続開示が必要となるが(法24条1項3号)、同項ただし書の3つ目の要件により、事業年度末の株主数が25名未満ということで当局の承認を受ければ、その申請後5年間、事業年度末の株主名簿などを提出することを条件として、継続開示義務の中断が認められる(令4条2項3号・3項、開示府令16条)。またその後、法24条1項ただし書の1つ目の要件により、5年間の事業年度末の所有者数が300名未満ということで、継続開示義務免除の承認が受けられる。
また、有価証券届出書の提出義務は、有価証券が発行または交付される場合において要求されるものであることから、組織再編成により有価証券が発行または交付されない場合にも、法4条の規定による届出義務が生じることはない。したがって、たとえば、金商法上の開示会社が分割会社としてその完全子会社に会社分割を行い、当該会社分割に際して株券等の発行または交付が行われないような場合には、有価証券届出書の提出義務が生ずることはない。
3 組織再編成に係る有価証券届出書の内容 組織再編成に関して発行または交付される有価証券が、開示府令に基づき開示される株券等である場合には、開示府令第2号の6様式(内国会社)と開示府令第2号の7様式(内国会社の新規公開)および第7号の4様式(外国会社)の3種類の様式が適用される。
一方、組織再編成に関して発行または交付される有価証券が、投資信託の受益証券などの特定有価証券(法5条1項)である場合には、特定有価証券開示府令10条1項各号に掲げる様式に組織再編成に係る記載項目を加えたものが開示されることとなる。
具体的には、組織再編成に係る主な6つの記載項目の内容は次のとおりである。
① 組織再編成の概要、目的等
② 組織再編成当事会社の概要
③ 組織再編成の契約の内容、割当ての内容およびその算定根拠
④ 組織再編成に関する手続
⑤ 統合財務情報(組織再編成後の主要な経営指標等)
⑥ 組織再編成対象会社の会社情報
会社法においては、平成19年5月1日に施行された合併等の対価柔軟化に対応するために改正された会社法施行規則において株主保護の観点から事前備置書類の拡充(同規則182条など)が行われていることから、その開示内容と有価証券届出書の記載内容が重なることも多いものと考えられるが、有価証券届出書では有価証券の割当比率の算定根拠が求められるなど、必ずしも開示内容が同一ではない。したがって、その記載にあたっては、多くの場合は困難はないものと考えられるが、注意を要する。
また、統合財務情報については、組織再編成後の会社の姿を示すものとして、組織再編成後の主要な経営指標等について記載が求められていることから、その記載については特に注意を要する必要がある5。
4 組織再編成に係る臨時報告書 有価証券報告書提出会社において組織再編成が行われることが「業務執行を決定する機関により決定された場合」には、臨時報告書を提出する必要がある(開示府令19条2項6号の2から7号の4まで。連結会社に係る場合には同項14号の2から15号の4まで)。
組織再編成時に提出される臨時報告書の内容については、平成18年12月13日に施行された開示府令の改正により大幅に記載事項が拡充されているが、平成19年9月30日に施行された開示府令の改正により、いわゆる三角合併に対応した改正も行われている。
具体的には、たとえば株式交換がなされる場合において、当該株式交換において割当てがなされる有価証券が株式交換完全親会社の発行する株式等以外の有価証券である場合には、当該有価証券の発行者についてその商号、資本金の額、事業の内容等の情報を開示することが求められている。
(なかむら・さとし/みねぎし・けんたろう)
脚注 1 「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等」に対するパブリック・コメントの結果に係る平成19年7月31日付公表資料「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(以下「パブコメ回答」という)を参照。
2 中村聡「集団投資スキームに関する規制について~組合型ファンドを中心に~」証券取引法研究会編『証券・会社法制の潮流』(日本証券経済研究所、平成19年)68頁から73頁までを参照。
3 「証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)」に対するパブリック・コメントの結果に係る平成19年10月2日付公表資料「証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)」に対するパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」を参照。
4 有価証券報告書提出会社である株式会社三越および株式会社伊勢丹は、株式移転により完全親会社である株式会社三越伊勢丹ホールディングスを設立するにあたって有価証券届出書の提出を行っており(平成19年10月31日提出)、その募集金額は、株式会社三越および株式会社伊勢丹の前事業年度末における株主資本の額を基準としている。また、近江マウンテンリゾート株式会社は、新設分割を行うにあたって有価証券届出書の提出を行っており(平成19年11月2日提出)、その募集金額は承継純資産の額を基準としている。いずれも、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET(http://info.edinet.go.jp/))を参照。
5 株式会社三越伊勢丹ホールディングスが提出した前述の有価証券届出書においては、統合財務情報の一部について当該情報を記載することにより投資者に誤解を招く情報があると考える情報については有価証券届出書に記載を行わないものとされている。したがって、統合財務情報の一部について正当な理由があれば記載を行わないとの対応が許容される場合もありうるものと考えられる。
ディスクロージャー制度における見落としがちな規制環境の変化
森・濱田松本法律事務所 弁護士 中村 聡/弁護士 峯岸健太郎
金融商品取引法が今年9月30日から施行されている。施行に伴う改正により、販売勧誘規制を始めとする金融商品取引業等の規制や、平成20年4月以後に開始する事業年度から適用される内部統制報告制度、四半期報告制度などに注目が集まりがちであるが、本稿は、情報開示に関する制度改正のうち見落とされがちなポイントについて取り上げるものである。
Ⅰ 第一項有価証券と開示規制
金融商品取引法では、開示規制の基礎となる有価証券の募集・私募・売出しの概念が、流通性の差に応じ、法2条1項各号に掲げられる私法上の有価証券およびそれに表示される権利である「第一項有価証券」と、「第二項有価証券」とに分けて定義されている。第一項有価証券に係る定義については、基本的に従来の枠組みが維持されつつも、いくつか注意すべき変更がなされている(第二項有価証券に係る定義については、Ⅱで後述する)。
1 適格機関投資家を相手方とする取得勧誘 適格機関投資家を相手方とする第一項有価証券の取得勧誘については、適格機関投資家のみを相手方とする場合(法2条3項1号第2括弧書)には、プロ私募の要件(同項2号イ)を満たすか否かにより、募集ではなく私募に該当するか否かが判定されることとなる。
これに対して、適格機関投資家以外の者が取得勧誘の相手方に含まれる場合には、一定の要件を満たす場合における適格機関投資家が相手方の人数計算から除かれることとなり(法2条3項1号第1括弧書)、そのうえで取得勧誘の人数が50名以上の場合には募集となるが(同号・令1条の5)、49名以下の場合には6か月の期間通算のうえ少人数私募の要件(法2条3項2号ロ)を満たすか否かにより、募集ではなく私募に該当するか否かが判定されることとなる。なお、期間通算においては、同種の新規発行証券に係る取得勧誘の相手方に同じ者が含まれる場合には延べ人数により計算されることとなるが(令1条の6、開示ガイドライン2-2)、これは同種であっても追加投資の判断が別の機会に行われるという考え方によるものと思われる。
取得勧誘の相手方の人数計算から除かれることとなる適格機関投資家に係る要件は、プロ私募の要件と同じものとされており(令1条の4、定義府令11条)、人数についても無制限となっている。また、人数計算から除かれる適格機関投資家を相手方とする取得勧誘については、プロ私募に係る告知義務と共通の告知義務が課せられることとなっている(法23条の13第1項・2項)。これにより、適格機関投資家を相手方とする取得勧誘については、プロ私募に該当するか否かを問わず、適格機関投資家向け勧誘(プロ向け発行勧誘)として規制の共通化が図られている。
以上を踏まえた第一項有価証券に係る募集・私募の概念は、図表1のとおり整理することができる(なお、第二項有価証券との主な相違について、図表2参照)。
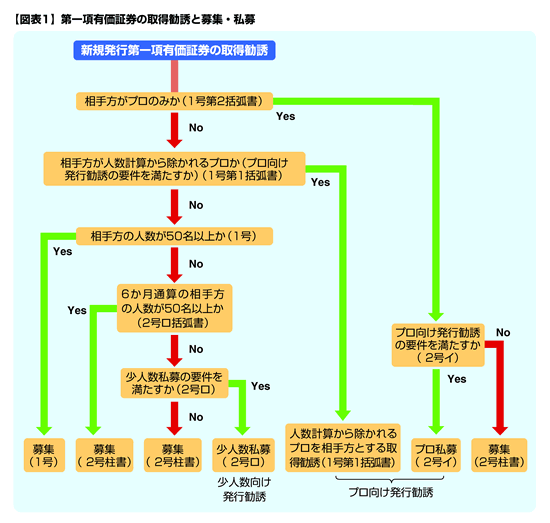
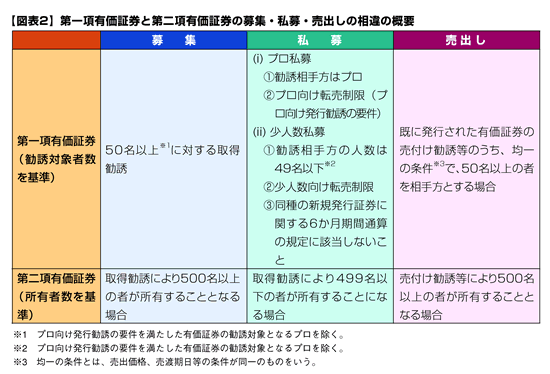
適格機関投資家を含む投資者を相手方とする第一項有価証券の取得勧誘全体が私募を構成するために、たとえば新株予約権付社債の場合には、適格機関投資家を人数計算から除くためのプロ向け発行勧誘の要件として、適格機関投資家以外への譲渡禁止の転売制限を付す必要があり(令1条の4第2号ロ、定義府令11条1項)、また少人数私募の要件を遵守するために、一括譲渡以外の譲渡禁止の転売制限を付すのが通常である(令1条の7第2号ロ、定義府令13条1項・2項ロ)。かかる場合、法令の文言上、転売制限ごとに有価証券を区分発行することは(もちろん可能であるが)必ずしも要求されていないため、同一の有価証券に2つの転売制限を付することが可能と解される。
このような場合、有価証券の取得者は、当該有価証券の内容のみによってはいずれの転売制限が適用されるかが判然としない。ただ、適格機関投資家向け勧誘または少人数向け勧誘に係る有価証券については、それぞれ、発行者から有価証券を原始取得する者に対しても、また法4条1項本文または2項本文による届出が行われない有価証券の交付勧誘等に応じて転売取得する者に対しても、告知義務が課せられているから(法23条の13)、これによっていずれの転売制限が付されているかを取得者は判別することができることとなる。
したがって、同一の有価証券に2つの転売制限が付されている場合には、かかる告知が明瞭に行われることが投資者の保護にとって重要な意味を有することに留意が必要である。
2 適格機関投資家と開示規制 適格機関投資家の範囲は大幅に拡大されており(定義府令10条1項)、たとえば、一般の事業法人投資家については、有価証券報告書提出会社である必要がなくなり、直近日の保有有価証券残高が10億円以上の法人であれば、届出を行うことにより適格機関投資家となることができる(同項23号イ)。また、直近日の保有有価証券残高が10億円以上で、金融商品取引業者等に口座を開設してから1年を経過した個人も、適格機関投資家となる届出を行うことができる(同項24号イ)。なお、金融商品取引業者に対する行為規制(契約締結前書面の交付義務など)が原則として免除される特定投資家の概念との関係においては、適格機関投資家は必ず特定投資家に含まれ(法2条31項1号)、一般投資家には移行できないため(法34条の2第1項参照)、適格機関投資家として届出可能な要件を満たすものの、行為規制による保護を受けたい場合もあると考える者は、適格機関投資家となる届出を行わないこととなろう。
また、組合型集団投資スキームについては、投資事業有限責任組合は組合自体が適格機関投資家であるが(同項18号)、任意組合、匿名組合もしくは有限責任事業組合または外国の法令に基づくこれらに類するもの(投資事業有限責任組合に類するリミテッド・パートナーシップも該当すると解すべきであろう)の場合は、直近日の保有有価証券残高が10億円以上のときに、すべての組合員の同意を得ている業務執行組合員等である法人あるいは個人において、適格機関投資家の届出を行うことができる(同項23号ロ・24号ロ)。ただし、適格機関投資家以外の組合員に現物配当(現物分配も含むと解すべきであろう)することを目的として、特定の有価証券の取得のみのために組成されたターゲット型ファンドである場合には、適格機関投資家に該当しない取扱いとされている(開示ガイドライン2-6④・⑤)。
したがって、かかるターゲット型ファンドはプロ向け発行勧誘の相手方にはなれないため、その取得することとなる第一項有価証券の取得勧誘については少人数私募の要件を満たすかが問題となるが、当該人数計算にあたっては、当該ファンド出資者が当該第一項有価証券の取得勧誘の事実上の対象者であって投資判断を行う者であることを勘案すると、実務上は慎重に、当該ファンド出資者の人数も含めて計算するのが適切であろう(パブコメ回答129頁49番参照)。
これに対して、業務執行組合員等の投資判断により分散投資を行う一般のポートフォリオ型ファンドの場合には、適格機関投資家性は維持されることとなるが、その後適格機関投資家以外の組合員に現物で配当または分配されるときは、法4条2項の有価証券交付勧誘等に該当して届出義務が生じるのではないかという問題がある(パブコメ回答19頁3番参照)2。
3 ストック・オプションに係る取得勧誘・売付け勧誘等 発行会社またはその完全子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役または使用人のみを相手方として譲渡が禁止される新株予約権証券の取得勧誘または売付け勧誘等が行われる(ストック・オプションが付与される)場合、当該役員および使用人も勧誘の相手方の人数計算に含めたうえで募集または売出しに該当するかが判定されることとなる(旧令1条の4第3項・1条の8第2項等の削除)。完全子会社の範囲については、孫会社は含まれないとされ(パブコメ回答122頁4番)、外国会社が発行会社である場合には本邦において設立されたものに限らないものとされている(旧定義府令3条の3第2項2号括弧書の削除)。
ただ、発行会社が上場会社であるとか、継続開示義務を負わない未上場会社でも勧誘対象者が50名以上であるなどにより、募集または売出しに該当した場合であっても、発行会社またはその完全子会社の役員および使用人のみを相手方とするときは、届出義務が免除されることとされている(法4条1項1号、令2条の12、開示府令2条1項・2項、開示ガイドライン4-2)。かかる場合、使用人に対して直近の定時株主総会に係る計算書類および事業報告などの会社情報を記載した書面の交付は要求されていない(旧令1条の4第3項2号ロ・旧定義府令3条の3第3項から9項までの削除)。
なお、届出義務が免除される場合には、発行会社が継続開示会社である場合には、ストック・オプションの発行内容について臨時報告書の提出が必要となる(開示府令19条2項2号の2)。
4 募集概念と有価証券通知書制度 従来、合併、株式交換、株式移転または会社分割(組織再編成)により株式を発行する場合は、「有価証券の募集」すなわち勧誘に該当しないと理解されてきた(削除された旧開示ガイドライン2-4④・⑤)。これに対し、金融商品取引法においては、有価証券の募集の定義自体に組織再編成発行手続は含まれないものの(法2条3項)、情報開示制度の適用上、特定組織再編成発行手続は募集の概念に含まれ、他方、これに該当しない組織再編成発行手続は募集に該当しないこととされている(法4条1項本文)。
この制度変更は、特定組織再編成発行手続について募集と同様の開示規制を新たに課すこととした(パブコメ回答118頁2番参照)だけにとどまらず、合併等についても投資者保護の観点から有価証券の募集に該当する場合があるという考え方(Gパブコメ回答36頁29番参照)に法令立案担当者の見解が変更されたことを意味するようである。たとえば、外国会社による外国法に基づく組織再編成行為であっても有価証券がわが国において発行される場合には、有価証券の取得の申込みの勧誘に該当しうるものとされている(同前)。
また、従来、少人数私募による場合、上記の組織再編成による場合などにおける「募集によらないで取得される株券」の総額1億円以上の発行については、有価証券通知書の提出が必要とされていたが(削除された旧開示府令6条、旧開示府令ガイドライン4-19から4-21まで)、金融商品取引法では、特定募集等(法4条4項)に該当する場合のみ、有価証券通知書の提出が必要となる。
Ⅱ 第二項有価証券と開示規制
1 みなし有価証券に開示規制が適用される場合 第一項有価証券と異なり、法2条2項各号に掲げる信託の受益権、合同会社などの社員権、集団投資スキーム持分などの有価証券とみなされる権利である第二項有価証券については、それぞれ、信託財産に属する資産の価額の総額、出資総額、集団投資スキーム持分に係る権利を有する者が出資または拠出した財産の価額の合計額などの50%を超える額を有価証券に対する投資に充てるもの(有価証券投資事業権利等)のみが、開示規制の対象となる(法3条3号)。
有価証券投資事業権利等に係る具体的な開示内容は、特定有価証券開示府令により定められている(令2条の13第7号)。ただし、令1条の3の4に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権については、学校法人等の財務内容が投資者に有用な情報であることから、開示府令により具体的な開示内容が定められている(令2条の13第7号)。
なお、次の権利を含む一定の権利は、有価証券投資事業権利等から除外されており、開示規制の適用除外とされている。
① いわゆる商品ファンドのうち、一の法人への出資を通じて商品投資を行うもの(令2条の9第1項1号・2項、令2条の10第1項1号ヌ・3項など)
② 年金関係の信託の受益権(令2条の10第1項1号イからトまで)
2 有価証券の募集と売出しの概念 (1)第一項有価証券との相違点 第一項有価証券と異なり、第二項有価証券については、有価証券の所有者を基準とした新たな有価証券の募集および売出しの概念が設けられている。
具体的には、第二項有価証券に関して、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得勧誘のうち、その取得勧誘に応じることにより500名以上の者が当該取得勧誘に係る有価証券を所有することとなる場合をいい(法2条3項3号・令1条の7の2)、「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付け勧誘等のうち、その売付け勧誘等に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を500名以上の者が所有することとなる場合をいう(法2条4項2号・令1条の8の2)。
図表2に記載したとおりであるが、大要、第二項有価証券の募集または売出しにおいては、次の点が第一項有価証券と異なる。
① 有価証券の所有者の数が募集または売出しに該当するか否かの基準となっていること
② プロ私募の概念が存在しないこと(したがって、プロも含めて有価証券の所有者として計算されること)
③ 私募とする場合に法律上は転売制限の要件が要求されないこと
④ 同種の新規発行証券に関する6か月の期間通算(令1条の6)に相当する規定がないこと
⑤ 売出しにおいては「均一の条件」が要件とはなっていないこと
その結果、相当に大きな違いが生じる。たとえば、1,000人に第二項有価証券の取得勧誘を行った場合であっても、当該取得勧誘に係る有価証券の所有者が499名以下となる場合には、第二項有価証券の私募として届出義務は発生しない(法4条1項参照)。したがって、499個以下に限定された第二項有価証券の取得勧誘を行う場合には、基本的には有価証券届出書を提出することは不要となる。
また、500個以上の第二項有価証券の取得勧誘を行うような場合であっても、取得者が499名となった時点において取得勧誘を停止すれば、第二項有価証券の募集には該当しないこととなる。
(2)当初意図と異なる販売結果となった場合の対応 募集または売出しの判断は、取得勧誘または売付け勧誘等を開始しようとする時点においてなされるため、当該時点において500名以上の者が第二項有価証券を所有することとなる見込みがある場合には募集または売出しに該当する(パブコメ回答30頁55番参照)。
当初500名以上の者に第二項有価証券を所有させる意図を有していたことから有価証券届出書を提出していたものの、結果として499名以下の者に対してしか第二項有価証券を販売できなかった場合には、有価証券届出書を提出した者は、遅滞なく、当該有価証券届出書を取り下げる旨を記載した「届出の取下げ願い」を関東財務局に提出するものとされている(特定有価証券開示ガイドライン4-2)。この結果、同日において有価証券通知書の提出があったものとみなされ、当該有価証券は、法24条5項の規定により準用される同条1項3号に規定する有価証券には該当せず、有価証券報告書の提出などの継続開示義務が発生しないこととなる(特定有価証券開示ガイドライン4-3)。
一方、取得勧誘または売付け勧誘等を開始しようとする時点においては499名以下の者に第二項有価証券を所有させる意図を有していたところ、その販売が好調であったため、500名以上の者に販売したい場合には、届出がなされていないことから、取得者が499名となったところで一旦販売を停止するほかない。停止せずに取得勧誘または売付け勧誘等を続け、有価証券の所有者が500名以上となってしまった場合には、無届け勧誘に該当し、勧誘者は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処せられ、または併科される(法197条の2第1号)。また、法人の両罰規定では、5億円以下の罰金とされている(法207条1項2号)。
それでは、当該有価証券をさらに販売したい場合には、どのようにすべきか。
第二項有価証券の募集については、前述のとおり、令1条の6の規定のような6か月以内の同種の新規発行証券の取得勧誘についての人数通算の規定がないこと、「その取得勧誘」または「その売付け勧誘等」に関して有価証券の所有者の人数を数えるものとされていることから、所有者の人数は一連の取得勧誘または売付け勧誘等ごとに判断すればよいと解される。
したがって、以前の取得勧誘または売付け勧誘等と異なるものと評価されるような形態で取得勧誘または売付け勧誘等を開始すれば、後の取得勧誘または売付け勧誘等の取得者の人数は別に計算される。ここで重要なのは、後から追加で行われる取得勧誘または売付け勧誘等が、以前のものと異なるものと評価されるような形態で行われることが必要なことである。
たとえば、以前の勧誘を中止した上で別の払込期日を定めて別途勧誘を開始するなどの適切な措置をとらない場合には、当初の取得勧誘または売付け勧誘等を開始しようとする時点から500名以上に有価証券を所有させる意図があったものとして、これについて無届け勧誘として前述の刑事罰の対象となる可能性がある点に注意が必要である(パブコメ回答30頁55番参照)。
また、たとえば、第二項有価証券の取得勧誘の結果として300名の者が有価証券の所有者となり、これと同時に売付け勧誘等の結果として300名の者に有価証券を所有させた場合には、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断されるべきであるが、基本的にはそれぞれ有価証券の募集と売出しには該当しないものされている(パブコメ回答29頁54番参照)。
なお、開示規制との関係においては、前述のとおり私募要件として第二項有価証券に転売制限を付すことは求められていないものの、集団投資スキーム持分の自己勧誘に関して、第二種金融商品取引業の登録を行わず、届出業務である適格機関投資家等特例業務として私募を行うためには、一定の者を相手方としてはならないとされるとともに、次の転売制限などの要件を満たす必要がある(法63条1項1号、令17条の12第3項)。
① 取得者が適格機関投資家である場合には、適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡禁止の転売制限が付されていること
② 取得者が適格機関投資家以外の一般投資家である場合には、一括譲渡以外の譲渡禁止の転売制限が付されていることおよび当該一般投資家の人数と6か月以内に発行された同種の新規発行権利の取得者である一般投資家の人数との合計が49名以下となること
この49名の数え方については、前述の開示規制における少人数私募の場合とは異なり、同一の投資家が複数回出資していたとしても1名と数えればよいとされている(パブコメ回答544頁29番参照)。
3 継続開示義務 第二項有価証券の募集または売出しに際して届出が行われた場合には、当該有価証券に係る特定期間(信託の計算期間または発行者の事業年度)の末日から3か月以内に有価証券報告書を提出することなどの継続開示義務が生ずる(法24条5項・1項3号)。
一方、届出が行われなかった場合においても、その第二項有価証券(法2条2項1号、3号および5号に掲げる権利に限る)の所有者が当該第二項有価証券に係るある特定期間の末日において500名以上となる場合には、継続開示義務が生ずる(法24条5項・1項4号、令4条の2第4項・5項)。したがって、私募を複数回行う場合であっても、継続開示義務の発生を避けたいときには注意を要する。
また、前述のとおり、第二項有価証券の私募として転売制限は開示規制上の要件とはなっていないものの、第二項有価証券の転売や分割が可能であると所有者が500名以上となってしまうことがあることから、継続開示義務の発生を避けるためには第二項有価証券の私募においても、実務上は499個以下としたうえで分割禁止とするか、499名以上が所有することとならないような転売制限を設ける必要がある。
Ⅲ 組織再編成と開示規制
1 組織再編成における届出義務 金融商品取引法は、一定の組織再編成(合併、会社分割、株式交換および株式移転をいう)に関して有価証券の発行者に当該有価証券やその発行者に関する情報の開示を義務付けている。
その概要は、図表3記載のとおりであるが、具体的には、次のいずれにも該当する場合、当該組織再編成に関して、「特定組織再編成発行手続」(法2条の2第4項)または「特定組織再編成交付手続」(法2条の2第5項)として、原則として届出が義務付けられる(法4条1項2号)。
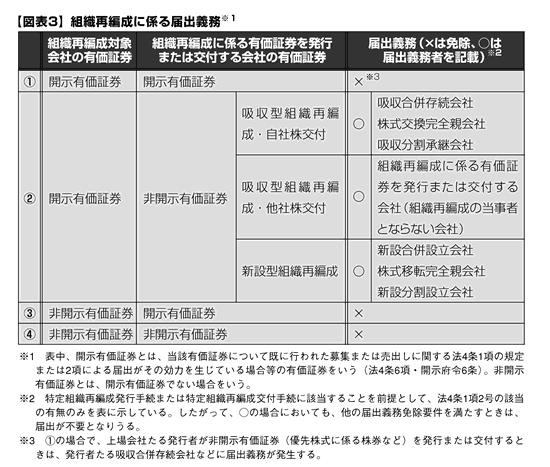
① 組織再編成対象会社(吸収合併消滅会社、新設合併消滅会社、吸収分割会社、新設分割会社、株式交換完全子会社および株式移転完全子会社をいう)の株券、新株予約権証券もしくは新株予約権付社債券またはこれらのいずれかを原券とする預託証券もしくは受託有価証券とする有価証券信託受益証券(令2条の3第3号)(以下「株券等」という)に関して、「開示が行われている場合」
② 組織再編成により発行または交付される有価証券に関して、開示が行われない場合
特定組織再編成発行手続または特定組織再編成交付手続に該当するか否かは、組織再編成対象会社株主等(法2条の2第4項1号)の人数により判断される。
具体的には、組織再編成発行手続または組織再編成交付手続に関して第一項有価証券が50名以上(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く)に発行または交付される場合、第二項有価証券が500名以上に発行または交付される場合には、特定組織再編成発行手続または特定組織再編成交付手続に該当する。この組織再編成対象会社株主等の人数は、前述の組織再編成対象会社が発行する株券等の所有者(実所有者の数)を合算して計算される。
なお、特定組織再編成手続または特定組織再編成交付手続に係る届出については、目論見書の交付は不要とされているが(法4条1項本文第1括弧書・3項本文第1括弧書参照)、これは組織再編成自体に関する組織再編成対象会社株主等の保護は会社法上の手続で足りるという考え方によるものと思われる。
2 届出義務が発生しない場合 届出義務が発生する場合については図表3のとおりであるが、表において原則として届出義務が発生する場合であっても、発行価額または売出価額の総額が1億円未満である募集または売出しで内閣府令で定めるもの(法4条1項5号、開示府令2条3項)に該当する場合には届出義務が免除される。
組織再編成においては、発行価額または売出価額の総額は、新設型組織再編成であれば、新設会社の株主資本または承継純資産により計算されるようであるから、当該金額が1億円未満である募集または売出しで、開示府令2条3項各号に該当するもの以外の募集または売出しである場合には、新設型組織再編成であっても、届出義務が免除される場合がありうるものと思われる4。
注意を要するのは、組織再編成対象会社株主等が当該有価証券の交付を受けない場合であっても、上場会社が①新設分割を行うときや②吸収分割を行い(非継続開示会社の)承継会社の株式の交付を受けるときは、組織再編成対象会社株主等の数が50名以上であるため「特定組織再編成」の定義に該当し(法2条の2第4項1号、令2条の4)、組織再編成に係る届出義務の免除要件にも該当しないため(法4条1項2号)、承継純資産額が1億円未満である場合(同項5号)を除き、届出義務が発生することである。
新設会社や承継会社について届出義務が発生すると継続開示が必要となるが(法24条1項3号)、同項ただし書の3つ目の要件により、事業年度末の株主数が25名未満ということで当局の承認を受ければ、その申請後5年間、事業年度末の株主名簿などを提出することを条件として、継続開示義務の中断が認められる(令4条2項3号・3項、開示府令16条)。またその後、法24条1項ただし書の1つ目の要件により、5年間の事業年度末の所有者数が300名未満ということで、継続開示義務免除の承認が受けられる。
また、有価証券届出書の提出義務は、有価証券が発行または交付される場合において要求されるものであることから、組織再編成により有価証券が発行または交付されない場合にも、法4条の規定による届出義務が生じることはない。したがって、たとえば、金商法上の開示会社が分割会社としてその完全子会社に会社分割を行い、当該会社分割に際して株券等の発行または交付が行われないような場合には、有価証券届出書の提出義務が生ずることはない。
3 組織再編成に係る有価証券届出書の内容 組織再編成に関して発行または交付される有価証券が、開示府令に基づき開示される株券等である場合には、開示府令第2号の6様式(内国会社)と開示府令第2号の7様式(内国会社の新規公開)および第7号の4様式(外国会社)の3種類の様式が適用される。
一方、組織再編成に関して発行または交付される有価証券が、投資信託の受益証券などの特定有価証券(法5条1項)である場合には、特定有価証券開示府令10条1項各号に掲げる様式に組織再編成に係る記載項目を加えたものが開示されることとなる。
具体的には、組織再編成に係る主な6つの記載項目の内容は次のとおりである。
① 組織再編成の概要、目的等
② 組織再編成当事会社の概要
③ 組織再編成の契約の内容、割当ての内容およびその算定根拠
④ 組織再編成に関する手続
⑤ 統合財務情報(組織再編成後の主要な経営指標等)
⑥ 組織再編成対象会社の会社情報
会社法においては、平成19年5月1日に施行された合併等の対価柔軟化に対応するために改正された会社法施行規則において株主保護の観点から事前備置書類の拡充(同規則182条など)が行われていることから、その開示内容と有価証券届出書の記載内容が重なることも多いものと考えられるが、有価証券届出書では有価証券の割当比率の算定根拠が求められるなど、必ずしも開示内容が同一ではない。したがって、その記載にあたっては、多くの場合は困難はないものと考えられるが、注意を要する。
また、統合財務情報については、組織再編成後の会社の姿を示すものとして、組織再編成後の主要な経営指標等について記載が求められていることから、その記載については特に注意を要する必要がある5。
4 組織再編成に係る臨時報告書 有価証券報告書提出会社において組織再編成が行われることが「業務執行を決定する機関により決定された場合」には、臨時報告書を提出する必要がある(開示府令19条2項6号の2から7号の4まで。連結会社に係る場合には同項14号の2から15号の4まで)。
組織再編成時に提出される臨時報告書の内容については、平成18年12月13日に施行された開示府令の改正により大幅に記載事項が拡充されているが、平成19年9月30日に施行された開示府令の改正により、いわゆる三角合併に対応した改正も行われている。
具体的には、たとえば株式交換がなされる場合において、当該株式交換において割当てがなされる有価証券が株式交換完全親会社の発行する株式等以外の有価証券である場合には、当該有価証券の発行者についてその商号、資本金の額、事業の内容等の情報を開示することが求められている。
(なかむら・さとし/みねぎし・けんたろう)
脚注 1 「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等」に対するパブリック・コメントの結果に係る平成19年7月31日付公表資料「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(以下「パブコメ回答」という)を参照。
2 中村聡「集団投資スキームに関する規制について~組合型ファンドを中心に~」証券取引法研究会編『証券・会社法制の潮流』(日本証券経済研究所、平成19年)68頁から73頁までを参照。
3 「証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)」に対するパブリック・コメントの結果に係る平成19年10月2日付公表資料「証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)」に対するパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」を参照。
4 有価証券報告書提出会社である株式会社三越および株式会社伊勢丹は、株式移転により完全親会社である株式会社三越伊勢丹ホールディングスを設立するにあたって有価証券届出書の提出を行っており(平成19年10月31日提出)、その募集金額は、株式会社三越および株式会社伊勢丹の前事業年度末における株主資本の額を基準としている。また、近江マウンテンリゾート株式会社は、新設分割を行うにあたって有価証券届出書の提出を行っており(平成19年11月2日提出)、その募集金額は承継純資産の額を基準としている。いずれも、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET(http://info.edinet.go.jp/))を参照。
5 株式会社三越伊勢丹ホールディングスが提出した前述の有価証券届出書においては、統合財務情報の一部について当該情報を記載することにより投資者に誤解を招く情報があると考える情報については有価証券届出書に記載を行わないものとされている。したがって、統合財務情報の一部について正当な理由があれば記載を行わないとの対応が許容される場合もありうるものと考えられる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















