解説記事2008年02月18日 【ニュース特集】 工事進行基準の会計処理と税務上の取扱いは?(2008年2月18日号・№247)
会計基準の見直しで税法も見直し
工事進行基準の会計処理と税務上の取扱いは?
平成20年度税制改正法案では、工事進行基準等に関する見直しが手当てされている。これは、工事契約に関する会計基準が平成19年12月27日に公表されたことに伴うものである(詳細は今号16頁以降参照)。
工事契約に関する会計基準では、原則として工事進行基準に1本化することとされている。しかし、税務上は、会計基準に近いものに見直しが行われるものの、完全には一致していないので留意したい。特集では、会計基準と税務の取扱いの違いを中心にその概要を紹介する。
会計基準のコンバージェンスから工事進行基準に原則1本化 工事契約に関する会計基準が策定された背景には、国際的な会計基準とのコンバージェンスがある。また、長期請負工事に関する収益の計上については、工事進行基準と工事完成基準の選択適用が認められているため、同じような請負工事契約であっても、企業の選択により異なる収益などの認識基準が適用されることにより、財務諸表間の比較可能性が損なわれているという指摘があった。
このため、会計基準を設定する民間団体である企業会計基準委員会(ASBJ)では、原則として工事進行基準を適用する方向で検討を行ってきたものだ。
要件を満たせば優先的に工事進行基準 工事契約に関する会計基準によると、対象となる「工事契約」とは、仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一部の機械装置の製造等基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものをいう。加えて、受注制作のソフトウェアの制作についても対象としている点が特徴といえる。
具体的に工事進行基準が適用されるケースとは、工事契約に関して、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合としている。「成果の確実性が認められる場合」とは、①工事収益総額、②工事原価総額、③決算日における工事進捗度について、信頼性をもって見積ることができることをいい、この場合には、工事進行基準に基づいて、当該工事契約に係る工事収益および工事原価を計上することになる。
一方、これらの要件を満たさない場合には、工事完成基準に基づき、工事契約に係る工事収益および工事原価を計上することになる。したがって、前記の要件を満たす場合には工事進行基準が優先して適用されることになる。
平成20年度税制改正の要綱(抜粋) 工事収益の計上方法等について、次のとおり見直しを行う。
(1)工事進行基準によるべき長期大規模工事の範囲について、工事期間要件を2年以上から1年以上に、請負金額要件を50億円以上から10億円以上に、それぞれ見直す。
(2)長期大規模工事以外の工事で損失が生ずると見込まれるものについて、工事進行基準を適用することができることとする。
(3)工事進行基準の対象に、ソフトウエアの受注制作を加える。
(4)工事進行基準の適用により計上した未収金は、その発注者を債務者とする金銭債権として、貸倒引当金制度等を適用することとする。
(5)その他所要の措置を講ずる。
税務上は工事期間が1年以上、請負対価の額が10億円以上に この工事契約に関する会計基準が策定されたことに伴い、平成20年度税制改正法案では、工事進行基準等の見直しが措置されている(今号35頁の新旧対照表を参照)。
現行の法人税法において、工事進行基準が強制適用されるのは、①工事期間が2年以上であること、②工事の請負対価の額が50億円以上であること、③工事契約において請負対価の2分の1以上が目的物の引渡期日から1年経過日後に支払われる旨が定められていないことといった一定規模の長期大規模工事とされている(法人税法64条1項、法人税法施行令129条1項、2項)。それ以外は工事完成基準との選択適用が認められている。また、受注制作のソフトウェアの制作については、工事の請負工事の対象外とされている。
工事進行基準の要件以外は会計基準に 平成20年度税制改正では、工事期間が1年以上、工事の請負対価の額が10億円以上に引き下げられる見通しだ。工事契約に関する会計基準では、前述したとおり、工事収益総額、工事原価総額、決算日における工事進捗度について、信頼性をもって見積ることができれば、工事進行基準の適用が求められるため、若干の齟齬が生じることになる。
ただし、工事進行基準の対象にソフトウェアの受注制作を加えるなど、他の見直しについては、工事契約に関する会計基準に合わせたものとなっている。長期大規模工事以外の工事で損失が生ずると見込まれるものについても、これまでは工事完成基準が適用されていたが、工事進行基準との選択適用が可能になっている(下図参照)。
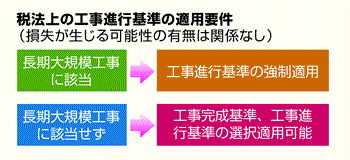
工事進行基準の要件のハードルが下がる 現行の工事進行基準の強制適用は、たとえば、工事の請負対価の額が50億円以上とされているため、50億円未満の中小規模工事の場合については、経理処理上の手間から多くの企業が工事完成基準を適用しているといわれている。
しかし、平成20年4月1日以後に着手される工事契約については、10億円以上に引き下げられるなど、工事進行基準が適用される要件のハードルが低くなる。このため、これまで以上に工事進行基準の適用の範囲が拡がることになり、税負担の前倒し(利益の早期計上)や事務負担が増えることになる。
適用時期は? 工事契約に関する会計基準については、平成21年4月1日以後開始する事業年度から適用することとされている(早期適用可能)。
一方、税法上の適用時期についても基本的に会計基準に合わせたものとなっている。具体的には、施行日(平成20年4月1日)以後開始する各事業年度において着手する工事について適用されることになるが、施行日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度において着手する工事については、現行の長期大規模工事を除き、これまでどおり工事完成基準が経過措置により認められている(附則19条、前頁参照)。
(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第19条 新法人税法第64条の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において着手する同条第1項に規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において着手した旧法人税法第64条第1項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
2 前項に規定する経過措置工事とは、施行日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度において、法人が請負をする工事(新法人税法第64条第1項に規定する工事をいう。)で当該事業年度に着手するもの(当該事業年度中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下この項において「着手工事」という。)のうち当該事業年度終了の時において同条第1項に規定する長期大規模工事に該当するもの(当該終了の時において旧法人税法第64条第1項に規定する長期大規模工事に該当するもの及びその進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて当該事業年度の確定した決算(新法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算)において新法人税法第64条第2項に規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該着手工事をいう。
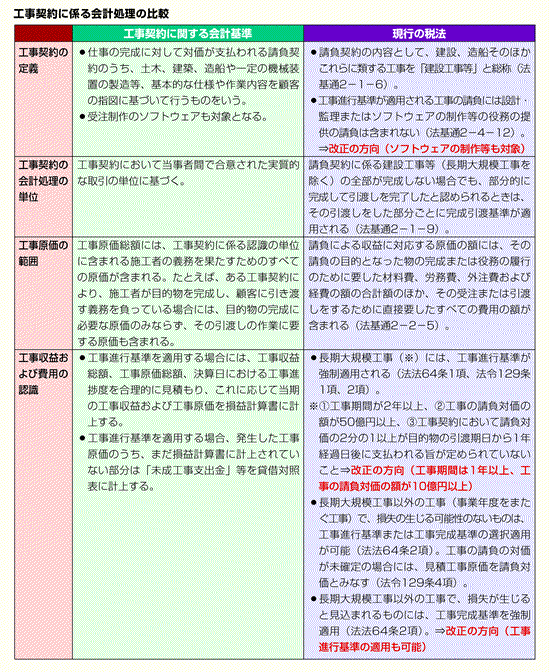
工事進行基準の会計処理と税務上の取扱いは?
平成20年度税制改正法案では、工事進行基準等に関する見直しが手当てされている。これは、工事契約に関する会計基準が平成19年12月27日に公表されたことに伴うものである(詳細は今号16頁以降参照)。
工事契約に関する会計基準では、原則として工事進行基準に1本化することとされている。しかし、税務上は、会計基準に近いものに見直しが行われるものの、完全には一致していないので留意したい。特集では、会計基準と税務の取扱いの違いを中心にその概要を紹介する。
会計基準のコンバージェンスから工事進行基準に原則1本化 工事契約に関する会計基準が策定された背景には、国際的な会計基準とのコンバージェンスがある。また、長期請負工事に関する収益の計上については、工事進行基準と工事完成基準の選択適用が認められているため、同じような請負工事契約であっても、企業の選択により異なる収益などの認識基準が適用されることにより、財務諸表間の比較可能性が損なわれているという指摘があった。
このため、会計基準を設定する民間団体である企業会計基準委員会(ASBJ)では、原則として工事進行基準を適用する方向で検討を行ってきたものだ。
要件を満たせば優先的に工事進行基準 工事契約に関する会計基準によると、対象となる「工事契約」とは、仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一部の機械装置の製造等基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものをいう。加えて、受注制作のソフトウェアの制作についても対象としている点が特徴といえる。
具体的に工事進行基準が適用されるケースとは、工事契約に関して、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合としている。「成果の確実性が認められる場合」とは、①工事収益総額、②工事原価総額、③決算日における工事進捗度について、信頼性をもって見積ることができることをいい、この場合には、工事進行基準に基づいて、当該工事契約に係る工事収益および工事原価を計上することになる。
一方、これらの要件を満たさない場合には、工事完成基準に基づき、工事契約に係る工事収益および工事原価を計上することになる。したがって、前記の要件を満たす場合には工事進行基準が優先して適用されることになる。
平成20年度税制改正の要綱(抜粋) 工事収益の計上方法等について、次のとおり見直しを行う。
(1)工事進行基準によるべき長期大規模工事の範囲について、工事期間要件を2年以上から1年以上に、請負金額要件を50億円以上から10億円以上に、それぞれ見直す。
(2)長期大規模工事以外の工事で損失が生ずると見込まれるものについて、工事進行基準を適用することができることとする。
(3)工事進行基準の対象に、ソフトウエアの受注制作を加える。
(4)工事進行基準の適用により計上した未収金は、その発注者を債務者とする金銭債権として、貸倒引当金制度等を適用することとする。
(5)その他所要の措置を講ずる。
税務上は工事期間が1年以上、請負対価の額が10億円以上に この工事契約に関する会計基準が策定されたことに伴い、平成20年度税制改正法案では、工事進行基準等の見直しが措置されている(今号35頁の新旧対照表を参照)。
現行の法人税法において、工事進行基準が強制適用されるのは、①工事期間が2年以上であること、②工事の請負対価の額が50億円以上であること、③工事契約において請負対価の2分の1以上が目的物の引渡期日から1年経過日後に支払われる旨が定められていないことといった一定規模の長期大規模工事とされている(法人税法64条1項、法人税法施行令129条1項、2項)。それ以外は工事完成基準との選択適用が認められている。また、受注制作のソフトウェアの制作については、工事の請負工事の対象外とされている。
工事進行基準の要件以外は会計基準に 平成20年度税制改正では、工事期間が1年以上、工事の請負対価の額が10億円以上に引き下げられる見通しだ。工事契約に関する会計基準では、前述したとおり、工事収益総額、工事原価総額、決算日における工事進捗度について、信頼性をもって見積ることができれば、工事進行基準の適用が求められるため、若干の齟齬が生じることになる。
ただし、工事進行基準の対象にソフトウェアの受注制作を加えるなど、他の見直しについては、工事契約に関する会計基準に合わせたものとなっている。長期大規模工事以外の工事で損失が生ずると見込まれるものについても、これまでは工事完成基準が適用されていたが、工事進行基準との選択適用が可能になっている(下図参照)。
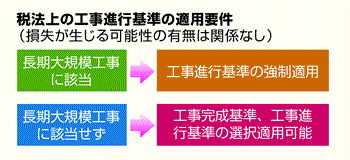
工事進行基準の要件のハードルが下がる 現行の工事進行基準の強制適用は、たとえば、工事の請負対価の額が50億円以上とされているため、50億円未満の中小規模工事の場合については、経理処理上の手間から多くの企業が工事完成基準を適用しているといわれている。
しかし、平成20年4月1日以後に着手される工事契約については、10億円以上に引き下げられるなど、工事進行基準が適用される要件のハードルが低くなる。このため、これまで以上に工事進行基準の適用の範囲が拡がることになり、税負担の前倒し(利益の早期計上)や事務負担が増えることになる。
適用時期は? 工事契約に関する会計基準については、平成21年4月1日以後開始する事業年度から適用することとされている(早期適用可能)。
一方、税法上の適用時期についても基本的に会計基準に合わせたものとなっている。具体的には、施行日(平成20年4月1日)以後開始する各事業年度において着手する工事について適用されることになるが、施行日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度において着手する工事については、現行の長期大規模工事を除き、これまでどおり工事完成基準が経過措置により認められている(附則19条、前頁参照)。
(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第19条 新法人税法第64条の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において着手する同条第1項に規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において着手した旧法人税法第64条第1項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
2 前項に規定する経過措置工事とは、施行日から平成21年3月31日までの間に開始する各事業年度において、法人が請負をする工事(新法人税法第64条第1項に規定する工事をいう。)で当該事業年度に着手するもの(当該事業年度中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下この項において「着手工事」という。)のうち当該事業年度終了の時において同条第1項に規定する長期大規模工事に該当するもの(当該終了の時において旧法人税法第64条第1項に規定する長期大規模工事に該当するもの及びその進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて当該事業年度の確定した決算(新法人税法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算)において新法人税法第64条第2項に規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該着手工事をいう。
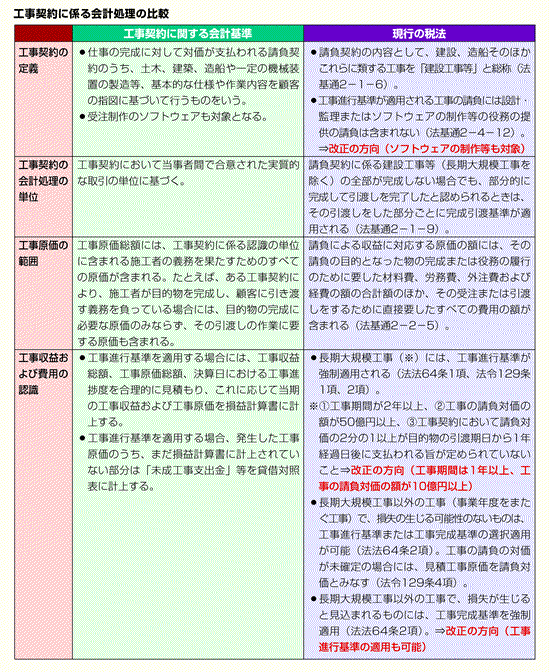
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















