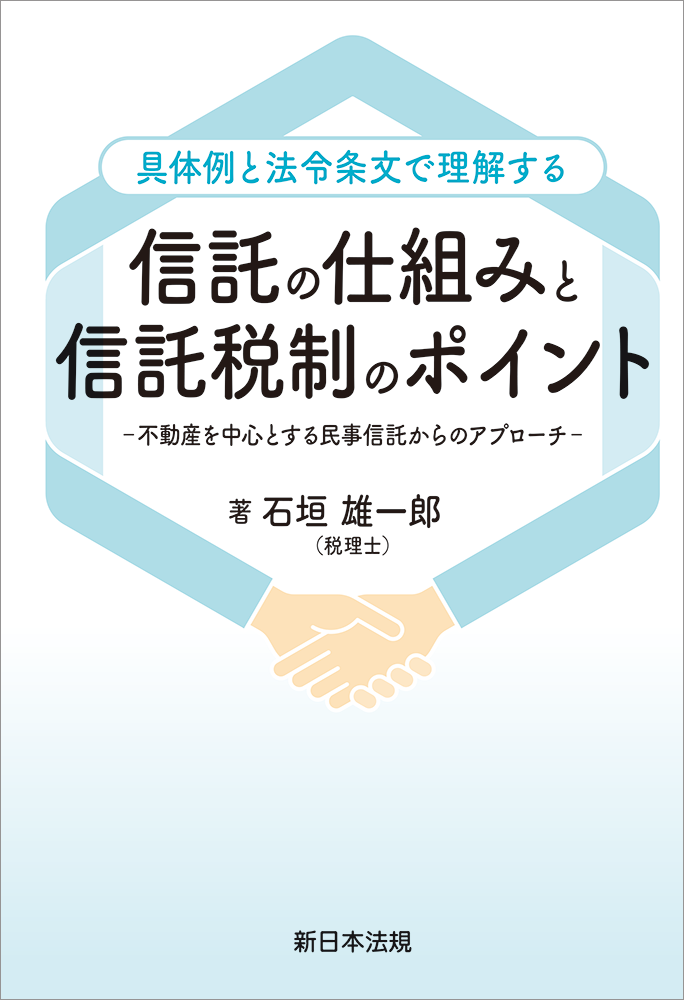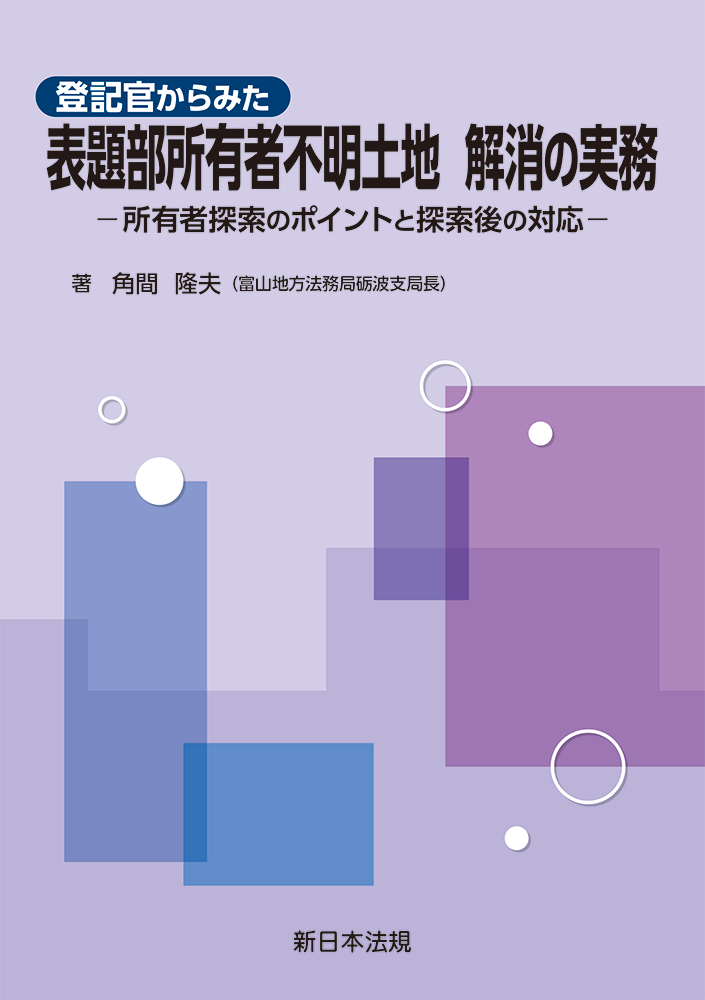解説記事2008年09月01日 【実務解説】 買収防衛策に関する経済産業省「企業価値研究会報告」をめぐって(2008年9月1日号・№272)
実務解説
買収防衛策に関する経済産業省「企業価値研究会報告」をめぐって
(社)日本経済団体連合会経済第二本部長 阿部泰久/経済第二本部 牧村恵利
Ⅰ はじめに
経済産業省の企業価値研究会(座長:神田秀樹東京大学大学院教授)は、6月30日に「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」と題する報告書を公表した。
今回の報告書は、2005年5月27日に発表された「企業価値研究会報告書~公正な企業社会のルール形成に向けた提案~」(以下、2005年報告書)および経産省・法務省による「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」(以下、指針)公表以後の実務の進展や市場の変化を踏まえ、買収防衛策に関する政策的な提言を取りまとめたものである。
今回の報告書については、公表直後から様々な批評・批判が寄せられ、これに対する反論もなされている。そこで、本稿ではこの報告書の概要を紹介するとともに、これをめぐる様々な議論について検証する。
Ⅱ 報告書の概要
まず、2005年報告書について確認しておきたい。2004年9月に企業価値研究会が発足当時、市場の抵抗や会社法上の疑念から企業は買収防衛策の導入を躊躇しており、買収防衛策は会社法上およそ認められないとする主張さえなされていた。そのような状況の中で2005年の報告書・指針は、「良い買収」は実現されるべきで「悪い買収」は実現されるべきではない、その良し悪しは企業価値を向上させるか毀損させるかで判断され、いわゆる友好的か敵対的かとは無関係であるとの考え方に基づき、買収防衛策の導入について会社法上適法と考えられる領域を明らかにした、「平時」導入に関する画期的なガイドラインであった。
その後、この指針をよりどころに上場企業の1割強が何らかの形で買収防衛策を導入する一方、いくつかの敵対的買収がなされたことで、裁判実務も動き始め、適法と認められる事例も現れた(表1参照)。
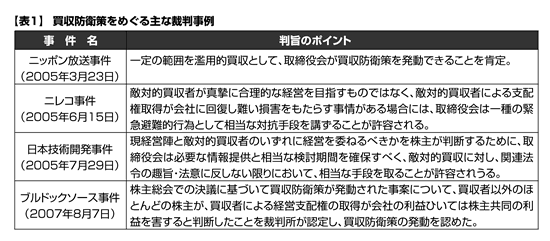
しかし、ブルドックソース事件を機に、実際に敵対的な買収者が現れた以後の防衛策の「有事」導入の可否や、買収者に対する金銭補償の是非をめぐって、実務に混乱が生じたため、今回の報告書では、2005年報告書・指針の基本的考え方を維持しつつ、防衛策の発動の局面に重点を置いて、まず前半で市場における評価を念頭に置いた「政策論」を提示し、後半において「政策論」と裁判例との関係を「法律論」として整理している。
「政策論」は、次の2つの柱から成っている。
① 買収者に金銭を支払うならば、買収防衛策の発動を誘発し、結果として、必要な時間・情報や交渉機会が確保された上で株式を買収者に売却する機会を株主から失わせ、健全な資本市場の育成の妨げとなるので好ましくない。
② 株主総会に付議すれば万能とすることは、総会決議を通せる株主構成であれば盤石な防衛体制がとれるという誤ったメッセージを関係者に送りかねず、結果として不合理な株式持合いを助長するおそれもあるから望ましくない。
この2点を踏まえ、「政策論」では買収防衛の実際の場面で、前面に出て買収者と交渉する主体である取締役の主体的判断と説明責任を重視し、情報・時間と交渉機会、そして株主によるインフォームド・ジャッジメントの機会を確保する、すなわち「株主共同の利益」を守ることに主眼を置くべきとする「取締役の行動規範」(表2参照)を8点にわたって整理している。この行動規範は、あくまでも倫理的な規範であり、取締役の法的責任とするものではない。
【表2】取締役の行動規範
① 取締役会は、株主共同の利益の確保・向上に適わない場合にもかかわらず、株主以外の利害関係者の利益に言及することで、買収防衛策によって保護しようとする利益を不明確としたり、自らの保身を目的として発動要件を幅広く解釈してはならない。
② 取締役会は、被買収者の資産を買収者の債務の担保とすることや、被買収者の遊休資産を処分し、その処分利益をもって高配当をさせることが予定されているなど、それのみでは当該買収が株主共同の利益を侵害するとまでは言い難い理由のみをもって、買収防衛策の発動が必要であるとの判断を行ってはならない。
③ 取締役会は、合理的な範囲を超えて買収提案の検討期間をいたずらに引き延ばしたり、意図的に繰り返し延長することによって、株主が買収の是非を判断する機会を奪ってはならない。
④ 取締役会は、当該買収提案が株主共同の利益を向上させるものか否かという観点から、買収条件、買収が株主共同の利益に与える影響等の買収提案の内容や、買収者の属性・資力等について、真摯な検討を行わなければならない。
⑤ 取締役会は、買収条件の改善により当該買収提案が株主共同の利益に資するものとなる可能性がある場合には、買収条件の改善に向けて、買収者との交渉を真摯に行わなければならない。
⑥ 取締役会は、株主共同の利益を向上させる買収提案であると判断した場合には、株主総会で株主の意思を問うまでもなく、直ちに買収防衛策の不発動を決議しなければならない。
⑦ 取締役会は、株主が買収の是非を判断できるよう、買収提案に対する取締役会の評価等について、できるだけ事実に基づいて、株主に対する説明責任を果たさなければならない。
⑧ 取締役会は、特別委員会を設置する場合は、現経営陣からの独立性を実質的に担保するとともに、その勧告内容に従うという判断に関する最終的な責任を負わなければならない。
後半の「法律論」では、買収防衛策に対する考え方として、株主意思の原則および買収者に対する金員などの交付について着目し、(1)株主が買収の是非を適切に判断するための時間・情報や、買収者・被買収者間の交渉機会を確保する場合と、(2)買収提案の内容に踏み込んで実質的に判断を下して防衛策を発動し買収を止める場合に分け、前半で示した「政策論」とこれまでの裁判事例との関係を整理している。
(1)の場合、株主意思の原則との関係において、時間・情報や交渉機会の確保を口実に買収を断念させることを目的とした恣意的な買収防衛策の発動は認められないとする一方、株主が買収の是非を適切に判断するための時間・情報や、買収者・被買収者間の交渉機会を確保するための買収防衛策の導入・発動は認められるとする。買収者に対する金銭等の交付については、買収者が合理的な手続に反し、買収の是非に関する判断を株主が適切に行うための時間・情報や交渉機会の確保を認めないような場合には、買収防衛策の発動に当たり、金銭等の交付を行う必要はないと明示している。
(2)の場合、株主意思の原則との関係では、①株主共同の利益を毀損することが明白である濫用的買収に対しては、株主共同の利益の保護の観点から、取締役会限りの判断により買収防衛策の発動が容認されるとし、②買収提案が株主共同の利益を毀損するかどうか実質判断に基づいて発動する場合は、必要性と相当性の要件を満たす必要があるとし、その判断に当たっては、多数の株主の賛成を得るだけではなく、取締役会の説明責任が果たされたか等の事情を勘案すべきとしている。
買収者に対する金銭等の交付については、①株主共同の利益を毀損することが明白である濫用的買収に対しては、買収防衛策の発動はいわば正当防衛に類し金銭等の交付は必要ないとしている。
次に②買収提案が株主共同の利益を毀損するとの実質的判断に基づいて発動する場合には、必要性と相当性の要件を満たさなければならないが、実質判断が株主の意思に基づくのであれば必要性の要件を満たすと考えられる。また、相当性を満たす論拠として、「危険の引受け」と「損害回避可能性」を挙げている。「危険の引受け」とは、買収開始前に買収防衛策の内容が開示されている場合であれば、買収者は発動による持分比率の希釈化という損害が生じうることを認識しながらあえて買収を開始しているのであるから、こうした損害が発生する危険を買収者が引き受けていると考えられることをいう。「損害回避可能性」とは、買収者が取締役の選解任等をめぐり株主総会等の場で買収防衛策の発動を争い、そこで自らの提案が自分以外の株主の多数の支持を得られないときに、買収者に買収を撤回・中止する時間が残っていること等によって、買収防衛策の発動による持株比率の希釈化という損害を回避できる可能性をいう。
「危険の引受け」については、導入と発動の間の時差そのものを適法となる論拠とするものであるが、「損害回避可能性」も適法となる論拠としたことで、ブルドックソース事件のように有事に防衛策を導入し、直ちに発動させる場合においても適法となる可能性が生じる。損害回避可能性を満たすためには、①株主総会に発動そのものが付議されている場合、②発動はまだされていないが、防衛策が導入済みであり、取締役の選任(経営陣の交代)を争うことで交代できれば防衛策を消却できる場合、③TOBを撤回できれば損害を受けない場合のいずれかにあてはまること(互いに排他的ではない)が必要と考えられる。
Ⅲ 批判の検証
以上が今回の報告書の概略であるが、同報告書には公表直後から多くの批判がなされている。果たしてそれらの批判が妥当かつ建設的なものか、検証してみたい。
1 企業価値研は方針を転換したのか 今回の報告書は2005年報告書から方針転換がなされたとする指摘が数多くある。2005年当時には奨励していた買収防衛策の導入を、今回の報告書では牽制しているとの主張である。
しかし、方針転換は決してなされていない。2005年報告書以降の実務界、世界の実情の変化に合わせて、取り組むべき問題や考えられる解決策は異なり、重点の置きどころも異なるのは当然であるが、それをもって、根底となる基本的理念が変わったと断ずるのは早計である。
そもそも2005年報告書は、買収防衛策の導入を奨励するものでも、阻もうとするものでもない。2005年当時は、敵対的買収に関する経験が少なく、「何が公正な攻撃方法で何が公正な防衛方法なのかといった点について、企業社会の関係者が共有する行動規範が形成されていない」状態であった。その弊害として、①企業価値向上のメカニズムである敵対的買収の効果が減退する、②ルール不在のために過剰防衛ないし過小防衛の懸念があるとし、「我が国の企業社会が共有すべき、敵対的買収に関する公正なルールの形成を促すこと」としたのが2005年報告書・指針であり、この基本理念は今回の報告書もまったく変わっていない。
もちろん、今回の報告書の中には、産業界の閉鎖性などを指摘する厳しい指摘もある。グローバル化の中で、多様な投資先を賢く受け入れる姿勢を見せなければ、日本の産業界が世界から取り残されることは明白であるし、株主の声を聞く機会も一層重要視していかなければいけないが、その取組みにはかなり企業ごとの差が存在するのも事実である。産業界として、もはや避けて通れない問題として正面から取り組むべき問題といえよう。
2 ブルドックソース事件最高裁決定と抵触するか また、ブルドックソース事件最高裁決定と抵触するとの指摘も多く見られる。
この点、最高裁判所は「抗告人関係者以外のほとんどの既存株主が、抗告人による経営支配権の取得が相手方の企業価値をき損し、相手方の利益ひいては株主共同の利益を害することになると判断したものということができ、この判断は尊重されるべきである」と判示している。
この判断のポイントは、あくまでも金銭賠償したとしても適法となる買収防衛策の発動がありうることを認めた点にあり、買収防衛策発動の要件として金銭賠償が必要とするものでは決してない。企業が現経営陣を守ろうとするあまり、安易な金銭賠償に走り、結果として「悪い買収」に対しても慣行上金銭賠償を強いられるようになることは避けるべきである。
金銭賠償が必要となれば、買収者は何らリスクを負うことなく買収をしかけられることになる中で「企業価値を向上させる良い買収」が果たして促進されるだろうか。金を払ってまで防ぎたいと考えられる「悪い買収(企業価値を毀損する買収)」だけが増えるにすぎないのではないか。大企業がディープポケットとして狙われるのはもちろん、高い技術を持つが株価が低く評価されている中小企業にとっては、金銭賠償が即座に経営危機につながりかねないというリスクもある。
投資の促進は今後の発展のためにも積極的に行わなければいけないが、日本経済の活性化という一義的な目的を見失い、バランスを失した制度を構築してはならない。その意味で、今回の報告書が、買収者への金銭補償が基本的には不要であることを明らかにしたことは極めて有意義であった。
さらに、経済産業省の研究会が、最高裁と必ずしも完全には一致しない見解を示すことへの疑問の声もあるが、この報告書はひとつの見解の提示に過ぎず、これに従ったから裁判でどう判断されるかが保障されるものではない。判断に最終的な権限と責任を持つのは各企業の取締役であり、それぞれの企業の実情を踏まえ、最適な方策を選択し、かつ投資家や株主の理解を得る努力が強く求められるのである。
日本経団連としては、今回の報告書と2005年報告書・指針を合わせて、買収防衛策の導入から発動に至るまでの一通りの法的論点の集約と企業実務へのガイドラインが整ったものと考える。後は、それぞれの企業とくに取締役が、自社にふさわしい対応を行い、個別事例について判例の蓄積を待つことが最善と考える。
(あべ・やすひさ/まきむら・えり)
買収防衛策に関する経済産業省「企業価値研究会報告」をめぐって
(社)日本経済団体連合会経済第二本部長 阿部泰久/経済第二本部 牧村恵利
Ⅰ はじめに
経済産業省の企業価値研究会(座長:神田秀樹東京大学大学院教授)は、6月30日に「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」と題する報告書を公表した。
今回の報告書は、2005年5月27日に発表された「企業価値研究会報告書~公正な企業社会のルール形成に向けた提案~」(以下、2005年報告書)および経産省・法務省による「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」(以下、指針)公表以後の実務の進展や市場の変化を踏まえ、買収防衛策に関する政策的な提言を取りまとめたものである。
今回の報告書については、公表直後から様々な批評・批判が寄せられ、これに対する反論もなされている。そこで、本稿ではこの報告書の概要を紹介するとともに、これをめぐる様々な議論について検証する。
Ⅱ 報告書の概要
まず、2005年報告書について確認しておきたい。2004年9月に企業価値研究会が発足当時、市場の抵抗や会社法上の疑念から企業は買収防衛策の導入を躊躇しており、買収防衛策は会社法上およそ認められないとする主張さえなされていた。そのような状況の中で2005年の報告書・指針は、「良い買収」は実現されるべきで「悪い買収」は実現されるべきではない、その良し悪しは企業価値を向上させるか毀損させるかで判断され、いわゆる友好的か敵対的かとは無関係であるとの考え方に基づき、買収防衛策の導入について会社法上適法と考えられる領域を明らかにした、「平時」導入に関する画期的なガイドラインであった。
その後、この指針をよりどころに上場企業の1割強が何らかの形で買収防衛策を導入する一方、いくつかの敵対的買収がなされたことで、裁判実務も動き始め、適法と認められる事例も現れた(表1参照)。
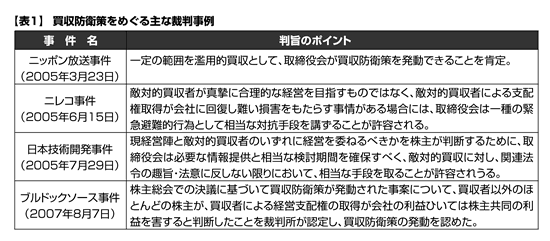
しかし、ブルドックソース事件を機に、実際に敵対的な買収者が現れた以後の防衛策の「有事」導入の可否や、買収者に対する金銭補償の是非をめぐって、実務に混乱が生じたため、今回の報告書では、2005年報告書・指針の基本的考え方を維持しつつ、防衛策の発動の局面に重点を置いて、まず前半で市場における評価を念頭に置いた「政策論」を提示し、後半において「政策論」と裁判例との関係を「法律論」として整理している。
「政策論」は、次の2つの柱から成っている。
① 買収者に金銭を支払うならば、買収防衛策の発動を誘発し、結果として、必要な時間・情報や交渉機会が確保された上で株式を買収者に売却する機会を株主から失わせ、健全な資本市場の育成の妨げとなるので好ましくない。
② 株主総会に付議すれば万能とすることは、総会決議を通せる株主構成であれば盤石な防衛体制がとれるという誤ったメッセージを関係者に送りかねず、結果として不合理な株式持合いを助長するおそれもあるから望ましくない。
この2点を踏まえ、「政策論」では買収防衛の実際の場面で、前面に出て買収者と交渉する主体である取締役の主体的判断と説明責任を重視し、情報・時間と交渉機会、そして株主によるインフォームド・ジャッジメントの機会を確保する、すなわち「株主共同の利益」を守ることに主眼を置くべきとする「取締役の行動規範」(表2参照)を8点にわたって整理している。この行動規範は、あくまでも倫理的な規範であり、取締役の法的責任とするものではない。
【表2】取締役の行動規範
① 取締役会は、株主共同の利益の確保・向上に適わない場合にもかかわらず、株主以外の利害関係者の利益に言及することで、買収防衛策によって保護しようとする利益を不明確としたり、自らの保身を目的として発動要件を幅広く解釈してはならない。
② 取締役会は、被買収者の資産を買収者の債務の担保とすることや、被買収者の遊休資産を処分し、その処分利益をもって高配当をさせることが予定されているなど、それのみでは当該買収が株主共同の利益を侵害するとまでは言い難い理由のみをもって、買収防衛策の発動が必要であるとの判断を行ってはならない。
③ 取締役会は、合理的な範囲を超えて買収提案の検討期間をいたずらに引き延ばしたり、意図的に繰り返し延長することによって、株主が買収の是非を判断する機会を奪ってはならない。
④ 取締役会は、当該買収提案が株主共同の利益を向上させるものか否かという観点から、買収条件、買収が株主共同の利益に与える影響等の買収提案の内容や、買収者の属性・資力等について、真摯な検討を行わなければならない。
⑤ 取締役会は、買収条件の改善により当該買収提案が株主共同の利益に資するものとなる可能性がある場合には、買収条件の改善に向けて、買収者との交渉を真摯に行わなければならない。
⑥ 取締役会は、株主共同の利益を向上させる買収提案であると判断した場合には、株主総会で株主の意思を問うまでもなく、直ちに買収防衛策の不発動を決議しなければならない。
⑦ 取締役会は、株主が買収の是非を判断できるよう、買収提案に対する取締役会の評価等について、できるだけ事実に基づいて、株主に対する説明責任を果たさなければならない。
⑧ 取締役会は、特別委員会を設置する場合は、現経営陣からの独立性を実質的に担保するとともに、その勧告内容に従うという判断に関する最終的な責任を負わなければならない。
後半の「法律論」では、買収防衛策に対する考え方として、株主意思の原則および買収者に対する金員などの交付について着目し、(1)株主が買収の是非を適切に判断するための時間・情報や、買収者・被買収者間の交渉機会を確保する場合と、(2)買収提案の内容に踏み込んで実質的に判断を下して防衛策を発動し買収を止める場合に分け、前半で示した「政策論」とこれまでの裁判事例との関係を整理している。
(1)の場合、株主意思の原則との関係において、時間・情報や交渉機会の確保を口実に買収を断念させることを目的とした恣意的な買収防衛策の発動は認められないとする一方、株主が買収の是非を適切に判断するための時間・情報や、買収者・被買収者間の交渉機会を確保するための買収防衛策の導入・発動は認められるとする。買収者に対する金銭等の交付については、買収者が合理的な手続に反し、買収の是非に関する判断を株主が適切に行うための時間・情報や交渉機会の確保を認めないような場合には、買収防衛策の発動に当たり、金銭等の交付を行う必要はないと明示している。
(2)の場合、株主意思の原則との関係では、①株主共同の利益を毀損することが明白である濫用的買収に対しては、株主共同の利益の保護の観点から、取締役会限りの判断により買収防衛策の発動が容認されるとし、②買収提案が株主共同の利益を毀損するかどうか実質判断に基づいて発動する場合は、必要性と相当性の要件を満たす必要があるとし、その判断に当たっては、多数の株主の賛成を得るだけではなく、取締役会の説明責任が果たされたか等の事情を勘案すべきとしている。
買収者に対する金銭等の交付については、①株主共同の利益を毀損することが明白である濫用的買収に対しては、買収防衛策の発動はいわば正当防衛に類し金銭等の交付は必要ないとしている。
次に②買収提案が株主共同の利益を毀損するとの実質的判断に基づいて発動する場合には、必要性と相当性の要件を満たさなければならないが、実質判断が株主の意思に基づくのであれば必要性の要件を満たすと考えられる。また、相当性を満たす論拠として、「危険の引受け」と「損害回避可能性」を挙げている。「危険の引受け」とは、買収開始前に買収防衛策の内容が開示されている場合であれば、買収者は発動による持分比率の希釈化という損害が生じうることを認識しながらあえて買収を開始しているのであるから、こうした損害が発生する危険を買収者が引き受けていると考えられることをいう。「損害回避可能性」とは、買収者が取締役の選解任等をめぐり株主総会等の場で買収防衛策の発動を争い、そこで自らの提案が自分以外の株主の多数の支持を得られないときに、買収者に買収を撤回・中止する時間が残っていること等によって、買収防衛策の発動による持株比率の希釈化という損害を回避できる可能性をいう。
「危険の引受け」については、導入と発動の間の時差そのものを適法となる論拠とするものであるが、「損害回避可能性」も適法となる論拠としたことで、ブルドックソース事件のように有事に防衛策を導入し、直ちに発動させる場合においても適法となる可能性が生じる。損害回避可能性を満たすためには、①株主総会に発動そのものが付議されている場合、②発動はまだされていないが、防衛策が導入済みであり、取締役の選任(経営陣の交代)を争うことで交代できれば防衛策を消却できる場合、③TOBを撤回できれば損害を受けない場合のいずれかにあてはまること(互いに排他的ではない)が必要と考えられる。
Ⅲ 批判の検証
以上が今回の報告書の概略であるが、同報告書には公表直後から多くの批判がなされている。果たしてそれらの批判が妥当かつ建設的なものか、検証してみたい。
1 企業価値研は方針を転換したのか 今回の報告書は2005年報告書から方針転換がなされたとする指摘が数多くある。2005年当時には奨励していた買収防衛策の導入を、今回の報告書では牽制しているとの主張である。
しかし、方針転換は決してなされていない。2005年報告書以降の実務界、世界の実情の変化に合わせて、取り組むべき問題や考えられる解決策は異なり、重点の置きどころも異なるのは当然であるが、それをもって、根底となる基本的理念が変わったと断ずるのは早計である。
そもそも2005年報告書は、買収防衛策の導入を奨励するものでも、阻もうとするものでもない。2005年当時は、敵対的買収に関する経験が少なく、「何が公正な攻撃方法で何が公正な防衛方法なのかといった点について、企業社会の関係者が共有する行動規範が形成されていない」状態であった。その弊害として、①企業価値向上のメカニズムである敵対的買収の効果が減退する、②ルール不在のために過剰防衛ないし過小防衛の懸念があるとし、「我が国の企業社会が共有すべき、敵対的買収に関する公正なルールの形成を促すこと」としたのが2005年報告書・指針であり、この基本理念は今回の報告書もまったく変わっていない。
もちろん、今回の報告書の中には、産業界の閉鎖性などを指摘する厳しい指摘もある。グローバル化の中で、多様な投資先を賢く受け入れる姿勢を見せなければ、日本の産業界が世界から取り残されることは明白であるし、株主の声を聞く機会も一層重要視していかなければいけないが、その取組みにはかなり企業ごとの差が存在するのも事実である。産業界として、もはや避けて通れない問題として正面から取り組むべき問題といえよう。
2 ブルドックソース事件最高裁決定と抵触するか また、ブルドックソース事件最高裁決定と抵触するとの指摘も多く見られる。
この点、最高裁判所は「抗告人関係者以外のほとんどの既存株主が、抗告人による経営支配権の取得が相手方の企業価値をき損し、相手方の利益ひいては株主共同の利益を害することになると判断したものということができ、この判断は尊重されるべきである」と判示している。
この判断のポイントは、あくまでも金銭賠償したとしても適法となる買収防衛策の発動がありうることを認めた点にあり、買収防衛策発動の要件として金銭賠償が必要とするものでは決してない。企業が現経営陣を守ろうとするあまり、安易な金銭賠償に走り、結果として「悪い買収」に対しても慣行上金銭賠償を強いられるようになることは避けるべきである。
金銭賠償が必要となれば、買収者は何らリスクを負うことなく買収をしかけられることになる中で「企業価値を向上させる良い買収」が果たして促進されるだろうか。金を払ってまで防ぎたいと考えられる「悪い買収(企業価値を毀損する買収)」だけが増えるにすぎないのではないか。大企業がディープポケットとして狙われるのはもちろん、高い技術を持つが株価が低く評価されている中小企業にとっては、金銭賠償が即座に経営危機につながりかねないというリスクもある。
投資の促進は今後の発展のためにも積極的に行わなければいけないが、日本経済の活性化という一義的な目的を見失い、バランスを失した制度を構築してはならない。その意味で、今回の報告書が、買収者への金銭補償が基本的には不要であることを明らかにしたことは極めて有意義であった。
さらに、経済産業省の研究会が、最高裁と必ずしも完全には一致しない見解を示すことへの疑問の声もあるが、この報告書はひとつの見解の提示に過ぎず、これに従ったから裁判でどう判断されるかが保障されるものではない。判断に最終的な権限と責任を持つのは各企業の取締役であり、それぞれの企業の実情を踏まえ、最適な方策を選択し、かつ投資家や株主の理解を得る努力が強く求められるのである。
日本経団連としては、今回の報告書と2005年報告書・指針を合わせて、買収防衛策の導入から発動に至るまでの一通りの法的論点の集約と企業実務へのガイドラインが整ったものと考える。後は、それぞれの企業とくに取締役が、自社にふさわしい対応を行い、個別事例について判例の蓄積を待つことが最善と考える。
(あべ・やすひさ/まきむら・えり)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -