解説記事2008年09月08日 【ニュース特集】 平成21年度における各省庁の税制改正要望を読み解く(2008年9月8日号・№273)
政治状況が不透明のなかで実現性は?
平成21年度における各省庁の税制改正要望を読み解く
各省庁の平成21年度税制改正要望が出揃った。消費税率の見直し等の議論が先送りされる公算が高くなった今、注目すべき大きな税制改正要望は少ない印象だが、住宅ローン減税の延長、証券税制の見直しなど、論点となりそうな項目はやはり多い。また、政府は8月29日、「安心実現のための緊急総合対策」を取りまとめた。税制に関しては、定額控除方式による特別減税の実施、海外子会社利益の国内還流に関する税制措置、住宅ローン減税の延長・拡充などが盛り込まれており、これらの項目についても、どのように実現するか要注目である。
ただし、突如、福田首相が辞任を表明するなど、政治状況は不透明だ。また、昨年と同様、参議院では民主党が第1党というねじれ現象も生じたままである。このため、現時点で平成21年度税制改正がどのようになるか予想もつかない状況だが、今回の特集では、先週(本誌272号4頁以下参照)お伝えした経済産業省以外の省庁の主な税制改正要望事項を紹介する。
Ⅰ 日本版ISAの創設を求める~金融庁
金融庁の平成21年度税制改正要望は「貯蓄から投資へ」の流れを促進するための措置がメインとなっている。証券税制については、平成20年度税制改正でも見直しが行われている(図表1参照)。現行でも制度が複雑との指摘があるなか、どの程度、要望が認められるか未知数だ。
このような状況のなか、金融庁の要望の目玉は、日本版ISA(小口の継続的長期投資非課税制度)の創設である。ISAとは、英国で導入されている個人貯蓄口座のこと。年間7,200ポンド(約154万円)を限度に、同口座内で生じる配当、利子、キャピタルゲインを非課税(ただし、株式等口座にある現金に対する利子は20%の源泉徴収)にするというもの。
金融庁では、小口投資家向けに、毎年一定額まで(たとえば100万円)の上場株式等への投資に対する配当を非課税とすることを要望している。長期安定保有を促す観点から、当面10年間の時限措置としている。毎年の投資限度額を100万円とした場合は、1,000万円までの累積投資が可能になる。
なお、年間の投資限度額の未使用枠は翌年以降に繰越不可とする。また、投資後の売却は自由で、売却時までの配当は非課税となるが、売却部分の再投資は非課税の対象外としている。
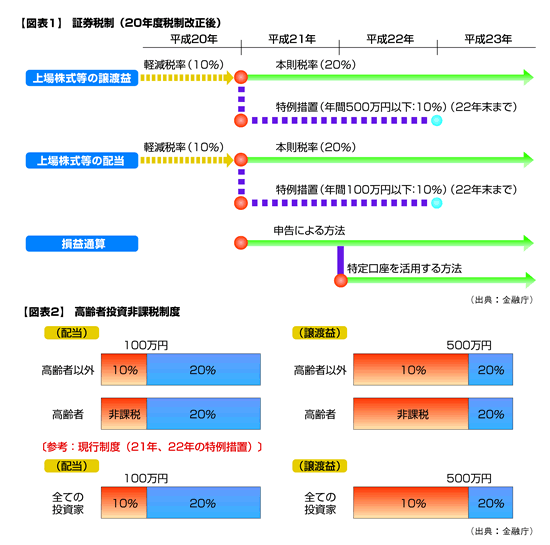
1 損益通算の対象範囲の拡大を また、平成20年度税制改正では、上場株式等の譲渡損失と配当に関して、損益通算が可能になっているが、現金・債券等の利子所得および先物取引に係る雑所得にまで損益通算の対象範囲を拡大することを求めている。
2 高齢者、100万円以下の配当等を非課税へ 高齢者が受け取る上場株式等の100万円以下の配当および500万円以下の譲渡益について、非課税とする高齢者投資非課税制度の創設を要望している(図表2参照)。少なくとも平成21年および22年の2年間とすることを求めている。
なお、現行制度では、配当が100万円を超えた場合には国民健康保険料等の計算に含まれ、配当課税以外の追加負担が発生するが、高齢者投資非課税制度の場合には、100万円部分は国民健康保険料等の計算に含まれず、100万円を超えた部分のみの追加負担に限られるというメリットもある。
しかし、8月28日に開催された自民党財務金融部会・金融調査会合同会議では、同制度に対して、対象を年齢で区切ることや高齢者も所得格差があるため、“金持ち優遇税制”と批判される可能性があるとの指摘がされた模様だ。
3 確定拠出年金の個人拠出容認等を求める 昨年に引き続き、確定拠出年金(401K)に係る個人拠出の容認と拠出限度額の引上げを求めている(図表3参照)。これについては、厚生労働省でも要望している点である。現在、確定拠出年金制度には、企業型と個人型があるが、企業型年金には個人拠出が認められていないなどの制約がある。このため、①企業型確定拠出年金における個人拠出の容認、②個人型確定拠出年金の加入対象者の見直し、③個人型確定拠出年金の拠出限度額の引上げを求めている。
金融庁では、具体的な個人型確定拠出年金の引上げの限度額を明示していないが、厚生労働省では、現行の1.8万円から2.3万円にするよう要望している。
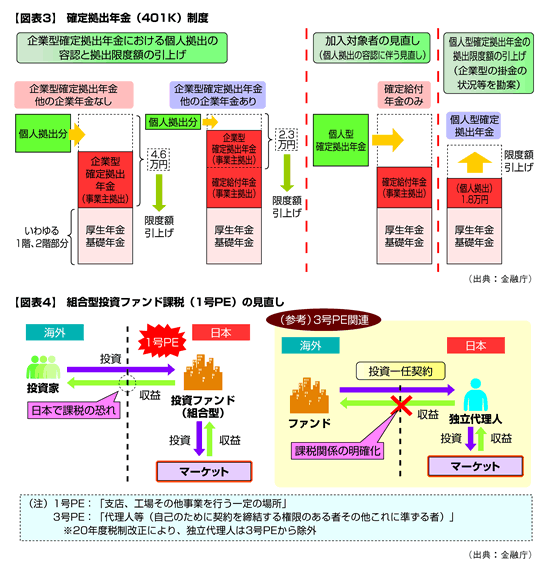
4 1号PEを非課税措置に 対日投資に係る課税関係を明確化するため、組合型投資ファンド課税(1号PE)の見直しも求めている。
海外の投資家が日本で組成された組合型の投資ファンドを通じて投資活動を行う場合、国内の業務執行組合員(資産運用業者)と共同事業を行っているとして、恒久的施設(1号PE)を有するとみなされ、日本での申告・納税義務を負うことになるおそれがある(図表4参照)。このため、海外からの資金がシンガポールなどに流れているといった指摘がされている。
今回の要望では、海外の投資家が国内の組合型投資ファンドを通じて行っている場合であっても、投資家が日本で1号PEを有するとされない措置を講じることとしている。なお、経済産業省でも同様の要望を行っている。
5 生命保険料控除の見直しを求める そのほか、少子高齢化が進むなか、生損保控除を抜本的に見直すことを要望している。平成20年度税制改正でも生損保控除の見直しの検討が行われたが、生保業界、損保業界において要望内容が異なり、見送りとなった経緯がある。
今回の要望(図表5参照)については、①「遺族」「医療」「介護」「老後」の4つの保障区分を設け、主契約の保障内容により、各保障区分への類別を判定する、②各保障区分に控除額上限を設ける(なお、主契約を遺族補償として、これに医療保障等が付加された契約は、「複合化商品」として「遺族補償」に上乗せした控除上限を設ける)、③制度全体の所得控除限度額を設けるというものになっている。
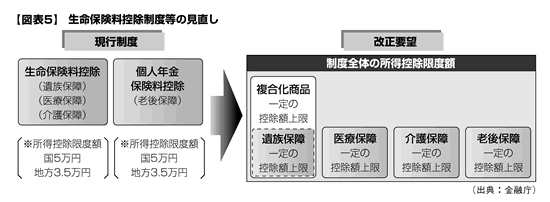
Ⅱ 住宅ローン控除制度の適用期限延長と拡充を~国土交通省
国土交通省の税制改正要望の目玉は、住宅ローン減税制度の延長と拡充だ。「安心実現のための緊急総合対策」にも盛り込まれた項目でもある。適用期限を5年延長するとともに、控除対象借入限度額を現行の2,000万円から3,000万円に拡大し、控除率も引き上げる(図表6参照)。長期優良住宅(200年住宅)や一定の省エネ住宅については、さらに優遇する。なお、耐震基準を満たさない既存住宅をローンにより取得した後に耐震改修工事を行った場合、当該既存住宅の取得費用について住宅ローン減税制度の適用対象とすることなど、適用条件の改善も求めている。
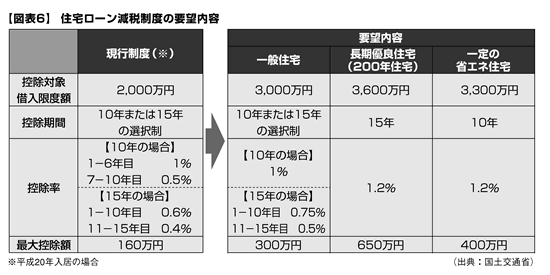
また、住宅ローン減税制度の最大控除額まで所得税額が控除されない者については、一定額を10年間または15年間、個人住民税から減額することを求めている。
1 長期優良住宅の取得費用を税額控除 住宅ローン減税制度の拡充だけでなく、住宅ローンを組まずに住宅を取得する者についても長期優良住宅へと誘導するための優遇措置を創設する。
具体的には、長期優良住宅を新築または取得した場合、通常の住宅よりも上乗せして必要となる費用(上限:500万円)の10%相当額を、3年間、所得税から控除するというもの。また、既存住宅の質の向上に資するリフォーム(一定のバリアフリー改修工事、一定の省エネ改修工事および一定の耐震改修工事)を行った場合に、工事に要した費用(上限:200万円)の10%相当額を当該年度の所得税額から控除するというものである。
2 三世代同居・近居支援の特例措置を創設へ また、今年度の特徴として挙げられるのは、三世代同居・近居支援の特例措置の創設である。
具体的には、二世帯住宅の供給を促進するため、不動産取得税について、課税標準からの控除額を一般住宅の特例(1,200万円控除)よりも拡充し、1,300万円とする。固定資産税については、新築住宅に係る減額特例の減額対象を120m2から200m2相当分に拡充するとしている。
また、親と同居・近居するために住宅の買換え等をした場合において、「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」などの適用要件を緩和することを求めている(図表7参照)。
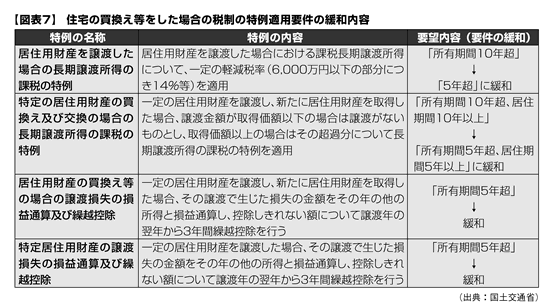
3 買換特例は3年延長を求める そのほか、住宅に係るバリアフリー改修促進税制の5年延長、住宅用家屋の所有権保存登記等に関する特例措置の2年延長、住宅に係る省エネ改修促進税制の5年延長、特定の事業用資産の買換え等の特例措置の3年延長、土地・住宅に係る不動産取得税の特例措置の3年延長、Jリート・SPCに係る不動産取得税の課税標準の特例措置の2年延長、都市再生促進税制の2年延長などを求めている。
Ⅲ 環境税の具体的内容は専門委員会で今秋までに検討~環境省
例年、税制改正での検討課題として挙がる環境税だが、今年も環境省が税制全般の横断的見直しとして要望している。
具体的な内容は、中央環境審議会総合政策・地球環境合同部会のもとに「グリーン税制とその経済分析等に関する専門委員会」を設置し、今秋までに結論を得る考えだ。
そのほかでは、省エネ住宅促進税制の延長や太陽光発電設備等の新エネ設備促進税制等の創設などを求めている。新エネ設備促進税制とは、①省エネ基準を満たす新築住宅に対し、太陽光発電設備を設置する場合、ローン減税のさらなる軽減措置を講じる、②住宅に対し新エネ設備(太陽光発電設備等)を設置する場合、所得税の税額控除の措置を講じるものとしている。
1 農商工等連携法の特例措置の2年延長を 農林水産省では、環境税についての総合的な検討を進めたうえで、必要な森林吸収源対策推進のための税制上の措置を講じることを求めている。
また、平成20年7月21日に施行された農商工等連携法では、同法に基づく農商工等連携事業計画により取得する機械等の特別償却(30%)または税額控除(7%)の特例措置が手当てされているが、この特例措置の2年延長を求めている。
2 内閣府は地域再生事業に係る税制措置の拡充を 内閣府の税制改正要望では、地域再生事業の推進に係る税制上の特例措置の拡充が挙げられる。特定地域再生事業会社に対して行った投資について、現行の投資額控除に加え、所得控除との選択適用を可能にするよう要望している。
また、株式会社地域力再生機構が再生支援をした事業者が資産の評価替えを行った場合の評価損の損金算入を求めている。民事再生等では、債務免除が行われた際に、資産売却による損の実現を待たずに評価損の損金算入ができるほか、期限切れの欠損金の優先利用を認める税制措置が講じられている。この措置について、地域力再生機構が再生支援を行った際にも適用すべきとしている。
そのほか、子育て支援税制(事業所内託児施設に係る法人税の優遇措置)の延長を経済産業省、厚生労働省とともに要望しているほか、三世代同居・近居支援の特例措置の要望を国土交通省、厚生労働省とともに行っている。
3 厚労省はたばこ税の税率引上げ等を求める 厚生労働省では、前述したとおり、企業型確定拠出年金に係る個人拠出の容認と拠出限度額の引上げなどを求めている。
そのほか、医療法人に係る法人税率の軽減措置の創設、たばこ税の税率引上げ、教育訓練費に係る税額控除制度の適用期限の2年延長、障害者自立支援法等の見直しに伴う税制上の所要の措置などを要望している。
平成21年度における各省庁の税制改正要望を読み解く
各省庁の平成21年度税制改正要望が出揃った。消費税率の見直し等の議論が先送りされる公算が高くなった今、注目すべき大きな税制改正要望は少ない印象だが、住宅ローン減税の延長、証券税制の見直しなど、論点となりそうな項目はやはり多い。また、政府は8月29日、「安心実現のための緊急総合対策」を取りまとめた。税制に関しては、定額控除方式による特別減税の実施、海外子会社利益の国内還流に関する税制措置、住宅ローン減税の延長・拡充などが盛り込まれており、これらの項目についても、どのように実現するか要注目である。
ただし、突如、福田首相が辞任を表明するなど、政治状況は不透明だ。また、昨年と同様、参議院では民主党が第1党というねじれ現象も生じたままである。このため、現時点で平成21年度税制改正がどのようになるか予想もつかない状況だが、今回の特集では、先週(本誌272号4頁以下参照)お伝えした経済産業省以外の省庁の主な税制改正要望事項を紹介する。
Ⅰ 日本版ISAの創設を求める~金融庁
金融庁の平成21年度税制改正要望は「貯蓄から投資へ」の流れを促進するための措置がメインとなっている。証券税制については、平成20年度税制改正でも見直しが行われている(図表1参照)。現行でも制度が複雑との指摘があるなか、どの程度、要望が認められるか未知数だ。
このような状況のなか、金融庁の要望の目玉は、日本版ISA(小口の継続的長期投資非課税制度)の創設である。ISAとは、英国で導入されている個人貯蓄口座のこと。年間7,200ポンド(約154万円)を限度に、同口座内で生じる配当、利子、キャピタルゲインを非課税(ただし、株式等口座にある現金に対する利子は20%の源泉徴収)にするというもの。
金融庁では、小口投資家向けに、毎年一定額まで(たとえば100万円)の上場株式等への投資に対する配当を非課税とすることを要望している。長期安定保有を促す観点から、当面10年間の時限措置としている。毎年の投資限度額を100万円とした場合は、1,000万円までの累積投資が可能になる。
なお、年間の投資限度額の未使用枠は翌年以降に繰越不可とする。また、投資後の売却は自由で、売却時までの配当は非課税となるが、売却部分の再投資は非課税の対象外としている。
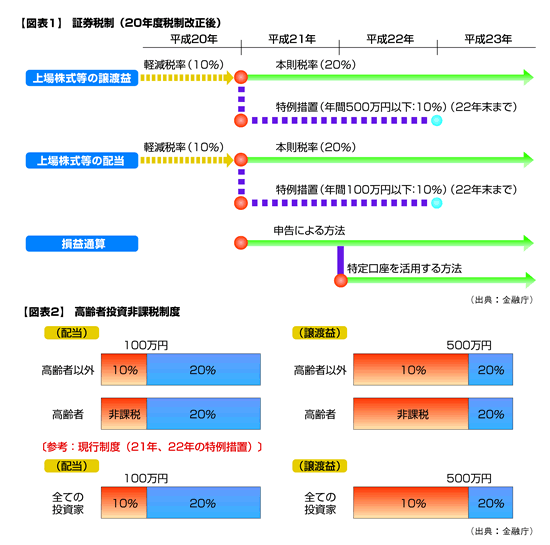
1 損益通算の対象範囲の拡大を また、平成20年度税制改正では、上場株式等の譲渡損失と配当に関して、損益通算が可能になっているが、現金・債券等の利子所得および先物取引に係る雑所得にまで損益通算の対象範囲を拡大することを求めている。
2 高齢者、100万円以下の配当等を非課税へ 高齢者が受け取る上場株式等の100万円以下の配当および500万円以下の譲渡益について、非課税とする高齢者投資非課税制度の創設を要望している(図表2参照)。少なくとも平成21年および22年の2年間とすることを求めている。
なお、現行制度では、配当が100万円を超えた場合には国民健康保険料等の計算に含まれ、配当課税以外の追加負担が発生するが、高齢者投資非課税制度の場合には、100万円部分は国民健康保険料等の計算に含まれず、100万円を超えた部分のみの追加負担に限られるというメリットもある。
しかし、8月28日に開催された自民党財務金融部会・金融調査会合同会議では、同制度に対して、対象を年齢で区切ることや高齢者も所得格差があるため、“金持ち優遇税制”と批判される可能性があるとの指摘がされた模様だ。
3 確定拠出年金の個人拠出容認等を求める 昨年に引き続き、確定拠出年金(401K)に係る個人拠出の容認と拠出限度額の引上げを求めている(図表3参照)。これについては、厚生労働省でも要望している点である。現在、確定拠出年金制度には、企業型と個人型があるが、企業型年金には個人拠出が認められていないなどの制約がある。このため、①企業型確定拠出年金における個人拠出の容認、②個人型確定拠出年金の加入対象者の見直し、③個人型確定拠出年金の拠出限度額の引上げを求めている。
金融庁では、具体的な個人型確定拠出年金の引上げの限度額を明示していないが、厚生労働省では、現行の1.8万円から2.3万円にするよう要望している。
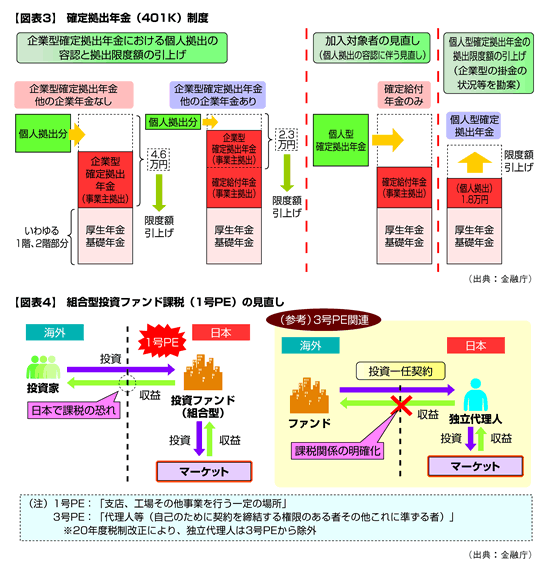
4 1号PEを非課税措置に 対日投資に係る課税関係を明確化するため、組合型投資ファンド課税(1号PE)の見直しも求めている。
海外の投資家が日本で組成された組合型の投資ファンドを通じて投資活動を行う場合、国内の業務執行組合員(資産運用業者)と共同事業を行っているとして、恒久的施設(1号PE)を有するとみなされ、日本での申告・納税義務を負うことになるおそれがある(図表4参照)。このため、海外からの資金がシンガポールなどに流れているといった指摘がされている。
今回の要望では、海外の投資家が国内の組合型投資ファンドを通じて行っている場合であっても、投資家が日本で1号PEを有するとされない措置を講じることとしている。なお、経済産業省でも同様の要望を行っている。
5 生命保険料控除の見直しを求める そのほか、少子高齢化が進むなか、生損保控除を抜本的に見直すことを要望している。平成20年度税制改正でも生損保控除の見直しの検討が行われたが、生保業界、損保業界において要望内容が異なり、見送りとなった経緯がある。
今回の要望(図表5参照)については、①「遺族」「医療」「介護」「老後」の4つの保障区分を設け、主契約の保障内容により、各保障区分への類別を判定する、②各保障区分に控除額上限を設ける(なお、主契約を遺族補償として、これに医療保障等が付加された契約は、「複合化商品」として「遺族補償」に上乗せした控除上限を設ける)、③制度全体の所得控除限度額を設けるというものになっている。
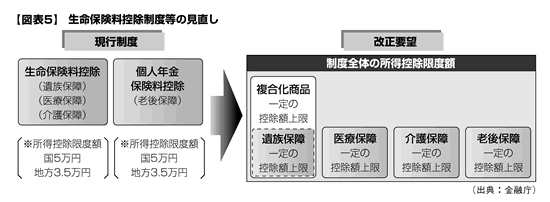
Ⅱ 住宅ローン控除制度の適用期限延長と拡充を~国土交通省
国土交通省の税制改正要望の目玉は、住宅ローン減税制度の延長と拡充だ。「安心実現のための緊急総合対策」にも盛り込まれた項目でもある。適用期限を5年延長するとともに、控除対象借入限度額を現行の2,000万円から3,000万円に拡大し、控除率も引き上げる(図表6参照)。長期優良住宅(200年住宅)や一定の省エネ住宅については、さらに優遇する。なお、耐震基準を満たさない既存住宅をローンにより取得した後に耐震改修工事を行った場合、当該既存住宅の取得費用について住宅ローン減税制度の適用対象とすることなど、適用条件の改善も求めている。
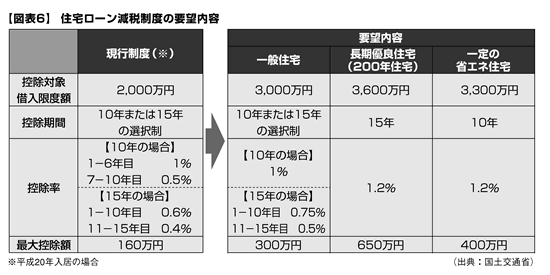
また、住宅ローン減税制度の最大控除額まで所得税額が控除されない者については、一定額を10年間または15年間、個人住民税から減額することを求めている。
1 長期優良住宅の取得費用を税額控除 住宅ローン減税制度の拡充だけでなく、住宅ローンを組まずに住宅を取得する者についても長期優良住宅へと誘導するための優遇措置を創設する。
具体的には、長期優良住宅を新築または取得した場合、通常の住宅よりも上乗せして必要となる費用(上限:500万円)の10%相当額を、3年間、所得税から控除するというもの。また、既存住宅の質の向上に資するリフォーム(一定のバリアフリー改修工事、一定の省エネ改修工事および一定の耐震改修工事)を行った場合に、工事に要した費用(上限:200万円)の10%相当額を当該年度の所得税額から控除するというものである。
2 三世代同居・近居支援の特例措置を創設へ また、今年度の特徴として挙げられるのは、三世代同居・近居支援の特例措置の創設である。
具体的には、二世帯住宅の供給を促進するため、不動産取得税について、課税標準からの控除額を一般住宅の特例(1,200万円控除)よりも拡充し、1,300万円とする。固定資産税については、新築住宅に係る減額特例の減額対象を120m2から200m2相当分に拡充するとしている。
また、親と同居・近居するために住宅の買換え等をした場合において、「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」などの適用要件を緩和することを求めている(図表7参照)。
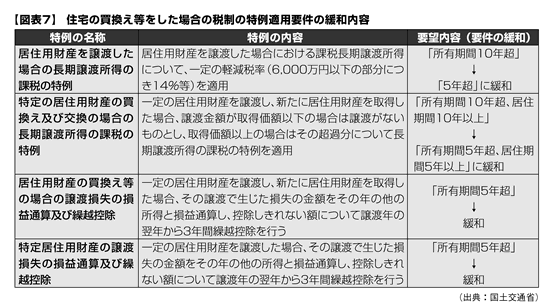
3 買換特例は3年延長を求める そのほか、住宅に係るバリアフリー改修促進税制の5年延長、住宅用家屋の所有権保存登記等に関する特例措置の2年延長、住宅に係る省エネ改修促進税制の5年延長、特定の事業用資産の買換え等の特例措置の3年延長、土地・住宅に係る不動産取得税の特例措置の3年延長、Jリート・SPCに係る不動産取得税の課税標準の特例措置の2年延長、都市再生促進税制の2年延長などを求めている。
Ⅲ 環境税の具体的内容は専門委員会で今秋までに検討~環境省
例年、税制改正での検討課題として挙がる環境税だが、今年も環境省が税制全般の横断的見直しとして要望している。
具体的な内容は、中央環境審議会総合政策・地球環境合同部会のもとに「グリーン税制とその経済分析等に関する専門委員会」を設置し、今秋までに結論を得る考えだ。
そのほかでは、省エネ住宅促進税制の延長や太陽光発電設備等の新エネ設備促進税制等の創設などを求めている。新エネ設備促進税制とは、①省エネ基準を満たす新築住宅に対し、太陽光発電設備を設置する場合、ローン減税のさらなる軽減措置を講じる、②住宅に対し新エネ設備(太陽光発電設備等)を設置する場合、所得税の税額控除の措置を講じるものとしている。
1 農商工等連携法の特例措置の2年延長を 農林水産省では、環境税についての総合的な検討を進めたうえで、必要な森林吸収源対策推進のための税制上の措置を講じることを求めている。
また、平成20年7月21日に施行された農商工等連携法では、同法に基づく農商工等連携事業計画により取得する機械等の特別償却(30%)または税額控除(7%)の特例措置が手当てされているが、この特例措置の2年延長を求めている。
2 内閣府は地域再生事業に係る税制措置の拡充を 内閣府の税制改正要望では、地域再生事業の推進に係る税制上の特例措置の拡充が挙げられる。特定地域再生事業会社に対して行った投資について、現行の投資額控除に加え、所得控除との選択適用を可能にするよう要望している。
また、株式会社地域力再生機構が再生支援をした事業者が資産の評価替えを行った場合の評価損の損金算入を求めている。民事再生等では、債務免除が行われた際に、資産売却による損の実現を待たずに評価損の損金算入ができるほか、期限切れの欠損金の優先利用を認める税制措置が講じられている。この措置について、地域力再生機構が再生支援を行った際にも適用すべきとしている。
そのほか、子育て支援税制(事業所内託児施設に係る法人税の優遇措置)の延長を経済産業省、厚生労働省とともに要望しているほか、三世代同居・近居支援の特例措置の要望を国土交通省、厚生労働省とともに行っている。
3 厚労省はたばこ税の税率引上げ等を求める 厚生労働省では、前述したとおり、企業型確定拠出年金に係る個人拠出の容認と拠出限度額の引上げなどを求めている。
そのほか、医療法人に係る法人税率の軽減措置の創設、たばこ税の税率引上げ、教育訓練費に係る税額控除制度の適用期限の2年延長、障害者自立支援法等の見直しに伴う税制上の所要の措置などを要望している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























