解説記事2009年01月05日 【ニュース特集】 投資事業組合を通じて取得した新株予約権行使益の課税関係(2009年1月5日号・№289)
審判所、一部報道された課税事案で注目判断
投資事業組合を通じて取得した新株予約権行使益の課税関係
国税不服審判所が、民法上の組合(投資事業組合)を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益の課税関係について判断を行った。新株予約権の権利行使による利益の所得区分は雑所得とし、権利行使益の額の算定は権利行使日における公表された当該株式の最終価格を基礎とするとして、原処分庁の主張を支持した。一方、請求人が権利行使益を得るための情報提供の対価として支払った手数料については、雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきとして、更正処分の一部を取り消した。
今回の裁決では、一部報道された課税事案である投資事業組合による企業再生スキームへの出資に係る課税関係が示されており、注目されるところだ(仙裁(所)平20第3号:平成20年10月30日裁決)。
1 新株予約権を行使し、投資会社株式を現物分配 請求人が投資事業組合の保有する新株予約権の権利行使益を得るまでの流れを確認しておこう。
請求人は、民法上の組合(以下「本件組合」という)の業務執行組合員との間で、平成17年4月16日付の投資事業組合契約書に署名押印した。この投資事業組合契約書の記載の要旨は、表1のとおり。
【表1】投資事業組合契約書の要旨 ○ 本件組合契約書中の次の用語は、前後の関係により他の意味を必要とする場合を除き、それぞれ次の意味を有する(1条)
A 投資会社 X社。
B 投資証券等 投資会社が発行した又は発行する株式、新株予約権等。
C 組合財産 出資金並びにこれを運用して取得した投資証券等、権利その他の財産及び現金で本件組合に帰属すべきもの。
○ 業務執行組合員は、本件組合の目的達成のため、適宜投資会社の業務状況を調査し、その経営に関し助言を与える等、合理的に可能な範囲で、その裁量により適切と考える行為をなすよう努めるものとする(18条)
○ 本件組合契約書6条2号に従い、組合員が出資金の全額を払い込んだ場合には、当該組合員と業務執行組合員が別途定める場合を除き、新株予約権を直ちに行使し、発行された株式を当該組合員に現物分配するものとする(22条3項)
○ 本件組合契約書22条に規定に基づき分配された組合財産は分配実施日の翌日から各組合員の専有に属する(24条)
X社(投資会社)は、証券取引所に上場する法人で、平成17年4月26日開催の臨時取締役会において、株式10株を1株に併合(併合後も1株につき22円)すること、旧商法280条の21第1項の規定に基づく第3回新株予約権(以下「本件新株予約権」という)を発行すること、本件新株予約権の譲渡は取締役会の承認を受けなければならないこと、および割当数11,670個の全部を本件組合に割り当てること等を決議した。X社は、平成17年8月10日に株式10株を1株に併合し、翌11日に本件新株予約権11,670個(1個につき1,000株)を発行し、本件組合にそのすべてを割り当てた。
請求人は、平成18年1月25日、本件組合に対して190口分、42,871,790円(1口当たり225,641円)を出資金として払い込んだ。本件組合は、請求人の出資を受けて、平成18年1月26日(以下「本件権利行使日」という)にX社に対し、請求人に割り当てられた新株予約権のうち190個を権利行使(以下「本件権利行使」という)した。その結果、請求人は、本件権利行使に係る利益(以下「本件権利行使益」という)を得ている。
請求人は、本件権利行使によって発行されたX社の株式1,900,000株(以下「本件株式」という)のうち、平成18年2月1日に450,000株の株式を受領(以下、受領した株式を「本件受領株式」という)し、残余の1,450,000株の株式は、本件組合において保管されている。X社の株式の本件権利行使日における証券取引所の最終価格は、1株当たり195円。
請求人は、本件受領株式について、平成18年2月7日に400,000株を、同月22日に50,000株を、それぞれ証券市場を通じて売却した。なお、請求人は、X社の取締役等ではない。
請求人は、平成18年2月24日、貸付金10,000,000円との相殺および銀行口座への5,561,944円の振込みの方法により、Yに対し、15,561,944円(以下「本件手数料」という)を支払った。
上記、X社の新株予約権を巡る取引については、図を参照。
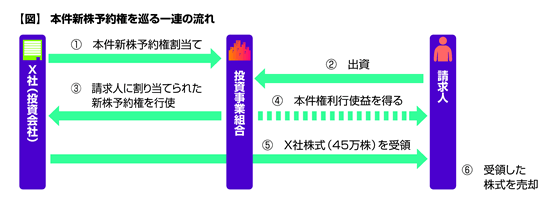
2 所得区分、価額算定、手数料の費用控除が争点に 今回の審査請求での争点は、次の3点となっている。①本件権利行使益に係る所得は、一時所得または雑所得のいずれに当たるか。②本件権利行使益の額を、本件権利行使日における公表されたX社の株式の最終価格を基礎に算定したことの適否、③本件手数料は、本件権利行使益に係る所得あるいは本件受領株式の譲渡に係る所得の金額の計算上、費用として控除できるか否か。
以下、それぞれの争点について、原処分庁と請求人の主張、審判所の判断を確認していく。
争点1 本件権利行使益の所得区分について 本件権利行使益について、請求人は一時所得に該当すると主張している。所得区分に関する原処分庁および請求人の主な主張は、前頁表2のとおり。
権利行使益を雑所得と判断
審判所の判断では、まずX社がホームページに公開した情報において、①本件新株予約権の発行によって資金を調達し、新規事業等を展開して経営の抜本的対策を図ること、②X社が長年赤字経営の状態にあることや、投資リスク等その他諸般の事情を考慮し、本件新株予約権の行使に際して振込みをなすべき額を株式併合後についても1株につき22円としたこと、③投資家自体による新規事業の支援という特殊な事情の存在と長期安定株主構成を重視し、第三者割当てとしたことをそれぞれ明らかにしているとした。また、そのことから、X社は、本件新株予約権の発行に当たり、事業拡大のための資金調達のほか、投資家による新規事業の支援や長期安定株主の確保も計画し、これらの確実な実現を図るために本件組合を引受先とし、本件組合の出資者の投資リスク等を考慮して、有利発行としたと認定し、本件権利行使益は、出資の対価としての性格を有しているといえると指摘した。
そのうえで、本件組合が民法上の組合であり、組合の権利義務関係は直接組合員に帰属することから、本件株式の分配を受けたことによって生じた本件権利行使益は、請求人に帰属することとなり、本件権利行使益には対価性が認められるから、一時所得には当たらないこととなると判断。また、請求人がX社の取締役等ではないから、本件権利行使益に係る所得は、給与所得には当たらず、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、退職所得、山林所得および譲渡所得のいずれにも当たらないので雑所得に区分されることになるとした。
争点2 本件権利行使益の額の算定について 本件権利行使益の額の算定に関しては譲渡制限の有無について争われた。原処分庁および請求人の主な主張は、表3のとおり。
譲渡制限株式が含まれていても違法、不当ではない
審判所は、本件権利行使益の算定に当たっては、所令83条3号の規定のとおり、本件権利行使により取得した株式のその行使の日の価額を基準に算定されるところ、X社の株式は証券取引所に上場されていることから、基本通達23~35共-9の定めにより、本件権利行使日の価額は、当該証券取引所の最終価格の195円によることとなると判断した。
また、請求人の譲渡制限に係る主張については、本件権利行使益に係る課税は、本件新株予約権の行使により請求人が本件株式を取得した結果生じることとなった経済的利益になされるものであって、その後の当該株式の売却によって生じる利益に課税するものではないから、課税の対象となる株式に譲渡制限株式が含まれているとしても何ら違法、不当ではないとした。
なお、請求人の(3)基本通達23~35共-9の適用に関する主張については、証券取引所に上場されている株式の価格については、時々の経済情勢をはじめ当該上場法人の固有事情など様々な要因を反映しているものと解され、X社の株式についても上場株式であるところ、請求人の主張する事情をもって証券取引所の最終価格を時価とすることを否定する根拠とはならないとしている。
争点3 本件手数料の費用控除について 本件手数料の費用控除に関しては、請求人は予備的主張で雑所得の必要経費に該当すると主張している。原処分庁および請求人の主な主張は、表4のとおり。
請求人の予備的主張を認める
審判所は、請求人がYに支払った本件手数料について、請求人とYとの間で書面による契約はしていないものの、以前から株式等に係る投資情報を得ており、当該情報を起因として利益を得た場合に情報提供料を支払うこととし、そして、本件新株予約権に係る情報についても同様の情報提供料の支払いが約束されていたものと認められると指摘した。
そのうえで、本件手数料は、Yの本件新株予約権に係る情報に基づき請求人が本件組合へ出資をし、その結果、本件権利行使益を得たことの対価と解するのが相当と判断。本件手数料は、本件権利行使益を得るために要した費用と認められ、本件権利行使益に係る所得が雑所得に区分されることから、本件手数料は、雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきものであるとした。
なお、原処分庁の主張に対しては、請求人が本件受領株式について証券市場を通じて売却しているところ、当該株式を売却するに当たり、必要なものとして本件手数料を支払ったわけではなく、また、Yが本件受領株式の売却に関与していないことからすれば、本件手数料が売却益に基づき計算され、当該株式を売却した時に支払う約束であったとしても、客観的にみて、本件手数料は、本件受領株式の譲渡に要した費用であるとは認められないと判断した。
投資事業組合を通じて取得した新株予約権行使益の課税関係
国税不服審判所が、民法上の組合(投資事業組合)を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益の課税関係について判断を行った。新株予約権の権利行使による利益の所得区分は雑所得とし、権利行使益の額の算定は権利行使日における公表された当該株式の最終価格を基礎とするとして、原処分庁の主張を支持した。一方、請求人が権利行使益を得るための情報提供の対価として支払った手数料については、雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきとして、更正処分の一部を取り消した。
今回の裁決では、一部報道された課税事案である投資事業組合による企業再生スキームへの出資に係る課税関係が示されており、注目されるところだ(仙裁(所)平20第3号:平成20年10月30日裁決)。
1 新株予約権を行使し、投資会社株式を現物分配 請求人が投資事業組合の保有する新株予約権の権利行使益を得るまでの流れを確認しておこう。
請求人は、民法上の組合(以下「本件組合」という)の業務執行組合員との間で、平成17年4月16日付の投資事業組合契約書に署名押印した。この投資事業組合契約書の記載の要旨は、表1のとおり。
【表1】投資事業組合契約書の要旨 ○ 本件組合契約書中の次の用語は、前後の関係により他の意味を必要とする場合を除き、それぞれ次の意味を有する(1条)
A 投資会社 X社。
B 投資証券等 投資会社が発行した又は発行する株式、新株予約権等。
C 組合財産 出資金並びにこれを運用して取得した投資証券等、権利その他の財産及び現金で本件組合に帰属すべきもの。
○ 業務執行組合員は、本件組合の目的達成のため、適宜投資会社の業務状況を調査し、その経営に関し助言を与える等、合理的に可能な範囲で、その裁量により適切と考える行為をなすよう努めるものとする(18条)
○ 本件組合契約書6条2号に従い、組合員が出資金の全額を払い込んだ場合には、当該組合員と業務執行組合員が別途定める場合を除き、新株予約権を直ちに行使し、発行された株式を当該組合員に現物分配するものとする(22条3項)
○ 本件組合契約書22条に規定に基づき分配された組合財産は分配実施日の翌日から各組合員の専有に属する(24条)
X社(投資会社)は、証券取引所に上場する法人で、平成17年4月26日開催の臨時取締役会において、株式10株を1株に併合(併合後も1株につき22円)すること、旧商法280条の21第1項の規定に基づく第3回新株予約権(以下「本件新株予約権」という)を発行すること、本件新株予約権の譲渡は取締役会の承認を受けなければならないこと、および割当数11,670個の全部を本件組合に割り当てること等を決議した。X社は、平成17年8月10日に株式10株を1株に併合し、翌11日に本件新株予約権11,670個(1個につき1,000株)を発行し、本件組合にそのすべてを割り当てた。
請求人は、平成18年1月25日、本件組合に対して190口分、42,871,790円(1口当たり225,641円)を出資金として払い込んだ。本件組合は、請求人の出資を受けて、平成18年1月26日(以下「本件権利行使日」という)にX社に対し、請求人に割り当てられた新株予約権のうち190個を権利行使(以下「本件権利行使」という)した。その結果、請求人は、本件権利行使に係る利益(以下「本件権利行使益」という)を得ている。
請求人は、本件権利行使によって発行されたX社の株式1,900,000株(以下「本件株式」という)のうち、平成18年2月1日に450,000株の株式を受領(以下、受領した株式を「本件受領株式」という)し、残余の1,450,000株の株式は、本件組合において保管されている。X社の株式の本件権利行使日における証券取引所の最終価格は、1株当たり195円。
請求人は、本件受領株式について、平成18年2月7日に400,000株を、同月22日に50,000株を、それぞれ証券市場を通じて売却した。なお、請求人は、X社の取締役等ではない。
請求人は、平成18年2月24日、貸付金10,000,000円との相殺および銀行口座への5,561,944円の振込みの方法により、Yに対し、15,561,944円(以下「本件手数料」という)を支払った。
上記、X社の新株予約権を巡る取引については、図を参照。
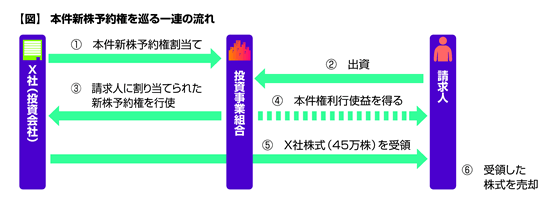
2 所得区分、価額算定、手数料の費用控除が争点に 今回の審査請求での争点は、次の3点となっている。①本件権利行使益に係る所得は、一時所得または雑所得のいずれに当たるか。②本件権利行使益の額を、本件権利行使日における公表されたX社の株式の最終価格を基礎に算定したことの適否、③本件手数料は、本件権利行使益に係る所得あるいは本件受領株式の譲渡に係る所得の金額の計算上、費用として控除できるか否か。
以下、それぞれの争点について、原処分庁と請求人の主張、審判所の判断を確認していく。
争点1 本件権利行使益の所得区分について 本件権利行使益について、請求人は一時所得に該当すると主張している。所得区分に関する原処分庁および請求人の主な主張は、前頁表2のとおり。
【表2】争点1における原処分庁および請求人の主張
| 原処分庁 | 請求人 |
| 本件権利行使益は、次のとおり、本件組合がX社の長期安定株主として、新規事業に係る出資のみならず、当該新規事業に係る人材提供、経営に関する助言その他役務の提供を約して新株予約権を取得し、これを行使したことによる利益であり、組合員である請求人に帰属し、対価としての性質を有すると認められることから、雑所得に該当する。 (1)本件組合契約書によれば、本件組合は、X社が発行する本件新株予約権を取得して同社の株式に投資することを目的として組成された組合であり、業務執行組合員は適宜X社の業務状況を調査し、その経営に関し助言を与える等とされ、Xの経営に協力する体制を整えていたと認められる。 (2)臨時取締役会の議事録および株主にあてた文書によれば、本件組合が、X社の新規事業への参画による企業再生、業績向上を図るために、当該新規事業の情報・ノウハウ・人材の提供および資金支援について長期安定株主になることにより、X社と一体となって当該新規事業に取り組む目的で本件新株予約権を付与し、本件組合を単独の第三者割当先とした旨記載されている。 | 本件権利行使益は、次のとおり、営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではなく、請求人の投資による一時的かつ偶発的な所得であり、労務その他の役務の提供または資産の譲渡の対価としての性質を有していないことから、一時所得に該当する。 (1)請求人は、本件組合に投資した一投資家にすぎないのであり、X社とは、雇用関係やこれに類する契約を締結していないし、雇用類似の実態を何ら有しておらず、本件組合を通じて本件株式を取得しただけであり、X社に対し、「労務」の提供を全く行っておらず、「その他の役務」についても何らこれを行っていない。 (2)X社の株主にあてた文書は、本件組合が関与したものではなく、X社が一方的に作成したもので本件新株予約権を付与する目的を対外的に記載した書面にすぎない。本件組合とX社との間で役務提供契約が締結されていたことを示すものはなく、本件組合から、X社に対して、情報・ノウハウ・人材の提供、資金援助をする約束および役務提供が行われた事実は認められない。 |
そのうえで、本件組合が民法上の組合であり、組合の権利義務関係は直接組合員に帰属することから、本件株式の分配を受けたことによって生じた本件権利行使益は、請求人に帰属することとなり、本件権利行使益には対価性が認められるから、一時所得には当たらないこととなると判断。また、請求人がX社の取締役等ではないから、本件権利行使益に係る所得は、給与所得には当たらず、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、退職所得、山林所得および譲渡所得のいずれにも当たらないので雑所得に区分されることになるとした。
争点2 本件権利行使益の額の算定について 本件権利行使益の額の算定に関しては譲渡制限の有無について争われた。原処分庁および請求人の主な主張は、表3のとおり。
【表3】争点2における原処分庁および請求人の主張
| 原処分庁 | 請求人 |
| 本件権利行使益の額を、本件権利行使日における公表された本件株式の最終価額(1株195円)をもって算定したことは、次の理由から相当である。 (1)所得税法は、現実に収入がない場合であっても収入の原因たる権利が確定的に発生した場合に、その時点で所得の実現があったものとする権利確定主義を採用しているところ、新株予約権に係る所得税法36条2項の価額は、当該権利の行使により取得した株式について、権利行使日における価額より低い価額で取得できたという経済的利益であり、権利行使日において権利の価額を算定し、課税することとされており、取得する株式に譲渡制限の約束が課せられていたとしても影響はなく、また、権利行使後にすぐ譲渡できるものに限定されているものではない。 (2)本件組合契約書には、本件権利行使により取得するX社株式について、譲渡制限特約が付されている旨の定めは明記されていない。 本件組合契約書において、本件権利行使により取得するX社株式は、組合員に現物分配すると定められていることから、X社株式145万株が本件組合に預けられていることは、本件権利行使後に、請求人が任意に第三者に対する譲渡を制限する旨同意した結果にすぎない。 | 本件株式のうち145万株の価額は、自由に譲渡できるという前提を欠くものであるから、鑑定資料等を基に算定すると1株当たり37.0円を上回るものではない。 (1)基本通達23~35共-9は、新株予約権の権利行使の日において、当該権利の行使により取得した株式を自由に譲渡できることをその適用の前提としており、株式等の自由な譲渡ができない本件について、同通達を適用することは合理性を欠く。 (2)本件組合契約書に譲渡制限特約が付されていないとしても、請求人が、業務執行組合員との間で締結した確約書において、本件株式のうち145万株について譲渡制限の合意がなされ、また、Xが公表した主要株主の異動に関する「お知らせ」には、本件組合から約7,500万株について原則として3年間の長期所有の約束を頂いているとの記載があることからも譲渡制限の合意があることは明らかである。 (3)本件に基本通達23~35共-9を適用することは、本件権利行使日において、株式併合による株価急騰の反動として株価下落が確実に予測されたこと、一般に新株が大量発行された場合、市場に流通する株式数が増加する結果、当該発行会社の株価は下落するものと予測され、本件においても希釈効果による株式の大幅な下落が確実に予測されたことから、実際上も不合理である。 |
また、請求人の譲渡制限に係る主張については、本件権利行使益に係る課税は、本件新株予約権の行使により請求人が本件株式を取得した結果生じることとなった経済的利益になされるものであって、その後の当該株式の売却によって生じる利益に課税するものではないから、課税の対象となる株式に譲渡制限株式が含まれているとしても何ら違法、不当ではないとした。
なお、請求人の(3)基本通達23~35共-9の適用に関する主張については、証券取引所に上場されている株式の価格については、時々の経済情勢をはじめ当該上場法人の固有事情など様々な要因を反映しているものと解され、X社の株式についても上場株式であるところ、請求人の主張する事情をもって証券取引所の最終価格を時価とすることを否定する根拠とはならないとしている。
争点3 本件手数料の費用控除について 本件手数料の費用控除に関しては、請求人は予備的主張で雑所得の必要経費に該当すると主張している。原処分庁および請求人の主な主張は、表4のとおり。
【表4】争点3における原処分庁および請求人の主張
| 原処分庁 | 請求人 |
| 本件手数料は、(1)本件権利行使日においても確定しているものではないことから、新株予約権の取得のために要した費用とは認められない、(2)本件受領株式の売却金額を基に計算されていることから、本件受領株式を譲渡して得た利益に対する報酬であり、株式の譲渡に密接に関連した費用である。 | 本件手数料は、本件権利行使益を得るために支出した費用または本件新株予約権の取得のための付随費用のいずれかに該当し、一時所得の収入を得るために支出した金額に当たる。 なお、仮に本件権利行使益が雑所得に該当するとした場合には、本件手数料は、雑所得の必要経費となることを予備的に主張する。 |
そのうえで、本件手数料は、Yの本件新株予約権に係る情報に基づき請求人が本件組合へ出資をし、その結果、本件権利行使益を得たことの対価と解するのが相当と判断。本件手数料は、本件権利行使益を得るために要した費用と認められ、本件権利行使益に係る所得が雑所得に区分されることから、本件手数料は、雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきものであるとした。
なお、原処分庁の主張に対しては、請求人が本件受領株式について証券市場を通じて売却しているところ、当該株式を売却するに当たり、必要なものとして本件手数料を支払ったわけではなく、また、Yが本件受領株式の売却に関与していないことからすれば、本件手数料が売却益に基づき計算され、当該株式を売却した時に支払う約束であったとしても、客観的にみて、本件手数料は、本件受領株式の譲渡に要した費用であるとは認められないと判断した。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























