解説記事2009年02月23日 【巻頭特集】 金融商品取引法改正後の課徴金制度における実務上の留意点(2009年2月23日号・№296)
巻頭特集
具体的事例を踏まえて紹介する
金融商品取引法改正後の課徴金制度における実務上の留意点
森・濱田松本法律事務所弁護士 中村 聡/弁護士 峯岸健太郎
本稿は、平成20年12月12日に施行された金融商品取引法の改正法(平成20年法律第65号)において重要な改正がなされた課徴金制度(脚注1)について、実務上の観点から考察するものである。以下では、改正の概要および留意点(本稿Ⅰ参照)、新たに設けられた減算制度の対象となる場合の対応方針・手続を述べたうえで(本稿Ⅱ参照)、「有価証券届出書の不提出」など新たに対象とされた違反行為について事例を設定しながら、各場合の具体的な対応・留意点を明らかにする(本稿Ⅲおよび図表1参照)(脚注2)。
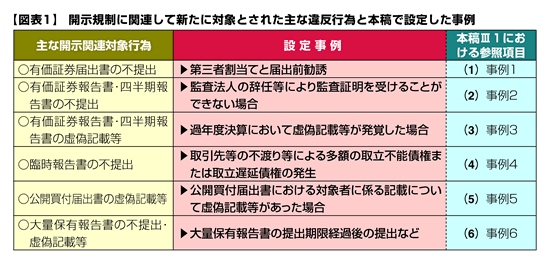
Ⅰ 課徴金の対象行為
1 改正後の課徴金制度の概要 金融商品取引法における課徴金は、金融・資本市場における違反行為を的確に抑止し、規制の実効性を確保していく観点から設けられた違反者に対して金銭的な負担を課す行政上の措置である。
今回の改正では、違反行為者が違反行為によって得た経済的利得相当額を基準として課徴金を課すという考え方を維持しつつも、違反行為の抑止の実効性をいっそう確保するという観点から、課徴金の水準を実質的に引き上げる方向での算定方法の見直し、課徴金の対象となる違反行為の拡大、加算・減算制度の導入などの措置が講じられている(脚注3)。
課徴金制度の対象となる違反行為は、開示規制違反と不公正取引とに大別される。改正後における課徴金の対象行為およびその課徴金額の基本的な計算方法について、改正で設けられた課徴金の減算制度の適用の有無および刑事罰則とともにまとめたものが、図表2-1(開示規制違反。今号6頁以下参照)、図表2-2(不公正取引。8頁以下参照)である。
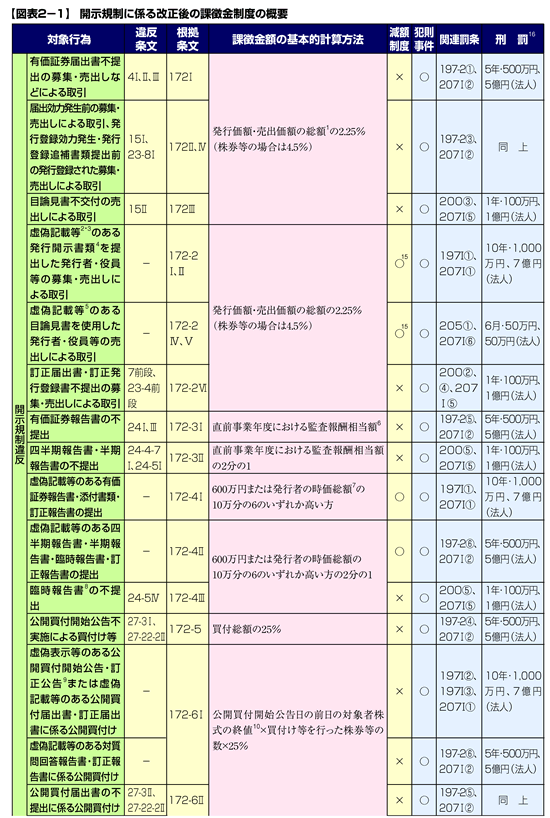
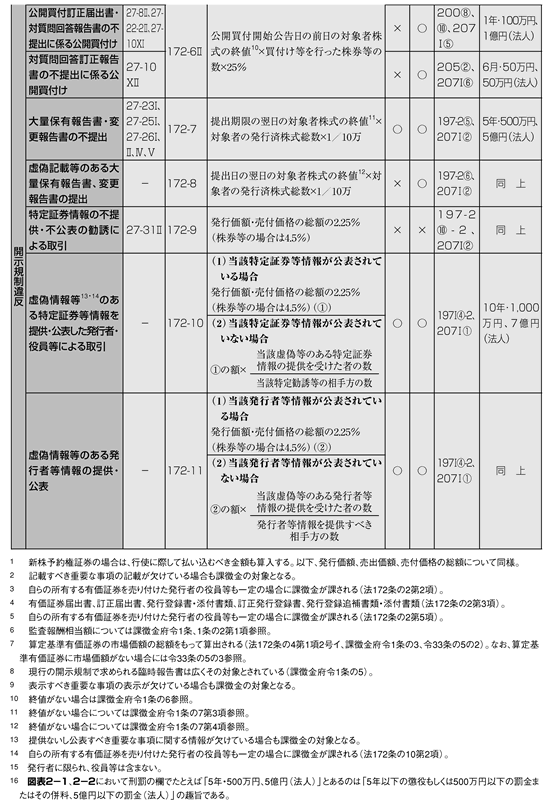
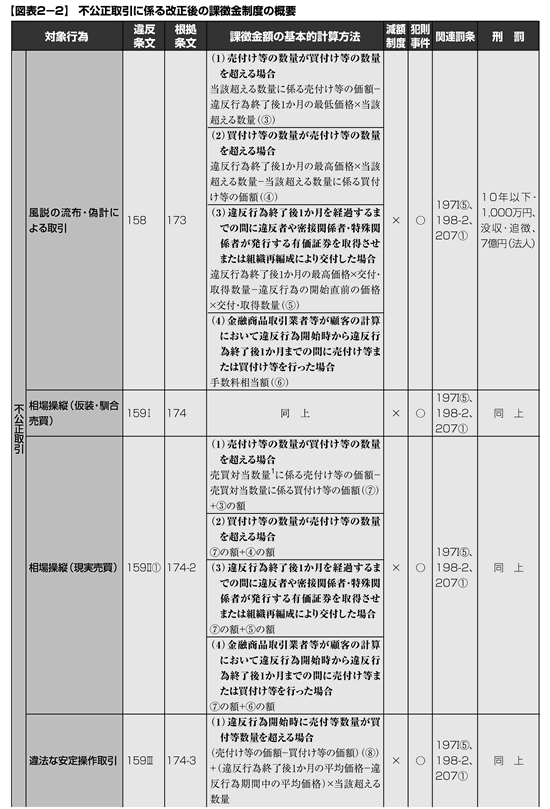
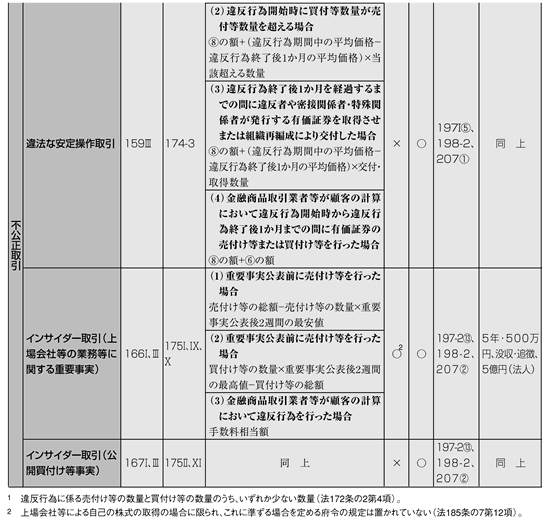
2 開示規制違反 開示規制違反に関する課徴金については、改正前の対象行為は次のものに限定されていた。
●発行開示書類(届出書類、発行登録関係書類、それらの添付書類、訂正書類および参照書類)ならびに目論見書の虚偽記載
●有価証券報告書(添付書類を含む)、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書およびそれらの訂正報告書の虚偽記載
改正により拡大された対象行為は図表2-1記載のとおりであるが、実務上留意すべき重要な事項としては、次の点が挙げられる。
第1に、情報開示における不実開示には、①重要な事項についての虚偽の記載、②記載すべき重要な事項が欠けていること、③誤解を生じさせないために必要な事実の記載が欠けていることの3類型があるところ、改正前は①の虚偽の記載のみが課徴金の対象とされていたが、改正後は②の記載すべき事項の不記載も対象とされたことである。
なお、罰則においては①の虚偽記載のみが対象とされ、民事責任規定においては①から③までのいずれもが責任根拠となりうる。
第2に、発行開示に関する違反行為抑止の観点から、届出前の勧誘禁止あるいは効力発生前の取引禁止に違反して有価証券を取得させた場合が課徴金制度の対象となったことである。この点については、後述Ⅲ・事例1を参照されたい。
第3に、開示書類の法定期限内における不提出の場合が対象とされた結果、たとえば決算処理を巡って監査法人または公認会計士が辞任した場合や監査意見を表明しない旨の監査報告書が出された場合には、有価証券報告書等を期限内に提出できなくなる結果、課徴金の対象とされることがありうる。また、臨時報告書については、開示府令19条2項各号に掲げる事由が発生した場合に遅滞なく提出しないときは課徴金の対象となる。これらの点については、後述Ⅲ・事例2・3・4を参照されたい。
公開買付けに関する開示書類についても課徴金制度の対象となったため、M&A実務や自己株公開買付けに携わる実務家は、開示の正確性・十分性に留意することが必要である。この点については、後述Ⅲ・事例5を参照されたい。
さらに、大量保有報告書またはその変更報告書についても、特例報告制度の適用を受けない通常の場合には、5営業日以内の提出が求められており、当該提出期限内に提出できないときは課徴金の対象となる。
特に、初めて大量保有報告書を提出する者の場合には、事前にEDINET利用のための電子開示システム届出書(添付書類として、内国法人の場合、定款またはこれに準ずるものおよび登記事項証明書またはこれに準ずるものが必要である)を提出しておくなどの準備をしておくことが望ましい(後述Ⅲ・事例6参照)。
なお、図表2-1からも明らかではあるが、開示書類のすべてが課徴金の対象となるものではない。参照の便宜を図るため、図表3(11頁参照)において各開示書類につき課徴金制度の適用の有無をまとめている。

3 不公正取引 課徴金の対象である不公正取引は、改正により、相場操縦行為等(法159条)のうち、現実売買による相場操縦(相場変動型相場操縦)(同条2項)に加えて、仮装売買・馴合売買による相場操縦(同条1項)および違法な安定操作取引(同条3項)が追加され、図表2-2に掲げたとおりとなっている。
実務上留意すべき重要な点としては、一定の範囲で他人の計算による不公正取引が追加されたことがある。
改正前は、違反行為による経済的利得を違反行為者に保持させないという課徴金制度の趣旨から、原則として自己の計算による不公正取引が対象行為とされ、例外的に上場会社等の計算によるインサイダー取引が行われた場合(法175条9項)が対象行為とされていた。
これに対し、改正により、違反行為の抑止の観点から、他人の計算による違反類型であっても、違反者が違反行為を通じて自己の利益を実現している場合と評価できるものとして、次のものが追加されている(脚注4)。
●金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業・登録金融機関業務における顧客または法42条1項に規定する権利者(投資運用業行為の相手方)(次の密接関係者・特殊関係者である場合を除く)の計算において不公正取引をした場合には、手数料相当額が課徴金の対象とされる(法175条1項3号、2項3号、課徴金府令1条の21等)。
●違反者と経済的に同一性があると認められる密接な関係にある者および特殊の関係にある者(図表4(16頁)参照)の計算において不公正取引(当該密接関係者・特殊関係者が自己の計算において行った不公正取引と同一のものを除く)を行った場合には、違反者が自己の計算において違反行為を行ったものとみなして課徴金が計算される(法175条10項、11項、課徴金府令1条の23等)。
Ⅱ 課徴金対象事実を発見した場合の減額報告
1 違法行為発見の場合の対応方針 課徴金の対象となる事実を発見した場合には、既に起きてしまったことについては所与の前提として、その時点で違反行為の是正、再発防止のための最大限の努力を行うのが正しい対応方針である。
開示書類の虚偽記載や記載すべき事項の不記載を発見した場合には(脚注5)、刑事・行政・民事上の責任がいずれも基本的には「重要な事実」を対象としていることから、まずは当該虚偽記載等が重要な事項に関するものであるかを検証することとなる。この際、決して事実を矮小化することなく、情報開示に通じた弁護士に相談するなどして健全かつ慎重な判断を行う必要がある。
虚偽記載等が重要な事項に関する場合には、訂正書類の提出が必要となるが(法7条後段、23条の4第2文、24条の2第1項、24条の4の7第4項、24条の5第5項等)、訂正書類の提出に向けて、開示すべき事項の確認、開示内容の確定などの作業を進めつつ、訂正書類の提出前に、管轄財務(支)局への報告および対応方針についての説明を行うことが適切である。
また、当該事項が上場証券取引所の規則に従い適時開示を行った事実である場合には、適時開示をした内容について訂正すべき事情が生じたときは直ちに訂正の内容を適時開示しなければならず、また事前に当該内容を上場証券取引所に説明をしなければならない(たとえば、東京証券取引所の有価証券上場規程416条)。
当該事項について適時開示を行ったか否かにかかわらず、課徴金の対象となる事実自体が法令違反行為(犯罪行為となる場合を含む)として投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすことが想定される場合には、当該事実を適時開示することが必要であり、また事前に上場証券取引所に説明することを要する(たとえば、上記規程402条1号ap、2号x、413条)。
このような適時開示を行うにあたっては、法令違反行為の事実、その原因、会社の運営、業績または財産状態に与える影響などにとどまらず、法令違反に対する是正措置、原因を踏まえた再発防止措置(検討中の場合にはその旨)についても投資者に対するメッセージとして盛り込むことが肝要である。
今般の改正により、課徴金の対象行為のうち一定のものについては、行政当局の調査のための処分が行われる前に自己申告した場合に課徴金額を半額とする課徴金の減算制度が導入されたため、所定の減額報告の手続に従い、証券取引等監視委員会に報告することも実務上の検討課題となる。
ただし、法令違反行為から5年を経過した時は課徴金手続の対象とはならない(法178条3項以下)。また、改正法の施行日以後の違反行為に対して適用されるため、平成20年12月11日以前に行われた違反行為については減算制度の対象とはならない。
2 減算制度 課徴金の減算制度は、違反行為者による自律的な是正機能の発揮を促すという観点から導入され、継続的・反復的に行われる可能性が高い違反行為については、早期発見がなされることの公益性が強く、早期発見のインセンティブを与えることが必要とされ(脚注6)、課徴金の対象行為のうち、図表2-1または2-2の「減額」欄において○が表示されているものについて、違反者が、行政当局(脚注7)による報告聴取または検査のいずれかの処分が行われる前に証券取引等監視員会に対し報告した場合には、課徴金額(複数の違反行為がある場合には最も遅いものに係る額に限る)が半額とされる(法185条の7第12項、課徴金府令61条の7)。
なお、課徴金の対象となる違反行為を繰り返す者は、違反行為が発覚して課徴金が課される危険を認識しつつ違反行為を行っているものと考えられ、前回と同じ算定方法による課徴金を課しても十分な違反行為の抑止効果は得られないことから(脚注8)、違反行為から過去5年以内に課徴金納付命令を受けたことがあるときは、課徴金額が1.5倍とされる(法185条の7第13項)。
3 減額報告手続
(1)減額報告書の作成および記載事項 課徴金の減算制度の適用を受けるためには、「課徴金の減額に係る報告書」(課徴金府令別紙様式)を作成して、証券取引等監視委員会に提出しなければならない。
減額報告書には、①違反の類型(いずれの対象行為に該当するか)、②違反の概要、③その他参考となるべき事項を具体的に記載しなければならない。
違反の概要としては、たとえば、次の事項を記載する。
●開示書類の虚偽記載等:開示書類の特定、虚偽記載等の内容
●開示書類の不提出:提出事由およびその発生時期、提出期限
●インサイダー取引:取引の方法・数量・価格および時期、重要事実の内容および時期
(2)減額報告書の提出方法 提出方法は、証券取引等監視委員会事務局課徴金・開示検査課に宛てて、①直接持参、②書留郵便、引受けおよび配達の記録を行う信書便またはこれらに準ずる方法(脚注9)による送付、③ファクシミリによる送信のいずれかの方法による(課徴金府令61条の7第1項)。金融庁または各財務局に提出しても受理されない。
①の方法による場合は、平日の午前9時30分から午後6時までが受理時間である。
②の方法による場合は、発送の時に提出されたものとみなされる(同条2項)。普通郵便による送付は受理されない。
③の方法による場合は、03-3506-6222に送信しなければならず、証券取引等監視委員会が受信した時に提出されたものとみなされるが、原本を遅滞なく証券取引等監視委員会に提出(郵送による場合は普通郵便も可)しなければならない(同条3項、4項)。
減額報告がなされると、記載事項の確認とその後の手続等に関する説明のための連絡がなされ、その後必要に応じて違反内容に関する資料の提出等が求められることがある。
(3)減額報告の際のその他の留意事項 減額報告は、上述のとおり、所定の手続に従って行われなければならないため、たとえば、開示書類の虚偽記載等について、訂正報告書などを提出したり、虚偽記載等がある旨を適時開示しても、また大量保有報告書・変更報告書を提出期限経過後に提出しても、課徴金の減算制度の適用を受けられないことに留意する必要がある。
したがって、減算制度の対象となる違反行為を発見した場合には、まずは減額報告をしたうえで、間を置かずに、たとえば、法定開示書類として訂正報告書、大量保有報告書・変更報告書などを提出し、併せて適時開示および上場証券取引所への事前説明を行うということになろう。
なお、課徴金の対象行為であっても、悪質な事案に対しては、犯則事件(法210条、令45条)として調査し、犯則の心証を得たときは刑事告発する(法226条1項)のが証券取引等監視委員会の一般的な方針のようである。減額報告をした場合に、証券取引等監視委員会が課徴金調査にとどまらず犯則調査の対象とすることがあるかについては、証券取引等監視委員会の方針は明らかにされていない(脚注10)。
刑事事件となることが想定される場合には、裁量的減軽事由である自首(刑法42条)に該当するには検察官または司法警察員に対する申告が必要となるため、減額報告とは別途手続をとる必要がある。
Ⅲ 課徴金リスクに留意すべき事例
1 開示関係
(1)有価証券届出書の不提出と課徴金 新規発行有価証券に関するある行為が、取得勧誘(法2条3項)に該当する場合には、当該取得勧誘を開始する前に有価証券届出書を提出して届出を行っていなければ、課徴金の対象となる。
具体的には、次のような事案が考えられる。
事例1 第三者割当てと届出前勧誘
X(日本における上場会社)は、その財務体質の強化のために資本増強を行う必要があるが、現在の市況ではいわゆる公募増資を行うことが難しいため、その発行する上場株式と同種の株式をY(Xの取引先)に対して割り当てる第三者割当増資を行うことを検討しており、日本においてYとの間で交渉を行っている。
日本における上場会社が、その上場株式と同種の株式の株式を発行する場合、私募を行うことができない(令1条の4第1号、1条の7第1号イ等)ことから、法4条1項各号に掲げるいずれかに該当しない限り、その株式に関して取得勧誘を行う前に届出を行わなければならない。
しかしながら、金商法において、どのような行為が取得勧誘に該当するかということについては明確に規定されておらず、わずかに、有価証券の募集または売出しに関する文書を頒布することや新聞等において募集または売出しに係る広告をすることは、「有価証券の募集又は売出し」に該当するということが開示ガイドラインで規定されているにすぎない(企業内容等の開示に関する留意事項4-1)。
そこで、どのような行為が有価証券の取得勧誘に該当するかということが解釈上問題となるが、一般的には、有価証券の勧誘とは、特定の有価証券についての投資者の関心を高め、その取得・買付けを促進することとなる行為と解されている(脚注11)。したがって、届出前の行為がこのように解されるものかどうかという観点から、検証を行う必要がある。
ただし、このように勧誘概念を捉えたとしても、どのような行為が「勧誘」に該当するかは、なお不明確であることから、個別具体的な事案においては慎重な判断とならざるを得ないが、特に上場株式と同種の株式を発行することによって第三者割当てを行う場合、取締役会による発行決議とその前後の届出前の行為が金商法上の勧誘に該当しないように留意する必要がある(脚注12)。
(2)有価証券報告書・四半期報告書の不提出と課徴金 上場会社においては、一般的に、有価証券報告書や四半期報告書がその提出期限までに提出されないということは想定し難いが、次のような事例ではどうか。
事例2 監査法人の辞任等により監査証明を受けることができない場合
X(日本における上場会社)は、有価証券報告書の提出準備を行っていたが、その提出期限が迫ってきているところで、監査法人との意見の相違により、監査契約を合意解約した。しかしながら、直ちに新たな監査法人との監査契約を締結することはできず、有価証券報告書をその提出期限までに提出できない見込みである。
改正前までは、有価証券報告書を提出期限までに提出できないような場合に関する規定が金商法上設けられていなかった。この場合、おそらくは、各社が管轄財務(支)局に事情と提出時期の目途を説明するなどして事実上の提出遅延の報告を行って対応している事案が多かったと思われる。
ただし、証券取引所の適時開示に関する規則では有価証券報告書等の提出の遅延は適時開示事由になっており、その会社が上場する証券取引所において「有価証券報告書提出の遅延について」等との表題で、有価証券報告書を期限までに提出できないこと、その理由および提出時期の見込み等を開示していた。
しかしながら、改正後の金商法においては、有価証券報告書等の不提出も課徴金の対象とされたことなどを踏まえ、やむを得ない理由による有価証券報告書等の提出期限延長に係る承認手続が設けられた(脚注13)こと(法24条1項、開示府令15条の2等)から、たとえば事例2のような場合であっても、有価証券報告書の提出期限延長に係る承認を得ない限りは、違法な有価証券報告書の不提出として、課徴金の対象とされるものと思われる。
したがって、事例2のような場合に限らず、何らかの事情により有価証券報告書等をその期限内に提出できないような見込みが発生した場合には、有価証券報告書等の提出期限延長に係る承認手続を申請し、承認を得られるよう努めることが必要である。
なお、承認がいかなる場合にされるかは明らかではない。
(3)有価証券報告書・四半期報告書の訂正と課徴金 近時、有価証券報告書の過年度決算に係る訂正報告書の提出がなされる事案が比較的多く見受けられるようになっている。次のような事案では、どのように対応すべきか。
事例3 過年度決算において虚偽記載等が発覚した場合
X(日本における上場会社)は、内部監査の過程において不適切な取引の疑惑が発覚し、さらに詳細な内部調査を行ったところ、過年度決算の訂正と有価証券報告書の訂正報告書を必要とし、かつ、当該訂正が行われなければ、記載すべき重要な事項が欠けているといえるような事態が内部調査で明らかになった。
このような場合、前述Ⅱ1に記載のとおり、不適切な取引の疑惑が発覚した時点において弁護士等の外部の専門家を入れ、集中的に事実の解明を行う必要がある。
そして、課徴金の減算制度の適用を受けられるように必要な準備を行ったうえで証券取引等監視委員会に減額報告をし、また同時並行的に、訂正報告書の作成と提出についても、事前に管轄財務(支)局への報告および対応方針についての説明を行うことが必要である。
(4)臨時報告書の不提出と課徴金 臨時報告書は、その提出事由に該当する場合には、遅滞なく提出しなければならないとされており(法24条の5第4項)、提出事由は多岐にわたる(開示府令19条2項)が、次のような事例ではどのように対応すべきか。
事例4 取引先等の不渡り等による多額の取立不能債権または取立遅延債権の発生
X(有価証券報告書を提出しなければならない会社)は、その取引先Yにおいて不渡りが発生し、Yからの売掛金債権を約定どおり回収できないことが明らかとなったことから、臨時報告書の提出の要否を検討している。
有価証券報告書提出会社の債務者や保証人に手形の不渡りや破産手続開始の申立て等があり、提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の3%以上に相当する額の債権につき取立不能または取立遅延のおそれが生じた場合には、臨時報告書を提出しなければならない(開示府令19条2項11号)。
この「取立不能または取立遅延のおそれが生じた場合」とは、一般的には正常な債権の回収が望めなくなった場合、すなわち約定などに従った回収が望めない場合をいうと解されている(脚注14)。
したがって、上記の金額基準以上の場合には、事例4において臨時報告書を遅滞なく提出する必要があり、これを怠った場合には、課徴金を課されることとなる。
(5)公開買付届出書の記載内容と課徴金 公開買付けにおいては、いわゆる敵対的な買収ではない限り、実務上、公開買付届出書において対象者側の行った措置まで記載されていることが多い。次のような事例ではどのように対応すべきか。
事例5 公開買付届出書における対象者に係る記載について虚偽記載等があった場合
X(公開買付者)は、その子会社であるYの株式に対する公開買付けに係る公開買付届出書において、Yにおける買付価格の公正性を担保するための措置および利益相反を回避するための措置が記載していたところ、Xの知らないところで、Yがその措置を講じていないことが後日判明した。
公開買付届出書の記載事項は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式において定められているところ、この様式の記載上の注意の文言上は、親子会社間における公開買付けであっても、対象者となる子会社において講じられた措置を公開買付届出書に記載すべき明示的な義務はないように思われる。
ただ、対象者となる子会社において講じられた措置が公開買付届出書の義務的記載事項でないとしても、当該措置が公開買付届出書に記載される限り、対象者の株主に対する適切な情報提供を行うという金商法の趣旨に鑑みると、その提出義務者である公開買付者が、金商法上の責任を免れることは難しいように思われる。
したがって、公開買付届出書に対象者における措置を記載するに際しては、その記載内容に虚偽記載等があれば課徴金を課されるリスクがあることを念頭に置いたうえで、今まで以上に公開買付届出書に記載する対象者において講じられた措置について事実をしっかり確認する必要があるものと考える。
(6)大量保有報告書の不提出・記載内容と課徴金 大量保有報告書については、有価証券報告書提出会社と異なり、開示書類の提出に不慣れな個人が提出することもあることなどから、他の開示書類に比して書類の不提出や記載事項の不備が生じやすいものと思われる。
事例6 大量保有報告または変更報告書の不提出事例(脚注15)
●ある上場会社の発行済株式総数の5%を超える株券を取得していたが、大量保有報告書の提出期限までに提出をせず、提出期限経過後に提出した。
●大量保有報告書を提出していたところ、その後、株式の買増しにより株券等保有割合が1%以上増加したが、大量保有変更報告書の提出期限までに提出をせず、提出期限経過後に提出した。
●大量保有報告書を提出していたところ、共同保有者が増えたことから、共同での株券等保有割合が1%以上増加したが、大量保有変更報告書の提出期限までに提出をせず、提出期限経過後に提出した。
いずれの場合も、課徴金を課されることとなるため、留意が必要である。
そのほか、保有株式について重要な契約を締結した場合(たとえば、1%以上の株式について貸株契約をする場合)や保有目的の変更を行った場合(たとえば、保有目的を純投資として大量保有報告書を提出していた者が、経営陣に対して重要提案行為を行うこととなった場合)についても、変更報告書の提出が必要であることも留意が必要である(脚注16)。
なお、保有目的については、保有目的に加え、その内容につきできる限り具体的に記載するものとされている(大量保有府令第1号様式)ところ、今まで以上に、その記載内容について慎重な判断を要することとなろう。
2 不公正取引関係
(1)インターネット上の掲示板に記載された事項と風説の流布 風説の流布については、改正前から課徴金制度の対象であったが、今般の改正により、明示的に違反行為と相場の変動の間の因果関係を法令で要求しなくとも、相場への影響と行為の目的から、外形的かつ合理的に因果関係が推認されるとの観点から、「違反行為による相場の変動」との要件が「違反行為による相場への影響」に改められている(脚注17)。
したがって、たとえば、インターネット上のある製薬会社に関する掲示板に同社が新薬を開発していないにもかかわらず、相場を変動させようとして新薬を開発したと記載して書込みを行った者が、当該書込みにより相場への影響を与え、同社の株式を市場において高値で売り抜けたといった場合には、課徴金の対象となるものと思われる。
(2)他人の計算によるインサイダー取引 前述Ⅰ3に記載のとおり、一定の範囲(図表4参照)で他人の計算による不公正取引が課徴金の対象行為とされた。
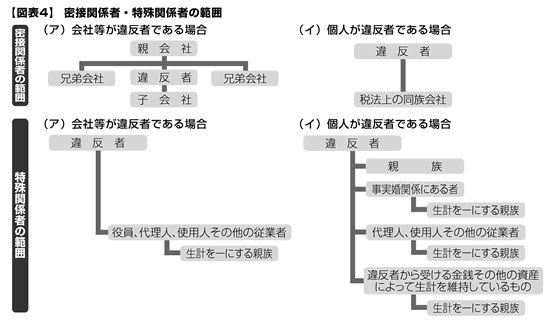
したがって、たとえば、未公表の重要事実を上場会社との契約の締結、交渉または履行に関して知った会社Xが(当該情報を知らない)子会社Yの計算でインサイダー取引を行わせた場合でも、Xの計算とみなされて、Xに課徴金が賦課されることとなる。ただし、Yが会社関係者または情報受領者として自らインサイダー取引規制に違反する場合には、Y自身が自己の計算によるインサイダー取引の課徴金の対象となり、Xは課徴金の対象とはならない。
違反行為が自己の計算によるか否かは、取引の実態に則し判断されるものであるが、たとえば、他人名義の口座が利用されている事案で自己の計算によると認定することが困難な場合に上記改正は意味があり、不公正取引における課徴金の補捉範囲が事実上拡大していると思われることから、グループ会社運営上も留意が必要である。
(なかむら・さとし/みねぎし・けんたろう)
脚注
1 大来志郎・鈴木謙輔「課徴金制度の見直し等に係る金融商品取引法等の改正の要点」本誌268号13頁以下、「課徴金制度の拡充に係る政府令改正を読み解く」本誌287号20頁以下、鈴木謙輔「課徴金制度の見直しに係る政府令整備の要点」本誌294号14頁以下参照。
2 本稿において、金融商品取引法は「法」または「金商法」、金融商品取引法施行令は「令」、企業内容等の開示に関する内閣府令は「開示府令」、株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令は「大量保有府令」、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令は「課徴金府令」という。
3 池田唯一・三井秀範ほか『逐条解説2008年金融商品取引法改正』(商事法務、2008年)100頁参照。
4 脚注1・大来ほか本誌268号20頁、脚注3・池田ほか101-102頁参照。
5 誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合は、前述のとおり課徴金の対象とはならないが、訂正命令の対象となり(法10条1項、23条の10第1項、24条の2第1項、24条の4の7第4項、24条の5第5項等)、民事責任の対象となるため(法18条、法21条の2第1項、法23条の12第5項等)、同様の対応をすることとなる。
6 脚注3・池田ほか402頁参照。
7 証券取引等監視委員会または金融庁もしくは各財務局・福岡財務支局・沖縄総合事務局。
8 脚注3・池田ほか110頁、402-403頁参照。
9 貨物運送業者のメール便では、信書(特定の受取人に対し差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書)を送付することはできない。
10 平成17年10月7日付「独占禁止法違反に対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取引委員会の方針」では、立入検査等の前に最初に課徴金の免除に係る報告および資料の提出を行った事業者および当該事業者の役員、従業員等であって調査への対応等において当該事業者と同様に評価すべき事情が認められる者については、告発を行わないこととすることが明記されている。
11 たとえば、神崎克郎・志谷匡史・川口恭弘『証券取引法』(青林書院、2006年)217頁参照。
12 勧誘については、そのほかにも様々な問題がある(中村聡・峯岸健太郎ほか『金融商品取引法 資本市場と開示編』(商事法務、2008年)106-115頁参照)。
13 脚注3・池田ほか178頁参照。
14 企業財務制度研究会編著『証券取引法における新「ディスクロージャー制度」詳解』(税務研究会出版局、2001年)180頁参照。
15 金融庁ホームページにおける平成20年11月28日付「大量保有報告制度における課徴金制度の開始について」参照。
16 変更報告書を提出すべき場合については、根本敏光『大量保有報告制度の実務』(商事法務、2009年)132頁以下参照。
17 脚注3・池田ほか338頁参照。
具体的事例を踏まえて紹介する
金融商品取引法改正後の課徴金制度における実務上の留意点
森・濱田松本法律事務所弁護士 中村 聡/弁護士 峯岸健太郎
本稿は、平成20年12月12日に施行された金融商品取引法の改正法(平成20年法律第65号)において重要な改正がなされた課徴金制度(脚注1)について、実務上の観点から考察するものである。以下では、改正の概要および留意点(本稿Ⅰ参照)、新たに設けられた減算制度の対象となる場合の対応方針・手続を述べたうえで(本稿Ⅱ参照)、「有価証券届出書の不提出」など新たに対象とされた違反行為について事例を設定しながら、各場合の具体的な対応・留意点を明らかにする(本稿Ⅲおよび図表1参照)(脚注2)。
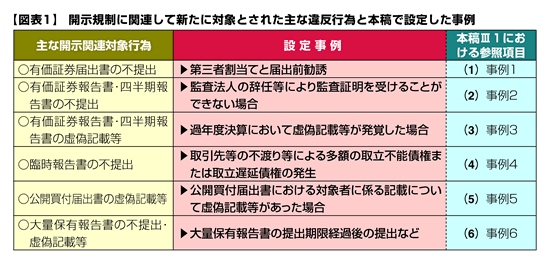
Ⅰ 課徴金の対象行為
1 改正後の課徴金制度の概要 金融商品取引法における課徴金は、金融・資本市場における違反行為を的確に抑止し、規制の実効性を確保していく観点から設けられた違反者に対して金銭的な負担を課す行政上の措置である。
今回の改正では、違反行為者が違反行為によって得た経済的利得相当額を基準として課徴金を課すという考え方を維持しつつも、違反行為の抑止の実効性をいっそう確保するという観点から、課徴金の水準を実質的に引き上げる方向での算定方法の見直し、課徴金の対象となる違反行為の拡大、加算・減算制度の導入などの措置が講じられている(脚注3)。
課徴金制度の対象となる違反行為は、開示規制違反と不公正取引とに大別される。改正後における課徴金の対象行為およびその課徴金額の基本的な計算方法について、改正で設けられた課徴金の減算制度の適用の有無および刑事罰則とともにまとめたものが、図表2-1(開示規制違反。今号6頁以下参照)、図表2-2(不公正取引。8頁以下参照)である。
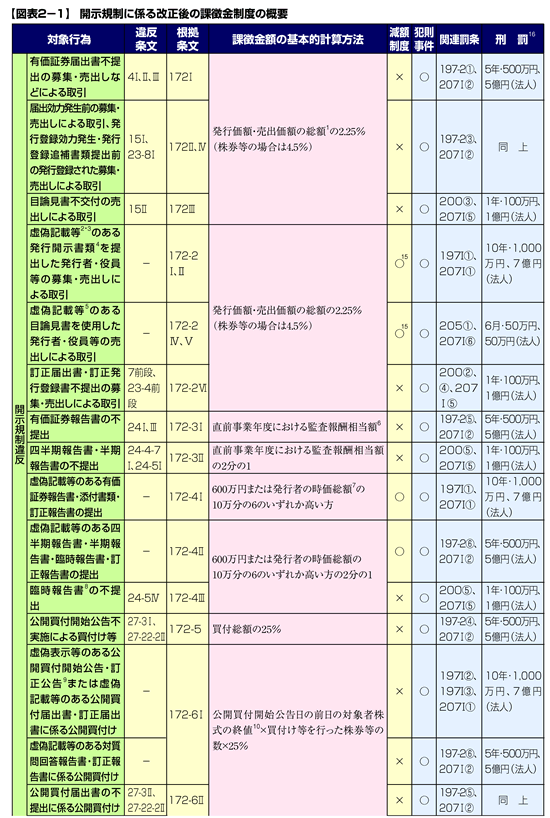
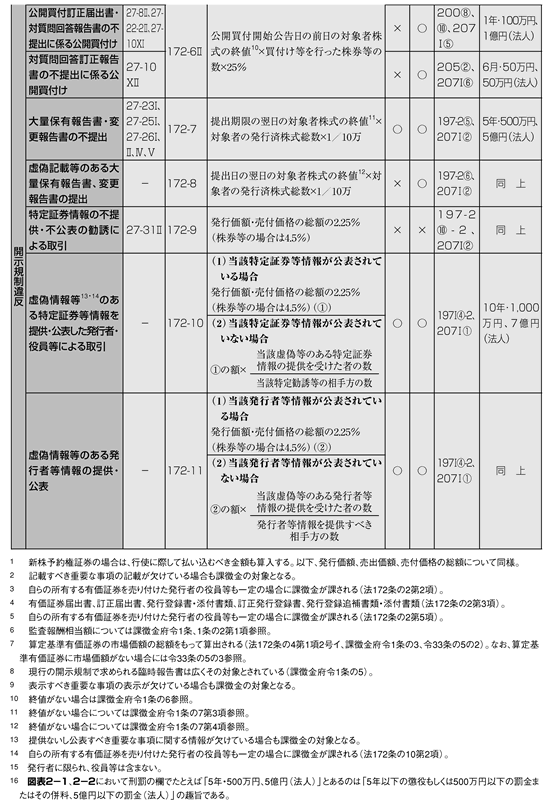
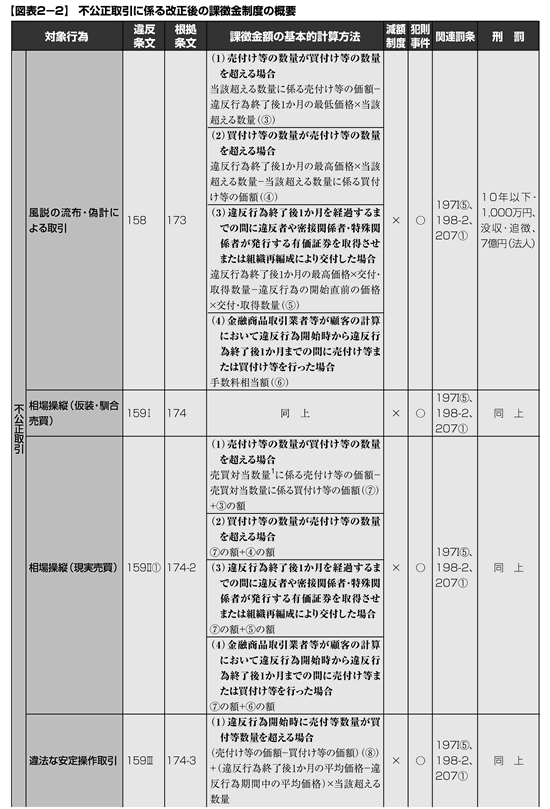
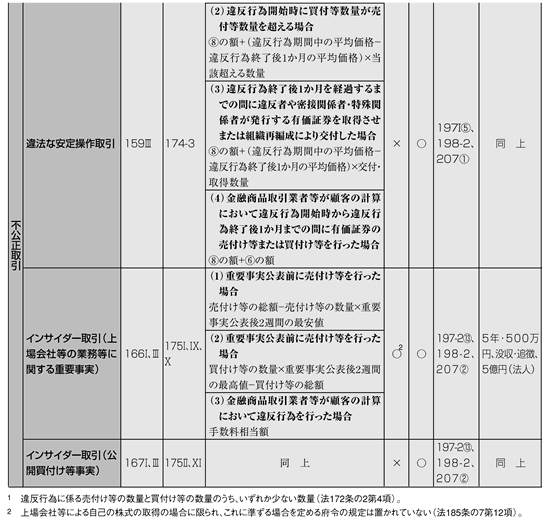
2 開示規制違反 開示規制違反に関する課徴金については、改正前の対象行為は次のものに限定されていた。
●発行開示書類(届出書類、発行登録関係書類、それらの添付書類、訂正書類および参照書類)ならびに目論見書の虚偽記載
●有価証券報告書(添付書類を含む)、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書およびそれらの訂正報告書の虚偽記載
改正により拡大された対象行為は図表2-1記載のとおりであるが、実務上留意すべき重要な事項としては、次の点が挙げられる。
第1に、情報開示における不実開示には、①重要な事項についての虚偽の記載、②記載すべき重要な事項が欠けていること、③誤解を生じさせないために必要な事実の記載が欠けていることの3類型があるところ、改正前は①の虚偽の記載のみが課徴金の対象とされていたが、改正後は②の記載すべき事項の不記載も対象とされたことである。
なお、罰則においては①の虚偽記載のみが対象とされ、民事責任規定においては①から③までのいずれもが責任根拠となりうる。
第2に、発行開示に関する違反行為抑止の観点から、届出前の勧誘禁止あるいは効力発生前の取引禁止に違反して有価証券を取得させた場合が課徴金制度の対象となったことである。この点については、後述Ⅲ・事例1を参照されたい。
第3に、開示書類の法定期限内における不提出の場合が対象とされた結果、たとえば決算処理を巡って監査法人または公認会計士が辞任した場合や監査意見を表明しない旨の監査報告書が出された場合には、有価証券報告書等を期限内に提出できなくなる結果、課徴金の対象とされることがありうる。また、臨時報告書については、開示府令19条2項各号に掲げる事由が発生した場合に遅滞なく提出しないときは課徴金の対象となる。これらの点については、後述Ⅲ・事例2・3・4を参照されたい。
公開買付けに関する開示書類についても課徴金制度の対象となったため、M&A実務や自己株公開買付けに携わる実務家は、開示の正確性・十分性に留意することが必要である。この点については、後述Ⅲ・事例5を参照されたい。
さらに、大量保有報告書またはその変更報告書についても、特例報告制度の適用を受けない通常の場合には、5営業日以内の提出が求められており、当該提出期限内に提出できないときは課徴金の対象となる。
特に、初めて大量保有報告書を提出する者の場合には、事前にEDINET利用のための電子開示システム届出書(添付書類として、内国法人の場合、定款またはこれに準ずるものおよび登記事項証明書またはこれに準ずるものが必要である)を提出しておくなどの準備をしておくことが望ましい(後述Ⅲ・事例6参照)。
なお、図表2-1からも明らかではあるが、開示書類のすべてが課徴金の対象となるものではない。参照の便宜を図るため、図表3(11頁参照)において各開示書類につき課徴金制度の適用の有無をまとめている。

3 不公正取引 課徴金の対象である不公正取引は、改正により、相場操縦行為等(法159条)のうち、現実売買による相場操縦(相場変動型相場操縦)(同条2項)に加えて、仮装売買・馴合売買による相場操縦(同条1項)および違法な安定操作取引(同条3項)が追加され、図表2-2に掲げたとおりとなっている。
実務上留意すべき重要な点としては、一定の範囲で他人の計算による不公正取引が追加されたことがある。
改正前は、違反行為による経済的利得を違反行為者に保持させないという課徴金制度の趣旨から、原則として自己の計算による不公正取引が対象行為とされ、例外的に上場会社等の計算によるインサイダー取引が行われた場合(法175条9項)が対象行為とされていた。
これに対し、改正により、違反行為の抑止の観点から、他人の計算による違反類型であっても、違反者が違反行為を通じて自己の利益を実現している場合と評価できるものとして、次のものが追加されている(脚注4)。
●金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業・登録金融機関業務における顧客または法42条1項に規定する権利者(投資運用業行為の相手方)(次の密接関係者・特殊関係者である場合を除く)の計算において不公正取引をした場合には、手数料相当額が課徴金の対象とされる(法175条1項3号、2項3号、課徴金府令1条の21等)。
●違反者と経済的に同一性があると認められる密接な関係にある者および特殊の関係にある者(図表4(16頁)参照)の計算において不公正取引(当該密接関係者・特殊関係者が自己の計算において行った不公正取引と同一のものを除く)を行った場合には、違反者が自己の計算において違反行為を行ったものとみなして課徴金が計算される(法175条10項、11項、課徴金府令1条の23等)。
Ⅱ 課徴金対象事実を発見した場合の減額報告
1 違法行為発見の場合の対応方針 課徴金の対象となる事実を発見した場合には、既に起きてしまったことについては所与の前提として、その時点で違反行為の是正、再発防止のための最大限の努力を行うのが正しい対応方針である。
開示書類の虚偽記載や記載すべき事項の不記載を発見した場合には(脚注5)、刑事・行政・民事上の責任がいずれも基本的には「重要な事実」を対象としていることから、まずは当該虚偽記載等が重要な事項に関するものであるかを検証することとなる。この際、決して事実を矮小化することなく、情報開示に通じた弁護士に相談するなどして健全かつ慎重な判断を行う必要がある。
虚偽記載等が重要な事項に関する場合には、訂正書類の提出が必要となるが(法7条後段、23条の4第2文、24条の2第1項、24条の4の7第4項、24条の5第5項等)、訂正書類の提出に向けて、開示すべき事項の確認、開示内容の確定などの作業を進めつつ、訂正書類の提出前に、管轄財務(支)局への報告および対応方針についての説明を行うことが適切である。
また、当該事項が上場証券取引所の規則に従い適時開示を行った事実である場合には、適時開示をした内容について訂正すべき事情が生じたときは直ちに訂正の内容を適時開示しなければならず、また事前に当該内容を上場証券取引所に説明をしなければならない(たとえば、東京証券取引所の有価証券上場規程416条)。
当該事項について適時開示を行ったか否かにかかわらず、課徴金の対象となる事実自体が法令違反行為(犯罪行為となる場合を含む)として投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすことが想定される場合には、当該事実を適時開示することが必要であり、また事前に上場証券取引所に説明することを要する(たとえば、上記規程402条1号ap、2号x、413条)。
このような適時開示を行うにあたっては、法令違反行為の事実、その原因、会社の運営、業績または財産状態に与える影響などにとどまらず、法令違反に対する是正措置、原因を踏まえた再発防止措置(検討中の場合にはその旨)についても投資者に対するメッセージとして盛り込むことが肝要である。
今般の改正により、課徴金の対象行為のうち一定のものについては、行政当局の調査のための処分が行われる前に自己申告した場合に課徴金額を半額とする課徴金の減算制度が導入されたため、所定の減額報告の手続に従い、証券取引等監視委員会に報告することも実務上の検討課題となる。
ただし、法令違反行為から5年を経過した時は課徴金手続の対象とはならない(法178条3項以下)。また、改正法の施行日以後の違反行為に対して適用されるため、平成20年12月11日以前に行われた違反行為については減算制度の対象とはならない。
2 減算制度 課徴金の減算制度は、違反行為者による自律的な是正機能の発揮を促すという観点から導入され、継続的・反復的に行われる可能性が高い違反行為については、早期発見がなされることの公益性が強く、早期発見のインセンティブを与えることが必要とされ(脚注6)、課徴金の対象行為のうち、図表2-1または2-2の「減額」欄において○が表示されているものについて、違反者が、行政当局(脚注7)による報告聴取または検査のいずれかの処分が行われる前に証券取引等監視員会に対し報告した場合には、課徴金額(複数の違反行為がある場合には最も遅いものに係る額に限る)が半額とされる(法185条の7第12項、課徴金府令61条の7)。
なお、課徴金の対象となる違反行為を繰り返す者は、違反行為が発覚して課徴金が課される危険を認識しつつ違反行為を行っているものと考えられ、前回と同じ算定方法による課徴金を課しても十分な違反行為の抑止効果は得られないことから(脚注8)、違反行為から過去5年以内に課徴金納付命令を受けたことがあるときは、課徴金額が1.5倍とされる(法185条の7第13項)。
3 減額報告手続
(1)減額報告書の作成および記載事項 課徴金の減算制度の適用を受けるためには、「課徴金の減額に係る報告書」(課徴金府令別紙様式)を作成して、証券取引等監視委員会に提出しなければならない。
減額報告書には、①違反の類型(いずれの対象行為に該当するか)、②違反の概要、③その他参考となるべき事項を具体的に記載しなければならない。
違反の概要としては、たとえば、次の事項を記載する。
●開示書類の虚偽記載等:開示書類の特定、虚偽記載等の内容
●開示書類の不提出:提出事由およびその発生時期、提出期限
●インサイダー取引:取引の方法・数量・価格および時期、重要事実の内容および時期
(2)減額報告書の提出方法 提出方法は、証券取引等監視委員会事務局課徴金・開示検査課に宛てて、①直接持参、②書留郵便、引受けおよび配達の記録を行う信書便またはこれらに準ずる方法(脚注9)による送付、③ファクシミリによる送信のいずれかの方法による(課徴金府令61条の7第1項)。金融庁または各財務局に提出しても受理されない。
①の方法による場合は、平日の午前9時30分から午後6時までが受理時間である。
②の方法による場合は、発送の時に提出されたものとみなされる(同条2項)。普通郵便による送付は受理されない。
③の方法による場合は、03-3506-6222に送信しなければならず、証券取引等監視委員会が受信した時に提出されたものとみなされるが、原本を遅滞なく証券取引等監視委員会に提出(郵送による場合は普通郵便も可)しなければならない(同条3項、4項)。
減額報告がなされると、記載事項の確認とその後の手続等に関する説明のための連絡がなされ、その後必要に応じて違反内容に関する資料の提出等が求められることがある。
(3)減額報告の際のその他の留意事項 減額報告は、上述のとおり、所定の手続に従って行われなければならないため、たとえば、開示書類の虚偽記載等について、訂正報告書などを提出したり、虚偽記載等がある旨を適時開示しても、また大量保有報告書・変更報告書を提出期限経過後に提出しても、課徴金の減算制度の適用を受けられないことに留意する必要がある。
したがって、減算制度の対象となる違反行為を発見した場合には、まずは減額報告をしたうえで、間を置かずに、たとえば、法定開示書類として訂正報告書、大量保有報告書・変更報告書などを提出し、併せて適時開示および上場証券取引所への事前説明を行うということになろう。
なお、課徴金の対象行為であっても、悪質な事案に対しては、犯則事件(法210条、令45条)として調査し、犯則の心証を得たときは刑事告発する(法226条1項)のが証券取引等監視委員会の一般的な方針のようである。減額報告をした場合に、証券取引等監視委員会が課徴金調査にとどまらず犯則調査の対象とすることがあるかについては、証券取引等監視委員会の方針は明らかにされていない(脚注10)。
刑事事件となることが想定される場合には、裁量的減軽事由である自首(刑法42条)に該当するには検察官または司法警察員に対する申告が必要となるため、減額報告とは別途手続をとる必要がある。
Ⅲ 課徴金リスクに留意すべき事例
1 開示関係
(1)有価証券届出書の不提出と課徴金 新規発行有価証券に関するある行為が、取得勧誘(法2条3項)に該当する場合には、当該取得勧誘を開始する前に有価証券届出書を提出して届出を行っていなければ、課徴金の対象となる。
具体的には、次のような事案が考えられる。
事例1 第三者割当てと届出前勧誘
X(日本における上場会社)は、その財務体質の強化のために資本増強を行う必要があるが、現在の市況ではいわゆる公募増資を行うことが難しいため、その発行する上場株式と同種の株式をY(Xの取引先)に対して割り当てる第三者割当増資を行うことを検討しており、日本においてYとの間で交渉を行っている。
日本における上場会社が、その上場株式と同種の株式の株式を発行する場合、私募を行うことができない(令1条の4第1号、1条の7第1号イ等)ことから、法4条1項各号に掲げるいずれかに該当しない限り、その株式に関して取得勧誘を行う前に届出を行わなければならない。
しかしながら、金商法において、どのような行為が取得勧誘に該当するかということについては明確に規定されておらず、わずかに、有価証券の募集または売出しに関する文書を頒布することや新聞等において募集または売出しに係る広告をすることは、「有価証券の募集又は売出し」に該当するということが開示ガイドラインで規定されているにすぎない(企業内容等の開示に関する留意事項4-1)。
そこで、どのような行為が有価証券の取得勧誘に該当するかということが解釈上問題となるが、一般的には、有価証券の勧誘とは、特定の有価証券についての投資者の関心を高め、その取得・買付けを促進することとなる行為と解されている(脚注11)。したがって、届出前の行為がこのように解されるものかどうかという観点から、検証を行う必要がある。
ただし、このように勧誘概念を捉えたとしても、どのような行為が「勧誘」に該当するかは、なお不明確であることから、個別具体的な事案においては慎重な判断とならざるを得ないが、特に上場株式と同種の株式を発行することによって第三者割当てを行う場合、取締役会による発行決議とその前後の届出前の行為が金商法上の勧誘に該当しないように留意する必要がある(脚注12)。
(2)有価証券報告書・四半期報告書の不提出と課徴金 上場会社においては、一般的に、有価証券報告書や四半期報告書がその提出期限までに提出されないということは想定し難いが、次のような事例ではどうか。
事例2 監査法人の辞任等により監査証明を受けることができない場合
X(日本における上場会社)は、有価証券報告書の提出準備を行っていたが、その提出期限が迫ってきているところで、監査法人との意見の相違により、監査契約を合意解約した。しかしながら、直ちに新たな監査法人との監査契約を締結することはできず、有価証券報告書をその提出期限までに提出できない見込みである。
改正前までは、有価証券報告書を提出期限までに提出できないような場合に関する規定が金商法上設けられていなかった。この場合、おそらくは、各社が管轄財務(支)局に事情と提出時期の目途を説明するなどして事実上の提出遅延の報告を行って対応している事案が多かったと思われる。
ただし、証券取引所の適時開示に関する規則では有価証券報告書等の提出の遅延は適時開示事由になっており、その会社が上場する証券取引所において「有価証券報告書提出の遅延について」等との表題で、有価証券報告書を期限までに提出できないこと、その理由および提出時期の見込み等を開示していた。
しかしながら、改正後の金商法においては、有価証券報告書等の不提出も課徴金の対象とされたことなどを踏まえ、やむを得ない理由による有価証券報告書等の提出期限延長に係る承認手続が設けられた(脚注13)こと(法24条1項、開示府令15条の2等)から、たとえば事例2のような場合であっても、有価証券報告書の提出期限延長に係る承認を得ない限りは、違法な有価証券報告書の不提出として、課徴金の対象とされるものと思われる。
したがって、事例2のような場合に限らず、何らかの事情により有価証券報告書等をその期限内に提出できないような見込みが発生した場合には、有価証券報告書等の提出期限延長に係る承認手続を申請し、承認を得られるよう努めることが必要である。
なお、承認がいかなる場合にされるかは明らかではない。
(3)有価証券報告書・四半期報告書の訂正と課徴金 近時、有価証券報告書の過年度決算に係る訂正報告書の提出がなされる事案が比較的多く見受けられるようになっている。次のような事案では、どのように対応すべきか。
事例3 過年度決算において虚偽記載等が発覚した場合
X(日本における上場会社)は、内部監査の過程において不適切な取引の疑惑が発覚し、さらに詳細な内部調査を行ったところ、過年度決算の訂正と有価証券報告書の訂正報告書を必要とし、かつ、当該訂正が行われなければ、記載すべき重要な事項が欠けているといえるような事態が内部調査で明らかになった。
このような場合、前述Ⅱ1に記載のとおり、不適切な取引の疑惑が発覚した時点において弁護士等の外部の専門家を入れ、集中的に事実の解明を行う必要がある。
そして、課徴金の減算制度の適用を受けられるように必要な準備を行ったうえで証券取引等監視委員会に減額報告をし、また同時並行的に、訂正報告書の作成と提出についても、事前に管轄財務(支)局への報告および対応方針についての説明を行うことが必要である。
(4)臨時報告書の不提出と課徴金 臨時報告書は、その提出事由に該当する場合には、遅滞なく提出しなければならないとされており(法24条の5第4項)、提出事由は多岐にわたる(開示府令19条2項)が、次のような事例ではどのように対応すべきか。
事例4 取引先等の不渡り等による多額の取立不能債権または取立遅延債権の発生
X(有価証券報告書を提出しなければならない会社)は、その取引先Yにおいて不渡りが発生し、Yからの売掛金債権を約定どおり回収できないことが明らかとなったことから、臨時報告書の提出の要否を検討している。
有価証券報告書提出会社の債務者や保証人に手形の不渡りや破産手続開始の申立て等があり、提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の3%以上に相当する額の債権につき取立不能または取立遅延のおそれが生じた場合には、臨時報告書を提出しなければならない(開示府令19条2項11号)。
この「取立不能または取立遅延のおそれが生じた場合」とは、一般的には正常な債権の回収が望めなくなった場合、すなわち約定などに従った回収が望めない場合をいうと解されている(脚注14)。
したがって、上記の金額基準以上の場合には、事例4において臨時報告書を遅滞なく提出する必要があり、これを怠った場合には、課徴金を課されることとなる。
(5)公開買付届出書の記載内容と課徴金 公開買付けにおいては、いわゆる敵対的な買収ではない限り、実務上、公開買付届出書において対象者側の行った措置まで記載されていることが多い。次のような事例ではどのように対応すべきか。
事例5 公開買付届出書における対象者に係る記載について虚偽記載等があった場合
X(公開買付者)は、その子会社であるYの株式に対する公開買付けに係る公開買付届出書において、Yにおける買付価格の公正性を担保するための措置および利益相反を回避するための措置が記載していたところ、Xの知らないところで、Yがその措置を講じていないことが後日判明した。
公開買付届出書の記載事項は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式において定められているところ、この様式の記載上の注意の文言上は、親子会社間における公開買付けであっても、対象者となる子会社において講じられた措置を公開買付届出書に記載すべき明示的な義務はないように思われる。
ただ、対象者となる子会社において講じられた措置が公開買付届出書の義務的記載事項でないとしても、当該措置が公開買付届出書に記載される限り、対象者の株主に対する適切な情報提供を行うという金商法の趣旨に鑑みると、その提出義務者である公開買付者が、金商法上の責任を免れることは難しいように思われる。
したがって、公開買付届出書に対象者における措置を記載するに際しては、その記載内容に虚偽記載等があれば課徴金を課されるリスクがあることを念頭に置いたうえで、今まで以上に公開買付届出書に記載する対象者において講じられた措置について事実をしっかり確認する必要があるものと考える。
(6)大量保有報告書の不提出・記載内容と課徴金 大量保有報告書については、有価証券報告書提出会社と異なり、開示書類の提出に不慣れな個人が提出することもあることなどから、他の開示書類に比して書類の不提出や記載事項の不備が生じやすいものと思われる。
事例6 大量保有報告または変更報告書の不提出事例(脚注15)
●ある上場会社の発行済株式総数の5%を超える株券を取得していたが、大量保有報告書の提出期限までに提出をせず、提出期限経過後に提出した。
●大量保有報告書を提出していたところ、その後、株式の買増しにより株券等保有割合が1%以上増加したが、大量保有変更報告書の提出期限までに提出をせず、提出期限経過後に提出した。
●大量保有報告書を提出していたところ、共同保有者が増えたことから、共同での株券等保有割合が1%以上増加したが、大量保有変更報告書の提出期限までに提出をせず、提出期限経過後に提出した。
いずれの場合も、課徴金を課されることとなるため、留意が必要である。
そのほか、保有株式について重要な契約を締結した場合(たとえば、1%以上の株式について貸株契約をする場合)や保有目的の変更を行った場合(たとえば、保有目的を純投資として大量保有報告書を提出していた者が、経営陣に対して重要提案行為を行うこととなった場合)についても、変更報告書の提出が必要であることも留意が必要である(脚注16)。
なお、保有目的については、保有目的に加え、その内容につきできる限り具体的に記載するものとされている(大量保有府令第1号様式)ところ、今まで以上に、その記載内容について慎重な判断を要することとなろう。
2 不公正取引関係
(1)インターネット上の掲示板に記載された事項と風説の流布 風説の流布については、改正前から課徴金制度の対象であったが、今般の改正により、明示的に違反行為と相場の変動の間の因果関係を法令で要求しなくとも、相場への影響と行為の目的から、外形的かつ合理的に因果関係が推認されるとの観点から、「違反行為による相場の変動」との要件が「違反行為による相場への影響」に改められている(脚注17)。
したがって、たとえば、インターネット上のある製薬会社に関する掲示板に同社が新薬を開発していないにもかかわらず、相場を変動させようとして新薬を開発したと記載して書込みを行った者が、当該書込みにより相場への影響を与え、同社の株式を市場において高値で売り抜けたといった場合には、課徴金の対象となるものと思われる。
(2)他人の計算によるインサイダー取引 前述Ⅰ3に記載のとおり、一定の範囲(図表4参照)で他人の計算による不公正取引が課徴金の対象行為とされた。
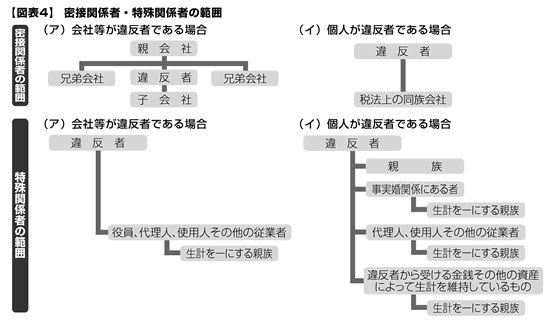
したがって、たとえば、未公表の重要事実を上場会社との契約の締結、交渉または履行に関して知った会社Xが(当該情報を知らない)子会社Yの計算でインサイダー取引を行わせた場合でも、Xの計算とみなされて、Xに課徴金が賦課されることとなる。ただし、Yが会社関係者または情報受領者として自らインサイダー取引規制に違反する場合には、Y自身が自己の計算によるインサイダー取引の課徴金の対象となり、Xは課徴金の対象とはならない。
違反行為が自己の計算によるか否かは、取引の実態に則し判断されるものであるが、たとえば、他人名義の口座が利用されている事案で自己の計算によると認定することが困難な場合に上記改正は意味があり、不公正取引における課徴金の補捉範囲が事実上拡大していると思われることから、グループ会社運営上も留意が必要である。
(なかむら・さとし/みねぎし・けんたろう)
脚注
1 大来志郎・鈴木謙輔「課徴金制度の見直し等に係る金融商品取引法等の改正の要点」本誌268号13頁以下、「課徴金制度の拡充に係る政府令改正を読み解く」本誌287号20頁以下、鈴木謙輔「課徴金制度の見直しに係る政府令整備の要点」本誌294号14頁以下参照。
2 本稿において、金融商品取引法は「法」または「金商法」、金融商品取引法施行令は「令」、企業内容等の開示に関する内閣府令は「開示府令」、株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令は「大量保有府令」、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令は「課徴金府令」という。
3 池田唯一・三井秀範ほか『逐条解説2008年金融商品取引法改正』(商事法務、2008年)100頁参照。
4 脚注1・大来ほか本誌268号20頁、脚注3・池田ほか101-102頁参照。
5 誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合は、前述のとおり課徴金の対象とはならないが、訂正命令の対象となり(法10条1項、23条の10第1項、24条の2第1項、24条の4の7第4項、24条の5第5項等)、民事責任の対象となるため(法18条、法21条の2第1項、法23条の12第5項等)、同様の対応をすることとなる。
6 脚注3・池田ほか402頁参照。
7 証券取引等監視委員会または金融庁もしくは各財務局・福岡財務支局・沖縄総合事務局。
8 脚注3・池田ほか110頁、402-403頁参照。
9 貨物運送業者のメール便では、信書(特定の受取人に対し差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書)を送付することはできない。
10 平成17年10月7日付「独占禁止法違反に対する刑事告発及び犯則事件の調査に関する公正取引委員会の方針」では、立入検査等の前に最初に課徴金の免除に係る報告および資料の提出を行った事業者および当該事業者の役員、従業員等であって調査への対応等において当該事業者と同様に評価すべき事情が認められる者については、告発を行わないこととすることが明記されている。
11 たとえば、神崎克郎・志谷匡史・川口恭弘『証券取引法』(青林書院、2006年)217頁参照。
12 勧誘については、そのほかにも様々な問題がある(中村聡・峯岸健太郎ほか『金融商品取引法 資本市場と開示編』(商事法務、2008年)106-115頁参照)。
13 脚注3・池田ほか178頁参照。
14 企業財務制度研究会編著『証券取引法における新「ディスクロージャー制度」詳解』(税務研究会出版局、2001年)180頁参照。
15 金融庁ホームページにおける平成20年11月28日付「大量保有報告制度における課徴金制度の開始について」参照。
16 変更報告書を提出すべき場合については、根本敏光『大量保有報告制度の実務』(商事法務、2009年)132頁以下参照。
17 脚注3・池田ほか338頁参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























