解説記事2009年05月18日 【巻頭特集】 インサイダー取引を巡る近時の関係機関の対応(2009年5月18日号・№306)
新しい監視体制も今春から稼動!
インサイダー取引を巡る近時の関係機関の対応
東京証券取引所自主規制法人売買審査部総務・企画・取引相談グループ調査役 吉松和彦
今年に入ってからも依然として跡を絶つことのないインサイダー取引を巡っては、関係法令の整備による課徴金制度の拡充とともに(大来志郎・鈴木謙輔「課徴金制度の見直し等に係る金融商品取引法等の改正の要点」本誌268号13頁、鈴木謙輔「課徴金制度の見直しに係る政府令整備の要点」294号14頁、中村聡・峯岸健太郎「金融商品取引法改正後の課徴金制度における実務上の留意点」296号4頁参照)、証券界を挙げての取組みが図られてきた。その一端として、東京証券取引所自主規制法人の対応等を中心に昨秋紹介したところであるが(吉松和彦「インサイダー取引の未然防止と東証COMLECの取組み」279号4頁)、今春に至り、市場監視のための2つのインフラが稼動するなど、インサイダー取引の未然防止を図るための環境はさらなる変貌を遂げている。近時の関係機関の対応をまとめていただいた。 (編集部)
Ⅰ はじめに
平成20年12月に改正金融商品取引法が施行され、課徴金制度が強化されるとともに子会社の解散に係る重要事実に軽微基準が新設された。
しかし、インサイダー取引については、引き続き課徴金事案や告発事案が散見されており、当局・自主規制機関を含めた市場監視体制の強化が進められている。
本稿は、このような関係機関におけるインサイダー取引関連の最近の対応状況を紹介するものである。
Ⅱ 市場監視体制の強化に係る対応
1 市場監視インフラの整備 まず、証券業界に新たに設けられた市場監視インフラを紹介する。
平成18年3月に金融庁監督局に設置された「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」の論点整理(平成18年6月)において、「不公正取引に関する市場関係者(当局を含む)間の情報交換を迅速かつ円滑に行うための電子データの様式の見直しやWANの構築等について検討を進める観点から、証券業協会及び証券取引所を中心として具体的な検討を行っていくことが必要」とされた。
これを受け、日本証券業協会および証券取引所を中心に具体的な施策の検討が進められ、市場監視のための情報交換インフラとして、当局・自主規制機関・証券会社を結ぶ専用ネットワークが開発された。これが「コンプライアンスWAN」である(図1参照)。
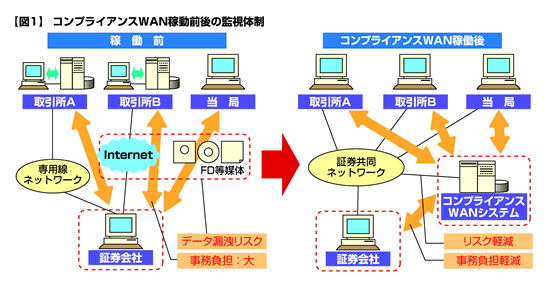
インサイダー取引等の不公正取引の監視は、当局・自主規制機関・証券会社が売買内容の分析に必要となる顧客情報を集約することで行われており、監視対象期間に関与した証券会社や投資者が多い場合には、その詳細データの収集に相当の時間を要していた。
また、監視対象銘柄が複数の市場で売買されている場合には、データ授受に関するフォーマットや提出方法を個々に調整する必要があるため、証券会社側の負担軽減の観点からも統一インフラの構築が求められていた。
このような問題点を解決するため、東京証券取引所を中心にコンプライアンスWANの開発が行われ、本年1月から東証および当局による利用が、4月から各地取引所および日本証券業協会による利用が開始した。
コンプライアンスWANの稼動により、これまで以上に迅速で円滑な市場監視が可能となる。
2 内部者登録制度の機能向上 前述の「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」では、不公正取引に関する論点整理のもう1つの柱として、日本証券業協会が定める「内部者登録制度」の実効性を高める施策の検討が提案された。
日本証券業協会では、インサイダー取引の未然防止の観点から、顧客が口座を開設する際、その者が上場会社の役職員であるなど一定の関係にある場合は、インサイダー取引規制上の会社関係者等に該当する可能性がある者として内部者登録を証券会社各社に義務付けているが、異動や住所変更等により登録情報が実際と異なるケースが多くあり、内部者登録制度の実効性の確保が求められていた。
そこで、同協会を中心に、日本経済団体連合会・上場会社・証券取引所による検討がなされ、上場会社役員の情報を一元的にデータベースに保持し、変更内容を随時更新できるシステム「J-IRISS(Japan-Insider Registration & Identification Support System:ジェイ・アイリス)」が構築されることとなり(図2参照)、本年5月下旬から運用が開始される予定である。
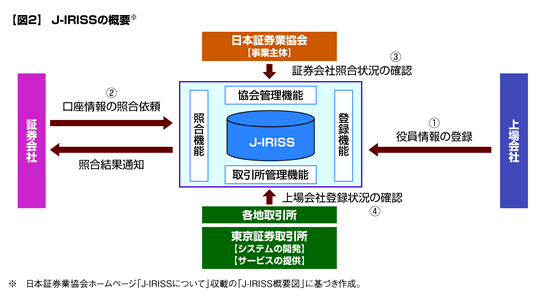
従前の内部者登録制度では、証券会社に対して、顧客の口座開設時の情報登録と、その後の定期的な更新を求めていたが、J-IRISSを用いた新制度では、上場会社に対して、自社役員等の情報の登録・更新を求めている点が大きく異なる。
具体的には、上場会社が、①上場会社役員、②適時開示対象となる非上場親会社役員、③上場会社が純粋持株会社の場合は中核子会社(1社)役員の氏名・生年月日・住所等をJ-IRISSにオンラインで登録し、変更の都度更新することとなる(詳細については、日本証券業協会ホームページ「J-IRISSについて」参照(http://www.jsda.or.jp/html/J-IRISS/index.html))。
登録された情報に基づき、証券会社が上場会社役員等からの注文受託時に確認を行うことから、上場会社各社における自社株売買に係る事前届出制等のインサイダー取引防止策との二重チェックが働き、インサイダー取引規制や上場会社自身の社内ルールの理解不足あるいは存在を知らずに行う売買に際して、いわゆる「うっかりインサイダー」を防止するとともに、上場会社等の役員等による売買報告義務(金商法163条)、短期売買差益の返還有無の確認(同法164条)などの手続漏れを防ぐ役割を果たすことが期待される。
なお、登録された情報については、証券会社が自社の顧客情報をJ-IRISSに登録された情報とマッチングさせ、合致したもののみその旨回答される仕組みであるため、当該証券会社の直接の顧客ではない役員の情報は閲覧されない仕組みとなっている。
昨今のインサイダー取引に伴う課徴金・告発事案の増加を背景として、上場会社による自社役職員のインサイダー取引防止策が講じられているところであるが、引き続き「うっかりインサイダー」が散見されていることから、上場会社各社においては、自社のコンプライアンス強化の一環として本制度を積極的に活用してくださるようお願いしたい。
3 売買実態に則した市場監視体制の強化 昨今のインサイダー取引に係る課徴金・告発事案にみられるように、インサイダー取引等の不公正取引は、海外の投資ファンドを利用するケースや、他人名義の口座を利用するなど複雑化が進んでいる。
このため、前述のような明らかな内部者ではない者によるインサイダー取引についても監視体制が強化されている。
具体的には、証券会社における不公正取引の未然防止策として、証券会社が自社顧客の発注形態に対して一定の監視を行うことを義務付けた規則「不公正取引の防止のための売買管理体制の整備に関する規則」が日本証券業協会と全国の取引所共通の規則として平成17年11月に制定されているが、証券会社が、自社顧客のなかから重要事実公表前後にタイミングよく売買を行った顧客を抽出し、当局および証券取引所に報告する内容の規則改正がなされ、本年4月から新運用が開始された。
先般摘発されたインサイダー取引事件に、投資会社元会長が業績下方修正の公表前に海外投資ファンドを経由して売却、損失回避した事案や、上場会社監査役がM&A情報の公表前に他人名義の口座を利用して対象会社の株式を買い付けた事案などがあるが、このような成りすましやクロスボーダー取引を利用して上場会社との関係をわかりにくくした発注形態であっても、確実に調査対象となるよう体制整備が図られている。
Ⅲ 上場会社の自己株式取得に係る対応
法制度面の対応としては、昨年12月に施行した改正金融商品取引法において、課徴金制度の強化と重要事実の子会社の解散に係る軽微基準の新設がなされており、また、自己株式取得時の留意点を示したQ&Aが公表されている。
このほか、インサイダー取引とは直接関係するわけではないが、法人による自己株式取得については「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」に規定された買付要件(①1日の買付数量の上限:直近4週間の1日当たり平均売買高の25%、②買付時間:取引終了時刻の直前30分は禁止、③買付価格:直近の売買価格を上回らない価格、④証券会社数:1日1社の証券会社のみを通じた買付け)を、本年7月31日までの時限措置として緩和(①を25%から100%に引上げ、②を適用しない)する旨、3月24日付で金融庁が発表しているため、留意されたい(金融庁ホームページ参照(http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20090324-4.html))。
Ⅳ 結びに代えて─全国上場会社内部者取引管理アンケートの実施─
最後に、東京証券取引所自主規制法人の最近の主な対応を紹介する。
当法人では、一昨年、全国の証券取引所とともに初めて行ったインサイダー取引管理に関する全国調査「全国上場会社内部者取引管理アンケート」(調査報告書は平成19年5月公表)の第2回を本年2月13日付で実施した。
前回のアンケート調査では、重要事実の認識時期が遅いと思われる上場会社が4割に達するなど、インサイダー取引規制に対する理解が十分ではないと思われる上場会社が多くみられたが、昨今の課徴金事案の増加等を背景として上場会社各社における規制に対する理解や体制整備等の対応が進展していることから、今回の調査では、このような進展度合いや具体的な施策例を取りまとめ、本年6月を目途に報告書として各取引所のホームページ等で公表する予定である。
なお、当法人が設置するコンプライアンス教育機関である東証COMLECでは、インサイダー取引規制の解説冊子『こんぷらくんのインサイダー取引規制Q&A(金融商品取引法平成20年改正対応版)』およびeラーニング研修サービス新コンテンツ「こんぷらくんの株価操作規制入門」等を新たに今春からリリースしている。是非ご利用いただきたい。 (よしまつ・かずひこ)
インサイダー取引を巡る近時の関係機関の対応
東京証券取引所自主規制法人売買審査部総務・企画・取引相談グループ調査役 吉松和彦
今年に入ってからも依然として跡を絶つことのないインサイダー取引を巡っては、関係法令の整備による課徴金制度の拡充とともに(大来志郎・鈴木謙輔「課徴金制度の見直し等に係る金融商品取引法等の改正の要点」本誌268号13頁、鈴木謙輔「課徴金制度の見直しに係る政府令整備の要点」294号14頁、中村聡・峯岸健太郎「金融商品取引法改正後の課徴金制度における実務上の留意点」296号4頁参照)、証券界を挙げての取組みが図られてきた。その一端として、東京証券取引所自主規制法人の対応等を中心に昨秋紹介したところであるが(吉松和彦「インサイダー取引の未然防止と東証COMLECの取組み」279号4頁)、今春に至り、市場監視のための2つのインフラが稼動するなど、インサイダー取引の未然防止を図るための環境はさらなる変貌を遂げている。近時の関係機関の対応をまとめていただいた。 (編集部)
Ⅰ はじめに
平成20年12月に改正金融商品取引法が施行され、課徴金制度が強化されるとともに子会社の解散に係る重要事実に軽微基準が新設された。
しかし、インサイダー取引については、引き続き課徴金事案や告発事案が散見されており、当局・自主規制機関を含めた市場監視体制の強化が進められている。
本稿は、このような関係機関におけるインサイダー取引関連の最近の対応状況を紹介するものである。
Ⅱ 市場監視体制の強化に係る対応
1 市場監視インフラの整備 まず、証券業界に新たに設けられた市場監視インフラを紹介する。
平成18年3月に金融庁監督局に設置された「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」の論点整理(平成18年6月)において、「不公正取引に関する市場関係者(当局を含む)間の情報交換を迅速かつ円滑に行うための電子データの様式の見直しやWANの構築等について検討を進める観点から、証券業協会及び証券取引所を中心として具体的な検討を行っていくことが必要」とされた。
これを受け、日本証券業協会および証券取引所を中心に具体的な施策の検討が進められ、市場監視のための情報交換インフラとして、当局・自主規制機関・証券会社を結ぶ専用ネットワークが開発された。これが「コンプライアンスWAN」である(図1参照)。
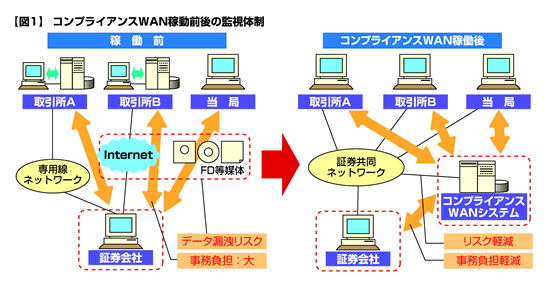
インサイダー取引等の不公正取引の監視は、当局・自主規制機関・証券会社が売買内容の分析に必要となる顧客情報を集約することで行われており、監視対象期間に関与した証券会社や投資者が多い場合には、その詳細データの収集に相当の時間を要していた。
また、監視対象銘柄が複数の市場で売買されている場合には、データ授受に関するフォーマットや提出方法を個々に調整する必要があるため、証券会社側の負担軽減の観点からも統一インフラの構築が求められていた。
このような問題点を解決するため、東京証券取引所を中心にコンプライアンスWANの開発が行われ、本年1月から東証および当局による利用が、4月から各地取引所および日本証券業協会による利用が開始した。
コンプライアンスWANの稼動により、これまで以上に迅速で円滑な市場監視が可能となる。
2 内部者登録制度の機能向上 前述の「証券会社の市場仲介機能等に関する懇談会」では、不公正取引に関する論点整理のもう1つの柱として、日本証券業協会が定める「内部者登録制度」の実効性を高める施策の検討が提案された。
日本証券業協会では、インサイダー取引の未然防止の観点から、顧客が口座を開設する際、その者が上場会社の役職員であるなど一定の関係にある場合は、インサイダー取引規制上の会社関係者等に該当する可能性がある者として内部者登録を証券会社各社に義務付けているが、異動や住所変更等により登録情報が実際と異なるケースが多くあり、内部者登録制度の実効性の確保が求められていた。
そこで、同協会を中心に、日本経済団体連合会・上場会社・証券取引所による検討がなされ、上場会社役員の情報を一元的にデータベースに保持し、変更内容を随時更新できるシステム「J-IRISS(Japan-Insider Registration & Identification Support System:ジェイ・アイリス)」が構築されることとなり(図2参照)、本年5月下旬から運用が開始される予定である。
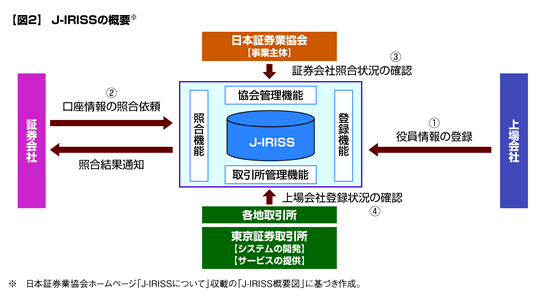
従前の内部者登録制度では、証券会社に対して、顧客の口座開設時の情報登録と、その後の定期的な更新を求めていたが、J-IRISSを用いた新制度では、上場会社に対して、自社役員等の情報の登録・更新を求めている点が大きく異なる。
具体的には、上場会社が、①上場会社役員、②適時開示対象となる非上場親会社役員、③上場会社が純粋持株会社の場合は中核子会社(1社)役員の氏名・生年月日・住所等をJ-IRISSにオンラインで登録し、変更の都度更新することとなる(詳細については、日本証券業協会ホームページ「J-IRISSについて」参照(http://www.jsda.or.jp/html/J-IRISS/index.html))。
登録された情報に基づき、証券会社が上場会社役員等からの注文受託時に確認を行うことから、上場会社各社における自社株売買に係る事前届出制等のインサイダー取引防止策との二重チェックが働き、インサイダー取引規制や上場会社自身の社内ルールの理解不足あるいは存在を知らずに行う売買に際して、いわゆる「うっかりインサイダー」を防止するとともに、上場会社等の役員等による売買報告義務(金商法163条)、短期売買差益の返還有無の確認(同法164条)などの手続漏れを防ぐ役割を果たすことが期待される。
なお、登録された情報については、証券会社が自社の顧客情報をJ-IRISSに登録された情報とマッチングさせ、合致したもののみその旨回答される仕組みであるため、当該証券会社の直接の顧客ではない役員の情報は閲覧されない仕組みとなっている。
昨今のインサイダー取引に伴う課徴金・告発事案の増加を背景として、上場会社による自社役職員のインサイダー取引防止策が講じられているところであるが、引き続き「うっかりインサイダー」が散見されていることから、上場会社各社においては、自社のコンプライアンス強化の一環として本制度を積極的に活用してくださるようお願いしたい。
3 売買実態に則した市場監視体制の強化 昨今のインサイダー取引に係る課徴金・告発事案にみられるように、インサイダー取引等の不公正取引は、海外の投資ファンドを利用するケースや、他人名義の口座を利用するなど複雑化が進んでいる。
このため、前述のような明らかな内部者ではない者によるインサイダー取引についても監視体制が強化されている。
具体的には、証券会社における不公正取引の未然防止策として、証券会社が自社顧客の発注形態に対して一定の監視を行うことを義務付けた規則「不公正取引の防止のための売買管理体制の整備に関する規則」が日本証券業協会と全国の取引所共通の規則として平成17年11月に制定されているが、証券会社が、自社顧客のなかから重要事実公表前後にタイミングよく売買を行った顧客を抽出し、当局および証券取引所に報告する内容の規則改正がなされ、本年4月から新運用が開始された。
先般摘発されたインサイダー取引事件に、投資会社元会長が業績下方修正の公表前に海外投資ファンドを経由して売却、損失回避した事案や、上場会社監査役がM&A情報の公表前に他人名義の口座を利用して対象会社の株式を買い付けた事案などがあるが、このような成りすましやクロスボーダー取引を利用して上場会社との関係をわかりにくくした発注形態であっても、確実に調査対象となるよう体制整備が図られている。
Ⅲ 上場会社の自己株式取得に係る対応
法制度面の対応としては、昨年12月に施行した改正金融商品取引法において、課徴金制度の強化と重要事実の子会社の解散に係る軽微基準の新設がなされており、また、自己株式取得時の留意点を示したQ&Aが公表されている。
このほか、インサイダー取引とは直接関係するわけではないが、法人による自己株式取得については「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」に規定された買付要件(①1日の買付数量の上限:直近4週間の1日当たり平均売買高の25%、②買付時間:取引終了時刻の直前30分は禁止、③買付価格:直近の売買価格を上回らない価格、④証券会社数:1日1社の証券会社のみを通じた買付け)を、本年7月31日までの時限措置として緩和(①を25%から100%に引上げ、②を適用しない)する旨、3月24日付で金融庁が発表しているため、留意されたい(金融庁ホームページ参照(http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20090324-4.html))。
Ⅳ 結びに代えて─全国上場会社内部者取引管理アンケートの実施─
最後に、東京証券取引所自主規制法人の最近の主な対応を紹介する。
当法人では、一昨年、全国の証券取引所とともに初めて行ったインサイダー取引管理に関する全国調査「全国上場会社内部者取引管理アンケート」(調査報告書は平成19年5月公表)の第2回を本年2月13日付で実施した。
前回のアンケート調査では、重要事実の認識時期が遅いと思われる上場会社が4割に達するなど、インサイダー取引規制に対する理解が十分ではないと思われる上場会社が多くみられたが、昨今の課徴金事案の増加等を背景として上場会社各社における規制に対する理解や体制整備等の対応が進展していることから、今回の調査では、このような進展度合いや具体的な施策例を取りまとめ、本年6月を目途に報告書として各取引所のホームページ等で公表する予定である。
なお、当法人が設置するコンプライアンス教育機関である東証COMLECでは、インサイダー取引規制の解説冊子『こんぷらくんのインサイダー取引規制Q&A(金融商品取引法平成20年改正対応版)』およびeラーニング研修サービス新コンテンツ「こんぷらくんの株価操作規制入門」等を新たに今春からリリースしている。是非ご利用いただきたい。 (よしまつ・かずひこ)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















