コラム2009年06月22日 【編集部レポート】 5月総会会社における付議議案等の状況(2)(2009年6月22日号・№311)
5月総会会社における付議議案等の状況(2)
東証上場94社367議案の詳細
前回は、2月期決算・5月総会会社における本年5月総会を迎えるにあたっての準備・対応等の状況について、東証第一部市場の上場会社94社の動向を中心に紹介した(本誌309号22頁参照)。今回は、引き続き当該94社を対象とし、本年総会に付議された議案の詳細を確認する(前年5月総会の付議議案等の状況について、261号16頁・262号4頁参照)。
全94社の計367議案を概観すると…… 平成21年5月に定時株主総会を開催した東証第一部上場会社は、計94社(EDINETによる有価証券報告書提出ベース(5月13日~6月1日))。前年総会は97社であったが、完全子会社化に伴う上場廃止2社、合併に伴う決算期変更1社、民事再生手続申立てに伴う上場廃止1社の計4社減に対し、東証第二部からの市場変更で1社増となった。商号変更は1社であった。
付議された総議案数は367議案(うち株主提案がアデランスホールディングス(証券コード:8170。以下同様)で1議案)で、1社平均の議案数は3.9議案。会社法の全面適用で注目された平成19年総会は468議案・1社平均4.9議案であったが、前年総会(359議案・1社平均3.7議案)とほぼ同水準であったといえる。
会社提案の否決例は5月28日開催の上記アデランスHD1社のみ。同社では前年総会で一部の取締役選任が否決されたが、本年総会では、米投資ファンドからの株主提案「取締役8名選任の件」が第6号議案として付議されていたところ、同社が計画した日系の投資ファンドとの資本業務提携に絡み、ファンド関係者を迎え入れる第3号議案「取締役7名選任の件」のうち3名が、第4号議案「監査役2名選任の件」のうち1名がそれぞれ否決、第5号議案「公開買付けに対する自己株式応募の件」が撤回されるという事態を生じ、一方の第6号議案は7名が可決(ほか1名は第3号議案で選任)された。
94社の議案の上程状況について、前年97社分と比較したのが表1である(議案名称は原則として企業年金連合会の分類によっており、本表では「補欠監査役選任」「役員賞与支給」「買収防衛策」を独自に付加。買収防衛策については、独立して付議された議案をカウントしている)。各議案付議会社数の第一部上場会社数に対する割合を算出すると、次のとおりとなっている(数値は平成20年、平成21年の順)。
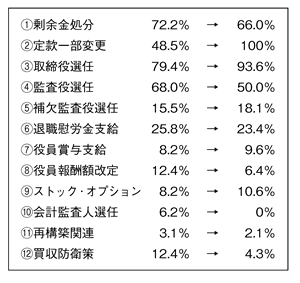
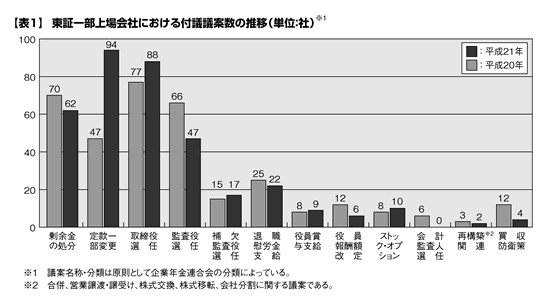
付議議案の傾向と本年総会での特徴 ①の剰余金処分議案は8社(6.2ポイント)の減少をみせており、前々年比では14社(13.2ポイント)減となる。当該議案は(ⅰ)期末配当の決定を取締役会授権している場合や(ⅱ)決定権は株主総会にあるが無配として付議しない場合などに存在しないこととなるが、期末配当の取締役会授権会社は対前年比2社増にとどまっており(309号23頁参照)、これに対して無配会社は対前年比6社増の13社にのぼっていることから、本年の主な減少要因は(ⅱ)によるものといえる(無配会社中、松屋(8237)と井筒屋(8260)2社の期末配当決定権は取締役会)。
なお、リンガーハット(8200)と東天紅(8181)は当該議案を付議しているが、繰越利益剰余金の欠損を補填するため、別途積立金の取崩しなどの承認を求めるもので無配である(今号28頁の表2参照。本表における同一決算日内の各社の掲載順序は、(ⅰ)定時総会開催日の早い順、(ⅱ)招集通知発送日の早い順、(ⅲ)証券コードの若い順(309号24頁参照)。役員選任欄では候補者数を、退職慰労金支給欄およびストック・オプション欄では複数付議されている場合にその数を掲げた。備考欄の記載は定款変更の内容が中心である)。
厳しい経済環境を窺わせる結果ともいえるが、⑦の役員賞与支給議案は1社増。当該議案は、前々年28社・前年8社が付議した状況があり、賞与が明確に「報酬等」とされたこと(会社法361条)、会計処理の変更などを受け、廃止する例が特に顕著となっていたものである。
これとともに、役員報酬制度の見直しの進展に伴って、近年は⑥の退職慰労金支給議案、⑧の役員報酬額改定議案の付議状況にも変動がみられていた。⑥の付議会社は前々年44社・前年25社、⑧は前々年31社・前年12社を数えており、⑦の廃止および支給決定過程に不透明感が高いとされる⑥の廃止に伴って、賞与相当分を⑧に組み込む形での改定や、⑥の打切支給議案と同時に⑧・⑨(ストック・オプション関連議案)を上程して総合的な役員報酬制度改革を進める例もみられたところである。
しかしながら、本年総会の状況をみると、⑦とともに⑨が微増に転じたほかは⑧の付議はさらに半減し、また、⑥の減少にも歯止めがかかったようだ(打切支給議案の付議も前々年16社・前年7社に対し、本年は4社)。役員報酬制度の見直しは、昨年にその兆候がみられた形ではあるが、一服感をより強めたといえるだろう。
このように少なくなってはいるが本年総会での事例をみると、取締役の報酬額改定とストック・オプション発行を同一の議案で行うものとしてシー・ヴイ・エス・ベイエリア(2687)、ポイント(2685)があるほか、前年総会で退職慰労金の打切支給を行ったCFSコーポレーション(8229)では本年、「業績連動部分を設けた新たな役員報酬制度」とし、社外役員を除く取締役・監査役に対して、平成18年総会で決定した報酬総額の枠内でストック・オプションの付与を図っているところである。
なお、レナウン(3606)では、取締役の報酬額改定議案において年額2億円以内の報酬総額を「業績に鑑み」半額とし、「当社のコーポレートガバナンス強化を図り幅広い人材を社外取締役として招聘するため」うち2千万円を社外取締役の報酬総額とすることを諮っている。
定款変更議案は全社が付議 役員選任関連の議案では、③の取締役選任議案で前年比11社(14.2ポイント)増と顕著な増加があった。しかし、前々年は90社(93.8%)の付議があり、取締役の任期を原則どおり2年とするか(会社法332条1項)、短縮して1年とするかによる会社方針の差異に基づく。
一方、監査役の任期は原則4年(会社法336条1項)。④の監査役選任議案の近年の付議状況をみると、前々年68社(70.8%)、前年66社(68.0%)に続く減少傾向を示した。
また、会社法制定により法文上、その予めの選任が明確にされた補欠役員(会社法329条2項)に係る⑤の補欠監査役選任議案は2社(2.6ポイント)増と引き続きの微増。本年付議17社のうち11社が前年も付議しており、残る6社中、東宝不動産(8833)、東武ストア(8274)では選任決議の効力を4年へと伸長した。
⑫の買収防衛策関連議案については、前々年10社・前年12社の付議に対し、本年は4社にとどまった。内訳をみると、3社は導入後、有効期間の満了に伴って継続を求めるもので、1社(イオン(8267))では有効期間はなかったものの本議案の決議時点で旧防衛策を廃止するとし、有効期間の設定を始め、株主意思を重視する観点からの内容の改定が図られている。
継続を求めるのはイズミヤ(8266)、タキヒヨー(9982)、ベスト電器(8175)の3社であるが、イズミヤが関連の定款変更議案で「買収防衛策に関する裁判所の一連の決定および買収防衛策をめぐる議論の状況を踏まえ」と謳い修正したように、タキヒヨーも内容を修正した。
②の定款変更議案の近年の付議状況は前々年56社(58.3%)、前年47社(48.5%)と推移していたところ、本年は全94社で付議された。
これは、いわゆる株券電子化が今年1月5日に実施されたことから、定款上不要となった「株券」「実質株主」「実質株主名簿」に係る規定の削除等を行うとともに、株券電子化の施行翌日から1年間だけ備え置くべき株券喪失登録簿について附則に所要の規定を置くものである(ランド(8918)1社でのみ付議していないが、同社では2月25日開催の臨時株主総会ですでに定款変更を行った)(なお、伴って株式取扱規則における株主権行使手続の明確化、単元未満株式買増制度導入を図る例もあり、表2では便宜上「株券電子化」として括っている)。
94社中、株券電子化のみを定款変更の内容としたのは57社(60.6%)。また、前年は2ケタにのぼった電子公告導入会社は3社、期末配当の決定権を取締役会に授権する会社法459条1項に係る定款変更は1社(前年2社)であった。
なお、株券電子化対応を柱としつつ、具体的説明はないままに「全般に亘って」変更を行う例として、あさひ(3333)がある。(了)
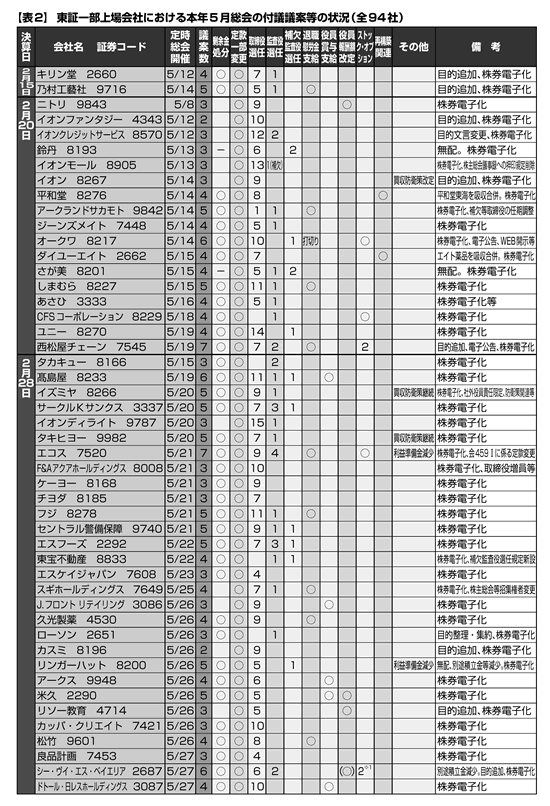
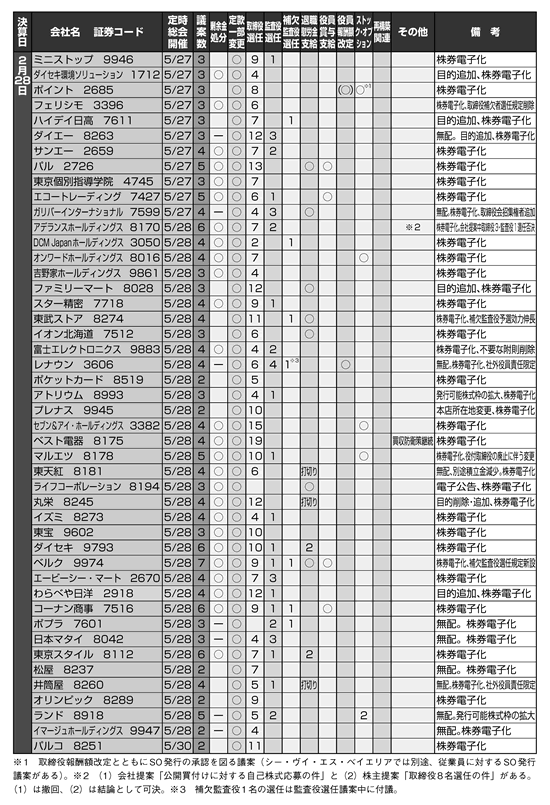
東証上場94社367議案の詳細
前回は、2月期決算・5月総会会社における本年5月総会を迎えるにあたっての準備・対応等の状況について、東証第一部市場の上場会社94社の動向を中心に紹介した(本誌309号22頁参照)。今回は、引き続き当該94社を対象とし、本年総会に付議された議案の詳細を確認する(前年5月総会の付議議案等の状況について、261号16頁・262号4頁参照)。
全94社の計367議案を概観すると…… 平成21年5月に定時株主総会を開催した東証第一部上場会社は、計94社(EDINETによる有価証券報告書提出ベース(5月13日~6月1日))。前年総会は97社であったが、完全子会社化に伴う上場廃止2社、合併に伴う決算期変更1社、民事再生手続申立てに伴う上場廃止1社の計4社減に対し、東証第二部からの市場変更で1社増となった。商号変更は1社であった。
付議された総議案数は367議案(うち株主提案がアデランスホールディングス(証券コード:8170。以下同様)で1議案)で、1社平均の議案数は3.9議案。会社法の全面適用で注目された平成19年総会は468議案・1社平均4.9議案であったが、前年総会(359議案・1社平均3.7議案)とほぼ同水準であったといえる。
会社提案の否決例は5月28日開催の上記アデランスHD1社のみ。同社では前年総会で一部の取締役選任が否決されたが、本年総会では、米投資ファンドからの株主提案「取締役8名選任の件」が第6号議案として付議されていたところ、同社が計画した日系の投資ファンドとの資本業務提携に絡み、ファンド関係者を迎え入れる第3号議案「取締役7名選任の件」のうち3名が、第4号議案「監査役2名選任の件」のうち1名がそれぞれ否決、第5号議案「公開買付けに対する自己株式応募の件」が撤回されるという事態を生じ、一方の第6号議案は7名が可決(ほか1名は第3号議案で選任)された。
94社の議案の上程状況について、前年97社分と比較したのが表1である(議案名称は原則として企業年金連合会の分類によっており、本表では「補欠監査役選任」「役員賞与支給」「買収防衛策」を独自に付加。買収防衛策については、独立して付議された議案をカウントしている)。各議案付議会社数の第一部上場会社数に対する割合を算出すると、次のとおりとなっている(数値は平成20年、平成21年の順)。
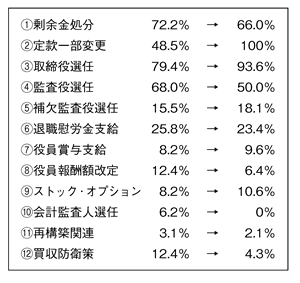
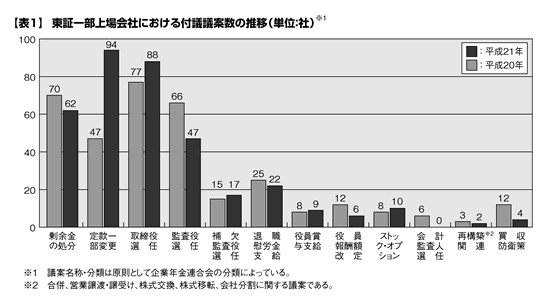
付議議案の傾向と本年総会での特徴 ①の剰余金処分議案は8社(6.2ポイント)の減少をみせており、前々年比では14社(13.2ポイント)減となる。当該議案は(ⅰ)期末配当の決定を取締役会授権している場合や(ⅱ)決定権は株主総会にあるが無配として付議しない場合などに存在しないこととなるが、期末配当の取締役会授権会社は対前年比2社増にとどまっており(309号23頁参照)、これに対して無配会社は対前年比6社増の13社にのぼっていることから、本年の主な減少要因は(ⅱ)によるものといえる(無配会社中、松屋(8237)と井筒屋(8260)2社の期末配当決定権は取締役会)。
なお、リンガーハット(8200)と東天紅(8181)は当該議案を付議しているが、繰越利益剰余金の欠損を補填するため、別途積立金の取崩しなどの承認を求めるもので無配である(今号28頁の表2参照。本表における同一決算日内の各社の掲載順序は、(ⅰ)定時総会開催日の早い順、(ⅱ)招集通知発送日の早い順、(ⅲ)証券コードの若い順(309号24頁参照)。役員選任欄では候補者数を、退職慰労金支給欄およびストック・オプション欄では複数付議されている場合にその数を掲げた。備考欄の記載は定款変更の内容が中心である)。
厳しい経済環境を窺わせる結果ともいえるが、⑦の役員賞与支給議案は1社増。当該議案は、前々年28社・前年8社が付議した状況があり、賞与が明確に「報酬等」とされたこと(会社法361条)、会計処理の変更などを受け、廃止する例が特に顕著となっていたものである。
これとともに、役員報酬制度の見直しの進展に伴って、近年は⑥の退職慰労金支給議案、⑧の役員報酬額改定議案の付議状況にも変動がみられていた。⑥の付議会社は前々年44社・前年25社、⑧は前々年31社・前年12社を数えており、⑦の廃止および支給決定過程に不透明感が高いとされる⑥の廃止に伴って、賞与相当分を⑧に組み込む形での改定や、⑥の打切支給議案と同時に⑧・⑨(ストック・オプション関連議案)を上程して総合的な役員報酬制度改革を進める例もみられたところである。
しかしながら、本年総会の状況をみると、⑦とともに⑨が微増に転じたほかは⑧の付議はさらに半減し、また、⑥の減少にも歯止めがかかったようだ(打切支給議案の付議も前々年16社・前年7社に対し、本年は4社)。役員報酬制度の見直しは、昨年にその兆候がみられた形ではあるが、一服感をより強めたといえるだろう。
このように少なくなってはいるが本年総会での事例をみると、取締役の報酬額改定とストック・オプション発行を同一の議案で行うものとしてシー・ヴイ・エス・ベイエリア(2687)、ポイント(2685)があるほか、前年総会で退職慰労金の打切支給を行ったCFSコーポレーション(8229)では本年、「業績連動部分を設けた新たな役員報酬制度」とし、社外役員を除く取締役・監査役に対して、平成18年総会で決定した報酬総額の枠内でストック・オプションの付与を図っているところである。
なお、レナウン(3606)では、取締役の報酬額改定議案において年額2億円以内の報酬総額を「業績に鑑み」半額とし、「当社のコーポレートガバナンス強化を図り幅広い人材を社外取締役として招聘するため」うち2千万円を社外取締役の報酬総額とすることを諮っている。
定款変更議案は全社が付議 役員選任関連の議案では、③の取締役選任議案で前年比11社(14.2ポイント)増と顕著な増加があった。しかし、前々年は90社(93.8%)の付議があり、取締役の任期を原則どおり2年とするか(会社法332条1項)、短縮して1年とするかによる会社方針の差異に基づく。
一方、監査役の任期は原則4年(会社法336条1項)。④の監査役選任議案の近年の付議状況をみると、前々年68社(70.8%)、前年66社(68.0%)に続く減少傾向を示した。
また、会社法制定により法文上、その予めの選任が明確にされた補欠役員(会社法329条2項)に係る⑤の補欠監査役選任議案は2社(2.6ポイント)増と引き続きの微増。本年付議17社のうち11社が前年も付議しており、残る6社中、東宝不動産(8833)、東武ストア(8274)では選任決議の効力を4年へと伸長した。
⑫の買収防衛策関連議案については、前々年10社・前年12社の付議に対し、本年は4社にとどまった。内訳をみると、3社は導入後、有効期間の満了に伴って継続を求めるもので、1社(イオン(8267))では有効期間はなかったものの本議案の決議時点で旧防衛策を廃止するとし、有効期間の設定を始め、株主意思を重視する観点からの内容の改定が図られている。
継続を求めるのはイズミヤ(8266)、タキヒヨー(9982)、ベスト電器(8175)の3社であるが、イズミヤが関連の定款変更議案で「買収防衛策に関する裁判所の一連の決定および買収防衛策をめぐる議論の状況を踏まえ」と謳い修正したように、タキヒヨーも内容を修正した。
②の定款変更議案の近年の付議状況は前々年56社(58.3%)、前年47社(48.5%)と推移していたところ、本年は全94社で付議された。
これは、いわゆる株券電子化が今年1月5日に実施されたことから、定款上不要となった「株券」「実質株主」「実質株主名簿」に係る規定の削除等を行うとともに、株券電子化の施行翌日から1年間だけ備え置くべき株券喪失登録簿について附則に所要の規定を置くものである(ランド(8918)1社でのみ付議していないが、同社では2月25日開催の臨時株主総会ですでに定款変更を行った)(なお、伴って株式取扱規則における株主権行使手続の明確化、単元未満株式買増制度導入を図る例もあり、表2では便宜上「株券電子化」として括っている)。
94社中、株券電子化のみを定款変更の内容としたのは57社(60.6%)。また、前年は2ケタにのぼった電子公告導入会社は3社、期末配当の決定権を取締役会に授権する会社法459条1項に係る定款変更は1社(前年2社)であった。
なお、株券電子化対応を柱としつつ、具体的説明はないままに「全般に亘って」変更を行う例として、あさひ(3333)がある。(了)
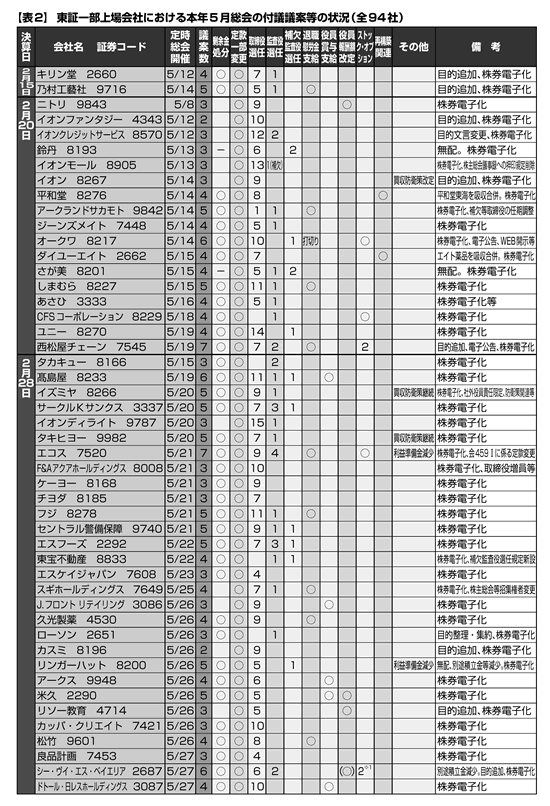
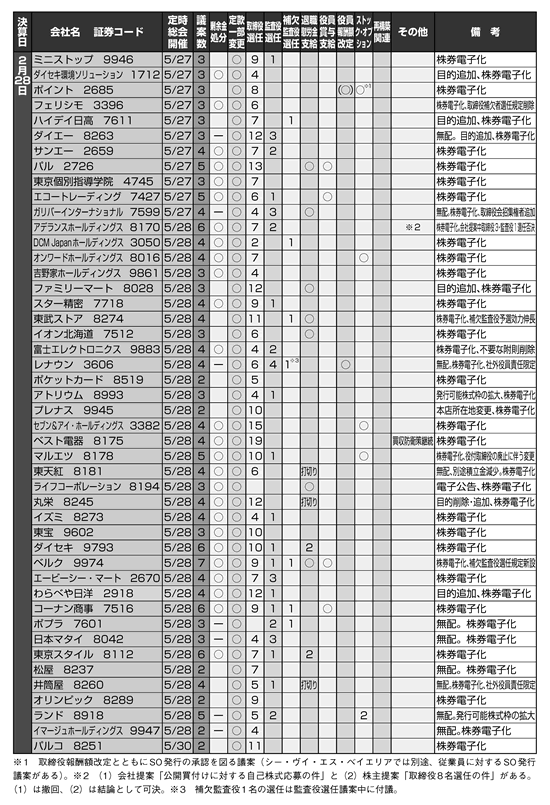
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























