解説記事2009年09月21日 【ニュース特集】 個人事業統合による法人化で営業権対価支払猶予に合理性(2009年9月21日号・№323)
補充的な売買契約による営業権の資産計上・減価償却を認容
個人事業統合による法人化で営業権対価支払猶予に合理性
複数人の個人事業を統合して設立された法人が、設立後年数を経て支払った金員を、営業権譲渡の対価とし、営業権の貸借対照表への資産計上および減価償却が認められた裁決事例があった(沖裁(法・諸)平20第3号・平成21年2月20日裁決・全部取消し)。このなかで審判所は、営業権譲渡人が営業権の対価の支払いを、譲受人(請求人)が支払可能となる時期が到来するまで猶予するとの合意をすることは不合理ともいえないと判断している。
1 顧客に設置した設備一式と全顧客名簿等を一括譲渡 裁決事例で譲渡の対象となった営業権は、当該事業者が顧客に設置した設備一式と全顧客名簿等を一括して譲渡するもので、その譲渡価額は、販売数量○当たりの単価に月平均販売数量を乗じた価格が基準になるといわれているもの。請求人は当該販売事業に係る営業権の取引慣行を証する書類として、「商権譲渡契約書一覧表」およびその販売実例の一部の契約書の写し(7件分)を提出しているが、昭和52年から平成3年にかけて営業権の譲渡があったとされる34件のうち、21件の売買単価が判明しており、その売買単価は販売数量○当たり150万円から450万円となっている。また、請求人は自らも当該商権および販売設備一切を475万円(内営業権価格400万円・単価200万円×2)で購入したことがある。
問題とされた営業権対価の支払いとは 請求人は、7事業者8名の個人事業者が、それぞれ営んでいた当該販売事業を統合する目的で、昭和X年に設立された法人。設立に際しては、8名の個人事業者(以下「本件各権利者」という)が有していた顧客数および年間の販売数量等を確認し、当該営業権を買い上げる約束をしていたが、設立当初、資金繰りが厳しく、会社経営が困難な状況だったため、営業権を買い上げる余裕がなかったという。なお、本件各権利者は請求人の設立時に、請求人の役員に就任している(その後、本件各権利者のうち2名の相続に伴い、請求人の株式を相続した相続人は役員に就任していない)。
請求人は、平成15年10月、本件各権利者5名と請求人株式を相続した3名との間でそれぞれ「営業権売買契約書」を作成し、同月31日、金融機関からの借入れを行い、営業権(販売数量および諸設備、経費等の一切)の対価として、総額1億7,441万円(単価は以前請求人が購入した営業権と同額の200万円)を各人の銀行口座に振り込んだ(図参照)。
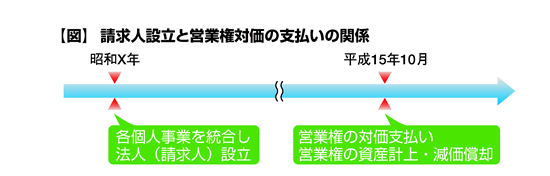
2 役員賞与・寄附金に該当するとして法人税の更正処分等 請求人は、平成16年6月期において、営業権対価の総額1億7,441万円(以下「本件金員」という)を営業権の取得価額として貸借対照表に資産計上するとともに、その金額の5分の1に相当する3,488万2,000円を減価償却費として損金算入した。また、その後、平成19年6月期まで、それぞれ減価償却費として3,488万2,000円を損金の額に算入した。
税務署は、営業権は有償取得に限り貸借対照表に計上することができるとし(商法施行規則33条、企業会計原則第三の五E・注解25)、当該営業権を無償譲渡により取得したものとして資産計上を認めず、また、本件金員が役員賞与または寄附金に該当するとして、法人税の更正処分等を行った。
3 営業権の有償・無償による譲渡の判定要素とは 裁決事例においては、①請求人設立時に当該営業権が無償で譲渡されたか否か、②有償で譲渡する旨の合意がなされたことを前提として、本件金員を営業権譲渡の対価とすることができるか否かが問題とされている。
まず、審判所は、営業権について、超過収益力の原因となる組織価値をいい、超過収益力の諸原因は、企業の創立当時の試練を経て過失なく若干年経過することにより社会的認識を得て、経営組織が完備することで自然に発生するものとし(下掲参照)、企業会計原則および商法の場合と同様に、法人税法上も有償取得に限って資産性を認めているものと解すべきだとした。そのうえで、上記①については、請求人設立時に、営業権を有償で譲渡する旨の合意がなされていたことを否定できないと判断している。
この有償譲渡の合意があったと判断するに至る過程は次のようになる。
(1)一般的な交換価値を有する資産の譲渡であれば、資産の譲渡時において当該資産の譲渡対価を取り決め、その代金の授受を約し、有償で譲渡されることが経済的に合理的なものであるということができる。
(2)複数人が支配する事業を経営統合するような場合で、営業権譲渡後も譲渡人と経営統合後の会社との間で取締役または株主などの関係が継続されるときには、営業権の譲渡自体は無償であっても、その営業権の対価に見合った価値を経営統合後の会社事業に伴う利益の配当や報酬といった形で得ることとされていれば、全体として経済的合理性を有するものということができる。
(3)以上によれば、営業権譲渡当時に営業権の対価が定まっておらず、代金の授受がされた事実がない場合でも、対価に代わる方法により、営業権譲渡に関する経済的合理性が担保されている場合には、一応、当該営業権が無償で譲渡されたものと推認することは可能である。
(4)この場合でも、対価が定まっていないこと、代金が授受されていないことについて合理的な理由があった場合にはこの推認は覆されるべきものというべきである。
そして、この事案においては、①当該営業権を有償で取引する慣行が成立していること、②請求人設立時に本件各権利者が有していた顧客を引き継いだものと認められ、営業権の取引対価は相当多額になるものと見込まれたこと、③請求人設立時の持株割合は、本件各権利者の販売数量に対応しておらず、株主には本件各権利者以外の者もいることから利益配当に営業譲渡の対価を加算したとも認められないこと、④役員報酬も営業権を反映したものとはなっていないことなどから、本件各権利者に自然に発生した営業権が請求人に有償で譲渡されることが合意されたことは、一応推認できるものとしている。
4 支払可能時期までの猶予の合意は不合理といえず このように審判所は、請求人設立時に営業権を有償で譲渡する旨の合意がなされていたと判断したが、次に問題となるのは、請求人が対価として支払った本件金員を営業権譲渡の対価とすることができるかどうかである。
平成15年の売買契約は補充的な契約 この点については、請求人設立時に営業権の譲受けがあったことを前提とするならば、譲渡人においてその営業権の対価の支払いを譲受人(請求人)が支払可能となる時期が到来するまで猶予するとの合意をすることを不合理ともいえないとしたうえで、「本件金員が本件営業権の対価の支払であることを否定するためには、請求人設立時に本件営業権の対価が授受されていない事実を主張立証するだけでは足りず、支払を猶予する合意が存しないこと、更に本件金員が本件営業権の譲渡対価以外の理由で支払われたことを主張立証する必要がある」と指摘。
そして、請求人設立当時に営業権の対価が授受されていない事実をもって、本件金員が営業権の対価ではないということはできず、平成15年に締結された営業権売買契約は、昭和X年有償譲渡契約のなかで、当時いまだ確定していなかった営業権の対価部分についての補充的な契約であり、この補充的契約で支払いが確定した本件金員は昭和X年に譲渡した本件営業権の譲渡対価であるということは否定できないとした。
利益調整と認めるに足りる証拠なし なお、税務署は、①法人は発生主義で営業権を認識するもので、昭和X年の営業権を平成16年6月期に計上することは認められない、②単なる資金繰りの都合で自由にその計上を認めることになれば利益調整にもつながるとも主張している。これに対し、審判所は、企業会計基準は発生主義を採用しておらず、あくまで取引が実現した時点において収益計上し、債務確定基準により債務計上を認識することとされている、請求人は本件金員の支払いのために借入れまで行っており、他に利益調整のために行ったと認めるに足りる証拠は存しないと判断している。
○裁決事例における営業権の解釈 営業権は、税法上の固有の概念ではないので、法人税法もこれについて直接規定せず、一般に会計学や商法で用いられる概念をそのまま使用しているところ、会計学あるいは商法でいう営業権とは、のれん、しにせ権などともいわれ、それは債権、無体財産権に属せず、いわゆる法律上の権利ではなく、既設の企業が、各種の有利な条件または特権の存在により他の同種企業のあげる通常の利潤よりも大きな収益を引き続き確実にあげている場合、その超過収益力の原因となる組織価値をいう。その超過収益力の原因としては、既設企業の名声、立地条件、経営手腕、製造秘訣、特殊の取引関係または独占性などが考えられるが、営業権は、これらの諸原因、諸収益力を総合した概念であり、個々に分立した特権の単なる集合ではない。そして、超過収益力の諸原因は、企業が設立されてから創立当時の試練を経て過失がなく若干年経過することにより外部的には社会的認識を得、内部的にも従業員の経験、熟練度が増し、経営組織が完備することにより自然に発生するものであると解されている。
個人事業統合による法人化で営業権対価支払猶予に合理性
複数人の個人事業を統合して設立された法人が、設立後年数を経て支払った金員を、営業権譲渡の対価とし、営業権の貸借対照表への資産計上および減価償却が認められた裁決事例があった(沖裁(法・諸)平20第3号・平成21年2月20日裁決・全部取消し)。このなかで審判所は、営業権譲渡人が営業権の対価の支払いを、譲受人(請求人)が支払可能となる時期が到来するまで猶予するとの合意をすることは不合理ともいえないと判断している。
1 顧客に設置した設備一式と全顧客名簿等を一括譲渡 裁決事例で譲渡の対象となった営業権は、当該事業者が顧客に設置した設備一式と全顧客名簿等を一括して譲渡するもので、その譲渡価額は、販売数量○当たりの単価に月平均販売数量を乗じた価格が基準になるといわれているもの。請求人は当該販売事業に係る営業権の取引慣行を証する書類として、「商権譲渡契約書一覧表」およびその販売実例の一部の契約書の写し(7件分)を提出しているが、昭和52年から平成3年にかけて営業権の譲渡があったとされる34件のうち、21件の売買単価が判明しており、その売買単価は販売数量○当たり150万円から450万円となっている。また、請求人は自らも当該商権および販売設備一切を475万円(内営業権価格400万円・単価200万円×2)で購入したことがある。
問題とされた営業権対価の支払いとは 請求人は、7事業者8名の個人事業者が、それぞれ営んでいた当該販売事業を統合する目的で、昭和X年に設立された法人。設立に際しては、8名の個人事業者(以下「本件各権利者」という)が有していた顧客数および年間の販売数量等を確認し、当該営業権を買い上げる約束をしていたが、設立当初、資金繰りが厳しく、会社経営が困難な状況だったため、営業権を買い上げる余裕がなかったという。なお、本件各権利者は請求人の設立時に、請求人の役員に就任している(その後、本件各権利者のうち2名の相続に伴い、請求人の株式を相続した相続人は役員に就任していない)。
請求人は、平成15年10月、本件各権利者5名と請求人株式を相続した3名との間でそれぞれ「営業権売買契約書」を作成し、同月31日、金融機関からの借入れを行い、営業権(販売数量および諸設備、経費等の一切)の対価として、総額1億7,441万円(単価は以前請求人が購入した営業権と同額の200万円)を各人の銀行口座に振り込んだ(図参照)。
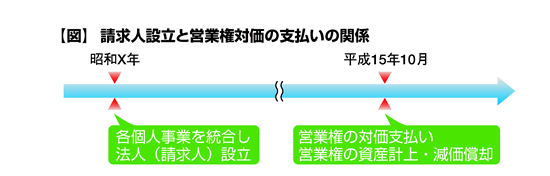
2 役員賞与・寄附金に該当するとして法人税の更正処分等 請求人は、平成16年6月期において、営業権対価の総額1億7,441万円(以下「本件金員」という)を営業権の取得価額として貸借対照表に資産計上するとともに、その金額の5分の1に相当する3,488万2,000円を減価償却費として損金算入した。また、その後、平成19年6月期まで、それぞれ減価償却費として3,488万2,000円を損金の額に算入した。
税務署は、営業権は有償取得に限り貸借対照表に計上することができるとし(商法施行規則33条、企業会計原則第三の五E・注解25)、当該営業権を無償譲渡により取得したものとして資産計上を認めず、また、本件金員が役員賞与または寄附金に該当するとして、法人税の更正処分等を行った。
3 営業権の有償・無償による譲渡の判定要素とは 裁決事例においては、①請求人設立時に当該営業権が無償で譲渡されたか否か、②有償で譲渡する旨の合意がなされたことを前提として、本件金員を営業権譲渡の対価とすることができるか否かが問題とされている。
まず、審判所は、営業権について、超過収益力の原因となる組織価値をいい、超過収益力の諸原因は、企業の創立当時の試練を経て過失なく若干年経過することにより社会的認識を得て、経営組織が完備することで自然に発生するものとし(下掲参照)、企業会計原則および商法の場合と同様に、法人税法上も有償取得に限って資産性を認めているものと解すべきだとした。そのうえで、上記①については、請求人設立時に、営業権を有償で譲渡する旨の合意がなされていたことを否定できないと判断している。
この有償譲渡の合意があったと判断するに至る過程は次のようになる。
(1)一般的な交換価値を有する資産の譲渡であれば、資産の譲渡時において当該資産の譲渡対価を取り決め、その代金の授受を約し、有償で譲渡されることが経済的に合理的なものであるということができる。
(2)複数人が支配する事業を経営統合するような場合で、営業権譲渡後も譲渡人と経営統合後の会社との間で取締役または株主などの関係が継続されるときには、営業権の譲渡自体は無償であっても、その営業権の対価に見合った価値を経営統合後の会社事業に伴う利益の配当や報酬といった形で得ることとされていれば、全体として経済的合理性を有するものということができる。
(3)以上によれば、営業権譲渡当時に営業権の対価が定まっておらず、代金の授受がされた事実がない場合でも、対価に代わる方法により、営業権譲渡に関する経済的合理性が担保されている場合には、一応、当該営業権が無償で譲渡されたものと推認することは可能である。
(4)この場合でも、対価が定まっていないこと、代金が授受されていないことについて合理的な理由があった場合にはこの推認は覆されるべきものというべきである。
そして、この事案においては、①当該営業権を有償で取引する慣行が成立していること、②請求人設立時に本件各権利者が有していた顧客を引き継いだものと認められ、営業権の取引対価は相当多額になるものと見込まれたこと、③請求人設立時の持株割合は、本件各権利者の販売数量に対応しておらず、株主には本件各権利者以外の者もいることから利益配当に営業譲渡の対価を加算したとも認められないこと、④役員報酬も営業権を反映したものとはなっていないことなどから、本件各権利者に自然に発生した営業権が請求人に有償で譲渡されることが合意されたことは、一応推認できるものとしている。
4 支払可能時期までの猶予の合意は不合理といえず このように審判所は、請求人設立時に営業権を有償で譲渡する旨の合意がなされていたと判断したが、次に問題となるのは、請求人が対価として支払った本件金員を営業権譲渡の対価とすることができるかどうかである。
平成15年の売買契約は補充的な契約 この点については、請求人設立時に営業権の譲受けがあったことを前提とするならば、譲渡人においてその営業権の対価の支払いを譲受人(請求人)が支払可能となる時期が到来するまで猶予するとの合意をすることを不合理ともいえないとしたうえで、「本件金員が本件営業権の対価の支払であることを否定するためには、請求人設立時に本件営業権の対価が授受されていない事実を主張立証するだけでは足りず、支払を猶予する合意が存しないこと、更に本件金員が本件営業権の譲渡対価以外の理由で支払われたことを主張立証する必要がある」と指摘。
そして、請求人設立当時に営業権の対価が授受されていない事実をもって、本件金員が営業権の対価ではないということはできず、平成15年に締結された営業権売買契約は、昭和X年有償譲渡契約のなかで、当時いまだ確定していなかった営業権の対価部分についての補充的な契約であり、この補充的契約で支払いが確定した本件金員は昭和X年に譲渡した本件営業権の譲渡対価であるということは否定できないとした。
利益調整と認めるに足りる証拠なし なお、税務署は、①法人は発生主義で営業権を認識するもので、昭和X年の営業権を平成16年6月期に計上することは認められない、②単なる資金繰りの都合で自由にその計上を認めることになれば利益調整にもつながるとも主張している。これに対し、審判所は、企業会計基準は発生主義を採用しておらず、あくまで取引が実現した時点において収益計上し、債務確定基準により債務計上を認識することとされている、請求人は本件金員の支払いのために借入れまで行っており、他に利益調整のために行ったと認めるに足りる証拠は存しないと判断している。
○裁決事例における営業権の解釈 営業権は、税法上の固有の概念ではないので、法人税法もこれについて直接規定せず、一般に会計学や商法で用いられる概念をそのまま使用しているところ、会計学あるいは商法でいう営業権とは、のれん、しにせ権などともいわれ、それは債権、無体財産権に属せず、いわゆる法律上の権利ではなく、既設の企業が、各種の有利な条件または特権の存在により他の同種企業のあげる通常の利潤よりも大きな収益を引き続き確実にあげている場合、その超過収益力の原因となる組織価値をいう。その超過収益力の原因としては、既設企業の名声、立地条件、経営手腕、製造秘訣、特殊の取引関係または独占性などが考えられるが、営業権は、これらの諸原因、諸収益力を総合した概念であり、個々に分立した特権の単なる集合ではない。そして、超過収益力の諸原因は、企業が設立されてから創立当時の試練を経て過失がなく若干年経過することにより外部的には社会的認識を得、内部的にも従業員の経験、熟練度が増し、経営組織が完備することにより自然に発生するものであると解されている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























