解説記事2009年11月02日 【解説】 法人税制の課題─見直すべき項目と改正の方向性─(2009年11月2日号・№328)
実務解説
法人税制の課題
─見直すべき項目と改正の方向性─
21世紀政策研究所研究主幹 朝長英樹
21世紀政策研究所では、2008年12月、法人税制の改正項目についての論点を整理するべく、朝長英樹氏を研究主幹とする研究プロジェクトを立ち上げ、本年9月、報告書「法人税制の課題─見直すべき項目と改正の方向性─」を取りまとめた。
今後のわが国経済の発展を確実なものにするためには、経済活動のインフラである法人税制を新たな時代に相応しい枠組みに改変する必要があると思われる。
本報告書では、事業体税制の再構築、無形資産税制の抜本改正、資本等取引に関する税制の構築などを取り上げており、今後の法人税制の改正論議に一石を投じられれば幸いである。
Ⅰ.はじめに
今年は、歴史的な政権交代の年となり、さまざまな分野で従来のあり方が大きく見直されつつあるが、わが国の経済が新しい政権のもとで大きく復活を果たし得るのか否かということが、これらの見直しの成否を大きく左右することとなるのではないかと思われる。
新政権の経済政策に関しては、現在までのところ、あまり深まった議論が行われていないように思われるが、これからのわが国の経済を考えるにあたっては、その主要な部分を担う法人に関する税制が非常に重要となると考えられる。わが国の法人が活力のある活動を行うようにならない限り、わが国の経済の復活は有り得ない、といってもよいのではないだろうか。
従来、経済対策として法人税制が用いられる場合には、租税特別措置として政策措置を講じたり、税率を引き下げたりすることが中心であったが、これらの従来の措置は、必ずしも十分な成果を上げてきたとはいえないように思われる。
その一番の原因は、「経済対策=減税」という考え方を基本として措置が講じられてきたことにあると考える。特に、旧政権下の昭和50年代以後の税制改正の歴史は、政策措置の歴史といってもよい。このような法人税制改正の歴史は、現在、新政権下で租税特別措置の問題として指摘されていることにとどまらず、長期にわたって法人税法における税制の仕組みの見直しがないがしろにされてきたという重大な問題が存在することを示している。私達は、このような法人税制改正の歴史から、法人税法における税制の仕組みを抜本的に見直して時代の要請に沿うものとする「現代化」が必要であることを学ばなければならないと考える。
平成12年度の金融取引に関する税制の抜本改正、平成13年度の組織再編成税制の創設、平成14年度の連結納税制度の創設などの法人税法の改正は、そのような法人税制の現代化への一歩と考えられるものだが、法人税法における税制の仕組みには、まだまだ多くの課題が山積している。
そして、これらの課題を適切に解決していくことができなければわが国の経済が大きく復活を遂げることはできない、といっても過言ではない。
このため、法人税法における税制の仕組みを抜本的に見直して改革を行うことが喫緊の課題となっているわけだが、この改革は、従来の租税特別措置のように、必ずしも減税を伴うものではないという点に留意しておく必要がある。
たとえば、平成13年度の組織再編成税制の創設は、わが国の企業の再編に非常に大きく貢献したといわれているが、同税制の創設による税収の増減額は零と試算されていた。同税制は、減税措置ではなかったわけだが、わが国の企業活動に大きく貢献し、結果として、税収の増加に大きく貢献したはずである。
法人税制は、会社法・企業会計とともに、経済活動の不可欠のインフラであるといわれるが、それは、すなわち、その仕組みを合理的なものとすることを常に求められることとなり、それが経済活動に大きく貢献することとなる、ということを意味している。
減税しなければ経済対策にならないという考え方は、もう捨てるべき時期に来ていると考える。従来のように、減税か増税かという議論によって税制を決めるのではなく、時代の要請に合った合理的な仕組みを創るためにはどうすればよいのかということを徹底して議論し、税制をあるべき姿に少しでも近づけることが必要となっている、と考える。
以下、そのような観点に立って、法人税法における税制の課題について述べることとする。
Ⅱ.事業体税制の再構築
わが国においては、大法人および中小法人の双方が合同会社等の持分会社、信託、任意組合・匿名組合などの多様な事業形態の選択をすることができるように税制の抜本的な整備を図ることが重要な課題となっている、と考えられる。
合名会社・合資会社・合同会社からなる持分会社に関しては、利益は構成員のものとされており、会社法のもとで設立されたものについては、諸外国の取扱いと同様に、法人税課税ではなく、構成員課税とするべきであると考える。
信託法上、信託財産から生ずる利益は受益者に帰属することが明確であり、受託者は手数料を得る権利があるのみで信託財産の利益を自らのものとすることはできないわけであるから、利益なきところに課税を行うこととなっている「法人課税信託」に関しては課税のあり方を再検討する必要があると考える。
また、受益権の多様化にどのように対応するのかということを明らかにするとともに、受益者における税制上の取扱いを整備することも欠かせないと考える。
任意組合・匿名組合に関する税制は、現在に至っても、その基本的な取扱いは通達に委ねられており、多くの課題が残されたままとなっている。組合の機能は、基本的には信託と同様であるため、信託に関する取扱いと平仄を合わせて組合の取扱いを法制化する必要がある。
また、これからのわが国においては民間の非営利活動を大きく発展させることが重要であり、公益法人税制については、民間の非営利活動を大きく促進するという観点に立って、再検討を行う必要があると考える。いわゆる天下りが問題となる公益法人は、全体からみると、ごく少数にとどまり、大多数の公益法人は、民間の非営利活動を担う重要な役割を果たしている。ごく一部に不適切な公益法人が存在することをもって、あたかもすべての公益法人に問題があるかのごとき対応がなされるとすれば、社会的に大きな取返しのつかない損失を生じさせることとなってしまいかねない。
特に、みなし寄附金の損金算入と利子等に対する源泉所得税を非課税とすることは、是非とも必要な喫緊の課題であると考える。
Ⅲ.無形資産税制の抜本改正
今後、わが国においては、無形資産の創造と活用を促進することが非常に重要となり、そのなかでもいわゆる知財が特に重要となると考えられる。わが国においては、アメリカ等と比較すると、無形資産に対する認識と評価が十分ではないといわれてきたが、現在においても、その状況に大きな変化はないように思われる。アメリカにおいては、通常、事業価値の最も大きな構成要素は無形資産であるといわれているが、わが国においては、いまだ有形資産が事業価値の大半を占めるとの認識が一般的である。これは、わが国においては価値のある無形資産が少ないという事情によるだけでなく、無形資産に大きな価値があるという認識自体が十分でないということが原因になっているものと考えられる。
このようなわが国の状況は、第三次産業が大きく拡大してきた現在の企業活動の実態を的確に捉えたものとはなっておらず、また、将来の企業活動の状態に適合するものでもないと考える。
将来にわたってわが国が世界のなかで枢要な地位を維持していくためは、無形資産の創造と活用を大きく促進することが不可欠となるということに、おそらく異論はなかろう。
無形資産の創造促進に関しては、平成14年に成立した知的財産基本法がその象徴的なものだが、税制においても、研究開発税制を始めとして様々な対策が講じられてきた。そして、それらは無形資産の創造や保護という点では一定の成果を挙げてきたものと想定されるが、無形資産の活用という点では必ずしも十分な成果を挙げきれておらず、そのため、無形資産の活用の拡大が無形資産の創造のインセンティブとなり、有用な無形資産の創造がさらなる無形資産の活用の拡大に繋がるという善循環が生まれない原因となっているように思われる。
無形資産が十分に活用されないのは、主に次のような理由によるものと考えられる。
① 価値が適切に計算できないこと
② 価値がゼロとなってしまう懸念があること
③ 自己の創造した無形資産を他の者が利用す
ることで自己が不利益を蒙ることになる懸念があること
④ 法制・会計・税制における取扱いが明確でないこと
まず、第一に挙げなければならないのは、上記①の「無形資産の価値が適切に計算できない」ということである。
現在、わが国には、不動産鑑定士と証券アナリストという資格制度があるが、前記の無形資産等の評価のニーズに対応できるものではない。資産全般にわたる評価資格制度を設けたとしても、それですぐに税務上の問題が解決したり取引が大きく拡大したりすることにはならないと考えられるが、このような制度を設けることが、それらを解決するための重要な一歩となることは間違いない。このため、わが国においても、諸外国の例にならい、早急に資産・負債・事業価値の包括的な評価基準を作成するとともに、評価資格制度を創設すべきであると考える。
現在、税制においても、移転価格税制、組織再編成税制、連結納税制度や相続税において、無形資産、事業評価、種類株式などの評価をどのように行うべきかということ等が大きな課題となっているわけだが、このように、包括的な評価資格制度を設けて無形資産の評価に関する信頼度を上げることは、この税制の課題を解決することにもなる。
次の上記②「価値がゼロとなってしまう懸念がある」という点に関しては、無形資産の性質上、やむを得ないことであり、また、上記③「自己が不利益を蒙ることになる懸念がある」という点に関しては、無形資産の譲渡や使用許諾に伴って必然的に生ずる事柄であり、基本的には、避けることができないものと考えておかなければならない。
上記④「取扱いが明確でない」という点に関しては、これらとは異なり、法制、企業会計や税制において積極的に対応することが必要となる。無形資産には、その価値をどのように計算するべきかという難しい課題があることは間違いないが、法制、企業会計や税制における取扱いを整備することで、その難しい課題の負担を軽くすることも、十分、可能であると考えられる。そうすることにより、少しずつ、無形資産の譲渡、使用許諾、信託、担保などが広がっていくものと期待される。法制、企業会計や税制における取扱いを整備することで、少しずつ、無形資産の取引等が広がり、その結果、トラックレコードが得られ、それがさらに適切な価値の計算に資する、という関係が生じてくることも、十分にあり得ることである。
税制における整備が先行した平成13年の組織再編成税制の創設がその好例だが、特に税制において無形資産の取扱いを整備することが無形資産の活用の低調な現状を大きく改革する鍵になるものと考える。
企業会計においては、近年、無形資産に関し、見直しが行われてきており、法人税法と比べると、相対的に実態に即した取扱いとなっている。このような企業会計における近年の見直しが法人税法における取扱いとの乖離を生むこととなり、両者の関係が不明確となっているわけである。
法人税法においては、昭和40年のその創設以来、無形固定資産等の範囲等に関する抜本的な見直しが行われていない。
現行の法人税法が定められた昭和40年当時、無形資産は、有形資産と比べると、その他の特殊な資産という程度の認識で済む状態であったものと考えられるが、現在は、第三次産業が大きく拡大しており、無形資産が事業価値の大きな部分を占めるということになることも、決して稀ではないと想定される。
このような事情からすると、法人税法において無形固定資産等に関する取扱いの抜本的な見直しを行うことが重要課題となっていると考える。
以下、無形固定資産の「活用」に重点を置く税制の具体的な見直し案を提示したい。
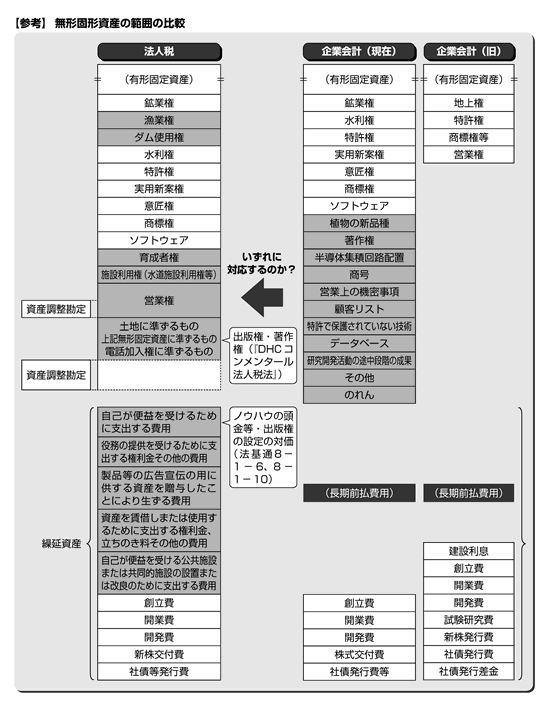
1 無形固定資産・繰延資産の資産区分を企業会計に合わせること 税制上の無形固定資産・繰延資産の資産区分は企業会計の無形資産等の資産区分とかなりの部分で異なっているが、両者の相違を合理的に説明することは困難であり、実務上も、両者が適切に処理されているとは思われない。
企業会計の取扱いと税制の取扱いを合わせること自体は、それが直接に無形資産の「活用」を促進するというものではないが、無形資産の「活用」の促進を図るということであれば、まず、その「活用」を促進しようとする無形資産がどのようなものであるのかということを明らかにしておくことが必要である。
細かくみていくと、企業会計における資産区分を修正しなければならない部分も出てくる可能性はあるが、総体的にみれば、企業会計の資産区分に合理性があると考えられるため、基本的には、税制における資産区分を企業会計のそれに合わせるのが適当であると考える。
税制上の無形固定資産・繰延資産の区分を企業会計の無形資産等の区分に合わせることとすれば、実務上、非常に大きな問題となっている営業権の問題が解消することとなって組織再編成も連結納税の拡大に大きく資することとなり、また、営業権と資産調整勘定の重複という問題も解消することができることとなる。
ただし、企業会計においては、国際会計基準との調整を行うにあたって、連結財務諸表制度における資産区分と個別財務諸表におけるそれとが異なることがあり得ると考えられるため、そのような場合には、税制においては、そのいずれも採り得ることとするべきである。
改めていうまでもないが、無形固定資産・繰延資産の範囲について、税制を企業会計に合わせるということになれば、税制の簡素化にも資することとなる。
なお、そもそもコンプライアンスの確保に難点がある制度はその妥当性に疑問があるということも、付言しておくこととする。
2 他から取得した無形固定資産のみを資産計上するものとすること 他の者から取得した無形固定資産は、適格組織再編成によって事業の移転を受ける場合にその一部としてそれらが含まれているような場合を除き、その価値が明らかであるが、自己が創造したそれらは資産としての価値があるのか否かが明らかでないものが少なくない。
このような実態があることからすると、税制において資産として計上すべき無形固定資産は、他の者から取得したものに限ることとし、適格組織再編成により取得したものを除くこととするのが適当であると考える。
企業会計においては、自己の研究開発費を無形資産として計上する部分があるが、税制においては、この自己の研究開発費を損金算入とせずにさまざまな政策措置を講ずるよりも、この自己の研究開発費を損金算入としたうえで、さらに必要な政策措置があれば、その政策措置を講ずる、とする方が適切であると考える。
研究開発を促進することは、わが国においては、一時的な政策措置というよりも、常に優先度の高い恒久措置と位置付けるべきものである。
なお、これは、上記1と同様に、税制の簡素化にも資することとなる。
3 無形固定資産の取得価額を一時の損金とするかまたは耐用年数を大幅に短縮すること 無形固定資産の取得価額を一時の損金とするかまたは耐用年数を大幅に短縮することで、これらの取引に大きなインセンティブを与えることができる。
無形固定資産の取得価額が一時の損金となるかまたは耐用年数が大幅に短縮されるということになれば、直接、無形固定資産を売買することも相当に増えてくると想定される。わが国においては、自己の使用しない特許等であってもそれを手放すことによって後に自己が不利な立場に立たされることになってしまうのではないかとの懸念からその売買が広がらないといわれており、確かにそのような部分があることは否めないため、無形固定資産を信託や組合を使って活用したり、無形固定資産の賃貸借を促進したりする措置を講ずることとすれば、なお一層の効果が期待できると考えられる。
特に、前者は、事業体税制の改正と併せて行うことにより、大きな成果を得ることが期待される。無形固定資産を取得して自ら事業を行うという投資の形態と無形固定資産を取得する会社の株式を取得するという投資の形態も、もちろん、あり得るわけだが、信託や組合を使って事業を行うというこの両者の中間の投資の形態が大きく拡大したとしても、何らおかしなことではない。そもそも、信託や組合は、そのような形態の事業を行うビークルとして存在しているからである。
このように、多様な形態で無形固定資産の活用が図られるとすれば、大きな活路が開かれることとなる。
ただし、無形固定資産の取得価額を一時の損金とするかまたは耐用年数を大幅に短縮するということになれば、それが租税回避に利用されることとなることも懸念されるため、これらの取引が租税回避に当たるか否かについて判断の基準を設ける必要がある。
この判断の基準は、リスクを負う取引となっているのか否かということを基本とするのが適当であると考えられる。
ところで、耐用年数が大幅に短縮された無形固定資産を節税の手段としても利用してもらうということは大いに歓迎すべきことであるという点には、十分に留意する必要がある。「租税回避」の範囲をむやみに拡大し、角を矯めて牛を殺すようなことは、あってはならない。
上記の1から3までの改正は、その内容に連動性があるため、一連の改正として行うのが適当であると考えるが、少なくとも、企業会計において無形資産に関するわが国の基準と国際会計基準との調整が済んで新基準が確定すると期待される後の改正となる平成23年度改正までに行うべきであると考える。
ただし、営業権に関してこれを企業会計と同様に無形固定資産から除外してのれんに吸収する改正は、単独で行い得るものであり、企業会計において爾後に変更が生ずることが想定されないため、平成22年度改正にて速やかに行うこととするのが適当と考える。
Ⅳ.資本等取引に関する税制の構築
現行の資本等取引に関する税制には、次の3つの大きな課題が残されており、これを解決する必要があると考える。
① 資本金等の額を1つの金額と捉えること
法人税においては、株主等からの拠出部分を複数に分けて捉える理由はないことから、資本の金額または出資金額と従来の資本積立金額とを区分せず、資本金等の額を1つの金額として捉えることとするべきである。
② 資本等取引を原則として時価取引とし特例として時価以外の取引を可とすること
資本等取引も、取引である以上、損益取引と同様に、時価によって行うべきことは、当然のことであり、資本等取引が時価で行われた場合に、これを否認する理由は存在しない。法人税法においては、資本等取引についても、原則として時価により処理することとし、株主において投資が継続していると考えられる場合には、特例として時価以外の金額での取引を認めることとするべきである。
③ 資産が移転する減資・払戻し・清算・配当について組織再編成と同様の観点から原則と特例を整理すること
減資・払戻し・清算・配当によって資産が移転する場合について、組織再編成により資産が移転した場合の取扱いと同様の観点から、税制における取扱いを整備する必要がある。
Ⅴ.そ の 他
連結納税制度においては、連結対象法人となる法人の持分割合を引き下げて50%超とするとともに、開始・加入時にその資産を時価評価しなくてよい法人とその欠損金を切り捨てなくてもよい法人の範囲を大幅に拡大するなど、抜本的な制度の見直しを行うべき時期に来ていると考える。
また、移転価格税制の法制整備や外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の適用基準の緩和も、不可欠であると考える。
加えて、理論的にも立法手続にも大きな問題がある特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度を廃止すること、そして、役員給与の損金不算入制度を平成18年度改正前に戻したうえで再検討することが不可欠であると考える。
(ともなが・ひでき)
法人税制の課題
─見直すべき項目と改正の方向性─
21世紀政策研究所研究主幹 朝長英樹
21世紀政策研究所では、2008年12月、法人税制の改正項目についての論点を整理するべく、朝長英樹氏を研究主幹とする研究プロジェクトを立ち上げ、本年9月、報告書「法人税制の課題─見直すべき項目と改正の方向性─」を取りまとめた。
今後のわが国経済の発展を確実なものにするためには、経済活動のインフラである法人税制を新たな時代に相応しい枠組みに改変する必要があると思われる。
本報告書では、事業体税制の再構築、無形資産税制の抜本改正、資本等取引に関する税制の構築などを取り上げており、今後の法人税制の改正論議に一石を投じられれば幸いである。
Ⅰ.はじめに
今年は、歴史的な政権交代の年となり、さまざまな分野で従来のあり方が大きく見直されつつあるが、わが国の経済が新しい政権のもとで大きく復活を果たし得るのか否かということが、これらの見直しの成否を大きく左右することとなるのではないかと思われる。
新政権の経済政策に関しては、現在までのところ、あまり深まった議論が行われていないように思われるが、これからのわが国の経済を考えるにあたっては、その主要な部分を担う法人に関する税制が非常に重要となると考えられる。わが国の法人が活力のある活動を行うようにならない限り、わが国の経済の復活は有り得ない、といってもよいのではないだろうか。
従来、経済対策として法人税制が用いられる場合には、租税特別措置として政策措置を講じたり、税率を引き下げたりすることが中心であったが、これらの従来の措置は、必ずしも十分な成果を上げてきたとはいえないように思われる。
その一番の原因は、「経済対策=減税」という考え方を基本として措置が講じられてきたことにあると考える。特に、旧政権下の昭和50年代以後の税制改正の歴史は、政策措置の歴史といってもよい。このような法人税制改正の歴史は、現在、新政権下で租税特別措置の問題として指摘されていることにとどまらず、長期にわたって法人税法における税制の仕組みの見直しがないがしろにされてきたという重大な問題が存在することを示している。私達は、このような法人税制改正の歴史から、法人税法における税制の仕組みを抜本的に見直して時代の要請に沿うものとする「現代化」が必要であることを学ばなければならないと考える。
平成12年度の金融取引に関する税制の抜本改正、平成13年度の組織再編成税制の創設、平成14年度の連結納税制度の創設などの法人税法の改正は、そのような法人税制の現代化への一歩と考えられるものだが、法人税法における税制の仕組みには、まだまだ多くの課題が山積している。
そして、これらの課題を適切に解決していくことができなければわが国の経済が大きく復活を遂げることはできない、といっても過言ではない。
このため、法人税法における税制の仕組みを抜本的に見直して改革を行うことが喫緊の課題となっているわけだが、この改革は、従来の租税特別措置のように、必ずしも減税を伴うものではないという点に留意しておく必要がある。
たとえば、平成13年度の組織再編成税制の創設は、わが国の企業の再編に非常に大きく貢献したといわれているが、同税制の創設による税収の増減額は零と試算されていた。同税制は、減税措置ではなかったわけだが、わが国の企業活動に大きく貢献し、結果として、税収の増加に大きく貢献したはずである。
法人税制は、会社法・企業会計とともに、経済活動の不可欠のインフラであるといわれるが、それは、すなわち、その仕組みを合理的なものとすることを常に求められることとなり、それが経済活動に大きく貢献することとなる、ということを意味している。
減税しなければ経済対策にならないという考え方は、もう捨てるべき時期に来ていると考える。従来のように、減税か増税かという議論によって税制を決めるのではなく、時代の要請に合った合理的な仕組みを創るためにはどうすればよいのかということを徹底して議論し、税制をあるべき姿に少しでも近づけることが必要となっている、と考える。
以下、そのような観点に立って、法人税法における税制の課題について述べることとする。
Ⅱ.事業体税制の再構築
わが国においては、大法人および中小法人の双方が合同会社等の持分会社、信託、任意組合・匿名組合などの多様な事業形態の選択をすることができるように税制の抜本的な整備を図ることが重要な課題となっている、と考えられる。
合名会社・合資会社・合同会社からなる持分会社に関しては、利益は構成員のものとされており、会社法のもとで設立されたものについては、諸外国の取扱いと同様に、法人税課税ではなく、構成員課税とするべきであると考える。
信託法上、信託財産から生ずる利益は受益者に帰属することが明確であり、受託者は手数料を得る権利があるのみで信託財産の利益を自らのものとすることはできないわけであるから、利益なきところに課税を行うこととなっている「法人課税信託」に関しては課税のあり方を再検討する必要があると考える。
また、受益権の多様化にどのように対応するのかということを明らかにするとともに、受益者における税制上の取扱いを整備することも欠かせないと考える。
任意組合・匿名組合に関する税制は、現在に至っても、その基本的な取扱いは通達に委ねられており、多くの課題が残されたままとなっている。組合の機能は、基本的には信託と同様であるため、信託に関する取扱いと平仄を合わせて組合の取扱いを法制化する必要がある。
また、これからのわが国においては民間の非営利活動を大きく発展させることが重要であり、公益法人税制については、民間の非営利活動を大きく促進するという観点に立って、再検討を行う必要があると考える。いわゆる天下りが問題となる公益法人は、全体からみると、ごく少数にとどまり、大多数の公益法人は、民間の非営利活動を担う重要な役割を果たしている。ごく一部に不適切な公益法人が存在することをもって、あたかもすべての公益法人に問題があるかのごとき対応がなされるとすれば、社会的に大きな取返しのつかない損失を生じさせることとなってしまいかねない。
特に、みなし寄附金の損金算入と利子等に対する源泉所得税を非課税とすることは、是非とも必要な喫緊の課題であると考える。
Ⅲ.無形資産税制の抜本改正
今後、わが国においては、無形資産の創造と活用を促進することが非常に重要となり、そのなかでもいわゆる知財が特に重要となると考えられる。わが国においては、アメリカ等と比較すると、無形資産に対する認識と評価が十分ではないといわれてきたが、現在においても、その状況に大きな変化はないように思われる。アメリカにおいては、通常、事業価値の最も大きな構成要素は無形資産であるといわれているが、わが国においては、いまだ有形資産が事業価値の大半を占めるとの認識が一般的である。これは、わが国においては価値のある無形資産が少ないという事情によるだけでなく、無形資産に大きな価値があるという認識自体が十分でないということが原因になっているものと考えられる。
このようなわが国の状況は、第三次産業が大きく拡大してきた現在の企業活動の実態を的確に捉えたものとはなっておらず、また、将来の企業活動の状態に適合するものでもないと考える。
将来にわたってわが国が世界のなかで枢要な地位を維持していくためは、無形資産の創造と活用を大きく促進することが不可欠となるということに、おそらく異論はなかろう。
無形資産の創造促進に関しては、平成14年に成立した知的財産基本法がその象徴的なものだが、税制においても、研究開発税制を始めとして様々な対策が講じられてきた。そして、それらは無形資産の創造や保護という点では一定の成果を挙げてきたものと想定されるが、無形資産の活用という点では必ずしも十分な成果を挙げきれておらず、そのため、無形資産の活用の拡大が無形資産の創造のインセンティブとなり、有用な無形資産の創造がさらなる無形資産の活用の拡大に繋がるという善循環が生まれない原因となっているように思われる。
無形資産が十分に活用されないのは、主に次のような理由によるものと考えられる。
① 価値が適切に計算できないこと
② 価値がゼロとなってしまう懸念があること
③ 自己の創造した無形資産を他の者が利用す
ることで自己が不利益を蒙ることになる懸念があること
④ 法制・会計・税制における取扱いが明確でないこと
まず、第一に挙げなければならないのは、上記①の「無形資産の価値が適切に計算できない」ということである。
現在、わが国には、不動産鑑定士と証券アナリストという資格制度があるが、前記の無形資産等の評価のニーズに対応できるものではない。資産全般にわたる評価資格制度を設けたとしても、それですぐに税務上の問題が解決したり取引が大きく拡大したりすることにはならないと考えられるが、このような制度を設けることが、それらを解決するための重要な一歩となることは間違いない。このため、わが国においても、諸外国の例にならい、早急に資産・負債・事業価値の包括的な評価基準を作成するとともに、評価資格制度を創設すべきであると考える。
現在、税制においても、移転価格税制、組織再編成税制、連結納税制度や相続税において、無形資産、事業評価、種類株式などの評価をどのように行うべきかということ等が大きな課題となっているわけだが、このように、包括的な評価資格制度を設けて無形資産の評価に関する信頼度を上げることは、この税制の課題を解決することにもなる。
次の上記②「価値がゼロとなってしまう懸念がある」という点に関しては、無形資産の性質上、やむを得ないことであり、また、上記③「自己が不利益を蒙ることになる懸念がある」という点に関しては、無形資産の譲渡や使用許諾に伴って必然的に生ずる事柄であり、基本的には、避けることができないものと考えておかなければならない。
上記④「取扱いが明確でない」という点に関しては、これらとは異なり、法制、企業会計や税制において積極的に対応することが必要となる。無形資産には、その価値をどのように計算するべきかという難しい課題があることは間違いないが、法制、企業会計や税制における取扱いを整備することで、その難しい課題の負担を軽くすることも、十分、可能であると考えられる。そうすることにより、少しずつ、無形資産の譲渡、使用許諾、信託、担保などが広がっていくものと期待される。法制、企業会計や税制における取扱いを整備することで、少しずつ、無形資産の取引等が広がり、その結果、トラックレコードが得られ、それがさらに適切な価値の計算に資する、という関係が生じてくることも、十分にあり得ることである。
税制における整備が先行した平成13年の組織再編成税制の創設がその好例だが、特に税制において無形資産の取扱いを整備することが無形資産の活用の低調な現状を大きく改革する鍵になるものと考える。
企業会計においては、近年、無形資産に関し、見直しが行われてきており、法人税法と比べると、相対的に実態に即した取扱いとなっている。このような企業会計における近年の見直しが法人税法における取扱いとの乖離を生むこととなり、両者の関係が不明確となっているわけである。
法人税法においては、昭和40年のその創設以来、無形固定資産等の範囲等に関する抜本的な見直しが行われていない。
現行の法人税法が定められた昭和40年当時、無形資産は、有形資産と比べると、その他の特殊な資産という程度の認識で済む状態であったものと考えられるが、現在は、第三次産業が大きく拡大しており、無形資産が事業価値の大きな部分を占めるということになることも、決して稀ではないと想定される。
このような事情からすると、法人税法において無形固定資産等に関する取扱いの抜本的な見直しを行うことが重要課題となっていると考える。
以下、無形固定資産の「活用」に重点を置く税制の具体的な見直し案を提示したい。
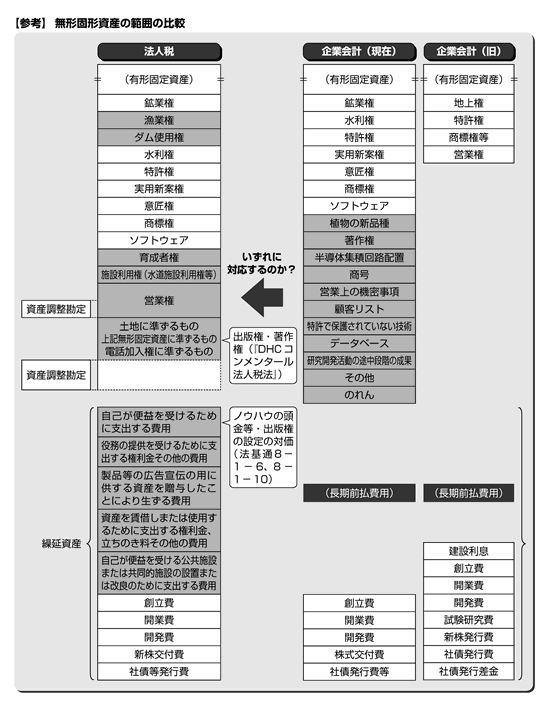
1 無形固定資産・繰延資産の資産区分を企業会計に合わせること 税制上の無形固定資産・繰延資産の資産区分は企業会計の無形資産等の資産区分とかなりの部分で異なっているが、両者の相違を合理的に説明することは困難であり、実務上も、両者が適切に処理されているとは思われない。
企業会計の取扱いと税制の取扱いを合わせること自体は、それが直接に無形資産の「活用」を促進するというものではないが、無形資産の「活用」の促進を図るということであれば、まず、その「活用」を促進しようとする無形資産がどのようなものであるのかということを明らかにしておくことが必要である。
細かくみていくと、企業会計における資産区分を修正しなければならない部分も出てくる可能性はあるが、総体的にみれば、企業会計の資産区分に合理性があると考えられるため、基本的には、税制における資産区分を企業会計のそれに合わせるのが適当であると考える。
税制上の無形固定資産・繰延資産の区分を企業会計の無形資産等の区分に合わせることとすれば、実務上、非常に大きな問題となっている営業権の問題が解消することとなって組織再編成も連結納税の拡大に大きく資することとなり、また、営業権と資産調整勘定の重複という問題も解消することができることとなる。
ただし、企業会計においては、国際会計基準との調整を行うにあたって、連結財務諸表制度における資産区分と個別財務諸表におけるそれとが異なることがあり得ると考えられるため、そのような場合には、税制においては、そのいずれも採り得ることとするべきである。
改めていうまでもないが、無形固定資産・繰延資産の範囲について、税制を企業会計に合わせるということになれば、税制の簡素化にも資することとなる。
なお、そもそもコンプライアンスの確保に難点がある制度はその妥当性に疑問があるということも、付言しておくこととする。
2 他から取得した無形固定資産のみを資産計上するものとすること 他の者から取得した無形固定資産は、適格組織再編成によって事業の移転を受ける場合にその一部としてそれらが含まれているような場合を除き、その価値が明らかであるが、自己が創造したそれらは資産としての価値があるのか否かが明らかでないものが少なくない。
このような実態があることからすると、税制において資産として計上すべき無形固定資産は、他の者から取得したものに限ることとし、適格組織再編成により取得したものを除くこととするのが適当であると考える。
企業会計においては、自己の研究開発費を無形資産として計上する部分があるが、税制においては、この自己の研究開発費を損金算入とせずにさまざまな政策措置を講ずるよりも、この自己の研究開発費を損金算入としたうえで、さらに必要な政策措置があれば、その政策措置を講ずる、とする方が適切であると考える。
研究開発を促進することは、わが国においては、一時的な政策措置というよりも、常に優先度の高い恒久措置と位置付けるべきものである。
なお、これは、上記1と同様に、税制の簡素化にも資することとなる。
3 無形固定資産の取得価額を一時の損金とするかまたは耐用年数を大幅に短縮すること 無形固定資産の取得価額を一時の損金とするかまたは耐用年数を大幅に短縮することで、これらの取引に大きなインセンティブを与えることができる。
無形固定資産の取得価額が一時の損金となるかまたは耐用年数が大幅に短縮されるということになれば、直接、無形固定資産を売買することも相当に増えてくると想定される。わが国においては、自己の使用しない特許等であってもそれを手放すことによって後に自己が不利な立場に立たされることになってしまうのではないかとの懸念からその売買が広がらないといわれており、確かにそのような部分があることは否めないため、無形固定資産を信託や組合を使って活用したり、無形固定資産の賃貸借を促進したりする措置を講ずることとすれば、なお一層の効果が期待できると考えられる。
特に、前者は、事業体税制の改正と併せて行うことにより、大きな成果を得ることが期待される。無形固定資産を取得して自ら事業を行うという投資の形態と無形固定資産を取得する会社の株式を取得するという投資の形態も、もちろん、あり得るわけだが、信託や組合を使って事業を行うというこの両者の中間の投資の形態が大きく拡大したとしても、何らおかしなことではない。そもそも、信託や組合は、そのような形態の事業を行うビークルとして存在しているからである。
このように、多様な形態で無形固定資産の活用が図られるとすれば、大きな活路が開かれることとなる。
ただし、無形固定資産の取得価額を一時の損金とするかまたは耐用年数を大幅に短縮するということになれば、それが租税回避に利用されることとなることも懸念されるため、これらの取引が租税回避に当たるか否かについて判断の基準を設ける必要がある。
この判断の基準は、リスクを負う取引となっているのか否かということを基本とするのが適当であると考えられる。
ところで、耐用年数が大幅に短縮された無形固定資産を節税の手段としても利用してもらうということは大いに歓迎すべきことであるという点には、十分に留意する必要がある。「租税回避」の範囲をむやみに拡大し、角を矯めて牛を殺すようなことは、あってはならない。
上記の1から3までの改正は、その内容に連動性があるため、一連の改正として行うのが適当であると考えるが、少なくとも、企業会計において無形資産に関するわが国の基準と国際会計基準との調整が済んで新基準が確定すると期待される後の改正となる平成23年度改正までに行うべきであると考える。
ただし、営業権に関してこれを企業会計と同様に無形固定資産から除外してのれんに吸収する改正は、単独で行い得るものであり、企業会計において爾後に変更が生ずることが想定されないため、平成22年度改正にて速やかに行うこととするのが適当と考える。
Ⅳ.資本等取引に関する税制の構築
現行の資本等取引に関する税制には、次の3つの大きな課題が残されており、これを解決する必要があると考える。
① 資本金等の額を1つの金額と捉えること
法人税においては、株主等からの拠出部分を複数に分けて捉える理由はないことから、資本の金額または出資金額と従来の資本積立金額とを区分せず、資本金等の額を1つの金額として捉えることとするべきである。
② 資本等取引を原則として時価取引とし特例として時価以外の取引を可とすること
資本等取引も、取引である以上、損益取引と同様に、時価によって行うべきことは、当然のことであり、資本等取引が時価で行われた場合に、これを否認する理由は存在しない。法人税法においては、資本等取引についても、原則として時価により処理することとし、株主において投資が継続していると考えられる場合には、特例として時価以外の金額での取引を認めることとするべきである。
③ 資産が移転する減資・払戻し・清算・配当について組織再編成と同様の観点から原則と特例を整理すること
減資・払戻し・清算・配当によって資産が移転する場合について、組織再編成により資産が移転した場合の取扱いと同様の観点から、税制における取扱いを整備する必要がある。
Ⅴ.そ の 他
連結納税制度においては、連結対象法人となる法人の持分割合を引き下げて50%超とするとともに、開始・加入時にその資産を時価評価しなくてよい法人とその欠損金を切り捨てなくてもよい法人の範囲を大幅に拡大するなど、抜本的な制度の見直しを行うべき時期に来ていると考える。
また、移転価格税制の法制整備や外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の適用基準の緩和も、不可欠であると考える。
加えて、理論的にも立法手続にも大きな問題がある特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度を廃止すること、そして、役員給与の損金不算入制度を平成18年度改正前に戻したうえで再検討することが不可欠であると考える。
(ともなが・ひでき)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















