解説記事2009年12月07日 【実務解説】 わが国の法人が特定外国子会社等から配当を受け取る場合の課税関係─外国子会社合算税制の適用除外となる中国子会社を例として─(2009年12月7日号・№333)
実務解説
わが国の法人が特定外国子会社等から配当を受け取る場合の課税関係
─外国子会社合算税制の適用除外となる中国子会社を例として─
日本税制研究所代表理事 税理士法人アクト22代表社員 朝長英樹
Ⅰ.はじめに
平成21年度改正により、間接外国税額控除制度の廃止、外国子会社配当益金不算入制度の創設およびこれらの改正に伴う外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)等の改正が行われたことから、外国に子会社を持つわが国の法人においては、現在、これらの改正への対応が課題となっている。
特に、中国に子会社を持つ法人においては、中国においても税法改正が行われて経過措置や新制度が適用される状態となっているため、上記の改正への対応をどのように行うのかということが、重要な課題となっている。
このため、本稿においては、わが国の法人が中国に子会社を持っているというケースを想定して、その課税関係について解説を行うこととする。
ただし、上記のとおり、わが国と中国は、現在、いずれも税制改正の経過措置期間に当たり、課税関係が錯綜して解りにくい状況にあること、そして、中国以外の国に子会社を持っているケースの参考としてもらうことを考慮して、本稿を2部に分けて構成することとし、ⅡからⅧまでの前半部分においては、わが国の3月決算の法人が外国に12月決算の100%子会社(外国子会社合算税制における特定外国子会社等には該当するが同税制の適用除外となるもの)を持っているという前提で解説を行い、それを踏まえて、ⅨからXIまでの後半部分において、わが国の3月決算の法人が中国に当該子会社と同様の子会社を持っている場合のわが国における課税関係等について解説を行うこととする。
なお、本稿は、わが国の法人の課税関係を主たるテーマとするものであり、中国における子会社に関しては、著者が得た範囲内の情報に基づき解説を行っていることを予めお断りしておく。
Ⅱ.課題の確認
平成21年度の間接外国税額控除制度の廃止、外国子会社配当益金不算入制度の創設等の改正は、基本的には、わが国の法人が平成21年4月1日以後に開始する事業年度において外国子会社から受ける配当について適用されるが(平成21年度改正法附則6条)、特定外国子会社等(外国子会社合算税制の適用除外となるものを含む)から受ける配当については、その特定外国子会社等の平成21年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについて新制度の適用があるものとされている(平成21年度改正法附則44条5項)。
この場合の「係る」とは、「支払に係る基準日の属する」という意であると解される(脚注1)。 このため、わが国の法人が特定外国子会社等を有する場合には、その特定外国子会社等から受け取る配当の支払いに係る基準日がその特定外国子会社等のいずれの事業年度に属するものとなっているのかによって、新旧制度のいずれを適用するのかということが変わってくることとなるが、旧制度の間接外国税額控除制度と新制度の外国子会社配当益金不算入制度は、いずれも申告を要件として適用される制度(法法23条の2第2項、旧法法69条16項)であるため、その適用関係を誤ると、いずれの制度の適用も受けられないという事態に直面することとならざるを得ない。
このように、平成21年度改正の経過措置期間における新旧制度の適用関係を正しく理解することが非常に重要となっている。
Ⅲ.法人税法における「基準日」に係る規定
上記Ⅱにおいて述べたとおり、平成21年度改正法附則においては「基準日」という用語は用いられていないが、この「基準日」がその解釈の鍵となるものと解される。
このため、「基準日」が法人税法においてどのように用いられているのかということを確認しておくこととする。
現在、法人税法およびその政省令において「基準日」という用語が用いられているのは、受取配当益金不算入制度(法法23条3項、法令20条ほか)、留保金課税制度(法法67条4項、法令139条の8第1・2項、139条の9、140条ほか)、連結納税制度(連結法人株式等の範囲に係る部分)(法令19条1項)および所得税額控除制度(法令140条の2第2項ほか)となっている。平成21年度改正前は、これらに加えて、間接外国税額控除に関する規定である旧法人税法施行令147条(外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)の2項1号に次のような規定が置かれていた。
この規定からも明らかなように、法人税法においては、法人に「基準日」があることを前提として各規定が設けられており、「基準日」は、平成21年度改正法附則だけでなく、法人税法における上記の諸制度において重要な役割を果たしているといってよい。
このため、この「基準日」がどのようなものであるのかということを明らかにしておかなければならないわけであるが、その検討の前に、法人税法に「基準日」の概念を入れるきっかけとなった会社法において、「基準日」がどのようなものとされているのかということを確認しておくこととする。
Ⅳ.会社法における「基準日」の規定
会社法においては、124条に「基準日」の定めが設けられているが、その全文を示すと、次のとおりである。
この規定からもわかるとおり、会社は「基準日」を定めることも、定めないこともできるわけであり、「基準日」が決算期末日や中間決算期末日でなければならないというわけでもない。権利の内容が異なるごとに複数の「基準日」を設けることも、また、「基準日」後に株式を取得した者に権利行使を認めることもできることとなっている。
このように、会社法においては、「基準日」はかなり柔軟に規定されている。
会社の現状をみてみると、公開会社の場合にはその多くが決算期末日と中間決算期末日となっているようであるが、会社法においては定款に定める「基準日」以外に一定の要件のもとで「基準日」を設けることも認められており、「基準日」を都度定めて剰余金の配当を行うケースも見受けられる。
これに対し、公開会社以外の会社の場合にはほとんど「基準日」の定めを設けていないようである。
非公開会社の場合には、株主の異動があまりないため、「基準日」を定めて公告をしたり定款に規定したりする必要性がないことがその最も大きな理由となっていると考えられるが、株主の異動があった場合に、議決権の行使をいずれの時点の株主としているのか、また、利益配当請求権の行使をいずれの時点の株主に認めているのかということは、必ずしも明らかではない。多くの場合、決算期末日の株主にこれらの権利の行使を認めることとしているものと想定されるが、これもあくまで想定でしかなく、現実には、株主総会の日等としたものがあることも考えられる。
Ⅴ.法人税法と会社法の関係
「基準日」という用語は、平成18年度改正において初めて用いられたものであり、そのきっかけとなったのは、上記Ⅳで述べた会社法の改正である。すなわち、会社法で「基準日」が用いられたことを受けて法人税法にも「基準日」という用語が用いられるようになったわけである。
このことからも察せられるように、法人税法において「基準日」やそれに相当する日がいずれの日となるのかということを考えるに当たっては、会社法における「基準日」と法人税法における「基準日」との関係を確認しておく必要があるが、これは、すなわち、法人税法と会社法という2つの法律がどのような関係となっているのかということの確認にほかならない。
法人税制と会社法制とがどのような関係となっているのかという制度論に関する議論には諸説が存在するが、ここでは、そのような制度論ではなく、法人税法の規定のなかで用いられている「基準日」がどのような内容のものであるのかということを明らかにするために、法人税法と会社法という2つの法律がどのような関係にあるのかということを確認することとする。
法人税法と会社法という2つの法律の関係を確認するために、「基準日」と不可分の関係にある「配当」を取り上げてみることとする。
会社法においては、改めていうまでもなく、その対象となっている「会社」に関して「剰余金の配当」に関する定めがあるのみで、利益配当請求権に係る「基準日」も「剰余金の配当」に関するものに止まると解される。
これに対し、法人税法においては、「剰余金の配当」は株式に係るものだけでなく出資に係るものも含み、そのほかに「利益の配当」や「剰余金の分配」等を含めてこれらの金額を「配当等の額」と呼び(法法23条1項)、非適格合併において生ずる利益積立金の株主への帰属額等を「剰余金の配当」等の金額とみなすこととしている(法法24条1項)。
このように、法人税法における「剰余金の配当」は、同じ用語を用いてはいるものの、会社法における「剰余金の配当」よりもその範囲が広く、また、法人税法においては、他の「利益の配当」等を含めてこれらの金額を「配当等の額」と捉えて同じように取り扱うこととしているわけである。
そして、法人税法においては、これらの「配当等の額」に関し、「基準日」があることを前提として、各種の取扱いを定めているのである。
当然のことながら、会社法が対象とするのはわが国の「会社」であり、法人税法が対象とする「法人」はわが国の「会社」に止まらない。
確かに、商法と会社法はわが国の商事の基本法であり、法人税法の適用対象者や適用対象行為も、これらの法律の対象となる会社であり、また、これらの法律の定める商行為となることが大半であるため、法人税法においては、自ずと、これらの法律の定めを前提として各種の定めを設けることとなることが多くなる。
このため、商法や会社法において用いられる用語と同じ用語を法人税法に用いることは、むしろ当然のことであり、その用語の法人税法における意味内容は商法や会社法におけるそれと基本的には同じということになることが多い。
しかし、法人税法とこれらの法律とは、そもそもその目的が異なり、その対象者やその対象とする行為等も同じではないため、同じ用語を用いていたとしても、その用語の意味内容が法人税法とこれらの法律とで同じとなるとは限らない。
上記の「配当」の例は、法人税法と会社法という2つの法律の関係を正しく理解するためのよき材料となっているが、このほか「譲渡」なども、法人税法におけるその意味内容が商法や会社法のそれとかなりの部分で異なる例といってよい。
このような事情にあるため、法人税法の解釈においては、法人税法におけるその用語がどのような意味内容を持つものであるのかということを、常に、考える必要がある。
この点は、法人税法が、商法や会社法とは異なり、国内取引等と同様に国外取引等も適用対象とするということを考えると、なお一層、明確となる。
Ⅵ.法人税法における「基準日」の取扱い
上記Ⅲでも記載したとおり、法人税法においては、国外税制としての外国税額控除制度や外国子会社配当益金不算入制度だけでなく国内税制としての所得税額控除制度、受取配当益金不算入制度、留保金課税制度や連結納税制度において、「基準日」に基づく規定が設けられている。
このため、「基準日」の定めがある場合には、それらの各規定に定められたとおりに取り扱うことで、問題はない。
法人税法には、「基準日」に特段の制限は設けられていないため、定款で定められたものであっても、都度設けられたものであっても、それが「基準日」である限り、上記の諸制度の各規定は、それぞれの定めに従って解釈をすることとなる。
ただし、上記Ⅳにおいて記載したとおり、この「基準日」は、議決権を行使することができる株主を決める日であったり、利益配当請求権を行使することができる株主を決める日であったり、また、それらの双方の権利やその他の権利を行使することができる株主を決める日であったりするため、その「基準日」がどのような内容の「基準日」であるのかということも明らかにしたうえで、上記の諸制度の各規定の適用を検討する必要がある。法人に「基準日」があったとしても、それが議決権を行使することができる株主を決める「基準日」であって、利益配当請求権を行使することができる株主を決めるものでないということであれば、その日を「基準日」として規定を適用することができないということになることもあり得る。
他方、わが国においては「基準日」を定めていない法人が多数存在しているという現実があり、また、わが国の法人が親会社となっている外国子会社等にも「基準日」を定めていないものが多数存在すると想定される状況があるものの、上記の諸制度の各規定には「基準日」がない場合の取扱いは定められていないため、「基準日」の定めがない場合には、これらの各規定をどのように解釈し、どのように適用するのかということが、重要な問題となる。
この点に関しては、基本的には、「基準日」に相当する日をもって「基準日」とし、上記の諸制度の「基準日」を含む各規定を解釈する、ということでよいものと考えられる。法人に「基準日」の定めがない場合にこれらの各規定を、別途、他の方法で解釈しなければならないとする理由は見当たらない。
このように、「基準日」に相当する日をもって上記の諸制度の各規定の「基準日」とするということになると、具体的な事案においては、その相当する日がいずれの日かということが問題となるわけであるが、上記Ⅳでも記載したとおり、現に「基準日」を定めている公開会社等と同様に、決算期末日とするのが妥当と認められるものが多いと考えられるが、一部、他の日をもって「基準日」に相当する日とするのが適切であるというものも生じてくると想定される。
Ⅶ.法人税法における国外取引等の取扱い
本稿は、外国の子会社がわが国の親会社に配当を行うというケースを想定してわが国の親会社の法人税法上の取扱いを説明するものであり、法人税法および平成21年改正法附則において、親会社が子会社から受ける配当に関する間接外国税額控除制度や外国子会社配当益金不算入制度の適用がどのようなものとなるのか、また、子会社から親会社への配当に課された源泉所得税に関する直接外国税額控除制度や損金不算入制度の適用がどのようなものとなるのかということが問題となる。
この問題に適切な解答を出すためには、わが国の法人税法が国外で行われた行為や国外で生じた事実に対してどのように適用されることとなるのかということを正しく理解しておくことも、不可欠である。
平成21年度改正において、国外所得免除の性格を有する外国子会社配当益金不算入制度が創設され、その選択が可能となったが、わが国の法人税法は、依然として、その基本は、全世界所得課税となっている。
わが国の法人税法は、国内で得た所得も国外で得た所得も区別なく1つの所得と捉えて課税を行う仕組みとなっており、基本的には、国外の行為も国内の行為と同様に取り扱うこととしている。
上記Ⅴで述べたとおり、わが国の法人税法は、商法や会社法において用いられる用語を用いてその規定を定めることが多いが、その解釈を行い、適用することとなる規定は、あくまでもわが国の法人税法の規定であり、それがどのような内容の規定となっているのかが、まず、問題となることになる。
わが国の商法や会社法における取扱いと外国のそれらに相当する法における取扱いとを比較することは、わが国の法人税法の規定を適用するにあたって、その適用対象となる行為や事実の内容等を確認するという点では有効であっても、それ以上のものではない。
わが国の法人税法の規定を適用する限りは、その規定の解釈をどのように行うべきかということが、まず、問題となるのである。
そして、次に、現に法人が行った行為や法人に生じた事実がどのような内容のものであり、どのような性質を持ったものであるのかというようなことが、問題となる。
このようにして、わが国の法人税法の規定の解釈が明らかになり、そして、法人の行為や事実の内容等が明らかになれば、その規定の適用関係が明らかとなり、取扱いが定まることとなる。
当然のことながら、国外で行われた行為や国外で生じた事実に関しては、国内のそれらよりもその内容等を把握することが難しくならざるを得ないが、わが国の法人税法を法人の行為や事実に対して適用するという点では、国内取引等と国外取引等に本質的な違いはない。
Ⅷ.平成21年度改正法附則等の取扱い
平成21年度改正の経過措置期間においては、親会社における特定外国子会社等に該当する子会社からの配当に課された源泉所得税の直接外国税額控除制度の適用の可否については、平成21年度改正法附則12条(外国税額の控除に関する経過措置)の1項、平成21年改正措令附則27条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の6・8項の確認が必要となり、親会社が子会社から配当を受ける場合の間接外国税額控除制度と外国子会社合算税制に係る外国税額控除制度の適用の可否については、平成21年度改正法附則1条(施行期日)、12条2項、44条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の5項後段・6項後段・2項の確認が必要となる。
しかし、紙幅の都合上、この詳細に関しては、前掲『国際的二重課税排除の制度と実務』346頁(脚注2)および378頁または本誌331号20頁に譲ることとし、ここでは、特定外国子会社等に該当する外国子会社の配当に係る「基準日」が平成21年4月1日前に開始するその子会社の事業年度(中国の子会社の場合には、平成21年12月期以前の事業年度)である場合(図表1の基準日①のような場合)には、配当に課された源泉所得税に関する直接外国税額控除制度と間接外国税額控除制度の適用が可能であり、特定外国子会社等に該当する外国子会社の配当に係る「基準日」が平成21年4月1日以後に開始するその子会社の事業年度(中国子会社の場合には、平成21年12月期の後の事業年度)である場合(図表1の基準日②のような場合)には、外国子会社配当益金不算入制度の適用が可能であり、配当に課された源泉所得税に関する直接外国税額控除制度と間接外国税額控除制度の適用はない、ということを確認するに止め、参考として、図表1・2を掲げておくこととする。
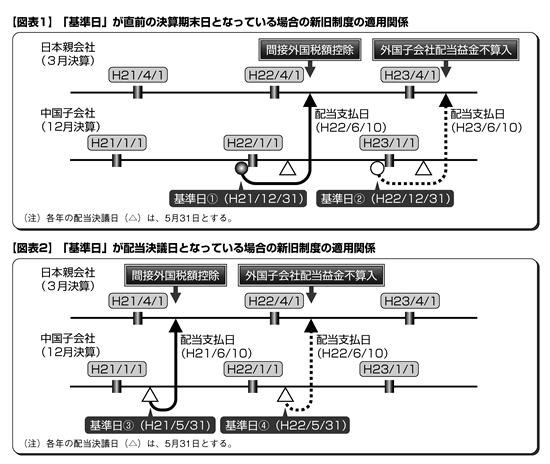 なお、外国子会社の場合には、非公開会社の場合と同様に、「基準日」を定める必要性が乏しいため、現状においては、「基準日」を定めているものは少ないものと想定されるが、上記Ⅵに記載したとおり、定款に「基準日」を定めたり、配当の都度「基準日」を設けているものは、その「基準日」を上記の制度の各規定中の「基準日」とし、「基準日」の定めがないものは、「基準日」に相当する日がいずれの日となるのかということを検討してその相当する日とした日をもって「基準日」とし、上記の制度の「基準日」を含む各規定を解釈することとなることを、ここで改めて確認しておくこととする。
なお、外国子会社の場合には、非公開会社の場合と同様に、「基準日」を定める必要性が乏しいため、現状においては、「基準日」を定めているものは少ないものと想定されるが、上記Ⅵに記載したとおり、定款に「基準日」を定めたり、配当の都度「基準日」を設けているものは、その「基準日」を上記の制度の各規定中の「基準日」とし、「基準日」の定めがないものは、「基準日」に相当する日がいずれの日となるのかということを検討してその相当する日とした日をもって「基準日」とし、上記の制度の「基準日」を含む各規定を解釈することとなることを、ここで改めて確認しておくこととする。
Ⅸ.中国における企業所得税の取扱いとわが国におけるその取扱い
中国においては、企業所得税法が改正され、従来、33%であった税率が2008年分から25%に引き下げられている。
このため、現在、中国子会社は、基本的には外国子会社合算税制における特定外国子会社等に該当することとなっているが、実際には、中国子会社のほとんどが外国子会社合算税制の適用除外法人となっているものと想定される。
このような中国子会社に配当可能利益があれば、今後、わが国の親会社に対して配当を行うこととなるものと考えられるが、上記Ⅷに記載したとおり、その配当に係る「基準日」が平成21年12月31日以前であれば、間接外国税額控除制度が適用されることとなり、25%または33%で課された企業所得税はわが国の親会社の法人税から控除されることとなる。
中国の場合には、従来、優遇措置として軽減税率(15%・24%)や期間減免措置(2免3減など)があったが、企業所得税法の改正に伴い、経過措置を設け、前者のうち15%のものに関しては2012年までに段階的に税率を25%とすることとされており、後者に関しては、2008年時点で適用を受けているものについては引き続き期間満了まで措置を継続適用することができることとされている。
そして、これらの措置によって減免された企業所得税に関しては、日中租税条約23条(二重課税の排除)の4(c)により、引き続き、みなし外国税額控除の対象とすることが認められることとなる(脚注3)。
間接外国税額控除制度の適用にあたっては、このみなし外国税額控除の効果を享受できるため、みなし外国税額控除に係る部分を含むすべての税額が控除できるという場合には、外国子会社配当益金不算入制度を適用するとした場合よりも、わが国の親会社と中国子会社の税負担の合計額が有利となるケースが多いものと考えられる。
一方、中国子会社の配当に係る「基準日」が平成22年1月1日以後であれば、その配当は、外国子会社配当益金不算入制度の対象となることとなる。
この場合には、配当の95%が益金不算入となり、間接外国税額控除制度の適用を受けることはできなくなる。
Ⅹ.中国において配当に課される源泉所得税とわが国におけるその取扱い
中国においては、わが国の法人がその100%の持分を有するような中国子会社から受ける配当に対しては、従来、旧税法の優遇措置の適用を受けて源泉所得税が課されておらず、加えて、日中租税条約23条3(a)により20%の税率で源泉所得税が課されたものとみなし、20%の部分をみなし外国税額控除の適用対象とする、というように、かなりの優遇が行われていた。
企業所得税法の改正後は、上記のような配当に対しては、免税措置が適用されなくなり、企業所得税法上は原則として20%の源泉所得税の課税がなされることとなったが、実施条例の減免規定が適用されて10%の課税で済むこととなり、また、日中租税条約10条(配当)の2により限度税率も10%とされていることから、実際には、10%の源泉所得税の課税が行われることとなっている。そして、このような配当に関しては、改正後も日中租税条約23条3(a)により、20%の税率で課税が行われたものとみなし、10%の部分がみなし外国税額控除の適用対象とすることができることとなっている。
この企業所得税法の改正に際しては、経過措置が設けられており、2007年以前の利益から成る部分については、従来どおり、源泉所得税は課されないこととなっており、20%の部分をみなし外国税額控除の適用対象とすることができることとなっている(図表3参照)(脚注4)。
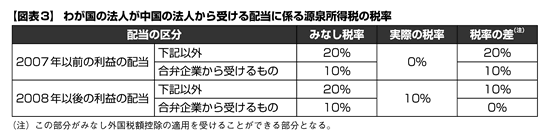 このように、中国子会社からの配当に関しては、それがいずれの時期の利益からなるものかということが非常に重要となる。
このように、中国子会社からの配当に関しては、それがいずれの時期の利益からなるものかということが非常に重要となる。
わが国においては、これらの配当に課される源泉所得税に関しては、その配当に係る「基準日」が平成21年12月31日以前であれば、みなし外国税額控除を含めて直接外国税額控除制度を適用することが可能であり、その「基準日」が同日後であれば、直接外国税額控除の適用は認められないこととなる。
このように、中国子会社からの配当に課される源泉所得税に関しても、その配当に係る「基準日」がいずれの日となっているのかということにより、わが国における取扱いが異なってくることとなる。
XI.中国子会社からの配当に関する対応
上記Ⅷに記載したとおり、わが国の平成21年度改正の経過措置は、外国子会社が特定外国子会社等に該当するものに関しては、その外国子会社からの配当に係る「基準日」に基づいて適用関係を定めている。
このため、わが国の法人が中国子会社からの配当に関して平成21年度改正の経過措置を適用する場合には、それを疑義なく適用するために、中国子会社において、早期に「基準日」を明確にしておくべきであると考えられる。上記Ⅱにおいても述べたとおり、旧制度である間接外国税額控除制度と直接外国税額控除制度と新制度である外国子会社配当益金不算入制度の適用関係を誤ると、いずれの制度の適用も受けられないという極めて深刻な事態に直面せざるを得なくなってしまう。
また、上記ⅨおよびⅩに記載したとおり、中国子会社からの配当に関し、間接外国税額控除制度と直接外国税額控除制度を適用するのか、あるいは、外国子会社配当益金不算入制度を適用するのかにより、税負担が異なることとなるため(脚注5)、この点からも、「基準日」を明確にしておくべきであると考えられる。
しかしながら、わが国の法人の中国子会社においては、実際には、「基準日」を定款等に定めているというケースはほとんどないものと想定される。
このような中国子会社の状態は、わが国の非公開会社の状態と同様ということにはなるが、上記のとおり、その影響の大きさを考慮すれば、中国子会社の配当に係る「基準日」が明確でないという状態は、早期に改善する必要がある(脚注6)。
今後、中国子会社に関しては、配当に係る「基準日」を定款等に定めることと、中国における税法改正に伴う経過措置の適用関係を考慮しつつ間接外国税額控除制度および直接外国税額控除制度を適用した場合と外国子会社配当益金不算入制度を適用した場合とのメリットとデメリットを正確に把握して配当政策に役立てることが課題となると考えられる。
この前者の「基準日」の定めに関しては、後日、税務調査において疑義を持たれることのないように、中国子会社において早期に対応を行っておく方がよいと考えられる。
また、後者のメリットとデメリットの把握に関しては、前者の「基準日」にも影響を与えるものであることから、前者よりも早く対応しなければならないわけであるが、中国とわが国の双方における税法改正の経過措置を正確に理解し、過去の申告の状況等も確認したうえで行う必要があり、繰り返し慎重に検討を行ったうえで最終的な判断を下すこととした方がよい、と考えられる。
なお、その判断がどのようなものとなったとしても、中国子会社に配当可能利益がある場合にはいずれかの形で配当が行われることとなって、わが国の親会社はその配当に関する税務申告を行わなければならないこととなるのであるが、上記のメリットとデメリットはこの税務申告によって最終的に実現するわけであり、申告誤りによって期せずして大きな損失を蒙るといったことのないように、税務申告まで細心の注意を払わなければならないという点にも留意しておく必要がある。(ともなが・ひでき)
脚注
1 詳細に関しては、著者監修・編著(共監・共著)『国際的二重課税排除の制度と実務』(法令出版、2009年)378頁または本誌331号20頁を参照のこと。
2 この部分は、平成21年度改正前の事業年度で配当の受取りが確定し同改正以後の事業年度でその受取りが行われる場合の直接外国税額控除に関して説明した部分であるが、追記事項があるため、日本税制研究所のホームページ(http://www.zeiseiken.or.jp/)を合わせて確認されたい。
3 「日中租税条約に規定する「みなし外国税額控除」の適用継続について」(財務省、2008年3月26日)において、日中租税条約に規定する中国の経済開発奨励措置に関するみなし外国税額控除が中国の国内法改正後も引き続き適用されることが確認されている。
ただし、中国の新税法において新たに措置された優遇税制によって減額される税額に関しては、日中租税条約のみなし外国税額控除の対象とする旨の交換公文等が新たに締結されるということにならない限り、その適用を受けることはできない。
4 中国子会社が合弁企業である場合には、従来は、旧税法の優遇措置の適用を受けて源泉所得税が課されておらず、日中租税条約23条3(a)により10%の税率で源泉所得税が課されたものとみなして10%の部分をみなし外国税額控除の適用対象とすることができたが、企業所得税法の改正後は、免税措置が適用されなくなり、10%の税率で源泉所得税が課税され、みなし外国税額控除の適用を受けることができる部分はなくなっている。
また、2007年以前の利益からなる部分については、経過措置により10%の部分をみなし外国税額控除の適用対象とすることができることとなっている。
5 中国子会社に関しては、特に、間接外国税額控除制度および直接外国税額控除制度の双方におけるみなし外国税額控除が税負担額の引下げに資することとなっている。
わが国の親会社において、このみなし外国税額控除に係る部分を含むすべての税額が控除できることとなるのか否かは、親会社の所得・税額の発生状況や外国税額控除の申告をどのように行っているのかによることとなるため、一概に有利不利の結論を出すことはできないが、このみなし外国税額控除に係る部分を含むすべての税額が控除できるという状態であるとすれば、基本的には旧制度の方が有利と考えてよい。
このため、中国子会社に関しては、平成21年12月31日以前を「基準日」として配当を行いたいというニーズが確実に存在するものと考えられる。
このような点からも明らかなように、「基準日」を定める場合には、中国とわが国の双方の改正の経過措置も十分に勘案して行う方がよいと考えられる。
6 著者が聞く限り、中国の法制上、わが国の会社法における「基準日」と同様のものを定めることは求められていないとのことであるが、中国においても、会社がわが国の会社法における「基準日」と同様のものを定めることを妨げる事情は存在しない。中国においても、わが国と同様に、会社が配当を行う場合にその対象となる株主をいつの時点の株主とするかということを定款等に定めることは、むしろ奨励されてしかるべきである、と考えられる。
わが国の法人が特定外国子会社等から配当を受け取る場合の課税関係
─外国子会社合算税制の適用除外となる中国子会社を例として─
日本税制研究所代表理事 税理士法人アクト22代表社員 朝長英樹
Ⅰ.はじめに
平成21年度改正により、間接外国税額控除制度の廃止、外国子会社配当益金不算入制度の創設およびこれらの改正に伴う外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)等の改正が行われたことから、外国に子会社を持つわが国の法人においては、現在、これらの改正への対応が課題となっている。
特に、中国に子会社を持つ法人においては、中国においても税法改正が行われて経過措置や新制度が適用される状態となっているため、上記の改正への対応をどのように行うのかということが、重要な課題となっている。
このため、本稿においては、わが国の法人が中国に子会社を持っているというケースを想定して、その課税関係について解説を行うこととする。
ただし、上記のとおり、わが国と中国は、現在、いずれも税制改正の経過措置期間に当たり、課税関係が錯綜して解りにくい状況にあること、そして、中国以外の国に子会社を持っているケースの参考としてもらうことを考慮して、本稿を2部に分けて構成することとし、ⅡからⅧまでの前半部分においては、わが国の3月決算の法人が外国に12月決算の100%子会社(外国子会社合算税制における特定外国子会社等には該当するが同税制の適用除外となるもの)を持っているという前提で解説を行い、それを踏まえて、ⅨからXIまでの後半部分において、わが国の3月決算の法人が中国に当該子会社と同様の子会社を持っている場合のわが国における課税関係等について解説を行うこととする。
なお、本稿は、わが国の法人の課税関係を主たるテーマとするものであり、中国における子会社に関しては、著者が得た範囲内の情報に基づき解説を行っていることを予めお断りしておく。
Ⅱ.課題の確認
平成21年度の間接外国税額控除制度の廃止、外国子会社配当益金不算入制度の創設等の改正は、基本的には、わが国の法人が平成21年4月1日以後に開始する事業年度において外国子会社から受ける配当について適用されるが(平成21年度改正法附則6条)、特定外国子会社等(外国子会社合算税制の適用除外となるものを含む)から受ける配当については、その特定外国子会社等の平成21年4月1日以後に開始する事業年度に係るものについて新制度の適用があるものとされている(平成21年度改正法附則44条5項)。
この場合の「係る」とは、「支払に係る基準日の属する」という意であると解される(脚注1)。 このため、わが国の法人が特定外国子会社等を有する場合には、その特定外国子会社等から受け取る配当の支払いに係る基準日がその特定外国子会社等のいずれの事業年度に属するものとなっているのかによって、新旧制度のいずれを適用するのかということが変わってくることとなるが、旧制度の間接外国税額控除制度と新制度の外国子会社配当益金不算入制度は、いずれも申告を要件として適用される制度(法法23条の2第2項、旧法法69条16項)であるため、その適用関係を誤ると、いずれの制度の適用も受けられないという事態に直面することとならざるを得ない。
このように、平成21年度改正の経過措置期間における新旧制度の適用関係を正しく理解することが非常に重要となっている。
Ⅲ.法人税法における「基準日」に係る規定
上記Ⅱにおいて述べたとおり、平成21年度改正法附則においては「基準日」という用語は用いられていないが、この「基準日」がその解釈の鍵となるものと解される。
このため、「基準日」が法人税法においてどのように用いられているのかということを確認しておくこととする。
現在、法人税法およびその政省令において「基準日」という用語が用いられているのは、受取配当益金不算入制度(法法23条3項、法令20条ほか)、留保金課税制度(法法67条4項、法令139条の8第1・2項、139条の9、140条ほか)、連結納税制度(連結法人株式等の範囲に係る部分)(法令19条1項)および所得税額控除制度(法令140条の2第2項ほか)となっている。平成21年度改正前は、これらに加えて、間接外国税額控除に関する規定である旧法人税法施行令147条(外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)の2項1号に次のような規定が置かれていた。
| 2 前項の規定の適用については、次に定める ところによる。 一 配当等の額に係る事業年度は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度とする。 イ 配当等の額が当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(以下この号において「基準事業年度」という。)の所得の金額(当該配当等の額に充てることができる部分の金額に限る。以下この号において同じ。)を超えない場合 当該基準事業年度 ロ 配当等の額が基準事業年度の所得の金額を超える場合 当該基準事業年度以前の各事業年度の所得の金額を、最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとした場合におけるその充てられることとなる当該所得の金額の属する事業年度 |
このため、この「基準日」がどのようなものであるのかということを明らかにしておかなければならないわけであるが、その検討の前に、法人税法に「基準日」の概念を入れるきっかけとなった会社法において、「基準日」がどのようなものとされているのかということを確認しておくこととする。
Ⅳ.会社法における「基準日」の規定
会社法においては、124条に「基準日」の定めが設けられているが、その全文を示すと、次のとおりである。
| (基準日) 第百二十四条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。 2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。 3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。 4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。 5 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。 |
このように、会社法においては、「基準日」はかなり柔軟に規定されている。
会社の現状をみてみると、公開会社の場合にはその多くが決算期末日と中間決算期末日となっているようであるが、会社法においては定款に定める「基準日」以外に一定の要件のもとで「基準日」を設けることも認められており、「基準日」を都度定めて剰余金の配当を行うケースも見受けられる。
これに対し、公開会社以外の会社の場合にはほとんど「基準日」の定めを設けていないようである。
非公開会社の場合には、株主の異動があまりないため、「基準日」を定めて公告をしたり定款に規定したりする必要性がないことがその最も大きな理由となっていると考えられるが、株主の異動があった場合に、議決権の行使をいずれの時点の株主としているのか、また、利益配当請求権の行使をいずれの時点の株主に認めているのかということは、必ずしも明らかではない。多くの場合、決算期末日の株主にこれらの権利の行使を認めることとしているものと想定されるが、これもあくまで想定でしかなく、現実には、株主総会の日等としたものがあることも考えられる。
Ⅴ.法人税法と会社法の関係
「基準日」という用語は、平成18年度改正において初めて用いられたものであり、そのきっかけとなったのは、上記Ⅳで述べた会社法の改正である。すなわち、会社法で「基準日」が用いられたことを受けて法人税法にも「基準日」という用語が用いられるようになったわけである。
このことからも察せられるように、法人税法において「基準日」やそれに相当する日がいずれの日となるのかということを考えるに当たっては、会社法における「基準日」と法人税法における「基準日」との関係を確認しておく必要があるが、これは、すなわち、法人税法と会社法という2つの法律がどのような関係となっているのかということの確認にほかならない。
法人税制と会社法制とがどのような関係となっているのかという制度論に関する議論には諸説が存在するが、ここでは、そのような制度論ではなく、法人税法の規定のなかで用いられている「基準日」がどのような内容のものであるのかということを明らかにするために、法人税法と会社法という2つの法律がどのような関係にあるのかということを確認することとする。
法人税法と会社法という2つの法律の関係を確認するために、「基準日」と不可分の関係にある「配当」を取り上げてみることとする。
会社法においては、改めていうまでもなく、その対象となっている「会社」に関して「剰余金の配当」に関する定めがあるのみで、利益配当請求権に係る「基準日」も「剰余金の配当」に関するものに止まると解される。
これに対し、法人税法においては、「剰余金の配当」は株式に係るものだけでなく出資に係るものも含み、そのほかに「利益の配当」や「剰余金の分配」等を含めてこれらの金額を「配当等の額」と呼び(法法23条1項)、非適格合併において生ずる利益積立金の株主への帰属額等を「剰余金の配当」等の金額とみなすこととしている(法法24条1項)。
このように、法人税法における「剰余金の配当」は、同じ用語を用いてはいるものの、会社法における「剰余金の配当」よりもその範囲が広く、また、法人税法においては、他の「利益の配当」等を含めてこれらの金額を「配当等の額」と捉えて同じように取り扱うこととしているわけである。
そして、法人税法においては、これらの「配当等の額」に関し、「基準日」があることを前提として、各種の取扱いを定めているのである。
当然のことながら、会社法が対象とするのはわが国の「会社」であり、法人税法が対象とする「法人」はわが国の「会社」に止まらない。
確かに、商法と会社法はわが国の商事の基本法であり、法人税法の適用対象者や適用対象行為も、これらの法律の対象となる会社であり、また、これらの法律の定める商行為となることが大半であるため、法人税法においては、自ずと、これらの法律の定めを前提として各種の定めを設けることとなることが多くなる。
このため、商法や会社法において用いられる用語と同じ用語を法人税法に用いることは、むしろ当然のことであり、その用語の法人税法における意味内容は商法や会社法におけるそれと基本的には同じということになることが多い。
しかし、法人税法とこれらの法律とは、そもそもその目的が異なり、その対象者やその対象とする行為等も同じではないため、同じ用語を用いていたとしても、その用語の意味内容が法人税法とこれらの法律とで同じとなるとは限らない。
上記の「配当」の例は、法人税法と会社法という2つの法律の関係を正しく理解するためのよき材料となっているが、このほか「譲渡」なども、法人税法におけるその意味内容が商法や会社法のそれとかなりの部分で異なる例といってよい。
このような事情にあるため、法人税法の解釈においては、法人税法におけるその用語がどのような意味内容を持つものであるのかということを、常に、考える必要がある。
この点は、法人税法が、商法や会社法とは異なり、国内取引等と同様に国外取引等も適用対象とするということを考えると、なお一層、明確となる。
Ⅵ.法人税法における「基準日」の取扱い
上記Ⅲでも記載したとおり、法人税法においては、国外税制としての外国税額控除制度や外国子会社配当益金不算入制度だけでなく国内税制としての所得税額控除制度、受取配当益金不算入制度、留保金課税制度や連結納税制度において、「基準日」に基づく規定が設けられている。
このため、「基準日」の定めがある場合には、それらの各規定に定められたとおりに取り扱うことで、問題はない。
法人税法には、「基準日」に特段の制限は設けられていないため、定款で定められたものであっても、都度設けられたものであっても、それが「基準日」である限り、上記の諸制度の各規定は、それぞれの定めに従って解釈をすることとなる。
ただし、上記Ⅳにおいて記載したとおり、この「基準日」は、議決権を行使することができる株主を決める日であったり、利益配当請求権を行使することができる株主を決める日であったり、また、それらの双方の権利やその他の権利を行使することができる株主を決める日であったりするため、その「基準日」がどのような内容の「基準日」であるのかということも明らかにしたうえで、上記の諸制度の各規定の適用を検討する必要がある。法人に「基準日」があったとしても、それが議決権を行使することができる株主を決める「基準日」であって、利益配当請求権を行使することができる株主を決めるものでないということであれば、その日を「基準日」として規定を適用することができないということになることもあり得る。
他方、わが国においては「基準日」を定めていない法人が多数存在しているという現実があり、また、わが国の法人が親会社となっている外国子会社等にも「基準日」を定めていないものが多数存在すると想定される状況があるものの、上記の諸制度の各規定には「基準日」がない場合の取扱いは定められていないため、「基準日」の定めがない場合には、これらの各規定をどのように解釈し、どのように適用するのかということが、重要な問題となる。
この点に関しては、基本的には、「基準日」に相当する日をもって「基準日」とし、上記の諸制度の「基準日」を含む各規定を解釈する、ということでよいものと考えられる。法人に「基準日」の定めがない場合にこれらの各規定を、別途、他の方法で解釈しなければならないとする理由は見当たらない。
このように、「基準日」に相当する日をもって上記の諸制度の各規定の「基準日」とするということになると、具体的な事案においては、その相当する日がいずれの日かということが問題となるわけであるが、上記Ⅳでも記載したとおり、現に「基準日」を定めている公開会社等と同様に、決算期末日とするのが妥当と認められるものが多いと考えられるが、一部、他の日をもって「基準日」に相当する日とするのが適切であるというものも生じてくると想定される。
Ⅶ.法人税法における国外取引等の取扱い
本稿は、外国の子会社がわが国の親会社に配当を行うというケースを想定してわが国の親会社の法人税法上の取扱いを説明するものであり、法人税法および平成21年改正法附則において、親会社が子会社から受ける配当に関する間接外国税額控除制度や外国子会社配当益金不算入制度の適用がどのようなものとなるのか、また、子会社から親会社への配当に課された源泉所得税に関する直接外国税額控除制度や損金不算入制度の適用がどのようなものとなるのかということが問題となる。
この問題に適切な解答を出すためには、わが国の法人税法が国外で行われた行為や国外で生じた事実に対してどのように適用されることとなるのかということを正しく理解しておくことも、不可欠である。
平成21年度改正において、国外所得免除の性格を有する外国子会社配当益金不算入制度が創設され、その選択が可能となったが、わが国の法人税法は、依然として、その基本は、全世界所得課税となっている。
わが国の法人税法は、国内で得た所得も国外で得た所得も区別なく1つの所得と捉えて課税を行う仕組みとなっており、基本的には、国外の行為も国内の行為と同様に取り扱うこととしている。
上記Ⅴで述べたとおり、わが国の法人税法は、商法や会社法において用いられる用語を用いてその規定を定めることが多いが、その解釈を行い、適用することとなる規定は、あくまでもわが国の法人税法の規定であり、それがどのような内容の規定となっているのかが、まず、問題となることになる。
わが国の商法や会社法における取扱いと外国のそれらに相当する法における取扱いとを比較することは、わが国の法人税法の規定を適用するにあたって、その適用対象となる行為や事実の内容等を確認するという点では有効であっても、それ以上のものではない。
わが国の法人税法の規定を適用する限りは、その規定の解釈をどのように行うべきかということが、まず、問題となるのである。
そして、次に、現に法人が行った行為や法人に生じた事実がどのような内容のものであり、どのような性質を持ったものであるのかというようなことが、問題となる。
このようにして、わが国の法人税法の規定の解釈が明らかになり、そして、法人の行為や事実の内容等が明らかになれば、その規定の適用関係が明らかとなり、取扱いが定まることとなる。
当然のことながら、国外で行われた行為や国外で生じた事実に関しては、国内のそれらよりもその内容等を把握することが難しくならざるを得ないが、わが国の法人税法を法人の行為や事実に対して適用するという点では、国内取引等と国外取引等に本質的な違いはない。
Ⅷ.平成21年度改正法附則等の取扱い
平成21年度改正の経過措置期間においては、親会社における特定外国子会社等に該当する子会社からの配当に課された源泉所得税の直接外国税額控除制度の適用の可否については、平成21年度改正法附則12条(外国税額の控除に関する経過措置)の1項、平成21年改正措令附則27条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の6・8項の確認が必要となり、親会社が子会社から配当を受ける場合の間接外国税額控除制度と外国子会社合算税制に係る外国税額控除制度の適用の可否については、平成21年度改正法附則1条(施行期日)、12条2項、44条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)の5項後段・6項後段・2項の確認が必要となる。
しかし、紙幅の都合上、この詳細に関しては、前掲『国際的二重課税排除の制度と実務』346頁(脚注2)および378頁または本誌331号20頁に譲ることとし、ここでは、特定外国子会社等に該当する外国子会社の配当に係る「基準日」が平成21年4月1日前に開始するその子会社の事業年度(中国の子会社の場合には、平成21年12月期以前の事業年度)である場合(図表1の基準日①のような場合)には、配当に課された源泉所得税に関する直接外国税額控除制度と間接外国税額控除制度の適用が可能であり、特定外国子会社等に該当する外国子会社の配当に係る「基準日」が平成21年4月1日以後に開始するその子会社の事業年度(中国子会社の場合には、平成21年12月期の後の事業年度)である場合(図表1の基準日②のような場合)には、外国子会社配当益金不算入制度の適用が可能であり、配当に課された源泉所得税に関する直接外国税額控除制度と間接外国税額控除制度の適用はない、ということを確認するに止め、参考として、図表1・2を掲げておくこととする。
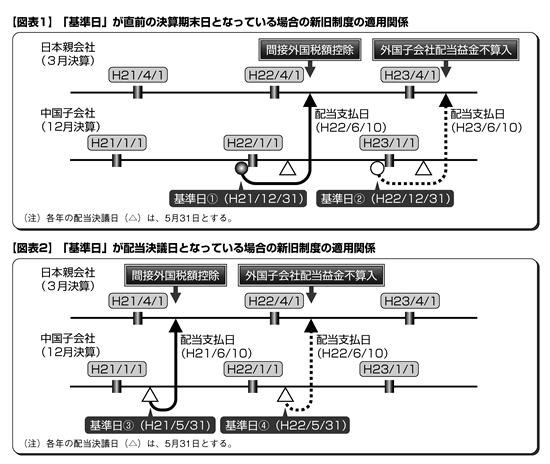 なお、外国子会社の場合には、非公開会社の場合と同様に、「基準日」を定める必要性が乏しいため、現状においては、「基準日」を定めているものは少ないものと想定されるが、上記Ⅵに記載したとおり、定款に「基準日」を定めたり、配当の都度「基準日」を設けているものは、その「基準日」を上記の制度の各規定中の「基準日」とし、「基準日」の定めがないものは、「基準日」に相当する日がいずれの日となるのかということを検討してその相当する日とした日をもって「基準日」とし、上記の制度の「基準日」を含む各規定を解釈することとなることを、ここで改めて確認しておくこととする。
なお、外国子会社の場合には、非公開会社の場合と同様に、「基準日」を定める必要性が乏しいため、現状においては、「基準日」を定めているものは少ないものと想定されるが、上記Ⅵに記載したとおり、定款に「基準日」を定めたり、配当の都度「基準日」を設けているものは、その「基準日」を上記の制度の各規定中の「基準日」とし、「基準日」の定めがないものは、「基準日」に相当する日がいずれの日となるのかということを検討してその相当する日とした日をもって「基準日」とし、上記の制度の「基準日」を含む各規定を解釈することとなることを、ここで改めて確認しておくこととする。Ⅸ.中国における企業所得税の取扱いとわが国におけるその取扱い
中国においては、企業所得税法が改正され、従来、33%であった税率が2008年分から25%に引き下げられている。
このため、現在、中国子会社は、基本的には外国子会社合算税制における特定外国子会社等に該当することとなっているが、実際には、中国子会社のほとんどが外国子会社合算税制の適用除外法人となっているものと想定される。
このような中国子会社に配当可能利益があれば、今後、わが国の親会社に対して配当を行うこととなるものと考えられるが、上記Ⅷに記載したとおり、その配当に係る「基準日」が平成21年12月31日以前であれば、間接外国税額控除制度が適用されることとなり、25%または33%で課された企業所得税はわが国の親会社の法人税から控除されることとなる。
中国の場合には、従来、優遇措置として軽減税率(15%・24%)や期間減免措置(2免3減など)があったが、企業所得税法の改正に伴い、経過措置を設け、前者のうち15%のものに関しては2012年までに段階的に税率を25%とすることとされており、後者に関しては、2008年時点で適用を受けているものについては引き続き期間満了まで措置を継続適用することができることとされている。
そして、これらの措置によって減免された企業所得税に関しては、日中租税条約23条(二重課税の排除)の4(c)により、引き続き、みなし外国税額控除の対象とすることが認められることとなる(脚注3)。
間接外国税額控除制度の適用にあたっては、このみなし外国税額控除の効果を享受できるため、みなし外国税額控除に係る部分を含むすべての税額が控除できるという場合には、外国子会社配当益金不算入制度を適用するとした場合よりも、わが国の親会社と中国子会社の税負担の合計額が有利となるケースが多いものと考えられる。
一方、中国子会社の配当に係る「基準日」が平成22年1月1日以後であれば、その配当は、外国子会社配当益金不算入制度の対象となることとなる。
この場合には、配当の95%が益金不算入となり、間接外国税額控除制度の適用を受けることはできなくなる。
Ⅹ.中国において配当に課される源泉所得税とわが国におけるその取扱い
中国においては、わが国の法人がその100%の持分を有するような中国子会社から受ける配当に対しては、従来、旧税法の優遇措置の適用を受けて源泉所得税が課されておらず、加えて、日中租税条約23条3(a)により20%の税率で源泉所得税が課されたものとみなし、20%の部分をみなし外国税額控除の適用対象とする、というように、かなりの優遇が行われていた。
企業所得税法の改正後は、上記のような配当に対しては、免税措置が適用されなくなり、企業所得税法上は原則として20%の源泉所得税の課税がなされることとなったが、実施条例の減免規定が適用されて10%の課税で済むこととなり、また、日中租税条約10条(配当)の2により限度税率も10%とされていることから、実際には、10%の源泉所得税の課税が行われることとなっている。そして、このような配当に関しては、改正後も日中租税条約23条3(a)により、20%の税率で課税が行われたものとみなし、10%の部分がみなし外国税額控除の適用対象とすることができることとなっている。
この企業所得税法の改正に際しては、経過措置が設けられており、2007年以前の利益から成る部分については、従来どおり、源泉所得税は課されないこととなっており、20%の部分をみなし外国税額控除の適用対象とすることができることとなっている(図表3参照)(脚注4)。
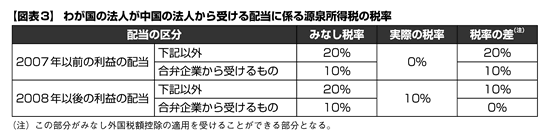 このように、中国子会社からの配当に関しては、それがいずれの時期の利益からなるものかということが非常に重要となる。
このように、中国子会社からの配当に関しては、それがいずれの時期の利益からなるものかということが非常に重要となる。わが国においては、これらの配当に課される源泉所得税に関しては、その配当に係る「基準日」が平成21年12月31日以前であれば、みなし外国税額控除を含めて直接外国税額控除制度を適用することが可能であり、その「基準日」が同日後であれば、直接外国税額控除の適用は認められないこととなる。
このように、中国子会社からの配当に課される源泉所得税に関しても、その配当に係る「基準日」がいずれの日となっているのかということにより、わが国における取扱いが異なってくることとなる。
XI.中国子会社からの配当に関する対応
上記Ⅷに記載したとおり、わが国の平成21年度改正の経過措置は、外国子会社が特定外国子会社等に該当するものに関しては、その外国子会社からの配当に係る「基準日」に基づいて適用関係を定めている。
このため、わが国の法人が中国子会社からの配当に関して平成21年度改正の経過措置を適用する場合には、それを疑義なく適用するために、中国子会社において、早期に「基準日」を明確にしておくべきであると考えられる。上記Ⅱにおいても述べたとおり、旧制度である間接外国税額控除制度と直接外国税額控除制度と新制度である外国子会社配当益金不算入制度の適用関係を誤ると、いずれの制度の適用も受けられないという極めて深刻な事態に直面せざるを得なくなってしまう。
また、上記ⅨおよびⅩに記載したとおり、中国子会社からの配当に関し、間接外国税額控除制度と直接外国税額控除制度を適用するのか、あるいは、外国子会社配当益金不算入制度を適用するのかにより、税負担が異なることとなるため(脚注5)、この点からも、「基準日」を明確にしておくべきであると考えられる。
しかしながら、わが国の法人の中国子会社においては、実際には、「基準日」を定款等に定めているというケースはほとんどないものと想定される。
このような中国子会社の状態は、わが国の非公開会社の状態と同様ということにはなるが、上記のとおり、その影響の大きさを考慮すれば、中国子会社の配当に係る「基準日」が明確でないという状態は、早期に改善する必要がある(脚注6)。
今後、中国子会社に関しては、配当に係る「基準日」を定款等に定めることと、中国における税法改正に伴う経過措置の適用関係を考慮しつつ間接外国税額控除制度および直接外国税額控除制度を適用した場合と外国子会社配当益金不算入制度を適用した場合とのメリットとデメリットを正確に把握して配当政策に役立てることが課題となると考えられる。
この前者の「基準日」の定めに関しては、後日、税務調査において疑義を持たれることのないように、中国子会社において早期に対応を行っておく方がよいと考えられる。
また、後者のメリットとデメリットの把握に関しては、前者の「基準日」にも影響を与えるものであることから、前者よりも早く対応しなければならないわけであるが、中国とわが国の双方における税法改正の経過措置を正確に理解し、過去の申告の状況等も確認したうえで行う必要があり、繰り返し慎重に検討を行ったうえで最終的な判断を下すこととした方がよい、と考えられる。
なお、その判断がどのようなものとなったとしても、中国子会社に配当可能利益がある場合にはいずれかの形で配当が行われることとなって、わが国の親会社はその配当に関する税務申告を行わなければならないこととなるのであるが、上記のメリットとデメリットはこの税務申告によって最終的に実現するわけであり、申告誤りによって期せずして大きな損失を蒙るといったことのないように、税務申告まで細心の注意を払わなければならないという点にも留意しておく必要がある。(ともなが・ひでき)
脚注
1 詳細に関しては、著者監修・編著(共監・共著)『国際的二重課税排除の制度と実務』(法令出版、2009年)378頁または本誌331号20頁を参照のこと。
2 この部分は、平成21年度改正前の事業年度で配当の受取りが確定し同改正以後の事業年度でその受取りが行われる場合の直接外国税額控除に関して説明した部分であるが、追記事項があるため、日本税制研究所のホームページ(http://www.zeiseiken.or.jp/)を合わせて確認されたい。
3 「日中租税条約に規定する「みなし外国税額控除」の適用継続について」(財務省、2008年3月26日)において、日中租税条約に規定する中国の経済開発奨励措置に関するみなし外国税額控除が中国の国内法改正後も引き続き適用されることが確認されている。
ただし、中国の新税法において新たに措置された優遇税制によって減額される税額に関しては、日中租税条約のみなし外国税額控除の対象とする旨の交換公文等が新たに締結されるということにならない限り、その適用を受けることはできない。
4 中国子会社が合弁企業である場合には、従来は、旧税法の優遇措置の適用を受けて源泉所得税が課されておらず、日中租税条約23条3(a)により10%の税率で源泉所得税が課されたものとみなして10%の部分をみなし外国税額控除の適用対象とすることができたが、企業所得税法の改正後は、免税措置が適用されなくなり、10%の税率で源泉所得税が課税され、みなし外国税額控除の適用を受けることができる部分はなくなっている。
また、2007年以前の利益からなる部分については、経過措置により10%の部分をみなし外国税額控除の適用対象とすることができることとなっている。
5 中国子会社に関しては、特に、間接外国税額控除制度および直接外国税額控除制度の双方におけるみなし外国税額控除が税負担額の引下げに資することとなっている。
わが国の親会社において、このみなし外国税額控除に係る部分を含むすべての税額が控除できることとなるのか否かは、親会社の所得・税額の発生状況や外国税額控除の申告をどのように行っているのかによることとなるため、一概に有利不利の結論を出すことはできないが、このみなし外国税額控除に係る部分を含むすべての税額が控除できるという状態であるとすれば、基本的には旧制度の方が有利と考えてよい。
このため、中国子会社に関しては、平成21年12月31日以前を「基準日」として配当を行いたいというニーズが確実に存在するものと考えられる。
このような点からも明らかなように、「基準日」を定める場合には、中国とわが国の双方の改正の経過措置も十分に勘案して行う方がよいと考えられる。
6 著者が聞く限り、中国の法制上、わが国の会社法における「基準日」と同様のものを定めることは求められていないとのことであるが、中国においても、会社がわが国の会社法における「基準日」と同様のものを定めることを妨げる事情は存在しない。中国においても、わが国と同様に、会社が配当を行う場合にその対象となる株主をいつの時点の株主とするかということを定款等に定めることは、むしろ奨励されてしかるべきである、と考えられる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























