解説記事2010年08月30日 【新会計基準解説】 企業会計基準公開草案第43号「公正価値測定及びその開示に関する会計基準(案)」等について(2010年8月30日号・№368)
新会計基準解説
企業会計基準公開草案第43号「公正価値測定及びその開示に関する会計基準(案)」等について
企業会計基準委員会 専門研究員 丸岡 健
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2010年7月9日に、企業会計基準公開草案第43号「公正価値測定及びその開示に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第38号「公正価値測定及びその開示に関する会計基準の適用指針(案)」(両案を合わせて、以下「本公開草案」という。)を公表し、9月10日までコメントを募集している(脚注1)。
本稿では本公開草案の概要について解説するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅱ.本公開草案の公表の経緯
公正価値測定に関するプロジェクトは、2006年2月に合意された国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)との覚書(MoU)項目の1つである。ASBJでは、本プロジェクトを「IASB/FASBのMoUに関連するプロジェクト項目(中長期)(脚注2)」として位置付けている。2009年5月にIASBから公開草案「公正価値測定」(以下「IASBのED」という。)が公表されたことを踏まえ、同年8月にASBJは論点整理を公表している。本公開草案は、当該論点整理に関して寄せられたコメントやIASBのEDに関して寄せられたコメントに対するIASB/FASBの合同での審議(特に2010年1Q)の内容を踏まえて公表したものである。
なお、本プロジェクトは金融危機を契機としたものではないものの、国際的な会計基準では、図表1のとおり、金融危機を踏まえた対応が行われており、ASBJの本公開草案もその内容を反映している。
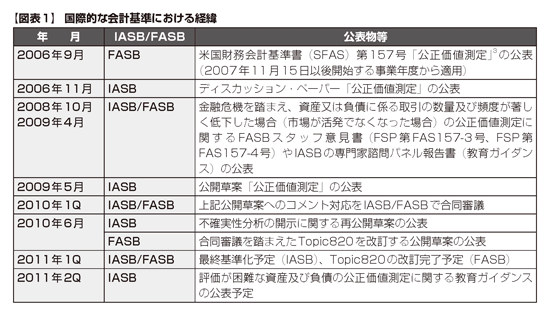
Ⅲ.本公開草案の内容
1.本公開草案の目的及び適用範囲等 本公開草案は、公正価値の考え方及び公正価値に関する開示の内容を定めることを目的としている。公正価値で測定する資産又は負債の範囲など個別の会計基準等で定められている会計処理等の見直しについて取り扱うものではない。
公正価値に関する会計処理等について適用する(脚注4)ため、金融商品だけでなく、非金融商品も対象となる。ただし、通常の販売目的で保有する棚卸資産やストック・オプションについては、コンバージェンスの観点から適用の対象外としている。その結果、非金融商品に関する会計処理等としては、賃貸等不動産の時価開示、トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価、固定資産の減損に係る会計基準における正味売却価額(時価から処分費用見込み額を控除したもの)、企業結合における時価を基礎とした取得原価の配分などが本公開草案の対象(脚注5)となると考えられる。
公正価値測定に関する基準を開発することに伴い、金融商品会計に関する実務指針などの既存の会計基準等の取扱いが問題となる。これについて、本公開草案に示した公正価値の考え方と不整合とならない限り、それらの定めを基本的に残すこととし、改訂等は必要最低限のものとする予定としている。なお、検討の過程では、その他有価証券の決算時の時価として、期末前1カ月の月中平均を用いることができる点について、見直しが必要ではないかとの意見があった。
2.公正価値の概念
(1)公正価値の定義 本公開草案では、公正価値の定義を、測定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われた場合に、資産の売却によって受け取るであろう価格又は負債の移転のために支払うであろう価格(出口価格)としている。一方、我が国における時価の定義は、例えば金融商品の場合、時価とは、公正な評価額であり、取引を実行するために必要な知識をもつ自発的な独立第三者の当事者が取引を行うと想定した場合の取引価額であるとされている。これについて、本公開草案の結論の背景では、「時価」と「公正価値」の会計基準上の考え方に大きな差異はないと考えられるとしている。
公正価値の定義を構成する特徴は図表2の7点と考えられる。
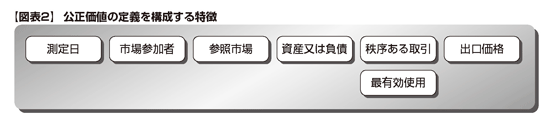 本公開草案では、市場参加者の要件や、秩序ある取引ではないことを示す状況の例示、公正価値を算定する際の参照市場、最有効使用(脚注6)などについて具体的な記述がなされている。このうち、公正価値の概念において特に重要な点は、それが市場参加者の観点に基づく評価であるということであると考えられる。また、参照市場の考え方は、2009年8月公表の論点整理から変更されている。ここではこの2点を詳述する。
本公開草案では、市場参加者の要件や、秩序ある取引ではないことを示す状況の例示、公正価値を算定する際の参照市場、最有効使用(脚注6)などについて具体的な記述がなされている。このうち、公正価値の概念において特に重要な点は、それが市場参加者の観点に基づく評価であるということであると考えられる。また、参照市場の考え方は、2009年8月公表の論点整理から変更されている。ここではこの2点を詳述する。
(2)市場参加者の観点 本公開草案では、まず、市場参加者を「互いに独立している」「すべての入手できる情報に基づき、資産又は負債並びに取引について合理的な理解を有している」「取引を行う能力がある」及び「自発的に取引を行う意思がある」の4条件すべてを満たす市場における買手及び売手と定義している。この市場参加者の定義は、従来の我が国における時価の定義で想定されている「取引を実行するために必要な知識をもつ自発的な独立第三者」と概念において大きな差はないとしている。
その上で、公正価値は、市場における価値であり、企業にとっての固有の価値ではないため、公正価値を算定するにあたっては、市場参加者が資産又は負債を価格設定する際に用いるであろう仮定を用いるとしている。このため、たとえ観察可能な取引が存在しない場合であっても、算定の対象となる資産又は負債、参照市場などを考慮して、市場参加者を特徴づける要素を識別した上で、公正価値を算定しなければならないとしている。
また、市場参加者が資産又は負債に固有の要素を考慮する場合は、公正価値を算定するにあたって、当該要素を考慮するとしている。例えば、市場参加者が考慮するであろう資産の売却に関する制限などは考慮する。一方、取引費用や大量保有要因による流動性コストの調整は、企業に固有のものであると考えられるため、そのような調整を禁止してる。の点に関し、大量保有要因による調整は明示的に禁止されていないため、実務において調整を行っているケースがあれば、本公開草案を適用するにあたっては、そのような調整は認められないことに留意する必要がある。
なお、大量保有要因による調整の禁止による影響額は、本公開草案の適用に伴って生じる会計方針の変更の影響額となるが、過去の期間の財務諸表に対する遡及処理は行わないため、期首の利益剰余金を加減することとなる。
(3)参照市場 本公開草案では、資産を売却する又は負債を移転する取引は、企業が利用できる主要な市場で行われると仮定するとしている。ただし、主要な市場が存在しない場合には、企業が利用できる最も有利な市場で行われると仮定するとしている。ここに、主要な市場とは「資産又は負債についての取引の数量及び頻度が最大の市場」を、最も有利な市場とは「取引費用及び輸送費用を考慮した上で、資産の売却による受取額を最大化又は負債の移転に対する支払額を最小化する市場」を言うとしている。
ASBJが論点整理を公表した時点では、国際的な会計基準では参照市場の考え方が分かれていた。すなわち、IASBのEDは「最も有利な市場アプローチ」(参照すべき市場は最も有利な市場。ただし、他に最も有利な市場が存在するという証拠がない限り、主要な市場を最も有利な市場とみなすことができる。)を採用し、一方、FASBのTopic820は「主要な市場アプローチ」(参照順番がIASBと逆)を採用していた。ASBJの論点整理は、IASBのEDと同様の最も有利な市場アプローチを提案したとしている。
しかし、最も有利な市場が存在するという証拠の有無を検討することは困難であるとの指摘や監査可能性などの観点から、最も有利な市場アプローチを支持する意見は少なかった。また、IASBがFASBと共同で検討を進めた結果、最終的には主要な市場アプローチを採用することとなった。これらの理由から、本公開草案は、主要な市場アプローチを取り入れることとしたとしている。なお、我が国では、1つの金融資産が複数の取引所に上場されている場合には、当該金融資産の取引が最も活発に行われている取引所の取引価格を用いるものとされており、主要な市場アプローチはこの取扱いとも整合的であると考えられるとしている。
3.公正価値の算定方法
(1)評価技法 公正価値を算定するための評価技法は、図表3のとおり「マーケットアプローチ」「インカムアプローチ」「コストアプローチ」に要約されるとしている。
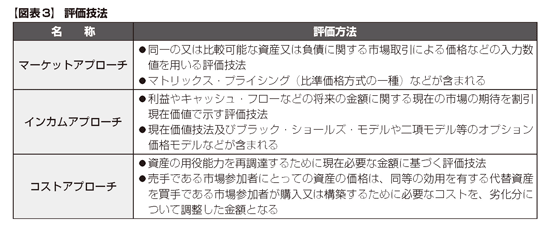
(2)レベル別の分類 公正価値を算定するにあたっては、状況に応じた、十分なデータが入手できる適切な評価技法を併用又は選択して用いなければならないとしている。また、評価技法に用いられる入力数値(脚注7)は、観察可能な入力数値を最大限利用し、観察不能な入力数値の利用を最小限にしなければならないとしている。さらに、図表4のとおり3つのレベルに分類の上、レベル1からレベル3の順に優先順位付けを行い、公正価値の算定を行うとしている。
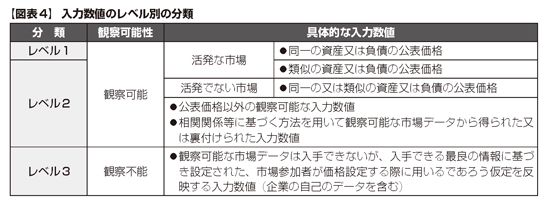
実務負担の軽減や判断基準の統一を図るため、より詳細なレベル別の分類のガイダンスとして、図表5のとおりレベル2及びレベル3の入力数値の具体例が示されている。
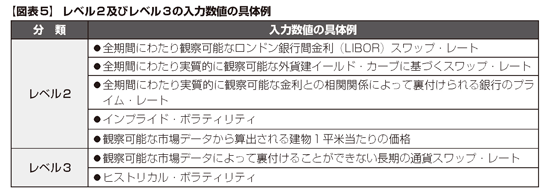
算定された公正価値は、その算定において重要な影響を与える入力数値が属するレベルに応じて、図表6のとおり3つのレベルに分類することとしている。また、評価技法に複数のレベルの入力数値が用いられた場合は、その算定に重要な影響を与える入力数値が属する最も低いレベルに分類するとしている。このため、株式や国債、社債、デリバティブといった資産又は負債の種類により形式的に分類するのではなく、公正価値を算定するにあたってどのレベルの入力数値が用いられているかを各資産又は負債ごとに確認する必要がある。このようなレベル別の分類は、公正価値の算定の首尾一貫性や比較可能性を高め、財務諸表の利用者に有用な情報をもたらすと考えられることから、コンバージェンスの観点も踏まえ、導入されたものである。
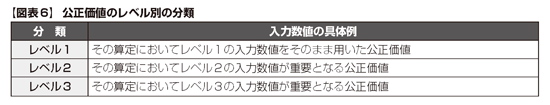
なお、分類の結果レベル3の公正価値とされたものは、レベル1よりも企業による見積り要素が強く、算定結果の不確実性が高いと考えられるため、それを補うためにレベル3の公正価値についてはより詳細な開示を求めている。
(3)資産又は負債の取引の数量及び頻度が著しく低下している場合及び秩序ある取引ではないと判断された場合における公正価値の算定 資産又は負債の取引の数量及び頻度が著しく低下しているか否かについては、入手できる情報に基づいて適切に判断する必要があるとしている。資産又は負債の取引の数量及び頻度が著しく低下していることを示す状況が図表7のとおり例示されている。
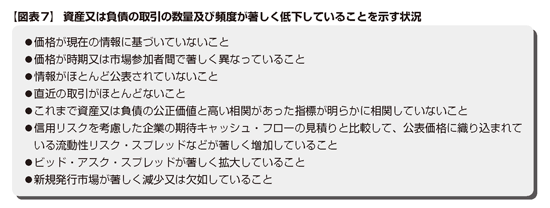
一方、秩序ある取引は、不利な条件で引き受けざるを得ない取引又は他から強制された取引ではなく、通常かつ慣習的なマーケティング活動ができるように、測定日以前の一定期間、市場にさらされていることを前提とした取引と定義されている。取引が市場参加者間の秩序ある取引であるか否かについては、入手できる情報に基づいて適切に判断する必要があるとしている。秩序ある取引ではないことを示す状況が図表8のとおり例示されている。
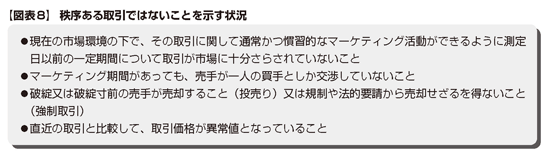
資産又は負債の取引の数量及び頻度が著しく低下していると判断された場合(かつ、秩序ある取引ではないと判断されない場合)は、取引価格はそのまま公正価値として用いることができない場合があり、さらなる分析の上、重要な調整が必要になることがあるとしている。そして、重要な調整を行う場合は、キャッシュ・フローの金額や時期の変動の可能性などに関して市場参加者が行うであろう適切なリスク調整(信用リスクや流動性リスクなどの調整)を行うとしている。検討の過程では、この調整を行った場合、我が国における合理的に算定された価額と実務上差異が生じる可能性があるとの指摘があった。これについて、本公開草案の結論の背景では、当該調整は、経営者による主観的又は保守的な判断によるものではなく、経営者が市場参加者に代わって適切な調整を行うものであり、合理的な金額を算定するという点で、考え方において両者に差異はないと考えられるとしている。
一方、取引が秩序ある取引ではないと判断された場合は、公正価値を算定するにあたって、当該取引価格を通常考慮してはならないとしている。
資産又は負債の取引の数量及び頻度が著しく低下している場合と秩序ある取引ではない場合の関係について、本公開草案では、前者と判断された場合であっても、当該市場におけるすべての取引が秩序ある取引ではないと結論付けるのは適切ではないとしている。検討の過程では、流動性リスクが大きい場合や、逆に市場が一時的に急騰した場合には、取引価格が資産が本来生み出すキャッシュ・フローを表さないので、当該取引価格を考慮すべきではないとの指摘があった。これについて、本公開草案の結論の背景では、そのような場合であっても、取引価格が秩序ある取引ではないと判断されない限り、当該取引価格を合理的に考慮することとなると考えられるとしている。
(4)ブローカー等の価格の利用 ブローカーや情報ベンダーなどから提供された価格を用いることができるが、この際、それがどのように算定されたのかを理解し、公正価値の定義を満たしているか否かを評価する必要があるとしている。ブローカー等から入手した価格について、これまでも自らの責任で使用し、必要に応じて時価としての妥当性の判断も行うこととされており、本公開草案によりその考え方が変わるものではない。しかし、実務においては、価格そのものの妥当性よりは、価格を算定したブローカーの信頼性や客観性を重視する傾向があるとの指摘があるため、実務の見直しが必要となる場合があると考えられる。
4.公正価値に関する注記事項 公正価値を毎期継続して貸借対照表価額としている資産及び負債(金融商品の一部及びトレーディング目的で保有する棚卸資産が該当)の公正価値に関して、図表9に記載されている事項を注記することを求めている。
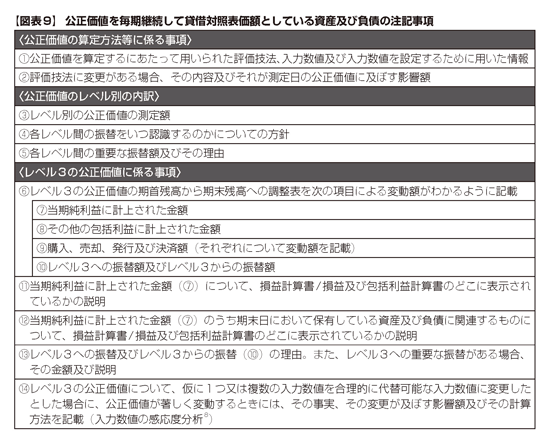
また、公正価値を毎期継続して注記している資産及び負債(金融商品(毎期継続して貸借対照表価額としているものを除く)及び賃貸等不動産)の公正価値に関して、図表9のうちレベル別の公正価値の測定額(③)を注記することを求めている。
ただし、重要性が乏しいものは注記を省略することができるとしており、また、連結財務諸表において注記している場合には、個別財務諸表において記載することを要しないとしている。
5.適用時期 本公開草案では、企業の受入準備等を考慮して、平成24年4月1日以後開始する事業年度から適用することを原則としている(早期適用可)。例えば、原則適用の場合、平成24年4月1日に事業年度を開始する企業においては、公正価値測定の考え方をその期首から適用することとなるが、本公開草案が定める新たな注記事項については、同事業年度の年度末(平成25年3月31日)に係る財務諸表から開示することとなる。
Ⅳ.IASB、FASBから最近公表された公開草案について
6月29日に、IASBから再公開草案「公正価値測定に関する測定の不確実性分析(脚注9)の開示」が公表され、FASBからは、Topic820を改訂する公開草案が公表されている(いずれもコメント締切は9月7日)。
IASBの再公開草案は、IASBのEDにおいて求められていたレベル3の公正価値に関する測定の不確実性分析の開示(前掲の図表9の⑭)に関する限定的なものである。EDは、仮に入力数値を合理的に用いることのできる別の数値に変更するならば、公正価値が著しく変動するであろう場合には、その公正価値の影響額を開示することを求めた。今回の再公開草案では、その公正価値の影響額を計算するにあたって、観察不能な入力数値どうしの相関により公正価値が影響を受ける場合は、その相関の影響を考慮して計算しなければならないという計算上の留意点が追加されている。
また、FASBの公開草案は、IASB/FASBが2010年1Qに合同で審議したIASBのEDに対するコメント対応及びその他のIASBのEDとFASBのTopic820との差異について、その審議の結果をTopic820に反映するために公開草案としてまとめたものである(IASBは、同FASBの公開草案に対するコメントを合同で審議し、最終基準に反映する予定)。ASBJの本公開草案は、IASB/FASBの2010年1Qの審議の内容を概ね反映しているため、当該FASBの公開草案の公表に伴う修正は行っていない。
Ⅴ.今後の予定
引き続き、IASB/FASBの動向を踏まえ対応することとなると考えられるが、前掲の図表1に記載のとおり、IASBにおける本プロジェクトの最終基準化は2011年1Qとなっているため、本公開草案の最終基準化は2011年度上半期となるものと考えられる。
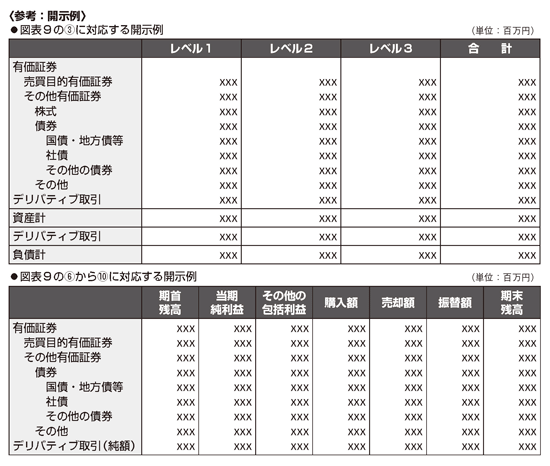
脚注
1 本公開草案の本文については、次のASBJウェブサイトを参照。https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/kouseikachi/ 2 当該中長期項目は、2007年8月にASBJがIASBと共同で公表した「東京合意」において定義された項目。2011年6月30日後に適用となる新たな基準を開発する現在のIASBの主要なプロジェクトにおける差異に係る分野であり、新たな基準が適用となる際に日本において国際的なアプローチが受け入れられるように、緊密に作業を行うこととされているものである。
3 現在は、FASB Accounting Standards CodificationTM(FASB-ASC)のTopic820「公正価値測定及び開示」に含まれている。
4 この際、基本的に「公正価値」という用語への置換えは行わず、「時価」を「公正価値」と読み替えてこれを適用することとしている。
5 この他、退職給付の年金資産の時価についても本公開草案の考え方が適用される。ただし、年金資産の時価に関するレベル別の開示については、ASBJにおける退職給付に関する会計基準の検討状況も踏まえ、本公開草案では求めていない。
6 最有効使用の概念は、複数の代替的な使用が行われる可能性がある不動産などの非金融資産に適用されるが、金融資産には適用せず、負債にも適用しないとしている。
7 入力数値(インプット)とは、市場参加者が資産又は負債を価格設定する際に用いるであろう仮定のことを幅広く指し、イールドカーブ、インプライド・ボラティリティ、信用リスクなどが含まれる。
8 2009年のIASBのEDで「感応度分析」との表現が用いられていたので、本公開草案でも「感応度分析」と表現している。2010年のIASBの再公開草案では「不確実性分析」という表現に変更されている。
9 脚注8参照。
企業会計基準公開草案第43号「公正価値測定及びその開示に関する会計基準(案)」等について
企業会計基準委員会 専門研究員 丸岡 健
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2010年7月9日に、企業会計基準公開草案第43号「公正価値測定及びその開示に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第38号「公正価値測定及びその開示に関する会計基準の適用指針(案)」(両案を合わせて、以下「本公開草案」という。)を公表し、9月10日までコメントを募集している(脚注1)。
本稿では本公開草案の概要について解説するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅱ.本公開草案の公表の経緯
公正価値測定に関するプロジェクトは、2006年2月に合意された国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)との覚書(MoU)項目の1つである。ASBJでは、本プロジェクトを「IASB/FASBのMoUに関連するプロジェクト項目(中長期)(脚注2)」として位置付けている。2009年5月にIASBから公開草案「公正価値測定」(以下「IASBのED」という。)が公表されたことを踏まえ、同年8月にASBJは論点整理を公表している。本公開草案は、当該論点整理に関して寄せられたコメントやIASBのEDに関して寄せられたコメントに対するIASB/FASBの合同での審議(特に2010年1Q)の内容を踏まえて公表したものである。
なお、本プロジェクトは金融危機を契機としたものではないものの、国際的な会計基準では、図表1のとおり、金融危機を踏まえた対応が行われており、ASBJの本公開草案もその内容を反映している。
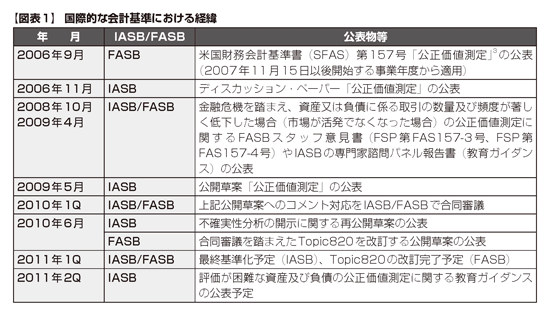
Ⅲ.本公開草案の内容
1.本公開草案の目的及び適用範囲等 本公開草案は、公正価値の考え方及び公正価値に関する開示の内容を定めることを目的としている。公正価値で測定する資産又は負債の範囲など個別の会計基準等で定められている会計処理等の見直しについて取り扱うものではない。
公正価値に関する会計処理等について適用する(脚注4)ため、金融商品だけでなく、非金融商品も対象となる。ただし、通常の販売目的で保有する棚卸資産やストック・オプションについては、コンバージェンスの観点から適用の対象外としている。その結果、非金融商品に関する会計処理等としては、賃貸等不動産の時価開示、トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価、固定資産の減損に係る会計基準における正味売却価額(時価から処分費用見込み額を控除したもの)、企業結合における時価を基礎とした取得原価の配分などが本公開草案の対象(脚注5)となると考えられる。
公正価値測定に関する基準を開発することに伴い、金融商品会計に関する実務指針などの既存の会計基準等の取扱いが問題となる。これについて、本公開草案に示した公正価値の考え方と不整合とならない限り、それらの定めを基本的に残すこととし、改訂等は必要最低限のものとする予定としている。なお、検討の過程では、その他有価証券の決算時の時価として、期末前1カ月の月中平均を用いることができる点について、見直しが必要ではないかとの意見があった。
2.公正価値の概念
(1)公正価値の定義 本公開草案では、公正価値の定義を、測定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われた場合に、資産の売却によって受け取るであろう価格又は負債の移転のために支払うであろう価格(出口価格)としている。一方、我が国における時価の定義は、例えば金融商品の場合、時価とは、公正な評価額であり、取引を実行するために必要な知識をもつ自発的な独立第三者の当事者が取引を行うと想定した場合の取引価額であるとされている。これについて、本公開草案の結論の背景では、「時価」と「公正価値」の会計基準上の考え方に大きな差異はないと考えられるとしている。
公正価値の定義を構成する特徴は図表2の7点と考えられる。
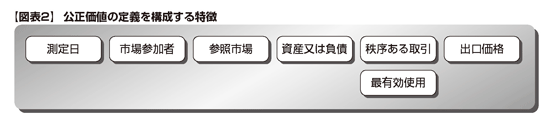 本公開草案では、市場参加者の要件や、秩序ある取引ではないことを示す状況の例示、公正価値を算定する際の参照市場、最有効使用(脚注6)などについて具体的な記述がなされている。このうち、公正価値の概念において特に重要な点は、それが市場参加者の観点に基づく評価であるということであると考えられる。また、参照市場の考え方は、2009年8月公表の論点整理から変更されている。ここではこの2点を詳述する。
本公開草案では、市場参加者の要件や、秩序ある取引ではないことを示す状況の例示、公正価値を算定する際の参照市場、最有効使用(脚注6)などについて具体的な記述がなされている。このうち、公正価値の概念において特に重要な点は、それが市場参加者の観点に基づく評価であるということであると考えられる。また、参照市場の考え方は、2009年8月公表の論点整理から変更されている。ここではこの2点を詳述する。(2)市場参加者の観点 本公開草案では、まず、市場参加者を「互いに独立している」「すべての入手できる情報に基づき、資産又は負債並びに取引について合理的な理解を有している」「取引を行う能力がある」及び「自発的に取引を行う意思がある」の4条件すべてを満たす市場における買手及び売手と定義している。この市場参加者の定義は、従来の我が国における時価の定義で想定されている「取引を実行するために必要な知識をもつ自発的な独立第三者」と概念において大きな差はないとしている。
その上で、公正価値は、市場における価値であり、企業にとっての固有の価値ではないため、公正価値を算定するにあたっては、市場参加者が資産又は負債を価格設定する際に用いるであろう仮定を用いるとしている。このため、たとえ観察可能な取引が存在しない場合であっても、算定の対象となる資産又は負債、参照市場などを考慮して、市場参加者を特徴づける要素を識別した上で、公正価値を算定しなければならないとしている。
また、市場参加者が資産又は負債に固有の要素を考慮する場合は、公正価値を算定するにあたって、当該要素を考慮するとしている。例えば、市場参加者が考慮するであろう資産の売却に関する制限などは考慮する。一方、取引費用や大量保有要因による流動性コストの調整は、企業に固有のものであると考えられるため、そのような調整を禁止してる。の点に関し、大量保有要因による調整は明示的に禁止されていないため、実務において調整を行っているケースがあれば、本公開草案を適用するにあたっては、そのような調整は認められないことに留意する必要がある。
なお、大量保有要因による調整の禁止による影響額は、本公開草案の適用に伴って生じる会計方針の変更の影響額となるが、過去の期間の財務諸表に対する遡及処理は行わないため、期首の利益剰余金を加減することとなる。
(3)参照市場 本公開草案では、資産を売却する又は負債を移転する取引は、企業が利用できる主要な市場で行われると仮定するとしている。ただし、主要な市場が存在しない場合には、企業が利用できる最も有利な市場で行われると仮定するとしている。ここに、主要な市場とは「資産又は負債についての取引の数量及び頻度が最大の市場」を、最も有利な市場とは「取引費用及び輸送費用を考慮した上で、資産の売却による受取額を最大化又は負債の移転に対する支払額を最小化する市場」を言うとしている。
ASBJが論点整理を公表した時点では、国際的な会計基準では参照市場の考え方が分かれていた。すなわち、IASBのEDは「最も有利な市場アプローチ」(参照すべき市場は最も有利な市場。ただし、他に最も有利な市場が存在するという証拠がない限り、主要な市場を最も有利な市場とみなすことができる。)を採用し、一方、FASBのTopic820は「主要な市場アプローチ」(参照順番がIASBと逆)を採用していた。ASBJの論点整理は、IASBのEDと同様の最も有利な市場アプローチを提案したとしている。
しかし、最も有利な市場が存在するという証拠の有無を検討することは困難であるとの指摘や監査可能性などの観点から、最も有利な市場アプローチを支持する意見は少なかった。また、IASBがFASBと共同で検討を進めた結果、最終的には主要な市場アプローチを採用することとなった。これらの理由から、本公開草案は、主要な市場アプローチを取り入れることとしたとしている。なお、我が国では、1つの金融資産が複数の取引所に上場されている場合には、当該金融資産の取引が最も活発に行われている取引所の取引価格を用いるものとされており、主要な市場アプローチはこの取扱いとも整合的であると考えられるとしている。
3.公正価値の算定方法
(1)評価技法 公正価値を算定するための評価技法は、図表3のとおり「マーケットアプローチ」「インカムアプローチ」「コストアプローチ」に要約されるとしている。
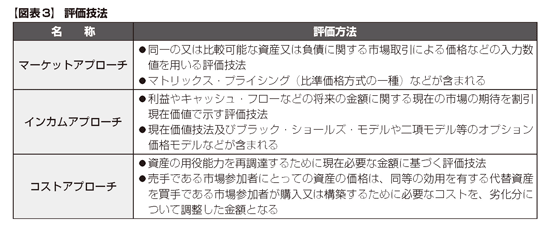
(2)レベル別の分類 公正価値を算定するにあたっては、状況に応じた、十分なデータが入手できる適切な評価技法を併用又は選択して用いなければならないとしている。また、評価技法に用いられる入力数値(脚注7)は、観察可能な入力数値を最大限利用し、観察不能な入力数値の利用を最小限にしなければならないとしている。さらに、図表4のとおり3つのレベルに分類の上、レベル1からレベル3の順に優先順位付けを行い、公正価値の算定を行うとしている。
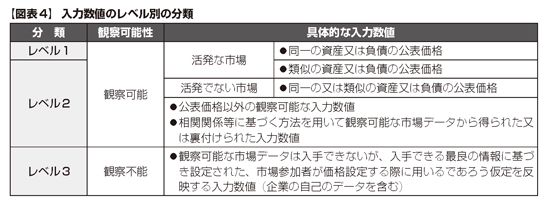
実務負担の軽減や判断基準の統一を図るため、より詳細なレベル別の分類のガイダンスとして、図表5のとおりレベル2及びレベル3の入力数値の具体例が示されている。
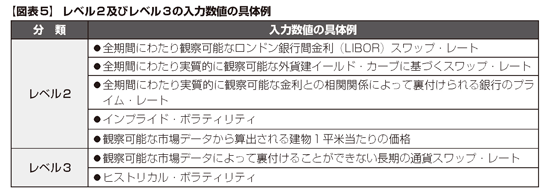
算定された公正価値は、その算定において重要な影響を与える入力数値が属するレベルに応じて、図表6のとおり3つのレベルに分類することとしている。また、評価技法に複数のレベルの入力数値が用いられた場合は、その算定に重要な影響を与える入力数値が属する最も低いレベルに分類するとしている。このため、株式や国債、社債、デリバティブといった資産又は負債の種類により形式的に分類するのではなく、公正価値を算定するにあたってどのレベルの入力数値が用いられているかを各資産又は負債ごとに確認する必要がある。このようなレベル別の分類は、公正価値の算定の首尾一貫性や比較可能性を高め、財務諸表の利用者に有用な情報をもたらすと考えられることから、コンバージェンスの観点も踏まえ、導入されたものである。
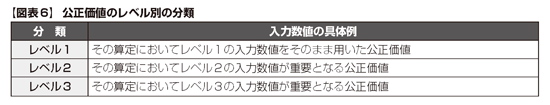
なお、分類の結果レベル3の公正価値とされたものは、レベル1よりも企業による見積り要素が強く、算定結果の不確実性が高いと考えられるため、それを補うためにレベル3の公正価値についてはより詳細な開示を求めている。
(3)資産又は負債の取引の数量及び頻度が著しく低下している場合及び秩序ある取引ではないと判断された場合における公正価値の算定 資産又は負債の取引の数量及び頻度が著しく低下しているか否かについては、入手できる情報に基づいて適切に判断する必要があるとしている。資産又は負債の取引の数量及び頻度が著しく低下していることを示す状況が図表7のとおり例示されている。
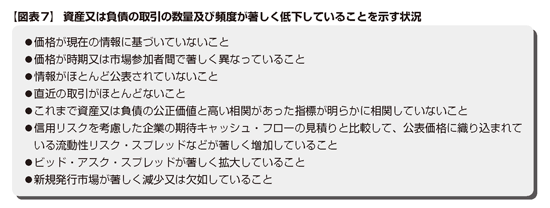
一方、秩序ある取引は、不利な条件で引き受けざるを得ない取引又は他から強制された取引ではなく、通常かつ慣習的なマーケティング活動ができるように、測定日以前の一定期間、市場にさらされていることを前提とした取引と定義されている。取引が市場参加者間の秩序ある取引であるか否かについては、入手できる情報に基づいて適切に判断する必要があるとしている。秩序ある取引ではないことを示す状況が図表8のとおり例示されている。
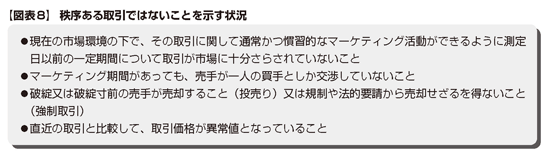
資産又は負債の取引の数量及び頻度が著しく低下していると判断された場合(かつ、秩序ある取引ではないと判断されない場合)は、取引価格はそのまま公正価値として用いることができない場合があり、さらなる分析の上、重要な調整が必要になることがあるとしている。そして、重要な調整を行う場合は、キャッシュ・フローの金額や時期の変動の可能性などに関して市場参加者が行うであろう適切なリスク調整(信用リスクや流動性リスクなどの調整)を行うとしている。検討の過程では、この調整を行った場合、我が国における合理的に算定された価額と実務上差異が生じる可能性があるとの指摘があった。これについて、本公開草案の結論の背景では、当該調整は、経営者による主観的又は保守的な判断によるものではなく、経営者が市場参加者に代わって適切な調整を行うものであり、合理的な金額を算定するという点で、考え方において両者に差異はないと考えられるとしている。
一方、取引が秩序ある取引ではないと判断された場合は、公正価値を算定するにあたって、当該取引価格を通常考慮してはならないとしている。
資産又は負債の取引の数量及び頻度が著しく低下している場合と秩序ある取引ではない場合の関係について、本公開草案では、前者と判断された場合であっても、当該市場におけるすべての取引が秩序ある取引ではないと結論付けるのは適切ではないとしている。検討の過程では、流動性リスクが大きい場合や、逆に市場が一時的に急騰した場合には、取引価格が資産が本来生み出すキャッシュ・フローを表さないので、当該取引価格を考慮すべきではないとの指摘があった。これについて、本公開草案の結論の背景では、そのような場合であっても、取引価格が秩序ある取引ではないと判断されない限り、当該取引価格を合理的に考慮することとなると考えられるとしている。
(4)ブローカー等の価格の利用 ブローカーや情報ベンダーなどから提供された価格を用いることができるが、この際、それがどのように算定されたのかを理解し、公正価値の定義を満たしているか否かを評価する必要があるとしている。ブローカー等から入手した価格について、これまでも自らの責任で使用し、必要に応じて時価としての妥当性の判断も行うこととされており、本公開草案によりその考え方が変わるものではない。しかし、実務においては、価格そのものの妥当性よりは、価格を算定したブローカーの信頼性や客観性を重視する傾向があるとの指摘があるため、実務の見直しが必要となる場合があると考えられる。
4.公正価値に関する注記事項 公正価値を毎期継続して貸借対照表価額としている資産及び負債(金融商品の一部及びトレーディング目的で保有する棚卸資産が該当)の公正価値に関して、図表9に記載されている事項を注記することを求めている。
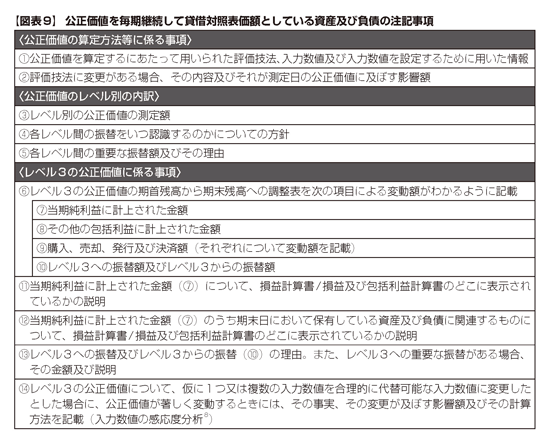
また、公正価値を毎期継続して注記している資産及び負債(金融商品(毎期継続して貸借対照表価額としているものを除く)及び賃貸等不動産)の公正価値に関して、図表9のうちレベル別の公正価値の測定額(③)を注記することを求めている。
ただし、重要性が乏しいものは注記を省略することができるとしており、また、連結財務諸表において注記している場合には、個別財務諸表において記載することを要しないとしている。
5.適用時期 本公開草案では、企業の受入準備等を考慮して、平成24年4月1日以後開始する事業年度から適用することを原則としている(早期適用可)。例えば、原則適用の場合、平成24年4月1日に事業年度を開始する企業においては、公正価値測定の考え方をその期首から適用することとなるが、本公開草案が定める新たな注記事項については、同事業年度の年度末(平成25年3月31日)に係る財務諸表から開示することとなる。
Ⅳ.IASB、FASBから最近公表された公開草案について
6月29日に、IASBから再公開草案「公正価値測定に関する測定の不確実性分析(脚注9)の開示」が公表され、FASBからは、Topic820を改訂する公開草案が公表されている(いずれもコメント締切は9月7日)。
IASBの再公開草案は、IASBのEDにおいて求められていたレベル3の公正価値に関する測定の不確実性分析の開示(前掲の図表9の⑭)に関する限定的なものである。EDは、仮に入力数値を合理的に用いることのできる別の数値に変更するならば、公正価値が著しく変動するであろう場合には、その公正価値の影響額を開示することを求めた。今回の再公開草案では、その公正価値の影響額を計算するにあたって、観察不能な入力数値どうしの相関により公正価値が影響を受ける場合は、その相関の影響を考慮して計算しなければならないという計算上の留意点が追加されている。
また、FASBの公開草案は、IASB/FASBが2010年1Qに合同で審議したIASBのEDに対するコメント対応及びその他のIASBのEDとFASBのTopic820との差異について、その審議の結果をTopic820に反映するために公開草案としてまとめたものである(IASBは、同FASBの公開草案に対するコメントを合同で審議し、最終基準に反映する予定)。ASBJの本公開草案は、IASB/FASBの2010年1Qの審議の内容を概ね反映しているため、当該FASBの公開草案の公表に伴う修正は行っていない。
Ⅴ.今後の予定
引き続き、IASB/FASBの動向を踏まえ対応することとなると考えられるが、前掲の図表1に記載のとおり、IASBにおける本プロジェクトの最終基準化は2011年1Qとなっているため、本公開草案の最終基準化は2011年度上半期となるものと考えられる。
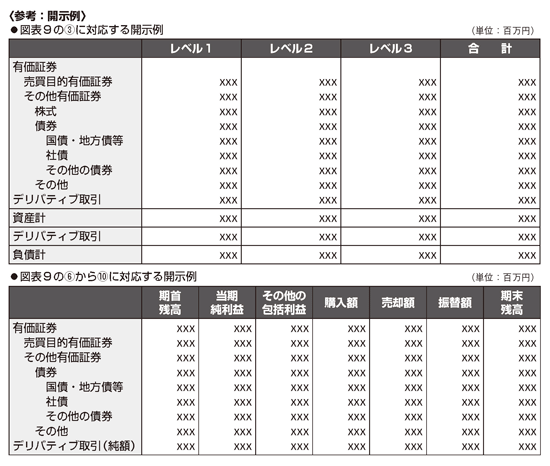
脚注
1 本公開草案の本文については、次のASBJウェブサイトを参照。https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/kouseikachi/ 2 当該中長期項目は、2007年8月にASBJがIASBと共同で公表した「東京合意」において定義された項目。2011年6月30日後に適用となる新たな基準を開発する現在のIASBの主要なプロジェクトにおける差異に係る分野であり、新たな基準が適用となる際に日本において国際的なアプローチが受け入れられるように、緊密に作業を行うこととされているものである。
3 現在は、FASB Accounting Standards CodificationTM(FASB-ASC)のTopic820「公正価値測定及び開示」に含まれている。
4 この際、基本的に「公正価値」という用語への置換えは行わず、「時価」を「公正価値」と読み替えてこれを適用することとしている。
5 この他、退職給付の年金資産の時価についても本公開草案の考え方が適用される。ただし、年金資産の時価に関するレベル別の開示については、ASBJにおける退職給付に関する会計基準の検討状況も踏まえ、本公開草案では求めていない。
6 最有効使用の概念は、複数の代替的な使用が行われる可能性がある不動産などの非金融資産に適用されるが、金融資産には適用せず、負債にも適用しないとしている。
7 入力数値(インプット)とは、市場参加者が資産又は負債を価格設定する際に用いるであろう仮定のことを幅広く指し、イールドカーブ、インプライド・ボラティリティ、信用リスクなどが含まれる。
8 2009年のIASBのEDで「感応度分析」との表現が用いられていたので、本公開草案でも「感応度分析」と表現している。2010年のIASBの再公開草案では「不確実性分析」という表現に変更されている。
9 脚注8参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























