解説記事2010年09月06日 【新会計基準解説】 「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の公表に伴う他の改正会計基準等(四半期、セグメント情報等)について(2010年9月6日号・№369)
新会計基準解説
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の公表に伴う他の改正会計基準等(四半期、セグメント情報等)について
企業会計基準委員会 専門研究員 前田 啓
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「会計基準第24号」という。)が平成21年12月に公表されたことに伴い、平成22年6月に以下の企業会計基準及び適用指針を公表している(脚注1)。
これらは、平成21年12月25日及び平成22年4月2日に公開草案を公表し、寄せられたコメントを検討して、公開草案の修正を行った上で公表するに至ったものである。本稿では、各会計基準及び適用指針の概要を紹介するが、文中の意見にわたる部分は私見であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅱ.四半期財務諸表に関する改正
1.会計方針の変更
(1)原則的な取扱い 会計基準第24号では、会計方針の変更を行った場合は、会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められている場合を除き、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用することとしている。このため、四半期財務諸表においても、年度の取扱いと同様に、遡及適用を求めることとした。会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場合で、会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められている場合は、その経過的な取扱いに従う(改正基準第12号第10-2項及び第21-2項)。
(2)原則的な取扱いが実務上不可能な場合 遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合も、年度の取扱い(会計基準第24号第9項)に準じて取り扱うこととしている。一方、四半期固有の論点として、第2四半期会計期間以降に会計方針の変更を行う場合の取扱いがある。
会計方針の変更は期首に行われることが一般的であると考えられるが、まれに第2四半期以降で自発的に重要な会計方針を変更する場合もある。国際的な会計基準では、会計年度の途中で会計方針の変更を行う際には、同一の会計年度中の変更時点より前の期間すべてに新たな会計方針を遡及適用することを定めている。これにより、会計年度(又は期首からの累計期間)を通じて会計方針は単一のものとなるため、同一の会計年度内(又は期首からの累計期間内)の財務諸表に複数の会計方針の適用を認める場合に比べて期間比較可能性が向上し、財務諸表の意思決定有用性が高まることが期待されている。
このような取扱いを設けるかどうかの審議の過程では、年度の途中で会計方針を変更する場合は、相応の理由があると考えられるため、遡及適用が実務上不可能なときには、変更した時点以降から新たな会計方針を適用することを認めるべきであるという意見があった。しかしながら、自発的に会計方針を変更するときは、通常、同一年度の期首から新たな会計方針を適用することが可能であると考えられる。さらに、年度との会計処理の首尾一貫性を重視し、国際的な会計基準とのコンバージェンスを図る観点も踏まえ、第2四半期会計期間以降に会計方針の変更を行う際に、当年度の期首時点において、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を算定することが実務上不可能なときは、当年度の期首以前の実行可能な最も古い日から新たな会計方針を適用する(すなわち、少なくとも当年度の期首以降は新たな会計方針を適用する。)こととした(改正基準第12号第10-3項及び第21-3項)。
なお、当年度に含まれる、会計方針の変更を行う四半期会計期間より前のすべての四半期会計期間に新たな会計方針を適用することが実務上不可能なときには、年度との会計処理の首尾一貫性の観点から、翌年度の期首時点で会計方針の変更を行い、当該期首以前の実行可能な最も古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用することになると考えられる(改正基準第12号第47-3項)。
2.表示方法の変更 会計基準第24号では、財務諸表の表示方法を変更した場合には、原則として、表示する過去の財務諸表について、新たな表示方法に従い財務諸表の組替えを行うこととしている。
このため、四半期財務諸表の表示方法を変更した場合も、年度の取扱いに準じて財務諸表の組替えを行うこととした。ただし、財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、財務諸表の組替えが実行可能な最も古い期間から新たな表示方法を適用する(改正基準第12号第18-2項及び第24-2項)。
3.過去の誤謬の訂正 会計基準第24号では、過去の財務諸表における誤謬が発見された場合には、比較情報として表示される過去の財務諸表を修正再表示することとしている。
このため、当四半期会計期間に発見された過去の誤謬の訂正についても、年度の財務諸表との整合性を図る観点から、四半期財務諸表において修正再表示を行うこととした(改正基準第12号第16-2項及び第22-2項)。
4.注記事項 (1)会計方針の変更 重要な会計方針について変更を行った場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、その内容、その理由(脚注2)及び影響額を記載する(改正基準第12号第19項(2)及び第25項(1))。この影響額とは、新たな会計方針の遡及適用により影響を受ける前年度の期首からの累計期間に係る税金等調整前四半期純損益又は税引前四半期純損益、その他の重要な項目への影響額をいうものとしている。その他の重要な項目には、例えば、前年度の期首の純資産に反映された、遡及適用による累積的影響額が考えられる(改正指針第14号第33項及び第104-2項)。
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更が行われた場合は、変更の理由に代えて、会計基準等の名称を記載する。経過的な取扱いに従って会計処理を行った場合には、その旨及び当該経過的な取扱いの概要を、変更の内容に含めて記載する(改正指針第14号第33項)。
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更で、経過的な取扱いに従って会計処理を行った場合並びに遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合(会計基準第24号第9項(1)又は(2))で、前年度の四半期財務諸表について遡及適用を行っていないときには、新たな会計方針の適用により影響を受ける前年度又は当年度の期首からの累計期間に係る税金等調整前四半期純損益又は税引前四半期純損益、その他の重要な項目への影響額を記載する。ただし、前年度の期首以前の実行可能な最も古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用している場合には、開示対象期間である前年度と当年度の四半期財務諸表に同一の会計方針が適用されていることから、前年度の影響額の記載のみを求めることとしている(改正指針第14号第33項)。このほか、遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合は、その理由、会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期を記載することとなる(改正基準第12号第19項(2-2)及び第25項(1-2))。
(2)会計上の見積りの変更 会計上の見積りについて重要な変更を行った場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、その内容及び影響額を記載する。また、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合(脚注3)には、変更を行った四半期会計期間以後において、変更の内容、その理由及び影響額を記載する(改正基準第12号第19項(4)、(4-2)及び第25項(3)、(3-2))。
上記の影響額とは、変更により影響を受ける当年度の期首からの累計期間に係る税金等調整前四半期純損益又は税引前四半期純損益、その他の重要な項目への影響額(脚注4)をいうものとしている(改正指針第14号第34項)。
(3)表示方法の変更 四半期財務諸表の表示方法を変更した場合には、その内容として、前年度に係る四半期財務諸表等との比較を行うために必要な事項(組替えの内容、組替えを行った理由、組み替えられた四半期財務諸表等の主な項目の金額及び四半期財務諸表等の組替えが実務上不可能な場合には、その理由)を記載する。ただし、変更の内容が明らかである場合には、記載しないことができる(改正指針第14号第36項)。
(4)過去の誤謬の訂正 過去の誤謬の修正再表示を行った場合には、その内容及び影響額を記載する。この影響額とは、過去の誤謬の修正再表示により影響を受ける前年度の期首からの累計期間に係る税金等調整前四半期純損益又は税引前四半期純損益、その他の重要な項目への影響額をいうものとしている(改正基準第12号第19項(22)、第25項(21)及び改正指針第14号第35項)。
5.1株当たり情報 企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(以下「改正基準第2号」という。)及び企業会計基準適用指針第4号「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」の改正に伴い、四半期財務諸表における1株当たり情報の取扱いについても、年度と同様の改正を行っている(図表1参照)。
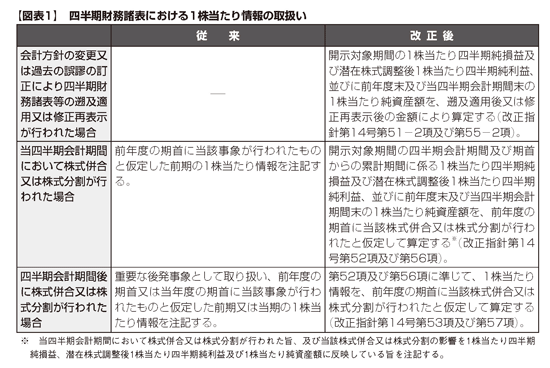
6.包括利益 企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」(以下「会計基準第25号」という。)が平成22年6月に公表され、当該基準において、1計算書方式の場合は、損益計算書に替えて損益及び包括利益計算書を作成することと、2計算書方式の場合は、損益計算書に加えて包括利益計算書を作成することが定められたことに伴い、四半期財務諸表の範囲について改正を行っている(改正基準第12号第5項など)。
なお、企業会計審議会で個別財務諸表に関する全般的な議論が行われているため、会計基準第25号の個別財務諸表への適用を求めるかどうかについては、当該基準の公表から1年後を目途に判断することとしている。したがって、包括利益の表示に関連した事項の四半期個別財務諸表への適用についても、これと同様になる(改正基準第12号第30-5項)。
Ⅲ.株主資本等変動計算書に関する改正
会計基準第24号により、遡及処理(「遡及処理」とは、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示により、過去の財務諸表を遡及的に処理することをいう。以下同じ。)における累積的影響額を期首残高に反映する取扱いが定められたことから、株主資本等変動計算書に表示されている各項目の前期末残高を、当期首残高に改正している。
また、遡及処理を行った場合には、表示期間のうち、最も古い期間の株主資本等変動計算書の期首残高に対する、表示期間より前の期間の累積的影響額を区分表示するとともに、遡及処理後の期首残高を記載することとしている(改正基準第6号第5項)(図表2参照)。
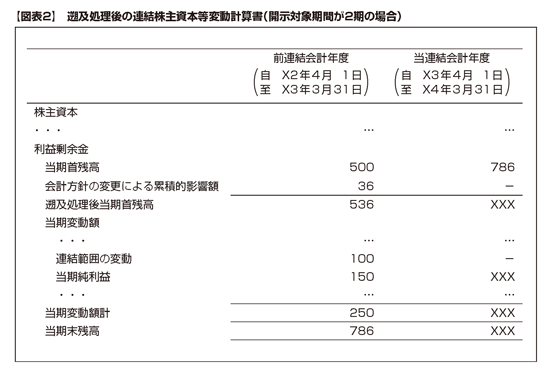
Ⅳ.セグメント情報に関する改正
1.年度の財務諸表での取扱い
(1)量的な重要性の変化による事業セグメントの範囲の変更 量的な重要性の変化によって、報告セグメントとして開示する事業セグメントの範囲を変更する場合には、従来は、その旨及びセグメント情報に与える影響を開示するものとしていたが、改正基準第17号では、前年度のセグメント情報との比較可能性を確保するため、その旨及び前年度のセグメント情報を当年度の報告セグメントの区分により作り直した情報を開示することとしている。
ただし、当該情報を開示することが実務上困難な場合(必要な情報の入手が困難な場合や、当該情報を作成するために過度の負担を要する場合には、実務上困難なものとする。)には、セグメント情報に与える影響を開示することができる。
この影響の開示には、当年度のセグメント情報を前年度の区分方法により作成した情報を開示することが含まれると考えられる(改正基準第17号第16項及び第76項)。
(2)会計上の変更又は過去の誤謬の訂正を行った場合 会計基準第24号に従い、会計上の変更又は過去の誤謬の訂正を行う場合、財務諸表を作成するために採用した会計処理に基づく数値によるセグメント情報等に影響を与える。
したがって、財務諸表の遡及処理を行う場合は、前年度のセグメント情報等について、遡及処理の影響を反映した情報を開示することに留意が必要であるとしている(改正基準第17号第97-2項)。
2.四半期財務諸表での取扱い 四半期財務諸表において、事業セグメントの量的な重要性の変化によって報告セグメントとして開示する事業セグメントの範囲を変更する場合は、適時性に係るより強い制約等を考慮し、その旨、期首からの累計期間に係る報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高の情報に与える影響を記載するという従来の取扱いを変えていない。
ただし、前年度の対応する期首からの累計期間に係る報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高の情報を当年度の報告セグメントの区分により作り直した情報が、最高経営意思決定機関に対して提供され、使用されている場合には、期首からの累計期間に係る報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高の情報に与える影響額そのものの記載に代えて、当該情報を記載することが考えられる(改正指針第14号第40項(1)①及び第106項)。
Ⅴ.適用時期
各会計基準等の適用時期は、図表3のとおりである。なお、改正基準第12号の適用初年度は、会計基準第24号第24項に準じた事項(脚注5)を注記することとしている。
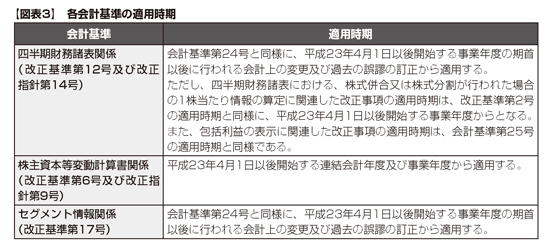
脚注
1 これらの全文については、ASBJのホームページ(https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/kaikei/)を参照のこと。
2 第2四半期以降に自発的に重要な会計方針について変更を行った場合(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合を含む。)には、当該記載に加え、第2四半期以降に変更した理由も注記する(改正基準第12号第19項(3)及び第25項(2))。
3 有形固定資産等の減価償却方法及び無形固定資産の償却方法の変更が、これに該当する(会計基準第24号第20項)。
4 当年度の影響額を適時に正確に算定することができない場合には、資本連結をやり直さないなど、適当な方法による概算額を記載することができる。
5 会計基準第24号の適用初年度においては、当該事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から当該基準を適用している旨を注記することとしている。
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の公表に伴う他の改正会計基準等(四半期、セグメント情報等)について
企業会計基準委員会 専門研究員 前田 啓
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「会計基準第24号」という。)が平成21年12月に公表されたことに伴い、平成22年6月に以下の企業会計基準及び適用指針を公表している(脚注1)。
| ・改正企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」(以下「改正基準第6号」という。) ・改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」(以下「改正基準第12号」という。) ・改正企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(以下「改正基準第17号」という。) ・改正企業会計基準適用指針第9号「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」(以下「改正指針第9号」という。) ・改正企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下「改正指針第14号」という。) |
Ⅱ.四半期財務諸表に関する改正
1.会計方針の変更
(1)原則的な取扱い 会計基準第24号では、会計方針の変更を行った場合は、会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められている場合を除き、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用することとしている。このため、四半期財務諸表においても、年度の取扱いと同様に、遡及適用を求めることとした。会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場合で、会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められている場合は、その経過的な取扱いに従う(改正基準第12号第10-2項及び第21-2項)。
(2)原則的な取扱いが実務上不可能な場合 遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合も、年度の取扱い(会計基準第24号第9項)に準じて取り扱うこととしている。一方、四半期固有の論点として、第2四半期会計期間以降に会計方針の変更を行う場合の取扱いがある。
会計方針の変更は期首に行われることが一般的であると考えられるが、まれに第2四半期以降で自発的に重要な会計方針を変更する場合もある。国際的な会計基準では、会計年度の途中で会計方針の変更を行う際には、同一の会計年度中の変更時点より前の期間すべてに新たな会計方針を遡及適用することを定めている。これにより、会計年度(又は期首からの累計期間)を通じて会計方針は単一のものとなるため、同一の会計年度内(又は期首からの累計期間内)の財務諸表に複数の会計方針の適用を認める場合に比べて期間比較可能性が向上し、財務諸表の意思決定有用性が高まることが期待されている。
このような取扱いを設けるかどうかの審議の過程では、年度の途中で会計方針を変更する場合は、相応の理由があると考えられるため、遡及適用が実務上不可能なときには、変更した時点以降から新たな会計方針を適用することを認めるべきであるという意見があった。しかしながら、自発的に会計方針を変更するときは、通常、同一年度の期首から新たな会計方針を適用することが可能であると考えられる。さらに、年度との会計処理の首尾一貫性を重視し、国際的な会計基準とのコンバージェンスを図る観点も踏まえ、第2四半期会計期間以降に会計方針の変更を行う際に、当年度の期首時点において、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を算定することが実務上不可能なときは、当年度の期首以前の実行可能な最も古い日から新たな会計方針を適用する(すなわち、少なくとも当年度の期首以降は新たな会計方針を適用する。)こととした(改正基準第12号第10-3項及び第21-3項)。
なお、当年度に含まれる、会計方針の変更を行う四半期会計期間より前のすべての四半期会計期間に新たな会計方針を適用することが実務上不可能なときには、年度との会計処理の首尾一貫性の観点から、翌年度の期首時点で会計方針の変更を行い、当該期首以前の実行可能な最も古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用することになると考えられる(改正基準第12号第47-3項)。
2.表示方法の変更 会計基準第24号では、財務諸表の表示方法を変更した場合には、原則として、表示する過去の財務諸表について、新たな表示方法に従い財務諸表の組替えを行うこととしている。
このため、四半期財務諸表の表示方法を変更した場合も、年度の取扱いに準じて財務諸表の組替えを行うこととした。ただし、財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、財務諸表の組替えが実行可能な最も古い期間から新たな表示方法を適用する(改正基準第12号第18-2項及び第24-2項)。
3.過去の誤謬の訂正 会計基準第24号では、過去の財務諸表における誤謬が発見された場合には、比較情報として表示される過去の財務諸表を修正再表示することとしている。
このため、当四半期会計期間に発見された過去の誤謬の訂正についても、年度の財務諸表との整合性を図る観点から、四半期財務諸表において修正再表示を行うこととした(改正基準第12号第16-2項及び第22-2項)。
4.注記事項 (1)会計方針の変更 重要な会計方針について変更を行った場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、その内容、その理由(脚注2)及び影響額を記載する(改正基準第12号第19項(2)及び第25項(1))。この影響額とは、新たな会計方針の遡及適用により影響を受ける前年度の期首からの累計期間に係る税金等調整前四半期純損益又は税引前四半期純損益、その他の重要な項目への影響額をいうものとしている。その他の重要な項目には、例えば、前年度の期首の純資産に反映された、遡及適用による累積的影響額が考えられる(改正指針第14号第33項及び第104-2項)。
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更が行われた場合は、変更の理由に代えて、会計基準等の名称を記載する。経過的な取扱いに従って会計処理を行った場合には、その旨及び当該経過的な取扱いの概要を、変更の内容に含めて記載する(改正指針第14号第33項)。
会計基準等の改正に伴う会計方針の変更で、経過的な取扱いに従って会計処理を行った場合並びに遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合(会計基準第24号第9項(1)又は(2))で、前年度の四半期財務諸表について遡及適用を行っていないときには、新たな会計方針の適用により影響を受ける前年度又は当年度の期首からの累計期間に係る税金等調整前四半期純損益又は税引前四半期純損益、その他の重要な項目への影響額を記載する。ただし、前年度の期首以前の実行可能な最も古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用している場合には、開示対象期間である前年度と当年度の四半期財務諸表に同一の会計方針が適用されていることから、前年度の影響額の記載のみを求めることとしている(改正指針第14号第33項)。このほか、遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合は、その理由、会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期を記載することとなる(改正基準第12号第19項(2-2)及び第25項(1-2))。
(2)会計上の見積りの変更 会計上の見積りについて重要な変更を行った場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、その内容及び影響額を記載する。また、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合(脚注3)には、変更を行った四半期会計期間以後において、変更の内容、その理由及び影響額を記載する(改正基準第12号第19項(4)、(4-2)及び第25項(3)、(3-2))。
上記の影響額とは、変更により影響を受ける当年度の期首からの累計期間に係る税金等調整前四半期純損益又は税引前四半期純損益、その他の重要な項目への影響額(脚注4)をいうものとしている(改正指針第14号第34項)。
(3)表示方法の変更 四半期財務諸表の表示方法を変更した場合には、その内容として、前年度に係る四半期財務諸表等との比較を行うために必要な事項(組替えの内容、組替えを行った理由、組み替えられた四半期財務諸表等の主な項目の金額及び四半期財務諸表等の組替えが実務上不可能な場合には、その理由)を記載する。ただし、変更の内容が明らかである場合には、記載しないことができる(改正指針第14号第36項)。
(4)過去の誤謬の訂正 過去の誤謬の修正再表示を行った場合には、その内容及び影響額を記載する。この影響額とは、過去の誤謬の修正再表示により影響を受ける前年度の期首からの累計期間に係る税金等調整前四半期純損益又は税引前四半期純損益、その他の重要な項目への影響額をいうものとしている(改正基準第12号第19項(22)、第25項(21)及び改正指針第14号第35項)。
5.1株当たり情報 企業会計基準第2号「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(以下「改正基準第2号」という。)及び企業会計基準適用指針第4号「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」の改正に伴い、四半期財務諸表における1株当たり情報の取扱いについても、年度と同様の改正を行っている(図表1参照)。
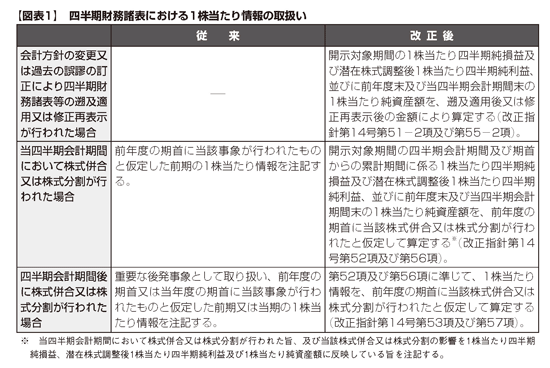
6.包括利益 企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」(以下「会計基準第25号」という。)が平成22年6月に公表され、当該基準において、1計算書方式の場合は、損益計算書に替えて損益及び包括利益計算書を作成することと、2計算書方式の場合は、損益計算書に加えて包括利益計算書を作成することが定められたことに伴い、四半期財務諸表の範囲について改正を行っている(改正基準第12号第5項など)。
なお、企業会計審議会で個別財務諸表に関する全般的な議論が行われているため、会計基準第25号の個別財務諸表への適用を求めるかどうかについては、当該基準の公表から1年後を目途に判断することとしている。したがって、包括利益の表示に関連した事項の四半期個別財務諸表への適用についても、これと同様になる(改正基準第12号第30-5項)。
Ⅲ.株主資本等変動計算書に関する改正
会計基準第24号により、遡及処理(「遡及処理」とは、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示により、過去の財務諸表を遡及的に処理することをいう。以下同じ。)における累積的影響額を期首残高に反映する取扱いが定められたことから、株主資本等変動計算書に表示されている各項目の前期末残高を、当期首残高に改正している。
また、遡及処理を行った場合には、表示期間のうち、最も古い期間の株主資本等変動計算書の期首残高に対する、表示期間より前の期間の累積的影響額を区分表示するとともに、遡及処理後の期首残高を記載することとしている(改正基準第6号第5項)(図表2参照)。
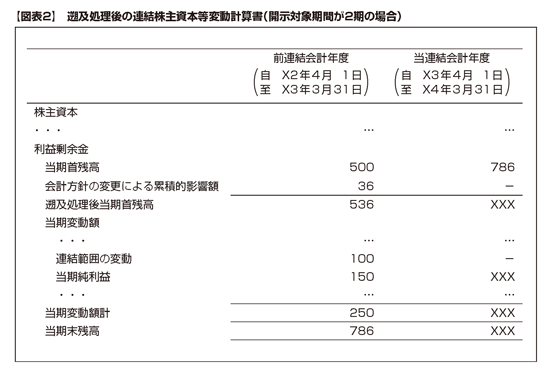
Ⅳ.セグメント情報に関する改正
1.年度の財務諸表での取扱い
(1)量的な重要性の変化による事業セグメントの範囲の変更 量的な重要性の変化によって、報告セグメントとして開示する事業セグメントの範囲を変更する場合には、従来は、その旨及びセグメント情報に与える影響を開示するものとしていたが、改正基準第17号では、前年度のセグメント情報との比較可能性を確保するため、その旨及び前年度のセグメント情報を当年度の報告セグメントの区分により作り直した情報を開示することとしている。
ただし、当該情報を開示することが実務上困難な場合(必要な情報の入手が困難な場合や、当該情報を作成するために過度の負担を要する場合には、実務上困難なものとする。)には、セグメント情報に与える影響を開示することができる。
この影響の開示には、当年度のセグメント情報を前年度の区分方法により作成した情報を開示することが含まれると考えられる(改正基準第17号第16項及び第76項)。
(2)会計上の変更又は過去の誤謬の訂正を行った場合 会計基準第24号に従い、会計上の変更又は過去の誤謬の訂正を行う場合、財務諸表を作成するために採用した会計処理に基づく数値によるセグメント情報等に影響を与える。
したがって、財務諸表の遡及処理を行う場合は、前年度のセグメント情報等について、遡及処理の影響を反映した情報を開示することに留意が必要であるとしている(改正基準第17号第97-2項)。
2.四半期財務諸表での取扱い 四半期財務諸表において、事業セグメントの量的な重要性の変化によって報告セグメントとして開示する事業セグメントの範囲を変更する場合は、適時性に係るより強い制約等を考慮し、その旨、期首からの累計期間に係る報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高の情報に与える影響を記載するという従来の取扱いを変えていない。
ただし、前年度の対応する期首からの累計期間に係る報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高の情報を当年度の報告セグメントの区分により作り直した情報が、最高経営意思決定機関に対して提供され、使用されている場合には、期首からの累計期間に係る報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高の情報に与える影響額そのものの記載に代えて、当該情報を記載することが考えられる(改正指針第14号第40項(1)①及び第106項)。
Ⅴ.適用時期
各会計基準等の適用時期は、図表3のとおりである。なお、改正基準第12号の適用初年度は、会計基準第24号第24項に準じた事項(脚注5)を注記することとしている。
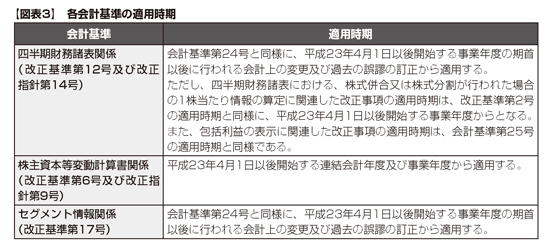
脚注
1 これらの全文については、ASBJのホームページ(https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/kaikei/)を参照のこと。
2 第2四半期以降に自発的に重要な会計方針について変更を行った場合(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分することが困難な場合を含む。)には、当該記載に加え、第2四半期以降に変更した理由も注記する(改正基準第12号第19項(3)及び第25項(2))。
3 有形固定資産等の減価償却方法及び無形固定資産の償却方法の変更が、これに該当する(会計基準第24号第20項)。
4 当年度の影響額を適時に正確に算定することができない場合には、資本連結をやり直さないなど、適当な方法による概算額を記載することができる。
5 会計基準第24号の適用初年度においては、当該事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から当該基準を適用している旨を注記することとしている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















