解説記事2010年10月04日 【新会計基準解説】 「金融商品会計基準(金融資産の分類及び測定)の見直しに関する検討状況の整理」について(2010年10月4日号・№372)
新会計基準解説
「金融商品会計基準(金融資産の分類及び測定)の見直しに関する検討状況の整理」について
企業会計基準委員会 専門研究員 高橋由彦
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成22年8月16日に「金融商品会計基準(金融資産の分類及び測定)の見直しに関する検討状況の整理」(以下「本検討状況の整理」という。)を公表し、本年11月30日までコメントを募集している(脚注1)。本稿では本検討状況の整理の概要について解説するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅱ.本検討状況の整理の目的
ASBJは、現在、国際会計基準審議会(IASB)との間で合意した「会計基準のコンバージェンスの加速化に向けた取組みへの合意(東京合意)」(平成19年8月)の趣旨を踏まえ、プロジェクト計画表に従い、金融商品会計の現行基準の見直しに向けた検討を進めている。本検討状況の整理は、そのプロジェクトの一環として、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下「金融商品会計基準」という。)及びこれに関連する適用指針の取扱いを見直すにあたり必要な内容を整理することを目的としている。
平成21年5月にASBJが公表した「金融商品会計の見直しに関する論点の整理」(以下「論点整理」という。)では、金融商品会計の範囲(【論点1】)、金融商品の測定(【論点2】)、ヘッジ会計(【論点3】)を論点として掲げた。本検討状況の整理では、【論点1】のうち金融商品の定義等に関連する金融商品の範囲、及び【論点2】のうち金融資産の分類及び測定(減損(貸倒引当金又は貸倒損失)を除く。)を扱っている。
Ⅲ.本検討状況の整理の公表の背景
我が国における金融商品に関する会計基準等としては、ASBJから金融商品会計基準及び関連する適用指針等が公表されており、また、日本公認会計士協会から「金融商品会計に関する実務指針」(以下「金融商品実務指針」という。)及び「金融商品会計に関するQ&A」が公表されている。
一方、IASBと米国財務会計基準審議会(FASB)は、平成18年2月に公表した会計基準のコンバージェンスに向けた作業計画(MoU)の中で金融商品会計に関する現行基準の見直しを取り上げ、従来から、見直しに向けた作業を進めてきている。特に、昨今の金融危機への対応の一環として主要20か国・地域(G20)首脳会合から要請を受けたこと等を踏まえ、その検討を加速している。IASBは、この見直し作業を大きく4つ(①金融資産の分類及び測定、②金融負債の分類及び測定、③減損(貸倒引当金又は貸倒損失)、④ヘッジ会計)に分割し、最初のフェーズである金融資産の分類及び測定について、平成21年11月に国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」(以下「IFRS第9号」という。)の公表を行った。FASBにおいても、分類及び測定、減損(貸倒引当金又は貸倒損失)、ヘッジ会計を包括する公開草案「デリバティブ及びヘッジ(Topic 815)並びに金融商品(Topic 825):金融商品に関する会計処理、並びに、デリバティブ金融商品及びヘッジ活動に関する会計処理の改訂」(以下「FASB公開草案」という。)を平成22年5月に公表している。
ASBJは、現在、東京合意の趣旨も踏まえ、プロジェクト計画表に従い、金融商品会計の現行基準の見直しに向けた検討を進めている。平成21年5月には「金融商品会計の見直しに関する論点の整理」を公表したが、本検討状況の整理は、当該論点整理に対する意見を踏まえるとともに、その後IASB及びFASBの議論が進む中で論点整理公表時から大きく環境が変化していることも考慮して、金融商品の範囲、金融資産の分類及び測定に関して検討の中間段階においてその方向性を示すものとして公表している。本検討状況の整理の金融資産の分類及び測定に関しては、IFRS第9号とのコンバージェンスを念頭に置いているが、会計基準(案)及び適用指針(案)に分けて内容を整理する中で、それらを我が国の会計上の取扱いとして受け入れるにあたり検討すべき観点を提供している。
Ⅳ.会計基準(案)及び適用指針(案)の概要
1.金融商品の範囲 本検討状況の整理では、金融商品の定義は、IFRSとほぼ同様であることから、当面、現行の取扱いを維持することが考えられるとしている。
ただし、金融資産、金融負債及びデリバティブの定義は、金融商品会計基準においては商品名の列挙により行われ、金融商品実務指針において定義が補足されている。このため、本検討状況の整理の会計基準(案)では、この定義の仕方を変更し、金融資産、金融負債及びデリバティブをその特徴により定義し、商品名を例示することが考えられるとしている。
また、論点整理では、デリバティブの特徴の1つとされる純額決済性をIFRSとの相違の1つとして取り上げ、デリバティブの定義や特徴について見直すべき点がないかどうか、意見を募ったが、コメントも踏まえ、本検討状況の整理では、コンバージェンスの観点からIFRSに合わせて削除することが考えられるとしている。
2.金融資産の分類及び測定の基本的なモデル 本検討状況の整理で示す金融資産の分類及び測定モデルの全体像を図表1に掲げる。
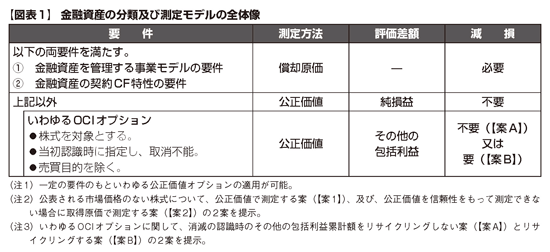
金融資産の分類及び測定に関して、本検討状況の整理はIFRS第9号を基礎として、主な分類を償却原価測定の分類及び公正価値測定の分類の2つとする混合測定属性アプローチを採用している。
① すなわち、原則として、金融資産は、次の両方の要件を満たす場合に、当初認識後、償却原価で測定するものとして分類され、それ以外の場合は、公正価値で測定するものとして分類することが考えられるとしている。契約キャッシュ・フローを回収するために資産を保有するという目的を有する事業モデルに基づいて、資産が保有されている(金融資産を管理する事業モデルの要件)。
② 金融資産の契約条件により特定の日にキャッシュ・フローが生じ、そのキャッシュ・フローが元本及び元本残高に対する利息の支払に限られる(金融資産の契約キャッシュ・フロー特性の要件)。
このように、①「金融資産を管理する事業モデルの要件」、及び、②「金融資産の契約キャッシュ・フロー特性の要件」により、金融資産を分類する考え方は、IASBが平成21年7月に公表した公開草案「金融商品:分類及び測定」で提案した基本的な考え方がIFRS第9号に引き継がれたものである。
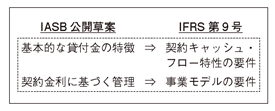
ASBJでは、IASBにおける検討の経緯やASBJを含む様々な意見を検討し議論を経てIFRS第9号が確定した経緯等を踏まえ、本検討状況の整理は、主な分類を償却原価測定の分類及び公正価値測定の分類の2つとする混合測定属性アプローチを採用し、償却原価測定を適用する金融資産を、金融資産を管理する事業モデル及び金融資産の契約キャッシュ・フロー特性の2要件により分類することが考えられるとしている(脚注2)。
① 「金融資産を管理する事業モデルの要件」における事業モデルは、個々の金融商品に関する経営者の意図に左右されるものではなく、それらの集合としてのレベルで判断されるとしている。また、契約キャッシュ・フローを回収するという事業モデルであっても、すべてを満期まで保有する必要はなく、途中での売却は必ずしも否定されていない。ただし、売却がしばしば実行される場合には、契約キャッシュ・フローを回収するという目的と整合しているか吟味する必要があるとされている。
② 「金融資産の契約キャッシュ・フロー特性の要件」における利息は、特定の期間における元本残高に関する貨幣の時間価値及び信用リスクへの対価となるものとすることが考えられるとしており、一部の金融資産の契約キャッシュ・フロー特性であるレバレッジは、契約キャッシュ・フローの変動性を高めるため、利息としての経済的特徴を有しないとされている。
なお、現行の満期保有目的の債券も償却原価で測定されるが、この債券に対しては、満期までに売却又は保有目的区分の変更を行った場合、その後2事業年度の間、満期保有目的の債券の分類を設けることができないとする定めがあり、国際的には、テインティング・ルールと呼ばれている。一方で、IFRS第9号では、金融資産を管理する企業の事業モデル及び当該金融資産の契約キャッシュ・フロー特性に基づいた分類は測定に関する明確な論拠を示すものであること、テインティング・ルールと同様の定めを設けることによって適用上の複雑性が増すことなどを勘案し、償却原価測定の分類の金融資産にこのような取扱いを設けないこととした。
本検討状況の整理では、IFRS第9号がテインティング・ルールを設けなかった上記の趣旨や、テインティング・ルールの結果、要件に照らして適切に分類できなくなることを踏まえ、テインティング・ルールを設けないIFRS第9号の取扱いを基礎としている。
3.公正価値測定の選択肢(いわゆる公正価値オプション) IFRS第9号では、事業モデル及び契約キャッシュ・フロー特性の2要件にかかわらず、公正価値で評価し、評価差額を純損益とする選択肢が設けられており(いわゆる公正価値オプション)、当初認識時に指定しその後の取消しは認められないこととされている。その要件を、このような指定を行わなければ資産若しくは負債の測定、又は資産若しくは負債に関する純損益の認識を異なる基準で行うことによって生じるであろう測定又は認識に関する不整合(いわゆる会計上のミスマッチ)が、その指定を行うことによって取り除かれる又は大幅に削減されることとしている。
本検討状況の整理の会計基準(案)でも、2の基本的な取扱いにかかわらず、金融資産を公正価値で測定し評価差額を純損益とするとの指定を、当初認識時に限り許容することが考えられるとしている。その条件として、このような指定を通じて、資産若しくは負債の測定、又は資産若しくは負債に関する純損益の認識に生じる不整合(いわゆる会計上のミスマッチ)が、取り除かれる又は大幅に削減される場合に限ることが考えられるとしている。
公正価値オプションは、このように、会計上のミスマッチを解消し複雑な測定を簡素化するとの利点がある一方で、論点整理に対するコメントでも指摘されたように、採用される分類モデルと異なる測定が恣意的に選択される懸念がある。ただし、こうした懸念に対しては、IFRS第9号の公正価値オプションは、恣意性を排除するため、会計上のミスマッチ解消の適格要件、当初認識時の指定及び事後の取消禁止など、その自由度を制限する取扱いが設けられている。
これまでASBJは公正価値オプションに必ずしも肯定的ではなかったが、公正価値オプションの利点や欠点、また、その欠点を是正するための対応等を総合的に勘案すると、この点に関するコンバージェンスを否定する程のものではないとも考えられることから、本検討状況の整理においては、IFRS第9号と同様に、会計上のミスマッチの解消又は大幅な削減を要件として、この指定を認めることとしている。
4.公表される市場価格のない株式の分類 株式への投資については、2の基本的な取扱いに従えば、通常は公正価値で測定するものとして分類することとなるが、公表される市場価格のない株式の分類については、次の案が考えられるとしている。【案1】は、2の基本的な取扱いに従い、公正価値で測定するものとして分類するというものである。【案2】は、2の基本的な取扱いにかかわらず、償却原価測定、公正価値測定の分類に、取得原価測定の分類を追加するというものである。すなわち、公表される市場価格のない株式について、公正価値を信頼性をもって測定できない場合には、2の基本的な取扱いにかかわらず、取得原価で測定する分類を追加するというものである。
そもそも本検討状況の整理は、特に金融資産の分類及び測定に関して、IFRS第9号を基礎としており、金融資産を管理する事業モデルとその契約キャッシュ・フロー特性に基づいて、償却原価測定又は公正価値測定のいずれかの分類とすることとしている。また、一定の金融資産に対しては、評価差額をその他の包括利益に認識する指定を許容することとしている。
しかしながら、IFRS第9号とのコンバージェンスを図っていく場合であっても、一部の事項について一層の検討を要するとの意見もある。ASBJでは、今後の審議の参考とするため、そうした事項のうち特に重要と考えられる点を質問として掲げているが、公表される市場価格のない株式の分類もその1つとされている。
【案1】の場合、株式に対する投資及び株式に関する契約は、すべて公正価値で測定しなければならない。しかし、適用指針(案)において、限定的ではあるが、取得原価が公正価値の適切な見積りとなる場合があるとされており、公正価値を算定するのに利用できる最近の情報が十分でない場合、又は、公正価値として測定できる範囲が広く当該範囲の中で取得原価が公正価値の最適な見積りを表す場合、取得原価が公正価値の適切な見積りとなる可能性があるとされている。
【案2】の場合、IFRSによる適用と我が国会計基準の適用の差異が小さくなることを意図して、現行のIAS第39号の取扱いを踏まえて「公正価値を信頼性をもって測定できない場合」との条件を付している。我が国では、「市場で売買されない株式について、たとえ何らかの方式により価額の算定が可能としても、それを時価(合理的に算定された価額)とはしない」(金融商品実務指針第63項)と扱われているが、「公正価値を信頼性をもって測定できる」とは我が国の会計基準のような市場での売買の有無を規準とするものでなく、IAS第39号の適用指針にあるように、合理的な公正価値の見積額の範囲での変動性が当該金融資産にとって重要でない、又は、その範囲内におけるさまざまな見積値の確率が合理的に評価でき公正価値の見積りに使用できる場合を意図している。
今後、ASBJでは、本検討状況の整理に対する意見も踏まえ、公表される市場価格のない株式の取扱いについて引き続き検討していくこととされている。
5.複合商品 組込デリバティブとは、デリバティブでない組込対象を含む複合商品の構成要素であり、それにより合成された商品のキャッシュ・フローの一部は、単独のデリバティブと同じように変化するものである。
IFRS第9号では、組込デリバティブを含む複合商品の組込対象がIFRS第9号の対象である金融資産の場合、複合商品全体に対して、複合商品でない通常の金融資産と同様の定めを適用しなければならないとされている。すなわち、金融商品全体について、事業モデル及び契約キャッシュ・フロー特性の2要件に照らして、償却原価測定の分類又は公正価値測定の分類のいずれかとされる。
金融商品会計基準では、複合商品を(a)払込資本を増加させる可能性のある部分を含むものと(b)その他のもの、に分けて定めているが、本検討状況の整理では、いずれの場合も、このようなIFRS第9号の取扱いを基礎とする取扱いによることとしている。すなわち、組込デリバティブを含む複合商品の組込対象が金融資産の場合、複合商品全体について、事業モデル及びキャッシュ・フロー特性の2要件に照らして、償却原価測定の分類又は公正価値測定の分類のいずれかとすることが考えられるとしている。
なお、転換社債型新株予約権付社債は、以前の転換社債と経済的実質が同一であることから、取得者側では1つの会計単位として扱われ、上述の考え方から公正価値測定の分類になると考えられる一方で、転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債については、払込資本を増加させる可能性のある部分とそれ以外の部分が同時に各々存在し得ることから、各々が別の金融商品として、それぞれの部分に区分して処理することが考えられるとしている。
6.分類の変更 IFRS第9号では、企業が金融資産を管理する事業モデルを変更した場合に、企業は影響を受ける金融資産のすべての分類を変更することとされている。分類を変更する場合、変更日から将来に向かって適用しなければならないとしている。当初IASB公開草案では、分類の変更を禁止することを提案していたが、ほぼすべてのコメントが、金融資産をその管理方法に基づいて分類するアプローチと整合的でないとして、提案に反対した。この結果、IASBはこうした主張を受け入れ、事業モデルを変更した場合に分類の変更を要求することとした。
本検討状況の整理では、IFRS第9号の取扱いを基礎として、企業が金融資産を管理する事業モデルを変更した場合に、企業は影響を受ける金融資産のすべての分類を、変更日から将来に向かって適用することとしている。この場合の分類変更日は、事業モデル変更の翌事業年度の期首とし、分類変更日から将来に向かって適用することが考えられるとしている(図表2参照)。
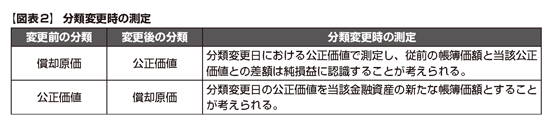
本検討状況の整理の適用指針(案)では、こうした事業モデルの変更は極めて稀にしか起こらないと考えられ、企業の経営者によって、外的又は内的変化の結果に基づいて判断されなければならず、かつ企業の営業にとって重要で、外部当事者に対して実証できるものでなければならないとされている。
なお、「変更日」として、本検討状況の整理では、翌事業年度の期首としている。この点に関して、ASBJの議論では、事業モデルの変更時期と異なる時期に分類を変更することとなり、それまでの間、事業モデルと整合しない分類となるとの懸念が示された。加えて、我が国では四半期報告の制度が導入されており、翌事業年度まで変更を待つ必要があるのかよく検討すべきであるとの意見もあったことから、今後、この点に関して、引き続き検討することが考えられるとしている。
7.株式への投資に関するその他の包括利益での評価差額の認識(いわゆるOCIオプション) 本検討状況の整理では、公正価値測定の分類の金融資産の評価差額は、純損益で認識することが考えられるとしている。しかし、一部の金融商品への投資は、投資価値の増加を目的とするものではないため、その投資の公正価値による評価差額を公正価値の変動時にそのまま純損益に反映することは企業の業績を示さない可能性があるとの理由から、IFRS第9号のOCIオプションと同様に、一定の株式について、公正価値測定の評価差額をその他の包括利益に認識する取扱いを設けることが考えられるとしている。
すなわち、株式への投資に関して、公正価値の変動により利益を得ることを目的とする(売買目的)場合を除き、評価差額をその他の包括利益で認識するとの指定を許容することが考えられ、この場合の指定は、当初認識時に行い、その後、取消不能とすることが考えられるとしている。
この指定による場合、IFRS第9号のOCIオプションと同様に、消滅の認識時点でその他の包括利益累計額をリサイクリングしないことが考えられるが、これまでの我が国の会計慣行等に大きな影響を及ぼすため、リサイクリングを維持すべきとの意見も多い。本検討状況の整理では、OCIオプションにおけるリサイクリングの禁止はコンバージェンス上の重要な問題の1つであると認識し、特段の方向性を設けず、リサイクリングを行わない案(【案A】)及びリサイクリングを行う案(【案B】)の2つの考え方を示すこととしている。
これに関連して、本検討状況の整理では、コンバージェンスの観点から連結財務諸表においてリサイクリングを禁止したとしても、当面、個別財務諸表では、これまでの会計慣行やその他の観点から、リサイクリングを維持する可能性を検討すべきとの意見のあったことも紹介されている。
今後、ASBJでは、本検討状況の整理に対する意見も踏まえ、リサイクリングを禁止すべきか否かについて引き続き検討していくこととしている。
8.個別財務諸表における子会社及び関連会社に対する株式の取扱い 子会社及び関連会社に対する株式への投資は、定義上は金融資産に該当する。このため、現行の金融商品会計基準では、子会社株式及び関連会社株式をその範囲に含めている。しかし、連結財務諸表上は、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」が適用されるため、金融商品会計基準の取扱いは、実質的に、個別財務諸表に限定されている。
子会社及び関連会社に対する株式の投資は、事業投資の性質を有し、子会社の支配、関連会社への重要な影響を通じてそれぞれの事業活動に係っているとも言えることから、従前から、金融商品会計の範囲として扱うべきか否かについて議論があった。また、その測定についても、子会社株式及び関連会社株式に含まれるのれん相当分が個別財務諸表上残ることとなる、減損のアプローチが個別財務諸表と連結財務諸表で異なるため個別財務諸表と連結財務諸表の測定の整合性が図られていない、との指摘があった。
個別財務諸表における子会社及び関連会社株式の取扱いに関しては、我が国の課題として検討する必要があるが、IFRSの取扱いも参考に、次のようなアプローチが考えられるとしている。
① 会計基準(案)の範囲に含め、取得原価とする。
② 会計基準(案)の範囲に含めるが、子会社株式及び関連会社株式に特別の定めを設けない。
③ 会計基準(案)の範囲に含めず、別の会計基準を改訂し、取得原価とする。
④ 会計基準(案)の範囲に含めず、別の会計基準を改訂し、持分法とする。
本検討状況の整理の会計基準(案)では、既存の金融商品会計基準の取扱いを踏襲し、①のように子会社株式及び関連会社株式を会計基準(案)の範囲とし、取得原価とすることとしているが、今後、本検討状況の整理に対するコメントも踏まえて、引き続き、個別財務諸表における子会社及び関連会社に対する株式の取扱いを検討していくことが考えられるとしている。
9.表示及び注記事項 本検討状況の整理では、IAS第1号「財務諸表の表示」及びIFRS第7号「金融商品:開示」のうち、IFRS第9号を受けて改訂された部分を基礎として、金融商品会計基準の既存の取扱いに付け加える内容を示している。これらの表示及び注記事項は、IFRS第9号の分類に一定の自由度を設けることの見合いで導入されたものであることから、本検討状況の整理においても、会計基準(案)での分類とセットで議論するとしている。
表示に関しては、①償却原価測定の分類の金融資産の消滅の認識時の利益又は損失、及び、②会計基準(案)に従って金融資産の分類を変更した結果生じる利益又は損失、をそれぞれ独立して掲記することが考えられるとしている。
また、注記事項に関しては、評価差額をその他の包括利益に含める指定を行う場合(OCIオプションの場合)、会計基準(案)に従って金融資産の分類を変更した場合、等について、一定の事項を注記することが考えられるとしている。
10.外貨建取引等会計処理基準への影響 平成11年に改正された「外貨建取引等会計処理基準」(以下「外貨建基準」という。)は、現行の金融商品会計基準の有価証券の分類及び測定を反映した取扱いとなっている。このため、本検討状況の整理では、会計基準(案)で示される取扱いを受けて、外貨建基準について想定される変更をまとめている。
例えば、外貨建債券でその他有価証券に分類されるものは、現行では、原則として金融商品会計基準の評価差額に関する処理方法に従うものとされており、償却原価に係る換算差額も含めて換算差額全体をその他の包括利益に含めることとなるが、外国通貨による公正価値の変動に係る換算差額を除いて為替差損益として処理できるとされている。
これに対して、会計基準(案)による場合、公正価値又は償却原価のいずれかで測定されるが、いずれの場合も、決算時の為替相場による換算差額は純損益に反映することが考えられるとされている。
また、外貨建株式でその他有価証券に分類されるものは、現行では、原則として金融商品会計基準の評価差額に関する処理方法に従うものとされており、取得原価に係る換算差額も含めて換算差額全体をその他の包括利益に含めることとなる。
これに対して、会計基準(案)の原則的な方法(公正価値で測定し評価差額を純損益に認識する)による場合、公正価値で測定されるが、決算時の為替相場による換算差額は、原則として、純損益に反映することが考えられる。ただし、評価差額をその他の包括利益に含める指定を行う場合(OCIオプションの場合)には、その評価差額に決算時の為替相場による換算差額を含めることが考えられるとされている。
11.契約上リンクしているトランシェの取扱い 仕組投資ビークルは、様々なトランシェを発行し、様々なトランシェの保有者に対して発行者による支払の優先順位を決める「ウォーターフォール」構造を作り出す可能性がある。典型的なウォーターフォール構造では、契約上複数の金融商品を結び付けることにより、各トランシェへの支払の優先順位を決めることで、信用リスクの集中が生じることになる。
本検討状況の整理の適用指針(案)には、このようなウォーターフォール構造により発行される契約上リンクしているトランシェに対して、IFRS第9号を基礎とした取扱いを提案している。
すなわち、実務上不可能な場合を除き、企業は金融資産の基になっているキャッシュ・フロー特性を評価し、そうした金融資産の信用リスクに対するエクスポージャーを原商品プールと比較して評価するために、原商品プールまで遡らなければならないとされている。また、原商品プールまで遡ることが実務上不可能な場合には、企業は分類対象の金融資産を公正価値で測定するものとして分類しなければならないとされている。
Ⅴ.おわりに
本検討状況の整理では、IFRS第9号を基礎として金融資産の分類及び測定の方向性を示しているが、従来の我が国の会計の考え方や取扱いと大きく異なる側面もあり、一部の事項について一層の検討を要するとの意見もある。このため、そうした事項のうち特に重要と考えられる点を質問として掲げている。ASBJでは、本検討状況に寄せられるコメントも参考に、金融商品会計基準等の見直しのとりまとめに向けた検討を続けていく予定である。
脚注
1 本検討状況の整理の本文については、以下のASBJウェブサイトを参照https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/summary_issue/kinsho-kentojokyo/ 2 一方、FASB公開草案では、これと異なる測定モデルが提案されている。すなわち、金融商品は公正価値で測定され、以下の要件を満たす場合に、その評価差額の特定部分をその他の包括利益で認識することができるとされている。
(a)満期日に元本が返済または決済される負債性金融資産である。
(b)第三者への売却を目的としてではなく、契約上のキャッシュ・フローを回収または、支払うことを目的に負債性金融商品を保有する事業戦略である。
(c)主契約から区分して会計処理することが求められることとなる複合金融商品でない。
このようなFASB公開草案の提案は、金融商品の契約キャッシュ・フローの特徴や、契約キャッシュ・フローの回収を目的とする事業戦略を考慮する点で、IFRS第9号の償却原価測定の分類に類似する。しかし、その場合であってもFASBは公正価値情報と償却原価情報の両方を提供すべきと考え、IFRS第9号と異なり、FASB公開草案では、金融商品を公正価値で測定することを提案している。
「金融商品会計基準(金融資産の分類及び測定)の見直しに関する検討状況の整理」について
企業会計基準委員会 専門研究員 高橋由彦
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成22年8月16日に「金融商品会計基準(金融資産の分類及び測定)の見直しに関する検討状況の整理」(以下「本検討状況の整理」という。)を公表し、本年11月30日までコメントを募集している(脚注1)。本稿では本検討状況の整理の概要について解説するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅱ.本検討状況の整理の目的
ASBJは、現在、国際会計基準審議会(IASB)との間で合意した「会計基準のコンバージェンスの加速化に向けた取組みへの合意(東京合意)」(平成19年8月)の趣旨を踏まえ、プロジェクト計画表に従い、金融商品会計の現行基準の見直しに向けた検討を進めている。本検討状況の整理は、そのプロジェクトの一環として、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下「金融商品会計基準」という。)及びこれに関連する適用指針の取扱いを見直すにあたり必要な内容を整理することを目的としている。
平成21年5月にASBJが公表した「金融商品会計の見直しに関する論点の整理」(以下「論点整理」という。)では、金融商品会計の範囲(【論点1】)、金融商品の測定(【論点2】)、ヘッジ会計(【論点3】)を論点として掲げた。本検討状況の整理では、【論点1】のうち金融商品の定義等に関連する金融商品の範囲、及び【論点2】のうち金融資産の分類及び測定(減損(貸倒引当金又は貸倒損失)を除く。)を扱っている。
Ⅲ.本検討状況の整理の公表の背景
我が国における金融商品に関する会計基準等としては、ASBJから金融商品会計基準及び関連する適用指針等が公表されており、また、日本公認会計士協会から「金融商品会計に関する実務指針」(以下「金融商品実務指針」という。)及び「金融商品会計に関するQ&A」が公表されている。
一方、IASBと米国財務会計基準審議会(FASB)は、平成18年2月に公表した会計基準のコンバージェンスに向けた作業計画(MoU)の中で金融商品会計に関する現行基準の見直しを取り上げ、従来から、見直しに向けた作業を進めてきている。特に、昨今の金融危機への対応の一環として主要20か国・地域(G20)首脳会合から要請を受けたこと等を踏まえ、その検討を加速している。IASBは、この見直し作業を大きく4つ(①金融資産の分類及び測定、②金融負債の分類及び測定、③減損(貸倒引当金又は貸倒損失)、④ヘッジ会計)に分割し、最初のフェーズである金融資産の分類及び測定について、平成21年11月に国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」(以下「IFRS第9号」という。)の公表を行った。FASBにおいても、分類及び測定、減損(貸倒引当金又は貸倒損失)、ヘッジ会計を包括する公開草案「デリバティブ及びヘッジ(Topic 815)並びに金融商品(Topic 825):金融商品に関する会計処理、並びに、デリバティブ金融商品及びヘッジ活動に関する会計処理の改訂」(以下「FASB公開草案」という。)を平成22年5月に公表している。
ASBJは、現在、東京合意の趣旨も踏まえ、プロジェクト計画表に従い、金融商品会計の現行基準の見直しに向けた検討を進めている。平成21年5月には「金融商品会計の見直しに関する論点の整理」を公表したが、本検討状況の整理は、当該論点整理に対する意見を踏まえるとともに、その後IASB及びFASBの議論が進む中で論点整理公表時から大きく環境が変化していることも考慮して、金融商品の範囲、金融資産の分類及び測定に関して検討の中間段階においてその方向性を示すものとして公表している。本検討状況の整理の金融資産の分類及び測定に関しては、IFRS第9号とのコンバージェンスを念頭に置いているが、会計基準(案)及び適用指針(案)に分けて内容を整理する中で、それらを我が国の会計上の取扱いとして受け入れるにあたり検討すべき観点を提供している。
Ⅳ.会計基準(案)及び適用指針(案)の概要
1.金融商品の範囲 本検討状況の整理では、金融商品の定義は、IFRSとほぼ同様であることから、当面、現行の取扱いを維持することが考えられるとしている。
ただし、金融資産、金融負債及びデリバティブの定義は、金融商品会計基準においては商品名の列挙により行われ、金融商品実務指針において定義が補足されている。このため、本検討状況の整理の会計基準(案)では、この定義の仕方を変更し、金融資産、金融負債及びデリバティブをその特徴により定義し、商品名を例示することが考えられるとしている。
また、論点整理では、デリバティブの特徴の1つとされる純額決済性をIFRSとの相違の1つとして取り上げ、デリバティブの定義や特徴について見直すべき点がないかどうか、意見を募ったが、コメントも踏まえ、本検討状況の整理では、コンバージェンスの観点からIFRSに合わせて削除することが考えられるとしている。
2.金融資産の分類及び測定の基本的なモデル 本検討状況の整理で示す金融資産の分類及び測定モデルの全体像を図表1に掲げる。
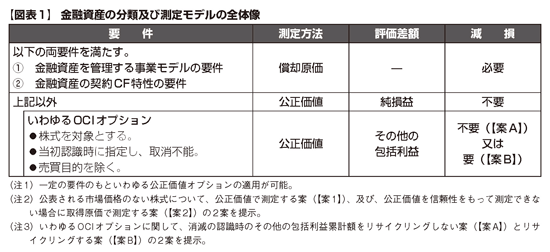
金融資産の分類及び測定に関して、本検討状況の整理はIFRS第9号を基礎として、主な分類を償却原価測定の分類及び公正価値測定の分類の2つとする混合測定属性アプローチを採用している。
① すなわち、原則として、金融資産は、次の両方の要件を満たす場合に、当初認識後、償却原価で測定するものとして分類され、それ以外の場合は、公正価値で測定するものとして分類することが考えられるとしている。契約キャッシュ・フローを回収するために資産を保有するという目的を有する事業モデルに基づいて、資産が保有されている(金融資産を管理する事業モデルの要件)。
② 金融資産の契約条件により特定の日にキャッシュ・フローが生じ、そのキャッシュ・フローが元本及び元本残高に対する利息の支払に限られる(金融資産の契約キャッシュ・フロー特性の要件)。
このように、①「金融資産を管理する事業モデルの要件」、及び、②「金融資産の契約キャッシュ・フロー特性の要件」により、金融資産を分類する考え方は、IASBが平成21年7月に公表した公開草案「金融商品:分類及び測定」で提案した基本的な考え方がIFRS第9号に引き継がれたものである。
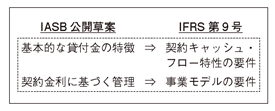
ASBJでは、IASBにおける検討の経緯やASBJを含む様々な意見を検討し議論を経てIFRS第9号が確定した経緯等を踏まえ、本検討状況の整理は、主な分類を償却原価測定の分類及び公正価値測定の分類の2つとする混合測定属性アプローチを採用し、償却原価測定を適用する金融資産を、金融資産を管理する事業モデル及び金融資産の契約キャッシュ・フロー特性の2要件により分類することが考えられるとしている(脚注2)。
① 「金融資産を管理する事業モデルの要件」における事業モデルは、個々の金融商品に関する経営者の意図に左右されるものではなく、それらの集合としてのレベルで判断されるとしている。また、契約キャッシュ・フローを回収するという事業モデルであっても、すべてを満期まで保有する必要はなく、途中での売却は必ずしも否定されていない。ただし、売却がしばしば実行される場合には、契約キャッシュ・フローを回収するという目的と整合しているか吟味する必要があるとされている。
② 「金融資産の契約キャッシュ・フロー特性の要件」における利息は、特定の期間における元本残高に関する貨幣の時間価値及び信用リスクへの対価となるものとすることが考えられるとしており、一部の金融資産の契約キャッシュ・フロー特性であるレバレッジは、契約キャッシュ・フローの変動性を高めるため、利息としての経済的特徴を有しないとされている。
なお、現行の満期保有目的の債券も償却原価で測定されるが、この債券に対しては、満期までに売却又は保有目的区分の変更を行った場合、その後2事業年度の間、満期保有目的の債券の分類を設けることができないとする定めがあり、国際的には、テインティング・ルールと呼ばれている。一方で、IFRS第9号では、金融資産を管理する企業の事業モデル及び当該金融資産の契約キャッシュ・フロー特性に基づいた分類は測定に関する明確な論拠を示すものであること、テインティング・ルールと同様の定めを設けることによって適用上の複雑性が増すことなどを勘案し、償却原価測定の分類の金融資産にこのような取扱いを設けないこととした。
本検討状況の整理では、IFRS第9号がテインティング・ルールを設けなかった上記の趣旨や、テインティング・ルールの結果、要件に照らして適切に分類できなくなることを踏まえ、テインティング・ルールを設けないIFRS第9号の取扱いを基礎としている。
3.公正価値測定の選択肢(いわゆる公正価値オプション) IFRS第9号では、事業モデル及び契約キャッシュ・フロー特性の2要件にかかわらず、公正価値で評価し、評価差額を純損益とする選択肢が設けられており(いわゆる公正価値オプション)、当初認識時に指定しその後の取消しは認められないこととされている。その要件を、このような指定を行わなければ資産若しくは負債の測定、又は資産若しくは負債に関する純損益の認識を異なる基準で行うことによって生じるであろう測定又は認識に関する不整合(いわゆる会計上のミスマッチ)が、その指定を行うことによって取り除かれる又は大幅に削減されることとしている。
本検討状況の整理の会計基準(案)でも、2の基本的な取扱いにかかわらず、金融資産を公正価値で測定し評価差額を純損益とするとの指定を、当初認識時に限り許容することが考えられるとしている。その条件として、このような指定を通じて、資産若しくは負債の測定、又は資産若しくは負債に関する純損益の認識に生じる不整合(いわゆる会計上のミスマッチ)が、取り除かれる又は大幅に削減される場合に限ることが考えられるとしている。
公正価値オプションは、このように、会計上のミスマッチを解消し複雑な測定を簡素化するとの利点がある一方で、論点整理に対するコメントでも指摘されたように、採用される分類モデルと異なる測定が恣意的に選択される懸念がある。ただし、こうした懸念に対しては、IFRS第9号の公正価値オプションは、恣意性を排除するため、会計上のミスマッチ解消の適格要件、当初認識時の指定及び事後の取消禁止など、その自由度を制限する取扱いが設けられている。
これまでASBJは公正価値オプションに必ずしも肯定的ではなかったが、公正価値オプションの利点や欠点、また、その欠点を是正するための対応等を総合的に勘案すると、この点に関するコンバージェンスを否定する程のものではないとも考えられることから、本検討状況の整理においては、IFRS第9号と同様に、会計上のミスマッチの解消又は大幅な削減を要件として、この指定を認めることとしている。
4.公表される市場価格のない株式の分類 株式への投資については、2の基本的な取扱いに従えば、通常は公正価値で測定するものとして分類することとなるが、公表される市場価格のない株式の分類については、次の案が考えられるとしている。【案1】は、2の基本的な取扱いに従い、公正価値で測定するものとして分類するというものである。【案2】は、2の基本的な取扱いにかかわらず、償却原価測定、公正価値測定の分類に、取得原価測定の分類を追加するというものである。すなわち、公表される市場価格のない株式について、公正価値を信頼性をもって測定できない場合には、2の基本的な取扱いにかかわらず、取得原価で測定する分類を追加するというものである。
そもそも本検討状況の整理は、特に金融資産の分類及び測定に関して、IFRS第9号を基礎としており、金融資産を管理する事業モデルとその契約キャッシュ・フロー特性に基づいて、償却原価測定又は公正価値測定のいずれかの分類とすることとしている。また、一定の金融資産に対しては、評価差額をその他の包括利益に認識する指定を許容することとしている。
しかしながら、IFRS第9号とのコンバージェンスを図っていく場合であっても、一部の事項について一層の検討を要するとの意見もある。ASBJでは、今後の審議の参考とするため、そうした事項のうち特に重要と考えられる点を質問として掲げているが、公表される市場価格のない株式の分類もその1つとされている。
【案1】の場合、株式に対する投資及び株式に関する契約は、すべて公正価値で測定しなければならない。しかし、適用指針(案)において、限定的ではあるが、取得原価が公正価値の適切な見積りとなる場合があるとされており、公正価値を算定するのに利用できる最近の情報が十分でない場合、又は、公正価値として測定できる範囲が広く当該範囲の中で取得原価が公正価値の最適な見積りを表す場合、取得原価が公正価値の適切な見積りとなる可能性があるとされている。
【案2】の場合、IFRSによる適用と我が国会計基準の適用の差異が小さくなることを意図して、現行のIAS第39号の取扱いを踏まえて「公正価値を信頼性をもって測定できない場合」との条件を付している。我が国では、「市場で売買されない株式について、たとえ何らかの方式により価額の算定が可能としても、それを時価(合理的に算定された価額)とはしない」(金融商品実務指針第63項)と扱われているが、「公正価値を信頼性をもって測定できる」とは我が国の会計基準のような市場での売買の有無を規準とするものでなく、IAS第39号の適用指針にあるように、合理的な公正価値の見積額の範囲での変動性が当該金融資産にとって重要でない、又は、その範囲内におけるさまざまな見積値の確率が合理的に評価でき公正価値の見積りに使用できる場合を意図している。
今後、ASBJでは、本検討状況の整理に対する意見も踏まえ、公表される市場価格のない株式の取扱いについて引き続き検討していくこととされている。
5.複合商品 組込デリバティブとは、デリバティブでない組込対象を含む複合商品の構成要素であり、それにより合成された商品のキャッシュ・フローの一部は、単独のデリバティブと同じように変化するものである。
IFRS第9号では、組込デリバティブを含む複合商品の組込対象がIFRS第9号の対象である金融資産の場合、複合商品全体に対して、複合商品でない通常の金融資産と同様の定めを適用しなければならないとされている。すなわち、金融商品全体について、事業モデル及び契約キャッシュ・フロー特性の2要件に照らして、償却原価測定の分類又は公正価値測定の分類のいずれかとされる。
金融商品会計基準では、複合商品を(a)払込資本を増加させる可能性のある部分を含むものと(b)その他のもの、に分けて定めているが、本検討状況の整理では、いずれの場合も、このようなIFRS第9号の取扱いを基礎とする取扱いによることとしている。すなわち、組込デリバティブを含む複合商品の組込対象が金融資産の場合、複合商品全体について、事業モデル及びキャッシュ・フロー特性の2要件に照らして、償却原価測定の分類又は公正価値測定の分類のいずれかとすることが考えられるとしている。
なお、転換社債型新株予約権付社債は、以前の転換社債と経済的実質が同一であることから、取得者側では1つの会計単位として扱われ、上述の考え方から公正価値測定の分類になると考えられる一方で、転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債については、払込資本を増加させる可能性のある部分とそれ以外の部分が同時に各々存在し得ることから、各々が別の金融商品として、それぞれの部分に区分して処理することが考えられるとしている。
6.分類の変更 IFRS第9号では、企業が金融資産を管理する事業モデルを変更した場合に、企業は影響を受ける金融資産のすべての分類を変更することとされている。分類を変更する場合、変更日から将来に向かって適用しなければならないとしている。当初IASB公開草案では、分類の変更を禁止することを提案していたが、ほぼすべてのコメントが、金融資産をその管理方法に基づいて分類するアプローチと整合的でないとして、提案に反対した。この結果、IASBはこうした主張を受け入れ、事業モデルを変更した場合に分類の変更を要求することとした。
本検討状況の整理では、IFRS第9号の取扱いを基礎として、企業が金融資産を管理する事業モデルを変更した場合に、企業は影響を受ける金融資産のすべての分類を、変更日から将来に向かって適用することとしている。この場合の分類変更日は、事業モデル変更の翌事業年度の期首とし、分類変更日から将来に向かって適用することが考えられるとしている(図表2参照)。
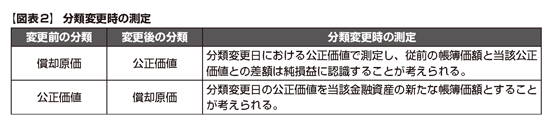
本検討状況の整理の適用指針(案)では、こうした事業モデルの変更は極めて稀にしか起こらないと考えられ、企業の経営者によって、外的又は内的変化の結果に基づいて判断されなければならず、かつ企業の営業にとって重要で、外部当事者に対して実証できるものでなければならないとされている。
なお、「変更日」として、本検討状況の整理では、翌事業年度の期首としている。この点に関して、ASBJの議論では、事業モデルの変更時期と異なる時期に分類を変更することとなり、それまでの間、事業モデルと整合しない分類となるとの懸念が示された。加えて、我が国では四半期報告の制度が導入されており、翌事業年度まで変更を待つ必要があるのかよく検討すべきであるとの意見もあったことから、今後、この点に関して、引き続き検討することが考えられるとしている。
7.株式への投資に関するその他の包括利益での評価差額の認識(いわゆるOCIオプション) 本検討状況の整理では、公正価値測定の分類の金融資産の評価差額は、純損益で認識することが考えられるとしている。しかし、一部の金融商品への投資は、投資価値の増加を目的とするものではないため、その投資の公正価値による評価差額を公正価値の変動時にそのまま純損益に反映することは企業の業績を示さない可能性があるとの理由から、IFRS第9号のOCIオプションと同様に、一定の株式について、公正価値測定の評価差額をその他の包括利益に認識する取扱いを設けることが考えられるとしている。
すなわち、株式への投資に関して、公正価値の変動により利益を得ることを目的とする(売買目的)場合を除き、評価差額をその他の包括利益で認識するとの指定を許容することが考えられ、この場合の指定は、当初認識時に行い、その後、取消不能とすることが考えられるとしている。
この指定による場合、IFRS第9号のOCIオプションと同様に、消滅の認識時点でその他の包括利益累計額をリサイクリングしないことが考えられるが、これまでの我が国の会計慣行等に大きな影響を及ぼすため、リサイクリングを維持すべきとの意見も多い。本検討状況の整理では、OCIオプションにおけるリサイクリングの禁止はコンバージェンス上の重要な問題の1つであると認識し、特段の方向性を設けず、リサイクリングを行わない案(【案A】)及びリサイクリングを行う案(【案B】)の2つの考え方を示すこととしている。
これに関連して、本検討状況の整理では、コンバージェンスの観点から連結財務諸表においてリサイクリングを禁止したとしても、当面、個別財務諸表では、これまでの会計慣行やその他の観点から、リサイクリングを維持する可能性を検討すべきとの意見のあったことも紹介されている。
今後、ASBJでは、本検討状況の整理に対する意見も踏まえ、リサイクリングを禁止すべきか否かについて引き続き検討していくこととしている。
8.個別財務諸表における子会社及び関連会社に対する株式の取扱い 子会社及び関連会社に対する株式への投資は、定義上は金融資産に該当する。このため、現行の金融商品会計基準では、子会社株式及び関連会社株式をその範囲に含めている。しかし、連結財務諸表上は、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」が適用されるため、金融商品会計基準の取扱いは、実質的に、個別財務諸表に限定されている。
子会社及び関連会社に対する株式の投資は、事業投資の性質を有し、子会社の支配、関連会社への重要な影響を通じてそれぞれの事業活動に係っているとも言えることから、従前から、金融商品会計の範囲として扱うべきか否かについて議論があった。また、その測定についても、子会社株式及び関連会社株式に含まれるのれん相当分が個別財務諸表上残ることとなる、減損のアプローチが個別財務諸表と連結財務諸表で異なるため個別財務諸表と連結財務諸表の測定の整合性が図られていない、との指摘があった。
個別財務諸表における子会社及び関連会社株式の取扱いに関しては、我が国の課題として検討する必要があるが、IFRSの取扱いも参考に、次のようなアプローチが考えられるとしている。
① 会計基準(案)の範囲に含め、取得原価とする。
② 会計基準(案)の範囲に含めるが、子会社株式及び関連会社株式に特別の定めを設けない。
③ 会計基準(案)の範囲に含めず、別の会計基準を改訂し、取得原価とする。
④ 会計基準(案)の範囲に含めず、別の会計基準を改訂し、持分法とする。
本検討状況の整理の会計基準(案)では、既存の金融商品会計基準の取扱いを踏襲し、①のように子会社株式及び関連会社株式を会計基準(案)の範囲とし、取得原価とすることとしているが、今後、本検討状況の整理に対するコメントも踏まえて、引き続き、個別財務諸表における子会社及び関連会社に対する株式の取扱いを検討していくことが考えられるとしている。
9.表示及び注記事項 本検討状況の整理では、IAS第1号「財務諸表の表示」及びIFRS第7号「金融商品:開示」のうち、IFRS第9号を受けて改訂された部分を基礎として、金融商品会計基準の既存の取扱いに付け加える内容を示している。これらの表示及び注記事項は、IFRS第9号の分類に一定の自由度を設けることの見合いで導入されたものであることから、本検討状況の整理においても、会計基準(案)での分類とセットで議論するとしている。
表示に関しては、①償却原価測定の分類の金融資産の消滅の認識時の利益又は損失、及び、②会計基準(案)に従って金融資産の分類を変更した結果生じる利益又は損失、をそれぞれ独立して掲記することが考えられるとしている。
また、注記事項に関しては、評価差額をその他の包括利益に含める指定を行う場合(OCIオプションの場合)、会計基準(案)に従って金融資産の分類を変更した場合、等について、一定の事項を注記することが考えられるとしている。
10.外貨建取引等会計処理基準への影響 平成11年に改正された「外貨建取引等会計処理基準」(以下「外貨建基準」という。)は、現行の金融商品会計基準の有価証券の分類及び測定を反映した取扱いとなっている。このため、本検討状況の整理では、会計基準(案)で示される取扱いを受けて、外貨建基準について想定される変更をまとめている。
例えば、外貨建債券でその他有価証券に分類されるものは、現行では、原則として金融商品会計基準の評価差額に関する処理方法に従うものとされており、償却原価に係る換算差額も含めて換算差額全体をその他の包括利益に含めることとなるが、外国通貨による公正価値の変動に係る換算差額を除いて為替差損益として処理できるとされている。
これに対して、会計基準(案)による場合、公正価値又は償却原価のいずれかで測定されるが、いずれの場合も、決算時の為替相場による換算差額は純損益に反映することが考えられるとされている。
また、外貨建株式でその他有価証券に分類されるものは、現行では、原則として金融商品会計基準の評価差額に関する処理方法に従うものとされており、取得原価に係る換算差額も含めて換算差額全体をその他の包括利益に含めることとなる。
これに対して、会計基準(案)の原則的な方法(公正価値で測定し評価差額を純損益に認識する)による場合、公正価値で測定されるが、決算時の為替相場による換算差額は、原則として、純損益に反映することが考えられる。ただし、評価差額をその他の包括利益に含める指定を行う場合(OCIオプションの場合)には、その評価差額に決算時の為替相場による換算差額を含めることが考えられるとされている。
11.契約上リンクしているトランシェの取扱い 仕組投資ビークルは、様々なトランシェを発行し、様々なトランシェの保有者に対して発行者による支払の優先順位を決める「ウォーターフォール」構造を作り出す可能性がある。典型的なウォーターフォール構造では、契約上複数の金融商品を結び付けることにより、各トランシェへの支払の優先順位を決めることで、信用リスクの集中が生じることになる。
本検討状況の整理の適用指針(案)には、このようなウォーターフォール構造により発行される契約上リンクしているトランシェに対して、IFRS第9号を基礎とした取扱いを提案している。
すなわち、実務上不可能な場合を除き、企業は金融資産の基になっているキャッシュ・フロー特性を評価し、そうした金融資産の信用リスクに対するエクスポージャーを原商品プールと比較して評価するために、原商品プールまで遡らなければならないとされている。また、原商品プールまで遡ることが実務上不可能な場合には、企業は分類対象の金融資産を公正価値で測定するものとして分類しなければならないとされている。
Ⅴ.おわりに
本検討状況の整理では、IFRS第9号を基礎として金融資産の分類及び測定の方向性を示しているが、従来の我が国の会計の考え方や取扱いと大きく異なる側面もあり、一部の事項について一層の検討を要するとの意見もある。このため、そうした事項のうち特に重要と考えられる点を質問として掲げている。ASBJでは、本検討状況に寄せられるコメントも参考に、金融商品会計基準等の見直しのとりまとめに向けた検討を続けていく予定である。
脚注
1 本検討状況の整理の本文については、以下のASBJウェブサイトを参照https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/summary_issue/kinsho-kentojokyo/ 2 一方、FASB公開草案では、これと異なる測定モデルが提案されている。すなわち、金融商品は公正価値で測定され、以下の要件を満たす場合に、その評価差額の特定部分をその他の包括利益で認識することができるとされている。
(a)満期日に元本が返済または決済される負債性金融資産である。
(b)第三者への売却を目的としてではなく、契約上のキャッシュ・フローを回収または、支払うことを目的に負債性金融商品を保有する事業戦略である。
(c)主契約から区分して会計処理することが求められることとなる複合金融商品でない。
このようなFASB公開草案の提案は、金融商品の契約キャッシュ・フローの特徴や、契約キャッシュ・フローの回収を目的とする事業戦略を考慮する点で、IFRS第9号の償却原価測定の分類に類似する。しかし、その場合であってもFASBは公正価値情報と償却原価情報の両方を提供すべきと考え、IFRS第9号と異なり、FASB公開草案では、金融商品を公正価値で測定することを提案している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























