解説記事2011年03月07日 【実務解説】 税制から見た新公益法人制度の留意点(4)(2011年3月7日号・№393)
実務解説
税制から見た新公益法人制度の留意点(4)
税理士法人アズール 公認会計士・税理士 長谷川敏也
Ⅳ.法人区分の移行に伴う課税問題
1.法人区分の変更のある場合とみなし事業年度 公益三法の規定においては、法人の区分の変更に伴い、事業年度が区切られる場合がある。例えば、一般社団・財団法人が、行政庁から公益認定を受けたときには、貸借対照表などの計算書類を事業年度開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間と公益認定を受けた日からその事業年度の末日までの期間とに分けて作成することとされている(認定法規則38の2)。
法人税法においても、図表1のとおり、みなし事業年度が定められている。例えば、公益法人等が普通法人に該当することとなった場合又は普通法人が公益法人等に該当することとなった場合には、定款等で定めた事業年度の開始の日からその該当することとなった日の前日までの期間及びその該当することとなった日から定款で定めた事業年度終了の日までの期間をそれぞれ1事業年度とみなすこととされている(法法13①、14二十)。
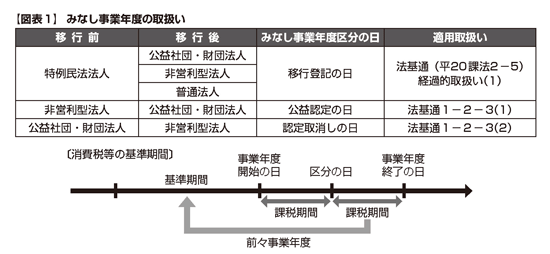
事業年度が区分されたときは法人の決算確定手続き及び確定申告書の提出が必要(納税義務がある法人に限る)である。認定・認可手続きの流れにおいて、幾度も理事会等を開催しなければならず、法人に負担のかかる制度であるので、スケジュール管理には留意が必要である。
特例民法法人の「該当することとなった日」は、行政庁の認定又は認可を受けた日ではなく、それぞれの移行の登記をした日となる。消費税においても同様である(基準期間につき図表1参照)。
なお、平成24年4月1日(日)は、たまたま行政機関の休日であり登記申請ができないので、みなし事業年度の取扱い上、何らかの手当てがされることを期待する。
2.収益事業課税 法人税法4条では、「内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合に限る。」とあり、法人税法上の収益事業は、法人税法施行令5条に特掲されている34業種(脚注1)である。なお、いわゆる実費弁償方式による業務等で確認を受けている業務は収益事業には該当しない(脚注2)。
一般に全所得課税の場合よりも収益事業課税のほうが納税者にとって有利であるとする見方が強いが、必ずしも有利でないことがあるので法人類型選択にあたっては留意が必要である(事例1参照)。
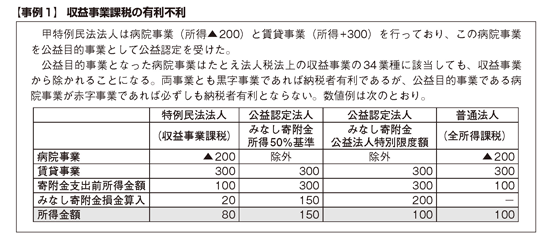
3.法人区分の移行に伴う累積所得金額の益金算入 公益法人等が普通法人等に移行する場合には、課税所得の範囲に変更が生じ、収益事業課税から全所得課税(非営利型法人以外の法人(普通法人)該当)となった場合には、原則として公益目的以外に特定の者に分配されないことを前提に非課税とされてきた所得の累積額について構成員に分配することも可能となる(脚注3)。
そこでこのような場合には、非課税とされていた前提が存在しなくなったことから、この時点で全所得課税が行われていたとしたならば課税されていたであろう部分について課税所得を構成するものとされた(そのケースは図表2のとおり)。いわゆる清算的な課税が行われるので、留意が必要である。
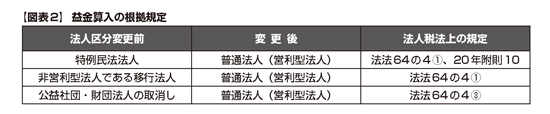
しかし、公益法人等である法人が普通法人となるとはいっても、法人税法4条、7条において収益事業以外の事業から生じた所得に対しては法人税を課さないと規定していたのであるから、公益法人制度が変わったからといって、過去の公益法人等の時代の収益事業以外の事業から生じた利益の留保額に対して、法人設立時まで遡って遡及的に所得課税を行うというのは理論的ではない(脚注4)。
なお、この法人税法64条の4は、当面は、特例民法法人等が普通法人たる一般社団・財団法人へ移行する場合のことであるから、特例民法法人が非営利型法人へ移行する場合や、公益社団・財団法人へ移行する場合には、課税範囲が変わらず、この累積所得金額についての課税問題は生じない。しかし、公益社団・財団法人の公益認定取消しや非営利型法人の否認があった場合にも生じる課税リスクであるので、あらかじめ留意しておく必要がある(本稿第1回図表7(本誌389号27頁)参照)。
ここでは、図表2の「公益社団・財団法人の公益認定取消し」に伴う普通法人への移行を下記4で、「特例民法法人」が普通法人に移行する場合及び「非営利型法人である移行法人(移行の認可を受けて移行の登記をした一般社団・財団法人のうち公益目的支出計画の実施の完了の確認を受けていない法人)」が普通法人となる場合を下記5で解説する。
4.公益認定取消しに伴う課税問題 (1)「公益目的取得財産残額」の贈与 公益法人は、公益認定基準に抵触した場合(認定法29②)、公益法人が自ら一般社団・財団法人となるべく申請した場合や役員が認定法に規定されている罪で罰金刑に処せられた場合等に、公益認定の取消しがなされ、「公益目的取得財産残額」の贈与という事態が生じる(認定法29①)。公益社団・財団法人に移行した後に公益認定が取り消されると、公益目的取得財産の残額に相当する金額の贈与が強制され(認定法30)、法人の財産を失ってしまう。
認定法上は、取消しの日から1か月以内に公益目的取得財産残額を他の公益法人等に贈与すべきとし、取消しの日における金額の確定を3か月以内としている(認定法規則50)。なお、1か月以内に贈与契約が成立していないときは国又は都道府県が公益目的取得財産残額に相当する額の金銭について認定取消法人から受贈されたとみなすことになっているので留意が必要である(認定法30①)。
(2)「公益目的取得財産残額」の範囲及び計算 したがって、「公益目的取得財産残額」の範囲及び計算については十分留意する必要がある。公益目的取得財産残額は法人の意思と宣言によって確定するからである。
公益目的取得財産残額は、毎事業年度末における公益目的事業財産の未使用残高であり、公益目的保有財産と公益目的増減差額との合計額で、毎事業年度末、計算の上行政庁に報告するものである(認定法30、認定法規則48)(上掲参照)。
このイおよびロと、貸借対照表内訳表、並びに財産目録は密接な関係にあるが、正確には公益法人の事業報告書(定期提出書類)別表Hにて計算することになり、損益計算書(公益目的事業会計)から誘導的に算出されることとなる。
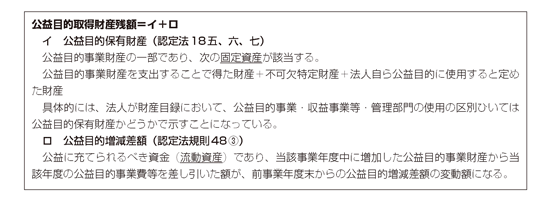
(3)公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算 公益社団・財団法人が行政庁から公益認定の取消しを受けたことにより非営利型法人以外の法人に該当することとなった場合には、当該取消しの日以降に公益目的のために支出されることが義務付けられている公益目的取得財産残額を累積所得金額から控除することとされている(法令131の5①一)。
もっとも、公益社団・財団法人に移行した後に公益認定が取り消された場合には、公益目的取得財産の残額の贈与(認定法30)が生じるので、控除するのは当然のことであり、公益三法上は債務であるので、法人税法上の簿価純資産額から単純に差し引く。なお、この贈与により生じた損失の額は損金に算入しない(法令131の5④)。寄附金損金不算入の特例(法法37⑦)の対象ともならない。
過去の収益事業以外の事業から生じた所得の累積額が大きい場合には、(1)の贈与に加えて、一時に多額の課税が生じることとなる(下記算式参照)。
(4)公益認定の取消リスクへの対応
① 役員を原因とする公益認定取消事由の整理 法人法には役員(理事及び監事)、会計監査人、評議員について資格要件がある(脚注5)。公益認定法人は、公益認定を受けた一般社団・財団法人であるので、この資格要件は公益認定法人にも妥当する。そしてその上で、認定法上、公益認定基準及び欠格事由に役員に関する規定がある。役員に関連する公益認定取消事由は以下のとおりである(認定法29)。
イ)役員が他の法人の業務を行う理事(脚注6)であり、当該他の法人が公益認定取消しをされた場合(いわゆる連座制(脚注7))
要件は以下の事項をすべて満たした場合。
・認定法29①②で他の法人が公益認定を取り消される
・原因事実のあった日以前1年以内にその公益法人の業務執行理事であった者
・取消しから5年以内
ロ)役員が犯罪行為や違法行為に関わって有罪判決を受けた場合(以下「欠格事由による取消し」という)や暴力団員にあたること(脚注8)。
② 公益認定取消しの手続き 公益認定取消しの手続きは、図表3のとおりである。
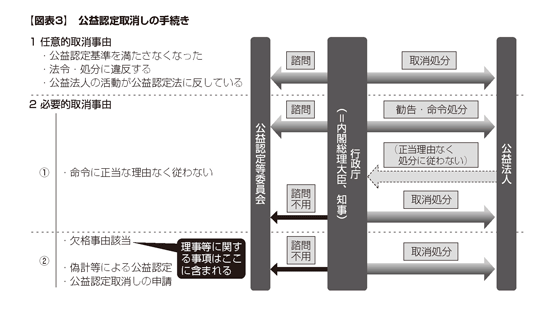
役員に関する公益認定取消事由があった場合、必ず取り消されることとなっている(認定法29①、以下「必要的取消事由」という)。そのため、取消事由の有無自体については争いうるが、取り消すことができる場合(認定法29②、以下「任意的取消事由」という)とは異なり、事前に是正についての勧告などは予定されていない。そのため、法人が気づかないうちに公益認定取消事由が発生しているという問題も生じうる。
③ 取消回避のための方法 以上のとおり、公益法人は法人自身の事由以外でも公益認定取消しを受けうることから、リスクコントロールを行うことが考えられる(脚注9)。
イ)情報収集及び欠格事由に該当した場合の解任の方法
①のイ)の連座制に対しては、
ⅰ 役員就任時に他に公益法人の理事等に就任していないかを確認し、
ⅱ 就任後
・新たに他の公益法人の理事等への就任があった場合
・他の役員を行っている法人に公益認定取消しがありうる事態が生じた場合
には自法人に届出を行うよう誓約させる
その上で、必要であれば解任などの手続きをとるという方法が考えられる。
ロ)リスクを避ける方策
もっとも、たしかに解任決議を行うことも考えられるが、不祥事であるために理事等が報告を避けた場合やこのような手続きを急遽行うことができない場合もありうる。このリスクを避けるための方策として以下の2つがありうる。
① 事前の辞任届の差入れ(停止条件つき退任届)
② 自動失職の定款規定
なお、これらの方策は例えば事前の条件付辞任届の差入れと定款規定というように組み合わせて使うこともできる。また、変更手続きが煩雑で公開されるべき定款にこのような失職条項を記載することを避けるため、役員規定に記載するということも考えられる。
5.普通法人(営利型法人)となる場合の課税問題(移行時点) ①特例民法法人が普通法人に移行する場合、②非営利型法人である移行法人(移行の認可を受けて移行の登記をした一般社団・財団法人のうち、公益目的支出計画の実施の完了の確認を受けていない法人)が営利型法人である移行法人(普通法人)となる場合の2つのケースでは、累積所得金額の計算に当たって、移行日における「修正公益目的財産残額」と「資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額」とのうちいずれか少ない金額(以下「当初調整公益目的財産残額」)を累積所得金額から控除し、累積所得金額から控除しきれないときは、その控除しきれない金額を累積欠損金額とみなすこととなる(法法64の4③、法令131の5①三・②)。
このうち「修正公益目的財産残額」は、整備法上の「公益目的財産残額」と公益目的収支差額の収入超過額の合計額に、時価評価資産の評価損の額を加算し、時価評価資産の評価益の額を控除した金額となる(法令131の5①三イ、法規27の16の4①)(図表4参照)。
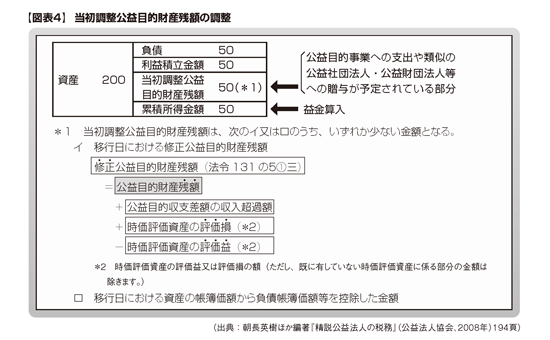
6.時価概念である公益目的財産額と当初調整公益目的財産残額
(1)公益目的財産額の算定 「公益目的財産額」とは、移行の登記をした日の前日(以下「算定日」という)における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に、一定の調整(時価評価)をして得た額をいう(整備法規則14①)。より具体的には、公益認定等ガイドラインⅡ-1(4)①公益目的財産額の算定方法について(整備法119①関係)において、「公益目的財産額の算定に必要な資産の評価に当たっては、過大な費用をかけることは適当でないと考えられるため」として、次のとおり規定されている。
① 土地の評価方法について 例えば、固定資産税評価額や不動産鑑定士が鑑定した価額などが考えられる。法人の保有する資産であって、移行後において当該法人が長期にわたり継続的に事業を行う場合にそれらの事業に継続して使用することが確実な資産(建物等の減価償却資産を含む)については、当該資産が継続して使用されることを前提に算定した額を評価額とすることができる。なお、土地及び建物を一体として評価する場合であっても、土地に係る算定額と建物に係る算定額を区分することが可能な場合は、それらを区分して申請することができる。
② 減価償却資産の評価方法について 建物等の減価償却資産については、時価評価資産に含めないものとする。ただし、不動産鑑定士による鑑定評価を妨げない。
③ 有価証券の評価方法について 上場されていることにより市場価格が容易に把握できる場合は、市場価格を用いた時価評価を行うものとする。市場性がない場合であっても評価を行うことが可能な場合は時価評価とする。なお、市場性がなく評価が困難な場合は当該有価証券の取得価額又は帳簿価額とする。
④ 美術品等その他の資産の評価方法について 法人において移行後も引き続き実施事業に使用するものは、時価評価が可能であっても帳簿価額とすることを認める。継続的に実施事業に使用する予定がないもの、売却の予定があるものについては、時価評価を行う。ただし、帳簿価額と時価との差額が著しく多額でないと法人において判断する場合や時価評価を行うことが困難な場合は、帳簿価額とすることを認める。
⑤ 引当金等について 負債(資産の控除を含む)として計上されている引当金(引当金に準ずるものを含む)については、公益目的財産額の算定から控除する。
また、会費等の積み立てによる準備金等(法令等により将来の支出又は不慮の支出に備えて設定することが要請されているもの)については、負債として計上されていない場合であっても、法人において合理的な算定根拠を示すことが可能である場合には、引当金と同様に公益目的財産額の算定から除くことができる。
⑥ 退職給付会計の導入に伴う会計基準変更時差異(脚注10)の扱いについて 費用処理期間を定めて当該期間にわたり費用処理を行っている法人にあっては、当該未処理額についても公益目的財産額の算定から控除することができる(この場合、未処理額の算定根拠などの資料の提出を求める)。なお、公益目的財産額の算定時に控除した未処理額について、移行後の各事業年度における費用処理の額は公益目的支出の額に算入しない。
(2)当初調整公益目的財産残額 以上のように、整備法上の「公益目的財産額」は時価概念であり、かつ純資産の部に保全が義務付けられている額、あるいは退職給付引当金の会計基準変更時差異も差し引く等の計算が認められているので、法人税法上そのまま採用できる概念ではない。
法人税法上は法人税法上の簿価へ修正(元に戻す)して控除することとなるため「修正公益目的財産残額」という。したがって用語こそ類似しているが、公益社団・財団法人に移行した後に公益認定が取り消された場合の「公益目的取得財産残額」とは、計算の難易度も概念も異なる。
「当初調整公益目的財産残額」は、会計上認識される資産と負債の差額である整備法上の純資産を基礎として算出されるものの、課税対象となる「累積所得金額」は、税制上認識される資産と負債等の差額として算出されることから(法令131の4①)差異が生じる。このことは、法人区分の変更に際して十分留意する必要がある(次号事例1参照)。
すなわち、公益法人会計基準では、たとえば賞与引当金、退職給付引当金、役員退職慰労引当金などは、通常の会計処理において負債として計上する(公益法人会計基準の運用指針12(1))が、法人税法上の負債には該当しない。このため、これら引当金は、「当初調整公益目的財産残額」の計算上は負債としてその減少項目となるが、累積所得金額の計算上は負債に該当せずその減少項目とはならないこととなる。
脚注
1 法人税法上の収益事業とは、次の34種類の事業を、継続して事業場を設けて営むことをいい、その収益事業の事業活動の一環として、あるいは関連して付随的に行われる行為も含まれる。
(1)物品販売業(2)不動産販売業(3)金銭貸付業(4)物品貸付業(5)不動産貸付業(6)製造業(7)通信業(8)運送業(9)倉庫業(10)請負業(11)印刷業(12)出版業(13)写真業(14)席貸業(15)旅館業(16)料理飲食業(17)周旋業(18)代理業(19)仲立業(20)問屋業(21)鉱業(22)土石採取業(23)浴場業(24)理容業(25)美容業(26)興行業(27)遊技所業(28)遊覧所業(29)医療保健業(30)技芸・学力教授業(31)駐車場業(32)信用保証業(33)無体財産権の提供業(34)労働者派遣業
2 【法人税基本通達15-1-28(実費弁償による事務処理の受託等)】
公益法人等が、事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合においても、当該業務が法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償(その委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことをいう。)により行われるものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね5年以内の期間とする。)を限って所轄税務署長の確認を受けたときは、その確認を受けた期間については、当該業務は、その委託者の計算に係るものとして当該公益法人等の収益事業としないものとする。
(注) 非営利型法人が1-1-11の確認を受けている場合には、本文の確認を受けたものとみなす。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律239条では、「残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。」「前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。」とある。
4 朝長英樹ほか編著『精説公益法人の税務』(公益法人協会、2008年)186頁に同趣旨。
5 役員の資格要件は法人法65①②、会計監査人の資格要件は法人法68(財団法人は評議員について法人法173①、役員及び会計監査人について法人法177で準用)。
6 FAQⅦ-②によると、ここでいう業務執行理事とは、代表理事及び取消原因となった事由の執行責任者たる理事に限られる。
なお、この前提となる問題として、業務執行理事は、一般法人法上複数の意味がある。
① 業務執行理事に選定された者(91①二)
② ①+代表理事(業務執行を予定されているため)
③ ②+②以外で業務執行を行ったことのある理事(113①二ロ、261①三(外部役員の定義の場合)。使用人兼務役員等が予定されうる)
FAQの記載でいう業務執行理事は少なくとも③の意味の業務執行理事であるので、後述する対応策において、他の公益法人の業務執行理事以上への選定ではなく理事に就任したことを把握しておく必要がある(なお、みなし役員の問題は今回は省く)。
7 公益法人が公益にそむく行為を行ったとして公益認定を取り消された場合、それを運営していた業務執行理事が公益にそむく行為を行ったものと考え、その者が理事を行っている他の公益法人も公益認定を取り消される。
8 この犯罪行為等の欠格事由の内容を見ると、以下のとおりに整理される。
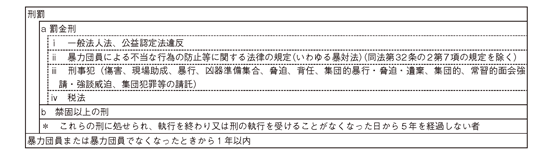
9 以下、富永さとる「公益認定取消しリスクとその回避策 理事・監事・評議員の欠格事由と失職条項」非営利法人786(2010年8月)号4頁を参考にした。
10 会計基準変更時において本来計上すべき引当金額の満額と実際に計上している引当金の差額をいう。会計基準変更時差異は、平成20年12月1日以後開始する最初の事業年度から12年以内の一定の年数にわたり定額法により費用処理をすることとなる。
税制から見た新公益法人制度の留意点(4)
税理士法人アズール 公認会計士・税理士 長谷川敏也
Ⅳ.法人区分の移行に伴う課税問題
1.法人区分の変更のある場合とみなし事業年度 公益三法の規定においては、法人の区分の変更に伴い、事業年度が区切られる場合がある。例えば、一般社団・財団法人が、行政庁から公益認定を受けたときには、貸借対照表などの計算書類を事業年度開始の日から公益認定を受けた日の前日までの期間と公益認定を受けた日からその事業年度の末日までの期間とに分けて作成することとされている(認定法規則38の2)。
法人税法においても、図表1のとおり、みなし事業年度が定められている。例えば、公益法人等が普通法人に該当することとなった場合又は普通法人が公益法人等に該当することとなった場合には、定款等で定めた事業年度の開始の日からその該当することとなった日の前日までの期間及びその該当することとなった日から定款で定めた事業年度終了の日までの期間をそれぞれ1事業年度とみなすこととされている(法法13①、14二十)。
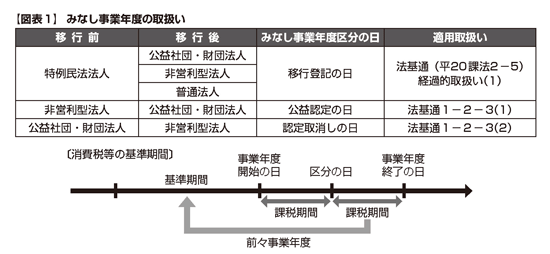
事業年度が区分されたときは法人の決算確定手続き及び確定申告書の提出が必要(納税義務がある法人に限る)である。認定・認可手続きの流れにおいて、幾度も理事会等を開催しなければならず、法人に負担のかかる制度であるので、スケジュール管理には留意が必要である。
特例民法法人の「該当することとなった日」は、行政庁の認定又は認可を受けた日ではなく、それぞれの移行の登記をした日となる。消費税においても同様である(基準期間につき図表1参照)。
なお、平成24年4月1日(日)は、たまたま行政機関の休日であり登記申請ができないので、みなし事業年度の取扱い上、何らかの手当てがされることを期待する。
2.収益事業課税 法人税法4条では、「内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合に限る。」とあり、法人税法上の収益事業は、法人税法施行令5条に特掲されている34業種(脚注1)である。なお、いわゆる実費弁償方式による業務等で確認を受けている業務は収益事業には該当しない(脚注2)。
一般に全所得課税の場合よりも収益事業課税のほうが納税者にとって有利であるとする見方が強いが、必ずしも有利でないことがあるので法人類型選択にあたっては留意が必要である(事例1参照)。
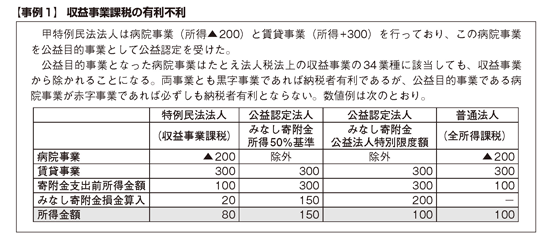
3.法人区分の移行に伴う累積所得金額の益金算入 公益法人等が普通法人等に移行する場合には、課税所得の範囲に変更が生じ、収益事業課税から全所得課税(非営利型法人以外の法人(普通法人)該当)となった場合には、原則として公益目的以外に特定の者に分配されないことを前提に非課税とされてきた所得の累積額について構成員に分配することも可能となる(脚注3)。
そこでこのような場合には、非課税とされていた前提が存在しなくなったことから、この時点で全所得課税が行われていたとしたならば課税されていたであろう部分について課税所得を構成するものとされた(そのケースは図表2のとおり)。いわゆる清算的な課税が行われるので、留意が必要である。
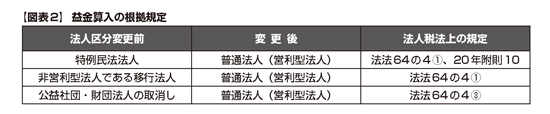
しかし、公益法人等である法人が普通法人となるとはいっても、法人税法4条、7条において収益事業以外の事業から生じた所得に対しては法人税を課さないと規定していたのであるから、公益法人制度が変わったからといって、過去の公益法人等の時代の収益事業以外の事業から生じた利益の留保額に対して、法人設立時まで遡って遡及的に所得課税を行うというのは理論的ではない(脚注4)。
なお、この法人税法64条の4は、当面は、特例民法法人等が普通法人たる一般社団・財団法人へ移行する場合のことであるから、特例民法法人が非営利型法人へ移行する場合や、公益社団・財団法人へ移行する場合には、課税範囲が変わらず、この累積所得金額についての課税問題は生じない。しかし、公益社団・財団法人の公益認定取消しや非営利型法人の否認があった場合にも生じる課税リスクであるので、あらかじめ留意しておく必要がある(本稿第1回図表7(本誌389号27頁)参照)。
ここでは、図表2の「公益社団・財団法人の公益認定取消し」に伴う普通法人への移行を下記4で、「特例民法法人」が普通法人に移行する場合及び「非営利型法人である移行法人(移行の認可を受けて移行の登記をした一般社団・財団法人のうち公益目的支出計画の実施の完了の確認を受けていない法人)」が普通法人となる場合を下記5で解説する。
4.公益認定取消しに伴う課税問題 (1)「公益目的取得財産残額」の贈与 公益法人は、公益認定基準に抵触した場合(認定法29②)、公益法人が自ら一般社団・財団法人となるべく申請した場合や役員が認定法に規定されている罪で罰金刑に処せられた場合等に、公益認定の取消しがなされ、「公益目的取得財産残額」の贈与という事態が生じる(認定法29①)。公益社団・財団法人に移行した後に公益認定が取り消されると、公益目的取得財産の残額に相当する金額の贈与が強制され(認定法30)、法人の財産を失ってしまう。
認定法上は、取消しの日から1か月以内に公益目的取得財産残額を他の公益法人等に贈与すべきとし、取消しの日における金額の確定を3か月以内としている(認定法規則50)。なお、1か月以内に贈与契約が成立していないときは国又は都道府県が公益目的取得財産残額に相当する額の金銭について認定取消法人から受贈されたとみなすことになっているので留意が必要である(認定法30①)。
(2)「公益目的取得財産残額」の範囲及び計算 したがって、「公益目的取得財産残額」の範囲及び計算については十分留意する必要がある。公益目的取得財産残額は法人の意思と宣言によって確定するからである。
公益目的取得財産残額は、毎事業年度末における公益目的事業財産の未使用残高であり、公益目的保有財産と公益目的増減差額との合計額で、毎事業年度末、計算の上行政庁に報告するものである(認定法30、認定法規則48)(上掲参照)。
このイおよびロと、貸借対照表内訳表、並びに財産目録は密接な関係にあるが、正確には公益法人の事業報告書(定期提出書類)別表Hにて計算することになり、損益計算書(公益目的事業会計)から誘導的に算出されることとなる。
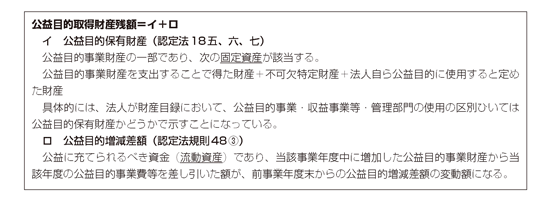
(3)公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算 公益社団・財団法人が行政庁から公益認定の取消しを受けたことにより非営利型法人以外の法人に該当することとなった場合には、当該取消しの日以降に公益目的のために支出されることが義務付けられている公益目的取得財産残額を累積所得金額から控除することとされている(法令131の5①一)。
もっとも、公益社団・財団法人に移行した後に公益認定が取り消された場合には、公益目的取得財産の残額の贈与(認定法30)が生じるので、控除するのは当然のことであり、公益三法上は債務であるので、法人税法上の簿価純資産額から単純に差し引く。なお、この贈与により生じた損失の額は損金に算入しない(法令131の5④)。寄附金損金不算入の特例(法法37⑦)の対象ともならない。
過去の収益事業以外の事業から生じた所得の累積額が大きい場合には、(1)の贈与に加えて、一時に多額の課税が生じることとなる(下記算式参照)。
| 【算式】 益金に算入すべき金額(累積所得金額) = 資産の帳簿価額-負債帳簿価額 -利益積立金額-公益目的取得財産残額 |
① 役員を原因とする公益認定取消事由の整理 法人法には役員(理事及び監事)、会計監査人、評議員について資格要件がある(脚注5)。公益認定法人は、公益認定を受けた一般社団・財団法人であるので、この資格要件は公益認定法人にも妥当する。そしてその上で、認定法上、公益認定基準及び欠格事由に役員に関する規定がある。役員に関連する公益認定取消事由は以下のとおりである(認定法29)。
イ)役員が他の法人の業務を行う理事(脚注6)であり、当該他の法人が公益認定取消しをされた場合(いわゆる連座制(脚注7))
要件は以下の事項をすべて満たした場合。
・認定法29①②で他の法人が公益認定を取り消される
・原因事実のあった日以前1年以内にその公益法人の業務執行理事であった者
・取消しから5年以内
ロ)役員が犯罪行為や違法行為に関わって有罪判決を受けた場合(以下「欠格事由による取消し」という)や暴力団員にあたること(脚注8)。
② 公益認定取消しの手続き 公益認定取消しの手続きは、図表3のとおりである。
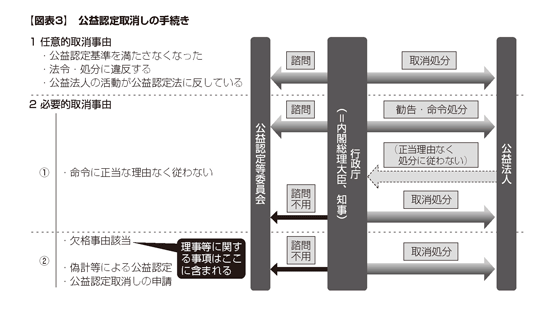
役員に関する公益認定取消事由があった場合、必ず取り消されることとなっている(認定法29①、以下「必要的取消事由」という)。そのため、取消事由の有無自体については争いうるが、取り消すことができる場合(認定法29②、以下「任意的取消事由」という)とは異なり、事前に是正についての勧告などは予定されていない。そのため、法人が気づかないうちに公益認定取消事由が発生しているという問題も生じうる。
③ 取消回避のための方法 以上のとおり、公益法人は法人自身の事由以外でも公益認定取消しを受けうることから、リスクコントロールを行うことが考えられる(脚注9)。
イ)情報収集及び欠格事由に該当した場合の解任の方法
①のイ)の連座制に対しては、
ⅰ 役員就任時に他に公益法人の理事等に就任していないかを確認し、
ⅱ 就任後
・新たに他の公益法人の理事等への就任があった場合
・他の役員を行っている法人に公益認定取消しがありうる事態が生じた場合
には自法人に届出を行うよう誓約させる
その上で、必要であれば解任などの手続きをとるという方法が考えられる。
ロ)リスクを避ける方策
もっとも、たしかに解任決議を行うことも考えられるが、不祥事であるために理事等が報告を避けた場合やこのような手続きを急遽行うことができない場合もありうる。このリスクを避けるための方策として以下の2つがありうる。
① 事前の辞任届の差入れ(停止条件つき退任届)
② 自動失職の定款規定
なお、これらの方策は例えば事前の条件付辞任届の差入れと定款規定というように組み合わせて使うこともできる。また、変更手続きが煩雑で公開されるべき定款にこのような失職条項を記載することを避けるため、役員規定に記載するということも考えられる。
5.普通法人(営利型法人)となる場合の課税問題(移行時点) ①特例民法法人が普通法人に移行する場合、②非営利型法人である移行法人(移行の認可を受けて移行の登記をした一般社団・財団法人のうち、公益目的支出計画の実施の完了の確認を受けていない法人)が営利型法人である移行法人(普通法人)となる場合の2つのケースでは、累積所得金額の計算に当たって、移行日における「修正公益目的財産残額」と「資産の帳簿価額から負債帳簿価額等を控除した金額」とのうちいずれか少ない金額(以下「当初調整公益目的財産残額」)を累積所得金額から控除し、累積所得金額から控除しきれないときは、その控除しきれない金額を累積欠損金額とみなすこととなる(法法64の4③、法令131の5①三・②)。
| 【算式】 益金に算入すべき金額(累積所得金額) = 資産の帳簿価額-負債帳簿価額 -利益積立金額-当初調整公益目的財産残額 |
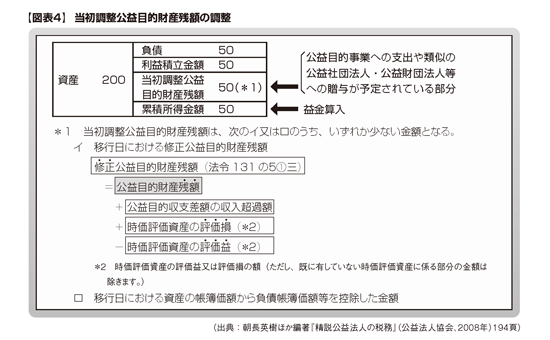
6.時価概念である公益目的財産額と当初調整公益目的財産残額
(1)公益目的財産額の算定 「公益目的財産額」とは、移行の登記をした日の前日(以下「算定日」という)における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に、一定の調整(時価評価)をして得た額をいう(整備法規則14①)。より具体的には、公益認定等ガイドラインⅡ-1(4)①公益目的財産額の算定方法について(整備法119①関係)において、「公益目的財産額の算定に必要な資産の評価に当たっては、過大な費用をかけることは適当でないと考えられるため」として、次のとおり規定されている。
① 土地の評価方法について 例えば、固定資産税評価額や不動産鑑定士が鑑定した価額などが考えられる。法人の保有する資産であって、移行後において当該法人が長期にわたり継続的に事業を行う場合にそれらの事業に継続して使用することが確実な資産(建物等の減価償却資産を含む)については、当該資産が継続して使用されることを前提に算定した額を評価額とすることができる。なお、土地及び建物を一体として評価する場合であっても、土地に係る算定額と建物に係る算定額を区分することが可能な場合は、それらを区分して申請することができる。
② 減価償却資産の評価方法について 建物等の減価償却資産については、時価評価資産に含めないものとする。ただし、不動産鑑定士による鑑定評価を妨げない。
③ 有価証券の評価方法について 上場されていることにより市場価格が容易に把握できる場合は、市場価格を用いた時価評価を行うものとする。市場性がない場合であっても評価を行うことが可能な場合は時価評価とする。なお、市場性がなく評価が困難な場合は当該有価証券の取得価額又は帳簿価額とする。
④ 美術品等その他の資産の評価方法について 法人において移行後も引き続き実施事業に使用するものは、時価評価が可能であっても帳簿価額とすることを認める。継続的に実施事業に使用する予定がないもの、売却の予定があるものについては、時価評価を行う。ただし、帳簿価額と時価との差額が著しく多額でないと法人において判断する場合や時価評価を行うことが困難な場合は、帳簿価額とすることを認める。
⑤ 引当金等について 負債(資産の控除を含む)として計上されている引当金(引当金に準ずるものを含む)については、公益目的財産額の算定から控除する。
また、会費等の積み立てによる準備金等(法令等により将来の支出又は不慮の支出に備えて設定することが要請されているもの)については、負債として計上されていない場合であっても、法人において合理的な算定根拠を示すことが可能である場合には、引当金と同様に公益目的財産額の算定から除くことができる。
⑥ 退職給付会計の導入に伴う会計基準変更時差異(脚注10)の扱いについて 費用処理期間を定めて当該期間にわたり費用処理を行っている法人にあっては、当該未処理額についても公益目的財産額の算定から控除することができる(この場合、未処理額の算定根拠などの資料の提出を求める)。なお、公益目的財産額の算定時に控除した未処理額について、移行後の各事業年度における費用処理の額は公益目的支出の額に算入しない。
(2)当初調整公益目的財産残額 以上のように、整備法上の「公益目的財産額」は時価概念であり、かつ純資産の部に保全が義務付けられている額、あるいは退職給付引当金の会計基準変更時差異も差し引く等の計算が認められているので、法人税法上そのまま採用できる概念ではない。
法人税法上は法人税法上の簿価へ修正(元に戻す)して控除することとなるため「修正公益目的財産残額」という。したがって用語こそ類似しているが、公益社団・財団法人に移行した後に公益認定が取り消された場合の「公益目的取得財産残額」とは、計算の難易度も概念も異なる。
「当初調整公益目的財産残額」は、会計上認識される資産と負債の差額である整備法上の純資産を基礎として算出されるものの、課税対象となる「累積所得金額」は、税制上認識される資産と負債等の差額として算出されることから(法令131の4①)差異が生じる。このことは、法人区分の変更に際して十分留意する必要がある(次号事例1参照)。
すなわち、公益法人会計基準では、たとえば賞与引当金、退職給付引当金、役員退職慰労引当金などは、通常の会計処理において負債として計上する(公益法人会計基準の運用指針12(1))が、法人税法上の負債には該当しない。このため、これら引当金は、「当初調整公益目的財産残額」の計算上は負債としてその減少項目となるが、累積所得金額の計算上は負債に該当せずその減少項目とはならないこととなる。
脚注
1 法人税法上の収益事業とは、次の34種類の事業を、継続して事業場を設けて営むことをいい、その収益事業の事業活動の一環として、あるいは関連して付随的に行われる行為も含まれる。
(1)物品販売業(2)不動産販売業(3)金銭貸付業(4)物品貸付業(5)不動産貸付業(6)製造業(7)通信業(8)運送業(9)倉庫業(10)請負業(11)印刷業(12)出版業(13)写真業(14)席貸業(15)旅館業(16)料理飲食業(17)周旋業(18)代理業(19)仲立業(20)問屋業(21)鉱業(22)土石採取業(23)浴場業(24)理容業(25)美容業(26)興行業(27)遊技所業(28)遊覧所業(29)医療保健業(30)技芸・学力教授業(31)駐車場業(32)信用保証業(33)無体財産権の提供業(34)労働者派遣業
2 【法人税基本通達15-1-28(実費弁償による事務処理の受託等)】
公益法人等が、事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合においても、当該業務が法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償(その委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことをいう。)により行われるものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね5年以内の期間とする。)を限って所轄税務署長の確認を受けたときは、その確認を受けた期間については、当該業務は、その委託者の計算に係るものとして当該公益法人等の収益事業としないものとする。
(注) 非営利型法人が1-1-11の確認を受けている場合には、本文の確認を受けたものとみなす。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律239条では、「残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。」「前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。」とある。
4 朝長英樹ほか編著『精説公益法人の税務』(公益法人協会、2008年)186頁に同趣旨。
5 役員の資格要件は法人法65①②、会計監査人の資格要件は法人法68(財団法人は評議員について法人法173①、役員及び会計監査人について法人法177で準用)。
6 FAQⅦ-②によると、ここでいう業務執行理事とは、代表理事及び取消原因となった事由の執行責任者たる理事に限られる。
なお、この前提となる問題として、業務執行理事は、一般法人法上複数の意味がある。
① 業務執行理事に選定された者(91①二)
② ①+代表理事(業務執行を予定されているため)
③ ②+②以外で業務執行を行ったことのある理事(113①二ロ、261①三(外部役員の定義の場合)。使用人兼務役員等が予定されうる)
FAQの記載でいう業務執行理事は少なくとも③の意味の業務執行理事であるので、後述する対応策において、他の公益法人の業務執行理事以上への選定ではなく理事に就任したことを把握しておく必要がある(なお、みなし役員の問題は今回は省く)。
7 公益法人が公益にそむく行為を行ったとして公益認定を取り消された場合、それを運営していた業務執行理事が公益にそむく行為を行ったものと考え、その者が理事を行っている他の公益法人も公益認定を取り消される。
8 この犯罪行為等の欠格事由の内容を見ると、以下のとおりに整理される。
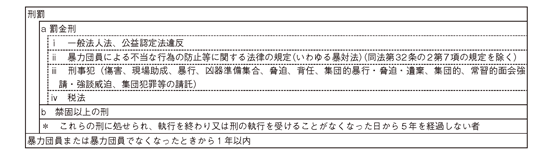
9 以下、富永さとる「公益認定取消しリスクとその回避策 理事・監事・評議員の欠格事由と失職条項」非営利法人786(2010年8月)号4頁を参考にした。
10 会計基準変更時において本来計上すべき引当金額の満額と実際に計上している引当金の差額をいう。会計基準変更時差異は、平成20年12月1日以後開始する最初の事業年度から12年以内の一定の年数にわたり定額法により費用処理をすることとなる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























