解説記事2011年03月21日 【実務解説】 税制から見た新公益法人制度の留意点(6・了)(2011年3月21日号・№395)
実務解説
税制から見た新公益法人制度の留意点(6・了)
税理士法人アズール 公認会計士・税理士 長谷川敏也
Ⅵ.合併と解散
1.合 併
(1)合併の法制 民法には合併に関する規定がないため、公益法人制度改革前は民法上の社団法人・財団法人は合併という行為はできなかったが、公益三法において新たに合併の規定が創設された。一般社団・財団法人(移行後の法人又は新設法人。公益社団・財団法人を含む)は、他の一般社団・財団法人と合併をすることができる(法人法242)。なお、合併の相手方については制限規定がある(法人法243)(図表1参照)。
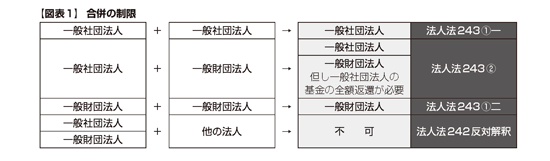
また、特例民法法人は、他の特例民法法人と合併(吸収合併に限る)をすることができる(整備法66①)。
(2)合併に関する税制 平成20年度税制改正においては、合併に係る税制について、適格要件の判定、資産等の譲渡・引継ぎに関する取扱い、納税義務者の区分の変更に関する取扱いに改正が行われている(法法2十二の八、法令4の3、123の3)。
合併に係る税制において最も重要なのは、法人の行った合併が適格組織再編成に該当するか否かの判断である。適格合併に該当すれば帳簿価額による資産の引継ぎが認められるが、該当しなければ(非適格合併であれば)資産の時価譲渡となり譲渡損益を認識しなければならない。
適格合併は、
① 企業グループ内の合併
イ 完全支配関係(100%保有関係)がある法人間で行われる合併
ロ 支配関係(50%超100%未満保有関係)がある法人間で行われる合併
② 共同事業を営むための合併
に分かれる。公益法人等は持分のない法人であるため、上記①に該当することなく、②の共同事業を営むための合併に該当して、適格合併となるか否かが問題となる(脚注1)。
共同で事業を営むための適格合併の要件とは、
① 事業関連性要件(法令4の3④一)
事業関連性要件とは、被合併法人の被合併事業と合併法人の合併事業とが相互に関連するものであるのか否かを判断するもの。
② 事業規模要件又は特定役員引継要件(法令4の3④二)
事業規模要件においては、合併法人と被合併法人の事業規模がおおむね5倍を超えないことを求めている。これは、事業規模がかけ離れた法人間の合併においては、共同で事業を営むのではなく、事業規模の大きい法人が小さい法人を買収したと見ることが通例であるという考えに基づくものである。一方、特定役員引継要件においては、事業規模は関係はない。
③ 従業者継続従事要件(法令4の3④三)
従業者継続従事要件とは、被合併法人の合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上の者が合併後に合併法人の業務に従事することが見込まれているのか否かを判断するもの。
④ 事業継続要件(法令4の3④四)
事業継続要件とは、被合併法人の被合併事業(合併事業と関連する事業に限る)が合併後に合併法人において引き続き営まれることが見込まれているのか否かを判断するもの。
⑤ 株式の継続保有に関する要件(法令4の3④五)
以上に該当するものとされている。
平成20年度税制改正においては、被合併法人の株主等の数が50人以上である場合と同様に、「当該合併に係る被合併法人のすべて若しくは合併法人が資本若しくは出資を有しない法人である場合」には、上記⑤株式等の継続保有要件(法令4の2④五)を適用しないこととされている。
また、適格合併の場合の収益事業以外の事業に属する資産又は負債の引継ぎに関して、「被合併法人である公益法人等の収益事業以外の事業に属する資産又は負債であつた場合には、当該資産又は負債の価額として当該合併法人の帳簿に記載された金額による引継ぎを受けたものとする」(法令123の3④)と規定し、帳簿価額による引継ぎを強制している。しかし、非適格合併の場合の収益事業以外の事業に属する資産又は負債の計算(法人税法上の受入時価及び譲渡損益の計上)をどのようにするのか、また公益三法とどのように整合性をとるのかなどの課題が残されている。
なお、国税庁のホームページでは「特例民法法人間において適格合併を行った場合の青色欠損金額の引継ぎ」(脚注2)及び「特例民法法人間の合併に対する適格判定における「事業関連性要件」の判定」(脚注3)について質疑応答事例が公開されている。いずれも特例民法法人の合併の税制を検討する上で重要であるので引用する。
2.解散(特にみなし解散について)
(1)公益法人等の解散 公益認定法人、一般社団・財団法人及び特例民法法人についてはおのおの解散事由が定められている。今回の改正に関してもっとも重要かつ可能性のある解散事由は、特例民法法人のみなし解散であると思われるので、これに絞って述べる。
(2)移行期間の終了に伴うみなし解散の概要 移行期間の終了に伴うみなし解散となる場合は、整備法の規定及び内閣府によるFAQによると以下のとおりである。
① 移行期間終了(平成25年11月30日)までに移行認定又は移行認可がなされなかった特例民法法人は、解散したものとみなされる(整備法46条1項本文)。
② ただし、移行認定申請又は移行認可申請がなされているがまだ認定又は認可処分がなされていないという場合には解散とはみなされない(同条同項但書)。
③ そして、この移行期間終了後は移行認可・認定申請は提出できなくなり、ただ、移行認定申請をしているがまだ処分を受けていないために存続している特例民法法人のみは移行認可申請を行いうることになる(整備法116条1項)。
④ 移行期間終了後に不認定処分・不認可処分を受けた場合には、解散したものとみなされる。
みなし解散においてどのような手続きがなされるかをみてみると、特例民法法人には、原則、民法法人であった時の規定が適用されることとなっている(整備法64、65、77。一般社団法人等登記通達第7部第5、25)。そこで、みなし解散についても民法法人の規定がそのまま用いられるなら、概要としては図表2のとおりとなる(脚注4)。
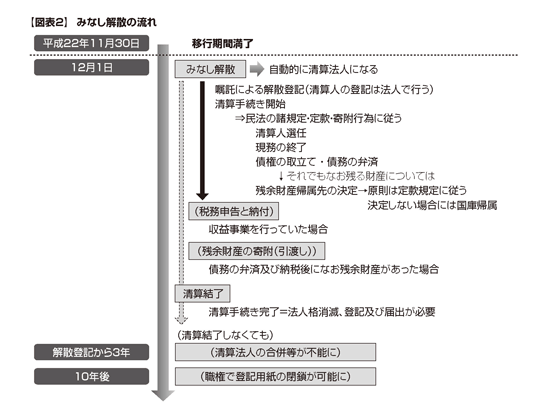
(3)法務-登記の嘱託と清算手続き 整備法46条2項は、移行期間の経過によるみなし解散という事態が起きた場合には、(旧)主務官庁は解散登記の嘱託を行うこととしている。これは、主務官庁が直接法務局に法人の解散登記を行わせるということで、法人は解散登記を申請する必要はない。
ただし、清算人は主務官庁が選任することはできないため、法人が自ら選任および選任登記をする必要がある。
そして、清算結了登記(整備法77⑥)がなされないまま3年が過ぎるとその清算法人の登記簿は登記を行えなくなり(登記用紙の閉鎖)、さらに10年が経過すると閉鎖される(法人登記規則7条、商業登記規則81条)。
(4)特例民法法人の残余財産の処分について 特例民法法人が解散することとした場合には、その残余財産の処分が問題となる。これについては、平成21年4月24日付で「特例民法法人の残余財産の処分について(通知)」が内閣府より発出されている。
ここでは、特例民法法人から一般社団・財団法人へ財産を贈与した場合には「一般論としては、当該財産が公益目的に使用されることが十分に担保されているとは言い難く、一般論としては、一般社団法人又は一般財団法人に残余財産を贈与することは不適切であると考えられる」とされている。すなわち贈与不可であるので注意が必要である。
(5)移行法人のみなし解散と清算 移行法人は、偽りその他不正の手段により移行認可を受けた場合には、その認可が取り消され、取消し処分の日が、移行期間満了日以後(特例民法法人の経過措置期間経過後)であると、みなし解散となる(整備法131①④)。
みなし解散後清算法人となった場合には、公益目的財産残額があるときはその公益目的財産残額に相当する財産について認定法第5条十七号に規定するもの(他の公益法人等、国、地方公共団体等)に帰属させなければならない(整備法130)(脚注5)。
脚注
1 合併等組織再編成税制の詳細については拙著(共著)『実践ガイド企業組織再編成税制』(清文社、2010年11月)、手続きについては内閣府平成20年8月6日付事務連絡「特例民法法人の合併の手続き等」参照。
2 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/16.htm参照。
3 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/15.htm参照。
4 これはまだ明言された資料がなく、また整備法の下位規定もそろっていないため、「従前の例による。」とした整備法65条に従い、もし移行期間後も手当がなされず特例民法法人であった清算法人について民法法人の手続きどおりでよければ、という記述であることをお断りする。なお、民法法人についての解散の登記嘱託の制度としては、破産及び設立許可の取消しの場合があった場合が挙げられている。破産については破産法の規定によるので、以下の手続きは設立許可の取消しの場合の手続きを記載した。法務省民事局第四課職員『法人登記書式精義(増補版)上』(テイハン、1988年11月(第3刷))208頁以下。
5 この場合、旧主務官庁の監督により、定款に定められた残余財産の帰属先は公益に資する法人若しくは国又は地方公共団体となっているはずである。
税制から見た新公益法人制度の留意点(6・了)
税理士法人アズール 公認会計士・税理士 長谷川敏也
Ⅵ.合併と解散
1.合 併
(1)合併の法制 民法には合併に関する規定がないため、公益法人制度改革前は民法上の社団法人・財団法人は合併という行為はできなかったが、公益三法において新たに合併の規定が創設された。一般社団・財団法人(移行後の法人又は新設法人。公益社団・財団法人を含む)は、他の一般社団・財団法人と合併をすることができる(法人法242)。なお、合併の相手方については制限規定がある(法人法243)(図表1参照)。
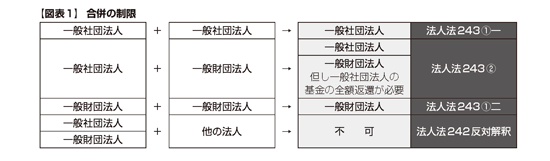
また、特例民法法人は、他の特例民法法人と合併(吸収合併に限る)をすることができる(整備法66①)。
(2)合併に関する税制 平成20年度税制改正においては、合併に係る税制について、適格要件の判定、資産等の譲渡・引継ぎに関する取扱い、納税義務者の区分の変更に関する取扱いに改正が行われている(法法2十二の八、法令4の3、123の3)。
合併に係る税制において最も重要なのは、法人の行った合併が適格組織再編成に該当するか否かの判断である。適格合併に該当すれば帳簿価額による資産の引継ぎが認められるが、該当しなければ(非適格合併であれば)資産の時価譲渡となり譲渡損益を認識しなければならない。
適格合併は、
① 企業グループ内の合併
イ 完全支配関係(100%保有関係)がある法人間で行われる合併
ロ 支配関係(50%超100%未満保有関係)がある法人間で行われる合併
② 共同事業を営むための合併
に分かれる。公益法人等は持分のない法人であるため、上記①に該当することなく、②の共同事業を営むための合併に該当して、適格合併となるか否かが問題となる(脚注1)。
共同で事業を営むための適格合併の要件とは、
① 事業関連性要件(法令4の3④一)
事業関連性要件とは、被合併法人の被合併事業と合併法人の合併事業とが相互に関連するものであるのか否かを判断するもの。
② 事業規模要件又は特定役員引継要件(法令4の3④二)
事業規模要件においては、合併法人と被合併法人の事業規模がおおむね5倍を超えないことを求めている。これは、事業規模がかけ離れた法人間の合併においては、共同で事業を営むのではなく、事業規模の大きい法人が小さい法人を買収したと見ることが通例であるという考えに基づくものである。一方、特定役員引継要件においては、事業規模は関係はない。
③ 従業者継続従事要件(法令4の3④三)
従業者継続従事要件とは、被合併法人の合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね80%以上の者が合併後に合併法人の業務に従事することが見込まれているのか否かを判断するもの。
④ 事業継続要件(法令4の3④四)
事業継続要件とは、被合併法人の被合併事業(合併事業と関連する事業に限る)が合併後に合併法人において引き続き営まれることが見込まれているのか否かを判断するもの。
⑤ 株式の継続保有に関する要件(法令4の3④五)
以上に該当するものとされている。
平成20年度税制改正においては、被合併法人の株主等の数が50人以上である場合と同様に、「当該合併に係る被合併法人のすべて若しくは合併法人が資本若しくは出資を有しない法人である場合」には、上記⑤株式等の継続保有要件(法令4の2④五)を適用しないこととされている。
また、適格合併の場合の収益事業以外の事業に属する資産又は負債の引継ぎに関して、「被合併法人である公益法人等の収益事業以外の事業に属する資産又は負債であつた場合には、当該資産又は負債の価額として当該合併法人の帳簿に記載された金額による引継ぎを受けたものとする」(法令123の3④)と規定し、帳簿価額による引継ぎを強制している。しかし、非適格合併の場合の収益事業以外の事業に属する資産又は負債の計算(法人税法上の受入時価及び譲渡損益の計上)をどのようにするのか、また公益三法とどのように整合性をとるのかなどの課題が残されている。
なお、国税庁のホームページでは「特例民法法人間において適格合併を行った場合の青色欠損金額の引継ぎ」(脚注2)及び「特例民法法人間の合併に対する適格判定における「事業関連性要件」の判定」(脚注3)について質疑応答事例が公開されている。いずれも特例民法法人の合併の税制を検討する上で重要であるので引用する。
| 特例民法法人間において適格合併を行った場合の青色欠損金額の引継ぎ 【照会要旨】 特例民法法人であるX協会及びY協会は、X協会を合併法人、Y協会を被合併法人とする合併を行う予定であるところ、Y協会は青色欠損金額を有しています。 当該合併が適格合併に該当する場合には、Y協会(被合併法人)が有する青色欠損金額はX協会(合併法人)に引き継がれると解してよろしいでしょうか。 なお、X協会及びY協会は、いずれの協会も株主等が存在していません。 【回答要旨】 Y協会(被合併法人)が有する青色欠損金額はX協会(合併法人)に引き継がれます。 (理由) 法人税法第57条第2項《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》においては、適格合併が行われた場合で被合併法人が合併前7年内事業年度に生じた青色欠損金額を有するときは、当該被合併法人において生じた青色欠損金額を合併法人において生じた青色欠損金額とみなすとされているところです。 ただし、同条第3項において、適格合併に係る被合併法人と合併法人との間に支配関係があり、かつ、支配関係が合併法人の合併の日を含む事業年度開始の日の5年前の日から継続していない場合には、その適格合併が共同で事業を営むための合併としての要件(いわゆる「みなし共同事業要件」)を満たさない限り、同条第2項において合併法人の青色欠損金額とみなされる被合併法人の青色欠損金額のうち支配関係事業年度前に生じた欠損金額等、一定の欠損金額はないものとされており、この同条第3項の規定は、支配関係がある法人間において行われる適格合併のみをその適用対象としています。 ご照会のX協会及びY協会は、いずれも株主等が存在しない法人ですので、X協会とY協会の合併は支配関係がない法人間の適格合併に該当しますから、同条第3項の適用を受けることなく、Y協会(被合併法人)が有する青色欠損金額はX協会(合併法人)に引き継がれることとなります。 |
| 特例民法法人間の合併に対する適格判定における「事業関連性要件」の判定 【照会要旨】 X協会及びY協会は、平成18年改正前の民法(以下「旧民法」といいます。)の規定により設立された財団法人であり、公益財団法人又は一般財団法人への移行の登記を了していない、いわゆる特例民法法人に該当します。 したがって、法人税法上は公益法人等に該当することとなりますが、いずれの協会もその事業の一部のみが収益事業に該当していますので、当該収益事業について法人税の申告を行っているところです。 この度、両協会の間で、X協会を合併法人とし、Y協会を被合併法人とする吸収合併を行うこととなりましたが、本件吸収合併に対する適格判定については、いずれの協会も株主等が存在しないため、「共同で事業を営むための合併」(法法2十二の八ハ)に該当するかについて検討を行うこととなりますが、適格要件の検討に当たり、その事業の相互関連性の有無や売上金額等による事業規模などの判定については、収益事業のみで判定を行うのではなく、非収益事業まで含めた事業全体により判定を行うと解して差し支えありませんか。 【回答要旨】 貴見のとおり解して差し支えありません。 (理由) 特例民法法人は、法人税法上の公益法人等に該当し、収益事業から生ずる所得に限って法人税が課されますので、合併に係る適格判定における共同事業要件の判定についても、その事業の相互関連性の有無や売上金額等による事業規模などの判定においては、収益事業のみを対象とするのではないかとの疑義が生じるところです。 しかしながら、共同事業要件の判定における「被合併事業」とは、被合併法人の合併前に営む主要な事業のうちいずれかの事業と規定し、「合併事業」とは、合併法人の合併前に営む事業のうちいずれかの事業と規定しているのみであり(法令4の3④一)、収益事業を行う公益法人等の間で合併が行われた場合について、「被合併事業」及び「合併事業」を収益事業に限る旨の特段の規定は設けられていません。 また、法人税法において特定の事業を収益事業として特掲して他の事業(非収益事業)と区分しているのは、同法が収益事業から生じた所得のみを課税対象としていることに基因するものであって、経済実態的には、その行う非収益事業と収益事業が一体となって公益法人等の事業を構成しているものと考えられます。 したがって、「資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更がない」かどうかは、経済実態的に収益事業と一体となって公益法人等の事業を構成する非収益事業まで含めた事業全体により共同事業要件の判定を行うと解することが相当です。 |
2.解散(特にみなし解散について)
(1)公益法人等の解散 公益認定法人、一般社団・財団法人及び特例民法法人についてはおのおの解散事由が定められている。今回の改正に関してもっとも重要かつ可能性のある解散事由は、特例民法法人のみなし解散であると思われるので、これに絞って述べる。
(2)移行期間の終了に伴うみなし解散の概要 移行期間の終了に伴うみなし解散となる場合は、整備法の規定及び内閣府によるFAQによると以下のとおりである。
① 移行期間終了(平成25年11月30日)までに移行認定又は移行認可がなされなかった特例民法法人は、解散したものとみなされる(整備法46条1項本文)。
② ただし、移行認定申請又は移行認可申請がなされているがまだ認定又は認可処分がなされていないという場合には解散とはみなされない(同条同項但書)。
③ そして、この移行期間終了後は移行認可・認定申請は提出できなくなり、ただ、移行認定申請をしているがまだ処分を受けていないために存続している特例民法法人のみは移行認可申請を行いうることになる(整備法116条1項)。
④ 移行期間終了後に不認定処分・不認可処分を受けた場合には、解散したものとみなされる。
みなし解散においてどのような手続きがなされるかをみてみると、特例民法法人には、原則、民法法人であった時の規定が適用されることとなっている(整備法64、65、77。一般社団法人等登記通達第7部第5、25)。そこで、みなし解散についても民法法人の規定がそのまま用いられるなら、概要としては図表2のとおりとなる(脚注4)。
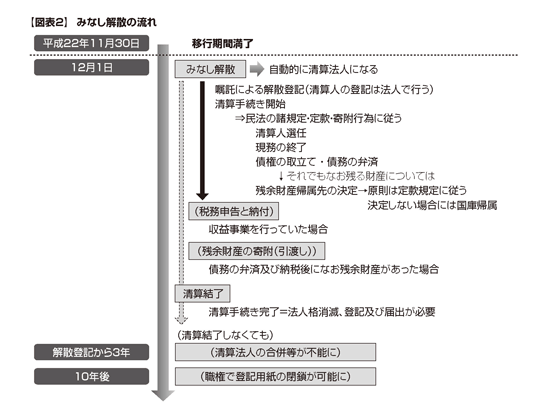
(3)法務-登記の嘱託と清算手続き 整備法46条2項は、移行期間の経過によるみなし解散という事態が起きた場合には、(旧)主務官庁は解散登記の嘱託を行うこととしている。これは、主務官庁が直接法務局に法人の解散登記を行わせるということで、法人は解散登記を申請する必要はない。
ただし、清算人は主務官庁が選任することはできないため、法人が自ら選任および選任登記をする必要がある。
そして、清算結了登記(整備法77⑥)がなされないまま3年が過ぎるとその清算法人の登記簿は登記を行えなくなり(登記用紙の閉鎖)、さらに10年が経過すると閉鎖される(法人登記規則7条、商業登記規則81条)。
(4)特例民法法人の残余財産の処分について 特例民法法人が解散することとした場合には、その残余財産の処分が問題となる。これについては、平成21年4月24日付で「特例民法法人の残余財産の処分について(通知)」が内閣府より発出されている。
ここでは、特例民法法人から一般社団・財団法人へ財産を贈与した場合には「一般論としては、当該財産が公益目的に使用されることが十分に担保されているとは言い難く、一般論としては、一般社団法人又は一般財団法人に残余財産を贈与することは不適切であると考えられる」とされている。すなわち贈与不可であるので注意が必要である。
(5)移行法人のみなし解散と清算 移行法人は、偽りその他不正の手段により移行認可を受けた場合には、その認可が取り消され、取消し処分の日が、移行期間満了日以後(特例民法法人の経過措置期間経過後)であると、みなし解散となる(整備法131①④)。
みなし解散後清算法人となった場合には、公益目的財産残額があるときはその公益目的財産残額に相当する財産について認定法第5条十七号に規定するもの(他の公益法人等、国、地方公共団体等)に帰属させなければならない(整備法130)(脚注5)。
脚注
1 合併等組織再編成税制の詳細については拙著(共著)『実践ガイド企業組織再編成税制』(清文社、2010年11月)、手続きについては内閣府平成20年8月6日付事務連絡「特例民法法人の合併の手続き等」参照。
2 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/16.htm参照。
3 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/33/15.htm参照。
4 これはまだ明言された資料がなく、また整備法の下位規定もそろっていないため、「従前の例による。」とした整備法65条に従い、もし移行期間後も手当がなされず特例民法法人であった清算法人について民法法人の手続きどおりでよければ、という記述であることをお断りする。なお、民法法人についての解散の登記嘱託の制度としては、破産及び設立許可の取消しの場合があった場合が挙げられている。破産については破産法の規定によるので、以下の手続きは設立許可の取消しの場合の手続きを記載した。法務省民事局第四課職員『法人登記書式精義(増補版)上』(テイハン、1988年11月(第3刷))208頁以下。
5 この場合、旧主務官庁の監督により、定款に定められた残余財産の帰属先は公益に資する法人若しくは国又は地方公共団体となっているはずである。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























