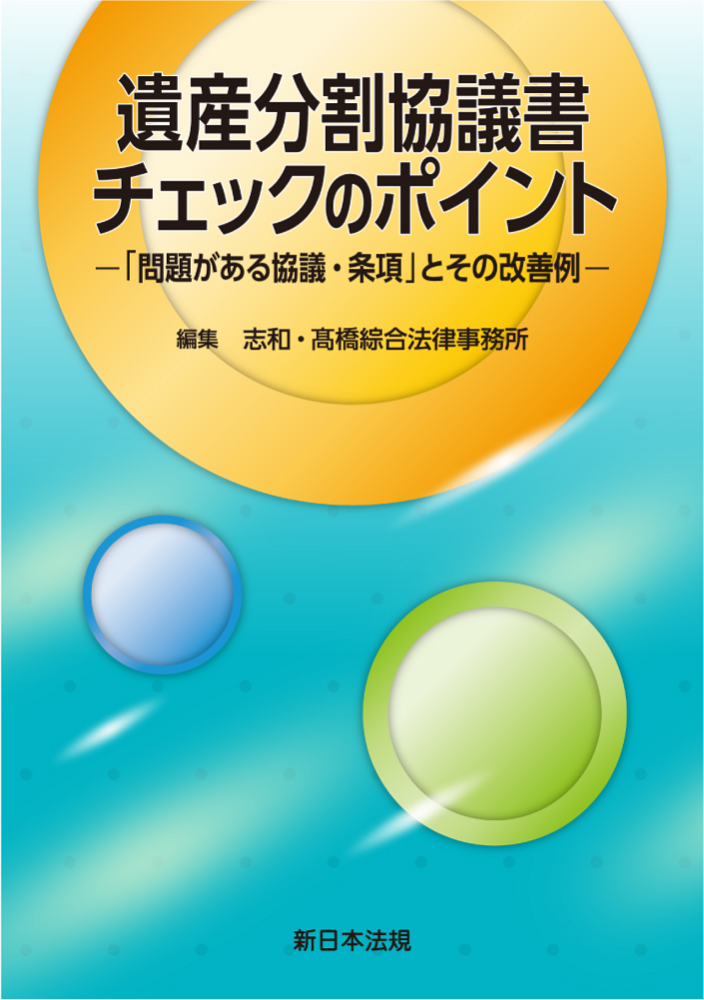解説記事2011年05月16日 【ニュース特集】 現物分配、会社分割に伴う「評価差額」の相続税における取扱い(2011年5月16日号・№402)
法人税額等相当額の控除は可能か?
現物分配、会社分割に伴う「評価差額」の相続税における取扱い
グループ法人税制というと文字どおり法人税の枠組みのなかだけでとらえがちだが、相続税への影響にも注意する必要がある。
平成22年10月1日以後、完全支配関係のある内国法人間で行われる現物分配は「適格現物分配」とされた。この制度を使えば、法人税等を負担することなく、帳簿価額により資産の移転を行うことができるが、現物分配の活用が、取引相場のない株式の相続税評価額にどのような影響を与えるかについては不明確な点も多い。
特に実務家の間で議論の的となっているのが、適格現物分配により資産が移転した場合でも、純資産価額方式の適用上、法人税額等相当額の控除が可能であるのかという点だ。また同様に、適格会社分割により資産が移転した場合、分割会社における帳簿価額を超える部分について法人税額等相当額の控除が認められるのかどうかという問題があるが、これには従来から「認められる」「認められない」の2つの説が存在するところだ。
本特集は、これらの疑問点に答えるものとしたい。
「現物出資等受入れ差額」は、法人税額等相当額の控除不可 株式の相続税評価の方法の1つである純資産価額方式では、株式の発行会社の課税時期における資産から、負債および「評価差額に対する法人税額等相当額」を控除して相続税評価額を求めることになる。
法人税額等相当額を控除する理由だが、会社を清算した場合には清算所得(顕在化した含み益)に対して法人税等が課されてきたことから(コラム参照)、清算所得と同様の考え方といえる純資産価額方式においても、この法人税額等相当額を控除することとしている。
法人税額等相当額の控除は、相続税評価額を引き下げ、相続税負担を軽減する効果があるだけに、その利用には制限が課されている。具体的には、現物出資、合併等により「著しく低い価額」で受け入れた資産(現物出資等受入れ資産)がある場合、原則として受入れ時における現物出資等受入れ資産の相続税評価額と受入れ帳簿価額との差額(現物出資等受入れ差額)については、法人税額等相当額が控除できないこととされている。(評基通186-2(2)のカッコ書き、図表1参照)。
「著しく低い価額での資産の受入れ」という経済的合理性のない行為によって作為的に評価差額(現物出資等受入れ差額)を創出しているような場合には、当該差額については法人税額等相当額の控除は認めないというのが、この取扱いの趣旨といえる。
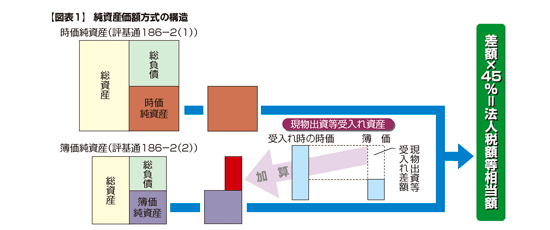
適格現物分配では「作為的な評価差額創出」の余地なし ここで問題となるのは、平成22年度税制改正で導入された現物分配や、以前から存在していた会社分割が、財産評価基本通達186-2(2)カッコ書きの適用対象になるのかどうかという点である。なぜなら、この取扱いは現物出資、合併、株式交換・移転について規定したものであり、通達中に「現物分配」「会社分割」という文言は一切含まれていないからだ。
まず現物分配について検討してみよう。平成22年度税制改正により、平成22年10月1日以後に完全支配関係のある内国法人間で行われる現物分配は「適格現物分配」として帳簿価額での資産移転が可能となったが、被現物分配法人の株式について相続が発生した場合には、被現物分配法人が適格現物分配により取得した資産が財産評価基本通達186-2(2)カッコ書きにいう「現物出資等受入れ資産」に該当するのかどうか疑問が生じる。現物出資等受入れ資産に該当すれば、受入れ時の相続税評価額と、現物分配法人から引き継いだ帳簿価額との差額から法人税額等相当額の控除は認められない。
この点、本誌取材によると、当局は、被現物分配法人が現物分配法人から適格現物分配により取得した資産は「現物出資等受入れ資産」には該当しないとの見解を持っているようだ。
こうした見解の根拠としては、以下の3つがある。第一に、前述のとおり財産評価基本通達186-2(2)カッコ書きには「現物分配」という文言が入っていないという点だ。「適格現物分配」という概念は平成22年度税制改正で創られた概念であり、同通達が適格現物分配により資産を取得した場合を想定していないことは明らかといえる。言い換えれば、通達中に「現物分配」という文言が入っていない以上、通達の適用対象にはならないと解釈せざるを得ないということだ。
第二に、恣意性の問題である。前述のとおり、この取扱いの趣旨は、「著しく低い価額での資産の受入れ」という経済的合理性のない行為により作為的に評価差額(現物出資等受入れ差額)を創出しているような場合には、当該差額について法人税額等相当額の控除を認めないということにある。この点からすると、現物分配法人から被現物分配法人に“強制的”に資産の帳簿価額が引き継がれる適格現物分配では、そのような恣意性が入る余地がないといえ、同通達の適用対象にはなり得ないというわけだ。
第三に、財産評価基本通達186-2(注)1の存在だ。ここでは、合併による資産の受入れについて、受入れ時の資産の相続税評価額から被合併法人において付されていた帳簿価額を控除した部分については、法人税額等相当額が控除できる旨が規定されている(図表2参照)。
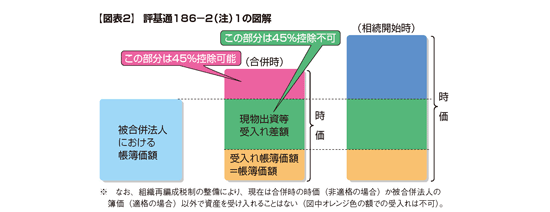
この規定の考え方を現物分配にも当てはめると、適格現物分配により取得した資産の取得時の相続税評価額が被現物分配法人における帳簿価額を超える場合、その差額部分については、法人税額等相当額の控除ができることになる。
すなわち、適格現物分配により取得した資産が現物出資等受入れ資産に該当すると仮定した場合であっても、評基通186-2(注)1の考え方を踏まえれば、引き継いだ帳簿価額(=現物分配法人における帳簿価額)を超える部分については法人税額等相当額が控除できることになるので、あえて適格現物分配により取得した資産が現物出資等受入れ資産に該当すると考える必然性がないというのが当局の見解だ。
新通達創設の可能性は? このように当局は、「適格現物分配」により取得した資産は財産評価基本通達186-2(2)「現物出資等受入れ資産」には該当しないとし、「適格現物分配」により受け入れた資産の受入れ時の相続税評価額と引継帳簿価額との差額からは、法人税額等相当額を控除できるとの見解を示している。
しかし、適格現物分配による資産の移転が、税務当局が想定していない租税回避行為につながる可能性も否定はできない。この点について当局は、財産評価基本通達・総則6項(この通達の定めにより難い場合の評価)の適用や、場合によっては新たな通達を創設することにより、租税回避行為に対処するとの姿勢も示しているので留意したい。
会社分割については諸説あるも、法人税額等相当額の控除可 現物分配同様、やはり財産評価基本通達186-2(2)カッコ書きに規定されていないのが、会社分割だ。このため、やはり適格会社分割により移転した資産の評価差額についても、純資産価額方式による相続税評価額の計算上、法人税額等相当額の控除を行ってよいのかどうか、これまで明確な答えはなかったといえる。
この点については、2つの説が存在している。一部の刊行物には、「財産評価基本通達186-2(2)カッコ書きは会社分割について言及していない」ことに加え、「組織再編税制施行後、会社分割において、恣意的で合理性のない取引は発生しない」として、財産評価基本通達186-2(2)カッコ書きの適用はない、すなわち法人税額等相当額の控除は認められる旨の見解がみられる。その一方で、他の刊行物では、会社分割にも財産評価基本通達186-2(2)カッコ書きが適用されるとして、法人税額等相当額の控除ができない旨を伝えている。
この点、本誌取材によると、適格会社分割を行った場合についても、基本的には、分割会社の帳簿価額(=分割承継会社の帳簿価額)を超える部分については、法人税額等相当額の控除が認められるとの見解が示されている。
その理由としては、財産評価基本通達186-2(2)には会社分割は挙げられていないことや財産評価基本通達186-2(注)1の存在など、現物分配と同様となっている。
Column
純資産価額方式における法人税額等相当額は42%→45%に 平成22年度税制改正により、法人税法上は清算所得課税が廃止され、平成22年10月1日以後の解散については、解散後も通常の法人税が課されることとなった。これに伴い、10月1日以後の相続・贈与により取得した取引相場のない株式に対して純資産価額方式を適用する場合、法人税額等相当額の割合が42%から45%に引き上げられている。これは、清算所得に対する法人税率が27.1%であるのに対し、通常の法人税率は30%であるためである。
法人税の清算所得課税が廃止されたことで、純資産価額方式における法人税額等相当額の控除もなくなるのではないかとの観測もあった。しかし、元々、法人税額等相当額の控除は株式の所有を通じて会社の資産を間接所有する株主と、事業用資産を直接所有する個人事業主との所有形態の相違に対する評価の均衡を図るための措置であることもあり、控除割合が変更された以外はそのまま維持されている。
現物分配、会社分割に伴う「評価差額」の相続税における取扱い
グループ法人税制というと文字どおり法人税の枠組みのなかだけでとらえがちだが、相続税への影響にも注意する必要がある。
平成22年10月1日以後、完全支配関係のある内国法人間で行われる現物分配は「適格現物分配」とされた。この制度を使えば、法人税等を負担することなく、帳簿価額により資産の移転を行うことができるが、現物分配の活用が、取引相場のない株式の相続税評価額にどのような影響を与えるかについては不明確な点も多い。
特に実務家の間で議論の的となっているのが、適格現物分配により資産が移転した場合でも、純資産価額方式の適用上、法人税額等相当額の控除が可能であるのかという点だ。また同様に、適格会社分割により資産が移転した場合、分割会社における帳簿価額を超える部分について法人税額等相当額の控除が認められるのかどうかという問題があるが、これには従来から「認められる」「認められない」の2つの説が存在するところだ。
本特集は、これらの疑問点に答えるものとしたい。
「現物出資等受入れ差額」は、法人税額等相当額の控除不可 株式の相続税評価の方法の1つである純資産価額方式では、株式の発行会社の課税時期における資産から、負債および「評価差額に対する法人税額等相当額」を控除して相続税評価額を求めることになる。
法人税額等相当額を控除する理由だが、会社を清算した場合には清算所得(顕在化した含み益)に対して法人税等が課されてきたことから(コラム参照)、清算所得と同様の考え方といえる純資産価額方式においても、この法人税額等相当額を控除することとしている。
法人税額等相当額の控除は、相続税評価額を引き下げ、相続税負担を軽減する効果があるだけに、その利用には制限が課されている。具体的には、現物出資、合併等により「著しく低い価額」で受け入れた資産(現物出資等受入れ資産)がある場合、原則として受入れ時における現物出資等受入れ資産の相続税評価額と受入れ帳簿価額との差額(現物出資等受入れ差額)については、法人税額等相当額が控除できないこととされている。(評基通186-2(2)のカッコ書き、図表1参照)。
「著しく低い価額での資産の受入れ」という経済的合理性のない行為によって作為的に評価差額(現物出資等受入れ差額)を創出しているような場合には、当該差額については法人税額等相当額の控除は認めないというのが、この取扱いの趣旨といえる。
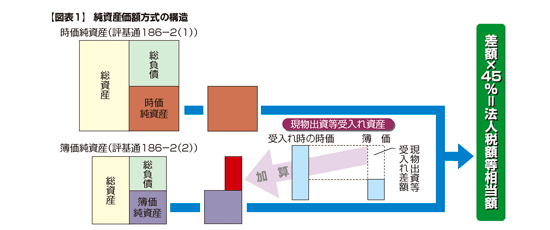
適格現物分配では「作為的な評価差額創出」の余地なし ここで問題となるのは、平成22年度税制改正で導入された現物分配や、以前から存在していた会社分割が、財産評価基本通達186-2(2)カッコ書きの適用対象になるのかどうかという点である。なぜなら、この取扱いは現物出資、合併、株式交換・移転について規定したものであり、通達中に「現物分配」「会社分割」という文言は一切含まれていないからだ。
まず現物分配について検討してみよう。平成22年度税制改正により、平成22年10月1日以後に完全支配関係のある内国法人間で行われる現物分配は「適格現物分配」として帳簿価額での資産移転が可能となったが、被現物分配法人の株式について相続が発生した場合には、被現物分配法人が適格現物分配により取得した資産が財産評価基本通達186-2(2)カッコ書きにいう「現物出資等受入れ資産」に該当するのかどうか疑問が生じる。現物出資等受入れ資産に該当すれば、受入れ時の相続税評価額と、現物分配法人から引き継いだ帳簿価額との差額から法人税額等相当額の控除は認められない。
この点、本誌取材によると、当局は、被現物分配法人が現物分配法人から適格現物分配により取得した資産は「現物出資等受入れ資産」には該当しないとの見解を持っているようだ。
こうした見解の根拠としては、以下の3つがある。第一に、前述のとおり財産評価基本通達186-2(2)カッコ書きには「現物分配」という文言が入っていないという点だ。「適格現物分配」という概念は平成22年度税制改正で創られた概念であり、同通達が適格現物分配により資産を取得した場合を想定していないことは明らかといえる。言い換えれば、通達中に「現物分配」という文言が入っていない以上、通達の適用対象にはならないと解釈せざるを得ないということだ。
第二に、恣意性の問題である。前述のとおり、この取扱いの趣旨は、「著しく低い価額での資産の受入れ」という経済的合理性のない行為により作為的に評価差額(現物出資等受入れ差額)を創出しているような場合には、当該差額について法人税額等相当額の控除を認めないということにある。この点からすると、現物分配法人から被現物分配法人に“強制的”に資産の帳簿価額が引き継がれる適格現物分配では、そのような恣意性が入る余地がないといえ、同通達の適用対象にはなり得ないというわけだ。
第三に、財産評価基本通達186-2(注)1の存在だ。ここでは、合併による資産の受入れについて、受入れ時の資産の相続税評価額から被合併法人において付されていた帳簿価額を控除した部分については、法人税額等相当額が控除できる旨が規定されている(図表2参照)。
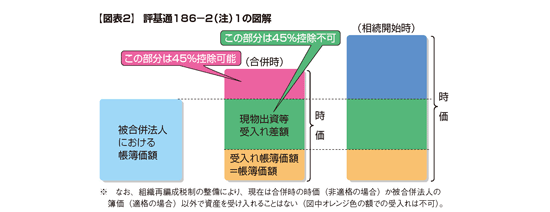
この規定の考え方を現物分配にも当てはめると、適格現物分配により取得した資産の取得時の相続税評価額が被現物分配法人における帳簿価額を超える場合、その差額部分については、法人税額等相当額の控除ができることになる。
すなわち、適格現物分配により取得した資産が現物出資等受入れ資産に該当すると仮定した場合であっても、評基通186-2(注)1の考え方を踏まえれば、引き継いだ帳簿価額(=現物分配法人における帳簿価額)を超える部分については法人税額等相当額が控除できることになるので、あえて適格現物分配により取得した資産が現物出資等受入れ資産に該当すると考える必然性がないというのが当局の見解だ。
| 財産評価基本通達186−2(評価差額に対する法人税額等に相当する金額) |
| 185((純資産価額))の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、次の(1)の金額から(2)の金額を控除した残額がある場合におけるその残額に45%を乗じて計算した金額とする。 (1)課税時期における相続税評価額による総資産価額から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額 (2)課税時期における相続税評価額による総資産価額の計算の基とした各資産の帳簿価額の合計額(当該各資産の中に、現物出資若しくは合併により著しく低い価額で受け入れた資産又は株式交換若しくは株式移転により著しく低い価額で受け入れた株式(現物出資等受入れ資産)がある場合には、当該各資産の帳簿価額の合計額に、現物出資、合併、株式交換又は株式移転の時において当該現物出資等受入れ資産をこの通達に定めるところにより評価した価額から当該現物出資等受入れ資産の帳簿価額を控除した金額(現物出資等受入れ差額)を加算した価額)から課税時期における各負債の金額の合計額を控除した金額 ※ 一部簡略化したうえで抜粋。 |
| 財産評価基本通達186−2(評価差額に対する法人税額等に相当する金額) |
| (注)1 現物出資等受入れ資産が合併により著しく低い価額で受け入れた資産(以下(注)1において「合併受入れ資産」という。)である場合において、上記(2)の「この通達に定めるところにより評価した価額」は、当該価額が合併受入れ資産に係る被合併会社の帳簿価額を超えるときには、当該帳簿価額とする。 |
新通達創設の可能性は? このように当局は、「適格現物分配」により取得した資産は財産評価基本通達186-2(2)「現物出資等受入れ資産」には該当しないとし、「適格現物分配」により受け入れた資産の受入れ時の相続税評価額と引継帳簿価額との差額からは、法人税額等相当額を控除できるとの見解を示している。
しかし、適格現物分配による資産の移転が、税務当局が想定していない租税回避行為につながる可能性も否定はできない。この点について当局は、財産評価基本通達・総則6項(この通達の定めにより難い場合の評価)の適用や、場合によっては新たな通達を創設することにより、租税回避行為に対処するとの姿勢も示しているので留意したい。
会社分割については諸説あるも、法人税額等相当額の控除可 現物分配同様、やはり財産評価基本通達186-2(2)カッコ書きに規定されていないのが、会社分割だ。このため、やはり適格会社分割により移転した資産の評価差額についても、純資産価額方式による相続税評価額の計算上、法人税額等相当額の控除を行ってよいのかどうか、これまで明確な答えはなかったといえる。
この点については、2つの説が存在している。一部の刊行物には、「財産評価基本通達186-2(2)カッコ書きは会社分割について言及していない」ことに加え、「組織再編税制施行後、会社分割において、恣意的で合理性のない取引は発生しない」として、財産評価基本通達186-2(2)カッコ書きの適用はない、すなわち法人税額等相当額の控除は認められる旨の見解がみられる。その一方で、他の刊行物では、会社分割にも財産評価基本通達186-2(2)カッコ書きが適用されるとして、法人税額等相当額の控除ができない旨を伝えている。
この点、本誌取材によると、適格会社分割を行った場合についても、基本的には、分割会社の帳簿価額(=分割承継会社の帳簿価額)を超える部分については、法人税額等相当額の控除が認められるとの見解が示されている。
その理由としては、財産評価基本通達186-2(2)には会社分割は挙げられていないことや財産評価基本通達186-2(注)1の存在など、現物分配と同様となっている。
Column
純資産価額方式における法人税額等相当額は42%→45%に 平成22年度税制改正により、法人税法上は清算所得課税が廃止され、平成22年10月1日以後の解散については、解散後も通常の法人税が課されることとなった。これに伴い、10月1日以後の相続・贈与により取得した取引相場のない株式に対して純資産価額方式を適用する場合、法人税額等相当額の割合が42%から45%に引き上げられている。これは、清算所得に対する法人税率が27.1%であるのに対し、通常の法人税率は30%であるためである。
法人税の清算所得課税が廃止されたことで、純資産価額方式における法人税額等相当額の控除もなくなるのではないかとの観測もあった。しかし、元々、法人税額等相当額の控除は株式の所有を通じて会社の資産を間接所有する株主と、事業用資産を直接所有する個人事業主との所有形態の相違に対する評価の均衡を図るための措置であることもあり、控除割合が変更された以外はそのまま維持されている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.