解説記事2011年08月08日 【実務解説】 外国法を準拠法とする組織再編における課税について(2011年8月8日号・№414)
実務解説
外国法を準拠法とする組織再編における課税について
森・濱田松本法律事務所 弁護士 小山 浩
Ⅰ はじめに
ここ数年の傾向として、日本企業が海外、特にアジア・南米・アフリカ等の新興国に子会社を設立して事業を開始した後、新たな事業展開を目的として海外子会社において組織再編を実施することが増加している。例えば、日本企業が現地法人を設立して事業を展開した後、現地資本の会社を合併により事業の拡大を図る、現地法人の事業部門を分社化して独立の法人を設立する、現地法人を他の海外現地法人の完全子会社とするなどである。これらの組織再編は、現地で行われることから、現地の法律に従うことになる。そして、これらの組織再編により、内国法人が対価を受領することがある。海外の現地法を準拠法として組織再編が実施され、内国法人が組織再編の対価を受領した場合、日本国内で内国法人に対していかなる課税関係が生じるかは難しい問題である。
本稿においては、海外子会社が外国法を準拠法として事業を分割し、新法人を設立したうえ、当該新会社の株式を内国法人である親会社に全て分配したという事例(次頁図1)を題材として、問題の所在を明らかにしたうえ、これまでの実務上の取扱い及び学説・裁判例を分析・検討し、実務上のポイントを解説した後、今後の展望について言及したい(脚注1)。
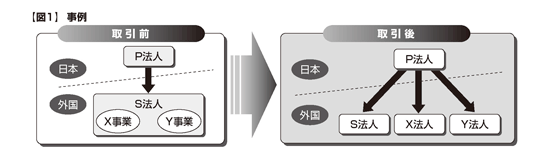
Ⅱ 問題の所在
まず、S法人が海外子会社ではなく、内国法人であり、日本の会社法を準拠法とする人的分割(会社法758条8号ロ、同法763条12号ロ)を行った場合、当該組織再編は法人税法上の「分割型分割」(法人税法2条12号の9)に該当し、「分割型分割」が適格要件(法人税法2条12号の11)を満たすときには、株主であるP法人に対する課税は繰り延べられる(法人税法24条1項2号、同法61条の2第4項)。
しかし、事例のように、S法人が海外子会社であり、外国法を準拠法として同様の組織再編を実施した場合、親会社であるP法人の課税関係はどうなるのであろうか。当該組織再編が法人税法上の「分割型分割」に該当し、適格要件も満たす場合に、P法人は日本の会社法を準拠法として人的分割が実施された場合と同じく課税は繰り延べられると解釈できるか。
この点について、法人税法は、「分割型分割」を「分割の日において当該分割に係る分割対価資産(括弧内省略)のすべてが分割法人の株主等に交付される場合の当該分割」と定めており、法人税法上の「分割」が、日本の会社法上の「会社分割」(会社法第5編第3章)を指すことは異論はない(脚注2)。しかし、外国法を準拠法とする組織再編が実施された場合については、法人税法上、明文の規定はない。そこで、まず、①そもそも外国法を準拠法とする組織再編が法人税法上の「分割」に該当しうるか(以下「論点①」という。)、さらに、②外国法を準拠法とする組織再編が「分割」に該当しうるとしても、如何なる要件を充足すれば「分割」に該当するのか(以下「論点②」という。)、が問題になる。
Ⅲ 検討・分析
1 実務上の取扱い この点については、実務での事例の積み重ねが先行している。まず、組織再編税制の立案担当者は、「……海外子会社が現地で適格合併又は適格分割型分割に類似する合併又は分割型分割を行い、内国法人である親会社が合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けた場合においても、みなし配当とはならないと考えてよろしいでしょうか。」という質問に対して、「外国における組織再編成は、我が国における組織再編成と同じ呼び方がされているものであっても、その手法やその前提となるもの等が同じであるとは限りませんし、その詳細も国ごとに区々となっているものと想定されます……税務執行の現場では、その事例における合併又は分割が我が国の商法等における合併又は分割と同様ということであれば、外国法人が現地で合併又は分割を行ったときのその株主である内国法人については、内国法人が合併又は分割を行ったときのその株主と同様に取り扱われると聞いています」と回答している(脚注3)。この考え方は、外国法を準拠法とする組織再編が法人税法上の「分割」に該当しうることを前提として(論点①)、日本の会社法上の「会社分割」に類似する組織再編が法人税法上の「分割」に該当する(論点②)と解釈するものと理解できる(脚注4)。
現在は、この回答における解釈を前提として実務上処理されていると思われる。日本公認会計士協会租税調査会国際租税専門部会専門委員の南波洋氏も「この海外の再編・取引(ここでは合併)の現地国における法律的取り扱い或いは経済的な特徴を明らかにして、日本の会社法上の合併が有するそれらの特徴と比べてみます。そして、その比較検討の結果、現地合併制度が日本の会社法上の合併制度とある程度近似あるいは類似しているのであれば、この場合には当該再編(合併)に日本の法人税法の合併に係る規定を適用していきましょう、ということを実務で行っているケースが多いのです。」とし、組織再編税制の立案担当者の回答に従って処理されていることを指摘している(脚注5)。
2 学説・裁判例の検討
(1)学説の整理 では、学説では如何なる議論がなされているのか。まず、そもそも外国法を準拠法とする組織再編が法人税法上の「分割」に該当しうるか(論点①)について、前述のとおり、法人税法上、明文の規定は見当たらないが、外国法を準拠法とする組織再編が法人税法上の「分割」に該当しうることに特に争いはないと思われる(脚注6)。その法的根拠としては、「分割型分割」の定義において、外国法を準拠法とする組織再編を排除していないこと(法人税法2条12号の9)、分割法人及び分割承継法人の定義から、外国法人が除かれていないこと(法人税法2条12号の2、同号の3)が挙げられよう。さらに、増井良啓教授=宮崎裕子弁護士は、日仏租税条約13(2)(b)条において、日本法人がフランス法人の株主である場合に、当該フランス法人がフランスの会社組織法に基づいて行う組織再編行為が日本における組織再編税制上課税繰延べの対象となるか否かについて、日本の当局の判断によって決定されること等が定められていることを1つの根拠として、「日本の国内税法に定められている組織再編税制が特に法令上の制限がない限り外国の組織再編行為にも適用されるとの公定解釈が背後にあることを示していると解することもできよう」と指摘されている(脚注7)。
争いがあるのは、外国法を準拠法とする組織再編が法人税法上の「分割」に該当しうるとしても、如何なる要件を充足すれば「分割」に該当するのか(論点②)という点である。この論点には、大きく分けて、2つのアプローチがあると思われる(脚注8)。
1つのアプローチとして、税法が他の法分野の概念と同じ概念を用いている場合には、同じ意義に解すべきであるとの解釈(統一説)を前提とし、法人税法上の「分割」は会社法上の「会社分割」と同一の意義であると解釈したうえ、会社法上の「会社分割」と外国の法制度が類似していれば、法人税法上の「分割」に該当するとの考え方である。この考え方は、まずは両国間の私法上の制度を比較したうえで、日本の法人税法の適用を判断するというアプローチであるため、実務上の取扱いと整合している。この点について、増井良啓教授=宮崎裕子弁護士は、外国法を準拠法とする合併に関する実務上の取扱いに言及され、「私法上の『合併』等の借用概念と解したうえで私法上合併として認められるために重要と思われる要素が何かを見つけ出したうえで、そのような要素を備えている外国法に基づく組織上の行為は法人税法上の合併に該当するというような解釈手順が用いられている」と分析している(脚注9)。
もう1つのアプローチとして、法人税法上の「分割」は、会社法上の「会社分割」の概念を借用したものと考えずに、租税法の目的に照らして合目的的に解釈すべきであるとの見解(目的適合説)を前提とし、国内私法を介さずに租税法の目的から合目的的に「分割」の意義を判断する考え方がある(脚注10)。この考え方によれば、法人税法上の「分割」の本質的な構成要素を抽出し、外国の法制度がかかる本質的な構成要素を具備しているかどうかによって解決を図ることになる。この考え方の論者の一人は、分割税制の沿革を辿り、①分割をする法人が資産・負債の一部を他の法人に移転すること、②分割をする法人から資産・負債の移転を受けた法人が、株式等を交付すること、③分割をする法人の株主が、資産・負債の移転を受けた他の法人の株式等の交付を受けること、④①から③が1つの行為として行われること、という4つの要素が法人税法の分割型分割の判断基準であると主張している(脚注11)。
以上の2つのアプローチのうち、いずれの考え方が妥当であろうか。前者の考え方は、税法が他の法分野から概念を借用している場合に、法的安定性及び予測可能性の確保の観点から当該他の法分野で用いられているのと同じ意義に解すべきであるとする統一説を本論点にも及ぼすものであり、現行法の解釈としては妥当であろうと思われる(脚注12)。後者の考え方は現行法の解釈としては難があるものの、私法に縛られることなく、税法の観点から課税繰延べを認める要件を検討するという点において、立法論として示唆的である。
(2)裁判例の検討 裁判所は、外国法を準拠法とする組織再編について、如何なる解釈を採用しているのであろうか。外国における組織再編によって日本の株主の課税関係が問題となった裁判例として、カナダ法人が子会社株式の現物配当を実施した際に、当該子会社株式を取得した居住者の課税関係が争われた事案(カナダ現物配当事件。東京高裁平成17年1月26日判決・税務訴訟資料255号順号9911)及び米国におけるスピンオフにより、株式を取得した居住者の課税関係が争われた事案(米国スピンオフ事件。東京地裁平成21年11月12日判決・判例タイムズ1324号134頁、東京高裁平成22年8月4日判決、最高裁平成23年4月21日決定により確定)がある。前者のカナダ現物配当事件は、居住者がカナダ法人の株式を保有しており、当該カナダ法人が剰余金の処分として子会社株式を株主に対して分配したところ(図2参照)、課税庁がその子会社株式の分配による株式取得は配当所得に該当することを前提として更正処分を行い、居住者が配当所得に該当しないとして課税処分を争ったものである(脚注13)。もっとも、カナダ現物配当事件は、我が国の組織再編税制が創設される前のものであることや、事業を分割して会社を設立し、当該新会社の株式を現物分配した事案ではなく、保有していた子会社株式を現物配当したものであるため、本稿との関係において直接の参考とはなりにくい。
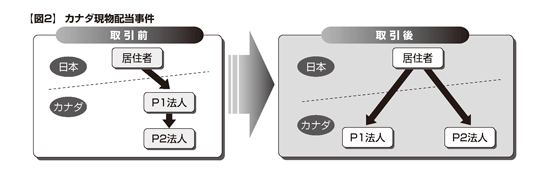
他方で、米国におけるスピンオフの事件については、まさに本件における検討対象の事例と同一の事実関係であり、参考となりうる事案である(図3参照)。
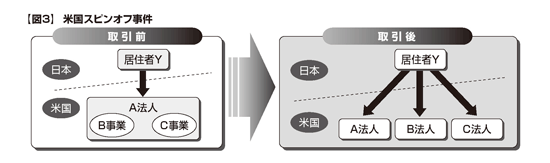
米国スピンオフ事件を具体的に説明すると、米国法人AがB事業とC事業を分社化し、各新設会社の株式を株主に分配するという取引(いわゆるスピンオフ)を行ったところ、このスピンオフにより、Aの株主である日本の居住者Yが新設会社株式を取得した事案である。この事案では、YはX証券会社の外国証券取引口座を通じてB及びC株式を取得し、XがB及びC株式の割当ては配当所得に該当することから源泉徴収が必要と判断してYに源泉徴収分を請求したところ、Yが源泉徴収分の支払を拒否し、XがYに対して源泉徴収分の支払請求訴訟を提起したというものである。
この事件において、第一審の東京地裁平成21年11月12日判決は、所得税法における「配当所得」及び「みなし配当」の意義を述べた上で、Yが取得したB及びC株式がAの利益剰余金を原資とする部分は配当所得に該当し、Aの資本剰余金を原資とする部分については、Yの出資額に対応する部分を超える部分についてはみなし配当に該当すると判示し、上級審においても、その判示内容は維持されている。この事案においては、米国におけるスピンオフが法人税法上の「分割」に該当するかという点については争点とされなかったため、裁判所は上記論点①及び②について明示的な判断をしていない。米国におけるスピンオフが法人税法上の「分割」に該当するかという点が争点とされたならば、論点①及び②に関する裁判所の考え方が明らかにされた可能性がある(脚注14)。
以上のとおり、裁判所においても、そもそも外国法を準拠法とする組織再編が法人税法上の「分割」に該当しうるか(論点①)、外国法を準拠法とする組織再編が如何なる要件を充足すれば日本の法人税法の「分割」に該当するか(論点②)という点について、解釈方法は未だ示されていない。
(3)小 括 以上のとおり、現行法の解釈として、外国法を準拠法とする組織再編は法人税法上の「分割」に該当し、さらに、「分割」を会社法からの借用概念と捉え、統一説を前提として、会社法上の会社分割と外国の法制度との比較を通じて法人税法の適用を検討する考え方が妥当であると考えられるが、裁判所において、この問題に対する解釈方法は示されていない。
このような議論状況のもとでは、実務上は、組織再編税制の立案担当者の回答や従前の実務上の取扱いに基づき、統一説の考え方に従って処理を行うのが現実的な選択となろう。
Ⅳ 実務上のポイント
1 具体的な検討手順 ここでは、実務上採用されている考え方を前提として、外国法を準拠法とする組織再編が如何なる要件を充足すれば日本の法人税法の「分割」に該当するかを具体的に検討する。
まず納税者が最初に行わなけれならないのは、日本法の弁護士のアドバイスを受けて、日本の会社法上の会社分割制度の重要な特徴を抽出する作業である(脚注15)。次に、外国の法制度が日本の会社分割制度の重要な特徴を有しているかどうかについて、外国法の条文を確認のうえ、外国法弁護士からの意見書などにより確認することになる。そして、日本の会社分割制度と外国の法制度が類似してるかどうかを日本法の弁護士のアドバイスをもとに比較分析して、類似しているとのロジックが構築できる場合には法人税法上の「分割」に該当するものとして、適格要件を充足するかどうかを判断し、最後に当局に事前相談して確認を得るという流れをとる(図4参照)。
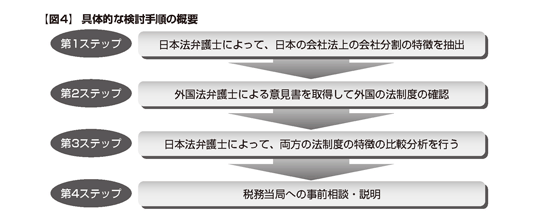
2 留 意 点 具体的な検討手順は上記のとおりであるが、実際に検討を行う場合には、(1)予測可能性、(2)コスト、及び(3)時間に留意する必要がある。
(1)予測可能性 具体的手順のうち、そもそも日本の会社分割の重要な特徴は何かという第1ステップで判断に迷うことになる。日本の会社分割制度の概要を述べると、会社分割は吸収分割と新設分割に分類されており、吸収分割契約を締結又は新設分割計画書を作成し、原則として株主総会の特別決議による承認を得る必要があり、また、事前の情報開示を実施したうえで株主保護手続及び債権者保護手続を経て、分割会社の事業に関して有する権利義務の全部又は一部が分割承継会社に包括的に承継されることになる。この一連の手続及び法的効果のうち、いずれが会社分割の特徴といえるかを判断する必要がある。会社分割の特徴に関し、法的効果については、包括承継であること、人的分割の場合には対価が直接株主に交付されるのではなく分割会社からの現物分配と構成されていることなどが挙げられるよう。また、手続については、意思決定機関が原則として株主総会であること、株主通知や反対株式買取請求権といった株主保護手続があること、債権者に対する公告・通知や債権者による異議の申述といった債権者保護手続があること、事前及び事後の情報開示が必要であること、手続上の瑕疵がある場合に無効の訴えが特別に設けられていることなどが挙げられよう。これらの特徴のうち、どれが会社分割の本質的要素であるのかを判断することは難しい。このことは、外国の法制度の特徴を抽出する際にも同様にあてはまる。
そして、外国の法制度が日本の会社分割制度の重要な特徴を有しているかを判断することが最も難しいと思われる。異なる法制度である以上、法的効果や手続に差異があることは否めない。しかも、大陸法系の国家(例えば、ドイツ、フランス)であれば、日本の法制度との類似性は比較的検討しやすいが、全く異なる法体系を有する国家の場合、日本と当該外国の各制度が類似しているかどうかの判断は困難を極める。
さらに、類似性を判断する際には、類似の程度の問題もある。例えば、日本の会社法においては、債権者保護手続(債権者への通知・官報公告、債権者による異議の申述など)が会社分割の本質的要素の1つであると判断される場合、仮に外国の法制度においては、債権者への通知しなければならない規定はあるものの、異議を申述することまでは認められていないことが判明したときに、債権者保護という特徴を有しているかを判断しなければならないが、その判断は難しいと思われる。
このように、内国法人が外国法を準拠法とする組織再編により課税されるのか否かについては、どの事項が、どの程度重要な特徴が類似していれば、「分割」に該当するのかという判断基準がないため、納税者側で両制度は類似しているとのロジックを構築したとしても、税務当局及び裁判所がそのロジックを是認するかどうは不明であり、納税者としては予測可能性が確保できないことが多いと思われる。
(2)コスト さらに、検討コストも無視することはできない。海外での組織再編を実施するためのコストの他に、まずは日本の法制度の分析が必要であるため、日本法の弁護士に依頼する必要がある。また、外国の法制度の分析や、後の税務当局への説明のために、当該外国法の該当条文を日本語に翻訳しておく必要がある。当該外国が英語を公用語とする国(シンガポール、インドなど)である場合には当該外国法を日本語に翻訳することは比較的容易であるが、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、マレーシア語等々が公用語の場合には、いったん外国法を英語に翻訳した上で日本語に翻訳しなければならないことが多く、正確な翻訳を入手するためのコストも無視できない。さらには、外国の法制度の分析のために、外国法弁護士に依頼し、意見書等を取得することが必要となる。
以上のように、検討コストが相当程度必要となることに留意を要する。
(3)時 間 日本法の分析にも一定程度の時間が必要となるが、さらに時間を要するのが、外国法弁護士とのコミュニケーションであると思われる。また、組織再編税制の立案担当者は、「海外子会社の現地における『合併』又は『分割』が我が国における合併又は分割と同様のものと考えて良いか否かを十分に検討し、執行当局に具体的な取扱いについてご確認をされた方が良いと思われます」と回答していることから(脚注16)、実際には、海外子会社が組織再編を行う前に、税務当局への説明を行うことになる(第4ステップ)。この税務当局への説明のための資料(日本の法制度、外国の法制度、及び両者の類似点・相違点を記載した三段表や当該外国法の条文の翻訳が考えられる。)の作成はもとより、当局とのやり取りにも時間がかかり、回答を取得するにはそれなりの時間を要することになる。この点も踏まえて海外での組織再編のスケジューリングを行う必要がある。
Ⅴ 今後の展望
1 執行の方向性 前記Ⅳの留意点のうち、現在の実務の取扱いが納税者の予測可能性を害している点については、問題が大きい。この点について、増井良啓教授は、「日本と異なる法制度を有する外国における取引をあてはめる上で、種々の困難が生ずることが予想される。あてはめの過程に不確実さが残れば、法的安定性と予測可能性を害することになってしまう」と指摘されており(脚注17)、まさに実務上の問題はこの点に尽きるといっても過言ではない。納税者のみならず、事前相談を受ける税務当局においても、日本の会社法のみならず、外国の法制度も理解しなけれならない。そのうえ、類似しているかどうかについての判断基準が何ら示されていないため、税務当局においても取扱いに困るのではないかと推察される。
この点については、外国法を準拠法とする事業体の性質決定に係る実務の対応が参考となる。外国法を準拠法とする事業体の性質決定の問題とは、外国で設立されたパートナーシップなどの事業体が日本の税法上の「法人」に該当するかという論点である。この点については、国税庁が「米国LLCに係る税務上の取扱い」と題する指針を出し、4つの基準から米国LLCが税法上「法人」に該当すると判断したことを公表した(脚注18)。また、外国法を準拠法とする事業体の性質決定の問題については、裁判例・裁決例も蓄積されており(脚注19)、一定の基準が形成されつつある。外国法を準拠法とする組織再編についても、税務当局から各組織再編の類似性についての判断基準が示されることや裁判所において基準が明らかとされることが望まれる。
2 立法への期待 現行の法解釈においては、前記Ⅲで検討したとおり、納税者の予測可能性・法的安定性を重視する統一説を前提として、会社法上の会社分割と外国の法制度との比較検討を踏まえて課税関係を決するという実務上の取扱いは妥当なものであると考えられる。しかし、立法論として、外国の法制度が日本の会社法上の制度と類似していない場合であっても、日本での課税繰延べを認めることはありえよう。吉村政穂准教授は、「……外国法人が当事法人となる組織再編に関して生じる課税上の問題は、わが国に居住する株主の課税、当該外国法人の日本所在のPEを構成する資産等の移転に係る課税、外国子会社合算税制との関係整理と多岐にわたる。(中略)これらの解決を、合併や分割などの解釈に係らしめるのは適当ではない。」と指摘されている(脚注20)。私法上の制度が類似していないことをもって課税繰延べを認めないとするのではなく、租税法独自の見地から、課税繰延べを認める必要性・許容性を検討し、外国法を準拠法とする組織再編について課税繰延べを認める要件を法律によって明確にしておくことが今後必要ではないかと思われる(脚注21)。課税繰延べが認められる具体的な要件については今後検討を進める必要があるが、差し当たりの方針として、①組織再編の前後で内国法人による投資が継続しており、②日本における課税権が当該組織再編によって脱漏しないことが確保されることが重要である。このような観点からすれば、具体的な要件としては、組織再編の対価が株式であること、組織再編後においても事業が継続すること、株主に比例的に対価が分配されること、などが挙げられよう(脚注22)。
以上のとおり、投資の継続性や海外での組織再編により日本の課税権が脱漏しないとの観点から、課税繰延べの要件を法律で明確に定めることが、納税者の予見可能性や租税負担の公平を確保し、さらには、日本企業の海外でのビジネス展開を促進することになると考えられる。
脚注
1 本稿に記載されている見解は、筆者の個人的な見解であり、筆者の属する法律事務所の見解でないことを付言する。
2 岡村忠生『法人税法講義[第3版]』(成文堂、2007年)405頁。
3 朝長英樹「企業組織再編成に係る税制について(第3回)」日本租税研究協会編『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』(日本租税研究協会、2001年)103頁。
4 税務当局は、一貫してこの解釈を採用しているものと考えられる(五枚橋實「企業再編税制にかかる誤り事例と留意点について」租税研究658号66頁等参照)。
5 南波洋「国外における組織再編等にかかる国内税法の適用関係について(中間報告)─日本公認会計士協会租税調査会研究報告第17号の解説─」租税研究721号118頁以下。
6 外国法上の概念が日本の租税法の借用概念との関係でどのように取り扱われるかという点については、平川雄士「借用概念論に関係する国際的企業租税実務上の諸問題」金子宏編『租税法の発展』(有斐閣、2010年)354頁以下参照。
7 増井良啓=宮崎裕子『国際租税法』(東京大学出版会、2008年)243頁。
8 なお、太田洋=佐藤修二「我が国の租税法規と外国私法との交錯」中里実ほか編『国際租税訴訟の最前線』(有斐閣、2010年)359頁以下は、租税法規趣旨探求説、外国私法基準説、及び内国私法基準説の3つに分類しているが、同書も指摘しているとおり、前2者の見解の区別が明確ではないため(360頁)、本稿では大きく2つの見解に分類している。
9 増井=宮崎・前掲(注7)244頁。
10 小林淳子「国外取引に対する租税法の適用と外国法人の分割に関する諸問題」税務大学校論叢45号272頁以下。
11 小林・前掲(注10)315~319頁。
12 借用概念に関する一般的な解説については、金子宏『租税法[第16版]』(弘文堂、2011年)110~113頁参照。
13 この事件に対する国税不服審判所裁決に関する解説として、増井良啓「外国会社からの現物分配と所得税―国税不服審判所平成15年4月9日裁決を素材として」税務事例研究84号41頁以下、浅妻敬=坂本英之「外国法人の組織再編により関連会社株式の分配を受けた株式に対する配当課税」税研20巻5号90頁以下がある。
14 但し、日本の会社分割制度が米国型の株主分配を利用した会社分割ではなく、分割を合併類似の組織再編として整理する欧州大陸型の制度となっていることを根拠として、米国におけるスピンオフが日本の法人税法上の「分割」には該当しない可能性が高いことを指摘するものとして、太田=佐藤・前掲(注8)358~359頁。
15 日本の会社法における合併について、事業譲渡と比較して重要な特徴を指摘するものとして、日本公認会計士協会「国外における組織再編等に係る国内税法の適用関係について(中間報告)」7~8頁参照。
16 朝長・前掲(注3)104頁。
17 増井・前掲(注13)60頁。
18 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/05/01.htm 19 米国ニューヨーク州のLLCが問題となった東京高裁平成19年10月10日判決・訟務月報54巻10号2516頁、ケイマン諸島の特例LPSが問題となった名古屋高裁平成19年3月8日判決・税務訴訟資料(250号~)257号10647順号(最高裁平成20年3月27日上告不受理決定により確定)、米国のLPSが問題となった国税不服審判所平成18年2月2日裁決がある。
20 吉村政穂「国際的組織再編をめぐる課税問題―日米比較を中心に―」租税法研究36号67頁脚注(50)。
21 米国においては、A型組織再編以外の適格組織再編は原則として民商法に依拠していない(渡辺徹也『企業組織再編成と課税』(弘文堂、2006年)29頁参照)。
22 もっとも、この点を突き詰めれば、米国のように、そもそも適格組織再編税制が会社法に依拠する必要はなく、準拠法が国内法か外国法かを問わず、組織再編が行われた場合の課税繰延べ要件を設定すべきであるとの議論につながっていくものと思われる。
外国法を準拠法とする組織再編における課税について
森・濱田松本法律事務所 弁護士 小山 浩
Ⅰ はじめに
ここ数年の傾向として、日本企業が海外、特にアジア・南米・アフリカ等の新興国に子会社を設立して事業を開始した後、新たな事業展開を目的として海外子会社において組織再編を実施することが増加している。例えば、日本企業が現地法人を設立して事業を展開した後、現地資本の会社を合併により事業の拡大を図る、現地法人の事業部門を分社化して独立の法人を設立する、現地法人を他の海外現地法人の完全子会社とするなどである。これらの組織再編は、現地で行われることから、現地の法律に従うことになる。そして、これらの組織再編により、内国法人が対価を受領することがある。海外の現地法を準拠法として組織再編が実施され、内国法人が組織再編の対価を受領した場合、日本国内で内国法人に対していかなる課税関係が生じるかは難しい問題である。
本稿においては、海外子会社が外国法を準拠法として事業を分割し、新法人を設立したうえ、当該新会社の株式を内国法人である親会社に全て分配したという事例(次頁図1)を題材として、問題の所在を明らかにしたうえ、これまでの実務上の取扱い及び学説・裁判例を分析・検討し、実務上のポイントを解説した後、今後の展望について言及したい(脚注1)。
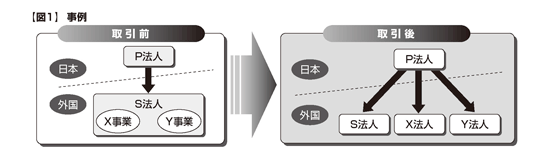
Ⅱ 問題の所在
まず、S法人が海外子会社ではなく、内国法人であり、日本の会社法を準拠法とする人的分割(会社法758条8号ロ、同法763条12号ロ)を行った場合、当該組織再編は法人税法上の「分割型分割」(法人税法2条12号の9)に該当し、「分割型分割」が適格要件(法人税法2条12号の11)を満たすときには、株主であるP法人に対する課税は繰り延べられる(法人税法24条1項2号、同法61条の2第4項)。
しかし、事例のように、S法人が海外子会社であり、外国法を準拠法として同様の組織再編を実施した場合、親会社であるP法人の課税関係はどうなるのであろうか。当該組織再編が法人税法上の「分割型分割」に該当し、適格要件も満たす場合に、P法人は日本の会社法を準拠法として人的分割が実施された場合と同じく課税は繰り延べられると解釈できるか。
この点について、法人税法は、「分割型分割」を「分割の日において当該分割に係る分割対価資産(括弧内省略)のすべてが分割法人の株主等に交付される場合の当該分割」と定めており、法人税法上の「分割」が、日本の会社法上の「会社分割」(会社法第5編第3章)を指すことは異論はない(脚注2)。しかし、外国法を準拠法とする組織再編が実施された場合については、法人税法上、明文の規定はない。そこで、まず、①そもそも外国法を準拠法とする組織再編が法人税法上の「分割」に該当しうるか(以下「論点①」という。)、さらに、②外国法を準拠法とする組織再編が「分割」に該当しうるとしても、如何なる要件を充足すれば「分割」に該当するのか(以下「論点②」という。)、が問題になる。
Ⅲ 検討・分析
1 実務上の取扱い この点については、実務での事例の積み重ねが先行している。まず、組織再編税制の立案担当者は、「……海外子会社が現地で適格合併又は適格分割型分割に類似する合併又は分割型分割を行い、内国法人である親会社が合併法人又は分割承継法人の株式の交付を受けた場合においても、みなし配当とはならないと考えてよろしいでしょうか。」という質問に対して、「外国における組織再編成は、我が国における組織再編成と同じ呼び方がされているものであっても、その手法やその前提となるもの等が同じであるとは限りませんし、その詳細も国ごとに区々となっているものと想定されます……税務執行の現場では、その事例における合併又は分割が我が国の商法等における合併又は分割と同様ということであれば、外国法人が現地で合併又は分割を行ったときのその株主である内国法人については、内国法人が合併又は分割を行ったときのその株主と同様に取り扱われると聞いています」と回答している(脚注3)。この考え方は、外国法を準拠法とする組織再編が法人税法上の「分割」に該当しうることを前提として(論点①)、日本の会社法上の「会社分割」に類似する組織再編が法人税法上の「分割」に該当する(論点②)と解釈するものと理解できる(脚注4)。
現在は、この回答における解釈を前提として実務上処理されていると思われる。日本公認会計士協会租税調査会国際租税専門部会専門委員の南波洋氏も「この海外の再編・取引(ここでは合併)の現地国における法律的取り扱い或いは経済的な特徴を明らかにして、日本の会社法上の合併が有するそれらの特徴と比べてみます。そして、その比較検討の結果、現地合併制度が日本の会社法上の合併制度とある程度近似あるいは類似しているのであれば、この場合には当該再編(合併)に日本の法人税法の合併に係る規定を適用していきましょう、ということを実務で行っているケースが多いのです。」とし、組織再編税制の立案担当者の回答に従って処理されていることを指摘している(脚注5)。
2 学説・裁判例の検討
(1)学説の整理 では、学説では如何なる議論がなされているのか。まず、そもそも外国法を準拠法とする組織再編が法人税法上の「分割」に該当しうるか(論点①)について、前述のとおり、法人税法上、明文の規定は見当たらないが、外国法を準拠法とする組織再編が法人税法上の「分割」に該当しうることに特に争いはないと思われる(脚注6)。その法的根拠としては、「分割型分割」の定義において、外国法を準拠法とする組織再編を排除していないこと(法人税法2条12号の9)、分割法人及び分割承継法人の定義から、外国法人が除かれていないこと(法人税法2条12号の2、同号の3)が挙げられよう。さらに、増井良啓教授=宮崎裕子弁護士は、日仏租税条約13(2)(b)条において、日本法人がフランス法人の株主である場合に、当該フランス法人がフランスの会社組織法に基づいて行う組織再編行為が日本における組織再編税制上課税繰延べの対象となるか否かについて、日本の当局の判断によって決定されること等が定められていることを1つの根拠として、「日本の国内税法に定められている組織再編税制が特に法令上の制限がない限り外国の組織再編行為にも適用されるとの公定解釈が背後にあることを示していると解することもできよう」と指摘されている(脚注7)。
争いがあるのは、外国法を準拠法とする組織再編が法人税法上の「分割」に該当しうるとしても、如何なる要件を充足すれば「分割」に該当するのか(論点②)という点である。この論点には、大きく分けて、2つのアプローチがあると思われる(脚注8)。
1つのアプローチとして、税法が他の法分野の概念と同じ概念を用いている場合には、同じ意義に解すべきであるとの解釈(統一説)を前提とし、法人税法上の「分割」は会社法上の「会社分割」と同一の意義であると解釈したうえ、会社法上の「会社分割」と外国の法制度が類似していれば、法人税法上の「分割」に該当するとの考え方である。この考え方は、まずは両国間の私法上の制度を比較したうえで、日本の法人税法の適用を判断するというアプローチであるため、実務上の取扱いと整合している。この点について、増井良啓教授=宮崎裕子弁護士は、外国法を準拠法とする合併に関する実務上の取扱いに言及され、「私法上の『合併』等の借用概念と解したうえで私法上合併として認められるために重要と思われる要素が何かを見つけ出したうえで、そのような要素を備えている外国法に基づく組織上の行為は法人税法上の合併に該当するというような解釈手順が用いられている」と分析している(脚注9)。
もう1つのアプローチとして、法人税法上の「分割」は、会社法上の「会社分割」の概念を借用したものと考えずに、租税法の目的に照らして合目的的に解釈すべきであるとの見解(目的適合説)を前提とし、国内私法を介さずに租税法の目的から合目的的に「分割」の意義を判断する考え方がある(脚注10)。この考え方によれば、法人税法上の「分割」の本質的な構成要素を抽出し、外国の法制度がかかる本質的な構成要素を具備しているかどうかによって解決を図ることになる。この考え方の論者の一人は、分割税制の沿革を辿り、①分割をする法人が資産・負債の一部を他の法人に移転すること、②分割をする法人から資産・負債の移転を受けた法人が、株式等を交付すること、③分割をする法人の株主が、資産・負債の移転を受けた他の法人の株式等の交付を受けること、④①から③が1つの行為として行われること、という4つの要素が法人税法の分割型分割の判断基準であると主張している(脚注11)。
以上の2つのアプローチのうち、いずれの考え方が妥当であろうか。前者の考え方は、税法が他の法分野から概念を借用している場合に、法的安定性及び予測可能性の確保の観点から当該他の法分野で用いられているのと同じ意義に解すべきであるとする統一説を本論点にも及ぼすものであり、現行法の解釈としては妥当であろうと思われる(脚注12)。後者の考え方は現行法の解釈としては難があるものの、私法に縛られることなく、税法の観点から課税繰延べを認める要件を検討するという点において、立法論として示唆的である。
(2)裁判例の検討 裁判所は、外国法を準拠法とする組織再編について、如何なる解釈を採用しているのであろうか。外国における組織再編によって日本の株主の課税関係が問題となった裁判例として、カナダ法人が子会社株式の現物配当を実施した際に、当該子会社株式を取得した居住者の課税関係が争われた事案(カナダ現物配当事件。東京高裁平成17年1月26日判決・税務訴訟資料255号順号9911)及び米国におけるスピンオフにより、株式を取得した居住者の課税関係が争われた事案(米国スピンオフ事件。東京地裁平成21年11月12日判決・判例タイムズ1324号134頁、東京高裁平成22年8月4日判決、最高裁平成23年4月21日決定により確定)がある。前者のカナダ現物配当事件は、居住者がカナダ法人の株式を保有しており、当該カナダ法人が剰余金の処分として子会社株式を株主に対して分配したところ(図2参照)、課税庁がその子会社株式の分配による株式取得は配当所得に該当することを前提として更正処分を行い、居住者が配当所得に該当しないとして課税処分を争ったものである(脚注13)。もっとも、カナダ現物配当事件は、我が国の組織再編税制が創設される前のものであることや、事業を分割して会社を設立し、当該新会社の株式を現物分配した事案ではなく、保有していた子会社株式を現物配当したものであるため、本稿との関係において直接の参考とはなりにくい。
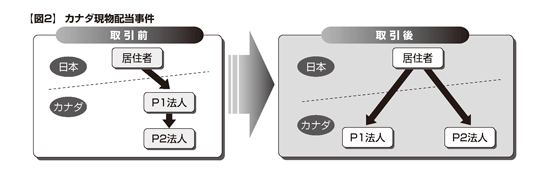
他方で、米国におけるスピンオフの事件については、まさに本件における検討対象の事例と同一の事実関係であり、参考となりうる事案である(図3参照)。
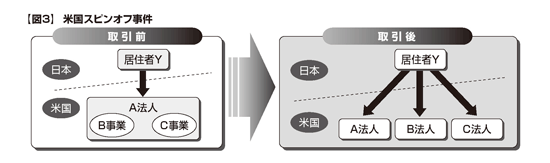
米国スピンオフ事件を具体的に説明すると、米国法人AがB事業とC事業を分社化し、各新設会社の株式を株主に分配するという取引(いわゆるスピンオフ)を行ったところ、このスピンオフにより、Aの株主である日本の居住者Yが新設会社株式を取得した事案である。この事案では、YはX証券会社の外国証券取引口座を通じてB及びC株式を取得し、XがB及びC株式の割当ては配当所得に該当することから源泉徴収が必要と判断してYに源泉徴収分を請求したところ、Yが源泉徴収分の支払を拒否し、XがYに対して源泉徴収分の支払請求訴訟を提起したというものである。
この事件において、第一審の東京地裁平成21年11月12日判決は、所得税法における「配当所得」及び「みなし配当」の意義を述べた上で、Yが取得したB及びC株式がAの利益剰余金を原資とする部分は配当所得に該当し、Aの資本剰余金を原資とする部分については、Yの出資額に対応する部分を超える部分についてはみなし配当に該当すると判示し、上級審においても、その判示内容は維持されている。この事案においては、米国におけるスピンオフが法人税法上の「分割」に該当するかという点については争点とされなかったため、裁判所は上記論点①及び②について明示的な判断をしていない。米国におけるスピンオフが法人税法上の「分割」に該当するかという点が争点とされたならば、論点①及び②に関する裁判所の考え方が明らかにされた可能性がある(脚注14)。
以上のとおり、裁判所においても、そもそも外国法を準拠法とする組織再編が法人税法上の「分割」に該当しうるか(論点①)、外国法を準拠法とする組織再編が如何なる要件を充足すれば日本の法人税法の「分割」に該当するか(論点②)という点について、解釈方法は未だ示されていない。
(3)小 括 以上のとおり、現行法の解釈として、外国法を準拠法とする組織再編は法人税法上の「分割」に該当し、さらに、「分割」を会社法からの借用概念と捉え、統一説を前提として、会社法上の会社分割と外国の法制度との比較を通じて法人税法の適用を検討する考え方が妥当であると考えられるが、裁判所において、この問題に対する解釈方法は示されていない。
このような議論状況のもとでは、実務上は、組織再編税制の立案担当者の回答や従前の実務上の取扱いに基づき、統一説の考え方に従って処理を行うのが現実的な選択となろう。
Ⅳ 実務上のポイント
1 具体的な検討手順 ここでは、実務上採用されている考え方を前提として、外国法を準拠法とする組織再編が如何なる要件を充足すれば日本の法人税法の「分割」に該当するかを具体的に検討する。
まず納税者が最初に行わなけれならないのは、日本法の弁護士のアドバイスを受けて、日本の会社法上の会社分割制度の重要な特徴を抽出する作業である(脚注15)。次に、外国の法制度が日本の会社分割制度の重要な特徴を有しているかどうかについて、外国法の条文を確認のうえ、外国法弁護士からの意見書などにより確認することになる。そして、日本の会社分割制度と外国の法制度が類似してるかどうかを日本法の弁護士のアドバイスをもとに比較分析して、類似しているとのロジックが構築できる場合には法人税法上の「分割」に該当するものとして、適格要件を充足するかどうかを判断し、最後に当局に事前相談して確認を得るという流れをとる(図4参照)。
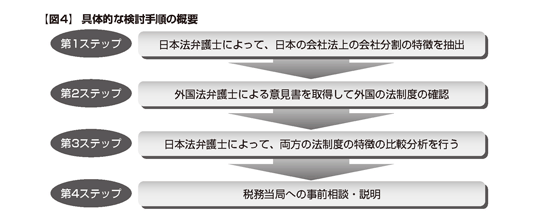
2 留 意 点 具体的な検討手順は上記のとおりであるが、実際に検討を行う場合には、(1)予測可能性、(2)コスト、及び(3)時間に留意する必要がある。
(1)予測可能性 具体的手順のうち、そもそも日本の会社分割の重要な特徴は何かという第1ステップで判断に迷うことになる。日本の会社分割制度の概要を述べると、会社分割は吸収分割と新設分割に分類されており、吸収分割契約を締結又は新設分割計画書を作成し、原則として株主総会の特別決議による承認を得る必要があり、また、事前の情報開示を実施したうえで株主保護手続及び債権者保護手続を経て、分割会社の事業に関して有する権利義務の全部又は一部が分割承継会社に包括的に承継されることになる。この一連の手続及び法的効果のうち、いずれが会社分割の特徴といえるかを判断する必要がある。会社分割の特徴に関し、法的効果については、包括承継であること、人的分割の場合には対価が直接株主に交付されるのではなく分割会社からの現物分配と構成されていることなどが挙げられるよう。また、手続については、意思決定機関が原則として株主総会であること、株主通知や反対株式買取請求権といった株主保護手続があること、債権者に対する公告・通知や債権者による異議の申述といった債権者保護手続があること、事前及び事後の情報開示が必要であること、手続上の瑕疵がある場合に無効の訴えが特別に設けられていることなどが挙げられよう。これらの特徴のうち、どれが会社分割の本質的要素であるのかを判断することは難しい。このことは、外国の法制度の特徴を抽出する際にも同様にあてはまる。
そして、外国の法制度が日本の会社分割制度の重要な特徴を有しているかを判断することが最も難しいと思われる。異なる法制度である以上、法的効果や手続に差異があることは否めない。しかも、大陸法系の国家(例えば、ドイツ、フランス)であれば、日本の法制度との類似性は比較的検討しやすいが、全く異なる法体系を有する国家の場合、日本と当該外国の各制度が類似しているかどうかの判断は困難を極める。
さらに、類似性を判断する際には、類似の程度の問題もある。例えば、日本の会社法においては、債権者保護手続(債権者への通知・官報公告、債権者による異議の申述など)が会社分割の本質的要素の1つであると判断される場合、仮に外国の法制度においては、債権者への通知しなければならない規定はあるものの、異議を申述することまでは認められていないことが判明したときに、債権者保護という特徴を有しているかを判断しなければならないが、その判断は難しいと思われる。
このように、内国法人が外国法を準拠法とする組織再編により課税されるのか否かについては、どの事項が、どの程度重要な特徴が類似していれば、「分割」に該当するのかという判断基準がないため、納税者側で両制度は類似しているとのロジックを構築したとしても、税務当局及び裁判所がそのロジックを是認するかどうは不明であり、納税者としては予測可能性が確保できないことが多いと思われる。
(2)コスト さらに、検討コストも無視することはできない。海外での組織再編を実施するためのコストの他に、まずは日本の法制度の分析が必要であるため、日本法の弁護士に依頼する必要がある。また、外国の法制度の分析や、後の税務当局への説明のために、当該外国法の該当条文を日本語に翻訳しておく必要がある。当該外国が英語を公用語とする国(シンガポール、インドなど)である場合には当該外国法を日本語に翻訳することは比較的容易であるが、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、マレーシア語等々が公用語の場合には、いったん外国法を英語に翻訳した上で日本語に翻訳しなければならないことが多く、正確な翻訳を入手するためのコストも無視できない。さらには、外国の法制度の分析のために、外国法弁護士に依頼し、意見書等を取得することが必要となる。
以上のように、検討コストが相当程度必要となることに留意を要する。
(3)時 間 日本法の分析にも一定程度の時間が必要となるが、さらに時間を要するのが、外国法弁護士とのコミュニケーションであると思われる。また、組織再編税制の立案担当者は、「海外子会社の現地における『合併』又は『分割』が我が国における合併又は分割と同様のものと考えて良いか否かを十分に検討し、執行当局に具体的な取扱いについてご確認をされた方が良いと思われます」と回答していることから(脚注16)、実際には、海外子会社が組織再編を行う前に、税務当局への説明を行うことになる(第4ステップ)。この税務当局への説明のための資料(日本の法制度、外国の法制度、及び両者の類似点・相違点を記載した三段表や当該外国法の条文の翻訳が考えられる。)の作成はもとより、当局とのやり取りにも時間がかかり、回答を取得するにはそれなりの時間を要することになる。この点も踏まえて海外での組織再編のスケジューリングを行う必要がある。
Ⅴ 今後の展望
1 執行の方向性 前記Ⅳの留意点のうち、現在の実務の取扱いが納税者の予測可能性を害している点については、問題が大きい。この点について、増井良啓教授は、「日本と異なる法制度を有する外国における取引をあてはめる上で、種々の困難が生ずることが予想される。あてはめの過程に不確実さが残れば、法的安定性と予測可能性を害することになってしまう」と指摘されており(脚注17)、まさに実務上の問題はこの点に尽きるといっても過言ではない。納税者のみならず、事前相談を受ける税務当局においても、日本の会社法のみならず、外国の法制度も理解しなけれならない。そのうえ、類似しているかどうかについての判断基準が何ら示されていないため、税務当局においても取扱いに困るのではないかと推察される。
この点については、外国法を準拠法とする事業体の性質決定に係る実務の対応が参考となる。外国法を準拠法とする事業体の性質決定の問題とは、外国で設立されたパートナーシップなどの事業体が日本の税法上の「法人」に該当するかという論点である。この点については、国税庁が「米国LLCに係る税務上の取扱い」と題する指針を出し、4つの基準から米国LLCが税法上「法人」に該当すると判断したことを公表した(脚注18)。また、外国法を準拠法とする事業体の性質決定の問題については、裁判例・裁決例も蓄積されており(脚注19)、一定の基準が形成されつつある。外国法を準拠法とする組織再編についても、税務当局から各組織再編の類似性についての判断基準が示されることや裁判所において基準が明らかとされることが望まれる。
2 立法への期待 現行の法解釈においては、前記Ⅲで検討したとおり、納税者の予測可能性・法的安定性を重視する統一説を前提として、会社法上の会社分割と外国の法制度との比較検討を踏まえて課税関係を決するという実務上の取扱いは妥当なものであると考えられる。しかし、立法論として、外国の法制度が日本の会社法上の制度と類似していない場合であっても、日本での課税繰延べを認めることはありえよう。吉村政穂准教授は、「……外国法人が当事法人となる組織再編に関して生じる課税上の問題は、わが国に居住する株主の課税、当該外国法人の日本所在のPEを構成する資産等の移転に係る課税、外国子会社合算税制との関係整理と多岐にわたる。(中略)これらの解決を、合併や分割などの解釈に係らしめるのは適当ではない。」と指摘されている(脚注20)。私法上の制度が類似していないことをもって課税繰延べを認めないとするのではなく、租税法独自の見地から、課税繰延べを認める必要性・許容性を検討し、外国法を準拠法とする組織再編について課税繰延べを認める要件を法律によって明確にしておくことが今後必要ではないかと思われる(脚注21)。課税繰延べが認められる具体的な要件については今後検討を進める必要があるが、差し当たりの方針として、①組織再編の前後で内国法人による投資が継続しており、②日本における課税権が当該組織再編によって脱漏しないことが確保されることが重要である。このような観点からすれば、具体的な要件としては、組織再編の対価が株式であること、組織再編後においても事業が継続すること、株主に比例的に対価が分配されること、などが挙げられよう(脚注22)。
以上のとおり、投資の継続性や海外での組織再編により日本の課税権が脱漏しないとの観点から、課税繰延べの要件を法律で明確に定めることが、納税者の予見可能性や租税負担の公平を確保し、さらには、日本企業の海外でのビジネス展開を促進することになると考えられる。
脚注
1 本稿に記載されている見解は、筆者の個人的な見解であり、筆者の属する法律事務所の見解でないことを付言する。
2 岡村忠生『法人税法講義[第3版]』(成文堂、2007年)405頁。
3 朝長英樹「企業組織再編成に係る税制について(第3回)」日本租税研究協会編『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』(日本租税研究協会、2001年)103頁。
4 税務当局は、一貫してこの解釈を採用しているものと考えられる(五枚橋實「企業再編税制にかかる誤り事例と留意点について」租税研究658号66頁等参照)。
5 南波洋「国外における組織再編等にかかる国内税法の適用関係について(中間報告)─日本公認会計士協会租税調査会研究報告第17号の解説─」租税研究721号118頁以下。
6 外国法上の概念が日本の租税法の借用概念との関係でどのように取り扱われるかという点については、平川雄士「借用概念論に関係する国際的企業租税実務上の諸問題」金子宏編『租税法の発展』(有斐閣、2010年)354頁以下参照。
7 増井良啓=宮崎裕子『国際租税法』(東京大学出版会、2008年)243頁。
8 なお、太田洋=佐藤修二「我が国の租税法規と外国私法との交錯」中里実ほか編『国際租税訴訟の最前線』(有斐閣、2010年)359頁以下は、租税法規趣旨探求説、外国私法基準説、及び内国私法基準説の3つに分類しているが、同書も指摘しているとおり、前2者の見解の区別が明確ではないため(360頁)、本稿では大きく2つの見解に分類している。
9 増井=宮崎・前掲(注7)244頁。
10 小林淳子「国外取引に対する租税法の適用と外国法人の分割に関する諸問題」税務大学校論叢45号272頁以下。
11 小林・前掲(注10)315~319頁。
12 借用概念に関する一般的な解説については、金子宏『租税法[第16版]』(弘文堂、2011年)110~113頁参照。
13 この事件に対する国税不服審判所裁決に関する解説として、増井良啓「外国会社からの現物分配と所得税―国税不服審判所平成15年4月9日裁決を素材として」税務事例研究84号41頁以下、浅妻敬=坂本英之「外国法人の組織再編により関連会社株式の分配を受けた株式に対する配当課税」税研20巻5号90頁以下がある。
14 但し、日本の会社分割制度が米国型の株主分配を利用した会社分割ではなく、分割を合併類似の組織再編として整理する欧州大陸型の制度となっていることを根拠として、米国におけるスピンオフが日本の法人税法上の「分割」には該当しない可能性が高いことを指摘するものとして、太田=佐藤・前掲(注8)358~359頁。
15 日本の会社法における合併について、事業譲渡と比較して重要な特徴を指摘するものとして、日本公認会計士協会「国外における組織再編等に係る国内税法の適用関係について(中間報告)」7~8頁参照。
16 朝長・前掲(注3)104頁。
17 増井・前掲(注13)60頁。
18 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/05/01.htm 19 米国ニューヨーク州のLLCが問題となった東京高裁平成19年10月10日判決・訟務月報54巻10号2516頁、ケイマン諸島の特例LPSが問題となった名古屋高裁平成19年3月8日判決・税務訴訟資料(250号~)257号10647順号(最高裁平成20年3月27日上告不受理決定により確定)、米国のLPSが問題となった国税不服審判所平成18年2月2日裁決がある。
20 吉村政穂「国際的組織再編をめぐる課税問題―日米比較を中心に―」租税法研究36号67頁脚注(50)。
21 米国においては、A型組織再編以外の適格組織再編は原則として民商法に依拠していない(渡辺徹也『企業組織再編成と課税』(弘文堂、2006年)29頁参照)。
22 もっとも、この点を突き詰めれば、米国のように、そもそも適格組織再編税制が会社法に依拠する必要はなく、準拠法が国内法か外国法かを問わず、組織再編が行われた場合の課税繰延べ要件を設定すべきであるとの議論につながっていくものと思われる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























