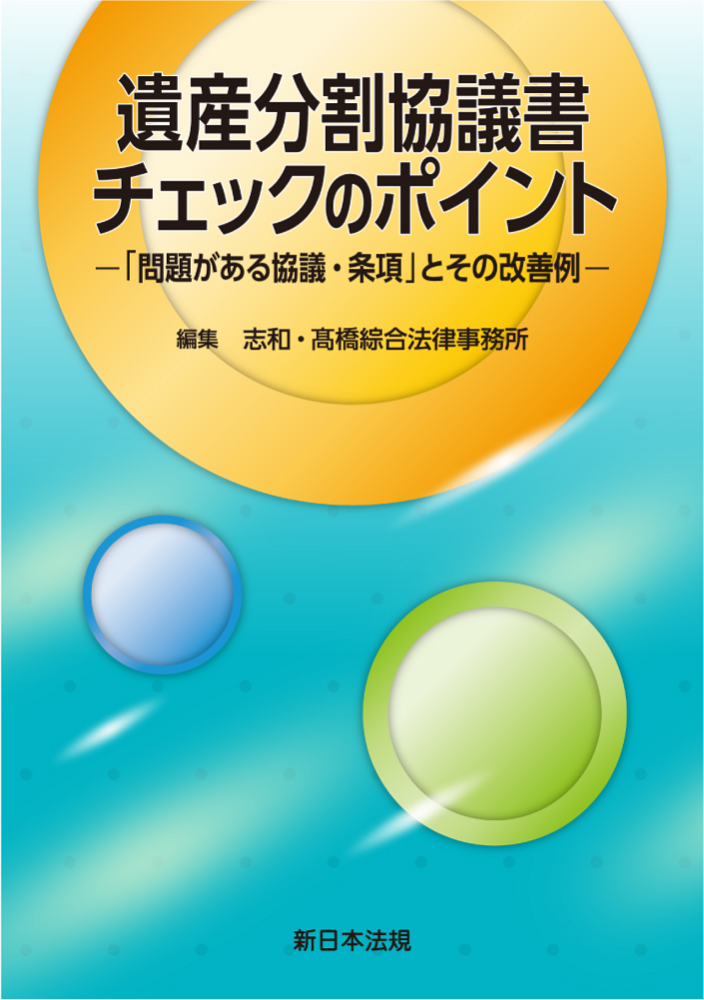解説記事2011年08月29日 【法令解説】 有価証券対価公開買付けに係る開示府令の改正の要点(2011年8月29日号・№416)
法令解説
有価証券対価公開買付けに係る開示府令の改正の要点
金融庁総務企画局企業開示課 課長補佐 小長谷章人
金融庁総務企画局企業開示課 専門官 有吉尚哉
Ⅰ はじめに
平成23年7月1日に施行された「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成23年法律第48号)に基づく産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「産活法」という)の改正により、買付者の自社株を対価とする公開買付け(以下「自社株対価公開買付け」という)に際しての株式の発行等に関する特例措置が設けられた(脚注1)。これまで、会社法の規制等を理由として自社株対価公開買付けが実施されることは限定的であったが、かかる産活法の特例により自社株対価公開買付けが実施される可能性が高まると考えられる(脚注2)。
このような状況を踏まえて、自社株対価公開買付けを含む有価証券をもって対価とする公開買付け(以下「有価証券対価公開買付け」という)に際して提出が必要とされる有価証券届出書等の記載事項の充実を図るため、平成23年6月17日から7月19日までの意見公募手続を経て、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成23年内閣府令第41号)が8月5日に公布され、同日に施行されている。
以下では、同府令に基づく改正の概要について解説する。なお、本稿において意見にわたる部分は筆者らの個人的な見解であることをお断りしておく。
Ⅱ 有価証券対価公開買付けに係る発行開示
有価証券対価公開買付けは公開買付けの1類型であり、買付者は公開買付開始公告(金融商品取引法(以下「法」という)27条の3第1項、27条の22の2第2項)、公開買付届出書の提出(法27条の3第2項、27条の22の2第2項)等の手続を行うことが必要となる。
同時に有価証券対価公開買付けは対価となる有価証券の取得または買付けの申込みの勧誘でもあり、募集または売出しに該当するため、公開買付けの対価となる有価証券に関して有価証券届出書の提出が必要となる(法4条1項)(脚注3)。
有価証券対価公開買付けに際して、買付者は、公開買付届出書の提出と同時に(脚注4)当該有価証券の発行者(自社株対価公開買付けの場合には発行者である買付者)が有価証券届出書等の提出を行っていなければ、売付け等の申込みの勧誘等の行為をしてはならない(法27条の4、27条の22の2第2項)。そして、法27条の4第1項の場合に提出する有価証券届出書の様式は、通常の有価証券の募集・売出しの際に用いられる企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という)第2号様式ではなく、特定組織再編成発行手続・特定組織再編成交付手続の際に用いられる開示府令第2号の6様式を用いることとされている(開示府令8条1項3号)(脚注5)。
金融商品取引法上、これまでも有価証券対価公開買付けが実施されることは想定されていたが、今後、産活法の特例により自社株対価公開買付けが実施される可能性が高まると考えられる。また、産活法の特例が適用される場合には、原則として株主総会における特別決議を要する(脚注6)などの規制が適用される一方で、会社法上の有利発行規制や現物出資規制といった株主(投資者)保護の規律が適用されないことになる。
自社株対価公開買付けに係る規制のあり方については、日本企業による企業買収の多様化・グローバル化のニーズを見極めつつ、株主・投資者保護を図りながらその実効性を高める観点から検討すべきものと考えられる(脚注7)。自社株対価公開買付けが日本企業の企業買収の現実的な選択肢となることは望ましいと考えられるが、その前提として株主・投資者保護が十全に図られることが必要である。
このような観点を踏まえて、今般の開示府令の改正は、主として自社株対価公開買付けにおける買付者の株主に対する情報提供の充実を図ることを目的として行うものである。
Ⅲ 開示府令の改正の概要
1 発行開示書類の記載事項の追加 開示府令第2号の6様式によって有価証券届出書を作成する場合においては、「組織再編成(公開買付け)に関する情報」として「組織再編成(公開買付け)の概要」を記載することが必要とされている。
今般の改正により、有価証券対価公開買付けの場合においては、「組織再編成(公開買付け)の概要」の項目として「有価証券をもって対価とする公開買付けの場合の発行(交付)条件に関する事項」を記載することを義務付けることとした(開示府令第2号の6様式第二部第1・6、「記載上の注意」(5-2))。具体的には、
① 発行(売出)価格(出資の目的とする有価証券との交換比率によって発行(売出)価格を決定している場合には、当該有価証券の種類および交換比率)その他の発行(交付)条件の合理性に関する考え方
② 当該発行(交付)条件により募集(売出し)を行う理由
③ 当該発行(交付)条件により募集(売出し)を行う判断の過程
について、具体的に記載することが求められる(脚注8)。
有価証券対価公開買付けの場合には、現行の様式においても「公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠」や「対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行(交付)される有価証券との相違」の記載が求められているが、これらの記載事項に加えて「有価証券をもって対価とする公開買付けの場合の発行(交付)条件に関する事項」の記載を求めることにより、公開買付けの条件が買付者の株主にとって不当に不利なものとなっていないか判断するための情報を提供することが可能となると考えられる(脚注9)。
2 臨時報告書の記載事項の追加 日本企業が外国企業を対象に自社株対価公開買付けを実施する場合など、国内ではなく海外で有価証券対価公開買付け(脚注10)が行われることも想定される。このような場合においても、株主・投資者保護の観点からは国内で有価証券対価公開買付けが実施された場合と同等の情報が開示されることが望ましいと考えられる。
本邦以外の地域において総額1億円以上の有価証券の募集等がなされた場合には、臨時報告書の提出が必要となり(開示府令19条2項1号、2号)、本邦以外の地域において有価証券対価公開買付けが実施された場合には、当該臨時報告書の提出が必要となるのが通常と考えられる。
今般の改正により、この場合の臨時報告書について、
① 公開買付けに係る割当ての内容およびその算定根拠
② 対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行(交付)される有価証券との相違
③ 有価証券をもって対価とする公開買付けの場合の発行(交付)条件に関する事項
を記載することを義務付けることとした(開示府令19条2項1号ワ、2号ヘ)。
なお、たとえば、金融商品取引法に基づく公開買付けと同時に、海外公開買付けを実施する場合など、実際に本邦以外の地域において株式の募集または売出しを行う場合には、有価証券届出書の提出に加えて、開示府令19条2項1号または2号に基づく臨時報告書の提出が必要となると考えられるが、外国株主が存在する会社を対象として金融商品取引法に基づく自社株対価公開買付けを実施する場合であっても、常に臨時報告書の提出が必要となるわけではないと考えられる(脚注11)。
3 企業内容等開示ガイドラインの改正 開示府令の改正によって有価証券対価公開買付けの場面における開示書類の記載事項を追加したことに伴い、企業内容等開示ガイドラインについても所要の改正を行っている。
Ⅳ 有価証券対価公開買付けに係る記載についてのその他の留意事項
今般の開示府令の改正に関わるものではないが、買付者の株式と対象会社の株式の交換比率によって発行の決議を行った場合における自社株対価公開買付けに係る有価証券届出書の次の3点の記載方法について、若干の解説を付言する(脚注12)。
① 「発行数」(開示府令第2号の6様式第一部第1・2(1))の欄には、買付予定数の上限と交換比率を基準に、発行される可能性のある最大の株式数を記載し、その旨を注記することが適当と考えられる(脚注13)。
② 「発行価額の総額」(開示府令第2号の6様式第一部第1・2(1))の欄には、届出書提出日現在における見込額として「発行数」と交換比率を基準に算定した金額を記載し、その旨を注記することが適当と考えられる。
③ 「発行価格」(開示府令第2号の6様式第一部第1・2(2))の欄には、対象会社の株式の種類と交換比率を記載することが適当と考えられる。
脚注
1 自社株対価公開買付けに関する産活法に基づく特例措置については、森規光=田端公美=持田恵梨=鈴木康平「改正産活法における会社法特例措置の要点」本誌414号28頁、藤田知也「改正産活法における会社法特例措置の概要」商事法務1933号26頁参照。
2 このような状況を踏まえて、自社株対価公開買付けが実施される場合における公開買付制度上の取扱いを明確化するため、平成23年7月1日に「株券等の公開買付けに関するQ&A」の追加が公表されている(野崎彰=池田賢生「自社株対価公開買付け等に係る公開買付制度上の取扱い(Q&A)の解説」商事法務1938号25頁参照)。
3 公開買付けは公告により不特定かつ多数の者に対し株券等の買付け等の申込み等を行うことであるので、この公開買付けの対価として有価証券を与えることは、一般的にいって有価証券の募集・売出しに該当する(内藤純一「新しい株式公開買付制度(中)」商事法務1221号23頁)。理論的には募集・売出しではなく私募・私売出しに該当する場合や法4条1項ただし書の規定により有価証券届出書の提出が必要とならない場合もまったくありえないわけではないと考えられるが、一般的には有価証券対価公開買付けは募集・売出しに該当し、有価証券届出書の提出が必要となることが通常であると考えられるため、本稿ではそのような場合を前提として解説を行うこととする。
4 公開買付届出書の提出前に有価証券届出書を提出することが否定されるものではなく、公開買付届出書の提出前に有価証券届出書を提出することは許容されると考えられる。
5 発行者が外国会社である場合には、開示府令第7号の4様式を用いることとされている(開示府令8条1項5号)。また、組込方式または参照方式による有価証券届出書を利用する場合や発行登録制度を利用する場合等には、それぞれ対応する様式を用いることとされている。各様式の改正事項は共通するため、本稿では開示府令第2号の6様式についてのみ言及し、他の様式についての改正の解説は省略する。
6 公開買付けの対価として交付する買付者の株式の数に1株当たり純資産額を乗じて得た額が、買付者の純資産額の5分の1以下のときには、一定の場合を除き、株主総会決議が不要となる(産活法21条の2第3項による会社法796条3項の読替適用)。
7 野崎彰=有吉尚哉=池田賢生「金融・資本市場の観点から重要と考えられる論点─会社法制関係─」商事法務1906号40頁参照。
8 なお、自社株対価公開買付けにおいては、公開買付けに応募した対象会社の株主に対して株式を割り当てることになり、株式を「特定の者に割り当てる方法」(開示府令19条2項1号ヲ)には該当しないため、基本的に「第三者割当」には該当せず、開示書類において「第三者割当」の場合に求められる特記事項の記載は必要とならないと考えられる。
9 今般の開示府令の改正では、「有価証券をもって対価とする公開買付けの場合の発行(交付)条件に関する事項」を記載事項として追加するための改正に加えて、有価証券対価公開買付けの場面で、公開買付届出書の提出がなされる前に有価証券届出書の提出がなされる場合の記載方法を明確にするための「記載上の注意」の改正を行っている(開示府令第2号の6様式「記載上の注意」柱書、(1)c)。
10 本稿Ⅲ2においては、有価証券をもって対価とする海外公開買付け(公開買付けに類するものであって外国の法令に基づいて不特定かつ多数の者に対して行われる株券等の買付け等の申込みまたは売付け等の申込みの勧誘)を含むものとする。
11 臨時報告書の提出が必要となる場合であっても、海外公開買付けに該当しない場合には、開示府令19条2項1号ワまたは2号ヘに規定する内容については記載を要しないと考えられる。
12 買付者が保有する株式を対価とする有価証券対価公開買付けの場合における有価証券届出書中の売出要項についても、以下に準じて記載することが求められる。
13 なお、公開買付期間が終了し、応募株券等の数が確定することにより、発行される株式数も確定することになるが、この段階では株式の取得の申込みは確定しているため、発行される株式数が確定することに関して訂正届出書を提出する必要はないと考えられる。
有価証券対価公開買付けに係る開示府令の改正の要点
金融庁総務企画局企業開示課 課長補佐 小長谷章人
金融庁総務企画局企業開示課 専門官 有吉尚哉
Ⅰ はじめに
平成23年7月1日に施行された「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成23年法律第48号)に基づく産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「産活法」という)の改正により、買付者の自社株を対価とする公開買付け(以下「自社株対価公開買付け」という)に際しての株式の発行等に関する特例措置が設けられた(脚注1)。これまで、会社法の規制等を理由として自社株対価公開買付けが実施されることは限定的であったが、かかる産活法の特例により自社株対価公開買付けが実施される可能性が高まると考えられる(脚注2)。
このような状況を踏まえて、自社株対価公開買付けを含む有価証券をもって対価とする公開買付け(以下「有価証券対価公開買付け」という)に際して提出が必要とされる有価証券届出書等の記載事項の充実を図るため、平成23年6月17日から7月19日までの意見公募手続を経て、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成23年内閣府令第41号)が8月5日に公布され、同日に施行されている。
以下では、同府令に基づく改正の概要について解説する。なお、本稿において意見にわたる部分は筆者らの個人的な見解であることをお断りしておく。
Ⅱ 有価証券対価公開買付けに係る発行開示
有価証券対価公開買付けは公開買付けの1類型であり、買付者は公開買付開始公告(金融商品取引法(以下「法」という)27条の3第1項、27条の22の2第2項)、公開買付届出書の提出(法27条の3第2項、27条の22の2第2項)等の手続を行うことが必要となる。
同時に有価証券対価公開買付けは対価となる有価証券の取得または買付けの申込みの勧誘でもあり、募集または売出しに該当するため、公開買付けの対価となる有価証券に関して有価証券届出書の提出が必要となる(法4条1項)(脚注3)。
有価証券対価公開買付けに際して、買付者は、公開買付届出書の提出と同時に(脚注4)当該有価証券の発行者(自社株対価公開買付けの場合には発行者である買付者)が有価証券届出書等の提出を行っていなければ、売付け等の申込みの勧誘等の行為をしてはならない(法27条の4、27条の22の2第2項)。そして、法27条の4第1項の場合に提出する有価証券届出書の様式は、通常の有価証券の募集・売出しの際に用いられる企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という)第2号様式ではなく、特定組織再編成発行手続・特定組織再編成交付手続の際に用いられる開示府令第2号の6様式を用いることとされている(開示府令8条1項3号)(脚注5)。
金融商品取引法上、これまでも有価証券対価公開買付けが実施されることは想定されていたが、今後、産活法の特例により自社株対価公開買付けが実施される可能性が高まると考えられる。また、産活法の特例が適用される場合には、原則として株主総会における特別決議を要する(脚注6)などの規制が適用される一方で、会社法上の有利発行規制や現物出資規制といった株主(投資者)保護の規律が適用されないことになる。
自社株対価公開買付けに係る規制のあり方については、日本企業による企業買収の多様化・グローバル化のニーズを見極めつつ、株主・投資者保護を図りながらその実効性を高める観点から検討すべきものと考えられる(脚注7)。自社株対価公開買付けが日本企業の企業買収の現実的な選択肢となることは望ましいと考えられるが、その前提として株主・投資者保護が十全に図られることが必要である。
このような観点を踏まえて、今般の開示府令の改正は、主として自社株対価公開買付けにおける買付者の株主に対する情報提供の充実を図ることを目的として行うものである。
Ⅲ 開示府令の改正の概要
1 発行開示書類の記載事項の追加 開示府令第2号の6様式によって有価証券届出書を作成する場合においては、「組織再編成(公開買付け)に関する情報」として「組織再編成(公開買付け)の概要」を記載することが必要とされている。
今般の改正により、有価証券対価公開買付けの場合においては、「組織再編成(公開買付け)の概要」の項目として「有価証券をもって対価とする公開買付けの場合の発行(交付)条件に関する事項」を記載することを義務付けることとした(開示府令第2号の6様式第二部第1・6、「記載上の注意」(5-2))。具体的には、
① 発行(売出)価格(出資の目的とする有価証券との交換比率によって発行(売出)価格を決定している場合には、当該有価証券の種類および交換比率)その他の発行(交付)条件の合理性に関する考え方
② 当該発行(交付)条件により募集(売出し)を行う理由
③ 当該発行(交付)条件により募集(売出し)を行う判断の過程
について、具体的に記載することが求められる(脚注8)。
有価証券対価公開買付けの場合には、現行の様式においても「公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠」や「対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行(交付)される有価証券との相違」の記載が求められているが、これらの記載事項に加えて「有価証券をもって対価とする公開買付けの場合の発行(交付)条件に関する事項」の記載を求めることにより、公開買付けの条件が買付者の株主にとって不当に不利なものとなっていないか判断するための情報を提供することが可能となると考えられる(脚注9)。
2 臨時報告書の記載事項の追加 日本企業が外国企業を対象に自社株対価公開買付けを実施する場合など、国内ではなく海外で有価証券対価公開買付け(脚注10)が行われることも想定される。このような場合においても、株主・投資者保護の観点からは国内で有価証券対価公開買付けが実施された場合と同等の情報が開示されることが望ましいと考えられる。
本邦以外の地域において総額1億円以上の有価証券の募集等がなされた場合には、臨時報告書の提出が必要となり(開示府令19条2項1号、2号)、本邦以外の地域において有価証券対価公開買付けが実施された場合には、当該臨時報告書の提出が必要となるのが通常と考えられる。
今般の改正により、この場合の臨時報告書について、
① 公開買付けに係る割当ての内容およびその算定根拠
② 対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行(交付)される有価証券との相違
③ 有価証券をもって対価とする公開買付けの場合の発行(交付)条件に関する事項
を記載することを義務付けることとした(開示府令19条2項1号ワ、2号ヘ)。
なお、たとえば、金融商品取引法に基づく公開買付けと同時に、海外公開買付けを実施する場合など、実際に本邦以外の地域において株式の募集または売出しを行う場合には、有価証券届出書の提出に加えて、開示府令19条2項1号または2号に基づく臨時報告書の提出が必要となると考えられるが、外国株主が存在する会社を対象として金融商品取引法に基づく自社株対価公開買付けを実施する場合であっても、常に臨時報告書の提出が必要となるわけではないと考えられる(脚注11)。
3 企業内容等開示ガイドラインの改正 開示府令の改正によって有価証券対価公開買付けの場面における開示書類の記載事項を追加したことに伴い、企業内容等開示ガイドラインについても所要の改正を行っている。
Ⅳ 有価証券対価公開買付けに係る記載についてのその他の留意事項
今般の開示府令の改正に関わるものではないが、買付者の株式と対象会社の株式の交換比率によって発行の決議を行った場合における自社株対価公開買付けに係る有価証券届出書の次の3点の記載方法について、若干の解説を付言する(脚注12)。
① 「発行数」(開示府令第2号の6様式第一部第1・2(1))の欄には、買付予定数の上限と交換比率を基準に、発行される可能性のある最大の株式数を記載し、その旨を注記することが適当と考えられる(脚注13)。
② 「発行価額の総額」(開示府令第2号の6様式第一部第1・2(1))の欄には、届出書提出日現在における見込額として「発行数」と交換比率を基準に算定した金額を記載し、その旨を注記することが適当と考えられる。
③ 「発行価格」(開示府令第2号の6様式第一部第1・2(2))の欄には、対象会社の株式の種類と交換比率を記載することが適当と考えられる。
脚注
1 自社株対価公開買付けに関する産活法に基づく特例措置については、森規光=田端公美=持田恵梨=鈴木康平「改正産活法における会社法特例措置の要点」本誌414号28頁、藤田知也「改正産活法における会社法特例措置の概要」商事法務1933号26頁参照。
2 このような状況を踏まえて、自社株対価公開買付けが実施される場合における公開買付制度上の取扱いを明確化するため、平成23年7月1日に「株券等の公開買付けに関するQ&A」の追加が公表されている(野崎彰=池田賢生「自社株対価公開買付け等に係る公開買付制度上の取扱い(Q&A)の解説」商事法務1938号25頁参照)。
3 公開買付けは公告により不特定かつ多数の者に対し株券等の買付け等の申込み等を行うことであるので、この公開買付けの対価として有価証券を与えることは、一般的にいって有価証券の募集・売出しに該当する(内藤純一「新しい株式公開買付制度(中)」商事法務1221号23頁)。理論的には募集・売出しではなく私募・私売出しに該当する場合や法4条1項ただし書の規定により有価証券届出書の提出が必要とならない場合もまったくありえないわけではないと考えられるが、一般的には有価証券対価公開買付けは募集・売出しに該当し、有価証券届出書の提出が必要となることが通常であると考えられるため、本稿ではそのような場合を前提として解説を行うこととする。
4 公開買付届出書の提出前に有価証券届出書を提出することが否定されるものではなく、公開買付届出書の提出前に有価証券届出書を提出することは許容されると考えられる。
5 発行者が外国会社である場合には、開示府令第7号の4様式を用いることとされている(開示府令8条1項5号)。また、組込方式または参照方式による有価証券届出書を利用する場合や発行登録制度を利用する場合等には、それぞれ対応する様式を用いることとされている。各様式の改正事項は共通するため、本稿では開示府令第2号の6様式についてのみ言及し、他の様式についての改正の解説は省略する。
6 公開買付けの対価として交付する買付者の株式の数に1株当たり純資産額を乗じて得た額が、買付者の純資産額の5分の1以下のときには、一定の場合を除き、株主総会決議が不要となる(産活法21条の2第3項による会社法796条3項の読替適用)。
7 野崎彰=有吉尚哉=池田賢生「金融・資本市場の観点から重要と考えられる論点─会社法制関係─」商事法務1906号40頁参照。
8 なお、自社株対価公開買付けにおいては、公開買付けに応募した対象会社の株主に対して株式を割り当てることになり、株式を「特定の者に割り当てる方法」(開示府令19条2項1号ヲ)には該当しないため、基本的に「第三者割当」には該当せず、開示書類において「第三者割当」の場合に求められる特記事項の記載は必要とならないと考えられる。
9 今般の開示府令の改正では、「有価証券をもって対価とする公開買付けの場合の発行(交付)条件に関する事項」を記載事項として追加するための改正に加えて、有価証券対価公開買付けの場面で、公開買付届出書の提出がなされる前に有価証券届出書の提出がなされる場合の記載方法を明確にするための「記載上の注意」の改正を行っている(開示府令第2号の6様式「記載上の注意」柱書、(1)c)。
10 本稿Ⅲ2においては、有価証券をもって対価とする海外公開買付け(公開買付けに類するものであって外国の法令に基づいて不特定かつ多数の者に対して行われる株券等の買付け等の申込みまたは売付け等の申込みの勧誘)を含むものとする。
11 臨時報告書の提出が必要となる場合であっても、海外公開買付けに該当しない場合には、開示府令19条2項1号ワまたは2号ヘに規定する内容については記載を要しないと考えられる。
12 買付者が保有する株式を対価とする有価証券対価公開買付けの場合における有価証券届出書中の売出要項についても、以下に準じて記載することが求められる。
13 なお、公開買付期間が終了し、応募株券等の数が確定することにより、発行される株式数も確定することになるが、この段階では株式の取得の申込みは確定しているため、発行される株式数が確定することに関して訂正届出書を提出する必要はないと考えられる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.