解説記事2012年04月09日 【ニュース特集】 平成24年度税制改正の政省令のポイント(2012年4月9日号・№446)
国外財産調書制度や買換特例等の全容は?
平成24年度税制改正の政省令のポイント
「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」および「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案」が3月30日に国会で成立。31日に公布された。平成23年度改正とは異なり、年度内での成立となった。平成24年度改正は、法律名が示すように租税特別措置の適用期限の延長などが主たる改正内容となっている。改正法とともに公布された政省令(要綱等は今号28頁参照)で明らかになった項目を中心に、そのポイントを解説する。
措置法関係のポイントとは?
事業用の賃貸マンションも適用可 租税特別措置法関係からみると、法人課税では、特定の事業用資産の買換え特例における「特定施設」が明らかとなった(措令25条、39条の7、39条の106関係)。同制度は、個人または法人が長期保有(10年超)の事業用の土地、建物等を譲渡し、新たに土地、建物、機械装置等の事業用資産(買換資産)を取得した場合には、譲渡した事業用資産の譲渡益について圧縮記帳(圧縮割合80%)を認めるという制度である(図表1参照)。
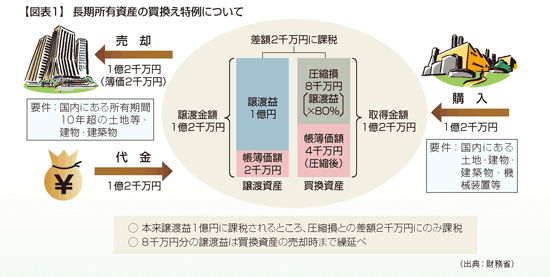
同制度は適用期限が3年延長されることになったが、現行制度では特に制限のなかった買換資産について、土地等の場合には、事業活動に活用される建物等の敷地の用に供される場合(特定施設)に限定されることになった(面積は300㎡以上のもの)。
特定施設とは、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設とされた。賃貸用マンションなども事業の用に供していれば特例の適用が認められることになる。ただし、福利厚生施設に該当するものは除かれているので要注意だ(本誌441号9頁参照)。
また、駐車場単独では、買換資産の対象とはならないが、「やむを得ない事情がある」場合に限っては適用が認められる。具体的には、①都市計画法29条1項または2項の規定による許可の手続、②建築基準法6条1項に規定する確認の手続、③文化財保護法93条2項に規定する発掘調査、④建築物の建築に関する条例に基づく手続(建物または構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものにつき国土交通大臣が証明したもの)が進行中である旨が明記された。
1台30万円以上で複数台120万円以上 中小企業投資促進税制については、適用期限が平成26年3月31日まで2年間延長されるとともに、対象資産の範囲に「製品の品質管理の向上に資する工具、器具及び備品」が追加された(図表2参照)。
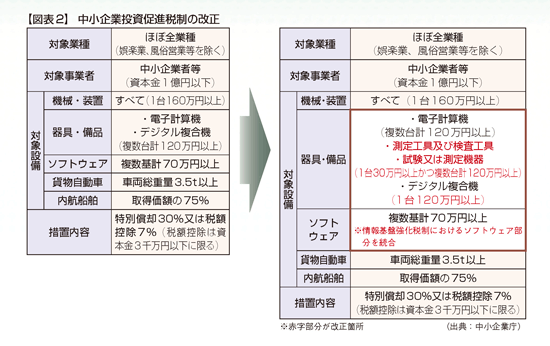
具体的には、「測定工具及び検査工具」「試験又は測定機器」と規定された。設備振動試験器や蛍光X線分子機器等が該当し、1台30万円以上かつ複数台計120万円以上との要件が付されている(措規5条の8、20条の3、22条の25関係)。
また、デジタル複合機については、これまで1事業年度における複数台の取得価額の合計額が120万円以上の場合、いわゆる“まとめ買い”についても対象となっていたが、1台120万円以上との制限が付されることになったので要注意だ(本誌442号11頁参照)。なお、情報基盤強化税制については、対象設備のうちソフトウェア部分が中小企業投資促進税制に統合されている。
太陽光発電設備は10kW以上 また、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却または特別税額控除制度について、即時償却の対象設備が明らかになっている(措令5条の4、27条の5、39条の40関係)。
同制度は、平成24年7月1日から平成25年3月31日までの間に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備に該当する太陽光または風力の利用に資する機械その他の減価償却資産のうち一定のものを取得等して1年以内に事業の用に供した場合には、その事業年度において即時償却ができるというもの。本誌ですでにお伝えしているとおり、「一定のもの」とは、太陽光発電設備の場合は10kW以上、風力発電設備の場合は1万kW以上とされている(本誌441号8頁参照)。
上限は240㎡ 資産課税では、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(図表3参照)について、適用対象となる住宅用の家屋の床面積の上限が240㎡とされた(措令40条の4の2関係)。
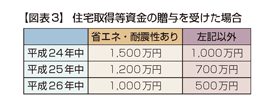
国外財産調書制度のポイントは? 平成24年度税制改正の大きな目玉の1つである国外財産調書制度については、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令等により、その全容が明らかとなっている。
本邦通貨への換算も12月31日時点 同制度では、その年の12月31日において5,000万円を超える国外財産を有する居住者については、国外財産調書を翌年の3月15日までに所轄税務署長に提出することが義務付けられている。
国外財産の所在の判定は「その年の12月31日」となり、最初は平成25年12月31日で判定される。国外財産の価額も時価または時価に準ずる価額(見積価額)とされる。なお、外国通貨で表示される場合の本邦通貨への換算は12月31日時点での外国為替の売買相場で行うことになる。
国外財産調書については、氏名および住所等のほか、図表4に掲げる国外財産の種類、数量、価額および所在その他必要な事項を記載することになる。
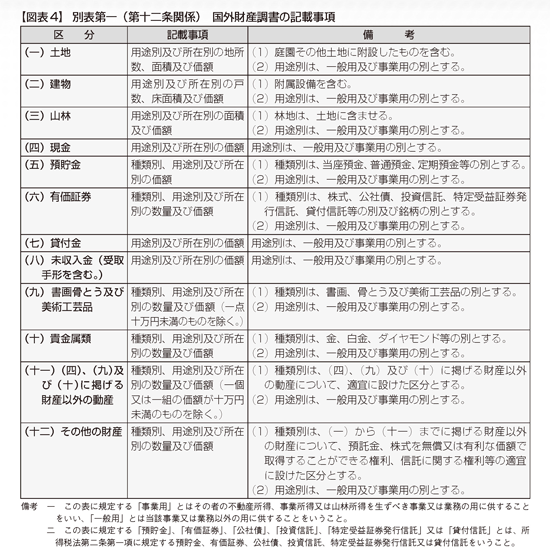
所得税関係のポイントは? 所得課税関係では、勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税が廃止されるが、役員等勤続年数の計算方法等が定められている(所令69条の2、71条の2、319条の3関係)。
また、給与所得者の特定支出控除の範囲が拡大され、職務に必要な書籍、新聞・雑誌など、また、制服や作業服など、職場で着用する衣服も対象となる(所令167条の3関係)。接待等をした場合の確定申告書等に添付する明細書の記載事項(支出内容、相手方の氏名、金額等)も定められている(所令167条の4、167条の5関係)。
そのほか、外国親会社から内国子法人の従業員等に対してストック・オプションが直接付与されることにより、所得の申告漏れが見受けられる状況を踏まえ、外国親会社等の経済的利益の供与等に関する調書制度が創設される。具体的には、外国法人がその発行済株式等の50%以上を保有する内国法人等の役員や従業員である居住者等に対して、ストック・オプション等が付与された場合となるが、その判定方法や調書の記載事項が定められている(所令354条の3関係)。
平成24年度税制改正の政省令のポイント
「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」および「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律案」が3月30日に国会で成立。31日に公布された。平成23年度改正とは異なり、年度内での成立となった。平成24年度改正は、法律名が示すように租税特別措置の適用期限の延長などが主たる改正内容となっている。改正法とともに公布された政省令(要綱等は今号28頁参照)で明らかになった項目を中心に、そのポイントを解説する。
措置法関係のポイントとは?
事業用の賃貸マンションも適用可 租税特別措置法関係からみると、法人課税では、特定の事業用資産の買換え特例における「特定施設」が明らかとなった(措令25条、39条の7、39条の106関係)。同制度は、個人または法人が長期保有(10年超)の事業用の土地、建物等を譲渡し、新たに土地、建物、機械装置等の事業用資産(買換資産)を取得した場合には、譲渡した事業用資産の譲渡益について圧縮記帳(圧縮割合80%)を認めるという制度である(図表1参照)。
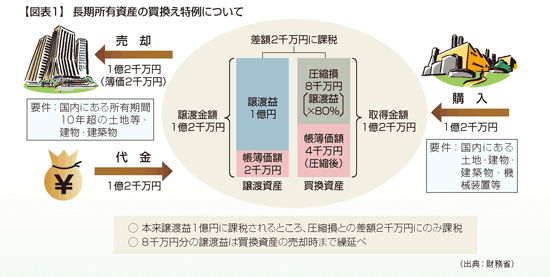
同制度は適用期限が3年延長されることになったが、現行制度では特に制限のなかった買換資産について、土地等の場合には、事業活動に活用される建物等の敷地の用に供される場合(特定施設)に限定されることになった(面積は300㎡以上のもの)。
特定施設とは、事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設とされた。賃貸用マンションなども事業の用に供していれば特例の適用が認められることになる。ただし、福利厚生施設に該当するものは除かれているので要注意だ(本誌441号9頁参照)。
また、駐車場単独では、買換資産の対象とはならないが、「やむを得ない事情がある」場合に限っては適用が認められる。具体的には、①都市計画法29条1項または2項の規定による許可の手続、②建築基準法6条1項に規定する確認の手続、③文化財保護法93条2項に規定する発掘調査、④建築物の建築に関する条例に基づく手続(建物または構築物の敷地の用に供されていないことが当該手続を理由とするものにつき国土交通大臣が証明したもの)が進行中である旨が明記された。
1台30万円以上で複数台120万円以上 中小企業投資促進税制については、適用期限が平成26年3月31日まで2年間延長されるとともに、対象資産の範囲に「製品の品質管理の向上に資する工具、器具及び備品」が追加された(図表2参照)。
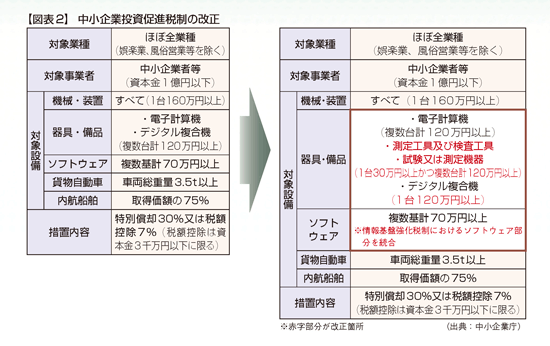
具体的には、「測定工具及び検査工具」「試験又は測定機器」と規定された。設備振動試験器や蛍光X線分子機器等が該当し、1台30万円以上かつ複数台計120万円以上との要件が付されている(措規5条の8、20条の3、22条の25関係)。
また、デジタル複合機については、これまで1事業年度における複数台の取得価額の合計額が120万円以上の場合、いわゆる“まとめ買い”についても対象となっていたが、1台120万円以上との制限が付されることになったので要注意だ(本誌442号11頁参照)。なお、情報基盤強化税制については、対象設備のうちソフトウェア部分が中小企業投資促進税制に統合されている。
太陽光発電設備は10kW以上 また、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却または特別税額控除制度について、即時償却の対象設備が明らかになっている(措令5条の4、27条の5、39条の40関係)。
同制度は、平成24年7月1日から平成25年3月31日までの間に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備に該当する太陽光または風力の利用に資する機械その他の減価償却資産のうち一定のものを取得等して1年以内に事業の用に供した場合には、その事業年度において即時償却ができるというもの。本誌ですでにお伝えしているとおり、「一定のもの」とは、太陽光発電設備の場合は10kW以上、風力発電設備の場合は1万kW以上とされている(本誌441号8頁参照)。
上限は240㎡ 資産課税では、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(図表3参照)について、適用対象となる住宅用の家屋の床面積の上限が240㎡とされた(措令40条の4の2関係)。
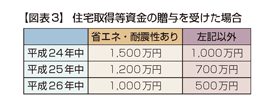
国外財産調書制度のポイントは? 平成24年度税制改正の大きな目玉の1つである国外財産調書制度については、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令等により、その全容が明らかとなっている。
本邦通貨への換算も12月31日時点 同制度では、その年の12月31日において5,000万円を超える国外財産を有する居住者については、国外財産調書を翌年の3月15日までに所轄税務署長に提出することが義務付けられている。
国外財産の所在の判定は「その年の12月31日」となり、最初は平成25年12月31日で判定される。国外財産の価額も時価または時価に準ずる価額(見積価額)とされる。なお、外国通貨で表示される場合の本邦通貨への換算は12月31日時点での外国為替の売買相場で行うことになる。
国外財産調書については、氏名および住所等のほか、図表4に掲げる国外財産の種類、数量、価額および所在その他必要な事項を記載することになる。
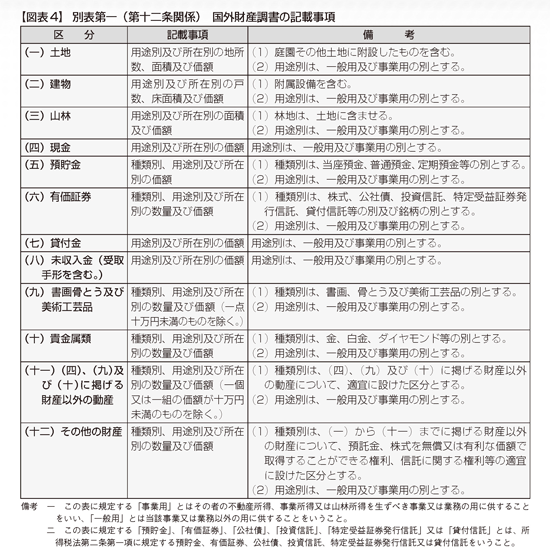
所得税関係のポイントは? 所得課税関係では、勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税が廃止されるが、役員等勤続年数の計算方法等が定められている(所令69条の2、71条の2、319条の3関係)。
また、給与所得者の特定支出控除の範囲が拡大され、職務に必要な書籍、新聞・雑誌など、また、制服や作業服など、職場で着用する衣服も対象となる(所令167条の3関係)。接待等をした場合の確定申告書等に添付する明細書の記載事項(支出内容、相手方の氏名、金額等)も定められている(所令167条の4、167条の5関係)。
そのほか、外国親会社から内国子法人の従業員等に対してストック・オプションが直接付与されることにより、所得の申告漏れが見受けられる状況を踏まえ、外国親会社等の経済的利益の供与等に関する調書制度が創設される。具体的には、外国法人がその発行済株式等の50%以上を保有する内国法人等の役員や従業員である居住者等に対して、ストック・オプション等が付与された場合となるが、その判定方法や調書の記載事項が定められている(所令354条の3関係)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























