解説記事2012年09月03日 【インタビュー】 株式保有特定会社、条件変われば25%基準妥当性の検証が必要(2012年9月3日号・№465)
評価通達制定に携わった品川芳宣筑波大学名誉教授に聞く
株式保有特定会社、条件変われば25%基準妥当性の検証が必要
裁判所が一石を投じた25%基準の合理性 本誌:平成元年頃に上場企業の経営者などが個人で保有していた上場株式を非上場会社に移したうえで、その非上場会社に類似業種比準方式を適用し、極端な株価の圧縮を図るという節税策が横行していました。節税策を封じる意味があったと思うのですが、平成2年の改正で評価通達189の(2)を新設。資産に占める株式保有割合が25%以上の大会社を株式保有特定会社としたうえ、類似業種比準方式の適用を原則として禁止する取扱いとしました。
この「25%以上」という数値はどのように算定したのですか。
品川教授:平成2年当時の法人企業統計を基に算定した資本金10億円以上のすべての業種の営利法人(金融業及び保険業を除く)の株式保有割合の数値は7.88%であり、評価通達ではその数値の3倍以上の25%を設定した。
本誌:評価通達において、「株式保有特定会社」と命名した理由を教えてください。
品川教授:実務では持株会社と言っていたので、当初は持株会社としようとした。
しかし、当時、独占禁止法上持株会社は認められていなかったため、公正取引委員会から持株会社という言葉は使わないでほしいと言われたので、持株会社と命名せず、株式保有特定会社と命名した。
本誌:平成2年の評価通達改正後、平成9年の独占禁止法改正で全面的に禁止されていた持株会社が一部容認されました。これを契機に、商法等で持株会社や完全親子会社を創設するための株式交換等の制度の創設、合併制度の合理化、会社分割制度の創設といった企業の組織再編に必要な規定の整備が進められました。評価通達改正時と比べて、会社の株式保有状況は大きく変化していると思われます。
株式保有割合25%以上という基準は現在でも合理的と考えられますか。
品川教授:20年以上前の数値が正しいとは限らない。類似業種比準方式適用の是非についての条件が変われば、25%基準の妥当性は検証していかなければならない。
先ほど述べたとおり、平成2年当時は25%と設定したが、(本件の相続開始時である)平成15年度において、その株式保有割合の数値が16.31%と倍以上の割合になっていたというのであれば、その当時において、25%という基準がなお合理的であるか否かについて検討する必要はある。
本誌:今回の東京地裁判決をお読みになり、どのような感想を持ちましたか。
品川教授:個別の株式についてどう評価するか(時価とは何か)という点が問題となっている。元々通達に拘束されない裁判所がその通達を前提に個別の評価を行ったものであるが、その個別評価の妥当性を論じるに当たっては、時価をめぐる諸条件を総合して判断を要する。
ただ、評価通達制定から20年以上経過した株式保有割合25%というものの合理性に関して、裁判所が一石を投じたものであり、今後、上級審がどのような判断を下すのか、非常に注目している。
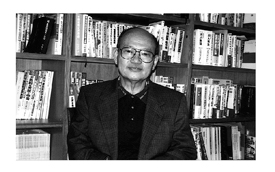
品川芳宣 しながわ よしのぶ
慶応義塾大学経済学部卒業。国税庁資産評価企画官、徴収課長、管理課長、高松国税局長等を経て、筑波大学大学院教授、早稲田大学大学院教授。現在は筑波大学名誉教授、弁護士。「附帯税の事例研究」(財経詳報社、日税研究奨励賞受賞)、「相続税財産評価の論点」(ぎょうせい)、「重要租税判決の実務研究」(大蔵財務協会)ほか、著書・論文多数。
株式保有特定会社、条件変われば25%基準妥当性の検証が必要
| 非上場株式の相続税評価を巡り、大会社に該当する会社が、株式保有特定会社に該当するか否かが争われていた事案で国側が全面的に敗訴する判決が平成24年3月2日、東京地裁(八木一洋裁判長)であった(平成21年(行ウ)第28号、本誌442号9頁、445号4頁参照)。八木裁判長は、相続開始時において、株式保有割合が25%以上である大会社について一律に財産評価基本通達189の(2)を適用することはできないと判断。評価通達が規定する「25%以上」の部分を画一的に運用してきた課税当局の姿勢に“待ったをかける”ものとなっている。 全面敗訴した国側は東京高裁へ控訴。控訴審の行方に注目が集まっているが、本誌では国税庁において当時の財産評価基本通達の制定に携わった品川芳宣筑波大学名誉教授に、今回の東京地裁の判断などについてインタビューを行った。 |
裁判所が一石を投じた25%基準の合理性 本誌:平成元年頃に上場企業の経営者などが個人で保有していた上場株式を非上場会社に移したうえで、その非上場会社に類似業種比準方式を適用し、極端な株価の圧縮を図るという節税策が横行していました。節税策を封じる意味があったと思うのですが、平成2年の改正で評価通達189の(2)を新設。資産に占める株式保有割合が25%以上の大会社を株式保有特定会社としたうえ、類似業種比準方式の適用を原則として禁止する取扱いとしました。
この「25%以上」という数値はどのように算定したのですか。
品川教授:平成2年当時の法人企業統計を基に算定した資本金10億円以上のすべての業種の営利法人(金融業及び保険業を除く)の株式保有割合の数値は7.88%であり、評価通達ではその数値の3倍以上の25%を設定した。
本誌:評価通達において、「株式保有特定会社」と命名した理由を教えてください。
品川教授:実務では持株会社と言っていたので、当初は持株会社としようとした。
しかし、当時、独占禁止法上持株会社は認められていなかったため、公正取引委員会から持株会社という言葉は使わないでほしいと言われたので、持株会社と命名せず、株式保有特定会社と命名した。
本誌:平成2年の評価通達改正後、平成9年の独占禁止法改正で全面的に禁止されていた持株会社が一部容認されました。これを契機に、商法等で持株会社や完全親子会社を創設するための株式交換等の制度の創設、合併制度の合理化、会社分割制度の創設といった企業の組織再編に必要な規定の整備が進められました。評価通達改正時と比べて、会社の株式保有状況は大きく変化していると思われます。
株式保有割合25%以上という基準は現在でも合理的と考えられますか。
品川教授:20年以上前の数値が正しいとは限らない。類似業種比準方式適用の是非についての条件が変われば、25%基準の妥当性は検証していかなければならない。
先ほど述べたとおり、平成2年当時は25%と設定したが、(本件の相続開始時である)平成15年度において、その株式保有割合の数値が16.31%と倍以上の割合になっていたというのであれば、その当時において、25%という基準がなお合理的であるか否かについて検討する必要はある。
本誌:今回の東京地裁判決をお読みになり、どのような感想を持ちましたか。
品川教授:個別の株式についてどう評価するか(時価とは何か)という点が問題となっている。元々通達に拘束されない裁判所がその通達を前提に個別の評価を行ったものであるが、その個別評価の妥当性を論じるに当たっては、時価をめぐる諸条件を総合して判断を要する。
ただ、評価通達制定から20年以上経過した株式保有割合25%というものの合理性に関して、裁判所が一石を投じたものであり、今後、上級審がどのような判断を下すのか、非常に注目している。
| 財産評価基本通達189の(2)(株式保有特定会社の株式) |
| 課税時期において評価会社の有する各資産をこの通達に定めるところにより評価した価額の合計額のうちに占める株式及び出資の価額の合計額の割合が25%以上である評価会社の株式の価額は、189-3≪株式保有特定会社の株式の評価≫の定めによる。(一部抜粋) |
| 東京地裁は評価通達制定時の合理性を認めるも…… |
| 本事案は、非上場会社であるX社(大会社)の株式を相続した納税者が行った相続税の申告に対して、税務署がX社の株式保有割合が約25.9%であることから、X株は株式保有特定会社に該当すると判断し、当初申告額に加えて約50億円の追徴課税を行っていたもの。審査請求では、審判所が評価通達の合理性を認めたうえで納税者の請求を棄却。このため、納税者が課税処分の取消しを求めて訴訟を提起したものである。 東京地裁民事第3部の八木一洋裁判長は、総資産に占める株式保有割合が25%以上である大会社を一律に株式保有特定会社とする部分の合理性について、評価通達の平成2年改正時においては、合理性があったことを指摘。しかし、通達改正後の独禁法改正による持株会社の一部容認、商法等における企業組織再編の規定整備などにより、本件相続開始時においては、通達改正当時と比べ、会社の株式保有状況が大きく変化していることなどを指摘。少なくとも、本件相続開始時においては、株式保有割合が25%以上である大会社のすべてについて、一律に同通達を適用することはできないと判断した。 |
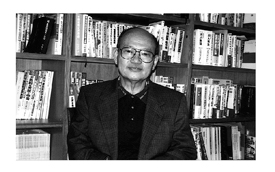
品川芳宣 しながわ よしのぶ
慶応義塾大学経済学部卒業。国税庁資産評価企画官、徴収課長、管理課長、高松国税局長等を経て、筑波大学大学院教授、早稲田大学大学院教授。現在は筑波大学名誉教授、弁護士。「附帯税の事例研究」(財経詳報社、日税研究奨励賞受賞)、「相続税財産評価の論点」(ぎょうせい)、「重要租税判決の実務研究」(大蔵財務協会)ほか、著書・論文多数。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























