解説記事2012年09月03日 【税務マエストロ】 タックスヘイブン対策税制─合算所得金額の計算①(2012年9月3日号・№465)
税務マエストロ
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
タックスヘイブン対策税制─合算所得金額の計算①
統括会社に係る例外規定
#52 品川克己
日本公認会計士協会租税調査会専門委員(国際租税専門部会)
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(マネージング・ディレクター)
略歴 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究。97年より00年までOECD租税委員会に主任行政官として出向(在フランス)し、「OECD移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財務省を辞職し現職。
次回のテーマ
#53 経営戦略に応える企業再編成税制 税理士 朝長英樹 経営戦略の1つとして組織再編成税制を活用できる方法を、同税制等の創設を主導した筆者が事例形式で解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
マエストロの解説 海外に有する子会社が特定外国子会社等に該当し、かつ、適用除外基準を満たしていない場合には、その子会社の所得は親会社たる日本法人の所得とみなして課税されることとなる。つまり、親会社の所得に合算して、日本で課税されることとなる。この場合、合算される所得は、外国法人たる特定外国子会社等の所得であり、必ずしも日本の法令に基づいて表示されているわけではない。こうした外国の法人の所得金額を、日本での課税にあたり、どのように計算するのかが次のテーマである。
1 概 要 タックスヘイブン対策税制による合算所得は、特定外国子会社等の課税所得を基礎として、「基準所得金額」、「適用対象金額」、「課税対象金額」の順に計算される(措法66の6①)(脚注1)。
(図1参照)。
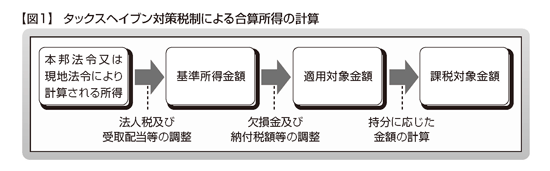
この「基準所得金額」は、原則的には、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額であり、一般的には、会計上の税引前利益を意味するところであるが、これを①法人税法および租税特別措置法における所得計算に準じた方法で計算する方法又は②現地法令により計算された課税所得にいくつかの調整を加える方法で計算し、最終的に我が国の法令により計算した課税所得金額に近いものとなる(措法66の6②二)。
次に「適用対象金額」は、基準所得金額に前7年の欠損の金額および当該年度の税額による調整を加えた金額となる(措法66の6②二)。
最後に「課税対象金額」は、適用対象金額のうち、直接および間接に所有する当該特定外国子会社等の株式等に対応する金額である(措法66の6①)。つまり持分に対応する金額となる。
2 基準所得金額の計算 基準所得金額は、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、原則として、法人税法および租税特別措置法における所得計算で計算した金額に、法人税及び特定の受取配当等の調整を加えた金額であり、課税所得金額に近似する金額となる。なお、「特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額」とは、特に定義されていない。
この金額の計算にあたっては、原則的方法として本邦法令に基づき計算する方法(措令39の15①)および例外的方法として、本店所在地国の法令(現地法令)に基づき計算する方法(措令39の15②)が選択適用として認められている。
(1)本邦法令:原則的計算方法 基準所得金額を、本邦法令、つまり日本の法人税法および租税特別措置法に準拠して計算する場合は、次の順序で行うこととなる(措令39の15①)(図2参照)。
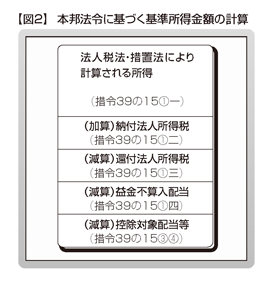
i)本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額を計算
ii)当該事業年度において納付する法人所得税の額を加算
iii)当該事業年度において還付を受ける法人所得税の額を減算
iv)他の特定外国子会社等からの受取配当を減算
① 適用される本邦法令 上記i)にいう「本邦法令」に基づく計算とは、基本的に内国法人の各事業年度の所得計算と同様に行われる。なお、この計算時に適用されない法人税法の規定は次のとおり。
◆第23条;受取配当金の益金不算入
◆第23条の2;外国子会社から受ける配当等の益金不算入
◆第25条の2;受贈益の益金不算入
◆第26条第1項から第5項;還付金等の益金不算入
◆第33条第5項;資産の評価損の損金不算入等
◆第37条第2項;寄附金の損金不算入
◆第38条;法人税等の損金不算入
◆第39条;第2次納税義務に係る納付税額の損金不算入
◆第40条;法人税額から控除する所得税額の損金算入
◆第41条;法人税額から控除する外国税額の損金不算入
◆第55条第3項;延滞税等の損金不算入
◆第57条;欠損金の繰越し
◆第58条;災害損失金の繰越し
◆第59条;債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入
◆第61条の2第16項;有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入
◆第61条の11;連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益
◆第61条の12;連結納税の加入に伴う資産の時価評価損益
◆第61条の13;分割等前事業年度等における連結法人間取引損益の調整
◆第62条の5第3項から第6項;現物分配による資産の譲渡
◆第62条の7;特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入(適格現物出資に係る部分)
また、本邦法令に含まれる租税特別措置法の規定は次のとおりであるが、特に第61条の4および第66条の4第3項に注意する必要がある。
◆第43条;特定設備等の特別償却
◆第45条の2;医療用機器等の特別償却
◆第52条の2;特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例
◆第57条の5;保険会社等の異常危険準備金
◆第57条の6;原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金
◆第57条の8;特別修繕準備金
◆第57条の10;中小企業等の貸倒引当金の特例
◆第61条の4;交際費等の損金不算入
◆第65条の7から第65条の9まで;特定の資産(船舶)の買替えの場合の課税の特例
◆第66条の4第3項;国外関連者に対する寄付金の損金不算入
◆第67条の12、第67条の13;組合事業に係る損失がある場合の課税の特例
② 適用要件の取扱いおよび添付書類 これらの規定の適用にあたっては、申告要件又は、事前の届出を要する制度となっている場合が多い。内国法人ではなく、外国の法人である特定外国子会社等に対して、どのようにしてこれらの要件を適用するかという点については、概ね以下のように取り扱われる(措通66の6-10)。
◆青色申告書を提出する法人であることを要件として適用することとされている規定については、特定外国子会社等がその要件を満たすものとして適用する。
◆減価償却費、評価損、圧縮記帳、引当金の繰入額、準備金の積立額等の損金算入又は長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る延払基準による収益および費用の計上等確定した決算における経理を要件として適用することとされている規定については、特定外国子会社等がその決算において行った経理のほか、タックスヘイブン対策税制の合算課税の適用にあたって修正した損益計算書等において行った経理をもって要件を満たすものとして取り扱う。
◆タックスヘイブン対策税制の適用にあたり採用したたな卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法、有価証券の1単位あたりの帳簿価額の算出方法等は、内国法人が最初に提出する確定申告書に添付する特定外国子会社等に係る損益計算書等に付記し、特段の事情がない限り継続適用する。
また、法人税法第33条の資産の評価損の損金不算入等および第42条から第53条までの圧縮記帳および各種引当金の規定に準じて計算した場合並びに租税特別措置法の規定に準じて計算した場合に、特定外国子会社等の各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、その金額の損金算入に関する明細書を合算課税に係る内国法人の各事業年度の確定申告書に添付しなければならない。添付がない場合には、特定外国子会社等の所得(つまり合算課税の対象となる金額)の計算にあたり損金算入できないことになる(措令39の15⑦)。なお、明細書は、具体的には、別表9(4)、別表11(1)から(2)、別表12(11)、別表12(12)、別表13(1)から別表13(3)、別表13(5)、別表14(3)および別表16(1)から別表16(5)に準じた書式が用いられることとなるが、当然そのものでも問題ない(措規22の11)。
③ 移転価格税制との関係 特定外国子会社等と内国法人との間で行われた取引について移転価格税制(措法66の4)の適用がある場合、つまり内国法人の所得が増加する場合には、その取引が独立企業間価格で行われたものとみなして特定外国子会社の基準所得金額を計算することとなる。これは、移転価格税制とタックスヘイブン対策税制の2重適用による二重課税を排除するためであり、理論上、取引の相手方である特定外国子会社等の所得が減少することとなる(措令39の15①一括弧書き)。
④ 他の子会社から受ける配当の除外 特定外国子会社等の基準所得金額の計算にあたり、特定外国子会社等が、一定の要件を満たす子会社から受ける配当を控除することができる(措令39の15①四)。これは、平成21年度改正により「外国子会社からの配当等の益金不算入」が導入されたことに伴い設けられた措置である。合算課税の対象となる特定外国子会社等は、合算課税を受けることにより実質的に日本の法人税が課せられることになり、それは特定外国子会社等が内国法人と同様の位置づけにおかれることを意味する。そこで、内国法人に対する取り扱いと整合させることが、この取り扱いの趣旨と考えられる。
この取扱いの対象となる子会社は次の2つの要件を満たした子会社に限定されるが、これは法人税法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)における外国子会社の範囲と基本的には同様のものとなっている(図3参照)。
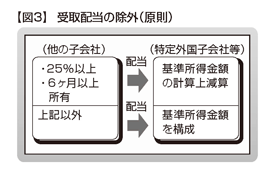 ◆発行済株式等のうちに特定外国子会社等が保有しているその株式等の数もしくは金額の占める割合または発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに特定外国子会社等が保有しているその株式等の数もしくは金額の占める割合のいずれかが25%以上であること
◆発行済株式等のうちに特定外国子会社等が保有しているその株式等の数もしくは金額の占める割合または発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに特定外国子会社等が保有しているその株式等の数もしくは金額の占める割合のいずれかが25%以上であること
◆配当等の額の支払い義務が確定する日(みなし配当である場合にはその発生日の前日)以前6ヶ月以上(6ヶ月以内の新設法人の場合には、設立の日以後確定日までの期間)25%以上の保有が継続していること
なお、特定目的会社(租税特別措置法第67条の14)、投資法人(租税特別措置法第67条の15)、特定目的信託に係る受託法人(租税特別措置法第68条の3の2)、特定投資信託に係る受託法人(租税特別措置法第68条の3の3)は除かれている。
また、こうした配当を控除する場合には、この金額の計算に関する明細書を確定申告書に添付する必要があり、添付されていないことについてやむを得ない事情があると税務署長が認める場合には、別途提出することにより認められることとなる(措令39の15⑧)。
④ 控除対象配当等の調整 特定外国子会社等に配当等を行うその子会社(孫会社に該当)が、上記③の要件を見たさない法人であり(たとえば持分が25%未満)、同時に「特定外国子会社等」に該当する場合には、2段階の特定外国子会社等で2度の合算課税を受けることも考えられる。こうした二重課税を排除するため、③の措置の対象とならない特定外国子会社等からの配当等についての二重課税排除については、別途の措置が設けられているところである(措令39の15⑧)。
脚注
1 平成21年度改正以前は、特定外国子会社等の合算対象となる所得の計算にあたって支払配当の控除が設けられていたことに伴い「未処分所得の金額」という概念が設けられていたが、外国子会社からの配当等の益金不算入の創設に伴って支払配当を控除することができなくなったことから、「未処分所得」および「留保」という用語をはずし、現在は、「基準所得金額」、「適用対象金額」、「課税対象金額」という概念により制度が構成されている。
記事に関連するお問い合わせ先 記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
今週のマエストロ&テーマ
タックスヘイブン対策税制─合算所得金額の計算①
統括会社に係る例外規定
#52 品川克己
日本公認会計士協会租税調査会専門委員(国際租税専門部会)
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(マネージング・ディレクター)
略歴 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究。97年より00年までOECD租税委員会に主任行政官として出向(在フランス)し、「OECD移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財務省を辞職し現職。
次回のテーマ
#53 経営戦略に応える企業再編成税制 税理士 朝長英樹 経営戦略の1つとして組織再編成税制を活用できる方法を、同税制等の創設を主導した筆者が事例形式で解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
マエストロの解説 海外に有する子会社が特定外国子会社等に該当し、かつ、適用除外基準を満たしていない場合には、その子会社の所得は親会社たる日本法人の所得とみなして課税されることとなる。つまり、親会社の所得に合算して、日本で課税されることとなる。この場合、合算される所得は、外国法人たる特定外国子会社等の所得であり、必ずしも日本の法令に基づいて表示されているわけではない。こうした外国の法人の所得金額を、日本での課税にあたり、どのように計算するのかが次のテーマである。
1 概 要 タックスヘイブン対策税制による合算所得は、特定外国子会社等の課税所得を基礎として、「基準所得金額」、「適用対象金額」、「課税対象金額」の順に計算される(措法66の6①)(脚注1)。
(図1参照)。
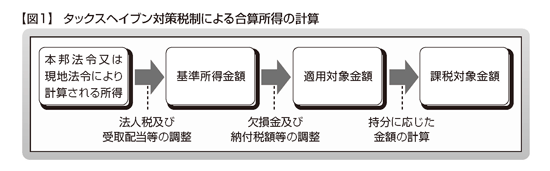
この「基準所得金額」は、原則的には、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額であり、一般的には、会計上の税引前利益を意味するところであるが、これを①法人税法および租税特別措置法における所得計算に準じた方法で計算する方法又は②現地法令により計算された課税所得にいくつかの調整を加える方法で計算し、最終的に我が国の法令により計算した課税所得金額に近いものとなる(措法66の6②二)。
次に「適用対象金額」は、基準所得金額に前7年の欠損の金額および当該年度の税額による調整を加えた金額となる(措法66の6②二)。
最後に「課税対象金額」は、適用対象金額のうち、直接および間接に所有する当該特定外国子会社等の株式等に対応する金額である(措法66の6①)。つまり持分に対応する金額となる。
2 基準所得金額の計算 基準所得金額は、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額について、原則として、法人税法および租税特別措置法における所得計算で計算した金額に、法人税及び特定の受取配当等の調整を加えた金額であり、課税所得金額に近似する金額となる。なお、「特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額」とは、特に定義されていない。
この金額の計算にあたっては、原則的方法として本邦法令に基づき計算する方法(措令39の15①)および例外的方法として、本店所在地国の法令(現地法令)に基づき計算する方法(措令39の15②)が選択適用として認められている。
(1)本邦法令:原則的計算方法 基準所得金額を、本邦法令、つまり日本の法人税法および租税特別措置法に準拠して計算する場合は、次の順序で行うこととなる(措令39の15①)(図2参照)。
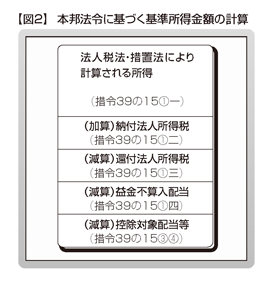
i)本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額を計算
ii)当該事業年度において納付する法人所得税の額を加算
iii)当該事業年度において還付を受ける法人所得税の額を減算
iv)他の特定外国子会社等からの受取配当を減算
① 適用される本邦法令 上記i)にいう「本邦法令」に基づく計算とは、基本的に内国法人の各事業年度の所得計算と同様に行われる。なお、この計算時に適用されない法人税法の規定は次のとおり。
◆第23条;受取配当金の益金不算入
◆第23条の2;外国子会社から受ける配当等の益金不算入
◆第25条の2;受贈益の益金不算入
◆第26条第1項から第5項;還付金等の益金不算入
◆第33条第5項;資産の評価損の損金不算入等
◆第37条第2項;寄附金の損金不算入
◆第38条;法人税等の損金不算入
◆第39条;第2次納税義務に係る納付税額の損金不算入
◆第40条;法人税額から控除する所得税額の損金算入
◆第41条;法人税額から控除する外国税額の損金不算入
◆第55条第3項;延滞税等の損金不算入
◆第57条;欠損金の繰越し
◆第58条;災害損失金の繰越し
◆第59条;債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入
◆第61条の2第16項;有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入
◆第61条の11;連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益
◆第61条の12;連結納税の加入に伴う資産の時価評価損益
◆第61条の13;分割等前事業年度等における連結法人間取引損益の調整
◆第62条の5第3項から第6項;現物分配による資産の譲渡
◆第62条の7;特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入(適格現物出資に係る部分)
また、本邦法令に含まれる租税特別措置法の規定は次のとおりであるが、特に第61条の4および第66条の4第3項に注意する必要がある。
◆第43条;特定設備等の特別償却
◆第45条の2;医療用機器等の特別償却
◆第52条の2;特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例
◆第57条の5;保険会社等の異常危険準備金
◆第57条の6;原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金
◆第57条の8;特別修繕準備金
◆第57条の10;中小企業等の貸倒引当金の特例
◆第61条の4;交際費等の損金不算入
◆第65条の7から第65条の9まで;特定の資産(船舶)の買替えの場合の課税の特例
◆第66条の4第3項;国外関連者に対する寄付金の損金不算入
◆第67条の12、第67条の13;組合事業に係る損失がある場合の課税の特例
② 適用要件の取扱いおよび添付書類 これらの規定の適用にあたっては、申告要件又は、事前の届出を要する制度となっている場合が多い。内国法人ではなく、外国の法人である特定外国子会社等に対して、どのようにしてこれらの要件を適用するかという点については、概ね以下のように取り扱われる(措通66の6-10)。
◆青色申告書を提出する法人であることを要件として適用することとされている規定については、特定外国子会社等がその要件を満たすものとして適用する。
◆減価償却費、評価損、圧縮記帳、引当金の繰入額、準備金の積立額等の損金算入又は長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る延払基準による収益および費用の計上等確定した決算における経理を要件として適用することとされている規定については、特定外国子会社等がその決算において行った経理のほか、タックスヘイブン対策税制の合算課税の適用にあたって修正した損益計算書等において行った経理をもって要件を満たすものとして取り扱う。
◆タックスヘイブン対策税制の適用にあたり採用したたな卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法、有価証券の1単位あたりの帳簿価額の算出方法等は、内国法人が最初に提出する確定申告書に添付する特定外国子会社等に係る損益計算書等に付記し、特段の事情がない限り継続適用する。
また、法人税法第33条の資産の評価損の損金不算入等および第42条から第53条までの圧縮記帳および各種引当金の規定に準じて計算した場合並びに租税特別措置法の規定に準じて計算した場合に、特定外国子会社等の各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、その金額の損金算入に関する明細書を合算課税に係る内国法人の各事業年度の確定申告書に添付しなければならない。添付がない場合には、特定外国子会社等の所得(つまり合算課税の対象となる金額)の計算にあたり損金算入できないことになる(措令39の15⑦)。なお、明細書は、具体的には、別表9(4)、別表11(1)から(2)、別表12(11)、別表12(12)、別表13(1)から別表13(3)、別表13(5)、別表14(3)および別表16(1)から別表16(5)に準じた書式が用いられることとなるが、当然そのものでも問題ない(措規22の11)。
③ 移転価格税制との関係 特定外国子会社等と内国法人との間で行われた取引について移転価格税制(措法66の4)の適用がある場合、つまり内国法人の所得が増加する場合には、その取引が独立企業間価格で行われたものとみなして特定外国子会社の基準所得金額を計算することとなる。これは、移転価格税制とタックスヘイブン対策税制の2重適用による二重課税を排除するためであり、理論上、取引の相手方である特定外国子会社等の所得が減少することとなる(措令39の15①一括弧書き)。
④ 他の子会社から受ける配当の除外 特定外国子会社等の基準所得金額の計算にあたり、特定外国子会社等が、一定の要件を満たす子会社から受ける配当を控除することができる(措令39の15①四)。これは、平成21年度改正により「外国子会社からの配当等の益金不算入」が導入されたことに伴い設けられた措置である。合算課税の対象となる特定外国子会社等は、合算課税を受けることにより実質的に日本の法人税が課せられることになり、それは特定外国子会社等が内国法人と同様の位置づけにおかれることを意味する。そこで、内国法人に対する取り扱いと整合させることが、この取り扱いの趣旨と考えられる。
この取扱いの対象となる子会社は次の2つの要件を満たした子会社に限定されるが、これは法人税法第23条の2(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)における外国子会社の範囲と基本的には同様のものとなっている(図3参照)。
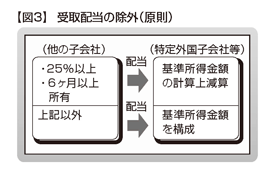 ◆発行済株式等のうちに特定外国子会社等が保有しているその株式等の数もしくは金額の占める割合または発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに特定外国子会社等が保有しているその株式等の数もしくは金額の占める割合のいずれかが25%以上であること
◆発行済株式等のうちに特定外国子会社等が保有しているその株式等の数もしくは金額の占める割合または発行済株式等のうちの議決権のある株式等の数若しくは金額のうちに特定外国子会社等が保有しているその株式等の数もしくは金額の占める割合のいずれかが25%以上であること◆配当等の額の支払い義務が確定する日(みなし配当である場合にはその発生日の前日)以前6ヶ月以上(6ヶ月以内の新設法人の場合には、設立の日以後確定日までの期間)25%以上の保有が継続していること
なお、特定目的会社(租税特別措置法第67条の14)、投資法人(租税特別措置法第67条の15)、特定目的信託に係る受託法人(租税特別措置法第68条の3の2)、特定投資信託に係る受託法人(租税特別措置法第68条の3の3)は除かれている。
また、こうした配当を控除する場合には、この金額の計算に関する明細書を確定申告書に添付する必要があり、添付されていないことについてやむを得ない事情があると税務署長が認める場合には、別途提出することにより認められることとなる(措令39の15⑧)。
④ 控除対象配当等の調整 特定外国子会社等に配当等を行うその子会社(孫会社に該当)が、上記③の要件を見たさない法人であり(たとえば持分が25%未満)、同時に「特定外国子会社等」に該当する場合には、2段階の特定外国子会社等で2度の合算課税を受けることも考えられる。こうした二重課税を排除するため、③の措置の対象とならない特定外国子会社等からの配当等についての二重課税排除については、別途の措置が設けられているところである(措令39の15⑧)。
脚注
1 平成21年度改正以前は、特定外国子会社等の合算対象となる所得の計算にあたって支払配当の控除が設けられていたことに伴い「未処分所得の金額」という概念が設けられていたが、外国子会社からの配当等の益金不算入の創設に伴って支払配当を控除することができなくなったことから、「未処分所得」および「留保」という用語をはずし、現在は、「基準所得金額」、「適用対象金額」、「課税対象金額」という概念により制度が構成されている。
記事に関連するお問い合わせ先 記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























