解説記事2012年10月15日 【実務解説】 医療法人のM&Aストラクチャリングの法務(2012年10月15日号・№471)
実務解説
医療法人のM&Aストラクチャリングの法務
長島・大野・常松法律事務所 弁護士 鈴木謙輔/弁護士 粂内将人
近年、医療法人の相続・承継対策として、また、経営再建・事業再生の手段として、医療法人のM&Aが注目される。M&Aが活用される場面は様々であるところ、医療法人を巡る厳しい経営環境が続く中、医療法人にとってM&Aは身近な選択肢となりつつある。その一方で、医療法人は、通常の事業会社とは異なり、非営利性が求められるなど医療法の下で厳格な規制に服していることから、医療法人のM&Aにあたっては、通常の事業会社のM&Aとは異なる特殊な制約や考慮要素にも留意する必要がある。本稿では、法務の観点から、医療法人のM&Aの手法や最近の動向を紹介し、M&Aのストラクチャリングを行うに際して注意すべきポイントを解説する。なお、本稿の内容はいずれも筆者らの個人的な見解であり、筆者らが現在所属し、又は過去に所属した団体・組織の見解を示すものではないことにご留意いただきたい。
Ⅰ.医療法人のM&Aの手法
医療法人は、医療法に基づき社団又は財団として設立された法人であり、医療法上の様々な厳格な規制が課されている。社団医療法人については、いわゆる「持分の定めのある」ものと「持分の定めのない」ものがあるが、前者については平成19年4月1日以降は新たに設立することは認められていない。
医療法人のM&Aの手法も医療法による制約を受けるところ、典型的な手法として、合併、事業譲渡及び持分譲渡が挙げられる。会社法において株式会社に認められている会社分割や株式移転、株式交換については、医療法人には認められていない。また、これらの手法と合わせて、又は単独で、医療法人の役員(理事及び監事)や社員(財団法人の場合は評議員)の交代を通じて、事実上、医療法人のコントロールを掌握することが考えられる。以下それぞれの手法について概説する。
1.合 併 合併は、医療法において明文で定められている唯一の組織再編手段である。合併の手続や効果については医療法上に規定されているほか、平成24年5月31日に発出された通知により明確化が図られている(「医療法人の合併について」医政指発0531第2号)。
「合併」とは、法定の手続によって行われる医療法人相互間の契約であり、当事者たる医療法人の一部(吸収合併)又は全部(新設合併)が解散し、その財産が清算手続を経ることなく、包括的に存続する医療法人(吸収合併)又は新設の医療法人(新設合併)に移転する効果を伴うもの(同通知第1)をいう(図1参照)。
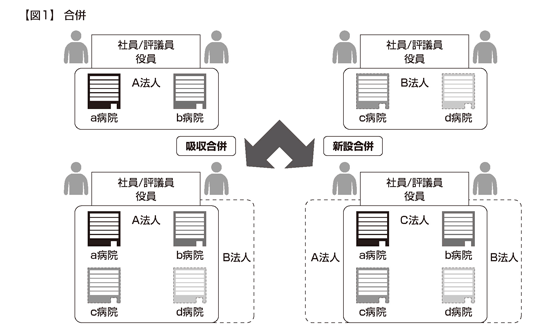
医療法人の合併については、医療法により厳格な手続・規制が定められている。まず、合併は、社団医療法人同士又は財団医療法人同士でのみ行うことが認められており、社団医療法人と財団医療法人が合併を行うことはできない。また、手続面では、合併当事者となる医療法人における機関決定(脚注1)が必要となるほか、都道府県知事の認可がなければ効力を生じないこととされており、また、2カ月以上の債権者保護手続を実施することが求められる(医療法57条~59条)。なお、都道府県知事はこの認可の可否に関してあらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴かなければならないとされているところ、医療法人合併手続の迅速化の観点から、前述の本年5月31日の通知において、都道府県医療審議会は、部会を置きその決議をもって審議会の決議とすることができることも踏まえ、必要に応じ、部会の開催を随時行う等、実態に応じた適切な運営を図ることが要請されている(同通知第2、3)。
合併の効果として、合併後存続する医療法人(吸収合併)又は合併によって設立した医療法人(新設合併)は、合併によって消滅した医療法人の一切の権利義務(病院開設の許可などの行政庁の認可に基づく権利義務も含む)を自動的かつ包括的に承継する。したがって、権利義務の移転手続が容易である一方で、隠れた負債も含め、全ての権利義務を承継することになり、デューディリジェンス等による承継資産・負債の事前検証が重要となる。なお、本年5月31日に医療法施行規則の改正が行われており、合併後に「持分の定めのある」医療法人となることが認められるのは、「持分の定めのある」医療法人同士による吸収合併の場合に限られ、「持分の定めのある」医療法人同士による合併の場合であっても、新設合併の場合には合併後は「持分の定めのない」医療法人となる(表1参照)。
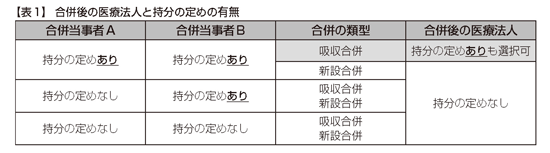
2.事業譲渡 事業譲渡は、M&Aの対象となる病院に関連する施設、資産、契約等を一括して譲渡することにより行われる(図2参照)。会社法と異なり、医療法では、事業譲渡に関する明文の規定は設けられていない。事業譲渡の当事者となる医療法人に法律上の制約はなく、医療法人の形態を問わず利用することができる。また、事業譲渡の対象となる資産等の範囲について柔軟に定めることが可能である。
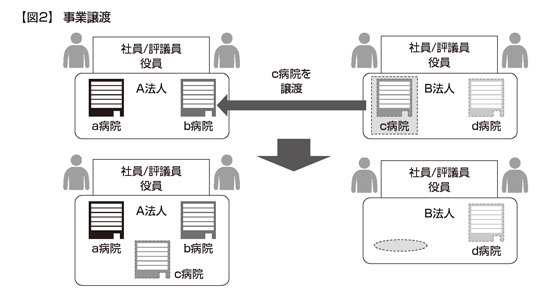 他方で、手続面においては、医療法上、資産等の譲渡に必要となる手続や、譲渡による対象病院の開設主体の変更手続を経ることが必要となる。すなわち、譲渡当事者となる医療法人における機関決定(脚注2)が必要となるほか、合併と異なり病院開設の許可の承継手続が設けられていないため、病院を譲り受ける医療法人において、新たに対象病院の開設許可申請を行う必要がある。したがって、事前準備を含め許可を得るまでに期間を要することに加え、病床数等につき、従前と同様の許可が得られるか留意する必要がある。
他方で、手続面においては、医療法上、資産等の譲渡に必要となる手続や、譲渡による対象病院の開設主体の変更手続を経ることが必要となる。すなわち、譲渡当事者となる医療法人における機関決定(脚注2)が必要となるほか、合併と異なり病院開設の許可の承継手続が設けられていないため、病院を譲り受ける医療法人において、新たに対象病院の開設許可申請を行う必要がある。したがって、事前準備を含め許可を得るまでに期間を要することに加え、病床数等につき、従前と同様の許可が得られるか留意する必要がある。
事業譲渡により、譲渡対象である財産や権利義務が、譲渡法人から譲受法人にそれぞれ譲渡されることとなる。したがって、個々の財産や権利義務につき、個別に譲渡手続を経ることが必要となる。例えば、取引先との契約や従業員との雇用契約等の契約を譲渡するためには、基本的にはそれぞれの契約の相手方当事者の同意を得る必要があると考えられ、同意が得られない場合には契約をそのまま譲渡することができない可能性がある。他方で、事業譲渡の対象となる財産や権利義務の範囲を柔軟に選択できることから、譲渡範囲を適切に設定することにより、隠れた負債を承継するリスクを低減することが可能となる。
3.持分譲渡 「持分の定めのある」社団医療法人については、持分譲渡によりM&Aを行うことが可能である(図3参照)。合併や事業譲渡と比べて手続上の負担が軽いことから、実務上M&Aの手法としてよく用いられる。ただし、対象医療法人が「持分の定めのない」社団医療法人や、財団医療法人である場合は、持分譲渡を行うことはできない。他方で、合併や事業譲渡と異なり、買収者側が医療法人を有している必要はないため、傘下に医療法人を有さない買収者が持分譲渡を受けることにより新たに医療法人を傘下におさめることが可能となる。
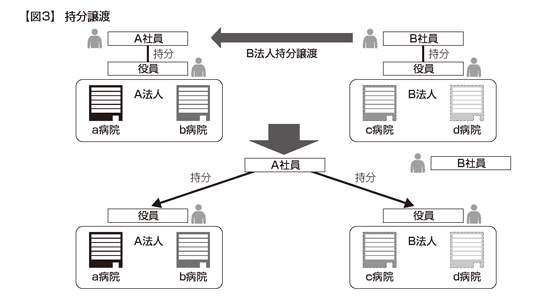
もっとも、医療法上、医療法人の運営に関与する機関はあくまで役員及び社員(財団医療法人の場合は評議員)であり、持分保有者(出資者)とは区別されていることから、持分を譲り受けた者が実際に対象医療法人のコントロールを掌握するためには、後述の役員等の変更を別途行う必要があることには注意を要する。
持分譲渡により、対象医療法人自体は従前どおり存続し、そのまま譲受人のコントロール下におかれることとなる。対象医療法人が当事者となっている法律関係に変動がないため、対象医療法人が保有する許認可や資産、権利義務について移転手続を経る必要はなく、持分譲渡後も、隠れた負債を含め対象医療法人の権利義務はそのまま存続することになる。
4.役員等の変更 医療法上、医療法人の運営に関与する機関として、役員(理事及び監事)及び社員(社団医療法人の場合)・評議員(財団医療法人の場合)が規定されている。すなわち、医療法人は、原則として、役員として理事3人以上及び監事1人以上を置くものとされ、理事により構成される理事会が医療法人の業務執行の意思決定を行い、監事が医療法人の業務・財産状況の監査等を行うこととされている(医療法46条の2、46条の4)。また、医療法人に関わる重要事項については、社員総会(社団医療法人の場合)又は評議員会(財団医療法人の場合)に諮られる(同法48条の3~49条の3)。
したがって、医療法人の役員及び社員・評議員のうち、これらによる意思決定に必要な人数の協力者がいれば、その医療法人のコントロールを事実上掌握することが可能となる。そのために必要な人数は医療法人の定款や寄附行為の内容によって異なりうる。医療法上は理事会、社員総会、評議員会のいずれも過半数決議が原則とされているが、定款・寄附行為により決議要件が加重されている場合があるため注意を要する。
この手法は、当事者となる医療法人の形態を問わず利用することができる。また、持分譲渡と同様、買収者側が医療法人を有している必要はないため、傘下に医療法人を有さない買収者もこの手法をとることができる。
役員等の変更を行うためには、医療法人において役員等の選任に必要な機関決定を行うほか、役員の変更については都道府県知事に届け出るものとされており(医療法施行令5条の13)、理事長の変更については登記手続が必要となる(組合等登記令2条)。
役員等の変更を行った場合、対象医療法人自体は従前どおり存続し、対象医療法人が当事者となっている法律関係に変動がないため、対象医療法人が保有する許認可や資産、権利義務について移転手続を経る必要はなく、役員等の変更後も、隠れた負債を含め対象医療法人の権利義務はそのまま存続する。
Ⅱ.ストラクチャリングにあたっての留意点
上記Ⅰで述べた各手法のいずれを選択するかは、最終的には、当事者となる医療法人の状況やM&Aで企図されている目的等の個別の案件ごとの具体的な事情に基づいて判断されることとなる。もちろん、合併や持分譲渡の場合は、そもそも当事者となりうる医療法人の種類が限定されているため、医療法人の種類によっては選択肢となりえない場合がある。また、一般的に、合併や事業譲渡については、手続面での負担が重く、相当の時間を要することとなることから、迅速かつ簡便に実行できる持分譲渡や役員等の変更が好まれる傾向にある。他方で、持分譲渡や役員等の変更については、買収者側が従前より医療法人を有している場合には、M&A後に二つの医療法人を傘下に抱えることとなり、役員等の配置や運営コスト等の負担が二重に生じる可能性がある。また、事業譲渡の方法による場合のみ、隠れた負債を遮断することが可能となる。
その他、医療法人のM&Aのストラクチャリングにあたって典型的に問題となるポイントとして、M&A対価の設定と役員等の配置・兼務が挙げられる。以下これらの点について解説する。ただし、ストラクチャリングにあたって考慮すべき要素は決してこれらに尽きるものではない。例えば、当事者が特定医療法人(脚注3)や社会医療法人(脚注4)である場合における買収後のそのステータスの維持の可否、個々の医療法人に関わる利害関係者(行政庁のみならず、取引金融機関や地元の医師会なども考えられる)の理解や協力が得られやすい形態、対象医療法人にいわゆるメディカル・サービス法人(MS法人)がある場合における買収後のMS法人との取引やMS法人自体の取扱い、売主側の理事長や他の重要人物から買収後における継続的な協力を確保するための方策なども問題となりうる。
1.M&A対価の設定 医療法人のM&Aにあたっては、まず、金銭対価の支払いの要否を含め、対価として誰に対してどのような金額を支払うこととするかを検討する必要がある。M&Aに伴って売主側の理事長個人に対して幾ばくかの金銭を支払うこととするのであれば、そのような支払いを前提としたストラクチャーを採用する必要がある。また、対価の支払主体が誰になるかによって、支払原資について資金調達の要否や方法が異なってくる。
上記Ⅰで述べた各手法のうち、金銭対価の支払いを伴うものは、事業譲渡と持分譲渡である。事業譲渡の場合は、譲受法人から譲渡法人に譲渡対価が支払われるため、譲受法人において支払原資を確保する必要がある。医療法人レベルで譲渡対価の支払いが行われるため、売主側の理事長個人への金銭の支払いはなされない。他方、持分譲渡の場合は、医療法人レベルではなく、持分の譲受人から譲渡人に譲渡対価が支払われるため、譲受人において支払原資を確保する必要がある。持分の譲渡当事者が個人である場合には、譲渡人たる個人に金銭の支払いがなされる一方、譲受人たる個人において支払原資を用意することとなる。
実務的には、M&Aに伴って売主側の個人に対して一定の金銭の支払いが行われるようなストラクチャーをとることが多く、その一つの方法として、役員の退職金の支払いが行われることがある。例えば、持分譲渡や役員等の変更を行う場合に、退職する売主側の理事長に対して、退職金の支払いを行うことが考えられる。この場合、退職金の支払主体はM&Aの対象医療法人となるため、対象医療法人において退職金の支払原資を確保する必要がある。
譲渡対価であれ退職金であれ、これらの支払金額については、医療法人の非営利性の観点からも、適正な金額であることが求められ、金額水準を決定するにあたっては、その妥当性につき税理士、会計士等と慎重に検証する必要がある。
2.役員等の配置・兼務 前述のとおり、一般的に、実施する際の手続面での負担に鑑みて、M&Aの手法として持分譲渡や役員等の変更が好まれる傾向があるが、これらの方法による場合、終局的には、対象医療法人のコントロールを掌握するために必要な人数の協力者を確保し、対象医療法人の役員等に就任してもらうことが必要となる。そのような人数の協力者を集めることは必ずしも容易ではない場合が多いことから、実務的な対応策として、買収者側の医療法人や関係会社の役職員に、対象医療法人の役員等に就任してもらうことが考えられる。従来の医療法人や関係会社での役職に就いたまま対象医療法人の役員等にも就任してもらう場合には、対象医療法人の役員等を兼務することとなる。このような医療法人の役員等の配置や兼務にあたっては様々な留意点がある。
まず、医療法人の役員等については、法令上、一定の資格要件が設けられている場合がある。例えば、医療法人の理事長は、原則として医師又は歯科医師であることが必要とされている(医療法46条の3)。また、医療法人の監事は、同じ医療法人の理事や職員を兼ねることはできない(同法48条)。さらには、財団医療法人における評議員については、同じ医療法人の役員を兼ねることができないほか、医師、看護師等の医療従事者などの資格要件が法定されている(同法49条の4)。このように、役員等の配置にあたっては、それぞれの役職の資格要件を満たしていることを確認することが重要となる。特定医療法人や社会医療法人についてはいわゆる同族要件が設けられている(租税特別措置法施行令39条の25、医療法42条の2)ことから、これらのステータスを維持するためには、同族要件に抵触しないよう、役員等に占める親族等の割合にも注意する必要がある。
医療法上、医療法人の役員等が、他の法人の役員等を兼務することを禁止する明文はない。しかし、だからといって兼務が自由に認められるものではなく、医療法人の非営利性等の観点から一定の制約に服すると解されている。
まず、医療法人の理事長が他の医療法人の理事長を兼ねることは、特別の理由・必然性がなければ認められないとの見解がある(脚注5)ことから、複数の医療法人の理事長を兼務する場合は、その可否につき慎重に検討する必要がある。
また、医療法人の役員の兼務に関しては、平成24年3月30日に行われた通知改正の内容に注意する必要がある。この通知改正において、医療法人の役員は、原則として医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務することが認められない一方で、例外的に兼務可能な範囲が明確化されている(「医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務について」(医政総発0330第4号、医政指発0330第4号)、「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」(平成5年総第5号・指第9号))。すなわち、医療法人の役員(監事を除く)の過半数を超えず、かつ、医療機関の非営利性に影響を与えない場合には、例外的に、一定の要件の下で兼務が認められている。具体的な要件については通知で詳細に定められており、例えば、営利法人等から物品の購入・賃貸又は役務提供を受ける商取引がある場合には、①医療法人の代表者の兼務でないこと、②営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること、③契約の内容が妥当であると認められることのいずれも満たすのであれば、兼務が認められる。営利法人等との取引が、医療法人が必要とする土地又は建物を賃借するものである場合には、上記のうち②及び③の要件を満たせば兼務が認められる。したがって、医療法人の役員を兼務してもらうことを検討するにあたっては、通知に定められている要件を充足するよう、注意する必要がある。
鈴木謙輔 すずき けんすけ
長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士。2000年弁護士登録、06年スタンフォード大学ロースクール(LL.M.)修了、07年~09年金融庁総務企画局市場課専門官。「大口株主による株式売却とインサイダー取引規制」(本誌444号16頁)など。
粂内将人 くめうち まさと
長島・大野・常松法律事務所 弁護士。2010年弁護士登録。不動産取引・流動化、M&A、薬事法、倒産法、知的財産法などを担当。
脚注
1 社団医療法人が他の社団医療法人と合併するためには総社員の同意が必要であり、財団医療法人が他の財団医療法人と合併するためには寄附行為に合併することができる旨の定めがなければならず、かつ、原則として理事の3分の2以上の同意が必要とされている。
2 個々の医療法人における定款(社団医療法人の場合)や寄附行為(財団医療法人の場合)の定めにもよるが、基本的には、社員総会(社団医療法人の場合)又は評議員会(財団医療法人の場合)の決議が必要になると考えられる。
3 特定医療法人は、医療法人のうち、租税特別措置法の規定により国税庁長官の承認を受けたものをいい、一定の法人税軽減措置の対象となる(同法67条の2)。
4 社会医療法人は、医療法人のうち、医療法の規定により都道府県知事の認定を受けたものをいい、一定の収益業務を行うことが認められている(同法42条の2)。
5 医療法制研究会編「病院・医院のための医療法人Q&A」(中央法規出版、平成3年)1531頁
医療法人のM&Aストラクチャリングの法務
長島・大野・常松法律事務所 弁護士 鈴木謙輔/弁護士 粂内将人
近年、医療法人の相続・承継対策として、また、経営再建・事業再生の手段として、医療法人のM&Aが注目される。M&Aが活用される場面は様々であるところ、医療法人を巡る厳しい経営環境が続く中、医療法人にとってM&Aは身近な選択肢となりつつある。その一方で、医療法人は、通常の事業会社とは異なり、非営利性が求められるなど医療法の下で厳格な規制に服していることから、医療法人のM&Aにあたっては、通常の事業会社のM&Aとは異なる特殊な制約や考慮要素にも留意する必要がある。本稿では、法務の観点から、医療法人のM&Aの手法や最近の動向を紹介し、M&Aのストラクチャリングを行うに際して注意すべきポイントを解説する。なお、本稿の内容はいずれも筆者らの個人的な見解であり、筆者らが現在所属し、又は過去に所属した団体・組織の見解を示すものではないことにご留意いただきたい。
Ⅰ.医療法人のM&Aの手法
医療法人は、医療法に基づき社団又は財団として設立された法人であり、医療法上の様々な厳格な規制が課されている。社団医療法人については、いわゆる「持分の定めのある」ものと「持分の定めのない」ものがあるが、前者については平成19年4月1日以降は新たに設立することは認められていない。
医療法人のM&Aの手法も医療法による制約を受けるところ、典型的な手法として、合併、事業譲渡及び持分譲渡が挙げられる。会社法において株式会社に認められている会社分割や株式移転、株式交換については、医療法人には認められていない。また、これらの手法と合わせて、又は単独で、医療法人の役員(理事及び監事)や社員(財団法人の場合は評議員)の交代を通じて、事実上、医療法人のコントロールを掌握することが考えられる。以下それぞれの手法について概説する。
1.合 併 合併は、医療法において明文で定められている唯一の組織再編手段である。合併の手続や効果については医療法上に規定されているほか、平成24年5月31日に発出された通知により明確化が図られている(「医療法人の合併について」医政指発0531第2号)。
「合併」とは、法定の手続によって行われる医療法人相互間の契約であり、当事者たる医療法人の一部(吸収合併)又は全部(新設合併)が解散し、その財産が清算手続を経ることなく、包括的に存続する医療法人(吸収合併)又は新設の医療法人(新設合併)に移転する効果を伴うもの(同通知第1)をいう(図1参照)。
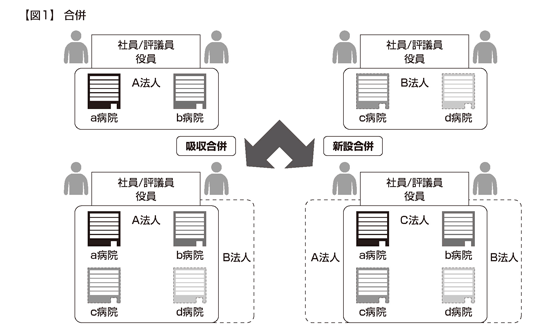
医療法人の合併については、医療法により厳格な手続・規制が定められている。まず、合併は、社団医療法人同士又は財団医療法人同士でのみ行うことが認められており、社団医療法人と財団医療法人が合併を行うことはできない。また、手続面では、合併当事者となる医療法人における機関決定(脚注1)が必要となるほか、都道府県知事の認可がなければ効力を生じないこととされており、また、2カ月以上の債権者保護手続を実施することが求められる(医療法57条~59条)。なお、都道府県知事はこの認可の可否に関してあらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴かなければならないとされているところ、医療法人合併手続の迅速化の観点から、前述の本年5月31日の通知において、都道府県医療審議会は、部会を置きその決議をもって審議会の決議とすることができることも踏まえ、必要に応じ、部会の開催を随時行う等、実態に応じた適切な運営を図ることが要請されている(同通知第2、3)。
合併の効果として、合併後存続する医療法人(吸収合併)又は合併によって設立した医療法人(新設合併)は、合併によって消滅した医療法人の一切の権利義務(病院開設の許可などの行政庁の認可に基づく権利義務も含む)を自動的かつ包括的に承継する。したがって、権利義務の移転手続が容易である一方で、隠れた負債も含め、全ての権利義務を承継することになり、デューディリジェンス等による承継資産・負債の事前検証が重要となる。なお、本年5月31日に医療法施行規則の改正が行われており、合併後に「持分の定めのある」医療法人となることが認められるのは、「持分の定めのある」医療法人同士による吸収合併の場合に限られ、「持分の定めのある」医療法人同士による合併の場合であっても、新設合併の場合には合併後は「持分の定めのない」医療法人となる(表1参照)。
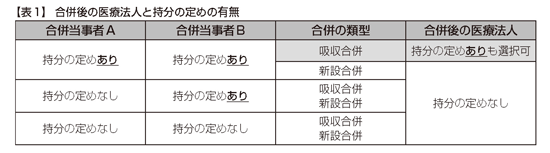
2.事業譲渡 事業譲渡は、M&Aの対象となる病院に関連する施設、資産、契約等を一括して譲渡することにより行われる(図2参照)。会社法と異なり、医療法では、事業譲渡に関する明文の規定は設けられていない。事業譲渡の当事者となる医療法人に法律上の制約はなく、医療法人の形態を問わず利用することができる。また、事業譲渡の対象となる資産等の範囲について柔軟に定めることが可能である。
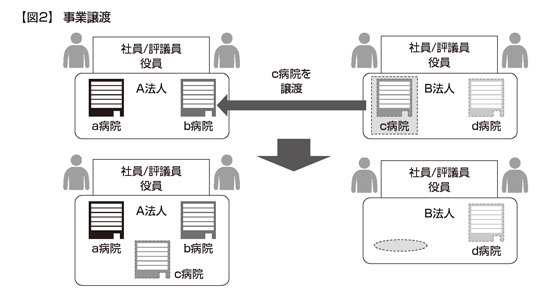 他方で、手続面においては、医療法上、資産等の譲渡に必要となる手続や、譲渡による対象病院の開設主体の変更手続を経ることが必要となる。すなわち、譲渡当事者となる医療法人における機関決定(脚注2)が必要となるほか、合併と異なり病院開設の許可の承継手続が設けられていないため、病院を譲り受ける医療法人において、新たに対象病院の開設許可申請を行う必要がある。したがって、事前準備を含め許可を得るまでに期間を要することに加え、病床数等につき、従前と同様の許可が得られるか留意する必要がある。
他方で、手続面においては、医療法上、資産等の譲渡に必要となる手続や、譲渡による対象病院の開設主体の変更手続を経ることが必要となる。すなわち、譲渡当事者となる医療法人における機関決定(脚注2)が必要となるほか、合併と異なり病院開設の許可の承継手続が設けられていないため、病院を譲り受ける医療法人において、新たに対象病院の開設許可申請を行う必要がある。したがって、事前準備を含め許可を得るまでに期間を要することに加え、病床数等につき、従前と同様の許可が得られるか留意する必要がある。事業譲渡により、譲渡対象である財産や権利義務が、譲渡法人から譲受法人にそれぞれ譲渡されることとなる。したがって、個々の財産や権利義務につき、個別に譲渡手続を経ることが必要となる。例えば、取引先との契約や従業員との雇用契約等の契約を譲渡するためには、基本的にはそれぞれの契約の相手方当事者の同意を得る必要があると考えられ、同意が得られない場合には契約をそのまま譲渡することができない可能性がある。他方で、事業譲渡の対象となる財産や権利義務の範囲を柔軟に選択できることから、譲渡範囲を適切に設定することにより、隠れた負債を承継するリスクを低減することが可能となる。
3.持分譲渡 「持分の定めのある」社団医療法人については、持分譲渡によりM&Aを行うことが可能である(図3参照)。合併や事業譲渡と比べて手続上の負担が軽いことから、実務上M&Aの手法としてよく用いられる。ただし、対象医療法人が「持分の定めのない」社団医療法人や、財団医療法人である場合は、持分譲渡を行うことはできない。他方で、合併や事業譲渡と異なり、買収者側が医療法人を有している必要はないため、傘下に医療法人を有さない買収者が持分譲渡を受けることにより新たに医療法人を傘下におさめることが可能となる。
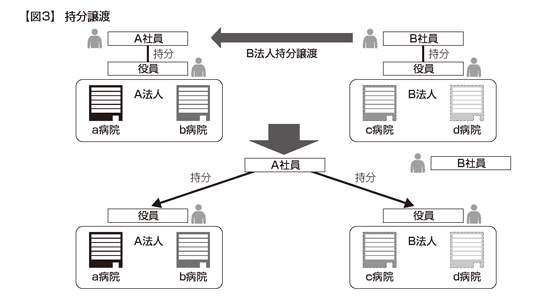
もっとも、医療法上、医療法人の運営に関与する機関はあくまで役員及び社員(財団医療法人の場合は評議員)であり、持分保有者(出資者)とは区別されていることから、持分を譲り受けた者が実際に対象医療法人のコントロールを掌握するためには、後述の役員等の変更を別途行う必要があることには注意を要する。
持分譲渡により、対象医療法人自体は従前どおり存続し、そのまま譲受人のコントロール下におかれることとなる。対象医療法人が当事者となっている法律関係に変動がないため、対象医療法人が保有する許認可や資産、権利義務について移転手続を経る必要はなく、持分譲渡後も、隠れた負債を含め対象医療法人の権利義務はそのまま存続することになる。
4.役員等の変更 医療法上、医療法人の運営に関与する機関として、役員(理事及び監事)及び社員(社団医療法人の場合)・評議員(財団医療法人の場合)が規定されている。すなわち、医療法人は、原則として、役員として理事3人以上及び監事1人以上を置くものとされ、理事により構成される理事会が医療法人の業務執行の意思決定を行い、監事が医療法人の業務・財産状況の監査等を行うこととされている(医療法46条の2、46条の4)。また、医療法人に関わる重要事項については、社員総会(社団医療法人の場合)又は評議員会(財団医療法人の場合)に諮られる(同法48条の3~49条の3)。
したがって、医療法人の役員及び社員・評議員のうち、これらによる意思決定に必要な人数の協力者がいれば、その医療法人のコントロールを事実上掌握することが可能となる。そのために必要な人数は医療法人の定款や寄附行為の内容によって異なりうる。医療法上は理事会、社員総会、評議員会のいずれも過半数決議が原則とされているが、定款・寄附行為により決議要件が加重されている場合があるため注意を要する。
この手法は、当事者となる医療法人の形態を問わず利用することができる。また、持分譲渡と同様、買収者側が医療法人を有している必要はないため、傘下に医療法人を有さない買収者もこの手法をとることができる。
役員等の変更を行うためには、医療法人において役員等の選任に必要な機関決定を行うほか、役員の変更については都道府県知事に届け出るものとされており(医療法施行令5条の13)、理事長の変更については登記手続が必要となる(組合等登記令2条)。
役員等の変更を行った場合、対象医療法人自体は従前どおり存続し、対象医療法人が当事者となっている法律関係に変動がないため、対象医療法人が保有する許認可や資産、権利義務について移転手続を経る必要はなく、役員等の変更後も、隠れた負債を含め対象医療法人の権利義務はそのまま存続する。
Ⅱ.ストラクチャリングにあたっての留意点
上記Ⅰで述べた各手法のいずれを選択するかは、最終的には、当事者となる医療法人の状況やM&Aで企図されている目的等の個別の案件ごとの具体的な事情に基づいて判断されることとなる。もちろん、合併や持分譲渡の場合は、そもそも当事者となりうる医療法人の種類が限定されているため、医療法人の種類によっては選択肢となりえない場合がある。また、一般的に、合併や事業譲渡については、手続面での負担が重く、相当の時間を要することとなることから、迅速かつ簡便に実行できる持分譲渡や役員等の変更が好まれる傾向にある。他方で、持分譲渡や役員等の変更については、買収者側が従前より医療法人を有している場合には、M&A後に二つの医療法人を傘下に抱えることとなり、役員等の配置や運営コスト等の負担が二重に生じる可能性がある。また、事業譲渡の方法による場合のみ、隠れた負債を遮断することが可能となる。
その他、医療法人のM&Aのストラクチャリングにあたって典型的に問題となるポイントとして、M&A対価の設定と役員等の配置・兼務が挙げられる。以下これらの点について解説する。ただし、ストラクチャリングにあたって考慮すべき要素は決してこれらに尽きるものではない。例えば、当事者が特定医療法人(脚注3)や社会医療法人(脚注4)である場合における買収後のそのステータスの維持の可否、個々の医療法人に関わる利害関係者(行政庁のみならず、取引金融機関や地元の医師会なども考えられる)の理解や協力が得られやすい形態、対象医療法人にいわゆるメディカル・サービス法人(MS法人)がある場合における買収後のMS法人との取引やMS法人自体の取扱い、売主側の理事長や他の重要人物から買収後における継続的な協力を確保するための方策なども問題となりうる。
1.M&A対価の設定 医療法人のM&Aにあたっては、まず、金銭対価の支払いの要否を含め、対価として誰に対してどのような金額を支払うこととするかを検討する必要がある。M&Aに伴って売主側の理事長個人に対して幾ばくかの金銭を支払うこととするのであれば、そのような支払いを前提としたストラクチャーを採用する必要がある。また、対価の支払主体が誰になるかによって、支払原資について資金調達の要否や方法が異なってくる。
上記Ⅰで述べた各手法のうち、金銭対価の支払いを伴うものは、事業譲渡と持分譲渡である。事業譲渡の場合は、譲受法人から譲渡法人に譲渡対価が支払われるため、譲受法人において支払原資を確保する必要がある。医療法人レベルで譲渡対価の支払いが行われるため、売主側の理事長個人への金銭の支払いはなされない。他方、持分譲渡の場合は、医療法人レベルではなく、持分の譲受人から譲渡人に譲渡対価が支払われるため、譲受人において支払原資を確保する必要がある。持分の譲渡当事者が個人である場合には、譲渡人たる個人に金銭の支払いがなされる一方、譲受人たる個人において支払原資を用意することとなる。
実務的には、M&Aに伴って売主側の個人に対して一定の金銭の支払いが行われるようなストラクチャーをとることが多く、その一つの方法として、役員の退職金の支払いが行われることがある。例えば、持分譲渡や役員等の変更を行う場合に、退職する売主側の理事長に対して、退職金の支払いを行うことが考えられる。この場合、退職金の支払主体はM&Aの対象医療法人となるため、対象医療法人において退職金の支払原資を確保する必要がある。
譲渡対価であれ退職金であれ、これらの支払金額については、医療法人の非営利性の観点からも、適正な金額であることが求められ、金額水準を決定するにあたっては、その妥当性につき税理士、会計士等と慎重に検証する必要がある。
2.役員等の配置・兼務 前述のとおり、一般的に、実施する際の手続面での負担に鑑みて、M&Aの手法として持分譲渡や役員等の変更が好まれる傾向があるが、これらの方法による場合、終局的には、対象医療法人のコントロールを掌握するために必要な人数の協力者を確保し、対象医療法人の役員等に就任してもらうことが必要となる。そのような人数の協力者を集めることは必ずしも容易ではない場合が多いことから、実務的な対応策として、買収者側の医療法人や関係会社の役職員に、対象医療法人の役員等に就任してもらうことが考えられる。従来の医療法人や関係会社での役職に就いたまま対象医療法人の役員等にも就任してもらう場合には、対象医療法人の役員等を兼務することとなる。このような医療法人の役員等の配置や兼務にあたっては様々な留意点がある。
まず、医療法人の役員等については、法令上、一定の資格要件が設けられている場合がある。例えば、医療法人の理事長は、原則として医師又は歯科医師であることが必要とされている(医療法46条の3)。また、医療法人の監事は、同じ医療法人の理事や職員を兼ねることはできない(同法48条)。さらには、財団医療法人における評議員については、同じ医療法人の役員を兼ねることができないほか、医師、看護師等の医療従事者などの資格要件が法定されている(同法49条の4)。このように、役員等の配置にあたっては、それぞれの役職の資格要件を満たしていることを確認することが重要となる。特定医療法人や社会医療法人についてはいわゆる同族要件が設けられている(租税特別措置法施行令39条の25、医療法42条の2)ことから、これらのステータスを維持するためには、同族要件に抵触しないよう、役員等に占める親族等の割合にも注意する必要がある。
医療法上、医療法人の役員等が、他の法人の役員等を兼務することを禁止する明文はない。しかし、だからといって兼務が自由に認められるものではなく、医療法人の非営利性等の観点から一定の制約に服すると解されている。
まず、医療法人の理事長が他の医療法人の理事長を兼ねることは、特別の理由・必然性がなければ認められないとの見解がある(脚注5)ことから、複数の医療法人の理事長を兼務する場合は、その可否につき慎重に検討する必要がある。
また、医療法人の役員の兼務に関しては、平成24年3月30日に行われた通知改正の内容に注意する必要がある。この通知改正において、医療法人の役員は、原則として医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務することが認められない一方で、例外的に兼務可能な範囲が明確化されている(「医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務について」(医政総発0330第4号、医政指発0330第4号)、「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」(平成5年総第5号・指第9号))。すなわち、医療法人の役員(監事を除く)の過半数を超えず、かつ、医療機関の非営利性に影響を与えない場合には、例外的に、一定の要件の下で兼務が認められている。具体的な要件については通知で詳細に定められており、例えば、営利法人等から物品の購入・賃貸又は役務提供を受ける商取引がある場合には、①医療法人の代表者の兼務でないこと、②営利法人等の規模が小さいことにより役職員を第三者に変更することが直ちには困難であること、③契約の内容が妥当であると認められることのいずれも満たすのであれば、兼務が認められる。営利法人等との取引が、医療法人が必要とする土地又は建物を賃借するものである場合には、上記のうち②及び③の要件を満たせば兼務が認められる。したがって、医療法人の役員を兼務してもらうことを検討するにあたっては、通知に定められている要件を充足するよう、注意する必要がある。
鈴木謙輔 すずき けんすけ
長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士。2000年弁護士登録、06年スタンフォード大学ロースクール(LL.M.)修了、07年~09年金融庁総務企画局市場課専門官。「大口株主による株式売却とインサイダー取引規制」(本誌444号16頁)など。
粂内将人 くめうち まさと
長島・大野・常松法律事務所 弁護士。2010年弁護士登録。不動産取引・流動化、M&A、薬事法、倒産法、知的財産法などを担当。
脚注
1 社団医療法人が他の社団医療法人と合併するためには総社員の同意が必要であり、財団医療法人が他の財団医療法人と合併するためには寄附行為に合併することができる旨の定めがなければならず、かつ、原則として理事の3分の2以上の同意が必要とされている。
2 個々の医療法人における定款(社団医療法人の場合)や寄附行為(財団医療法人の場合)の定めにもよるが、基本的には、社員総会(社団医療法人の場合)又は評議員会(財団医療法人の場合)の決議が必要になると考えられる。
3 特定医療法人は、医療法人のうち、租税特別措置法の規定により国税庁長官の承認を受けたものをいい、一定の法人税軽減措置の対象となる(同法67条の2)。
4 社会医療法人は、医療法人のうち、医療法の規定により都道府県知事の認定を受けたものをいい、一定の収益業務を行うことが認められている(同法42条の2)。
5 医療法制研究会編「病院・医院のための医療法人Q&A」(中央法規出版、平成3年)1531頁
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























