解説記事2012年12月10日 【最新判決研究】 評価通達における広大地と貸家建付地の評価方法の是非(2012年12月10日号・№478)
最新判決研究
評価通達における広大地と貸家建付地の評価方法の是非
東京地裁平成21年(行ウ)第486号、平成24年6月20日判決
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)X1(原告、甲の長女)及び乙(甲の長男)は、平成16年7月23日、甲の死亡により、次の土地等を含む財産を相続(以下「本件相続」という。)した。
① P市所在の土地1,227.52㎡(地目:畑、山林及び原野、以下「本件土地A」という。)
② P市所在の土地710.52㎡(地目:宅地、以下「本件土地B」という。なお、本件土地A及び本件土地Bを以下「本件各土地」という。)。
③ 本件土地Bを敷地とする賃貸アパート2棟(1棟は、「C荘Ⅰ」といい、その敷地を「C荘Ⅰ敷地」といい、もう1棟は、「C荘Ⅱ」といい、その敷地を「C荘Ⅱ敷地」という。この2棟を併せて以下「本件各建物」という。)
(2)以上の財産のうち、本件土地Aは、昭和58年12月20日に所定の認可を受けて施行されたP都市計画事業Q土地区画整理事業(以下「本件土地区画整理事業」という。)によりP市内の丘陵地に開発されたQ地区(以下「Q地区」という。)内の××街区(以下「本件同一街区」という。)にある1画地の宅地であり、その南西側はP市道G線(以下「G線」という。)に面しており、その北東側はP市道H3号線(以下「H3号線」という。)に面している。本件土地Aは、本件相続開始時、既に造成工事が完了していたものの、未だ利用されていない更地であった。また、Q地区内の土地においては、本件土地Aを含めG線との境界から北東及び南西に約25mまでの範囲は、都市計画法8条1項1号に規定する第2種住居地域とされており、その余は、同号に規定する第1種中高層住居専用地域とされていて、いずれも、容積率は200%、建ぺい率は60%とされている。なお、本件土地Aは、路線価地域にあり、地区の区分は普通住宅地区であり、周囲の路線価は、1㎡当たり、G線18万円、H3号線17万円と設定されている。
本件土地Bは、本件相続開始時、本件各建物が存在しており、C荘Ⅰ敷地の面積が285.08㎡とされ、C荘Ⅱ敷地の面積が425.44㎡とされていた。また、C荘Ⅰ及びC荘Ⅱの賃貸割合は、いずれも50%であった。
(3)X1及び乙は、平成17年5月20日、本件相続に係る相続税について、本件土地Aが財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)の広大地に当たり、本件土地Bが貸家建付地に当たる等とした上で課税価格を計算して申告した。これに対し、処分行政庁は、平成19年6月22日、本件土地Aは広大地に該当せず、本件土地B及び本件各建物はその全体が賃貸されていないとして、各人に対し更正処分等(以下「本件各更正等」という。)をした。
X1及び乙は、本件各更正等の取消しを求めて前審手続きを経た後、平成21年4月26日、乙が死亡したため、乙の妻X2、乙の長男X3及び次男X4が、乙を相続し、その地位を承継した(以下X1、X2、X3及びX4を「X1ら」という。)。X1らは、平成21年9月29日、国(被告)に対し、本件各更正等の取消しを求めて、本訴を提起した。
二、争点及び当事者の主張
1 争 点 本件の主要な争点は、次のとおりである。
① 広大地に該当するかの判断基準
② 本件土地Aは広大地に該当するか
③ 本件土地Bは広大地に該当するか
④ 本件土地Bが2つの画地の宅地とされる場合の同土地の価額の評価について
2 国の主張 (1)本件各土地が広大地に該当するかどうかについては、まず、評価通達24-4の定めに従って判定するのが基本であり、次に、評価通達の具体的事例への当てはめに際して、「「財産評価基本通達の一部改正について」通達のあらましについて(情報)」(平成16年6月29日付資産評価企画官情報第2号他、以下「16年情報」という。)及び「広大地の判定に当たり留意すべき事項(情報)」(平成17年6月17日付資産評価企画官情報第1号他、以下「17年情報」という。)を参考として活用するのが広大地評価の解釈の本旨である。
(2)本件土地Aは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地ではないこと及び本件土地Aがマンション適地であることからみて、広大地には該当しない。
(3)P市における開発許可面積基準は、500㎡以上とされており、500㎡未満の宅地については、広大地には該当しないこととなる。本件土地B上のC荘Ⅰ敷地及びC荘Ⅱ敷地は、いずれも500㎡未満であるから、広大地の評価対象にならない。
(4)本件土地Bの価額については、C荘Ⅰ敷地及びC荘Ⅱ敷地に区分され、C荘Ⅰ及びC荘Ⅱの賃貸割合がそれぞれ50%であるから、貸家建付地としての評価額は、それぞれの路線価等を適用すると、C荘Ⅰ敷地が3,196万円余及びC荘Ⅱ敷地が4,575万円余となる。
3 X1らの主張 (1)広大地の評価方法について国税庁が示した判断基準は、評価通達24-4、16年情報及び17年情報であるから、広大地に該当するかどうかは、これらの判断基準に従って判断されなければならない。国の主張は、納税者の信頼を裏切るものであり、失当である。
(2)本件土地Aは、評価通達24-4及び16年情報の判断基準により、広大地に該当する。
(3)本件土地Bは、一体として利用されているものであるから1画地として評価されるべきであるから、16年情報及び17年情報を適用すると、広大地に該当する。
(4)本件土地BをC荘Ⅰ敷地とC荘Ⅱ敷地に分けて評価したとしても、適用する路線価は西側市道をそれぞれ正面路線とすべきであること等から、C荘Ⅰ敷地の評価額は、2,772万円余となり、C荘Ⅱ敷地は、最高評価額でも3,831万円余となる。
三、判決要旨
請求棄却。
1 広大地に該当するかの判断基準について (1)相続税法22条は、相続により取得した財産の価額は、原則として、当該財産の取得の時における時価による旨を定めているが、財産の価額を客観的かつ適正に把握することは必ずしも容易なことではなく、また、納税者ごとに財産の評価の方法が異なることは公平の観点から好ましくないことから、課税実務上、国税庁長官が発した評価通達に基づいて、相続により取得した財産の価額の評価がされているところである。
(2)ところで、評価通達24-4に係る16年改正に関しては、16年情報が公表され、さらに、16年改正に係る評価通達24-4を適用する場合の広大地に該当するかどうかの判定について、17年情報が公表された。16年情報及び17年情報が公表されたこのような経緯に鑑みれば、X1らが本件において主張するように、評価通達24-4はいわば定義であり広大地に該当するか否かの具体的な判定基準は16年情報及び17年情報に委ねられているとの関係にあるとは解し難い。また、16年情報と17年情報との関係については、17年情報は、16年情報において整理された16年改正に係る評価通達24-4に定める広大地に該当するかどうかを判定する場合の考え方について、更なる考え方の統一性を図るため、16年情報の一部につき留意事項を取りまとめたものであって、X1らの主張するように、相互に矛盾する内容を含むことを前提に、17年情報が16年情報の一部を変更したものであるとは解し難い。
2 本件土地Aは広大地に該当するかについて (1)本件土地Aについては、各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
① 本件土地Aは、その南西側は幅員約18mのG線に面し、その北東側は幅員約8mのH3号線に面する間口24.55m、奥行50m、実測地積1,227.52㎡の1画地の宅地である。G線は、地形上はその周辺におけるいわゆる谷底部分となっていて上り勾配となっていることから、本件土地Aのうち、G線に近い南西側約5分の3の部分の地盤に対して、北東側約5分の2の部分の地盤は、約2.6m高くなっている。また、G線は、幅員約18mのP市の幹線道路であり、Q地区内の土地においては、G線との境界から北東及び南西に各25mまでの範囲が第2種住居地域とされているが、それ以外は、全て第1種中高層住居専用地域とされており、いずれも、容積率は200%、建ぺい率は60%とされている。
② 本件土地Aは、昭和58年に所定の認可を受けて施行された本件土地区画整理事業によりP市内の丘陵地に開発行為がされたQ地区内にあり、a線b駅の東方約1㎞、c線P駅の北西方約1.7kmに位置している本件同一街区内にある。
本件土地区画整理事業においては、Q地区の土地の利用について、①G線沿いの住居地域及び中・高層住宅建設希望調査に基づき集合換地をする街区から成り、換地については1,000㎡以上の割込みを主に行うものとされ、中高層などの非接地型の住宅や一部店舗などが形成されることが期待される「中・高層住宅ゾーン」(本件同一街区もこれに含まれる。)、②D中学校等から成る「教育・スポーツゾーン」並びに③上記①及び②以外の住宅地で、第2種住居専用地域に指定され、主に中層の非接地型の住宅や戸建ての接地型住宅が形成されることが期待される「中・低層住宅ゾーン」の3つのゾーンに区分し計画するものとされていた。
③ 平成16年当時、本件土地Aの正面路線であるG線のうち、B地点より北側には1㎡当たり16万円、B地点より南側は18万円と17万円の路線価が設定されていた。
④ 本件土地Aを含みG線に面する街区から成る地域にあっては、本件相続の開始時点において、42区画のうち21区画は、3階建てないし10階建てのマンションの敷地の用に供されており、4区画が戸建住宅の敷地、7区画が店舗の敷地、8区画が空き地、1区画が駐車場、1区画がP市の遊水地であった。同地域全体の面積に対する21棟のマンションの敷地の面積の占める割合は、55.7パーセントであった。
(2)評価通達24の4の趣旨は、評価の対象となる1画地の宅地の地積が、当該宅地の価額の形成に関して直接影響を与えるような特性を持つ当該宅地の属する地域における標準的な宅地の地積に比して著しく広大で、評価の時点において、当該宅地を、当該地域における経済的に最も合理的な宅地の利用を反映すると一般に見られる当該標準的な宅地の規模を踏まえて類似の利用に供しようとする際に、都市計画法に規定する許可を受けた上で開発行為を行わなければならない場合にあっては、当該開発行為により所要の土地の区画形質の変更を行ったときに、道路、公園等の公共公益的施設用地として相当のいわゆる潰れ地が生ずるのを免れないことがあり、評価通達15から評価通達20-5までによる減額の補正では十分とはいえないことがあることから、当該宅地の価額に影響を及ぼすべき客観的な個別事情として、価額が減少していると認められる範囲に対応させたものに相当する特殊な補正をすることとしたものと解される。このような趣旨に鑑みれば、評価通達24-4にいう評価の対象となる1画地の宅地の属する「その地域」とは、①河川や山などの自然的状況、②行政区域、③都市計画法による土地利用の規制などの公法上の規制等、④道路、⑤鉄道及び公園など、土地の利用の状況の連続性及び地域としての一体性を分断することがあると一般に考えられる客観的な状況を総合勘案し、各土地の利用の状況、環境等がおおむね同一と認められる、ある特定の用途に供されることを中心としたひとまとまりとみるのが相当な地域を指すものと解するのが相当である。
(3)以上を前提として、本件土地Aが広大地に該当するかの判断に当たっての基礎となる「その地域」の範囲を検討する。
前記のとおり、本件土地Aは、本件土地区画整理事業が施行されたQ地区内にあり、P市の幹線道路であるG線に面しているところ、①これまでに認定したところ及び弁論の全趣旨によれば、Q地区内のG線に面する各土地については、自然的状況及び行政区域については同一であると認められ、②公法上の規制については、Q地区内のうちG線の両側各25mまでの範囲のみが第2種住居地域とされ、その余は第1種中高層住居専用地域とされており、③道路の状況については、G線とB地点で交差するP市道K中央線及び同L線は、いずれもP市内における補助幹線道路と位置付けられており、G線の上記のB地点より南側の部分に面する地域内の各土地の周縁にある道路も、直線となっているG線の上記の部分に面する各街区を格子状に画するものとして整備されているのであって、④上記の各土地の連たんする部分について、鉄道や公園等の存在は認められない。そして、本件土地区画整理事業においても、Q地区のうちG線沿いの各街区を「中・高層住宅ゾーン」とし、「中・高層住宅ゾーン」においては、主に1,000㎡以上の規模での換地をすることが計画され、証拠によれば、換地処分がされた後の本件相続の開始当時において、本件土地Aを含むG線に面する各土地については、おおむね上記の計画に沿った土地の利用がされている状況にあったことが認められ、これらの土地については、路線価も同一であったものである。
これらの事情を前提に、前記に述べたところに照らすと、国主張地域をもって本件土地Aに係る評価通達24-4の「その地域」に当たるとする国の主張については、これを首肯するに足りる。
また、以上のほか、不動産鑑定士及び一級建築士であるK鑑定士の「その地域」の範囲についての意見が国主張地域とほぼ一致していることなどに照らすと、X1らの主張を考慮しても、国主張地域をもって、本件土地Aに係る評価通達24-4の「その地域」に当たると認めるのが相当というべきである(以下「本件地域」という。)。
(4)本件土地Aは、路線価方式により宅地の価額を評価する路線価区域中の地区の区分として普通住宅地区内にあり、その面積は1,227.52㎡であるところ、P市においては、土地の面積が500㎡以上の宅地について開発行為を行う場合には都市計画法所定の開発許可を受けることを要するとされているから、本件土地Aは、16年情報が広大地に該当する条件の例示として掲げる開発許可面積基準以上の土地に当たるものの、前記のとおり、本件土地区画整理事業においては、本件土地Aを含む「中・高層住宅ゾーン」においては主に1,000㎡以上の換地をすることが計画され、換地処分を経ておおむね上記の計画に沿った土地の利用がされる状況に至っていたものである。また、証拠によれば、本件相続の開始当時において、本件地域内の42区画の土地については、1区画当たりの平均面積は約927.2㎡であり、戸建住宅のある4区画(本件地域全体の面積に占める割合は1.2%)を除いた場合の1区画当たりの平均面積は約1,012.2㎡で、マンションの敷地の用に供されていた21区画の1区画当たりの平均面積は1,032.28㎡であり、これらのうち8区画は本件土地Aよりも面積が大きく、そのうち1,500㎡を超えるものは3区画であったこと(うち2区画は2,000㎡を超えるものであった。)、なお、店舗の敷地の用に供されていた7区画の1区画当たりの平均面積は1,513.89㎡であり、そのうち4区画は1,000㎡を超えるものであったことが認められる。そうすると、本件土地Aは、本件地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地に当たるとは認め難いというべきであるから、広大地に該当するとはいえない。
3 本件土地Bは広大地に該当するかについて (1)各証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件土地Bについて以下の事実が認められる。
① 本件相続の開始当時、本件土地B上には、C荘Ⅰ及びC荘Ⅱの2棟の木造2階建ての建物(本件各建物)が存在していた。C荘Ⅰ敷地の面積は285.08㎡であり、C荘Ⅱ敷地の面積は425.44㎡であった。
② 本件土地Bの南西側は西側市道に面し(接面距離7.13m)、南側は南側道路に面していたところ、南側道路は、いずれも本件相続により乙が取得した土地の一部であって、P市により名称をM1号線、幅員を1.82mとする市道として認定された道路の一部であり、西側市道及び南側道路には、いずれも1㎡当たり13万円の路線価が設定されていた。
③ 本件各建物は、昭和49年8月頃に建築され、その建築に当たっては、所定の確認の手続がされていた。
(2)評価通達7及び7-2の定めを本件土地Bについてみると、前記のとおり、本件土地Bは、2棟の本件各建物の敷地の用に供されていたほか、各建物の前面の駐車場の用に供されていたものであり、本件各建物は同じ時期に建築されたものの、建築に当たっての所要の確認手続も別個にされたそれぞれ独立の建物である。前記のとおり、本件相続の開始当時、C荘Ⅰの前面の駐車場は利用されておらず、C荘Ⅱの前面の駐車場のうち2区画をC荘Ⅱの入居者が利用していたものである。また、西側市道からのC荘Ⅱへの出入りに際しては、C荘Ⅰの前面の駐車場とは有蓋の側溝をもって画された南側道路を利用することができたものである。このような状況を踏まえて、X1及び乙は、本件相続税申告の際、C荘Ⅰ敷地及びC荘Ⅱ敷地について、それぞれの前面の駐車場と一体として利用されている一団の土地として、そのうちの主たる地目である宅地から成るものとし、かつ、それぞれ、別個の画地であるとした上で、申告したものと推認される。
これらの事情を前提として、前記に述べたところに照らすと、本件土地Bのうち、C荘Ⅰ敷地とC荘Ⅱ敷地については、それぞれをもって1画地の宅地に当たると評価すべきである。
(3)C荘Ⅰ敷地及びC荘Ⅱ敷地の面積は、いずれも16年情報にいう開発許可面積基準である500㎡に満たず、他の全証拠に照らしても、C荘Ⅰ敷地及びC荘Ⅱ敷地については、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大であるとは認め難く、評価通達24-4の広大地に該当するとはいえない。
4 本件土地Bが2つの画地の宅地とされる場合の同土地の価額の評価について 国は、本件土地Bの価額について、C荘Ⅰ敷地及びC荘Ⅱ敷地の2つの画地の宅地から成ることを前提に、それらの接する南側道路に設定された路線価に基づいて評価をするのに対し、X1らは、C荘Ⅱ敷地は、建築基準法上の接道義務を満たさない土地であることを前提に、西側市道を正面路線として評価されるべきである旨を主張する。
しかし、路線価は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに設定するものとされ、ここでいう路線は、不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいうものとされており、前記に述べた南側道路の本件相続の開始当時の状況に照らすと、上記の国の主張はこれを肯認することができ、X1らの上記主張は採用することができないものというべきである。
そうすると、本件土地BのうちC荘Ⅰ敷地の価額は、3,196万円余であり、C荘Ⅱ敷地の価額は、4,575万円余であると認められる。
四、解説
はじめに 評価通達において広大地の評価方法が初めて明らかにされたのは、平成6年の通達改正においてである。その時には、広大地が路線価地域に所在する場合には、通常の評価額から「公共公益的施設用地となる部分の地積」に対応する額を控除することとされた。この時には、「公共公益的施設用地」とは何かという実質判断が求められた。
ところが、平成16年の評価通達の改正によって、広大地の評価額は、通常の評価額よりも最大65%減額されるという数値が明確にされることになった。しかし、同通達改正は、「広大地」の該当要件を非常に厳しくすることにした。このため、「広大地」と認められれば、通常の評価額に対して最大65%の評価減が認められるが、認められなければ、一切評価減が認められなくなるということで、相続税における土地評価において多大な関心を呼ぶこととなった。
その結果、評価通達上の「広大地」の適用の可否をめぐる争訟事件も多発しており(注1)、本件もその一例である。このような争訟事件では、当該土地の相続税法上の「時価」が幾許であるかでなく、専ら評価上有利な「広大地」に該当するか否かのみ争われている。また、このような「広大地」の評価は、評価通達や同通達に係る国税庁の「情報」によって行われているが故に、「通達」や「情報」の租税法律主義における法的性格も問題となるところである。
本件においては、本件土地A及び本件土地Bについて「広大地」の適用の可否が争われたほか、本件土地Bが2つの賃貸アパートに係る貸家建付地であるところ、当該土地の評価単位(評価上の区分)や当該貸家の賃貸割合等も評価上問題とされている。以下、これらの諸問題について、検討することとする。
1 土地の価額と広大地の評価 (1)相続税法22条は、「……相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によ」ることを定めている。しかし、各財産の「時価」を評価することが困難であることもあって、実務では、評価通達の取扱いに依存することとなる。
ところで、評価通達では、「時価とは、課税時期(〈略〉)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」(評基通1(2))と定めている。この「不特定多数の……通常成立すると認められる価額」は、一般に、客観的交換価額又は客観的交換価値を意味するものとして、学説、判例において広く支持されている(注2)。
しかしながら、「時価」の意義が客観的交換価額を意味するものであることを明らかにするのみでは通達の機能である職務命令としての時価解釈の統一を図ることは困難である。そこで、同通達は、前記規定に続けて、「その価額は、この通達の定めによって評価した価額による」(評基通1(2))と定め、2項以下において各財産について具体的な評価方法を定めている。
(2)評価通達では、土地の価額について、土地を宅地、田、畑等の10種類の地目に区分し、かつ、「一体として利用されている一団の土地」ごとに評価する(評基通7)。本件で問題となっている宅地については、「一画地の宅地(利用の単位となっている一区画の宅地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。」(評基通7-2)こととしている。
また、宅地については、市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式によることとし、それ以外の宅地については倍率方式によることとしている(評基通11)。
本件土地A及び本件土地Bについて適用される路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、奥行価格補正等(評基通15~20-5)の画地調整により計算した金額によって評価する方式をいう(評基通13)。路線価は、宅地の価額が概ね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに設定し、売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長によって定められる(評基通14)。
この路線価方式は、いわゆる評価基準制度の代表的なものであるが、それによって算定される価額は、路線価が標準宅地を想定して定められていること、評価日がその年の1月1日とされていること等からみて、課税時期における当該財産の「時価」というよりも標準的価額を意味することになる。なお、大規模工場用地、広大地等の特別の土地については、通常の路線価方式又は倍率方式のみで「時価」を適正に評価し難いということで、それぞれ特別の評価方法を定めている(評基通22~24の8)。
(3)本件で問題となっている広大地の評価方法は、次のとおりである(評基通24-4(抄))。
「その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条(定義)第12項に規定する開発行為(以下本項において「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(22-2(大規模工場用地)に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいう。)を除く。以下「広大地」という。)の価額は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価する。
(1)その広大地が路線価地域に所在する場合
その広大地の面する路線の路線価に、15(奥行価格補正)から20-5(容積率の異なる二以上の地域にわたる宅地の評価)までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額
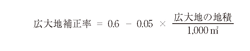 」
」
2 評価通達24-4と16年情報等との関係 (1)前記1で述べたように、相続税における土地の「価額」は、相続税法上は「時価」に因るのであるが、「時価」の解釈・把握が困難であること等もあって、実務上、国税庁の評価通達の取扱いによって「時価」評価が行われることになる。しかも、本件で問題となっている広大地については、評価通達上の土地の評価の中でも同通達24-4によって特別の取扱いが定められている。更に、問題となるのは、このような通達の取扱いのみでは理解し難いということで、国税庁では、重要な通達を発遣する場合に、同通達の取扱いを解説する「情報」を発出することがある。本件における16年情報及び17年情報は、その「情報」の一つである。
このような場合に問題となるのは、法律、政省令、通達及び情報の法的性質とそれぞれの関係である。この場合、法律及び政省令は、租税法律主義における法源として機能するのは当然であるが、通達は、行政庁部内の命令手段であって(行政組織法14②参照)、法源ではない。しかし、通達は、行政庁部内を拘束するのみならず、実質的には、納税者の判断を拘束するということで法的機能を有している(注3)。他方、「情報」については、その発出について通達のように法的根拠があるわけではなく、通達の取扱いを理解させるために行政上の便宜から発出されている。それも、通達が行政庁職員を対象としているわけであるから、情報も行政庁職員を対象にしていることになる。
(2)しかしながら、実務においては、法律、政省令、通達又は情報の法律上の区分が正確に行われているわけではなく、実質的には、いずれも税務職員や納税者を拘束することになる。特に、通達と情報との関係については、後者が通達の発遣後に発出されることから、後者が国税庁の最終的な考え方であると誤解されることにもなる。
そのため、本件においても、X1らは、広大地の判定に当たって、むしろ16年情報及び17年情報の考え方を優先して判断すべきである旨主張した。これに対し、本判決は、国税庁が発出する各種情報の趣旨には十分配慮されるべきものであるが、「第一義的には評価通達24-4の定めとの関係が考慮されるべきものといえ、その定める内容を理解するのに際して、16年情報及び17年情報において述べられているところを参照することとなると解するのが相当である。」と判示して、X1らの主張を排斥している。
このような判示は、前述の通達と情報の法的性質の差異に照らし、当然のことではあるが、通達の取扱いと情報との間に差異があるかのような誤解が生じること自体が問題であろう。けだし、両者の間にそのような誤解を生じさせるような余地がなければ、X1らの主張それ自体も成立しないはずであり、裁判所の判断も必要ないはずである。
(3)ところで、16年情報については、本件に関係が強い部分を抜粋して示すと、次のとおりである。
① 広大地に該当するもの、しないものの例示
「(広大地に該当する条件の例示)
・普通住宅地等に所在する土地で、各自治体が定める開発許可を要する面積基準以上のもの(ただし、下記の該当しない条件の例示に該当するものを除く。)。
(注)ミニ開発分譲が多い地域に存する土地については、開発許可を要する面積基準(例え
ば、三大都市圏500㎡)に満たない場合であっても、広大地に該当する場合があることに留意する。
(広大地に該当しない条件の例示)
・既に開発を了しているマンション・ビル等の敷地用地
・現に宅地として有効利用されている建築物等の敷地(例えば、大規模店舗、ファミリーレストラン等)
・原則として容積率300%以上の地域に所在する土地
・公共公益的施設用地の負担がほとんど生じないと認められる土地
(例)道路に面しており、間口が広く、奥行きがそれほどではない土地(道路が二方、三方及び四方にある場合も同様)」
② マンション適地の判定
「なお、評価する土地がマンション適地かどうかの判断基準としては、次のような基準が参考となる(清文社刊「特殊な画地と鑑定評価」土地評価理論研究会(1993年8月)より抜粋)。
イ 近隣地域又は周辺の類似地域に現にマンションが建てられているし、また現在も建築工事中のものが多数ある場合、つまりマンション敷地としての利用に地域が移行しつつある状態で、しかもその移行の程度が相当進んでいる場合
ロ 現実のマンションの建築状況はどうであれ、用途地域・建ぺい率・容積率や当該地方公共団体の開発規制等が厳しくなく、交通、教育、医療等の公的施設や商業地への接近性から判断しても、換言すれば、社会的・経済的・行政的見地から判断して、まさにマンション適地と認められる場合」
(4)また、17年情報については、本件に関係が強い部分を抜粋して示すと、次のとおりである。
① 広大地該当の面積基準
「(面積基準)
原則として、次に掲げる面積以上の宅地については、面積基準の要件を満たすものとする。
① 市街化区域、非線引き都市計画区域(②に該当するものを除く。)
……都市計画法施行令第19条第1項及び第2項に定める面積(※)
※ 1 市街化区域
三大都市圏………………500㎡
それ以外の地域…………1,000㎡
2 非線引き都市計画区域……3,000㎡
(略)」
② マンション適地の判定
「評価しようとする土地が、課税時期においてマンション等の敷地でない場合、マンション等の敷地として使用するのが最有効使用と認められるかどうかの判定については、その土地の周辺地域の標準的使用の状況を参考とすることとなる。しかし、戸建住宅とマンション等が混在する地域(主に容積率200%の地域)は、最有効使用の判定が困難な場合もあることから、このような場合には、周囲の状況や専門家の意見から判断して、明らかにマンション等の敷地に適していると認められる土地を除き、広大地に該当する。
一方、容積率が300%以上の地域内にあり、かつ、開発許可面積基準以上の土地は、戸建住宅の敷地用地として利用するよりもマンション等の敷地として利用する方が最有効使用と判定される場合が多いことから、原則として、広大地に該当しないこととなる。」
3 本件各土地の評価方法 (1)本件においては、本件各土地につき、前記1及び2で述べた評価通達上の広大地の評価の取扱いを適用し、主として、それぞれの土地が広大地に該当するか否かが問題とされた。まず、本件土地Aについては、本判決は、本件土地区画整理事業においては、本件土地Aを含む「中・高層住宅ゾーン」においては1,000㎡以上の換地をすることが計画され、本件地域全体面積の55.7%を占めるマンション敷地の1区画当たりの平均面積が1,032.28㎡であること等を認定し、「そうすると、面積1,227.52㎡である本件土地Aは、本件地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地に当たるとは認め難いというべきであって、その余の点について判断するまでもなく、評価通達24-4の広大地に該当するとはいえないものというべきである。」と判示した。
更に、本判決は、「16年情報にいう開発許可面積基準以上の土地であっても、その属する地域内の他の土地の規模の状況のいかんによっては、広大地に該当しないと判断されることがあることは、17年情報に述べられているとおりである。」と判示し、評価通達24-4と16年情報及び17年情報との関係を明らかにした。
本判決におけるこのような判断は、「広大地」として評価されるかどうかは、全て国税庁が発出する評価通達と16年情報と17年情報によって判断されることからみて、当然の帰結であると考えられる。しかしながら、本件土地Aが実質的にみてマンション適地に該当するから広大地に該当しないという理由のみで、本件土地Aの「時価」が適正に評価されたとは認め難い問題がある。その問題は、後記4で述べる。
(2)次に、本件土地Bについては、主位的には、本件土地Bを一画地の宅地として広大地として評価されるべきか否か、二次的には、本件土地BをC荘Ⅰ敷地とC荘Ⅱ敷地に区分した場合の評価方法が争われた。
本判決は、前述のように、本件土地Bの使用実態からみて、C荘Ⅰ敷地とC荘Ⅱ敷地をそれぞれ一画地の宅地として評価されるべきところ、いずれの敷地も、P市における16年情報にいう開発許可面積基準である500㎡に満たないのであるから、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく広大であるとは認め難いとして、広大地に該当することを否定した。
また、本判決は、C荘Ⅰ敷地及びC荘Ⅱ敷地の価額の評価方法については、評価通達26に定める貸家建付地としての評価方法によるべきであるとして、国側の主張を全面的に容認している。しかし、評価通達26に定める貸家建付地の評価方法には、後記4で述べるような問題を抱えているわけであるから、そのような問題点の是非が検討されるべきであったと考えられる。もっとも、この点については、X1らも何ら主張していない。
4 マンション用地・貸家建付地の評価 (1)本件においては、主として、本件各土地が広大地に該当するか否かが争われたものであるが、広大地に該当しない理由の一つとして、本件各土地がマンション適地であることが指摘されている。その結果、本件土地Aについては、1億9,917万円余で評価されることになったが、これが広大地に該当すると、補正率0.594が適用されるので、1億1,183万円余となる。そして、仮に、本件土地Aが5,000㎡であると、補正率0.35が適用されるので、6,970万円余となる。このことは、広大地に該当すると納税者にとって余りに有利に評価されるのに対し、マンション適地に該当すると余りに不利に評価されることになる。
ところで、マンション用の敷地であっても、評価通達24-4がいう「公共公益的施設用地」に準ずる公益的用地の負担が不可欠であり、かつ、マンション所有者にとっては、その敷地が共有地であるが故に自由に処分できるわけではない。そうであるから、マンション敷地の適切な評価減の導入が求められていたのである(注4)が、それが放置されたままとなっている。
他方、広大地の評価方法については、平成16年の改正によって余りに有利に評価されることとなり、当該土地の通常の売買価額よりも大幅な低評価となることが現出している。このことは、広大地の評価額が相続税法上の「時価」を表わしていないことを意味している。そして、そのことが、本件のような争訟事件を多発させる原因にもなっている。ともあれ、このようなことは、評価通達上の評価の合理性に問題があることを示している。
(2)また、本件土地Bについては、C荘Ⅰ敷地とC荘Ⅱ敷地とに区分され、それぞれ貸家建付地として評価されることとなった。この場合、貸家建付地の評価については、評価通達26によって、次の算式によって評価されることになっている。
この算式における「賃貸割合」は、平成11年の評価通達の改正によって設けられたものである。その結果、賃貸アパートのように、満室であれば、当該アパートの最有効利用が達成され、その敷地の経済的価値が最高になるはずであるが、評価通達上の評価額は最も低く評価されることになる。逆に、空室が増えて当該敷地の経済的価値が低くなると、評価通達上の評価額が高くなるという矛盾が生じることになる(注5)。これも、貸家建付地の評価額が相続税法上の「時価」を表わしていないことを意味している。
このような通達改正は、最高裁平成10年2月26日第一小法廷判決(税資230号851頁)(注6)に起因している。この判決では、アパートの賃貸を開始し、21室中4室入居した段階で相続が開始し、17室が未入居だった事案につき、空室の17室に対応する貸家建付地が自用地として高額に評価された、というものである。このような判断は、前述の賃貸アパートとその敷地の経済的価値の実態に適合しているとは考えられない。そのため、これを起因とする評価通達の改正にも合理性があったとも考えられない。その点では、本件においても、本件土地Bの評価に当たって、評価通達26の不当性が検討されて然るべきであったと考えられる。しかし、X1らは、この点についても主張していないようである。
5 本判決の意義と問題点 (1)以上のように、本件は、P市の土地区画整理事業内に存する本件土地Aと既にP市内に貸家の用に供されていた本件土地Bについて、主として、それぞれ評価通達上の広大地に該当するか否かが争われたものである。このような広大地の評価については、法律の規定ではなく、国税庁部内の職務命令である評価通達と同通達の取扱いを説明する情報によって行われることに特色がある。これは、評価通達24-4に定める広大地の評価額が最高65%評価減されるということで、当該土地の相続税法上の「時価」が幾許であるかということが問題にならず、専ら当該土地が評価通達上の「広大地」に該当するか否かが問題とされるからでもある。換言すると、広大地の該当の有無が争われる当該土地については、広大地に該当しない場合の評価額が、ほとんどの場合、相続税法上の「時価」を上回ることなく、当該「時価」を争う必要がないからである。
しかも、評価通達24-4の評価方法は、広大地に該当すれば寛大な評価減の適用が受けられるが、広大地の該当要件については非常に厳しく定められているため、広大地の該当の有無をめぐって争われることが多く、単に争訟事件になった事案に限らず、申告、課税段階で問題とされることが多い。そのため、税理士等の専門家の関心も高い。したがって、本判決は、実務上注目が高いという点では、意義のある判決である。
(2)結局、本判決は、評価通達24-4と16年情報及び17年情報の取扱いに合理性があるものとして、本件各土地が広大地に該当せずその価額(時価)について、本件各更正等における認定額を適法と認めたものである。しかしながら、前記3及び4で述べたように、評価通達24-4に定める広大地の評価額が相続税法上の「時価」を適正に表わしているものか否かについては、問題を残しているところである。
また、本件土地Aがマンション適地であるとして広大地に該当しない場合にも、マンション用地の評価方法それ自体に前記4で述べたように、その特質に応じた評価減を要するという問題を抱えている。更に、本件土地Bについては、C荘Ⅰ敷地とC荘Ⅱ敷地に区分して貸家建付地として評価する場合に、貸家建付地の評価方法を定めている評価通達26自体に前記4で述べた問題を内包している。しかしながら、本訴においては、そのような問題が検討されることもなかった。そのことは、本判決の意義を低下させることにもなった。
(注1)金沢地裁平成18年4月10日判決(税資256号順号10361)、仙台地裁平成17年3月24日判決(同255号順号9971)、仙台高裁平成19年1月26日判決(同257号順号10617)、東京地裁平成20年8月29日判決(同258号順号11014)、平成21年6月25日裁決(裁決事例集77集383頁)、平成21年12月15日裁決(同78集432頁)、平成23年9月5日裁決(同84集314頁)等参照。
(注2)金子宏『租税法 第17版』(弘文堂 平成24年)551頁、東京高裁平成7年12月13日判決(行裁例集46巻12号1143頁)等参照。
(注3)詳細は、品川芳宣『租税法律主義と税務通達』(ぎょうせい 平成16年)34頁以下参照。
(注4)品川芳宣・緑川正博『相続税財産評価の論点~財産評価の理論と実務の疑問を糾す~』(ぎょうせい 平成9年)107頁等参照。
(注5)品川芳宣・緑川正博『相続税財産評価の理論と実践』(ぎょうせい 平成17年)85頁等参照。
(注6)品川芳宣『重要租税判決の実務研究』(大蔵財務協会 平成17年)555頁参照。
評価通達における広大地と貸家建付地の評価方法の是非
東京地裁平成21年(行ウ)第486号、平成24年6月20日判決
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)X1(原告、甲の長女)及び乙(甲の長男)は、平成16年7月23日、甲の死亡により、次の土地等を含む財産を相続(以下「本件相続」という。)した。
① P市所在の土地1,227.52㎡(地目:畑、山林及び原野、以下「本件土地A」という。)
② P市所在の土地710.52㎡(地目:宅地、以下「本件土地B」という。なお、本件土地A及び本件土地Bを以下「本件各土地」という。)。
③ 本件土地Bを敷地とする賃貸アパート2棟(1棟は、「C荘Ⅰ」といい、その敷地を「C荘Ⅰ敷地」といい、もう1棟は、「C荘Ⅱ」といい、その敷地を「C荘Ⅱ敷地」という。この2棟を併せて以下「本件各建物」という。)
(2)以上の財産のうち、本件土地Aは、昭和58年12月20日に所定の認可を受けて施行されたP都市計画事業Q土地区画整理事業(以下「本件土地区画整理事業」という。)によりP市内の丘陵地に開発されたQ地区(以下「Q地区」という。)内の××街区(以下「本件同一街区」という。)にある1画地の宅地であり、その南西側はP市道G線(以下「G線」という。)に面しており、その北東側はP市道H3号線(以下「H3号線」という。)に面している。本件土地Aは、本件相続開始時、既に造成工事が完了していたものの、未だ利用されていない更地であった。また、Q地区内の土地においては、本件土地Aを含めG線との境界から北東及び南西に約25mまでの範囲は、都市計画法8条1項1号に規定する第2種住居地域とされており、その余は、同号に規定する第1種中高層住居専用地域とされていて、いずれも、容積率は200%、建ぺい率は60%とされている。なお、本件土地Aは、路線価地域にあり、地区の区分は普通住宅地区であり、周囲の路線価は、1㎡当たり、G線18万円、H3号線17万円と設定されている。
本件土地Bは、本件相続開始時、本件各建物が存在しており、C荘Ⅰ敷地の面積が285.08㎡とされ、C荘Ⅱ敷地の面積が425.44㎡とされていた。また、C荘Ⅰ及びC荘Ⅱの賃貸割合は、いずれも50%であった。
(3)X1及び乙は、平成17年5月20日、本件相続に係る相続税について、本件土地Aが財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)の広大地に当たり、本件土地Bが貸家建付地に当たる等とした上で課税価格を計算して申告した。これに対し、処分行政庁は、平成19年6月22日、本件土地Aは広大地に該当せず、本件土地B及び本件各建物はその全体が賃貸されていないとして、各人に対し更正処分等(以下「本件各更正等」という。)をした。
X1及び乙は、本件各更正等の取消しを求めて前審手続きを経た後、平成21年4月26日、乙が死亡したため、乙の妻X2、乙の長男X3及び次男X4が、乙を相続し、その地位を承継した(以下X1、X2、X3及びX4を「X1ら」という。)。X1らは、平成21年9月29日、国(被告)に対し、本件各更正等の取消しを求めて、本訴を提起した。
二、争点及び当事者の主張
1 争 点 本件の主要な争点は、次のとおりである。
① 広大地に該当するかの判断基準
② 本件土地Aは広大地に該当するか
③ 本件土地Bは広大地に該当するか
④ 本件土地Bが2つの画地の宅地とされる場合の同土地の価額の評価について
2 国の主張 (1)本件各土地が広大地に該当するかどうかについては、まず、評価通達24-4の定めに従って判定するのが基本であり、次に、評価通達の具体的事例への当てはめに際して、「「財産評価基本通達の一部改正について」通達のあらましについて(情報)」(平成16年6月29日付資産評価企画官情報第2号他、以下「16年情報」という。)及び「広大地の判定に当たり留意すべき事項(情報)」(平成17年6月17日付資産評価企画官情報第1号他、以下「17年情報」という。)を参考として活用するのが広大地評価の解釈の本旨である。
(2)本件土地Aは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地ではないこと及び本件土地Aがマンション適地であることからみて、広大地には該当しない。
(3)P市における開発許可面積基準は、500㎡以上とされており、500㎡未満の宅地については、広大地には該当しないこととなる。本件土地B上のC荘Ⅰ敷地及びC荘Ⅱ敷地は、いずれも500㎡未満であるから、広大地の評価対象にならない。
(4)本件土地Bの価額については、C荘Ⅰ敷地及びC荘Ⅱ敷地に区分され、C荘Ⅰ及びC荘Ⅱの賃貸割合がそれぞれ50%であるから、貸家建付地としての評価額は、それぞれの路線価等を適用すると、C荘Ⅰ敷地が3,196万円余及びC荘Ⅱ敷地が4,575万円余となる。
3 X1らの主張 (1)広大地の評価方法について国税庁が示した判断基準は、評価通達24-4、16年情報及び17年情報であるから、広大地に該当するかどうかは、これらの判断基準に従って判断されなければならない。国の主張は、納税者の信頼を裏切るものであり、失当である。
(2)本件土地Aは、評価通達24-4及び16年情報の判断基準により、広大地に該当する。
(3)本件土地Bは、一体として利用されているものであるから1画地として評価されるべきであるから、16年情報及び17年情報を適用すると、広大地に該当する。
(4)本件土地BをC荘Ⅰ敷地とC荘Ⅱ敷地に分けて評価したとしても、適用する路線価は西側市道をそれぞれ正面路線とすべきであること等から、C荘Ⅰ敷地の評価額は、2,772万円余となり、C荘Ⅱ敷地は、最高評価額でも3,831万円余となる。
三、判決要旨
請求棄却。
1 広大地に該当するかの判断基準について (1)相続税法22条は、相続により取得した財産の価額は、原則として、当該財産の取得の時における時価による旨を定めているが、財産の価額を客観的かつ適正に把握することは必ずしも容易なことではなく、また、納税者ごとに財産の評価の方法が異なることは公平の観点から好ましくないことから、課税実務上、国税庁長官が発した評価通達に基づいて、相続により取得した財産の価額の評価がされているところである。
(2)ところで、評価通達24-4に係る16年改正に関しては、16年情報が公表され、さらに、16年改正に係る評価通達24-4を適用する場合の広大地に該当するかどうかの判定について、17年情報が公表された。16年情報及び17年情報が公表されたこのような経緯に鑑みれば、X1らが本件において主張するように、評価通達24-4はいわば定義であり広大地に該当するか否かの具体的な判定基準は16年情報及び17年情報に委ねられているとの関係にあるとは解し難い。また、16年情報と17年情報との関係については、17年情報は、16年情報において整理された16年改正に係る評価通達24-4に定める広大地に該当するかどうかを判定する場合の考え方について、更なる考え方の統一性を図るため、16年情報の一部につき留意事項を取りまとめたものであって、X1らの主張するように、相互に矛盾する内容を含むことを前提に、17年情報が16年情報の一部を変更したものであるとは解し難い。
2 本件土地Aは広大地に該当するかについて (1)本件土地Aについては、各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
① 本件土地Aは、その南西側は幅員約18mのG線に面し、その北東側は幅員約8mのH3号線に面する間口24.55m、奥行50m、実測地積1,227.52㎡の1画地の宅地である。G線は、地形上はその周辺におけるいわゆる谷底部分となっていて上り勾配となっていることから、本件土地Aのうち、G線に近い南西側約5分の3の部分の地盤に対して、北東側約5分の2の部分の地盤は、約2.6m高くなっている。また、G線は、幅員約18mのP市の幹線道路であり、Q地区内の土地においては、G線との境界から北東及び南西に各25mまでの範囲が第2種住居地域とされているが、それ以外は、全て第1種中高層住居専用地域とされており、いずれも、容積率は200%、建ぺい率は60%とされている。
② 本件土地Aは、昭和58年に所定の認可を受けて施行された本件土地区画整理事業によりP市内の丘陵地に開発行為がされたQ地区内にあり、a線b駅の東方約1㎞、c線P駅の北西方約1.7kmに位置している本件同一街区内にある。
本件土地区画整理事業においては、Q地区の土地の利用について、①G線沿いの住居地域及び中・高層住宅建設希望調査に基づき集合換地をする街区から成り、換地については1,000㎡以上の割込みを主に行うものとされ、中高層などの非接地型の住宅や一部店舗などが形成されることが期待される「中・高層住宅ゾーン」(本件同一街区もこれに含まれる。)、②D中学校等から成る「教育・スポーツゾーン」並びに③上記①及び②以外の住宅地で、第2種住居専用地域に指定され、主に中層の非接地型の住宅や戸建ての接地型住宅が形成されることが期待される「中・低層住宅ゾーン」の3つのゾーンに区分し計画するものとされていた。
③ 平成16年当時、本件土地Aの正面路線であるG線のうち、B地点より北側には1㎡当たり16万円、B地点より南側は18万円と17万円の路線価が設定されていた。
④ 本件土地Aを含みG線に面する街区から成る地域にあっては、本件相続の開始時点において、42区画のうち21区画は、3階建てないし10階建てのマンションの敷地の用に供されており、4区画が戸建住宅の敷地、7区画が店舗の敷地、8区画が空き地、1区画が駐車場、1区画がP市の遊水地であった。同地域全体の面積に対する21棟のマンションの敷地の面積の占める割合は、55.7パーセントであった。
(2)評価通達24の4の趣旨は、評価の対象となる1画地の宅地の地積が、当該宅地の価額の形成に関して直接影響を与えるような特性を持つ当該宅地の属する地域における標準的な宅地の地積に比して著しく広大で、評価の時点において、当該宅地を、当該地域における経済的に最も合理的な宅地の利用を反映すると一般に見られる当該標準的な宅地の規模を踏まえて類似の利用に供しようとする際に、都市計画法に規定する許可を受けた上で開発行為を行わなければならない場合にあっては、当該開発行為により所要の土地の区画形質の変更を行ったときに、道路、公園等の公共公益的施設用地として相当のいわゆる潰れ地が生ずるのを免れないことがあり、評価通達15から評価通達20-5までによる減額の補正では十分とはいえないことがあることから、当該宅地の価額に影響を及ぼすべき客観的な個別事情として、価額が減少していると認められる範囲に対応させたものに相当する特殊な補正をすることとしたものと解される。このような趣旨に鑑みれば、評価通達24-4にいう評価の対象となる1画地の宅地の属する「その地域」とは、①河川や山などの自然的状況、②行政区域、③都市計画法による土地利用の規制などの公法上の規制等、④道路、⑤鉄道及び公園など、土地の利用の状況の連続性及び地域としての一体性を分断することがあると一般に考えられる客観的な状況を総合勘案し、各土地の利用の状況、環境等がおおむね同一と認められる、ある特定の用途に供されることを中心としたひとまとまりとみるのが相当な地域を指すものと解するのが相当である。
(3)以上を前提として、本件土地Aが広大地に該当するかの判断に当たっての基礎となる「その地域」の範囲を検討する。
前記のとおり、本件土地Aは、本件土地区画整理事業が施行されたQ地区内にあり、P市の幹線道路であるG線に面しているところ、①これまでに認定したところ及び弁論の全趣旨によれば、Q地区内のG線に面する各土地については、自然的状況及び行政区域については同一であると認められ、②公法上の規制については、Q地区内のうちG線の両側各25mまでの範囲のみが第2種住居地域とされ、その余は第1種中高層住居専用地域とされており、③道路の状況については、G線とB地点で交差するP市道K中央線及び同L線は、いずれもP市内における補助幹線道路と位置付けられており、G線の上記のB地点より南側の部分に面する地域内の各土地の周縁にある道路も、直線となっているG線の上記の部分に面する各街区を格子状に画するものとして整備されているのであって、④上記の各土地の連たんする部分について、鉄道や公園等の存在は認められない。そして、本件土地区画整理事業においても、Q地区のうちG線沿いの各街区を「中・高層住宅ゾーン」とし、「中・高層住宅ゾーン」においては、主に1,000㎡以上の規模での換地をすることが計画され、証拠によれば、換地処分がされた後の本件相続の開始当時において、本件土地Aを含むG線に面する各土地については、おおむね上記の計画に沿った土地の利用がされている状況にあったことが認められ、これらの土地については、路線価も同一であったものである。
これらの事情を前提に、前記に述べたところに照らすと、国主張地域をもって本件土地Aに係る評価通達24-4の「その地域」に当たるとする国の主張については、これを首肯するに足りる。
また、以上のほか、不動産鑑定士及び一級建築士であるK鑑定士の「その地域」の範囲についての意見が国主張地域とほぼ一致していることなどに照らすと、X1らの主張を考慮しても、国主張地域をもって、本件土地Aに係る評価通達24-4の「その地域」に当たると認めるのが相当というべきである(以下「本件地域」という。)。
(4)本件土地Aは、路線価方式により宅地の価額を評価する路線価区域中の地区の区分として普通住宅地区内にあり、その面積は1,227.52㎡であるところ、P市においては、土地の面積が500㎡以上の宅地について開発行為を行う場合には都市計画法所定の開発許可を受けることを要するとされているから、本件土地Aは、16年情報が広大地に該当する条件の例示として掲げる開発許可面積基準以上の土地に当たるものの、前記のとおり、本件土地区画整理事業においては、本件土地Aを含む「中・高層住宅ゾーン」においては主に1,000㎡以上の換地をすることが計画され、換地処分を経ておおむね上記の計画に沿った土地の利用がされる状況に至っていたものである。また、証拠によれば、本件相続の開始当時において、本件地域内の42区画の土地については、1区画当たりの平均面積は約927.2㎡であり、戸建住宅のある4区画(本件地域全体の面積に占める割合は1.2%)を除いた場合の1区画当たりの平均面積は約1,012.2㎡で、マンションの敷地の用に供されていた21区画の1区画当たりの平均面積は1,032.28㎡であり、これらのうち8区画は本件土地Aよりも面積が大きく、そのうち1,500㎡を超えるものは3区画であったこと(うち2区画は2,000㎡を超えるものであった。)、なお、店舗の敷地の用に供されていた7区画の1区画当たりの平均面積は1,513.89㎡であり、そのうち4区画は1,000㎡を超えるものであったことが認められる。そうすると、本件土地Aは、本件地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地に当たるとは認め難いというべきであるから、広大地に該当するとはいえない。
3 本件土地Bは広大地に該当するかについて (1)各証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件土地Bについて以下の事実が認められる。
① 本件相続の開始当時、本件土地B上には、C荘Ⅰ及びC荘Ⅱの2棟の木造2階建ての建物(本件各建物)が存在していた。C荘Ⅰ敷地の面積は285.08㎡であり、C荘Ⅱ敷地の面積は425.44㎡であった。
② 本件土地Bの南西側は西側市道に面し(接面距離7.13m)、南側は南側道路に面していたところ、南側道路は、いずれも本件相続により乙が取得した土地の一部であって、P市により名称をM1号線、幅員を1.82mとする市道として認定された道路の一部であり、西側市道及び南側道路には、いずれも1㎡当たり13万円の路線価が設定されていた。
③ 本件各建物は、昭和49年8月頃に建築され、その建築に当たっては、所定の確認の手続がされていた。
(2)評価通達7及び7-2の定めを本件土地Bについてみると、前記のとおり、本件土地Bは、2棟の本件各建物の敷地の用に供されていたほか、各建物の前面の駐車場の用に供されていたものであり、本件各建物は同じ時期に建築されたものの、建築に当たっての所要の確認手続も別個にされたそれぞれ独立の建物である。前記のとおり、本件相続の開始当時、C荘Ⅰの前面の駐車場は利用されておらず、C荘Ⅱの前面の駐車場のうち2区画をC荘Ⅱの入居者が利用していたものである。また、西側市道からのC荘Ⅱへの出入りに際しては、C荘Ⅰの前面の駐車場とは有蓋の側溝をもって画された南側道路を利用することができたものである。このような状況を踏まえて、X1及び乙は、本件相続税申告の際、C荘Ⅰ敷地及びC荘Ⅱ敷地について、それぞれの前面の駐車場と一体として利用されている一団の土地として、そのうちの主たる地目である宅地から成るものとし、かつ、それぞれ、別個の画地であるとした上で、申告したものと推認される。
これらの事情を前提として、前記に述べたところに照らすと、本件土地Bのうち、C荘Ⅰ敷地とC荘Ⅱ敷地については、それぞれをもって1画地の宅地に当たると評価すべきである。
(3)C荘Ⅰ敷地及びC荘Ⅱ敷地の面積は、いずれも16年情報にいう開発許可面積基準である500㎡に満たず、他の全証拠に照らしても、C荘Ⅰ敷地及びC荘Ⅱ敷地については、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大であるとは認め難く、評価通達24-4の広大地に該当するとはいえない。
4 本件土地Bが2つの画地の宅地とされる場合の同土地の価額の評価について 国は、本件土地Bの価額について、C荘Ⅰ敷地及びC荘Ⅱ敷地の2つの画地の宅地から成ることを前提に、それらの接する南側道路に設定された路線価に基づいて評価をするのに対し、X1らは、C荘Ⅱ敷地は、建築基準法上の接道義務を満たさない土地であることを前提に、西側市道を正面路線として評価されるべきである旨を主張する。
しかし、路線価は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに設定するものとされ、ここでいう路線は、不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいうものとされており、前記に述べた南側道路の本件相続の開始当時の状況に照らすと、上記の国の主張はこれを肯認することができ、X1らの上記主張は採用することができないものというべきである。
そうすると、本件土地BのうちC荘Ⅰ敷地の価額は、3,196万円余であり、C荘Ⅱ敷地の価額は、4,575万円余であると認められる。
四、解説
はじめに 評価通達において広大地の評価方法が初めて明らかにされたのは、平成6年の通達改正においてである。その時には、広大地が路線価地域に所在する場合には、通常の評価額から「公共公益的施設用地となる部分の地積」に対応する額を控除することとされた。この時には、「公共公益的施設用地」とは何かという実質判断が求められた。
ところが、平成16年の評価通達の改正によって、広大地の評価額は、通常の評価額よりも最大65%減額されるという数値が明確にされることになった。しかし、同通達改正は、「広大地」の該当要件を非常に厳しくすることにした。このため、「広大地」と認められれば、通常の評価額に対して最大65%の評価減が認められるが、認められなければ、一切評価減が認められなくなるということで、相続税における土地評価において多大な関心を呼ぶこととなった。
その結果、評価通達上の「広大地」の適用の可否をめぐる争訟事件も多発しており(注1)、本件もその一例である。このような争訟事件では、当該土地の相続税法上の「時価」が幾許であるかでなく、専ら評価上有利な「広大地」に該当するか否かのみ争われている。また、このような「広大地」の評価は、評価通達や同通達に係る国税庁の「情報」によって行われているが故に、「通達」や「情報」の租税法律主義における法的性格も問題となるところである。
本件においては、本件土地A及び本件土地Bについて「広大地」の適用の可否が争われたほか、本件土地Bが2つの賃貸アパートに係る貸家建付地であるところ、当該土地の評価単位(評価上の区分)や当該貸家の賃貸割合等も評価上問題とされている。以下、これらの諸問題について、検討することとする。
1 土地の価額と広大地の評価 (1)相続税法22条は、「……相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によ」ることを定めている。しかし、各財産の「時価」を評価することが困難であることもあって、実務では、評価通達の取扱いに依存することとなる。
ところで、評価通達では、「時価とは、課税時期(〈略〉)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」(評基通1(2))と定めている。この「不特定多数の……通常成立すると認められる価額」は、一般に、客観的交換価額又は客観的交換価値を意味するものとして、学説、判例において広く支持されている(注2)。
しかしながら、「時価」の意義が客観的交換価額を意味するものであることを明らかにするのみでは通達の機能である職務命令としての時価解釈の統一を図ることは困難である。そこで、同通達は、前記規定に続けて、「その価額は、この通達の定めによって評価した価額による」(評基通1(2))と定め、2項以下において各財産について具体的な評価方法を定めている。
(2)評価通達では、土地の価額について、土地を宅地、田、畑等の10種類の地目に区分し、かつ、「一体として利用されている一団の土地」ごとに評価する(評基通7)。本件で問題となっている宅地については、「一画地の宅地(利用の単位となっている一区画の宅地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。」(評基通7-2)こととしている。
また、宅地については、市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式によることとし、それ以外の宅地については倍率方式によることとしている(評基通11)。
本件土地A及び本件土地Bについて適用される路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、奥行価格補正等(評基通15~20-5)の画地調整により計算した金額によって評価する方式をいう(評基通13)。路線価は、宅地の価額が概ね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに設定し、売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長によって定められる(評基通14)。
この路線価方式は、いわゆる評価基準制度の代表的なものであるが、それによって算定される価額は、路線価が標準宅地を想定して定められていること、評価日がその年の1月1日とされていること等からみて、課税時期における当該財産の「時価」というよりも標準的価額を意味することになる。なお、大規模工場用地、広大地等の特別の土地については、通常の路線価方式又は倍率方式のみで「時価」を適正に評価し難いということで、それぞれ特別の評価方法を定めている(評基通22~24の8)。
(3)本件で問題となっている広大地の評価方法は、次のとおりである(評基通24-4(抄))。
「その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条(定義)第12項に規定する開発行為(以下本項において「開発行為」という。)を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(22-2(大規模工場用地)に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるものをいう。)を除く。以下「広大地」という。)の価額は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次により計算した金額によって評価する。
(1)その広大地が路線価地域に所在する場合
その広大地の面する路線の路線価に、15(奥行価格補正)から20-5(容積率の異なる二以上の地域にわたる宅地の評価)までの定めに代わるものとして次の算式により求めた広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額
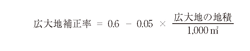 」
」2 評価通達24-4と16年情報等との関係 (1)前記1で述べたように、相続税における土地の「価額」は、相続税法上は「時価」に因るのであるが、「時価」の解釈・把握が困難であること等もあって、実務上、国税庁の評価通達の取扱いによって「時価」評価が行われることになる。しかも、本件で問題となっている広大地については、評価通達上の土地の評価の中でも同通達24-4によって特別の取扱いが定められている。更に、問題となるのは、このような通達の取扱いのみでは理解し難いということで、国税庁では、重要な通達を発遣する場合に、同通達の取扱いを解説する「情報」を発出することがある。本件における16年情報及び17年情報は、その「情報」の一つである。
このような場合に問題となるのは、法律、政省令、通達及び情報の法的性質とそれぞれの関係である。この場合、法律及び政省令は、租税法律主義における法源として機能するのは当然であるが、通達は、行政庁部内の命令手段であって(行政組織法14②参照)、法源ではない。しかし、通達は、行政庁部内を拘束するのみならず、実質的には、納税者の判断を拘束するということで法的機能を有している(注3)。他方、「情報」については、その発出について通達のように法的根拠があるわけではなく、通達の取扱いを理解させるために行政上の便宜から発出されている。それも、通達が行政庁職員を対象としているわけであるから、情報も行政庁職員を対象にしていることになる。
(2)しかしながら、実務においては、法律、政省令、通達又は情報の法律上の区分が正確に行われているわけではなく、実質的には、いずれも税務職員や納税者を拘束することになる。特に、通達と情報との関係については、後者が通達の発遣後に発出されることから、後者が国税庁の最終的な考え方であると誤解されることにもなる。
そのため、本件においても、X1らは、広大地の判定に当たって、むしろ16年情報及び17年情報の考え方を優先して判断すべきである旨主張した。これに対し、本判決は、国税庁が発出する各種情報の趣旨には十分配慮されるべきものであるが、「第一義的には評価通達24-4の定めとの関係が考慮されるべきものといえ、その定める内容を理解するのに際して、16年情報及び17年情報において述べられているところを参照することとなると解するのが相当である。」と判示して、X1らの主張を排斥している。
このような判示は、前述の通達と情報の法的性質の差異に照らし、当然のことではあるが、通達の取扱いと情報との間に差異があるかのような誤解が生じること自体が問題であろう。けだし、両者の間にそのような誤解を生じさせるような余地がなければ、X1らの主張それ自体も成立しないはずであり、裁判所の判断も必要ないはずである。
(3)ところで、16年情報については、本件に関係が強い部分を抜粋して示すと、次のとおりである。
① 広大地に該当するもの、しないものの例示
「(広大地に該当する条件の例示)
・普通住宅地等に所在する土地で、各自治体が定める開発許可を要する面積基準以上のもの(ただし、下記の該当しない条件の例示に該当するものを除く。)。
(注)ミニ開発分譲が多い地域に存する土地については、開発許可を要する面積基準(例え
ば、三大都市圏500㎡)に満たない場合であっても、広大地に該当する場合があることに留意する。
(広大地に該当しない条件の例示)
・既に開発を了しているマンション・ビル等の敷地用地
・現に宅地として有効利用されている建築物等の敷地(例えば、大規模店舗、ファミリーレストラン等)
・原則として容積率300%以上の地域に所在する土地
・公共公益的施設用地の負担がほとんど生じないと認められる土地
(例)道路に面しており、間口が広く、奥行きがそれほどではない土地(道路が二方、三方及び四方にある場合も同様)」
② マンション適地の判定
「なお、評価する土地がマンション適地かどうかの判断基準としては、次のような基準が参考となる(清文社刊「特殊な画地と鑑定評価」土地評価理論研究会(1993年8月)より抜粋)。
イ 近隣地域又は周辺の類似地域に現にマンションが建てられているし、また現在も建築工事中のものが多数ある場合、つまりマンション敷地としての利用に地域が移行しつつある状態で、しかもその移行の程度が相当進んでいる場合
ロ 現実のマンションの建築状況はどうであれ、用途地域・建ぺい率・容積率や当該地方公共団体の開発規制等が厳しくなく、交通、教育、医療等の公的施設や商業地への接近性から判断しても、換言すれば、社会的・経済的・行政的見地から判断して、まさにマンション適地と認められる場合」
(4)また、17年情報については、本件に関係が強い部分を抜粋して示すと、次のとおりである。
① 広大地該当の面積基準
「(面積基準)
原則として、次に掲げる面積以上の宅地については、面積基準の要件を満たすものとする。
① 市街化区域、非線引き都市計画区域(②に該当するものを除く。)
……都市計画法施行令第19条第1項及び第2項に定める面積(※)
※ 1 市街化区域
三大都市圏………………500㎡
それ以外の地域…………1,000㎡
2 非線引き都市計画区域……3,000㎡
(略)」
② マンション適地の判定
「評価しようとする土地が、課税時期においてマンション等の敷地でない場合、マンション等の敷地として使用するのが最有効使用と認められるかどうかの判定については、その土地の周辺地域の標準的使用の状況を参考とすることとなる。しかし、戸建住宅とマンション等が混在する地域(主に容積率200%の地域)は、最有効使用の判定が困難な場合もあることから、このような場合には、周囲の状況や専門家の意見から判断して、明らかにマンション等の敷地に適していると認められる土地を除き、広大地に該当する。
一方、容積率が300%以上の地域内にあり、かつ、開発許可面積基準以上の土地は、戸建住宅の敷地用地として利用するよりもマンション等の敷地として利用する方が最有効使用と判定される場合が多いことから、原則として、広大地に該当しないこととなる。」
3 本件各土地の評価方法 (1)本件においては、本件各土地につき、前記1及び2で述べた評価通達上の広大地の評価の取扱いを適用し、主として、それぞれの土地が広大地に該当するか否かが問題とされた。まず、本件土地Aについては、本判決は、本件土地区画整理事業においては、本件土地Aを含む「中・高層住宅ゾーン」においては1,000㎡以上の換地をすることが計画され、本件地域全体面積の55.7%を占めるマンション敷地の1区画当たりの平均面積が1,032.28㎡であること等を認定し、「そうすると、面積1,227.52㎡である本件土地Aは、本件地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地に当たるとは認め難いというべきであって、その余の点について判断するまでもなく、評価通達24-4の広大地に該当するとはいえないものというべきである。」と判示した。
更に、本判決は、「16年情報にいう開発許可面積基準以上の土地であっても、その属する地域内の他の土地の規模の状況のいかんによっては、広大地に該当しないと判断されることがあることは、17年情報に述べられているとおりである。」と判示し、評価通達24-4と16年情報及び17年情報との関係を明らかにした。
本判決におけるこのような判断は、「広大地」として評価されるかどうかは、全て国税庁が発出する評価通達と16年情報と17年情報によって判断されることからみて、当然の帰結であると考えられる。しかしながら、本件土地Aが実質的にみてマンション適地に該当するから広大地に該当しないという理由のみで、本件土地Aの「時価」が適正に評価されたとは認め難い問題がある。その問題は、後記4で述べる。
(2)次に、本件土地Bについては、主位的には、本件土地Bを一画地の宅地として広大地として評価されるべきか否か、二次的には、本件土地BをC荘Ⅰ敷地とC荘Ⅱ敷地に区分した場合の評価方法が争われた。
本判決は、前述のように、本件土地Bの使用実態からみて、C荘Ⅰ敷地とC荘Ⅱ敷地をそれぞれ一画地の宅地として評価されるべきところ、いずれの敷地も、P市における16年情報にいう開発許可面積基準である500㎡に満たないのであるから、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく広大であるとは認め難いとして、広大地に該当することを否定した。
また、本判決は、C荘Ⅰ敷地及びC荘Ⅱ敷地の価額の評価方法については、評価通達26に定める貸家建付地としての評価方法によるべきであるとして、国側の主張を全面的に容認している。しかし、評価通達26に定める貸家建付地の評価方法には、後記4で述べるような問題を抱えているわけであるから、そのような問題点の是非が検討されるべきであったと考えられる。もっとも、この点については、X1らも何ら主張していない。
4 マンション用地・貸家建付地の評価 (1)本件においては、主として、本件各土地が広大地に該当するか否かが争われたものであるが、広大地に該当しない理由の一つとして、本件各土地がマンション適地であることが指摘されている。その結果、本件土地Aについては、1億9,917万円余で評価されることになったが、これが広大地に該当すると、補正率0.594が適用されるので、1億1,183万円余となる。そして、仮に、本件土地Aが5,000㎡であると、補正率0.35が適用されるので、6,970万円余となる。このことは、広大地に該当すると納税者にとって余りに有利に評価されるのに対し、マンション適地に該当すると余りに不利に評価されることになる。
ところで、マンション用の敷地であっても、評価通達24-4がいう「公共公益的施設用地」に準ずる公益的用地の負担が不可欠であり、かつ、マンション所有者にとっては、その敷地が共有地であるが故に自由に処分できるわけではない。そうであるから、マンション敷地の適切な評価減の導入が求められていたのである(注4)が、それが放置されたままとなっている。
他方、広大地の評価方法については、平成16年の改正によって余りに有利に評価されることとなり、当該土地の通常の売買価額よりも大幅な低評価となることが現出している。このことは、広大地の評価額が相続税法上の「時価」を表わしていないことを意味している。そして、そのことが、本件のような争訟事件を多発させる原因にもなっている。ともあれ、このようなことは、評価通達上の評価の合理性に問題があることを示している。
(2)また、本件土地Bについては、C荘Ⅰ敷地とC荘Ⅱ敷地とに区分され、それぞれ貸家建付地として評価されることとなった。この場合、貸家建付地の評価については、評価通達26によって、次の算式によって評価されることになっている。
| その宅地の自用地としての価額 - その宅地の自用地としての価額 × 借地権割合 × 94(借家権の評価)に定める借家権割合× 賃貸割合 |
このような通達改正は、最高裁平成10年2月26日第一小法廷判決(税資230号851頁)(注6)に起因している。この判決では、アパートの賃貸を開始し、21室中4室入居した段階で相続が開始し、17室が未入居だった事案につき、空室の17室に対応する貸家建付地が自用地として高額に評価された、というものである。このような判断は、前述の賃貸アパートとその敷地の経済的価値の実態に適合しているとは考えられない。そのため、これを起因とする評価通達の改正にも合理性があったとも考えられない。その点では、本件においても、本件土地Bの評価に当たって、評価通達26の不当性が検討されて然るべきであったと考えられる。しかし、X1らは、この点についても主張していないようである。
5 本判決の意義と問題点 (1)以上のように、本件は、P市の土地区画整理事業内に存する本件土地Aと既にP市内に貸家の用に供されていた本件土地Bについて、主として、それぞれ評価通達上の広大地に該当するか否かが争われたものである。このような広大地の評価については、法律の規定ではなく、国税庁部内の職務命令である評価通達と同通達の取扱いを説明する情報によって行われることに特色がある。これは、評価通達24-4に定める広大地の評価額が最高65%評価減されるということで、当該土地の相続税法上の「時価」が幾許であるかということが問題にならず、専ら当該土地が評価通達上の「広大地」に該当するか否かが問題とされるからでもある。換言すると、広大地の該当の有無が争われる当該土地については、広大地に該当しない場合の評価額が、ほとんどの場合、相続税法上の「時価」を上回ることなく、当該「時価」を争う必要がないからである。
しかも、評価通達24-4の評価方法は、広大地に該当すれば寛大な評価減の適用が受けられるが、広大地の該当要件については非常に厳しく定められているため、広大地の該当の有無をめぐって争われることが多く、単に争訟事件になった事案に限らず、申告、課税段階で問題とされることが多い。そのため、税理士等の専門家の関心も高い。したがって、本判決は、実務上注目が高いという点では、意義のある判決である。
(2)結局、本判決は、評価通達24-4と16年情報及び17年情報の取扱いに合理性があるものとして、本件各土地が広大地に該当せずその価額(時価)について、本件各更正等における認定額を適法と認めたものである。しかしながら、前記3及び4で述べたように、評価通達24-4に定める広大地の評価額が相続税法上の「時価」を適正に表わしているものか否かについては、問題を残しているところである。
また、本件土地Aがマンション適地であるとして広大地に該当しない場合にも、マンション用地の評価方法それ自体に前記4で述べたように、その特質に応じた評価減を要するという問題を抱えている。更に、本件土地Bについては、C荘Ⅰ敷地とC荘Ⅱ敷地に区分して貸家建付地として評価する場合に、貸家建付地の評価方法を定めている評価通達26自体に前記4で述べた問題を内包している。しかしながら、本訴においては、そのような問題が検討されることもなかった。そのことは、本判決の意義を低下させることにもなった。
(注1)金沢地裁平成18年4月10日判決(税資256号順号10361)、仙台地裁平成17年3月24日判決(同255号順号9971)、仙台高裁平成19年1月26日判決(同257号順号10617)、東京地裁平成20年8月29日判決(同258号順号11014)、平成21年6月25日裁決(裁決事例集77集383頁)、平成21年12月15日裁決(同78集432頁)、平成23年9月5日裁決(同84集314頁)等参照。
(注2)金子宏『租税法 第17版』(弘文堂 平成24年)551頁、東京高裁平成7年12月13日判決(行裁例集46巻12号1143頁)等参照。
(注3)詳細は、品川芳宣『租税法律主義と税務通達』(ぎょうせい 平成16年)34頁以下参照。
(注4)品川芳宣・緑川正博『相続税財産評価の論点~財産評価の理論と実務の疑問を糾す~』(ぎょうせい 平成9年)107頁等参照。
(注5)品川芳宣・緑川正博『相続税財産評価の理論と実践』(ぎょうせい 平成17年)85頁等参照。
(注6)品川芳宣『重要租税判決の実務研究』(大蔵財務協会 平成17年)555頁参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















