コラム2013年02月25日 【SCOPE】 日本版ESOPの会計処理は追加負担の可否がポイント(2013年2月25日号・№488)
信託期間の長さで異なる方向
日本版ESOPの会計処理は追加負担の可否がポイント
企業会計基準委員会(ASBJ)は実務対応専門委員会を設置し、実務対応報告を策定すべく日本版ESOP制度の会計処理について検討を行っている。会計処理のうち、問題となっているのは受給権を付与された従業員に自社株式を給付するスキーム(退職時給付型および在職時給付型)だ。同委員会では、同スキームについては信託の追加負担の可能性があるか否かで会計処理を変える方向で検討を進めている。追加負担が考えられる長期スキームであれば、従業員へのポイント付与時の株価で費用計上する可能性がある。この場合、影響を受ける企業も少なからずありそうだ。
信託の追加負担の可能性があるか否かで判断
企業会計基準委員会では、「従業員持株会に自社株式を譲渡するスキーム」と「受給権を付与された従業員に自社株式を給付するスキーム(退職時給付型および在職時給付型)」に分けて検討を行っている。
個別と連結上の取扱いは現行の実務を考慮 個別財務諸表上の取扱いについては、現行の実務を考慮し、「連結財務諸表における特別目的会社の取扱い等に関する論点整理」の脚注10の要件を満たすものであれば、総額法を適用する方向となっている。この場合、信託財産が個別財務諸表に取り込まれているため、連結財務諸表上、子会社の判定は不要となる。これは、従業員持株会型だけでなく、退職時給付型および在職時給付型についても同様の方向で検討が進められている(本誌487号11頁参照)。
以上のように、個別財務諸表と連結財務諸表上の取扱いに関しては大きな混乱とはなりそうにないが、一番の問題となるのは受給権を付与された従業員に自社株式を給付するスキーム(退職時給付型および在職時給付型)の会計処理(自己株式処分差額の認識時点)である。
同スキームのうち、退職時給付型とは、自社の株式を信託に予め取得させ、企業の規程に従って従業員にポイントが付与され、退職時には累積ポイントに対応する自社株式を信託から給付してもらう制度のことである。また、在職時給付型とは退職時給付型とほぼ同様の仕組みだが、5年程度の信託期間終了時に自社株式を信託から給付してもらう制度。大きな違いは信託期間の長さといえる。
ただ、企業会計基準委員会では、退職時給付型と在職時給付型という切り分けではなく、信託の追加負担の可能性があるかどうかで会計処理の取扱いを変更することを想定しているようだ。
在職時給付型は信託拠出時の株価で算定 スキーム開始後の追加負担の可能性が低いスキームについては、スキーム開始時に契約期間における費用総額が概ね確定していることから、あえてスキーム開始後の株価の変動を費用計上額に反映させる必要はないと判断。「株式給付規程設定時の株価を基礎とする方法」(企業が信託に拠出した金額をもって費用総額とし、付与ポイント数により配分する)によることになる方向だ(表の案a参照)。5年程度の比較的短期のスキームである在職時給付型が主な対象になる模様だ。
退職時給付型はポイント付与時の株価か? 一方、追加負担の可能性が低くないと思われるスキームについては、スキーム開始時に契約期間における費用総額が確定されないことになるため、株式給付規程設定時の株価を基礎に費用配分を行うことは適切ではないと判断。ポイントの付与を従業員が提供する労働サービスの都度、費用計上するように、「ポイント付与時の株価を基礎とする方法」(毎期洗替を行わない方法)をベースに検討が進められている(表の案b参照)。たとえば、10年超の長期スキームである退職時給付型が主な対象となる模様だ。
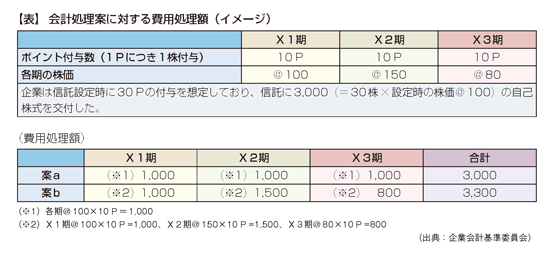
日本版ESOPの会計処理は追加負担の可否がポイント
企業会計基準委員会(ASBJ)は実務対応専門委員会を設置し、実務対応報告を策定すべく日本版ESOP制度の会計処理について検討を行っている。会計処理のうち、問題となっているのは受給権を付与された従業員に自社株式を給付するスキーム(退職時給付型および在職時給付型)だ。同委員会では、同スキームについては信託の追加負担の可能性があるか否かで会計処理を変える方向で検討を進めている。追加負担が考えられる長期スキームであれば、従業員へのポイント付与時の株価で費用計上する可能性がある。この場合、影響を受ける企業も少なからずありそうだ。
信託の追加負担の可能性があるか否かで判断
企業会計基準委員会では、「従業員持株会に自社株式を譲渡するスキーム」と「受給権を付与された従業員に自社株式を給付するスキーム(退職時給付型および在職時給付型)」に分けて検討を行っている。
個別と連結上の取扱いは現行の実務を考慮 個別財務諸表上の取扱いについては、現行の実務を考慮し、「連結財務諸表における特別目的会社の取扱い等に関する論点整理」の脚注10の要件を満たすものであれば、総額法を適用する方向となっている。この場合、信託財産が個別財務諸表に取り込まれているため、連結財務諸表上、子会社の判定は不要となる。これは、従業員持株会型だけでなく、退職時給付型および在職時給付型についても同様の方向で検討が進められている(本誌487号11頁参照)。
| 「連結財務諸表における特別目的会社の取扱い等に関する論点整理」脚注10(抜粋) 委託者以外の第三者が当初受益者となるもの(いわゆる他益信託)のうち、受益者が信託行為に定められた要件を満たすまで受益権を有しない場合は、受益者の定めのない信託(いわゆる目的信託)と類似している。目的信託については、「委託者がいつでも信託を終了できるなど、通常の信託とは異なるため、原則として、委託者の財産として処理することが適当であると考えられる。ただし、信託契約の内容等からみて、委託者に信託財産の経済的効果が帰属しないことが明らかであると認められる場合には、もはや委託者の財産ではないものとして処理する(実務対応報告23号Q6のA)。」とされている。これらを踏まえれば、他の会計基準等において定められている場合を除き、委託者が信託の変更をする権限を有しており、委託者である当該企業に信託財産の経済的効果が帰属しないことが明らかであるとは認められない場合には、会計上、委託者である当該企業の財産として処理することが適当であると考えられる。また、この場合には、いわゆる総額法による処理と同様となり、自益信託と同様に、改めて子会社や関連会社に該当するか否かについて判定する必要はないものと考えられる。 |
以上のように、個別財務諸表と連結財務諸表上の取扱いに関しては大きな混乱とはなりそうにないが、一番の問題となるのは受給権を付与された従業員に自社株式を給付するスキーム(退職時給付型および在職時給付型)の会計処理(自己株式処分差額の認識時点)である。
同スキームのうち、退職時給付型とは、自社の株式を信託に予め取得させ、企業の規程に従って従業員にポイントが付与され、退職時には累積ポイントに対応する自社株式を信託から給付してもらう制度のことである。また、在職時給付型とは退職時給付型とほぼ同様の仕組みだが、5年程度の信託期間終了時に自社株式を信託から給付してもらう制度。大きな違いは信託期間の長さといえる。
ただ、企業会計基準委員会では、退職時給付型と在職時給付型という切り分けではなく、信託の追加負担の可能性があるかどうかで会計処理の取扱いを変更することを想定しているようだ。
在職時給付型は信託拠出時の株価で算定 スキーム開始後の追加負担の可能性が低いスキームについては、スキーム開始時に契約期間における費用総額が概ね確定していることから、あえてスキーム開始後の株価の変動を費用計上額に反映させる必要はないと判断。「株式給付規程設定時の株価を基礎とする方法」(企業が信託に拠出した金額をもって費用総額とし、付与ポイント数により配分する)によることになる方向だ(表の案a参照)。5年程度の比較的短期のスキームである在職時給付型が主な対象になる模様だ。
退職時給付型はポイント付与時の株価か? 一方、追加負担の可能性が低くないと思われるスキームについては、スキーム開始時に契約期間における費用総額が確定されないことになるため、株式給付規程設定時の株価を基礎に費用配分を行うことは適切ではないと判断。ポイントの付与を従業員が提供する労働サービスの都度、費用計上するように、「ポイント付与時の株価を基礎とする方法」(毎期洗替を行わない方法)をベースに検討が進められている(表の案b参照)。たとえば、10年超の長期スキームである退職時給付型が主な対象となる模様だ。
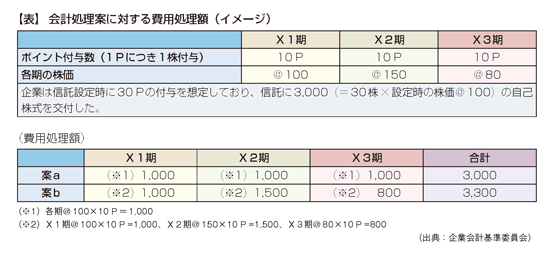
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























