解説記事2013年05月27日 【法令等解説】 「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」について(2013年5月27日号・№500)
法令等解説
「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」について
金融庁企業開示課企業会計調整官 野村昭文
Ⅰ はじめに
企業会計審議会(会長 安藤英義 専修大学教授)は、重要な虚偽の表示の原因となる不正(以下単に「不正」という。)に対応した監査手続等の検討を行い、監査基準等の見直しの審議を行ってきたが、2013年3月26日に開催した同審議会の総会において、「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」をとりまとめ、公表した。
我が国における近時の会計不正事案において、結果として公認会計士監査が有効に機能しておらず、より実効的な監査手続を求める指摘があった。こうしたことから、我が国の監査をより実効性のあるものとしていくとの観点から見直しを行ったものであり、監査における不正リスク対応基準(以下「不正リスク対応基準」という。)は、企業の不正による重要な虚偽表示のリスクにより有効に対応することにより、我が国資本市場の透明性、公正性を確保することを最終目的に、不正リスクに対応するために特に監査人が行うべき監査手続等を一括して整理し、現行の監査基準等からは独立した基準として設定されたものである。
本稿では、不正リスク対応基準の設定に係る企業会計審議会における審議状況や基準の概要について紹介する。
なお、文中意見にわたる部分は、私見であることをお断りしておく。
(注)意見書については、金融庁のホームページ(http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130326-3.html)に掲載されているので参照されたい。
Ⅱ 不正リスク対応基準の設定について
1 審議の背景・経過
(1)不正リスク対応基準の設定 近時、オリンパス株式会社(以下「オリンパス社」という。)、大王製紙株式会社の事案のほか、証券取引等監視委員会より、いわゆる「循環取引」などによる開示書類の虚偽記載に対して、課徴金納付命令勧告が年間10数件行われるなど、数々の会計不正事案が発生している。
特に、オリンパス社の事案は、国内のみならず海外の投資家から我が国市場の透明性・公正性に対し、疑念を持たれたとされた事案であり、適切な対応が強く求められたところである。
オリンパス社をはじめとする近時の不適切な事例に対しては、現行の監査基準では、不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況等があるような場合に、どのように対応すべきかが必ずしも明確でなく、実務にバラツキが生じているという指摘や、そうした状況がある時には、監査手続をより慎重に行うべきであるとの指摘があった。
こうしたことから、監査をめぐる内外の動向を踏まえ、不正リスクに対応した監査手続を明確化するとともに、一定の場合には監査手続をより慎重に実施することを求めるとの観点から、不正リスク対応基準を設けることとしたものである。
(2)審議の経過 企業会計審議会における議論は、2012年5月から監査部会(部会長脇田良一名古屋経済大学大学院教授)において審議が進められ、同年12月に公開草案として公表し、広く各界の意見を求めた。公開草案に対しては、11団体13個人より、主として実務上の観点から明確化や修正を求めるコメントが寄せられた。同審議会では、寄せられた意見を参考に更に審議を行い、公開草案の一部を修正して、意見書としてとりまとめたものである。
なお、監査部会で審議された「取引先企業の監査人との連携」については、被監査企業と取引先企業との通謀が疑われる場合の一つの監査手続であると考えられたが、解決すべき論点が多いことから、今回の基準には含めずに、いわゆる「循環取引」等への対応として、監査部会において継続して検討を行うこととなった。
2 不正リスク対応基準の基本的な考え方・位置づけ
(1)基本的な考え方
本基準は、以下の基本的な考え方に基づいて策定されている。
① 財務諸表の虚偽の表示は、不正又は誤謬から生じるが、本基準においては、監査人が財務諸表監査において対象とする重要な虚偽の表示の原因となる不正について取り扱う。したがって、誤謬や重要な虚偽の表示とは関係しない不正は対象としていない。なお、不正には、経営者による不正だけでなく、従業員不正も含まれる。
② 財務諸表監査の目的を変えるものではなく、不正摘発自体を意図していない。
③ すべての財務諸表監査において画一的に不正リスクに対応するための追加的な監査手続の実施を求めることを意図しているものではなく、被監査企業に不正による財務諸表に重要な虚偽の表示を示唆するような状況がないような場合や監査人において既に本基準に規定されているような監査手続等を実施している場合には、現行の監査基準に基づく監査の実務と基本的には変わらない。したがって、監査人は、個々の監査の状況に応じて、対応を検討する必要がある。
④ 経営者の作成した財務諸表に重要な虚偽の表示がないことについて、職業的専門家としての正当な注意を払って監査を行った場合には、監査人としてはその責任を果たしたことになる。なお、個々の監査の状況に応じて、職業的専門家としての正当な注意を払ったかどうかが重要であり、本基準等に形式的に従ったことをもって常に免責になるものではないことに留意が必要である。
(2)位置付け
① 不正リスク対応基準の適用 本基準は、すべての監査において実施されるのではなく、主として、財務諸表及び監査報告について広範な利用者が存在する金融商品取引法に基づいて開示を行っている企業(非上場企業のうち資本金5億円未満又は売上高10億円未満かつ負債総額200億円未満の企業は除く。以下「上場企業等」という。)に対する監査において実施する。なお、本基準の金融商品取引法上の適用範囲は財務諸表等の監査証明に関する内閣府令において明確化される予定であり、同規則において明示的に求められていない限り、本基準に準拠することを要しない。例えば、特定有価証券のみの発行者としての企業に対する監査は、適用範囲に含まれないこととなる。
一方で、金融商品取引法以外の法令に基づく監査においては、準拠する監査の基準が明示されていないと考えられ、例えば、会社法に基づく監査のみでは本基準は適用されない。ただし、連結財務諸表の監査において、金融商品取引法に基づく監査と会社法に基づく監査の両方が求められている場合には、両者の監査は区別することなく実施されることから、本基準は適用される。さらに、グループ監査の対象となる在外子会社等についても本基準が適用されることとなる。
② 不正リスク対応基準の位置付け 監査基準は、公認会計士監査のすべてに共通するものであるのに対し、本基準は、上場企業等に対する監査に限定して実施することなどの理由から、現行の監査基準、監査に関する品質管理基準(以下「品質管理基準」という。)からは独立した基準としている。
ただし、本基準は、上場企業等の不正リスクへの対応に関し監査基準及び品質管理基準に追加して準拠すべき基準であり、法令により準拠が求められている場合は、監査基準及び品質管理基準とともに、一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成し、監査基準及び品質管理基準並びに日本公認会計士協会の作成する実務の指針と一体となって適用される。
なお、本基準に準拠することを要しない企業の監査報告書上、「一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。」との文言に「ただし、監査における不正リスク対応基準を除く。」といったただし書きを付す必要はないことに留意が必要である。
③ 不正リスク対応基準と中間監査及び四半期レビューとの関係
本基準は、年度監査のみではなく、中間監査基準上不正に関する実証手続が定められている中間監査にも準用される。
また、四半期レビューについては、年度監査と同様の合理的保証を得ることを目的としているものではないことから、本基準は四半期レビューには適用されない。
なお、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令において、年度監査及び中間監査に適用されることが明確化される予定である。
3 不正リスク対応基準の主な内容
(1)不正リスク対応基準の構成 本基準は、①職業的懐疑心の強調、②不正リスクに対応した監査の実施、及び③不正リスクに対応した監査事務所の品質管理の三つから構成されている。
(2)職業的懐疑心の強調 現行の監査基準においては、監査人は、監査の実施に際しては、「職業的専門家としての正当な注意を払い、懐疑心を保持して監査を行」うことが求められるとともに、「職業的専門家としての懐疑心をもって、不正及び誤謬により財務諸表に重要な虚偽の表示がもたらされる可能性に関して評価を行い、その結果を監査計画に反映」しなければならないとされている。
監査人は、不正リスクに対応するためには、誤謬による重要な虚偽表示のリスクに比し、より注意深く、批判的な姿勢で臨むことが必要であり、監査人としての職業的懐疑心の保持及びその発揮が特に重要であると考えられる。このため、本基準においては、「職業的懐疑心の強調」として冒頭に掲記し、不正リスクの評価、不正リスクに対応する監査手続の実施及び監査証拠の評価の各段階において、職業的懐疑心を発揮することを求めている。さらに、監査手続を実施した結果、不正による重要な虚偽の表示の疑義に該当するかどうかを判断する場合や、不正による重要な虚偽の表示の疑義に該当すると判断した場合には、職業的懐疑心を高めて監査手続を実施することを求めており、不正リスクの程度に応じて、職業的懐疑心を保持から発揮へ、さらに職業的懐疑心を高めることが必要になる。
職業的懐疑心の保持や発揮が適切であったか否かは、具体的な状況において監査人の行った監査手続の内容により判断されるものと考えられることから、監査人は本基準に基づいて監査の各段階で必要とされる職業的懐疑心を保持又は発揮し、具体的な監査手続を実施することが求められる。
なお、本基準における職業的懐疑心の考え方は、これまでの監査基準で採られている、監査を実施するに際して、経営者が誠実であるとも不誠実であるとも想定しないという中立的な観点を変更するものではないことに留意が必要であるが、監査実施の過程において、重要な虚偽の表示を示唆するような状況があったような場合にも中立的な観点を維持することを求めているものでないことは言うまでもない。
(3)不正リスクに対応した監査の実施 本基準においては、監査の各段階における不正リスクに対応した監査手続等を規定している([図表]参照・図表の点線で囲まれた部分が現行監査基準に基づくリスクモデルが改訂等になっている部分である。)。
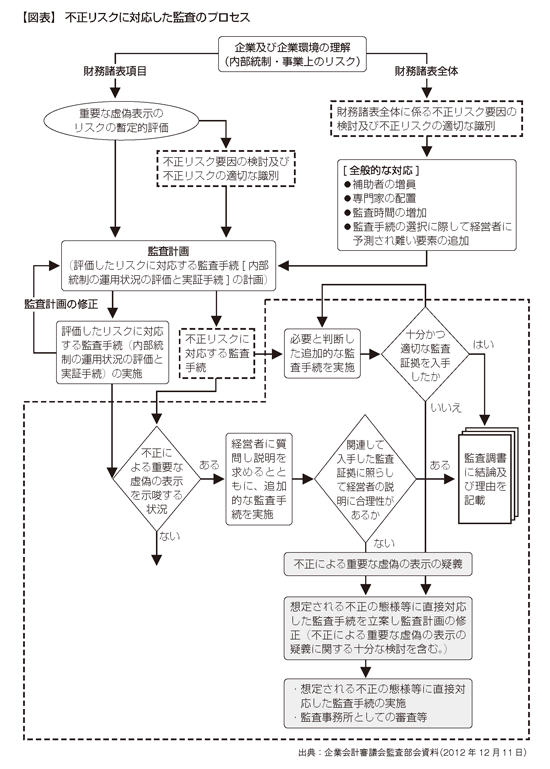
① 不正リスクに対応した監査計画の策定
本基準においては、現行の重要な虚偽表示のリスクの検討に際し、不正リスク要因の検討や不正リスクを把握するために必要な手続を規定した。監査人は、入手した情報が不正リスク要因の存在を示しているかどうかを検討し、それらを財務諸表全体及び財務諸表項目の不正リスクの識別において考慮しなければならないこととした。その上で、監査人は、識別・評価した不正リスクに応じた監査計画を策定することが求められる。
不正リスク要因とは、不正を実行する動機やプレッシャーの存在を示し、不正を実行する機会を与え、又は、不正を実行する際にそれを正当化する事象や状況を指し、典型的な不正リスク要因は付録1に例示されている。
また、監査人は、財務諸表全体に関連する不正リスクが識別された場合には、実施する監査手続の種類、時期及び範囲の選択に当たり、評価した不正リスクに応じて、監査手続の種類、時期若しくは範囲の変更、往査先の選択方法の変更又は予告なしに往査することなど、企業が想定しない要素を監査計画に組み込むことが必要になる。特に、不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合において、その状況によっては、修正する監査計画に企業が想定しない要素を組み込むことが有効なことがあると考えられる。
② 不正リスクに対応して実施する確認 監査人が、不正リスクに対応する監査手続として、照会事項の内容の正否にかかわらず回答を求める積極的確認を実施する場合には、回答がない又は回答が不十分なときには、代替的な手続により十分かつ適切な監査証拠を入手できるか否か慎重に判断しなければならないことを明確にした。特に、不正リスクが存在する場合の確認状に回答が得られない又は回答が不十分な場合(例えば、担保差入その他引出制限のある資産の状況等が未記入等)、すべての記載事項についての回答を入手できるよう留意し、代替的な手続に移行する場合には慎重に判断する必要がある。
③ 不正リスクに関連する監査証拠 監査人は、不正リスクを識別している監査要点に対しては、当該監査要点について不正リスクを識別していない場合に比べ、より適合性が高く、より証明力が強く、又はより多くの監査証拠を入手しなければならないこと、十分かつ適切な監査証拠を入手していないと判断した場合は、追加的な監査手続を実施しなければならないことを明確にした。
④ 不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況 監査実施の過程において、付録2に例示されているような「不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況」を識別した場合には、「不正による重要な虚偽の表示の疑義」が存在していないかどうかを判断するために、適切な階層の経営者に質問し説明を求めるとともに、追加的な監査手続を実施しなければならないこととしている。
付録2に例示されている状況は、国際監査基準における付録の記載や我が国における会計不正事案を踏まえ、現行の監査基準に基づく現在の実務においても、監査人としては、重要な虚偽の表示の可能性が高いものとして、特に注意すべき状況を念頭に記載されている。
なお、付録2はあくまで例示であり、監査実施の過程においてそのような状況に遭遇した場合に、「不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況」として追加的な監査手続を求めているものである。したがって、付録2に記載されている状況の有無について網羅的に監査証拠をもって確かめなければならないということではなく、また、付録2をチェック・リストとして扱うことを意図したものではない。
⑤ 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合の監査手続 不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況について、関連して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明に合理性がないと判断した場合や、識別した不正リスクに対応して追加的な監査手続を実施してもなお十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合には、不正による重要な虚偽の表示の疑いがより強くなることから、これを不正による重要な虚偽の表示の疑義と扱わなければならないものとした。なお、追加的な監査手続の実施の結果、不正による重要な虚偽の表示の疑義がないと判断した場合には、その旨と理由を監査調書に記載しなければならない。
不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合には、想定される不正の態様等に直接対応した監査手続を立案し監査計画を修正するとともに、修正した監査計画に従って監査手続を実施しなければならないこととなる。
⑥ 不正リスクに関連する審査 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合には、監査事務所として適切な監査意見を形成するため、審査についてもより慎重な対応が求められる。したがって、監査事務所の方針と手続に従って、適切な審査の担当者による審査が完了するまでは意見の表明ができないことを明記した。
⑦ 監査役等との連携 監査人は、不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合や経営者の関与が疑われる不正を発見した場合には、取締役の職務の執行を監査する監査役や監査委員会と適切に協議する等、連携を図ることが有効であり、監査の各段階において、監査役等との連携を図らなければならないことを明記した。
⑧ 監査調書 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合には、監査人が当該疑義に対して実施した監査手続の内容とその結果、また、監査人としての結論及びその際になされた重要な判断は、監査意見に重要な意味を有していると考えられることから、そうした内容については、監査調書に記載しなければならないことを明記した。
4 不正リスクに対応した監査事務所の品質管理 本基準においては、監査実施の各段階における不正リスクに対応した監査手続を実施するための監査事務所としての品質管理を規定している。
ただし、不正リスク対応基準における品質管理に係る規定は、現在各監査事務所で行っている品質管理のシステムに加えて、新たな品質管理のシステムの導入を求めているものではなく、監査事務所が整備すべき品質管理のシステムにおいて、不正リスクに対応する観点から特に留意すべき点を明記したものである。
また、整備及び運用が求められる監査事務所の方針と手続は、監査事務所の規模及び組織、当該監査業務の内容等により異なることから、すべての監査事務所において画一的な品質管理の方針と手続が求められているものではないことは言うまでもない。
① 不正リスクに対応した品質管理のシステムの整備及び運用 全般的な規定として、監査事務所に、不正リスクに適切に対応できるよう、監査業務の各段階における品質管理のシステムを整備及び運用するとともに、品質管理システムの監視を求めることとした。
② 監査契約の新規の締結及び更新 監査契約の新規の締結及び更新に関する方針及び手続に、不正リスクを考慮して監査契約の締結及び更新に伴うリスクを評価することを含めるとともに、監査契約の新規の締結及び更新の判断に際して、監査事務所としての検討を求めている。なお、更新時においては、監査チームだけでなく監査事務所としての検討を行うか否かについては、当該企業のリスクの程度に応じて判断することに留意する。
③ 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断された場合の審査 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断された場合には、通常の審査担当者による審査に比べて、監査事務所としてより慎重な審査が行われる必要がある。このため、当該監査業務の監査意見が適切に形成されるよう、当該疑義に対応する十分かつ適切な経験や職位等の資格を有する審査の担当者(適格者で構成される会議体を含む)を監査事務所として選任することを、審査に関する方針及び手続に定めなければならないこととした。
この監査事務所としての審査は、監査事務所の規模や組織等により、名称や体制等は異なることとなると考えられるが、例えば、大規模監査事務所の場合には、監査事務所本部における審査など、小規模事務所の場合には、社員全員による社員会における審査などが該当するものと考えられる。
④ 監査事務所間の引継 監査事務所交代時において、前任監査事務所は、後任の監査事務所に対して、不正リスクへの対応状況を含め、企業との間の重要な意見の相違等の監査上の重要な事項を伝達するとともに、後任監査事務所から要請のあったそれらに関連する監査調書の閲覧に応じるように、引継に関する方針と手続に定めなければならないこととした。
また、後任監査事務所は、前任監査事務所に対して、監査事務所の交代理由のほか、不正リスクへの対応状況、企業との間の重要な意見の相違等の監査上の重要な事項について質問するように、引継に関する方針及び手続に定めなければならないこととした。
Ⅲ 実施時期等
不正リスク対応基準は、平成26年3月決算に係る財務諸表の監査から実施する。なお、不正リスク対応基準中、不正リスクに対応した監査事務所の品質管理については、平成25年10月1日から実施する。
不正リスク対応基準は、中間監査に準用し、平成26年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施する。
Ⅳ 終わりに
不正に関しては、財務諸表作成者である経営者に責任があるところであり、経営者による組織ぐるみの不正や循環取引などの第三者と通謀した不正のように、不正によっては、公認会計士監査のみによって発見することが困難なケースもあると考えられ、対応としては、公認会計士監査における監査手続の充実とともに、企業におけるコーポレート・ガバナンスのあり方の検討などを含め、幅広い観点からの取組みが重要である。
そうした観点から、今般の不正リスク対応基準においては、公認会計士監査が、監査役など企業における監視・監督を担う機能と連携して対応することが有効であり、基準上も多く規定が設けられたところである。
不正リスクへの対応が国際的にも継続的な見直しが行われているところである。本基準の実施を契機に、監査人が不正リスクに対しより適切に対応するとともに、財務諸表作成者などの関係者においても従前にも増して不正リスクへの対応を行うことを通じ、不正抑止につながることが期待される。
「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」について
金融庁企業開示課企業会計調整官 野村昭文
Ⅰ はじめに
企業会計審議会(会長 安藤英義 専修大学教授)は、重要な虚偽の表示の原因となる不正(以下単に「不正」という。)に対応した監査手続等の検討を行い、監査基準等の見直しの審議を行ってきたが、2013年3月26日に開催した同審議会の総会において、「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」をとりまとめ、公表した。
我が国における近時の会計不正事案において、結果として公認会計士監査が有効に機能しておらず、より実効的な監査手続を求める指摘があった。こうしたことから、我が国の監査をより実効性のあるものとしていくとの観点から見直しを行ったものであり、監査における不正リスク対応基準(以下「不正リスク対応基準」という。)は、企業の不正による重要な虚偽表示のリスクにより有効に対応することにより、我が国資本市場の透明性、公正性を確保することを最終目的に、不正リスクに対応するために特に監査人が行うべき監査手続等を一括して整理し、現行の監査基準等からは独立した基準として設定されたものである。
本稿では、不正リスク対応基準の設定に係る企業会計審議会における審議状況や基準の概要について紹介する。
なお、文中意見にわたる部分は、私見であることをお断りしておく。
(注)意見書については、金融庁のホームページ(http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130326-3.html)に掲載されているので参照されたい。
Ⅱ 不正リスク対応基準の設定について
1 審議の背景・経過
(1)不正リスク対応基準の設定 近時、オリンパス株式会社(以下「オリンパス社」という。)、大王製紙株式会社の事案のほか、証券取引等監視委員会より、いわゆる「循環取引」などによる開示書類の虚偽記載に対して、課徴金納付命令勧告が年間10数件行われるなど、数々の会計不正事案が発生している。
特に、オリンパス社の事案は、国内のみならず海外の投資家から我が国市場の透明性・公正性に対し、疑念を持たれたとされた事案であり、適切な対応が強く求められたところである。
オリンパス社をはじめとする近時の不適切な事例に対しては、現行の監査基準では、不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況等があるような場合に、どのように対応すべきかが必ずしも明確でなく、実務にバラツキが生じているという指摘や、そうした状況がある時には、監査手続をより慎重に行うべきであるとの指摘があった。
こうしたことから、監査をめぐる内外の動向を踏まえ、不正リスクに対応した監査手続を明確化するとともに、一定の場合には監査手続をより慎重に実施することを求めるとの観点から、不正リスク対応基準を設けることとしたものである。
(2)審議の経過 企業会計審議会における議論は、2012年5月から監査部会(部会長脇田良一名古屋経済大学大学院教授)において審議が進められ、同年12月に公開草案として公表し、広く各界の意見を求めた。公開草案に対しては、11団体13個人より、主として実務上の観点から明確化や修正を求めるコメントが寄せられた。同審議会では、寄せられた意見を参考に更に審議を行い、公開草案の一部を修正して、意見書としてとりまとめたものである。
なお、監査部会で審議された「取引先企業の監査人との連携」については、被監査企業と取引先企業との通謀が疑われる場合の一つの監査手続であると考えられたが、解決すべき論点が多いことから、今回の基準には含めずに、いわゆる「循環取引」等への対応として、監査部会において継続して検討を行うこととなった。
2 不正リスク対応基準の基本的な考え方・位置づけ
(1)基本的な考え方
本基準は、以下の基本的な考え方に基づいて策定されている。
① 財務諸表の虚偽の表示は、不正又は誤謬から生じるが、本基準においては、監査人が財務諸表監査において対象とする重要な虚偽の表示の原因となる不正について取り扱う。したがって、誤謬や重要な虚偽の表示とは関係しない不正は対象としていない。なお、不正には、経営者による不正だけでなく、従業員不正も含まれる。
② 財務諸表監査の目的を変えるものではなく、不正摘発自体を意図していない。
③ すべての財務諸表監査において画一的に不正リスクに対応するための追加的な監査手続の実施を求めることを意図しているものではなく、被監査企業に不正による財務諸表に重要な虚偽の表示を示唆するような状況がないような場合や監査人において既に本基準に規定されているような監査手続等を実施している場合には、現行の監査基準に基づく監査の実務と基本的には変わらない。したがって、監査人は、個々の監査の状況に応じて、対応を検討する必要がある。
④ 経営者の作成した財務諸表に重要な虚偽の表示がないことについて、職業的専門家としての正当な注意を払って監査を行った場合には、監査人としてはその責任を果たしたことになる。なお、個々の監査の状況に応じて、職業的専門家としての正当な注意を払ったかどうかが重要であり、本基準等に形式的に従ったことをもって常に免責になるものではないことに留意が必要である。
(2)位置付け
① 不正リスク対応基準の適用 本基準は、すべての監査において実施されるのではなく、主として、財務諸表及び監査報告について広範な利用者が存在する金融商品取引法に基づいて開示を行っている企業(非上場企業のうち資本金5億円未満又は売上高10億円未満かつ負債総額200億円未満の企業は除く。以下「上場企業等」という。)に対する監査において実施する。なお、本基準の金融商品取引法上の適用範囲は財務諸表等の監査証明に関する内閣府令において明確化される予定であり、同規則において明示的に求められていない限り、本基準に準拠することを要しない。例えば、特定有価証券のみの発行者としての企業に対する監査は、適用範囲に含まれないこととなる。
一方で、金融商品取引法以外の法令に基づく監査においては、準拠する監査の基準が明示されていないと考えられ、例えば、会社法に基づく監査のみでは本基準は適用されない。ただし、連結財務諸表の監査において、金融商品取引法に基づく監査と会社法に基づく監査の両方が求められている場合には、両者の監査は区別することなく実施されることから、本基準は適用される。さらに、グループ監査の対象となる在外子会社等についても本基準が適用されることとなる。
② 不正リスク対応基準の位置付け 監査基準は、公認会計士監査のすべてに共通するものであるのに対し、本基準は、上場企業等に対する監査に限定して実施することなどの理由から、現行の監査基準、監査に関する品質管理基準(以下「品質管理基準」という。)からは独立した基準としている。
ただし、本基準は、上場企業等の不正リスクへの対応に関し監査基準及び品質管理基準に追加して準拠すべき基準であり、法令により準拠が求められている場合は、監査基準及び品質管理基準とともに、一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成し、監査基準及び品質管理基準並びに日本公認会計士協会の作成する実務の指針と一体となって適用される。
なお、本基準に準拠することを要しない企業の監査報告書上、「一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。」との文言に「ただし、監査における不正リスク対応基準を除く。」といったただし書きを付す必要はないことに留意が必要である。
③ 不正リスク対応基準と中間監査及び四半期レビューとの関係
本基準は、年度監査のみではなく、中間監査基準上不正に関する実証手続が定められている中間監査にも準用される。
また、四半期レビューについては、年度監査と同様の合理的保証を得ることを目的としているものではないことから、本基準は四半期レビューには適用されない。
なお、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令において、年度監査及び中間監査に適用されることが明確化される予定である。
3 不正リスク対応基準の主な内容
(1)不正リスク対応基準の構成 本基準は、①職業的懐疑心の強調、②不正リスクに対応した監査の実施、及び③不正リスクに対応した監査事務所の品質管理の三つから構成されている。
(2)職業的懐疑心の強調 現行の監査基準においては、監査人は、監査の実施に際しては、「職業的専門家としての正当な注意を払い、懐疑心を保持して監査を行」うことが求められるとともに、「職業的専門家としての懐疑心をもって、不正及び誤謬により財務諸表に重要な虚偽の表示がもたらされる可能性に関して評価を行い、その結果を監査計画に反映」しなければならないとされている。
監査人は、不正リスクに対応するためには、誤謬による重要な虚偽表示のリスクに比し、より注意深く、批判的な姿勢で臨むことが必要であり、監査人としての職業的懐疑心の保持及びその発揮が特に重要であると考えられる。このため、本基準においては、「職業的懐疑心の強調」として冒頭に掲記し、不正リスクの評価、不正リスクに対応する監査手続の実施及び監査証拠の評価の各段階において、職業的懐疑心を発揮することを求めている。さらに、監査手続を実施した結果、不正による重要な虚偽の表示の疑義に該当するかどうかを判断する場合や、不正による重要な虚偽の表示の疑義に該当すると判断した場合には、職業的懐疑心を高めて監査手続を実施することを求めており、不正リスクの程度に応じて、職業的懐疑心を保持から発揮へ、さらに職業的懐疑心を高めることが必要になる。
職業的懐疑心の保持や発揮が適切であったか否かは、具体的な状況において監査人の行った監査手続の内容により判断されるものと考えられることから、監査人は本基準に基づいて監査の各段階で必要とされる職業的懐疑心を保持又は発揮し、具体的な監査手続を実施することが求められる。
なお、本基準における職業的懐疑心の考え方は、これまでの監査基準で採られている、監査を実施するに際して、経営者が誠実であるとも不誠実であるとも想定しないという中立的な観点を変更するものではないことに留意が必要であるが、監査実施の過程において、重要な虚偽の表示を示唆するような状況があったような場合にも中立的な観点を維持することを求めているものでないことは言うまでもない。
(3)不正リスクに対応した監査の実施 本基準においては、監査の各段階における不正リスクに対応した監査手続等を規定している([図表]参照・図表の点線で囲まれた部分が現行監査基準に基づくリスクモデルが改訂等になっている部分である。)。
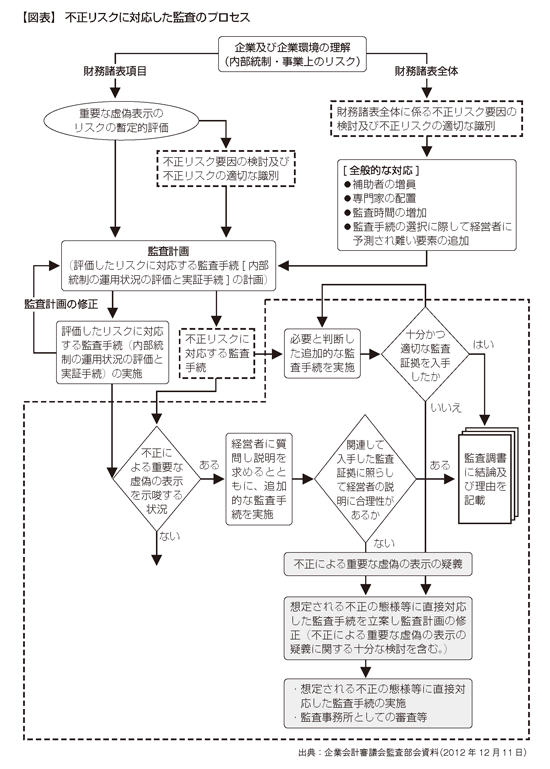
① 不正リスクに対応した監査計画の策定
本基準においては、現行の重要な虚偽表示のリスクの検討に際し、不正リスク要因の検討や不正リスクを把握するために必要な手続を規定した。監査人は、入手した情報が不正リスク要因の存在を示しているかどうかを検討し、それらを財務諸表全体及び財務諸表項目の不正リスクの識別において考慮しなければならないこととした。その上で、監査人は、識別・評価した不正リスクに応じた監査計画を策定することが求められる。
不正リスク要因とは、不正を実行する動機やプレッシャーの存在を示し、不正を実行する機会を与え、又は、不正を実行する際にそれを正当化する事象や状況を指し、典型的な不正リスク要因は付録1に例示されている。
また、監査人は、財務諸表全体に関連する不正リスクが識別された場合には、実施する監査手続の種類、時期及び範囲の選択に当たり、評価した不正リスクに応じて、監査手続の種類、時期若しくは範囲の変更、往査先の選択方法の変更又は予告なしに往査することなど、企業が想定しない要素を監査計画に組み込むことが必要になる。特に、不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合において、その状況によっては、修正する監査計画に企業が想定しない要素を組み込むことが有効なことがあると考えられる。
② 不正リスクに対応して実施する確認 監査人が、不正リスクに対応する監査手続として、照会事項の内容の正否にかかわらず回答を求める積極的確認を実施する場合には、回答がない又は回答が不十分なときには、代替的な手続により十分かつ適切な監査証拠を入手できるか否か慎重に判断しなければならないことを明確にした。特に、不正リスクが存在する場合の確認状に回答が得られない又は回答が不十分な場合(例えば、担保差入その他引出制限のある資産の状況等が未記入等)、すべての記載事項についての回答を入手できるよう留意し、代替的な手続に移行する場合には慎重に判断する必要がある。
③ 不正リスクに関連する監査証拠 監査人は、不正リスクを識別している監査要点に対しては、当該監査要点について不正リスクを識別していない場合に比べ、より適合性が高く、より証明力が強く、又はより多くの監査証拠を入手しなければならないこと、十分かつ適切な監査証拠を入手していないと判断した場合は、追加的な監査手続を実施しなければならないことを明確にした。
④ 不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況 監査実施の過程において、付録2に例示されているような「不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況」を識別した場合には、「不正による重要な虚偽の表示の疑義」が存在していないかどうかを判断するために、適切な階層の経営者に質問し説明を求めるとともに、追加的な監査手続を実施しなければならないこととしている。
付録2に例示されている状況は、国際監査基準における付録の記載や我が国における会計不正事案を踏まえ、現行の監査基準に基づく現在の実務においても、監査人としては、重要な虚偽の表示の可能性が高いものとして、特に注意すべき状況を念頭に記載されている。
なお、付録2はあくまで例示であり、監査実施の過程においてそのような状況に遭遇した場合に、「不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況」として追加的な監査手続を求めているものである。したがって、付録2に記載されている状況の有無について網羅的に監査証拠をもって確かめなければならないということではなく、また、付録2をチェック・リストとして扱うことを意図したものではない。
⑤ 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合の監査手続 不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況について、関連して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明に合理性がないと判断した場合や、識別した不正リスクに対応して追加的な監査手続を実施してもなお十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合には、不正による重要な虚偽の表示の疑いがより強くなることから、これを不正による重要な虚偽の表示の疑義と扱わなければならないものとした。なお、追加的な監査手続の実施の結果、不正による重要な虚偽の表示の疑義がないと判断した場合には、その旨と理由を監査調書に記載しなければならない。
不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合には、想定される不正の態様等に直接対応した監査手続を立案し監査計画を修正するとともに、修正した監査計画に従って監査手続を実施しなければならないこととなる。
⑥ 不正リスクに関連する審査 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合には、監査事務所として適切な監査意見を形成するため、審査についてもより慎重な対応が求められる。したがって、監査事務所の方針と手続に従って、適切な審査の担当者による審査が完了するまでは意見の表明ができないことを明記した。
⑦ 監査役等との連携 監査人は、不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合や経営者の関与が疑われる不正を発見した場合には、取締役の職務の執行を監査する監査役や監査委員会と適切に協議する等、連携を図ることが有効であり、監査の各段階において、監査役等との連携を図らなければならないことを明記した。
⑧ 監査調書 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合には、監査人が当該疑義に対して実施した監査手続の内容とその結果、また、監査人としての結論及びその際になされた重要な判断は、監査意見に重要な意味を有していると考えられることから、そうした内容については、監査調書に記載しなければならないことを明記した。
4 不正リスクに対応した監査事務所の品質管理 本基準においては、監査実施の各段階における不正リスクに対応した監査手続を実施するための監査事務所としての品質管理を規定している。
ただし、不正リスク対応基準における品質管理に係る規定は、現在各監査事務所で行っている品質管理のシステムに加えて、新たな品質管理のシステムの導入を求めているものではなく、監査事務所が整備すべき品質管理のシステムにおいて、不正リスクに対応する観点から特に留意すべき点を明記したものである。
また、整備及び運用が求められる監査事務所の方針と手続は、監査事務所の規模及び組織、当該監査業務の内容等により異なることから、すべての監査事務所において画一的な品質管理の方針と手続が求められているものではないことは言うまでもない。
① 不正リスクに対応した品質管理のシステムの整備及び運用 全般的な規定として、監査事務所に、不正リスクに適切に対応できるよう、監査業務の各段階における品質管理のシステムを整備及び運用するとともに、品質管理システムの監視を求めることとした。
② 監査契約の新規の締結及び更新 監査契約の新規の締結及び更新に関する方針及び手続に、不正リスクを考慮して監査契約の締結及び更新に伴うリスクを評価することを含めるとともに、監査契約の新規の締結及び更新の判断に際して、監査事務所としての検討を求めている。なお、更新時においては、監査チームだけでなく監査事務所としての検討を行うか否かについては、当該企業のリスクの程度に応じて判断することに留意する。
③ 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断された場合の審査 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断された場合には、通常の審査担当者による審査に比べて、監査事務所としてより慎重な審査が行われる必要がある。このため、当該監査業務の監査意見が適切に形成されるよう、当該疑義に対応する十分かつ適切な経験や職位等の資格を有する審査の担当者(適格者で構成される会議体を含む)を監査事務所として選任することを、審査に関する方針及び手続に定めなければならないこととした。
この監査事務所としての審査は、監査事務所の規模や組織等により、名称や体制等は異なることとなると考えられるが、例えば、大規模監査事務所の場合には、監査事務所本部における審査など、小規模事務所の場合には、社員全員による社員会における審査などが該当するものと考えられる。
④ 監査事務所間の引継 監査事務所交代時において、前任監査事務所は、後任の監査事務所に対して、不正リスクへの対応状況を含め、企業との間の重要な意見の相違等の監査上の重要な事項を伝達するとともに、後任監査事務所から要請のあったそれらに関連する監査調書の閲覧に応じるように、引継に関する方針と手続に定めなければならないこととした。
また、後任監査事務所は、前任監査事務所に対して、監査事務所の交代理由のほか、不正リスクへの対応状況、企業との間の重要な意見の相違等の監査上の重要な事項について質問するように、引継に関する方針及び手続に定めなければならないこととした。
Ⅲ 実施時期等
不正リスク対応基準は、平成26年3月決算に係る財務諸表の監査から実施する。なお、不正リスク対応基準中、不正リスクに対応した監査事務所の品質管理については、平成25年10月1日から実施する。
不正リスク対応基準は、中間監査に準用し、平成26年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施する。
Ⅳ 終わりに
不正に関しては、財務諸表作成者である経営者に責任があるところであり、経営者による組織ぐるみの不正や循環取引などの第三者と通謀した不正のように、不正によっては、公認会計士監査のみによって発見することが困難なケースもあると考えられ、対応としては、公認会計士監査における監査手続の充実とともに、企業におけるコーポレート・ガバナンスのあり方の検討などを含め、幅広い観点からの取組みが重要である。
そうした観点から、今般の不正リスク対応基準においては、公認会計士監査が、監査役など企業における監視・監督を担う機能と連携して対応することが有効であり、基準上も多く規定が設けられたところである。
不正リスクへの対応が国際的にも継続的な見直しが行われているところである。本基準の実施を契機に、監査人が不正リスクに対しより適切に対応するとともに、財務諸表作成者などの関係者においても従前にも増して不正リスクへの対応を行うことを通じ、不正抑止につながることが期待される。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























