コラム2013年11月25日 【SCOPE】 上場株式の市場外取引、売却価格に潜む税務リスク(2013年11月25日号・№524)
裁判所、時価を超える部分を一時所得と認定
上場株式の市場外取引、売却価格に潜む税務リスク
上場株式の市場外取引(相対取引)をめぐり、売却価格が課税問題に発展していた事案で裁判所の判断が下された(東京地裁平成25年9月27日判決)。裁判所は、証券取引所の終値(1株当たり290円)を超える価格(同550円)によって行われた売却取引について、差額部分は株式の譲渡対価には当たらないと指摘し、終値を超える部分の金額(総額で約3億円)を納税者の「一時所得」と判断した。裁判所は、取引所の終値と売却単価の差額部分について、譲渡先法人から納税者への贈与であると認定している。
相続税の納付が目的、時価の2倍弱で実質支配会社に売却
本事案の発端は、金融機関への借入金返済と相続税納付のための資金を必要としていた納税者(原告)が実施したあるスキームに始まる。具体的なスキームは次のようなものだ。
納税者は、保有する上場株式(A社株式)を納税者が実質的に支配するX社へ売却する。A社株式を取得したX社は、納税者から取得したA社株式を担保として、金融機関から借り入れを行う。そして、X社は、金融機関から借り入れた資金をもとに納税者にA社株式の取得代金を支払う。納税者は、その売却代金をもって、自身の借入金を返済、実父の死亡により発生した相続税を納付していた(図参照)。
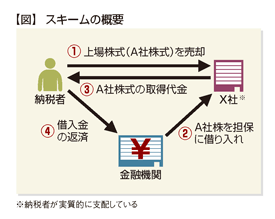
当局、時価を超える部分を譲渡所得と認めず 一見するとスキームの実行にあたり、課税問題が発生しないようにもみえる。
ただ、納税者が上場株式(A社株式)を証券取引所価格(終値)を超える価格でX社に売却したことが、税務当局の更正処分を招来することとなった(表参照)。
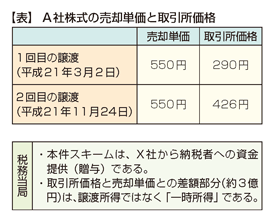
具体的にみると、1回目の取引は、1株当たりの取引所価格が290円のところ550円で売却(112万株)、2回目の取引は、1株当たりの取引所価格が426円のところ550円で売却(31万7,550株)していた。
なお、売却単価の550円は、A社株式のみなし取得価額(568円)を基準として納税者とその顧問税理士が決定していた。
この取引所価格と実際の売却単価の差額について、税務当局は、X社から納税者への資金提供(すなわち贈与)であると認定し、差額部分は納税者の一時所得に該当する旨の所得税更正処分を行っていた。この処分を不服とする納税者は、国税不服審判所の裁決を待たずに、訴訟を提起していた。
納税者は、上場株式の時価は必ずしも市場価格に限定されるものではなく、個々の取引ごとに売買の当事者が合意・決定した価格も時価となり得ると指摘。A社株式の売却単価550円は、客観的に合理的な範囲内の金額であると主張していた。
時価と売却価格の差額約3億円、譲渡先から納税者への贈与と認定
購入を急ぐ事情、譲渡先法人には認められず 納税者の訴えに対して裁判所は、納税者が実施したスキームについて、自己の借入金返済と相続税納付のために必要な資金を調達するための手段として、納税者は取引所価格(1回目290円、2回目426円)の水準をあえて無視してその価格に一定の金額を上乗せして売却単価(550円)を設定したと認定した。
また、裁判所は、納税者がA社株式を売却した当時、債務超過状態であったX社が、多額の融資を受けてまで取引所価格よりも高い価格でA社株式の購入を急がなければならない具体的な事情があったとは認められないなどと指摘している。
そのうえで、取引所価格と売却単価との差額である約3億円は、株式の譲渡対価たる性格を有しているとはいえないとして、納税者が実質的に支配するX社から納税者への贈与である(一時所得である)と結論付けた。
裁判所の判断内容は、税務当局の更正処分を全面的に支持した格好だ。
納税者、事前に国税庁の回答を得るも…… 今回の事案の納税者は、A社株式を売却した当時、財務省の副大臣を務めていた。A社株式の売却にあたり、納税者は、財務省の秘書官を通じて、国税庁から上場株式の相対取引の場合の課税関係についての回答を得ていたことが判決文から判明している(下の囲みを参照)。
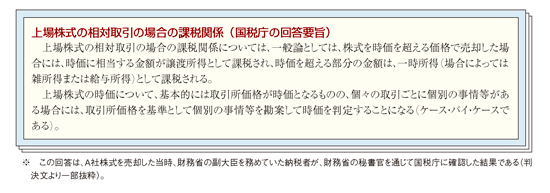
上場株式の市場外取引、売却価格に潜む税務リスク
上場株式の市場外取引(相対取引)をめぐり、売却価格が課税問題に発展していた事案で裁判所の判断が下された(東京地裁平成25年9月27日判決)。裁判所は、証券取引所の終値(1株当たり290円)を超える価格(同550円)によって行われた売却取引について、差額部分は株式の譲渡対価には当たらないと指摘し、終値を超える部分の金額(総額で約3億円)を納税者の「一時所得」と判断した。裁判所は、取引所の終値と売却単価の差額部分について、譲渡先法人から納税者への贈与であると認定している。
相続税の納付が目的、時価の2倍弱で実質支配会社に売却
本事案の発端は、金融機関への借入金返済と相続税納付のための資金を必要としていた納税者(原告)が実施したあるスキームに始まる。具体的なスキームは次のようなものだ。
納税者は、保有する上場株式(A社株式)を納税者が実質的に支配するX社へ売却する。A社株式を取得したX社は、納税者から取得したA社株式を担保として、金融機関から借り入れを行う。そして、X社は、金融機関から借り入れた資金をもとに納税者にA社株式の取得代金を支払う。納税者は、その売却代金をもって、自身の借入金を返済、実父の死亡により発生した相続税を納付していた(図参照)。
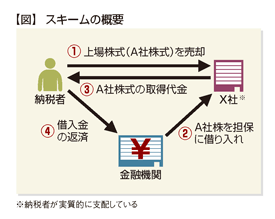
当局、時価を超える部分を譲渡所得と認めず 一見するとスキームの実行にあたり、課税問題が発生しないようにもみえる。
ただ、納税者が上場株式(A社株式)を証券取引所価格(終値)を超える価格でX社に売却したことが、税務当局の更正処分を招来することとなった(表参照)。
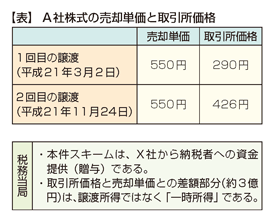
具体的にみると、1回目の取引は、1株当たりの取引所価格が290円のところ550円で売却(112万株)、2回目の取引は、1株当たりの取引所価格が426円のところ550円で売却(31万7,550株)していた。
なお、売却単価の550円は、A社株式のみなし取得価額(568円)を基準として納税者とその顧問税理士が決定していた。
この取引所価格と実際の売却単価の差額について、税務当局は、X社から納税者への資金提供(すなわち贈与)であると認定し、差額部分は納税者の一時所得に該当する旨の所得税更正処分を行っていた。この処分を不服とする納税者は、国税不服審判所の裁決を待たずに、訴訟を提起していた。
納税者は、上場株式の時価は必ずしも市場価格に限定されるものではなく、個々の取引ごとに売買の当事者が合意・決定した価格も時価となり得ると指摘。A社株式の売却単価550円は、客観的に合理的な範囲内の金額であると主張していた。
時価と売却価格の差額約3億円、譲渡先から納税者への贈与と認定
購入を急ぐ事情、譲渡先法人には認められず 納税者の訴えに対して裁判所は、納税者が実施したスキームについて、自己の借入金返済と相続税納付のために必要な資金を調達するための手段として、納税者は取引所価格(1回目290円、2回目426円)の水準をあえて無視してその価格に一定の金額を上乗せして売却単価(550円)を設定したと認定した。
また、裁判所は、納税者がA社株式を売却した当時、債務超過状態であったX社が、多額の融資を受けてまで取引所価格よりも高い価格でA社株式の購入を急がなければならない具体的な事情があったとは認められないなどと指摘している。
そのうえで、取引所価格と売却単価との差額である約3億円は、株式の譲渡対価たる性格を有しているとはいえないとして、納税者が実質的に支配するX社から納税者への贈与である(一時所得である)と結論付けた。
裁判所の判断内容は、税務当局の更正処分を全面的に支持した格好だ。
納税者、事前に国税庁の回答を得るも…… 今回の事案の納税者は、A社株式を売却した当時、財務省の副大臣を務めていた。A社株式の売却にあたり、納税者は、財務省の秘書官を通じて、国税庁から上場株式の相対取引の場合の課税関係についての回答を得ていたことが判決文から判明している(下の囲みを参照)。
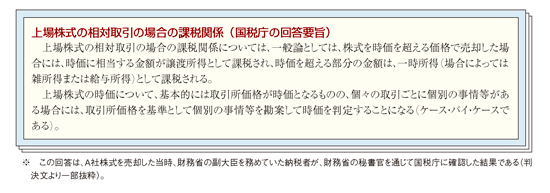
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















