解説記事2014年04月21日 【ニュース特集】 輸入サービスに関する消費税課税ルールの実務への影響(2014年4月21日号・№543)
BtoB取引なら申告義務なし、BtoC取引では仕入控除不可
輸入サービスに関する消費税課税ルールの実務への影響
政府が2012年から検討を重ねてきた「外国から輸入されるサービス」への消費税の課税ルールがほぼ固まり、平成27年度税制改正に盛り込まれることが確実となった。
国内事業者の消費税事務は、BtoB、BtoCいずれの取引に係る仕入れかによって異なることとなり、BtoBに係る仕入れでは消費税を納税しなくてよい代わりに仕入税額控除も認めないというように「申告義務」自体が免除される方向。一方、BtoC取引では現行消費税法どおり消費税の負担のみが求められ、仕入税額控除は認められないことになる。
ただ、「BtoB」「BtoC」の定義は改正消費税法で独自に定められることになるため、国内事業者が国外事業者から仕入れを行う場合であっても、支払った消費税の仕入税額控除が認められないケースが出てくるので要注意だ。
本特集では、外国から輸入されるサービスへの消費税の課税ルールの導入に伴い、消費税実務がどのような影響を受けるのかについてまとめた。
新たな課税ルールが検討されてきた背景とは?
政府は2012年7月以来、外国から「インターネット」を通じて輸入される役務提供に対し、いかに日本の消費税を課税するかを検討してきた。
同じ「輸入」でも、物理的に手に取れるモノが伴う場合には輸入者が税関に消費税を納める仕組みとなっているが(消法5条②)、インターネットを通じて外国から音楽や電子書籍、映像などをダウンロードするような“サービスの輸入”に対しては現行消費税は「不課税」となっている(図1参照)。これは、現行消費税法では、「事業者が国内で行った資産の譲渡や役務の提供」を課税対象としているところ(消法5条①)、役務の提供(サービス)が国内で行われたかどうかの判定は、「役務提供が行われた場所」がどこにあるかで行うこととされているためだ(消法4条③二)。
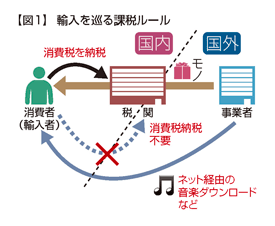
役務提供が行われた場所は、消費税法施行令6条2項において役務提供の種類ごとに規定されており、インターネットを通じた映像のダウンロード等のサービスは、「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」となる(同項七)。つまり、外国の事業者からサービスを受けている以上、たとえ日本国内で消費が行われていたとしても、消費税法上は「国内で行った資産の譲渡等」には該当せず、不課税になるというわけだ。
こうした中、コンテンツの配信サービス等を行う事業者の中には、海外のコンテンツ配信会社等との価格競争に耐え得るよう、「海外からの配信を検討する」と表明するところも出現していた。国内と海外のコンテンツ配信会社等の間には消費税導入当初から消費税分の価格格差が生じていたとはいえ、税率の引上げに伴いこの格差が拡大すれば、海外配信を行う国内事業者が相次ぐのではないかとの懸念が生じていた。
BtoCには課税者登録制度、BtoBにはリバースチャージ制度
財務省は早ければ平成25年度税制改正にも新たな課税ルールを盛り込むことを検討していたが、後述するように、日本にはVAT番号(付加価値税登録番号)やインボイスの仕組みがないことなどがネックとなり、課税ルールを詰め切れなかったという経緯がある。しかし、このほどようやくその内容が固まり、平成27年度税制改正での実現が確実となった。
大枠の仕組みは議論開始当初から変わっていない。すなわち、BtoC取引(国外事業者から国内の個人消費者へのサービス提供)については「課税事業者登録制度」、BtoB取引(国外事業者から国内事業者へのサービス提供)については「リバースチャージ制度」が導入されることになる(図2参照)。
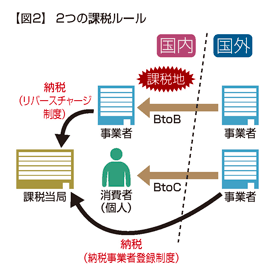
このうち「課税事業者登録制度」とは、国外事業者を日本の税務当局に登録させたうえ、日本国内の個人消費者にサービスを提供した場合には、日本の納税管理人(税理士など)を通じて納税を求める仕組み。
一方、リバースチャージ制度とは、本来は国外事業者にある納税義務を国内事業者に“転換”するものだ。国内事業者が国外事業者からサービスを輸入した場合、本来であれば、国内事業者は「税抜価格+消費税」を国外事業者に支払うことになるが、リバースチャージ制度では、国外事業者は国内事業者に対してあらかじめ「税抜価格」で販売する一方、国内事業者は国外事業者に対して「税抜価格」を、税務当局に対しては「消費税」を別々に支払うことになる。
ただ、これらの仕組みを導入するうえでネックとなっていたのが、国外事業者が日本国内の個人消費者および事業者の両方にサービスを提供している場合だ。EUでは、加盟国内の各企業にVAT番号が与えられ、インボイス等にVAT番号の記載があるかないかで、サービスの販売先が事業者なのか個人消費者なのかが分かるようになっている一方、日本にはVAT番号もインボイスもないため、国外事業者からすれば、サービスを販売した先が「事業者」なのか「個人消費者」なのかを判別するのは困難だ。
そこで、課税ルールを確定するにあたっては、この点についてある種の“割切り”がなされている。この点は政府税調の資料だけでは読み取れないので、次で詳しく解説する。
BtoCとBtoBが混在する場合には「BtoC」とみなす方向
海外から輸入するサービスの課税ルールは、4月4日に開催された「第3回 国際課税ディスカッショングループ」でほぼ確定したと言っていいが、この会合で提出された資料の中でポイントとなるのが、「国境を越えた役務の提供に対する消費税について(内外判定の見直しについて)」の2ページ目「課税方式の見直しについて」だ(税調のHP参照)。
この中で特に重要なのが、「BtoB取引」「BtoC取引」の定義。税調の資料によると、これは右記とされている。
このように、BtoC取引が「役務の提供を受ける者が事業者であることが明らかでないもの」、BtoB取引が「BtoC取引以外のもの」と定義されていることからすると、BtoB取引は「役務の提供を受ける者が事業者であることが明らかなもの」に限定されていることが分かる。
したがって、上述のとおり課税ルールを検討するうえで問題となっていた、国外事業者が日本国内の個人消費者および事業者の両方にサービスを提供しているケースは「BtoC取引」に分類されることになる。
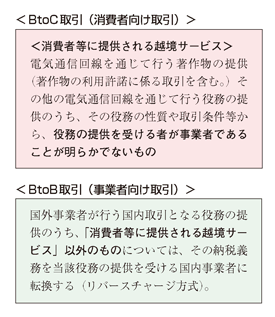
実際に負担した消費税が仕入税額控除できず
この結果、このような国外事業者(日本国内の個人消費者および事業者の両方にサービスを提供している事業者)からサービスを購入している国内事業者には不利益がおよぶことになりそうだ。
リバースチャージ制度の導入にあたっては、同制度の適用を受ける国内事業者の事務負担増加が懸念されていたが、税調の資料にもあるように、政府は、国内事業者に対しては同制度に係る消費税の「申告義務」を課さない方向で検討を進めている。これは、リバースチャージ制度が適用された場合、通常、国内事業者は、国外事業者から納税義務が転換された消費税と同額の仕入控除税額を計上することになるため。要するに、結局納税額が生じないのであれば、申告義務自体を免除してしまおうというわけだ。
もっとも、申告義務は免除されたとしても、「納税義務」まで免除されるわけではない。したがって、国内事業者は、リバースチャージ制度に係る消費税の納税が不要となる代わりに、当該消費税に係る仕入税額控除もできない。
一方、右記の税調資料のとおり、BtoC取引とされたものについては、海外事業者からの適正な納税を確保することに限界があることを踏まえ「慎重な検討が必要」としており、ここからは「仕入控除を認めたくない」という当局の考え方が透けて見える。
そうなった場合、日本国内の個人消費者および事業者の両方にサービスを提供している国外事業者からサービスを購入した国内事業者は、実際に消費税を負担しているにもかかわらず、当該消費税を仕入税額控除できないことになる。
この点、国内事業者にとっては不利益なルールと言えよう。
仕入税額控除を行えば税務調査の対象に
リバースチャージ制度においては、国外事業者は国内事業者に対して、リバースチャージ制度の適用対象取引である旨を通知する義務が課される。
その趣旨は、見かけ上の価格の不均衡を防止することにある。上述のとおり、リバースチャージ制度の下では、国外事業者は国内事業者にあらかじめ「税抜価格」で販売を行うことになる。消費税率引上げに伴い、現在は総額表示義務が免除されているとはいえ、仮に国内事業者間の取引で価格が「税込」で表示されている場合には、国内事業者より国外事業者の方が価格表示上有利となりかねない。そこで国外事業者に「表示価格の他に、リバースチャージ制度により○円の消費税がかかる」旨を通知させることで、こうした不均衡が生じないようにしようというわけだ。
では、国外事業者がその通知を忘れた場合どうなるのだろうか。仮に国内事業者が、リバースチャージ制度が適用されていることを伝えられなかったとして仕入税額控除を行った場合には、税務調査等で是正されることになろう。これは、国外事業者からの通知がなかったとしても、国内事業者の納税義務がなくなるわけではないからだ。国内事業者としては、「国外事業者からの仕入れは仕入税額控除の対象にしない」といった業務フローを確立しておく必要があろう。
輸入サービスに関する消費税課税ルールの実務への影響
政府が2012年から検討を重ねてきた「外国から輸入されるサービス」への消費税の課税ルールがほぼ固まり、平成27年度税制改正に盛り込まれることが確実となった。
国内事業者の消費税事務は、BtoB、BtoCいずれの取引に係る仕入れかによって異なることとなり、BtoBに係る仕入れでは消費税を納税しなくてよい代わりに仕入税額控除も認めないというように「申告義務」自体が免除される方向。一方、BtoC取引では現行消費税法どおり消費税の負担のみが求められ、仕入税額控除は認められないことになる。
ただ、「BtoB」「BtoC」の定義は改正消費税法で独自に定められることになるため、国内事業者が国外事業者から仕入れを行う場合であっても、支払った消費税の仕入税額控除が認められないケースが出てくるので要注意だ。
本特集では、外国から輸入されるサービスへの消費税の課税ルールの導入に伴い、消費税実務がどのような影響を受けるのかについてまとめた。
新たな課税ルールが検討されてきた背景とは?
政府は2012年7月以来、外国から「インターネット」を通じて輸入される役務提供に対し、いかに日本の消費税を課税するかを検討してきた。
同じ「輸入」でも、物理的に手に取れるモノが伴う場合には輸入者が税関に消費税を納める仕組みとなっているが(消法5条②)、インターネットを通じて外国から音楽や電子書籍、映像などをダウンロードするような“サービスの輸入”に対しては現行消費税は「不課税」となっている(図1参照)。これは、現行消費税法では、「事業者が国内で行った資産の譲渡や役務の提供」を課税対象としているところ(消法5条①)、役務の提供(サービス)が国内で行われたかどうかの判定は、「役務提供が行われた場所」がどこにあるかで行うこととされているためだ(消法4条③二)。
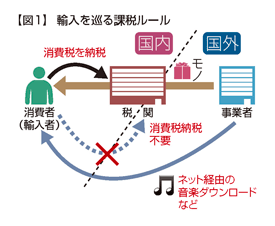
役務提供が行われた場所は、消費税法施行令6条2項において役務提供の種類ごとに規定されており、インターネットを通じた映像のダウンロード等のサービスは、「役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地」となる(同項七)。つまり、外国の事業者からサービスを受けている以上、たとえ日本国内で消費が行われていたとしても、消費税法上は「国内で行った資産の譲渡等」には該当せず、不課税になるというわけだ。
こうした中、コンテンツの配信サービス等を行う事業者の中には、海外のコンテンツ配信会社等との価格競争に耐え得るよう、「海外からの配信を検討する」と表明するところも出現していた。国内と海外のコンテンツ配信会社等の間には消費税導入当初から消費税分の価格格差が生じていたとはいえ、税率の引上げに伴いこの格差が拡大すれば、海外配信を行う国内事業者が相次ぐのではないかとの懸念が生じていた。
BtoCには課税者登録制度、BtoBにはリバースチャージ制度
財務省は早ければ平成25年度税制改正にも新たな課税ルールを盛り込むことを検討していたが、後述するように、日本にはVAT番号(付加価値税登録番号)やインボイスの仕組みがないことなどがネックとなり、課税ルールを詰め切れなかったという経緯がある。しかし、このほどようやくその内容が固まり、平成27年度税制改正での実現が確実となった。
大枠の仕組みは議論開始当初から変わっていない。すなわち、BtoC取引(国外事業者から国内の個人消費者へのサービス提供)については「課税事業者登録制度」、BtoB取引(国外事業者から国内事業者へのサービス提供)については「リバースチャージ制度」が導入されることになる(図2参照)。
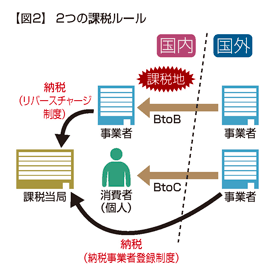
このうち「課税事業者登録制度」とは、国外事業者を日本の税務当局に登録させたうえ、日本国内の個人消費者にサービスを提供した場合には、日本の納税管理人(税理士など)を通じて納税を求める仕組み。
一方、リバースチャージ制度とは、本来は国外事業者にある納税義務を国内事業者に“転換”するものだ。国内事業者が国外事業者からサービスを輸入した場合、本来であれば、国内事業者は「税抜価格+消費税」を国外事業者に支払うことになるが、リバースチャージ制度では、国外事業者は国内事業者に対してあらかじめ「税抜価格」で販売する一方、国内事業者は国外事業者に対して「税抜価格」を、税務当局に対しては「消費税」を別々に支払うことになる。
ただ、これらの仕組みを導入するうえでネックとなっていたのが、国外事業者が日本国内の個人消費者および事業者の両方にサービスを提供している場合だ。EUでは、加盟国内の各企業にVAT番号が与えられ、インボイス等にVAT番号の記載があるかないかで、サービスの販売先が事業者なのか個人消費者なのかが分かるようになっている一方、日本にはVAT番号もインボイスもないため、国外事業者からすれば、サービスを販売した先が「事業者」なのか「個人消費者」なのかを判別するのは困難だ。
そこで、課税ルールを確定するにあたっては、この点についてある種の“割切り”がなされている。この点は政府税調の資料だけでは読み取れないので、次で詳しく解説する。
BtoCとBtoBが混在する場合には「BtoC」とみなす方向
海外から輸入するサービスの課税ルールは、4月4日に開催された「第3回 国際課税ディスカッショングループ」でほぼ確定したと言っていいが、この会合で提出された資料の中でポイントとなるのが、「国境を越えた役務の提供に対する消費税について(内外判定の見直しについて)」の2ページ目「課税方式の見直しについて」だ(税調のHP参照)。
この中で特に重要なのが、「BtoB取引」「BtoC取引」の定義。税調の資料によると、これは右記とされている。
このように、BtoC取引が「役務の提供を受ける者が事業者であることが明らかでないもの」、BtoB取引が「BtoC取引以外のもの」と定義されていることからすると、BtoB取引は「役務の提供を受ける者が事業者であることが明らかなもの」に限定されていることが分かる。
したがって、上述のとおり課税ルールを検討するうえで問題となっていた、国外事業者が日本国内の個人消費者および事業者の両方にサービスを提供しているケースは「BtoC取引」に分類されることになる。
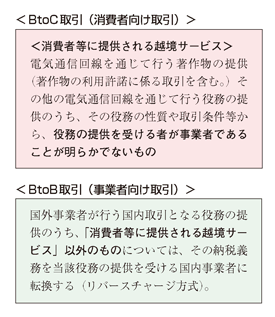
実際に負担した消費税が仕入税額控除できず
この結果、このような国外事業者(日本国内の個人消費者および事業者の両方にサービスを提供している事業者)からサービスを購入している国内事業者には不利益がおよぶことになりそうだ。
リバースチャージ制度の導入にあたっては、同制度の適用を受ける国内事業者の事務負担増加が懸念されていたが、税調の資料にもあるように、政府は、国内事業者に対しては同制度に係る消費税の「申告義務」を課さない方向で検討を進めている。これは、リバースチャージ制度が適用された場合、通常、国内事業者は、国外事業者から納税義務が転換された消費税と同額の仕入控除税額を計上することになるため。要するに、結局納税額が生じないのであれば、申告義務自体を免除してしまおうというわけだ。
もっとも、申告義務は免除されたとしても、「納税義務」まで免除されるわけではない。したがって、国内事業者は、リバースチャージ制度に係る消費税の納税が不要となる代わりに、当該消費税に係る仕入税額控除もできない。
一方、右記の税調資料のとおり、BtoC取引とされたものについては、海外事業者からの適正な納税を確保することに限界があることを踏まえ「慎重な検討が必要」としており、ここからは「仕入控除を認めたくない」という当局の考え方が透けて見える。
| 仮に、国内事業者が上記越境サービスの提供を受けた場合の仕入税額控除の扱いについては、執行管轄の及ばない膨大な国外事業者からの適正な納税を確保することには限界があることを踏まえ、慎重な検討が必要。 |
そうなった場合、日本国内の個人消費者および事業者の両方にサービスを提供している国外事業者からサービスを購入した国内事業者は、実際に消費税を負担しているにもかかわらず、当該消費税を仕入税額控除できないことになる。
この点、国内事業者にとっては不利益なルールと言えよう。
仕入税額控除を行えば税務調査の対象に
リバースチャージ制度においては、国外事業者は国内事業者に対して、リバースチャージ制度の適用対象取引である旨を通知する義務が課される。
その趣旨は、見かけ上の価格の不均衡を防止することにある。上述のとおり、リバースチャージ制度の下では、国外事業者は国内事業者にあらかじめ「税抜価格」で販売を行うことになる。消費税率引上げに伴い、現在は総額表示義務が免除されているとはいえ、仮に国内事業者間の取引で価格が「税込」で表示されている場合には、国内事業者より国外事業者の方が価格表示上有利となりかねない。そこで国外事業者に「表示価格の他に、リバースチャージ制度により○円の消費税がかかる」旨を通知させることで、こうした不均衡が生じないようにしようというわけだ。
では、国外事業者がその通知を忘れた場合どうなるのだろうか。仮に国内事業者が、リバースチャージ制度が適用されていることを伝えられなかったとして仕入税額控除を行った場合には、税務調査等で是正されることになろう。これは、国外事業者からの通知がなかったとしても、国内事業者の納税義務がなくなるわけではないからだ。国内事業者としては、「国外事業者からの仕入れは仕入税額控除の対象にしない」といった業務フローを確立しておく必要があろう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























