解説記事2014年12月01日 【事例で学ぶ資産税】 最近の申告事例などから〈ショートQ&A〉(2014年12月1日号・№573)
事例で学ぶ資産税
第10回
最近の申告事例などから〈ショートQ&A〉
税理士 塩野入文雄
はじめに
今回は、最近、筆者が接する機会があった相続税の申告事案などに関連して、その概略・ポイントを短いQ&Aにとりまとめています。
Ⅰ 基礎的資料収集及び現地確認の重要性(土地評価)
A 土地の評価については、「基礎的資料の収集」及び「現地確認」を行うことが重要です。
上記事例のモデルとした事案では、後日、公図と登記事項証明書を取り寄せたところ、裏面側に、市の所有地となっている「擁壁(のり面)」があることが分かり、急遽、現地確認も行った上で、正面路線価のみで評価額の再算定(更正の請求)を行いました。
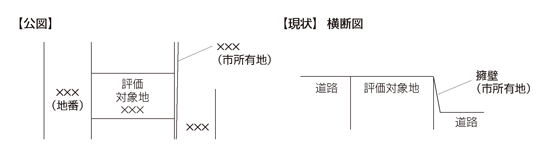
解 説
1 土地の評価を行う際は、「基礎的資料の収集」及び「現地確認」が必須であると言われていますが、(結果として、)上記事例は、その典型例であったといえます。
2 正面路線価のみで評価額を算定して申告を行った場合、税務署側も、路線価図だけを見て、二方加算漏れではないかとの疑問を持つことが想定されます。そこで、適宜、説明文や写真などを申告書に添付しておくことが得策です。
(注)上記事例については、現地確認を行わずに、基礎的資料の収集だけによっても、問題点を解消できたケースともなっています。
Ⅱ 贈与加算(相続税法19条(脚注1))
A 乙は、相続税の非課税対象となる財産であっても、相続財産である墓地・祭具を相続により取得しているので、相続税法19条の対象となり、贈与財産300万円を課税対象(贈与加算)とした相続税の申告が必要です(脚注2)。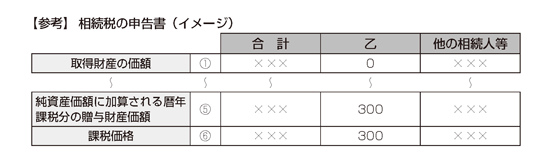
解 説
1 相続等(相続又は遺贈(脚注3))により財産を取得しなかった者には、贈与加算の適用はありません(相法19)(脚注4)。
2 墓地や祭具などは、相続税の非課税財産となっています(相法12二)。
3 しかしながら、相続税法19条における「財産」の取得には、非課税財産の取得も含まれています。
4 すなわち、墓地などを非課税と規定している相続税法12条(脚注5)は、「次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。」(同条①柱書)と規定しているのであって、墓地などの相続財産が、相続税法の適用上、「財産」であるという属性までを否定する規定にはなっていません。
5 よって、甲は、父の相続により相続財産(墓地・祭具)を取得していることから、相続開始前3年以内に父から贈与を受けた300万円が贈与加算の対象になります。
<関連事例>
A
相続税の申告は必要はありませんが、受贈額200万円の贈与税(相続開始年分)の申告が必要です。
なお、丙は、母の相続財産が相続税の基礎控除額を超えるか否か(相続税の申告の必要の有無)の点に関係なく、贈与税の申告が必要になります。
解 説
1 相続税法21条の2(脚注6)第4項の規定により、相続開始の年における被相続人からの贈与財産については贈与税を課税しないこととされています。
2 この贈与税の規定(条項)には、「……相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第19条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前3項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。」とされています。
3 丙は、相続の放棄を行っており、相続等により非課税財産も含め一切の相続財産を取得しなかったことから、相続税法21条の2第4項(及び同法19条)の適用対象者に該当しません。
4 よって、丙には、相続税法21条の2第4項の適用がなく、相続開始年分に関する贈与税の申告が必要です。
5 一方、丙は相続を放棄しているので(一切の財産を取得していない)、贈与加算(相法19)の適用対象者にならず、その結果、相続税の申告は必要ありません(脚注7)。
(注)例えば、丙が母の死亡に伴う生命保険金(みなし相続財産)を受け取っている場合は、相続税法21条の2第4項の適用対象となり、200万円は相続税の申告対象になりますので注意が必要です(その場合は、相続開始年分の贈与税の申告は不要です)。
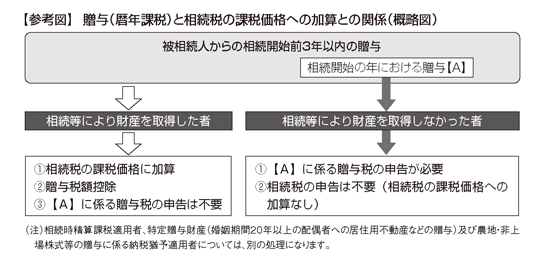
Ⅲ 合名会社の超過債務額(債務控除)
A
A社の出資の評価額は「0」(▲50)になります。
しかしながら、債務控除の対象となる超過債務の金額は「実額」によって算定することが必要です。
具体的には、A社に係る「超過債務金額」の算定は、出資の評価額の算定とは異なり、次のように、A社の保有資産を相続開始時における「通常の取引価額」によって評価して、その金額を算定します。
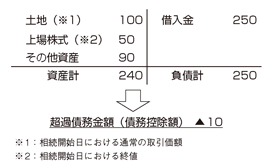
解 説
1 合名会社の超過債務額は、債務控除の対象となり得ます(【資料2】(23頁)の国税庁HP質疑応答事例を参照)。
(条件等)
・A社の「会社財産をもって会社の債務を完済することができない状態」にあるとき
・被相続人の負担すべき持分に対応する金額
2 出資の評価額の算定は、財産評価基本通達194(持分会社の出資の評価)の定めによります。
3 しかしながら、超過債務金額(債務控除額)は、「実額」の算定が必要です〔財産評価基本通達の定めによって、その金額を算定することはできません〕。
4 相続税法22条(脚注8)の規定に沿って、上記の点を整理すると、次表のとおりです。
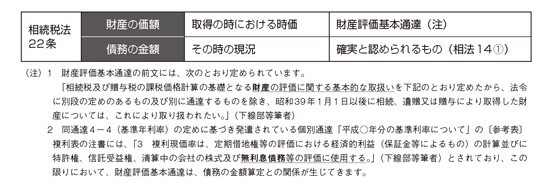
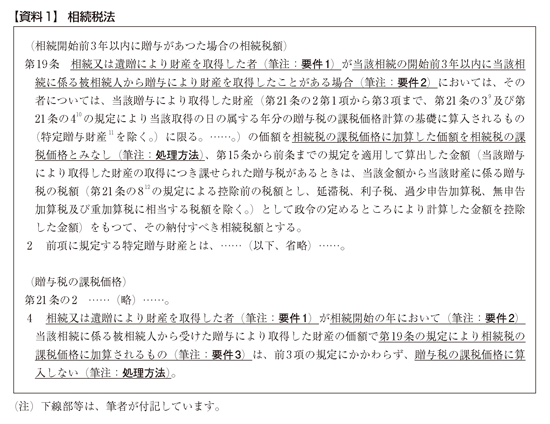
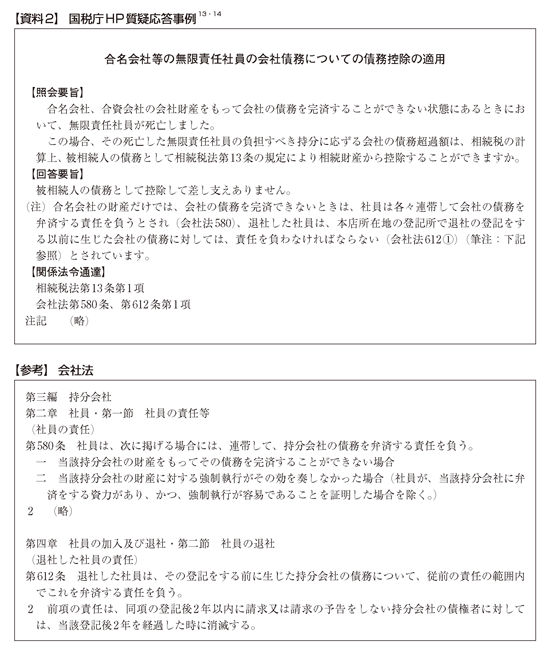
脚注
1 見出し:相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額(条文は、【資料1】(22頁)を参照)
2 贈与加算は、被相続人(父)からの贈与金額が、贈与税の基礎控除額以下の金額であっても加算することが必要です。
3 「遺贈」には「死因贈与」を含みます(相法1の3一かっこ書)。なお、措置法の適用に当たっては、措置法69条の2(在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例)第1項かっこ書に、同様の規定が設けられています。
4 ただし、仮に、乙が父(被相続人)からの贈与に係る「相続時精算課税適用者」である場合、乙が、父からの相続等により一切の財産を取得しない場合であっても加算対象となっています(相法21の16:相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者)。
5 見出し:相続税の非課税財産
6 見出し:贈与税の課税価格(条文は、【資料1】(22頁)を参照)
7 ただし、脚注4を参照。
8 見出し:評価の原則
9 見出し:贈与税の非課税財産
10 見出し:特定障害者に対する贈与税の非課税
11 贈与税の配偶者控除適用(可能)財産の一定額(本条第2項)を指しています。
12 見出し:在外財産に対する贈与税額の控除
13 相続・贈与税>債務控除に登載されています。
14 多様な事業体に関する税務処理については、実務家の多くが、その処理に悩む場面が少なくないと思われます。平成26年11月5日にRe-Newされた、国税庁HP・質疑応答事例・財産評価に、①匿名組合契約に係る権利の評価、②持分会社の退社時の出資の評価、及び、③企業組合の定款に特別の定めがある場合の出資の評価の3事例が追加されています。例えば、匿名組合は、旧商法時代からあった古くからの制度ですが、これらの事例が追加されたことからも、当該多様化等の状況が、相続税などの課税場面にも顕われてきている一端が窺われます。
第10回
最近の申告事例などから〈ショートQ&A〉
税理士 塩野入文雄
はじめに
今回は、最近、筆者が接する機会があった相続税の申告事案などに関連して、その概略・ポイントを短いQ&Aにとりまとめています。
Ⅰ 基礎的資料収集及び現地確認の重要性(土地評価)
| Q1
税理士甲は、相続税の申告書の作成に当たって、評価対象地が地方に所在する物件であったことや申告期限が迫っていたこともあって、路線価図のみを確認し、100千円を正面路線、80千円を裏面路線として(二方路線影響加算を行って)、その土地の評価額を算定して申告書を提出しました(相続人も現地を見たことがなく、土地の具体的な状況等については不知でした)。 その結果、過大な評価額になっていました。 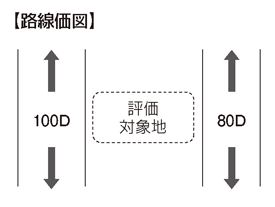 |
A 土地の評価については、「基礎的資料の収集」及び「現地確認」を行うことが重要です。
上記事例のモデルとした事案では、後日、公図と登記事項証明書を取り寄せたところ、裏面側に、市の所有地となっている「擁壁(のり面)」があることが分かり、急遽、現地確認も行った上で、正面路線価のみで評価額の再算定(更正の請求)を行いました。
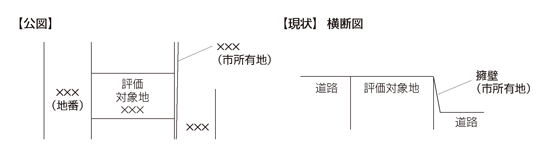
解 説
1 土地の評価を行う際は、「基礎的資料の収集」及び「現地確認」が必須であると言われていますが、(結果として、)上記事例は、その典型例であったといえます。
2 正面路線価のみで評価額を算定して申告を行った場合、税務署側も、路線価図だけを見て、二方加算漏れではないかとの疑問を持つことが想定されます。そこで、適宜、説明文や写真などを申告書に添付しておくことが得策です。
(注)上記事例については、現地確認を行わずに、基礎的資料の収集だけによっても、問題点を解消できたケースともなっています。
Ⅱ 贈与加算(相続税法19条(脚注1))
| Q2
相続人乙は、父の相続(平成26年○月)により墓地と祭具だけを相続し、土地や預金などの全ての財産は、他の相続人が相続しました。 なお、乙は、父が亡くなる前3年以内に、父から、平成23~25年の各年に、100万円ずつ(合計300万円)の現金の贈与を受けています。 相続により財産を取得しなかった者は、贈与加算の対象とならないので、乙は相続税の申告が不要であると思いますが、いかがですか? |
A 乙は、相続税の非課税対象となる財産であっても、相続財産である墓地・祭具を相続により取得しているので、相続税法19条の対象となり、贈与財産300万円を課税対象(贈与加算)とした相続税の申告が必要です(脚注2)。
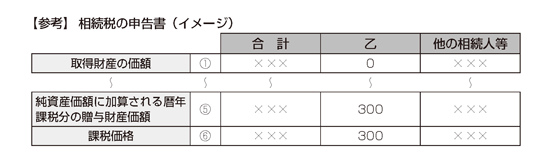
解 説
1 相続等(相続又は遺贈(脚注3))により財産を取得しなかった者には、贈与加算の適用はありません(相法19)(脚注4)。
2 墓地や祭具などは、相続税の非課税財産となっています(相法12二)。
3 しかしながら、相続税法19条における「財産」の取得には、非課税財産の取得も含まれています。
4 すなわち、墓地などを非課税と規定している相続税法12条(脚注5)は、「次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。」(同条①柱書)と規定しているのであって、墓地などの相続財産が、相続税法の適用上、「財産」であるという属性までを否定する規定にはなっていません。
5 よって、甲は、父の相続により相続財産(墓地・祭具)を取得していることから、相続開始前3年以内に父から贈与を受けた300万円が贈与加算の対象になります。
<関連事例>
| Q2-1
丙は、母の相続に関して相続を放棄しました。 なお、丙は、相続開始の年において、母から200万円の現金の贈与を受けていますが、丙は相続税や贈与税の申告が必要ですか? |
なお、丙は、母の相続財産が相続税の基礎控除額を超えるか否か(相続税の申告の必要の有無)の点に関係なく、贈与税の申告が必要になります。
解 説
1 相続税法21条の2(脚注6)第4項の規定により、相続開始の年における被相続人からの贈与財産については贈与税を課税しないこととされています。
2 この贈与税の規定(条項)には、「……相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第19条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前3項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。」とされています。
3 丙は、相続の放棄を行っており、相続等により非課税財産も含め一切の相続財産を取得しなかったことから、相続税法21条の2第4項(及び同法19条)の適用対象者に該当しません。
4 よって、丙には、相続税法21条の2第4項の適用がなく、相続開始年分に関する贈与税の申告が必要です。
5 一方、丙は相続を放棄しているので(一切の財産を取得していない)、贈与加算(相法19)の適用対象者にならず、その結果、相続税の申告は必要ありません(脚注7)。
(注)例えば、丙が母の死亡に伴う生命保険金(みなし相続財産)を受け取っている場合は、相続税法21条の2第4項の適用対象となり、200万円は相続税の申告対象になりますので注意が必要です(その場合は、相続開始年分の贈与税の申告は不要です)。
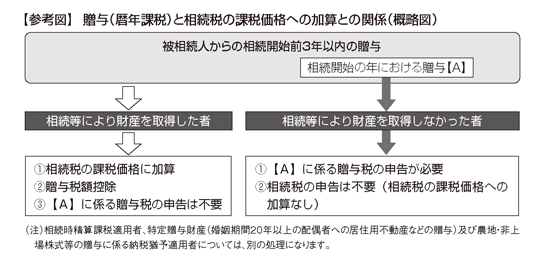
Ⅲ 合名会社の超過債務額(債務控除)
| Q3
合名会社A社の無限責任社員であった父が他界しました。 相続開始時におけるA社の資産の保有状況などは、右のとおりです。 A社への出資の評価額を「0」とし、かつ、超過債務の金額を▲50と算定し、その金額を債務控除することができますか? 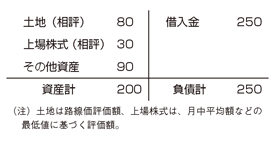 |
しかしながら、債務控除の対象となる超過債務の金額は「実額」によって算定することが必要です。
具体的には、A社に係る「超過債務金額」の算定は、出資の評価額の算定とは異なり、次のように、A社の保有資産を相続開始時における「通常の取引価額」によって評価して、その金額を算定します。
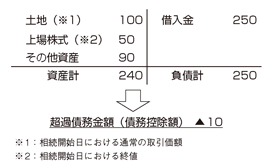
解 説
1 合名会社の超過債務額は、債務控除の対象となり得ます(【資料2】(23頁)の国税庁HP質疑応答事例を参照)。
(条件等)
・A社の「会社財産をもって会社の債務を完済することができない状態」にあるとき
・被相続人の負担すべき持分に対応する金額
2 出資の評価額の算定は、財産評価基本通達194(持分会社の出資の評価)の定めによります。
3 しかしながら、超過債務金額(債務控除額)は、「実額」の算定が必要です〔財産評価基本通達の定めによって、その金額を算定することはできません〕。
4 相続税法22条(脚注8)の規定に沿って、上記の点を整理すると、次表のとおりです。
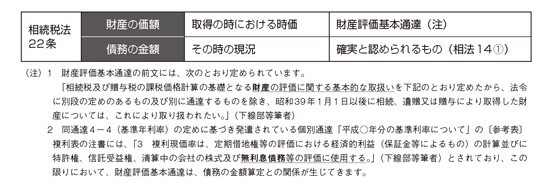
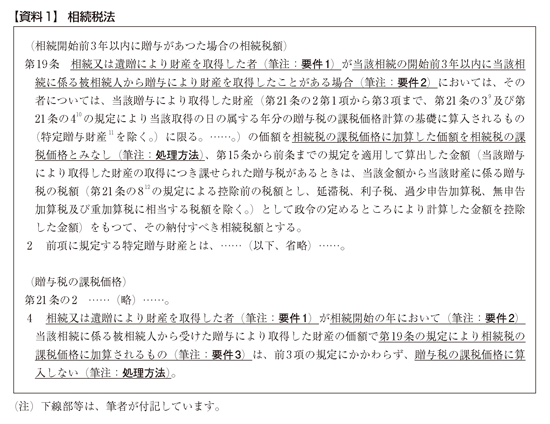
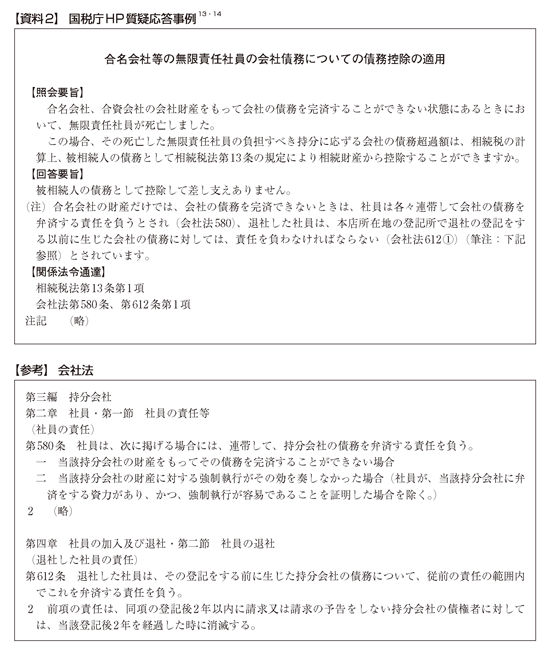
脚注
1 見出し:相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額(条文は、【資料1】(22頁)を参照)
2 贈与加算は、被相続人(父)からの贈与金額が、贈与税の基礎控除額以下の金額であっても加算することが必要です。
3 「遺贈」には「死因贈与」を含みます(相法1の3一かっこ書)。なお、措置法の適用に当たっては、措置法69条の2(在外財産等についての相続税の課税価格の計算の特例)第1項かっこ書に、同様の規定が設けられています。
4 ただし、仮に、乙が父(被相続人)からの贈与に係る「相続時精算課税適用者」である場合、乙が、父からの相続等により一切の財産を取得しない場合であっても加算対象となっています(相法21の16:相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者)。
5 見出し:相続税の非課税財産
6 見出し:贈与税の課税価格(条文は、【資料1】(22頁)を参照)
7 ただし、脚注4を参照。
8 見出し:評価の原則
9 見出し:贈与税の非課税財産
10 見出し:特定障害者に対する贈与税の非課税
11 贈与税の配偶者控除適用(可能)財産の一定額(本条第2項)を指しています。
12 見出し:在外財産に対する贈与税額の控除
13 相続・贈与税>債務控除に登載されています。
14 多様な事業体に関する税務処理については、実務家の多くが、その処理に悩む場面が少なくないと思われます。平成26年11月5日にRe-Newされた、国税庁HP・質疑応答事例・財産評価に、①匿名組合契約に係る権利の評価、②持分会社の退社時の出資の評価、及び、③企業組合の定款に特別の定めがある場合の出資の評価の3事例が追加されています。例えば、匿名組合は、旧商法時代からあった古くからの制度ですが、これらの事例が追加されたことからも、当該多様化等の状況が、相続税などの課税場面にも顕われてきている一端が窺われます。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























