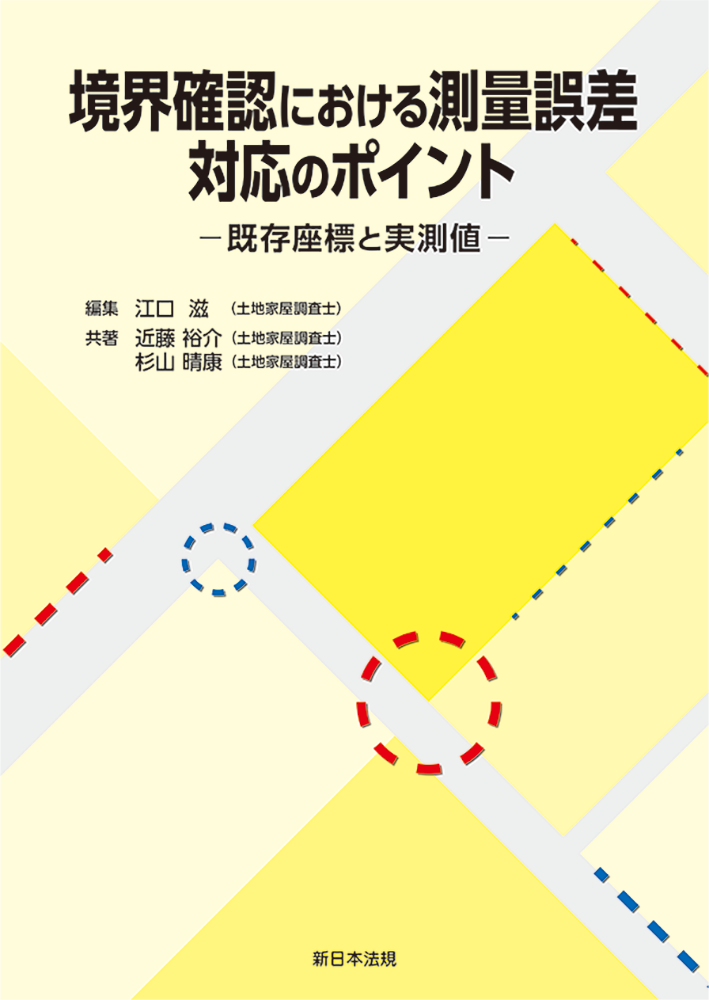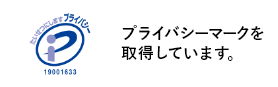解説記事2014年12月22日 【税務マエストロ】 消費税の会計処理(2014年12月22日号・№576)
税務マエストロ
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
消費税の会計処理
#127 熊王征秀(税理士)
略歴 学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師として入社し、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。その後、会計事務所勤務を経て税理士登録、独立開業。『消費税トラブルの傾向と対策』等、著書多数。
現在
東京税理士会会員相談室委員
東京税理士会税務審議部委員
東京地方税理士会税法研究所研究員
日本税務会計学会委員
大原大学院大学准教授
次回のテーマ
#128 BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響③
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 品川克己 税制改正や、中国進出企業の増加に伴い、国際課税上のリスクは高まっている。国際課税の第一人者がそのリスクを検証する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
マエストロの解説 消費税に関する会計処理には「税込経理方式」と「税抜経理方式」があり、事業者はそのいずれかの方法により記帳(入力)処理をすることになる。
処理方法の選択にあたっては、原則課税の場合には税抜経理方式、簡易課税の場合には税込経理方式といったような制約はない。ただし、免税事業者は税込経理方式しか採用することができないので、仮払(仮受)消費税等の計上は認められない(消費税法等の関係取扱通達~消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(以下「関係取扱通達」という。)五)。
今回は、消費税に関する会計処理について「税込経理方式」と「税抜経理方式」(図1参照)を比較し、それぞれの留意点を確認する。
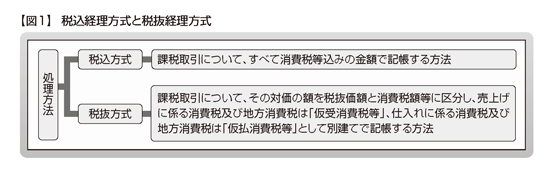
1 期末一括税抜経理方式(関係取扱通達四) 税抜経理方式による場合には、原則として取引の都度税抜処理をするわけであるが、期中は税込経理方式により処理をしておいて、事業年度末に一括して税抜にすることもできる。なお、税抜経理方式により、仮受(仮払)消費税等を計上する場合には、次のいずれかの方法によることになるものと思われる。
①請求書等に別記されている消費税額等を仮受(仮払)消費税等として計上する方法
②税込金額に8/108を乗じて仮受(仮払)消費税等を計算し、計上する方法
この場合の端数処理は、切捨て、四捨五入、切上げのいずれかを継続して適用するべきであろう。
また、私見ではあるが、6で後述する混合方式との関係で、課税売上高と課税仕入高、また、課税仕入高の内容は、棚卸資産、固定資産(繰延資産)、経費等のグループ毎に異なる端数処理をすることも認められるものと思われる。
2 仮受消費税等と仮払消費税等の精算 決算にあたり、仮払消費税等と仮受消費税等を精算する際には、端数処理等の影響で、貸借の差額は通常一致しない。このような場合には、控除対象外消費税額等が発生する場合を除き、貸借の差額は雑損失又は雑収入勘定で処理することになる(具体例1参照)。
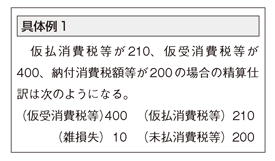
仮払消費税等と仮受消費税等を精算する場合の差額については、その事業年度において益金の額又は損金の額に算入することとされているので、これを精算せずに翌期に繰り延べることは認められない(関係取扱通達六)。
3 簡易課税制度との関係 簡易課税制度の適用を受けている事業者であっても税抜経理方式を採用することは何ら問題ない。ただし、簡易課税制度の適用を受ける場合には、みなし仕入率により仕入控除税額を計算する関係上、実際の仕入控除税額等と仮払消費税等の金額が連動しないことになる。
結果、仮払消費税等と仮受消費税等を精算する際に、貸借の差額が多額になることも想定されるものの、控除対象外消費税額等が発生する場合を除き、貸借の差額は雑損失又は雑収入として処理することができる(関係取扱通達六)。
4 納付(還付)税額の処理方法 税込経理方式を採用した場合には、納付消費税額等は、原則として申告書を提出した日の属する事業年度において損金処理をすることとされているが、これを前倒しで未払計上することも認められている(関係取扱通達七)。
納付消費税額等の未払計上については、継続適用が要件とはされていない。したがって、赤字決算の時には翌期に納付した時点で損金計上をし、黒字決算の時には前倒しで未払計上して所得を圧縮するといったように、決算期毎に異なる処理をすることもできる(図2参照)。
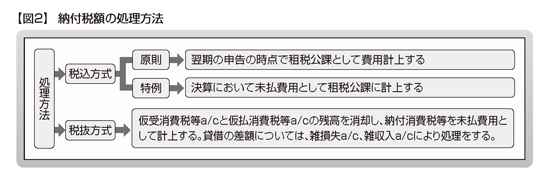
なお、納付消費税額等が損金算入される時期は、実際に消費税額等を納付した事業年度ではなく、納税申告書の提出日の属する事業年度である。したがって、納税申告書は提出したものの、資金繰りの都合などにより滞納を抱えている事業者は、納付税額が損金に算入されないこともあるので注意が必要だ。
納税申告書を提出した事業年度後の事業年度で納付税額を損金処理した場合には、法人税の計算上、その損金処理をした納付税額は別表四で加算調整することになる(具体例2参照)。
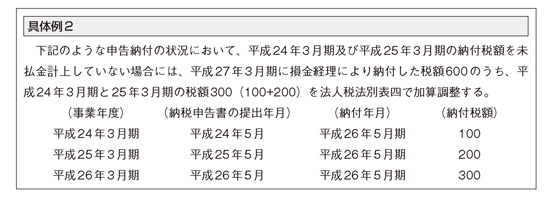
また、還付消費税額等は、図3のように、原則として申告書を提出した日の属する事業年度において益金計上することとされているが、これを未収入金として前倒しで収益計上することも認められている(関係取扱通達八)。
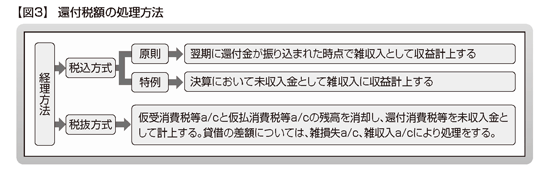
5 税抜経理方式のメリット 法人税の場合、税抜経理方式を採用した場合、税込経理方式と比較すると以下のようなメリットがある。
(1)売上原価の計算 物品販売業の場合、期首商品棚卸高に期中仕入金額をプラスし、期末棚卸高をマイナスすることにより売上原価を計算する。
税抜経理方式の場合には、棚卸資産の評価も税抜きで行うことになるので、税込経理方式に比べて売上総利益を圧縮する効果がある。
なお、税込経理方式の場合には、期末棚卸資産の評価も税込みで行うので、これを誤って税抜金額で評価すると「商品計上漏れ」として否認されることとなるので注意が必要だ。
(2)減価償却資産(繰延資産)の取扱い 減価償却資産については取得価額が10万円未満のもの、繰延資産については取得価額が20万円未満のものは一時に損金とすることが認められている(法令133、134)。
税抜経理方式の場合には、この判定の基礎となる取得価額も税抜金額で判定するので、税込経理方式と比較し、有利となる(関係取扱通達九)。
なお、税込経理方式の場合には、少額減価償却資産(繰延資産)の判定も税込金額で行うので、税込金額が10万円(20万円)をわずかに超えているような減価償却資産(繰延資産)を誤って税抜金額で判定し、損金処理をすると「減価償却超過」として否認されることとなる。
また、減価償却資産について課された消費税等については、税込経理方式の場合、減価償却費として毎期費用配分することになるわけであるが、税抜経理方式の場合には、その消費税等の額が仮払消費税等として精算されるため、結果として、取得の期にその全額が費用計上できることになる(具体例3参照)。
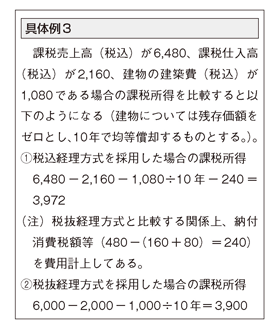
具体例3における課税所得の差額72は、税込経理方式を採用した場合の建物の未償却残額のうち、消費税等相当額である。つまり、税抜経理方式を採用した場合には、建物に課された消費税等80が取得時に費用計上できるのに対し、税込経理を採用した場合には、建物に課された消費税等80は減価償却費として10年にわたり費用配分するため、所得計算上は不利になる。
(3)交際費等の損金不算入額の計算 法人税法上、交際費等については資本等の額により、損金算入額が制限されている。
この損金不算入額の計算の基礎となる支出交際費等についても、税込経理方式の場合には税込金額で、税抜経理方式の場合には税抜金額で計算することとなっているので、税抜処理をしたほうが、損金不算入となる交際費等の額が少なくなり、所得計算上有利となる。
ただし、控除対象外消費税額等については、支出交際費等の額に含めることとされている(関係取扱通達十二)。
6 混合方式 税抜経理方式を採用する場合には、課税売上高と課税仕入高のすべてについて税抜きにすることが原則であるが、個人事業者などの小規模事業者に配慮して「混合方式」によることも認められている(関係取扱通達三)。
「混合方式」とは、課税売上高についてはすべて税抜きにすることを前提に、課税仕入高を下記の①~③のグループに区分し、各グループのうちどれか一つでも税抜処理をしていれば、他のグループの課税仕入高については税込処理でもよいという経理方法である(表参照)。

①棚卸資産
②固定資産(繰延資産)
③経費等
個人事業者などの小規模事業者が高額な設備投資をし、上記5(2)の<具体例3>のように税抜経理方式のメリットを享受しようとする場合には、売上高と固定資産について税抜処理をし、経費等については税込みで処理することもできるということである。
ただし、棚卸資産のグループについて、固定資産(繰延資産)と異なる処理をしようとする場合には、税込みあるいは税抜きの処理を継続適用することが条件とされているので注意が必要だ。固定資産については税抜きで処理をし、棚卸資産については税込みで処理をしようとする場合には、棚卸資産については翌期以降も継続して税込みにしなければいけないということである。
なお、「混合方式」を採用する場合には、課税売上高はすべて税抜きにすることが条件となるので、例えば、商品売上高だけを税抜きにし、雑収入勘定については税込処理をするようなことは認められない。
7 年又は事業年度の中途からの経理方法の変更 免税事業者が、設備投資について消費税の還付を受けるため、課税期間を短縮した上で「課税事業者選択届出書」を提出した場合には、年又は事業年度の中途から課税事業者に切り替わることになる。例えば、5月10日に「課税期間特例選択・変更届出書」及び「課税事業者選択届出書」を提出し、7月1日から課税事業者となる個人事業者は、1月1日~6月30日期間中は免税事業者、7月1日~12月31日期間中は課税事業者となるのであるが、この場合において、免税事業者の期間中は税込経理方式、課税事業者の期間中は税抜経理方式を採用することはできるのであろうか。
私見としては、混合方式を採用した場合には、課税仕入高のグループ毎に異なる経理処理を採用することができるのであるから、年の中途からの税抜経理方式への切り替えも認められるものと思われる。なお、1月1日~6月30日期間中は免税事業者であるから、7月1日から課税事業者になるとしても当然に税抜経理方式の採用は認められない(図4参照)。
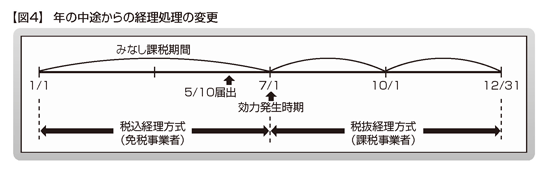
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
消費税の会計処理
#127 熊王征秀(税理士)
略歴 学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師として入社し、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。その後、会計事務所勤務を経て税理士登録、独立開業。『消費税トラブルの傾向と対策』等、著書多数。
現在
東京税理士会会員相談室委員
東京税理士会税務審議部委員
東京地方税理士会税法研究所研究員
日本税務会計学会委員
大原大学院大学准教授
次回のテーマ
#128 BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響③
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 品川克己 税制改正や、中国進出企業の増加に伴い、国際課税上のリスクは高まっている。国際課税の第一人者がそのリスクを検証する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
マエストロの解説 消費税に関する会計処理には「税込経理方式」と「税抜経理方式」があり、事業者はそのいずれかの方法により記帳(入力)処理をすることになる。
処理方法の選択にあたっては、原則課税の場合には税抜経理方式、簡易課税の場合には税込経理方式といったような制約はない。ただし、免税事業者は税込経理方式しか採用することができないので、仮払(仮受)消費税等の計上は認められない(消費税法等の関係取扱通達~消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(以下「関係取扱通達」という。)五)。
今回は、消費税に関する会計処理について「税込経理方式」と「税抜経理方式」(図1参照)を比較し、それぞれの留意点を確認する。
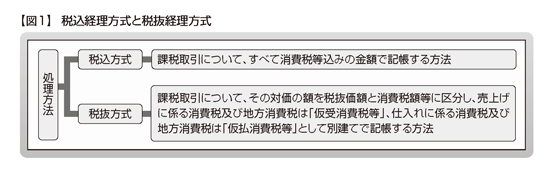
1 期末一括税抜経理方式(関係取扱通達四) 税抜経理方式による場合には、原則として取引の都度税抜処理をするわけであるが、期中は税込経理方式により処理をしておいて、事業年度末に一括して税抜にすることもできる。なお、税抜経理方式により、仮受(仮払)消費税等を計上する場合には、次のいずれかの方法によることになるものと思われる。
①請求書等に別記されている消費税額等を仮受(仮払)消費税等として計上する方法
②税込金額に8/108を乗じて仮受(仮払)消費税等を計算し、計上する方法
この場合の端数処理は、切捨て、四捨五入、切上げのいずれかを継続して適用するべきであろう。
また、私見ではあるが、6で後述する混合方式との関係で、課税売上高と課税仕入高、また、課税仕入高の内容は、棚卸資産、固定資産(繰延資産)、経費等のグループ毎に異なる端数処理をすることも認められるものと思われる。
2 仮受消費税等と仮払消費税等の精算 決算にあたり、仮払消費税等と仮受消費税等を精算する際には、端数処理等の影響で、貸借の差額は通常一致しない。このような場合には、控除対象外消費税額等が発生する場合を除き、貸借の差額は雑損失又は雑収入勘定で処理することになる(具体例1参照)。
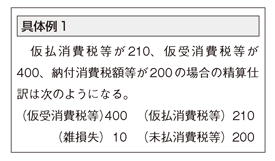
仮払消費税等と仮受消費税等を精算する場合の差額については、その事業年度において益金の額又は損金の額に算入することとされているので、これを精算せずに翌期に繰り延べることは認められない(関係取扱通達六)。
3 簡易課税制度との関係 簡易課税制度の適用を受けている事業者であっても税抜経理方式を採用することは何ら問題ない。ただし、簡易課税制度の適用を受ける場合には、みなし仕入率により仕入控除税額を計算する関係上、実際の仕入控除税額等と仮払消費税等の金額が連動しないことになる。
結果、仮払消費税等と仮受消費税等を精算する際に、貸借の差額が多額になることも想定されるものの、控除対象外消費税額等が発生する場合を除き、貸借の差額は雑損失又は雑収入として処理することができる(関係取扱通達六)。
4 納付(還付)税額の処理方法 税込経理方式を採用した場合には、納付消費税額等は、原則として申告書を提出した日の属する事業年度において損金処理をすることとされているが、これを前倒しで未払計上することも認められている(関係取扱通達七)。
納付消費税額等の未払計上については、継続適用が要件とはされていない。したがって、赤字決算の時には翌期に納付した時点で損金計上をし、黒字決算の時には前倒しで未払計上して所得を圧縮するといったように、決算期毎に異なる処理をすることもできる(図2参照)。
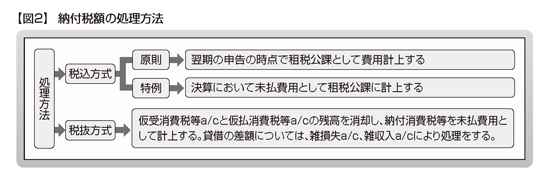
なお、納付消費税額等が損金算入される時期は、実際に消費税額等を納付した事業年度ではなく、納税申告書の提出日の属する事業年度である。したがって、納税申告書は提出したものの、資金繰りの都合などにより滞納を抱えている事業者は、納付税額が損金に算入されないこともあるので注意が必要だ。
納税申告書を提出した事業年度後の事業年度で納付税額を損金処理した場合には、法人税の計算上、その損金処理をした納付税額は別表四で加算調整することになる(具体例2参照)。
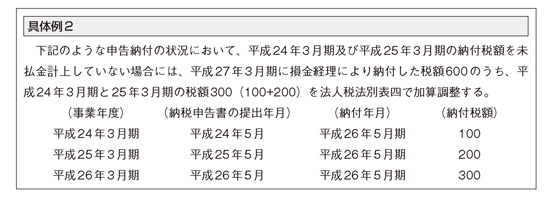
また、還付消費税額等は、図3のように、原則として申告書を提出した日の属する事業年度において益金計上することとされているが、これを未収入金として前倒しで収益計上することも認められている(関係取扱通達八)。
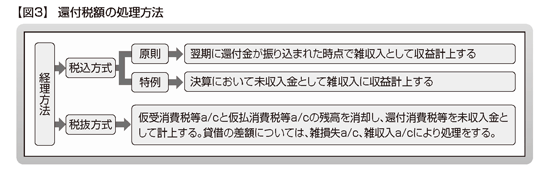
5 税抜経理方式のメリット 法人税の場合、税抜経理方式を採用した場合、税込経理方式と比較すると以下のようなメリットがある。
(1)売上原価の計算 物品販売業の場合、期首商品棚卸高に期中仕入金額をプラスし、期末棚卸高をマイナスすることにより売上原価を計算する。
税抜経理方式の場合には、棚卸資産の評価も税抜きで行うことになるので、税込経理方式に比べて売上総利益を圧縮する効果がある。
なお、税込経理方式の場合には、期末棚卸資産の評価も税込みで行うので、これを誤って税抜金額で評価すると「商品計上漏れ」として否認されることとなるので注意が必要だ。
(2)減価償却資産(繰延資産)の取扱い 減価償却資産については取得価額が10万円未満のもの、繰延資産については取得価額が20万円未満のものは一時に損金とすることが認められている(法令133、134)。
税抜経理方式の場合には、この判定の基礎となる取得価額も税抜金額で判定するので、税込経理方式と比較し、有利となる(関係取扱通達九)。
なお、税込経理方式の場合には、少額減価償却資産(繰延資産)の判定も税込金額で行うので、税込金額が10万円(20万円)をわずかに超えているような減価償却資産(繰延資産)を誤って税抜金額で判定し、損金処理をすると「減価償却超過」として否認されることとなる。
また、減価償却資産について課された消費税等については、税込経理方式の場合、減価償却費として毎期費用配分することになるわけであるが、税抜経理方式の場合には、その消費税等の額が仮払消費税等として精算されるため、結果として、取得の期にその全額が費用計上できることになる(具体例3参照)。
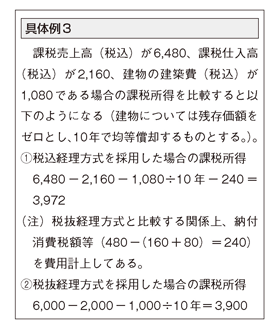
具体例3における課税所得の差額72は、税込経理方式を採用した場合の建物の未償却残額のうち、消費税等相当額である。つまり、税抜経理方式を採用した場合には、建物に課された消費税等80が取得時に費用計上できるのに対し、税込経理を採用した場合には、建物に課された消費税等80は減価償却費として10年にわたり費用配分するため、所得計算上は不利になる。
(3)交際費等の損金不算入額の計算 法人税法上、交際費等については資本等の額により、損金算入額が制限されている。
この損金不算入額の計算の基礎となる支出交際費等についても、税込経理方式の場合には税込金額で、税抜経理方式の場合には税抜金額で計算することとなっているので、税抜処理をしたほうが、損金不算入となる交際費等の額が少なくなり、所得計算上有利となる。
ただし、控除対象外消費税額等については、支出交際費等の額に含めることとされている(関係取扱通達十二)。
6 混合方式 税抜経理方式を採用する場合には、課税売上高と課税仕入高のすべてについて税抜きにすることが原則であるが、個人事業者などの小規模事業者に配慮して「混合方式」によることも認められている(関係取扱通達三)。
「混合方式」とは、課税売上高についてはすべて税抜きにすることを前提に、課税仕入高を下記の①~③のグループに区分し、各グループのうちどれか一つでも税抜処理をしていれば、他のグループの課税仕入高については税込処理でもよいという経理方法である(表参照)。

①棚卸資産
②固定資産(繰延資産)
③経費等
個人事業者などの小規模事業者が高額な設備投資をし、上記5(2)の<具体例3>のように税抜経理方式のメリットを享受しようとする場合には、売上高と固定資産について税抜処理をし、経費等については税込みで処理することもできるということである。
ただし、棚卸資産のグループについて、固定資産(繰延資産)と異なる処理をしようとする場合には、税込みあるいは税抜きの処理を継続適用することが条件とされているので注意が必要だ。固定資産については税抜きで処理をし、棚卸資産については税込みで処理をしようとする場合には、棚卸資産については翌期以降も継続して税込みにしなければいけないということである。
なお、「混合方式」を採用する場合には、課税売上高はすべて税抜きにすることが条件となるので、例えば、商品売上高だけを税抜きにし、雑収入勘定については税込処理をするようなことは認められない。
7 年又は事業年度の中途からの経理方法の変更 免税事業者が、設備投資について消費税の還付を受けるため、課税期間を短縮した上で「課税事業者選択届出書」を提出した場合には、年又は事業年度の中途から課税事業者に切り替わることになる。例えば、5月10日に「課税期間特例選択・変更届出書」及び「課税事業者選択届出書」を提出し、7月1日から課税事業者となる個人事業者は、1月1日~6月30日期間中は免税事業者、7月1日~12月31日期間中は課税事業者となるのであるが、この場合において、免税事業者の期間中は税込経理方式、課税事業者の期間中は税抜経理方式を採用することはできるのであろうか。
私見としては、混合方式を採用した場合には、課税仕入高のグループ毎に異なる経理処理を採用することができるのであるから、年の中途からの税抜経理方式への切り替えも認められるものと思われる。なお、1月1日~6月30日期間中は免税事業者であるから、7月1日から課税事業者になるとしても当然に税抜経理方式の採用は認められない(図4参照)。
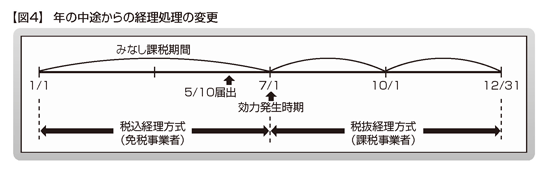
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -