解説記事2015年01月26日 【税務マエストロ】 課税標準額に対する消費税額&仕入税額の特例計算(2015年1月26日号・№580)
税務マエストロ
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
課税標準額に対する消費税額&仕入税額の特例計算
#129 熊王征秀(税理士)
略歴 学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師として入社し、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。その後、会計事務所勤務を経て税理士登録、独立開業。『消費税トラブルの傾向と対策』等、著書多数。
現在
東京税理士会会員相談室委員
東京税理士会税務審議部委員
東京地方税理士会税法研究所研究員
日本税務会計学会委員
大原大学院大学准教授
次回のテーマ
#130 BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響④
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 品川克己 税制改正や、中国進出企業の増加に伴い、国際課税上のリスクは高まっている。国際課税の第一人者がそのリスクを検証する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
マエストロの解説 転嫁対策法の成立により、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの期間に限り、いわゆる「外税表示」が時限的に認められている。ただし、消費者に対する表示価格が税込価格であると誤認されないようにすることが外税表示の条件とされているので、店内に値札が税抜価格である旨を記載した張り紙をするなどの工夫が必要となっている(転嫁対策法10①、附則2①)。
これに伴い、外税決済により代金の受領をする事業者は、総額表示をしているか否かにかかわらず、平成26年4月1日以後の取引について、課税標準額に対する消費税額の特例計算(旧消費税法施行規則22条1項)を適用することができることとされた(消規(平25年)附則2④~⑤)。
今回は、この課税標準額に対する消費税額の特例計算(旧消規22条1項)の内容を整理するとともに、税抜経理方式を採用した場合の仕入税額の特例計算について確認する。
1 課税標準額に対する消費税額の特例計算 旧消規22条1項の特例計算とはどんなものなのか……。以下、税抜単価が160円の商品を1,000人の顧客に1個ずつ販売したケースを例にとって考えてみたい。
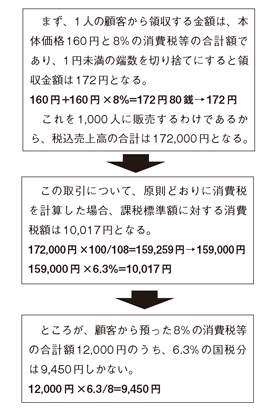
つまり、原則どおりに計算した場合には、実際には9,450円の消費税しか預っていないのに、納税額は10,017円を基に計算しなければならないという矛盾が生ずることとなるので、この矛盾点を解消するために設けられたのが、旧消規22条1項の特例計算である。
旧消規22条1項の特例計算は、平成16年4月1日からの総額表示義務の創設に伴い、原則として廃止された。ただし、レジシステム等の変更が間に合わないなどの事情を考慮して、総額表示を条件に、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの期間限定で認められていたものである。
要は、転嫁対策法の成立を受け、平成19年3月31日をもって廃止された特例計算(図1の経過措置C)を当分の間復活させるということである。
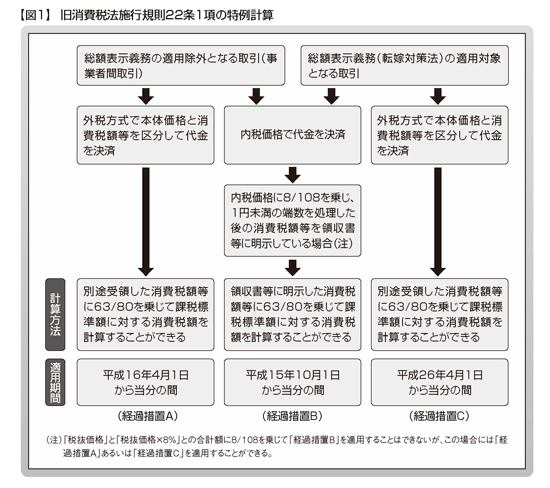
なお、図1の経過措置Aと経過措置Bは平成16年4月1日より認められている経過措置であり、今後も当分の間は適用することができる。
経過措置Aは、いわゆる事業者間取引であるから総額表示義務の規定は適用されない。したがって、旧消規22条1項の特例計算を適用しても問題ないということである。
また、「経過措置B」は、従来の外税方式から内税価格での代金決済に移行した事業者と、引き続き外税方式で代金決済をする事業者との課税上のバランスをとるための措置(内税決済に移行した事業者から不満がでないように配慮した措置)と考えられる。
※「経過措置B」が適用できるのは、次のような領収書で代金決済をするような場合である。
(税込価格172円、税抜価格160円の商品を販売した場合)
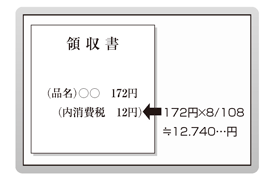
2 税抜経理方式を採用した場合の課税標準額に対する消費税額の計算 たとえ税抜経理方式を採用している場合であっても、税抜きの課税売上高と仮受消費税等を合計し、税込みの課税売上高に100/108を乗じて課税標準額を計算しなければならない(計算式参照)。
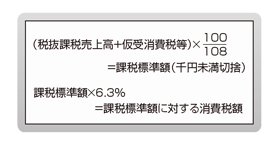
ただし、旧消規22条1項の特例計算(経過措置)の適用を受ける場合には、別途受領した消費税額等を仮受消費税等として処理し、これに63/80を乗じた金額を課税標準額に対する消費税額として採用することができる。
3 仕入税額の特例計算 課税仕入れ等の税額の計算は、国内仕入れについては、その支払対価の額にまとめて6.3/108を乗ずるのが原則である。
しかし、税抜仕入高とこれに対する消費税等を区分経理している場合には、課税仕入れ等の税額等がすでに計算されているわけであり、これを合計してあらためて6.3/108を乗ずる必要もないことから、区分経理した仮払消費税等に63/80を乗じて課税仕入れ等の税額を計算することが認められている(事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて/法令解釈通達14)。
仮払消費税等を計上する場合には、次のいずれかの経理方法によることとされている。
① 外税決済により、本体価額と1円未満の端数を処理した後の消費税額等が区分して領収される場合において、その領収書または請求書等に別記された消費税額等を仮払消費税等として計上する方法
② 内税価格に8/108を乗じ、1円未満の端数を処理した後の消費税額等が領収書または請求書等に明示されている場合において、その領収書または請求書等に明示された消費税額等を仮払消費税等として計上する方法
③ 上記①および②以外の場合において、税込課税仕入高に8/108を乗じて計算した仮払消費税等を帳簿等で区分経理する方法
この場合の消費税額等の端数については、1円未満の端数を切捨てか四捨五入のいずれかで処理することとされており、切上げ処理は認められていない(図2参照)。
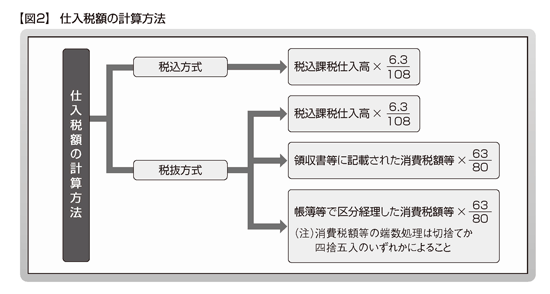
記事に関連するお問い合わせ先 記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp ※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
課税標準額に対する消費税額&仕入税額の特例計算
#129 熊王征秀(税理士)
略歴 学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師として入社し、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。その後、会計事務所勤務を経て税理士登録、独立開業。『消費税トラブルの傾向と対策』等、著書多数。
現在
東京税理士会会員相談室委員
東京税理士会税務審議部委員
東京地方税理士会税法研究所研究員
日本税務会計学会委員
大原大学院大学准教授
次回のテーマ
#130 BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響④
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 品川克己 税制改正や、中国進出企業の増加に伴い、国際課税上のリスクは高まっている。国際課税の第一人者がそのリスクを検証する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
マエストロの解説 転嫁対策法の成立により、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの期間に限り、いわゆる「外税表示」が時限的に認められている。ただし、消費者に対する表示価格が税込価格であると誤認されないようにすることが外税表示の条件とされているので、店内に値札が税抜価格である旨を記載した張り紙をするなどの工夫が必要となっている(転嫁対策法10①、附則2①)。
これに伴い、外税決済により代金の受領をする事業者は、総額表示をしているか否かにかかわらず、平成26年4月1日以後の取引について、課税標準額に対する消費税額の特例計算(旧消費税法施行規則22条1項)を適用することができることとされた(消規(平25年)附則2④~⑤)。
今回は、この課税標準額に対する消費税額の特例計算(旧消規22条1項)の内容を整理するとともに、税抜経理方式を採用した場合の仕入税額の特例計算について確認する。
1 課税標準額に対する消費税額の特例計算 旧消規22条1項の特例計算とはどんなものなのか……。以下、税抜単価が160円の商品を1,000人の顧客に1個ずつ販売したケースを例にとって考えてみたい。
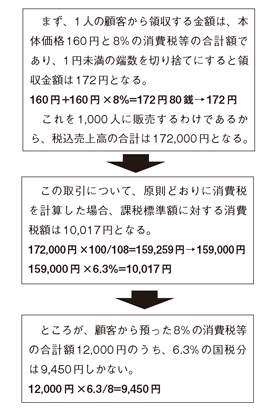
つまり、原則どおりに計算した場合には、実際には9,450円の消費税しか預っていないのに、納税額は10,017円を基に計算しなければならないという矛盾が生ずることとなるので、この矛盾点を解消するために設けられたのが、旧消規22条1項の特例計算である。
旧消規22条1項の特例計算は、平成16年4月1日からの総額表示義務の創設に伴い、原則として廃止された。ただし、レジシステム等の変更が間に合わないなどの事情を考慮して、総額表示を条件に、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの期間限定で認められていたものである。
要は、転嫁対策法の成立を受け、平成19年3月31日をもって廃止された特例計算(図1の経過措置C)を当分の間復活させるということである。
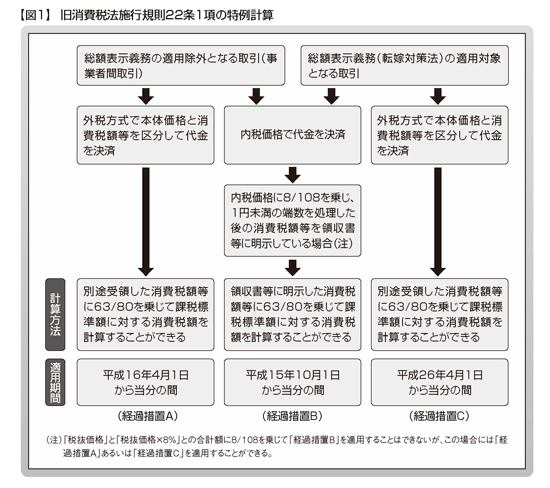
なお、図1の経過措置Aと経過措置Bは平成16年4月1日より認められている経過措置であり、今後も当分の間は適用することができる。
経過措置Aは、いわゆる事業者間取引であるから総額表示義務の規定は適用されない。したがって、旧消規22条1項の特例計算を適用しても問題ないということである。
また、「経過措置B」は、従来の外税方式から内税価格での代金決済に移行した事業者と、引き続き外税方式で代金決済をする事業者との課税上のバランスをとるための措置(内税決済に移行した事業者から不満がでないように配慮した措置)と考えられる。
※「経過措置B」が適用できるのは、次のような領収書で代金決済をするような場合である。
(税込価格172円、税抜価格160円の商品を販売した場合)
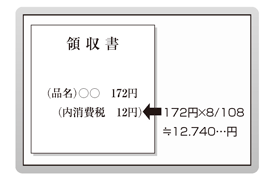
2 税抜経理方式を採用した場合の課税標準額に対する消費税額の計算 たとえ税抜経理方式を採用している場合であっても、税抜きの課税売上高と仮受消費税等を合計し、税込みの課税売上高に100/108を乗じて課税標準額を計算しなければならない(計算式参照)。
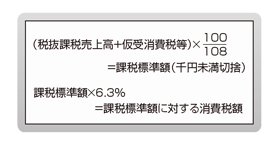
ただし、旧消規22条1項の特例計算(経過措置)の適用を受ける場合には、別途受領した消費税額等を仮受消費税等として処理し、これに63/80を乗じた金額を課税標準額に対する消費税額として採用することができる。
3 仕入税額の特例計算 課税仕入れ等の税額の計算は、国内仕入れについては、その支払対価の額にまとめて6.3/108を乗ずるのが原則である。
しかし、税抜仕入高とこれに対する消費税等を区分経理している場合には、課税仕入れ等の税額等がすでに計算されているわけであり、これを合計してあらためて6.3/108を乗ずる必要もないことから、区分経理した仮払消費税等に63/80を乗じて課税仕入れ等の税額を計算することが認められている(事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い及び課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置の取扱いについて/法令解釈通達14)。
仮払消費税等を計上する場合には、次のいずれかの経理方法によることとされている。
① 外税決済により、本体価額と1円未満の端数を処理した後の消費税額等が区分して領収される場合において、その領収書または請求書等に別記された消費税額等を仮払消費税等として計上する方法
② 内税価格に8/108を乗じ、1円未満の端数を処理した後の消費税額等が領収書または請求書等に明示されている場合において、その領収書または請求書等に明示された消費税額等を仮払消費税等として計上する方法
③ 上記①および②以外の場合において、税込課税仕入高に8/108を乗じて計算した仮払消費税等を帳簿等で区分経理する方法
この場合の消費税額等の端数については、1円未満の端数を切捨てか四捨五入のいずれかで処理することとされており、切上げ処理は認められていない(図2参照)。
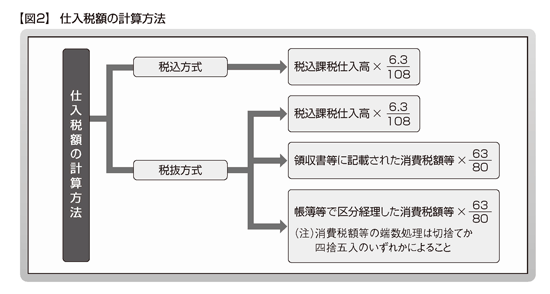
記事に関連するお問い合わせ先 記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp ※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















