解説記事2015年06月15日 【実務解説】 受益権複層化信託の所得課税(2015年6月15日号・№598)
実務解説
受益権複層化信託の所得課税
高橋倫彦
はじめに
1 本稿の趣旨 米国の伝統的な家族の為の信託では、配偶者が生涯にわたって年金給付を受け(life interest:生涯受益権)、配偶者が死亡後、子供が残余の信託財産を相続する(remainder:残余財産受益権)ことが多い。こうした家族の為の信託は我が国において公的年金の給付額の引き下げが懸念される中、これを補完する私的年金として残された配偶者等の長生きリスクをカバーするのに好適である。この信託は信託受益権が質的に異なる受益権に分割される最も信託らしい信託(以下「受益権複層化信託」という)である(図参照)。
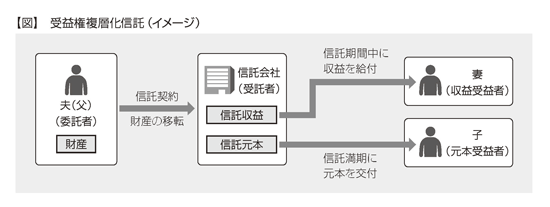
しかし、信託の実務家も税理士等専門家もこの信託の利用に躊躇する向きが多いようである。この信託では、信託の受益者が信託財産を構成する資産を持分により共有する(単層化)のではなく、この資産を重畳的に合有している(複層化)と考えられる(脚注1)ので、この信託財産から発生した信託収益がどの受益者にどのように帰属するのか、この信託の受益権が相続等により移転した場合に受益権の課税価額がどのように評価されるのか等について、現行税制ではその取り扱いが必ずしも明瞭ではない為である。
我が国においてこの信託の利用が期待される中で、税制の不透明さがその利用の障害になるような事態は解消しなければならない。一般社団法人信託協会は実務家と専門家による研究会を組成してこの検討を行っている。また税制改正の要望項目として、受益権複層化信託の課税関係を明確化する観点から所要の税法上の措置を講じること、及び受益者連続型信託に関する権利の価額の特例の対象から、例えば、家族の扶養のための給付や資産承継を目的とする一定の類型の信託を除外することを要望している(脚注2)。
2 信託実務の観点 受益権複層化信託の税務の取り扱いの明確化は、現行法のもとでは困難であり、法改正が必要であるとの論調が多いように見受けられるが、信託実務においては、この信託に対する顧客ニーズが強いので、法改正を待つ余裕がない。現行法の良し悪しは別として、これを忠実に適用した場合の税務の取り扱いの明確化が望まれる。
しかし、受益権複層化信託の公表された事例も論文も少ないので、税務当局も税務の専門家もその明確化のための検討を進め難い状況のように見受けられる。幸い信託実務の現場には、現実に起きている事例が豊富にある。筆者は税務の専門家の方々の今後の検討の一助になることを目的として、長年信託業務に従事した経験を基に、手元の事例に基づき、利用者の意図(信託目的)に照らして、信託の権利の内容と、経済合理性とを根拠に、現行法の下における税務の取り扱いを明らかにすることを試みた。今後の明確化のための一助になることを期待したい。
なお、本稿は受益権複層化信託のうち、「受益者等課税信託」の類型を対象として、その所得課税を分析する。法人課税信託等の他の課税類型は対象としない。信託受益権の相続税評価、相続・贈与課税及び受益者連続型信託の問題については、誌面の都合から別の機会に譲る。また、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。
本稿では、信託実務で遭遇する受益権複層化信託の事例をここに紹介し、質的に異なる受益者が信託財産に属する資産・負債をどのように保有し、どの受益者への収益・費用が帰属するかを考える。
Ⅰ 現実に起っている事例と問題点
1 当初信託財産の種類が異なる事例
(1)債券の場合 債券の場合、債券の年次のクーポン収益は一定であることから、信託受益権を収益受益権と元本受益権とに分割し、年次のクーポン収益から得られるキャッシュフローを年金として収益受益者に給付することが多い。この受益権複層化信託では、クーポン収益は収益受益者に帰属し、利子所得として所得税等が源泉徴収され、他の所得から分離課税される(租税特別措置法3条1項)。債券の償還元本のキャッシュフローは元本受益者に交付され、債券の償還差益は元本受益者に帰属し、雑所得として課税される。信託の期中において債券の売買損益が発生した場合は、その売買損益は元本受益者に帰属し、譲渡所得税が非課税とされる(脚注3)。信託の満期が到来したが、信託財産の債券の満期が到来しない場合は、当初信託財産である当該債券はそのまま元本受益者に交付される。
しかし、信託債券が繰り上げ償還されれば、その後の信託期間の信託収益額が当初の信託収益額と同じとは限らない(脚注4)。年次の信託収益から得られるキャッシュフローは税込ではなく源泉税引きであり、収益受益者にのみに源泉徴収税を負担させてよいのかどうか、信託所得を収益受益者のみへ帰属させる税法の明文の規定は存在しない。
(2)株式や投資信託の場合 株式配当から発生する配当所得等の金額は必ずしも安定しないので、その将来の信託収益額の見積もりが困難である。このため信託受益権を収益受益権と元本受益権とに分割する場合、収益受益権の相続税評価が難しい。これに対し、委託者が定期金受益権を留保し、残余財産受益権を家族に贈与する仕組みを採用する、米国の委託者定期金留保信託(Grantor Retained Annuity Trust)では、定期金が年次の信託収益額にかかわらず一定額の定期金を給付する場合に限って適格とされ、残余財産受益権の贈与税の評価額は信託財産を構成する資産の評価額から定期金の現在価値相当額を控除した額とすることができる(米国内国歳入法2702条)。定期金の給付は、実際の信託収益額が定期金額より少なかった場合は不足額を信託元本から取り崩して行い、定期金額より多かった場合は余剰額を信託元本に追加する(脚注5)。
(3)金銭の場合 投資家が金銭信託し、信託金を有価証券にポートフォリオ運用した場合、運用益はインカムゲインのみではなく、キャピタルゲインもある。信託期間中は運用益を収益受益者に給付する。当初信託財産は金銭であるから、信託満期にはポートフォリオを換金し、信託元本相当額(当初信託金額)の金銭を元本受益者に交付し、余剰金があれば、これを収益受益者に交付することになる。しかし、ポートフォリオ運用の場合、将来の運用益が不確実で信託収益額の見積もりが困難であるために、収益受益権の相続税評価をすることができない。また、信託満期に運用損失が残った場合、収益受益者がこの損失補填をしないと、元本受益者への償還が元本割れになる。信託実務ではポートフォリオ運用目的の金銭信託は原則として受益権を複層化しない。
(4)不動産の場合 収益不動産から発生する収益は必ずしも安定しない(脚注6)。その所得は不動産所得や事業所得等として他の所得と通算され総合課税されるので、しばしば減価償却の扱いが問題となる。賃貸物件が信託財産である信託において、もし収益受益者に配布される収益が減価償却費等を控除した純収益である場合は、諸経費を差し引いた純賃料が収益受益者に帰属し、減価償却費相当額の収益は信託勘定に留保され、元本受益者に帰属することになると思われる。この場合、元本受益者は信託の満期に不動産と減価償却費相当額の金銭を受領することになる。
これに対して減価償却費等の控除前の総収益である場合は、総賃料及び減価償却費を含む諸経費は収益受益者に帰属することになると思われる。この場合は、収益受益権の評価額が減価償却費等相当額だけ高くなり、元本受益権の評価額がその分安くなる。信託の満期に元本の受益者が交付を受ける資産は減価償却後の資産になる。
2 信託受益権の種類が異なる事例
(1)収益受益権と元本受益権とに分ける場合 会計的に信託利益を受益者配当として支払うためには、原則として、信託決算により信託利益を確定しなければならない。信託決算を待たずに信託給付を行う場合は、信託元本を取り崩して支給することになる。しかし実務では、信託利益が確実に得られる見込みがある場合は信託決算を待たずに信託収益(収入)から信託給付を行っている。
資産運用の観点から見ると、収益受益権と元本受益権とに分けるということは、収益受益者が運用リスクを負担し、年次のキャッシュフローの変動を甘受することを意味する。これに対し定期金受益権と残余財産受益権とに分けるということは、残余財産受益者が運用リスクを負担し、信託満期の残余財産の変動を甘受することを意味する。
信託収益から源泉税が徴収されて、受託者が税引きキャッシュフローを受領する場合は、収益受益者の課税所得額は信託財産全体の税込の総収益額であるが、キャッシュフローの受領額は税引き額になる。
(2)定期金受益権と残余財産受益権とに分ける場合 定期金受益者の権利の内容が信託元本の取崩しの場合は、定期金受益者は信託財産に属する資産・負債を保有せず、信託収益・費用は定期金受益者に帰属しない。定期金受益権の内容は元本を分割して受領する一種の金銭債権になる。この場合、残余財産受益者が信託財産に属する資産・負債を保有するとみなされるので、残余財産受益者は収益の受益者を兼ねることになる。その結果、信託の期間中は、同受益者に信託収益・費用が帰属し、同受益者に信託所得を申告納税する義務が出てくる。
Ⅱ 現行法における信託の設定、所得に対する課税の原則
1 信託の設定課税 受益者等課税信託の設定時において、受益者が存する場合は受託者に対する課税はない。受益者が法人の場合は受益者となる法人(法人受益者)が適正な対価を負担していない場合、個人委託者が信託設定時に信託財産をその法人に贈与したものとされる(所得税法67条の3第3項)。また個人の法人への資産の贈与は譲渡とみなされるので(所得税法59条1項)、個人委託者が信託財産を時価で譲渡したものとして時価と取得価額の差額に対して譲渡所得税が課税される。法人受益者が対価を負担している場合は、その対価の額を収入金額として譲渡所得の計算をするが、その対価の額が時価の2分の1未満の場合は、時価を収入金額として譲渡所得の計算をするものとされている。法人受益者は時価と対価との差額を受贈益として課税される。
受益者の有する信託に関する権利がその信託に関する権利の全部でない場合において、受益者が1名である場合は、その受益者がその信託に関する権利の全部を有するものとみなし、受益者が複数の場合は、その信託に関する権利の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとみなされる(所得税法施行令197条の3第5項)。
2 信託の所得課税の原則
(1)一般原則 相続、遺贈又は個人からの贈与により財産を取得する場合、その財産に対して所得税は課されない(所得税法9条1項16号)が、このように取得した財産から発生する収益に対しては所得税が課税される。
信託財産を構成する資産は法形式的には受託者の所有であるから、信託財産から発生する損益は受託者に帰属するが、受益者等課税信託の場合、税務的には信託財産を構成する資産は受益者の保有とみなされ、信託収益・費用は受益者に帰属するとみなされる(所得税法13条1項)。この取扱いは、信託制度を受益者に所得を分配する導管(パススルー)に過ぎないと考える導管論に基づく。
これに対して受益者等課税信託でない資産証券化信託等では、信託財産を一種の法人とみなし、信託財産に属する資産から発生するキャッシュフローをいくつかの種類のトランシュ(金融商品としての受益権)に切り分けて、信託受益権を金融商品(ペイスルー)として投資家に販売するので、これを取得した投資家の所得は金融所得になる。受益権複層化信託においても金融商品と同様の税務の取り扱いを適用する可能性を検討する研究がある(脚注7)。
特定受益者(受益者等課税信託の個人受益者)が、信託から生ずる不動産所得を有する場合に、その年分の不動産所得の金額の計算上信託による不動産所得の損失の金額があるときは、当該損失の金額に相当する金額は、不動産所得の金額の計算の規定および損益通算の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなされる(租税特別措置法41条の4の2第1項)。
(2)譲渡の所得課税 信託財産に属する資産の譲渡よる所得は譲渡所得になり、またその資産が権利の目的になっている信託の権利の譲渡による所得も譲渡所得になる。譲渡所得の収入金額はその対価になる(所得税基本通達33-1の7)。いわゆる物の信託の場合、信託財産の譲渡所得課税はその多くが元本の受益者に対して行われる。
信託の設定により信託財産に属することになった資産の譲渡にかかる譲渡所得の計算基礎となる資産の取得費は、その委託者がその資産を引き続き有しているものとして計算される(所得税基本通達33-1の7(4))。信託満期まで資産の売却を行わない場合は、元本受益者がその資産について委託者の取得価額を引き継ぐ。贈与などにより取得した資産の譲渡所得の計算における取得費については贈与者などが引き続き所有していたものとみなされる(所得税法60条)。
受益者が複数いる場合に、信託財産の譲渡益がどの受益者に帰属するかは、それぞれの受益者が有する権利の内容に応じて決まる問題である。
(3)受益者が複数いる場合 受益者が複数いる場合は、信託財産に属する資産・負債の全部をそれぞれの受益者がそれぞれの有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益・費用の全部がそれぞれの受益者の有する信託の権利の内容に応じて帰せられるものとされ、この受益者には信託の変更権限を有するみなし受益者(所得税法13条2項)を含むものとされる(所得税法13条4項、所得税法施行令52条4項)。家族の為の受益権複層化信託は、それぞれの家族の事情に応じて設計されるので、金融商品のように税法の条文で一律に決めることができない。そこで、それぞれの受益者の有する権利の内容(信託受益権の内容)に応じて、その保有とその帰属が決まると規定せざるを得ない。信託受益権の権利の内容は信託行為により決まり、信託行為とは、信託契約、遺言、自己信託による信託の設定行為を言う(信託法2条1項)。信託契約は委託者と受託者との合意で、遺言や自己信託では委託者の意思で決まるから、信託税制は信託の当事者の設定行為、いわば私的自治によることになる。
(4)受益者が収益受益者と元本受益者の場合 税法には収益受益権、元本受益権という用語そのものは出て来ないが、相続税法9条の3(受益者連続型信託の特例)の1項には受益者連続型信託に関する権利(「収益に関する権利」を含むものに限る)を有している場合の規定がある。相続税法基本通達9-13は、信託に関する収益受益権(信託に関する権利のうち信託財産の管理及び運用によって生ずる利益を受ける権利をいう)を有する者と元本受益権(同権利のうち信託財産自体を受ける権利をいう)を有する者とが異なる信託(「受益権が複層化された信託」という)についての合意等により終了した場合の取り扱いを定め、同通達9の3-1は受益権が複層化された受益者連続型信託についての取り扱いを定めている。要するに、収益受益者とは信託財産から生ずる収益を受領する権利を有する受益者であり、元本受益者とは信託財産又はその代替物を受領する権利を有する受益者であると考えられる。
何が収益で何が元本かは決めの問題であり、米国では信託行為の定めによるが、その定めがない場合は、ディフォールト・ルールとして統一元本収益法(the Uniform Principal and Income Act=UPIA)の定めに従うことになっている(脚注8)。
収益受益権の内容が総収益か純収益か、インカムゲインのみかキャピタルゲインを含むかは、信託行為の定めによる。例えば信託財産が賃貸不動産で、収益受益権の内容が総収益と定められていれば、減価償却費等を含む総賃料が収益受益者に給付される。この場合、受託者の行う信託会計では減価償却費等を認識しないが、収益受益者が不動産所得を申告する時にこれを費用として計上する。
受益権複層化信託において、元本受益権と収益受益権とに分割される場合は、資産・負債の保有と収益・費用の帰属とが直接に結びつかないことになるが、受益者が複数いる場合は、信託財産に属する資産・負債の全部(一部ではない)をそれぞれの受益者がそれぞれの有する権利の内容に応じて有するものとされる(前述、所得税法13条4項、所得税法施行令52条4項)ので、信託の期中においては、収益受益者は信託財産に属する資産・負債の全部を有するものとみなされ、信託財産から発生する収益の全部が収益受益者に帰属すると考えられる。また信託満期においては元本受益者が、信託財産に属する資産・負債の全部を有するものとみなされ、信託元本の全部が元本受益者に帰属するものと考えられる。
(5)受益者が定期金受益者と残余財産受益者の場合 年々の給付の額が変動せず定額であるものを「定期金」と言う。受益権複層化信託を活用し年金給付を行おうとする場合、配偶者の生活保障のためには、収益受益権ではなく定期金受益権が望ましい。現行の信託税制では年金給付は信託収益から支払うものと想定されているようであるが、信託収益は信託財産の種類や運用方法によっては必ずしも安定的に生じるとは限らない。安定した年金給付を行うためには、年次の信託収益が余剰の時は余剰収益額を信託勘定に留保し、逆に不足する時は、留保金を取り崩して定期金として支給することが望ましい。この場合、残余の財産を受領する権利を残余財産受益権と言う。
受益者等課税信託の場合、受益者へのキャッシュフローの給付が現に行われるか否かにかかわらず、受益者に対して信託財産から発生した収益の全額を課税するので、信託行為により余剰収益が定期金受益者に帰属する場合は、同受益者が信託期間中に課税され、信託満期に残余の余剰収益を受領する。逆に余剰収益が残余財産受益者に帰属する場合は、同受益者が信託期間中に課税され、信託満期に残余の余剰収益を受領すると考えられる。
(6)信託受益権の内容 信託受益権の内容が私的自治により決まるとしても、信託の当事者が受益権の内容を自由に決めることができるわけではない。信託受益権の内容には経済合理性が必要であり、信託の衣を取り外した場合には通常の権利関係が想定されなければならない。財務省はこのことを、「この規定は各受益者等に質的に均等に帰属させることまでを定めたものではなく、例えば、ある受益者は信託財産に属する土地の底地権を有するものとみなされるし、他の受益者はその土地の借地権を有するものとみなされる場合もあるといったように信託行為の実態に応じて帰属を判定するものと考えられる。この判定については仮に信託でないものとした場合に同様の権利関係を作り出そうとすれば、どのような権利関係になるかが参考になる。」と解説する(財務省「平成19年度改正税法のすべて」)。
(7)仮に信託でないものとした場合の信託類似の権利関係
① 不動産信託の場合 収益受益者が信託の期間中信託不動産から発生する賃料収入を受領し、元本受益者は信託の満期に信託不動産を受領する場合、この信託の権利関係は、不動産の売買において、売り手が不動産を譲渡して代金を受領したが、買い手への不動産の引き渡しは一定期間後とする場合の権利関係に類似する。売り手は引き渡し期間満了までは不動産を保有し続け、その間に不動産から発生する収益を受領し、買い手は期間満了後に不動産の引き渡しを受け、所有権移転登記をし、登録免許税を負担し、その後の不動産収益を享受する。
これに対し残余財産受益者が信託財産に属する資産を保有し、同受益者に信託費用・収益が帰属し、定期金受益者が信託期間中に信託元本から定期金を受領する信託の場合、この信託の権利関係は、売り手が不動産を譲渡して直ちにこれを買い手に引き渡したが、買い手の代金の支払いは一定期間の年賦とし、年賦金支払い完了後に買い手への所有権移転登記が行われる場合の権利関係に類似する。買い手は当初から不動産を保有し、これを使用・収益をするが、年賦支払いを完了して後に所有権移転登記を受ける。
またこの信託の権利関係は、負担付贈与において、贈与者が受贈者に贈与財産を引き渡したが、受贈者に対して毎年一定額の金銭の支払い債務を負担させる場合の権利関係に類似する。贈与者は受贈者から満期まで定期金を受領する。
② 公社債信託の場合 収益受益者は信託の期間中信託公社債から発生するクーポン収入等を受領し、元本受益者は信託の満期に信託公社債を受領する信託の場合、この信託の権利関係は公社債市場における着地取引に類似する。公社債の着地取引は将来の売り渡し時点(受渡日)での売り渡し価格
(受渡金額)を現時点で予め定める取引である。着地取引において売買予定の債券の権利は受渡日に買い手が売り手に受渡金額の全額を支払った時に移転する。売り手は受渡日までは売買予定の債券の権利を有するので、この社債のクーポン収入は売り手に帰属することになる。もし売り手が受渡日前に売渡予定の債券を市場売却してしまった場合は、売り手は満期までに同一の銘柄を同額面だけ買い戻して、買い手に対してこれを受け渡す必要がある。信託の満期に元本の受益者が受け渡しを受ける債券の取得価額は当初決めた受渡金額になる。
Ⅲ 受益権複層化信託の所得税に関する論点
1 受益者による資産・負債の保有、受益者に帰属する所得の種類 受益者等課税信託の場合、受益者が複数いるとしても、受託者は一人であるから、受託者一人に対する課税状況以上の課税関係になることはあり得ないと思われる。例えば、信託財産を構成する資産が不動産である場合、受託者に不動産所得が発生しているのであるから、みなし規定を適用したとしても、複数の受益者のいずれかに金融所得等の不動産所得以外の種類の所得が発生することにはならないし、複数の受益者の課税所得額の合計が受託者の不動産所得額と異なることはない。また、みなし規定を適用した結果、資産の保有者が、ある受益者から別の受益者に変わるとしても、信託財産を構成する資産の所有者が受託者であることに変わりはないので、新たな課税関係が発生することにはならないと考えられる。例えば、信託期間中は信託財産を構成する資産の保有者を収益受益者とみなし、同受益者に信託所得が帰属するが、信託満期になった時に資産の保有者が元本受益者と変わったとみなし、同受益者に信託財産が交付するとしても、両受益者間に新たに売買や贈与の課税が行われることはない。
2 所得計算における収益と費用の対応関係 所得課税を受ける受益者は受益者としての権利を現に有する者(所得税法13条1項)である。残余財産受益者は信託行為により指名されているので(信託法182条1項2号)、権利を現に有する者に含まれる(所得税基本通達13-7)。ある受益者の権利が信託の権利の一部にとどまっている場合でも、残余の権利を有する者が存しないか、または特定されていないときは、当該受益者が信託財産に属する資産・負債の全部を有するものとされ、当該受益者に信託収益・費用の全部が帰属するものとされる(所得税基本通達13-1)。信託収益・費用は当該信託の計算期間にかかわらず当該受益者のその年分の所得の計算上、総収入金額または必要経費に算入するものとされる(所得税基本通達13-2)。受益者の総収入金額または必要経費に算入する額は、信託財産から生ずる利益または損失を言うのではなく、当該信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用を当該受益者のこれらの金額として計算するものとされる(所得税基本通達13-3)。
受益者が複数いる場合の収益と費用の対応関係は、やはりそれぞれの受益者が有する信託の権利の内容に応じて決まる問題である(所得税法13条4項、所得税法施行令52条4項)。仮に元本受益者が信託財産を構成する土地の底地権を有するものとみなされるのであれば、当該土地の賃借人から受領する地代等の信託収益も当該土地にかかる固定資産税等の信託費用も元本受益者に帰属することになると思われる。これに対して、仮に収益の受益者が信託財産を構成する土地の借地権と土地の上に建設した建物を有するものとみなされるのであれば、この建物から生ずる賃貸収入等の信託収益も、この建物の減価償却費や底地権者に支払う地代等の信託費用も、共に収益受益者に帰属することになると思われる。
3 キャッシュフローの給付と収益・費用の帰属 信託の権利の内容とは、信託実務家にとっては受益者へのキャッシュフロー又は信託財産の交付の内容である。受益者が複数いる場合、信託の収益・費用の帰属は、一般的には、担税力から考えてキャッシュフローの受領者と考えられているが、キャッシュフローの受領者は必ずしも収益の受益者だけとは限らない。例えば定期金の受益者は、定期金額に対して信託収益額が不足するときには、不足額は信託元本を取り崩して支給するので、収益だけではなく元本の一部の受益権も有することになる。逆に定期金額に対して信託収益額が余剰のときには、余剰額を留保して信託元本に追加するので、残余財産受益者は元本だけではなく収益の一部の受益権も有することになる。また、法人信託ではキャッシュフローの交付の順位において優先・劣後する点で優先受益権と劣後受益権に分けることがある。定期金受益者は信託収益が不足するときには、信託元本を取り崩して支給するので、優先受益者であり、残余財産受益者は劣後受益者であるとも考えられる。収益受益者は毎年キャッシュフローの交付を受け、元本受益者は信託財産の交付を信託満期まで待たなければならないので、両者の関係はやはり優先・劣後の関係にある。しかし、金銭の信託において信託金を証券のポートフォリオ運用する場合、収益受益者が運用リスクを負担し、信託元本を保証しているのであれば、むしろ元本受益者が優先受益者と考えられる。実務においては受益権の内容に収益受益権と元本受益権と言った二分法の適用はなく、権利の内容は信託行為の規定の仕方に依存するファジーなものと思われる。
4 所得課税の受益者間の偏頗性 ストリップス債は利付国債のクーポン部分と元本部分を分離した一種の割引債券で、分離元本振替国債と分離利息振替国債とがある。ストリップス債の保有は法人に限定されている。投資法人に課税される金額は分離前の利付国債のクーポン支払額ではない。課税所得は、それぞれの投資家が有するそれぞれ割引債券の償還差益である。
資本市場における収益とは投下資本を上回るリターンのことをいう。もし投資家が収益受益権を市場で買ったならば、収益受益権の取得価額が投下資本であり、収益受益者の年次の所得は、信託収益額(クーポン額)の全部ではなく、ストリップス債への投資と同じように、年次の信託収益額から取得価額の年次の償却額を控除した残額になるはずである。同様に、もし元本受益権を市場で買ったならば、当該元本受益権の取得価額が投下資本であり、元本受益者の所得は信託満期に受領する信託元本相当額(債券元本償還額)から元本受益権の取得価額を控除した残額になるはずである(脚注9)。
信託財産から発生する所得は担税力から収益受益者に帰属することが望ましいので、信託財産を構成する資産がストリップス債ではなく利付債の場合は、信託収益の所得課税はクーポンの全額について収益受益者に対してのみ行われ、元本受益者が信託満期に信託財産を受領しても課税はされない。この受益者の間の課税の偏頗性については、収益受益者が委託者の場合はまだしも、委託者以外の者の場合は、その者が対価または贈与税等を支払っているために負担感がある(脚注10)。米国では贈与者課税であるから贈与を受けた収益受益者は贈与税を支払っていないので負担感が少ない(脚注11)。
おわりに
金融商品の場合は税務の取り扱いが税法の条文で一律に決まっている一方、家族の為の受益権複層化信託の場合はそうではないことに不安を抱く向きがないわけではない。しかし、家族の為の信託の設計に長年携わってきた筆者としては、現行法の信託の設計に対応する柔軟な取扱いを高く評価しているものである。
脚注
1 中世英国では、土地に対して衡平法(equity)による財産権と普通法(common law)による財産権とが併存した。
2 信託協会 平成27年度税制改正に関する要望:Ⅱ.要望項目1.信託に関する税制措置(6)。平成26年度の要望:Ⅱ.要望項目1.信託に関する税制措置(6)。
3 平成27年末までは非課税(租税特別措置法37条の15第1項)。
4 債券の収益は必ずしも安定しない。例えば債券が外貨建ての場合は受領する円貨の額が為替レートにより変動する。債券の満期が信託の満期より早く来る場合や、債券が満期前に繰り上げ償還される場合は、その後は従前の収益水準を維持できないことがある。債券を信託の満期前に中途換金した場合は、その時点の市場利率や発行体の信用の変化により当初の取得価額で売れるとは限らない。また債券がデフォールトになる危険もある。
5 米国の委託者定期金留保信託では、年次の信託収益が定期金額より多い場合、委託者は超過収益に対して課税されるが、信託満期に超過収益の累積額を受領することはできない。なお、信託給付が信託財産の年次の評価額の一定割合である場合はGrantor Retained Unitrust と呼ばれ、適格な給付であるとされている。
6 賃貸不動産からの収益は、テナントの退出、賃貸契約の終了、賃料の改定、建物の大規模修繕、火災や自然災害による滅失や毀損等により変動する。
7 吉村政穂 金融庁金融研究センター特別研究員「受益権が複層化された信託に対する課税ルールに関する一考察」2012年ディスカッション・ペーパーは米国の課税ルールを参考に、わが国においても、「受益者等」の範囲を定めるにあたって直接帰属の擬制を働かせるだけの実質が必要であり、それを欠く場合には、単一種類の受益者等のみが信託財産を保有し、その他の受益者は信託財産との関係が切断されるという仕組みを導入することが可能であることを主張する。
8 Jacqueline A. Patterson, Esq.「The Income Taxation of Trusts and Estates」page 108-26
9 金融商品会計に関する実務指針105
10 この所得課税における偏頗性の是正のためには、年次の信託給付を定期金とし、信託収益を定期金受益者と残余財産受益者の両方にそれぞれの相続税評価額で案分して帰属させることが望ましい。信託財産を構成する資産が公社債のような源泉分離課税になる財産である場合は、残余財産受益者はその持分の信託収益額に相当するキャッシュフローを受領しないで、これを信託元本に追加することができる。残余財産受益者の信託元本に対する持分は信託期間の経過と共に徐々に増加し信託満期には100%になる。定期金受益者はその持分の信託収益に対する税額を控除した純額のキャッシュフローを受領する。
現行の財産評価基本通達によれば、収益受益権の相続税評価額は、信託財産の税込収益額に対して割引率を適用して現在価値を算出して計算する(税込割引)ことになっているが、源泉分離課税になる財産が信託財産の場合、収益受益者が受領するキャッシュフローは信託財産の税引き後の収益(実受領額)であるから、税引き後の信託収益を税引き後の割引率を適用して現在価値を算出して計算する(税引き割引)方が合理的である。
具体的にいえば、各受益者が相続税評価額相当の投資をしたものと考えて、各受益者のキャッシュフローからそれぞれの受益者の源泉税を控除し、各受益者が受領すべき税引きキャッシュフロー額(理論受領額)を計算する場合、これを税込割引で計算すると、収益受益者の理論受領額が実受領額を上回るのに対し、税引き割引で計算すると理論受領額が実受領額に一致する。
11 米国内国歳入法102条(a)は総所得に贈与等により取得する財産の価値を含まない(非課税)としたうえ、(b)はその例外として、受贈財産から発生する収益又は贈与等が財産からの収益の収受権である場合は、その収益の額は総収益に含む(課税する)としている。
受益権複層化信託の所得課税
高橋倫彦
はじめに
1 本稿の趣旨 米国の伝統的な家族の為の信託では、配偶者が生涯にわたって年金給付を受け(life interest:生涯受益権)、配偶者が死亡後、子供が残余の信託財産を相続する(remainder:残余財産受益権)ことが多い。こうした家族の為の信託は我が国において公的年金の給付額の引き下げが懸念される中、これを補完する私的年金として残された配偶者等の長生きリスクをカバーするのに好適である。この信託は信託受益権が質的に異なる受益権に分割される最も信託らしい信託(以下「受益権複層化信託」という)である(図参照)。
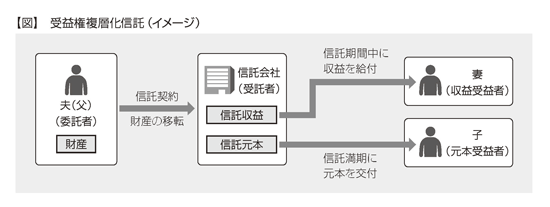
しかし、信託の実務家も税理士等専門家もこの信託の利用に躊躇する向きが多いようである。この信託では、信託の受益者が信託財産を構成する資産を持分により共有する(単層化)のではなく、この資産を重畳的に合有している(複層化)と考えられる(脚注1)ので、この信託財産から発生した信託収益がどの受益者にどのように帰属するのか、この信託の受益権が相続等により移転した場合に受益権の課税価額がどのように評価されるのか等について、現行税制ではその取り扱いが必ずしも明瞭ではない為である。
我が国においてこの信託の利用が期待される中で、税制の不透明さがその利用の障害になるような事態は解消しなければならない。一般社団法人信託協会は実務家と専門家による研究会を組成してこの検討を行っている。また税制改正の要望項目として、受益権複層化信託の課税関係を明確化する観点から所要の税法上の措置を講じること、及び受益者連続型信託に関する権利の価額の特例の対象から、例えば、家族の扶養のための給付や資産承継を目的とする一定の類型の信託を除外することを要望している(脚注2)。
2 信託実務の観点 受益権複層化信託の税務の取り扱いの明確化は、現行法のもとでは困難であり、法改正が必要であるとの論調が多いように見受けられるが、信託実務においては、この信託に対する顧客ニーズが強いので、法改正を待つ余裕がない。現行法の良し悪しは別として、これを忠実に適用した場合の税務の取り扱いの明確化が望まれる。
しかし、受益権複層化信託の公表された事例も論文も少ないので、税務当局も税務の専門家もその明確化のための検討を進め難い状況のように見受けられる。幸い信託実務の現場には、現実に起きている事例が豊富にある。筆者は税務の専門家の方々の今後の検討の一助になることを目的として、長年信託業務に従事した経験を基に、手元の事例に基づき、利用者の意図(信託目的)に照らして、信託の権利の内容と、経済合理性とを根拠に、現行法の下における税務の取り扱いを明らかにすることを試みた。今後の明確化のための一助になることを期待したい。
なお、本稿は受益権複層化信託のうち、「受益者等課税信託」の類型を対象として、その所得課税を分析する。法人課税信託等の他の課税類型は対象としない。信託受益権の相続税評価、相続・贈与課税及び受益者連続型信託の問題については、誌面の都合から別の機会に譲る。また、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。
本稿では、信託実務で遭遇する受益権複層化信託の事例をここに紹介し、質的に異なる受益者が信託財産に属する資産・負債をどのように保有し、どの受益者への収益・費用が帰属するかを考える。
Ⅰ 現実に起っている事例と問題点
1 当初信託財産の種類が異なる事例
(1)債券の場合 債券の場合、債券の年次のクーポン収益は一定であることから、信託受益権を収益受益権と元本受益権とに分割し、年次のクーポン収益から得られるキャッシュフローを年金として収益受益者に給付することが多い。この受益権複層化信託では、クーポン収益は収益受益者に帰属し、利子所得として所得税等が源泉徴収され、他の所得から分離課税される(租税特別措置法3条1項)。債券の償還元本のキャッシュフローは元本受益者に交付され、債券の償還差益は元本受益者に帰属し、雑所得として課税される。信託の期中において債券の売買損益が発生した場合は、その売買損益は元本受益者に帰属し、譲渡所得税が非課税とされる(脚注3)。信託の満期が到来したが、信託財産の債券の満期が到来しない場合は、当初信託財産である当該債券はそのまま元本受益者に交付される。
しかし、信託債券が繰り上げ償還されれば、その後の信託期間の信託収益額が当初の信託収益額と同じとは限らない(脚注4)。年次の信託収益から得られるキャッシュフローは税込ではなく源泉税引きであり、収益受益者にのみに源泉徴収税を負担させてよいのかどうか、信託所得を収益受益者のみへ帰属させる税法の明文の規定は存在しない。
(2)株式や投資信託の場合 株式配当から発生する配当所得等の金額は必ずしも安定しないので、その将来の信託収益額の見積もりが困難である。このため信託受益権を収益受益権と元本受益権とに分割する場合、収益受益権の相続税評価が難しい。これに対し、委託者が定期金受益権を留保し、残余財産受益権を家族に贈与する仕組みを採用する、米国の委託者定期金留保信託(Grantor Retained Annuity Trust)では、定期金が年次の信託収益額にかかわらず一定額の定期金を給付する場合に限って適格とされ、残余財産受益権の贈与税の評価額は信託財産を構成する資産の評価額から定期金の現在価値相当額を控除した額とすることができる(米国内国歳入法2702条)。定期金の給付は、実際の信託収益額が定期金額より少なかった場合は不足額を信託元本から取り崩して行い、定期金額より多かった場合は余剰額を信託元本に追加する(脚注5)。
(3)金銭の場合 投資家が金銭信託し、信託金を有価証券にポートフォリオ運用した場合、運用益はインカムゲインのみではなく、キャピタルゲインもある。信託期間中は運用益を収益受益者に給付する。当初信託財産は金銭であるから、信託満期にはポートフォリオを換金し、信託元本相当額(当初信託金額)の金銭を元本受益者に交付し、余剰金があれば、これを収益受益者に交付することになる。しかし、ポートフォリオ運用の場合、将来の運用益が不確実で信託収益額の見積もりが困難であるために、収益受益権の相続税評価をすることができない。また、信託満期に運用損失が残った場合、収益受益者がこの損失補填をしないと、元本受益者への償還が元本割れになる。信託実務ではポートフォリオ運用目的の金銭信託は原則として受益権を複層化しない。
(4)不動産の場合 収益不動産から発生する収益は必ずしも安定しない(脚注6)。その所得は不動産所得や事業所得等として他の所得と通算され総合課税されるので、しばしば減価償却の扱いが問題となる。賃貸物件が信託財産である信託において、もし収益受益者に配布される収益が減価償却費等を控除した純収益である場合は、諸経費を差し引いた純賃料が収益受益者に帰属し、減価償却費相当額の収益は信託勘定に留保され、元本受益者に帰属することになると思われる。この場合、元本受益者は信託の満期に不動産と減価償却費相当額の金銭を受領することになる。
これに対して減価償却費等の控除前の総収益である場合は、総賃料及び減価償却費を含む諸経費は収益受益者に帰属することになると思われる。この場合は、収益受益権の評価額が減価償却費等相当額だけ高くなり、元本受益権の評価額がその分安くなる。信託の満期に元本の受益者が交付を受ける資産は減価償却後の資産になる。
2 信託受益権の種類が異なる事例
(1)収益受益権と元本受益権とに分ける場合 会計的に信託利益を受益者配当として支払うためには、原則として、信託決算により信託利益を確定しなければならない。信託決算を待たずに信託給付を行う場合は、信託元本を取り崩して支給することになる。しかし実務では、信託利益が確実に得られる見込みがある場合は信託決算を待たずに信託収益(収入)から信託給付を行っている。
資産運用の観点から見ると、収益受益権と元本受益権とに分けるということは、収益受益者が運用リスクを負担し、年次のキャッシュフローの変動を甘受することを意味する。これに対し定期金受益権と残余財産受益権とに分けるということは、残余財産受益者が運用リスクを負担し、信託満期の残余財産の変動を甘受することを意味する。
信託収益から源泉税が徴収されて、受託者が税引きキャッシュフローを受領する場合は、収益受益者の課税所得額は信託財産全体の税込の総収益額であるが、キャッシュフローの受領額は税引き額になる。
(2)定期金受益権と残余財産受益権とに分ける場合 定期金受益者の権利の内容が信託元本の取崩しの場合は、定期金受益者は信託財産に属する資産・負債を保有せず、信託収益・費用は定期金受益者に帰属しない。定期金受益権の内容は元本を分割して受領する一種の金銭債権になる。この場合、残余財産受益者が信託財産に属する資産・負債を保有するとみなされるので、残余財産受益者は収益の受益者を兼ねることになる。その結果、信託の期間中は、同受益者に信託収益・費用が帰属し、同受益者に信託所得を申告納税する義務が出てくる。
Ⅱ 現行法における信託の設定、所得に対する課税の原則
1 信託の設定課税 受益者等課税信託の設定時において、受益者が存する場合は受託者に対する課税はない。受益者が法人の場合は受益者となる法人(法人受益者)が適正な対価を負担していない場合、個人委託者が信託設定時に信託財産をその法人に贈与したものとされる(所得税法67条の3第3項)。また個人の法人への資産の贈与は譲渡とみなされるので(所得税法59条1項)、個人委託者が信託財産を時価で譲渡したものとして時価と取得価額の差額に対して譲渡所得税が課税される。法人受益者が対価を負担している場合は、その対価の額を収入金額として譲渡所得の計算をするが、その対価の額が時価の2分の1未満の場合は、時価を収入金額として譲渡所得の計算をするものとされている。法人受益者は時価と対価との差額を受贈益として課税される。
受益者の有する信託に関する権利がその信託に関する権利の全部でない場合において、受益者が1名である場合は、その受益者がその信託に関する権利の全部を有するものとみなし、受益者が複数の場合は、その信託に関する権利の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとみなされる(所得税法施行令197条の3第5項)。
2 信託の所得課税の原則
(1)一般原則 相続、遺贈又は個人からの贈与により財産を取得する場合、その財産に対して所得税は課されない(所得税法9条1項16号)が、このように取得した財産から発生する収益に対しては所得税が課税される。
信託財産を構成する資産は法形式的には受託者の所有であるから、信託財産から発生する損益は受託者に帰属するが、受益者等課税信託の場合、税務的には信託財産を構成する資産は受益者の保有とみなされ、信託収益・費用は受益者に帰属するとみなされる(所得税法13条1項)。この取扱いは、信託制度を受益者に所得を分配する導管(パススルー)に過ぎないと考える導管論に基づく。
これに対して受益者等課税信託でない資産証券化信託等では、信託財産を一種の法人とみなし、信託財産に属する資産から発生するキャッシュフローをいくつかの種類のトランシュ(金融商品としての受益権)に切り分けて、信託受益権を金融商品(ペイスルー)として投資家に販売するので、これを取得した投資家の所得は金融所得になる。受益権複層化信託においても金融商品と同様の税務の取り扱いを適用する可能性を検討する研究がある(脚注7)。
特定受益者(受益者等課税信託の個人受益者)が、信託から生ずる不動産所得を有する場合に、その年分の不動産所得の金額の計算上信託による不動産所得の損失の金額があるときは、当該損失の金額に相当する金額は、不動産所得の金額の計算の規定および損益通算の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなされる(租税特別措置法41条の4の2第1項)。
(2)譲渡の所得課税 信託財産に属する資産の譲渡よる所得は譲渡所得になり、またその資産が権利の目的になっている信託の権利の譲渡による所得も譲渡所得になる。譲渡所得の収入金額はその対価になる(所得税基本通達33-1の7)。いわゆる物の信託の場合、信託財産の譲渡所得課税はその多くが元本の受益者に対して行われる。
信託の設定により信託財産に属することになった資産の譲渡にかかる譲渡所得の計算基礎となる資産の取得費は、その委託者がその資産を引き続き有しているものとして計算される(所得税基本通達33-1の7(4))。信託満期まで資産の売却を行わない場合は、元本受益者がその資産について委託者の取得価額を引き継ぐ。贈与などにより取得した資産の譲渡所得の計算における取得費については贈与者などが引き続き所有していたものとみなされる(所得税法60条)。
受益者が複数いる場合に、信託財産の譲渡益がどの受益者に帰属するかは、それぞれの受益者が有する権利の内容に応じて決まる問題である。
(3)受益者が複数いる場合 受益者が複数いる場合は、信託財産に属する資産・負債の全部をそれぞれの受益者がそれぞれの有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益・費用の全部がそれぞれの受益者の有する信託の権利の内容に応じて帰せられるものとされ、この受益者には信託の変更権限を有するみなし受益者(所得税法13条2項)を含むものとされる(所得税法13条4項、所得税法施行令52条4項)。家族の為の受益権複層化信託は、それぞれの家族の事情に応じて設計されるので、金融商品のように税法の条文で一律に決めることができない。そこで、それぞれの受益者の有する権利の内容(信託受益権の内容)に応じて、その保有とその帰属が決まると規定せざるを得ない。信託受益権の権利の内容は信託行為により決まり、信託行為とは、信託契約、遺言、自己信託による信託の設定行為を言う(信託法2条1項)。信託契約は委託者と受託者との合意で、遺言や自己信託では委託者の意思で決まるから、信託税制は信託の当事者の設定行為、いわば私的自治によることになる。
(4)受益者が収益受益者と元本受益者の場合 税法には収益受益権、元本受益権という用語そのものは出て来ないが、相続税法9条の3(受益者連続型信託の特例)の1項には受益者連続型信託に関する権利(「収益に関する権利」を含むものに限る)を有している場合の規定がある。相続税法基本通達9-13は、信託に関する収益受益権(信託に関する権利のうち信託財産の管理及び運用によって生ずる利益を受ける権利をいう)を有する者と元本受益権(同権利のうち信託財産自体を受ける権利をいう)を有する者とが異なる信託(「受益権が複層化された信託」という)についての合意等により終了した場合の取り扱いを定め、同通達9の3-1は受益権が複層化された受益者連続型信託についての取り扱いを定めている。要するに、収益受益者とは信託財産から生ずる収益を受領する権利を有する受益者であり、元本受益者とは信託財産又はその代替物を受領する権利を有する受益者であると考えられる。
何が収益で何が元本かは決めの問題であり、米国では信託行為の定めによるが、その定めがない場合は、ディフォールト・ルールとして統一元本収益法(the Uniform Principal and Income Act=UPIA)の定めに従うことになっている(脚注8)。
収益受益権の内容が総収益か純収益か、インカムゲインのみかキャピタルゲインを含むかは、信託行為の定めによる。例えば信託財産が賃貸不動産で、収益受益権の内容が総収益と定められていれば、減価償却費等を含む総賃料が収益受益者に給付される。この場合、受託者の行う信託会計では減価償却費等を認識しないが、収益受益者が不動産所得を申告する時にこれを費用として計上する。
受益権複層化信託において、元本受益権と収益受益権とに分割される場合は、資産・負債の保有と収益・費用の帰属とが直接に結びつかないことになるが、受益者が複数いる場合は、信託財産に属する資産・負債の全部(一部ではない)をそれぞれの受益者がそれぞれの有する権利の内容に応じて有するものとされる(前述、所得税法13条4項、所得税法施行令52条4項)ので、信託の期中においては、収益受益者は信託財産に属する資産・負債の全部を有するものとみなされ、信託財産から発生する収益の全部が収益受益者に帰属すると考えられる。また信託満期においては元本受益者が、信託財産に属する資産・負債の全部を有するものとみなされ、信託元本の全部が元本受益者に帰属するものと考えられる。
(5)受益者が定期金受益者と残余財産受益者の場合 年々の給付の額が変動せず定額であるものを「定期金」と言う。受益権複層化信託を活用し年金給付を行おうとする場合、配偶者の生活保障のためには、収益受益権ではなく定期金受益権が望ましい。現行の信託税制では年金給付は信託収益から支払うものと想定されているようであるが、信託収益は信託財産の種類や運用方法によっては必ずしも安定的に生じるとは限らない。安定した年金給付を行うためには、年次の信託収益が余剰の時は余剰収益額を信託勘定に留保し、逆に不足する時は、留保金を取り崩して定期金として支給することが望ましい。この場合、残余の財産を受領する権利を残余財産受益権と言う。
受益者等課税信託の場合、受益者へのキャッシュフローの給付が現に行われるか否かにかかわらず、受益者に対して信託財産から発生した収益の全額を課税するので、信託行為により余剰収益が定期金受益者に帰属する場合は、同受益者が信託期間中に課税され、信託満期に残余の余剰収益を受領する。逆に余剰収益が残余財産受益者に帰属する場合は、同受益者が信託期間中に課税され、信託満期に残余の余剰収益を受領すると考えられる。
(6)信託受益権の内容 信託受益権の内容が私的自治により決まるとしても、信託の当事者が受益権の内容を自由に決めることができるわけではない。信託受益権の内容には経済合理性が必要であり、信託の衣を取り外した場合には通常の権利関係が想定されなければならない。財務省はこのことを、「この規定は各受益者等に質的に均等に帰属させることまでを定めたものではなく、例えば、ある受益者は信託財産に属する土地の底地権を有するものとみなされるし、他の受益者はその土地の借地権を有するものとみなされる場合もあるといったように信託行為の実態に応じて帰属を判定するものと考えられる。この判定については仮に信託でないものとした場合に同様の権利関係を作り出そうとすれば、どのような権利関係になるかが参考になる。」と解説する(財務省「平成19年度改正税法のすべて」)。
(7)仮に信託でないものとした場合の信託類似の権利関係
① 不動産信託の場合 収益受益者が信託の期間中信託不動産から発生する賃料収入を受領し、元本受益者は信託の満期に信託不動産を受領する場合、この信託の権利関係は、不動産の売買において、売り手が不動産を譲渡して代金を受領したが、買い手への不動産の引き渡しは一定期間後とする場合の権利関係に類似する。売り手は引き渡し期間満了までは不動産を保有し続け、その間に不動産から発生する収益を受領し、買い手は期間満了後に不動産の引き渡しを受け、所有権移転登記をし、登録免許税を負担し、その後の不動産収益を享受する。
これに対し残余財産受益者が信託財産に属する資産を保有し、同受益者に信託費用・収益が帰属し、定期金受益者が信託期間中に信託元本から定期金を受領する信託の場合、この信託の権利関係は、売り手が不動産を譲渡して直ちにこれを買い手に引き渡したが、買い手の代金の支払いは一定期間の年賦とし、年賦金支払い完了後に買い手への所有権移転登記が行われる場合の権利関係に類似する。買い手は当初から不動産を保有し、これを使用・収益をするが、年賦支払いを完了して後に所有権移転登記を受ける。
またこの信託の権利関係は、負担付贈与において、贈与者が受贈者に贈与財産を引き渡したが、受贈者に対して毎年一定額の金銭の支払い債務を負担させる場合の権利関係に類似する。贈与者は受贈者から満期まで定期金を受領する。
② 公社債信託の場合 収益受益者は信託の期間中信託公社債から発生するクーポン収入等を受領し、元本受益者は信託の満期に信託公社債を受領する信託の場合、この信託の権利関係は公社債市場における着地取引に類似する。公社債の着地取引は将来の売り渡し時点(受渡日)での売り渡し価格
(受渡金額)を現時点で予め定める取引である。着地取引において売買予定の債券の権利は受渡日に買い手が売り手に受渡金額の全額を支払った時に移転する。売り手は受渡日までは売買予定の債券の権利を有するので、この社債のクーポン収入は売り手に帰属することになる。もし売り手が受渡日前に売渡予定の債券を市場売却してしまった場合は、売り手は満期までに同一の銘柄を同額面だけ買い戻して、買い手に対してこれを受け渡す必要がある。信託の満期に元本の受益者が受け渡しを受ける債券の取得価額は当初決めた受渡金額になる。
Ⅲ 受益権複層化信託の所得税に関する論点
1 受益者による資産・負債の保有、受益者に帰属する所得の種類 受益者等課税信託の場合、受益者が複数いるとしても、受託者は一人であるから、受託者一人に対する課税状況以上の課税関係になることはあり得ないと思われる。例えば、信託財産を構成する資産が不動産である場合、受託者に不動産所得が発生しているのであるから、みなし規定を適用したとしても、複数の受益者のいずれかに金融所得等の不動産所得以外の種類の所得が発生することにはならないし、複数の受益者の課税所得額の合計が受託者の不動産所得額と異なることはない。また、みなし規定を適用した結果、資産の保有者が、ある受益者から別の受益者に変わるとしても、信託財産を構成する資産の所有者が受託者であることに変わりはないので、新たな課税関係が発生することにはならないと考えられる。例えば、信託期間中は信託財産を構成する資産の保有者を収益受益者とみなし、同受益者に信託所得が帰属するが、信託満期になった時に資産の保有者が元本受益者と変わったとみなし、同受益者に信託財産が交付するとしても、両受益者間に新たに売買や贈与の課税が行われることはない。
2 所得計算における収益と費用の対応関係 所得課税を受ける受益者は受益者としての権利を現に有する者(所得税法13条1項)である。残余財産受益者は信託行為により指名されているので(信託法182条1項2号)、権利を現に有する者に含まれる(所得税基本通達13-7)。ある受益者の権利が信託の権利の一部にとどまっている場合でも、残余の権利を有する者が存しないか、または特定されていないときは、当該受益者が信託財産に属する資産・負債の全部を有するものとされ、当該受益者に信託収益・費用の全部が帰属するものとされる(所得税基本通達13-1)。信託収益・費用は当該信託の計算期間にかかわらず当該受益者のその年分の所得の計算上、総収入金額または必要経費に算入するものとされる(所得税基本通達13-2)。受益者の総収入金額または必要経費に算入する額は、信託財産から生ずる利益または損失を言うのではなく、当該信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用を当該受益者のこれらの金額として計算するものとされる(所得税基本通達13-3)。
受益者が複数いる場合の収益と費用の対応関係は、やはりそれぞれの受益者が有する信託の権利の内容に応じて決まる問題である(所得税法13条4項、所得税法施行令52条4項)。仮に元本受益者が信託財産を構成する土地の底地権を有するものとみなされるのであれば、当該土地の賃借人から受領する地代等の信託収益も当該土地にかかる固定資産税等の信託費用も元本受益者に帰属することになると思われる。これに対して、仮に収益の受益者が信託財産を構成する土地の借地権と土地の上に建設した建物を有するものとみなされるのであれば、この建物から生ずる賃貸収入等の信託収益も、この建物の減価償却費や底地権者に支払う地代等の信託費用も、共に収益受益者に帰属することになると思われる。
3 キャッシュフローの給付と収益・費用の帰属 信託の権利の内容とは、信託実務家にとっては受益者へのキャッシュフロー又は信託財産の交付の内容である。受益者が複数いる場合、信託の収益・費用の帰属は、一般的には、担税力から考えてキャッシュフローの受領者と考えられているが、キャッシュフローの受領者は必ずしも収益の受益者だけとは限らない。例えば定期金の受益者は、定期金額に対して信託収益額が不足するときには、不足額は信託元本を取り崩して支給するので、収益だけではなく元本の一部の受益権も有することになる。逆に定期金額に対して信託収益額が余剰のときには、余剰額を留保して信託元本に追加するので、残余財産受益者は元本だけではなく収益の一部の受益権も有することになる。また、法人信託ではキャッシュフローの交付の順位において優先・劣後する点で優先受益権と劣後受益権に分けることがある。定期金受益者は信託収益が不足するときには、信託元本を取り崩して支給するので、優先受益者であり、残余財産受益者は劣後受益者であるとも考えられる。収益受益者は毎年キャッシュフローの交付を受け、元本受益者は信託財産の交付を信託満期まで待たなければならないので、両者の関係はやはり優先・劣後の関係にある。しかし、金銭の信託において信託金を証券のポートフォリオ運用する場合、収益受益者が運用リスクを負担し、信託元本を保証しているのであれば、むしろ元本受益者が優先受益者と考えられる。実務においては受益権の内容に収益受益権と元本受益権と言った二分法の適用はなく、権利の内容は信託行為の規定の仕方に依存するファジーなものと思われる。
4 所得課税の受益者間の偏頗性 ストリップス債は利付国債のクーポン部分と元本部分を分離した一種の割引債券で、分離元本振替国債と分離利息振替国債とがある。ストリップス債の保有は法人に限定されている。投資法人に課税される金額は分離前の利付国債のクーポン支払額ではない。課税所得は、それぞれの投資家が有するそれぞれ割引債券の償還差益である。
資本市場における収益とは投下資本を上回るリターンのことをいう。もし投資家が収益受益権を市場で買ったならば、収益受益権の取得価額が投下資本であり、収益受益者の年次の所得は、信託収益額(クーポン額)の全部ではなく、ストリップス債への投資と同じように、年次の信託収益額から取得価額の年次の償却額を控除した残額になるはずである。同様に、もし元本受益権を市場で買ったならば、当該元本受益権の取得価額が投下資本であり、元本受益者の所得は信託満期に受領する信託元本相当額(債券元本償還額)から元本受益権の取得価額を控除した残額になるはずである(脚注9)。
信託財産から発生する所得は担税力から収益受益者に帰属することが望ましいので、信託財産を構成する資産がストリップス債ではなく利付債の場合は、信託収益の所得課税はクーポンの全額について収益受益者に対してのみ行われ、元本受益者が信託満期に信託財産を受領しても課税はされない。この受益者の間の課税の偏頗性については、収益受益者が委託者の場合はまだしも、委託者以外の者の場合は、その者が対価または贈与税等を支払っているために負担感がある(脚注10)。米国では贈与者課税であるから贈与を受けた収益受益者は贈与税を支払っていないので負担感が少ない(脚注11)。
おわりに
金融商品の場合は税務の取り扱いが税法の条文で一律に決まっている一方、家族の為の受益権複層化信託の場合はそうではないことに不安を抱く向きがないわけではない。しかし、家族の為の信託の設計に長年携わってきた筆者としては、現行法の信託の設計に対応する柔軟な取扱いを高く評価しているものである。
| 高橋倫彦 たかはし ともひこ 東洋信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)、外資系の信託銀行を経て、最近までベルニナ信託(現FPG信託)の取締役。富裕層向けの信託の設計では15年以上の経験を有す。家族信託の分野では日本でも数少ない専門家。 著書に『信託を活用した ケース別 相続・贈与・事業承継対策』日本法令(共著)がある。 |
脚注
1 中世英国では、土地に対して衡平法(equity)による財産権と普通法(common law)による財産権とが併存した。
2 信託協会 平成27年度税制改正に関する要望:Ⅱ.要望項目1.信託に関する税制措置(6)。平成26年度の要望:Ⅱ.要望項目1.信託に関する税制措置(6)。
3 平成27年末までは非課税(租税特別措置法37条の15第1項)。
4 債券の収益は必ずしも安定しない。例えば債券が外貨建ての場合は受領する円貨の額が為替レートにより変動する。債券の満期が信託の満期より早く来る場合や、債券が満期前に繰り上げ償還される場合は、その後は従前の収益水準を維持できないことがある。債券を信託の満期前に中途換金した場合は、その時点の市場利率や発行体の信用の変化により当初の取得価額で売れるとは限らない。また債券がデフォールトになる危険もある。
5 米国の委託者定期金留保信託では、年次の信託収益が定期金額より多い場合、委託者は超過収益に対して課税されるが、信託満期に超過収益の累積額を受領することはできない。なお、信託給付が信託財産の年次の評価額の一定割合である場合はGrantor Retained Unitrust と呼ばれ、適格な給付であるとされている。
6 賃貸不動産からの収益は、テナントの退出、賃貸契約の終了、賃料の改定、建物の大規模修繕、火災や自然災害による滅失や毀損等により変動する。
7 吉村政穂 金融庁金融研究センター特別研究員「受益権が複層化された信託に対する課税ルールに関する一考察」2012年ディスカッション・ペーパーは米国の課税ルールを参考に、わが国においても、「受益者等」の範囲を定めるにあたって直接帰属の擬制を働かせるだけの実質が必要であり、それを欠く場合には、単一種類の受益者等のみが信託財産を保有し、その他の受益者は信託財産との関係が切断されるという仕組みを導入することが可能であることを主張する。
8 Jacqueline A. Patterson, Esq.「The Income Taxation of Trusts and Estates」page 108-26
9 金融商品会計に関する実務指針105
10 この所得課税における偏頗性の是正のためには、年次の信託給付を定期金とし、信託収益を定期金受益者と残余財産受益者の両方にそれぞれの相続税評価額で案分して帰属させることが望ましい。信託財産を構成する資産が公社債のような源泉分離課税になる財産である場合は、残余財産受益者はその持分の信託収益額に相当するキャッシュフローを受領しないで、これを信託元本に追加することができる。残余財産受益者の信託元本に対する持分は信託期間の経過と共に徐々に増加し信託満期には100%になる。定期金受益者はその持分の信託収益に対する税額を控除した純額のキャッシュフローを受領する。
現行の財産評価基本通達によれば、収益受益権の相続税評価額は、信託財産の税込収益額に対して割引率を適用して現在価値を算出して計算する(税込割引)ことになっているが、源泉分離課税になる財産が信託財産の場合、収益受益者が受領するキャッシュフローは信託財産の税引き後の収益(実受領額)であるから、税引き後の信託収益を税引き後の割引率を適用して現在価値を算出して計算する(税引き割引)方が合理的である。
具体的にいえば、各受益者が相続税評価額相当の投資をしたものと考えて、各受益者のキャッシュフローからそれぞれの受益者の源泉税を控除し、各受益者が受領すべき税引きキャッシュフロー額(理論受領額)を計算する場合、これを税込割引で計算すると、収益受益者の理論受領額が実受領額を上回るのに対し、税引き割引で計算すると理論受領額が実受領額に一致する。
11 米国内国歳入法102条(a)は総所得に贈与等により取得する財産の価値を含まない(非課税)としたうえ、(b)はその例外として、受贈財産から発生する収益又は贈与等が財産からの収益の収受権である場合は、その収益の額は総収益に含む(課税する)としている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















