解説記事2015年12月28日 【ニュース特集】 軽減税率導入後の事業者の経理処理(2015年12月28日号・№624)
ニュース特集
現行制度とインボイス制度の違いは?
軽減税率導入後の事業者の経理処理
消費税の軽減税率制度が平成29年4月1日から導入されることが決まった。これに併せて、平成33年4月1日より「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)も益税防止の観点から導入されることになる。インボイス制度導入後は、一定の経過措置はあるものの、免税事業者からの課税仕入れについては仕入税額控除ができないことになるため、その影響は大きい。また、軽減税率制度の対象範囲が「飲食料品」(食品表示法に規定する食品)となったことで多くの事業者にも影響を及ぼすことになった。軽減税率制度導入後、事業者の経理はどうなっていくのか、与党税制協議会の内容も踏まえてレポートする(図表1参照)。
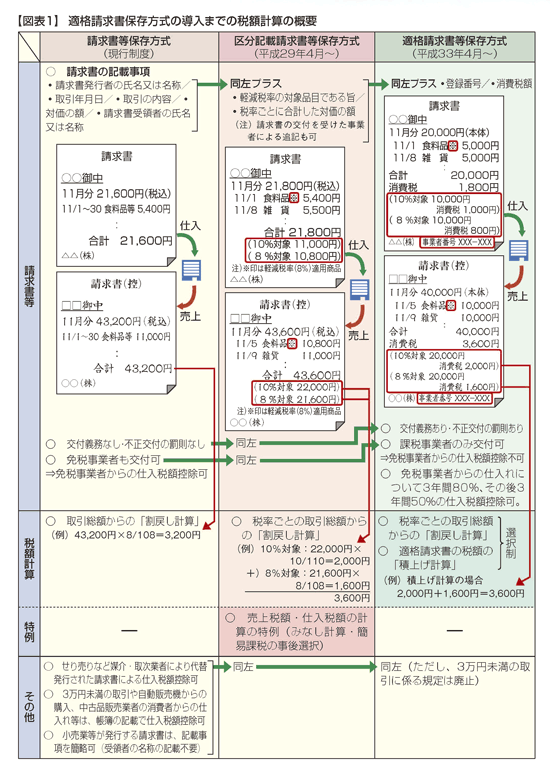
簡易な税額計算、現行制度との違いは記載事項
平成28年度税制改正大綱が12月16日に決定されたが、最後まで調整が続けられたのが消費税の軽減税率制度だ。平成29年4月1日から軽減税率制度が導入されるが、事業者の事務負担などを考慮し、インボイス制度は平成33年4月1日からの導入となり、4年間の経過措置として簡素な経理方法が設けられることになった(本誌621号4頁参照)。これが「区分記載請求書等保存方式」であり、事業者の記帳事務やシステム改修に大きな負担が生じないよう、現行の税額計算の方法を維持。税込価格を割り戻す方法(例えば、売上108円×8/108)も現状通りとなる。また、請求書等の発行義務や請求書等の写しの保存義務を課さないほか、罰則も行わない点は現行制度のままとなっている。
現行制度から変更されたのは、請求書等への記載事項だ。具体的には、課税仕入れが軽減税率対象品目に係るものである場合には、「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」及び「税率の異なるごとに合計した対価の額」を記載することになる。これまでは単一税率のため不要であったものだ。ただし、登録番号などの記載は求められておらず、必要最小限の記載事項となっている。
売上税額の計算の特例、中小事業者は4年間適用が可能
ただし、前述の「区分記載請求書等保存方式」によっても、売上を税率ごとに区分することが困難な事業者を対象として3つの特例計算方法を用意することになった。具体的には、①卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等に占める軽減対象課税資産の譲渡等にのみ要するものの割合を用いる、②通常の事業を行う連続する10営業日の課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲渡等の割合、③軽減対象課税資産の譲渡等の割合を50%のいずれかを用いて、当該期間の売上税額を簡便に計算することを認めている(図表2参照)。
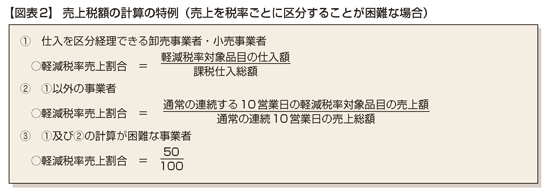
簡易課税制度と同様、2期前の課税売上高が5,000万円以下の事業者については、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの4年間が対象となる。当初は、基準期間の課税売上高5,000万円超の事業者は対象外であったが、軽減税率の対象品目が拡大したことから、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間に限り特例計算を適用することが可能になった(本誌623号80頁参照)。
仕入税額の計算の特例はすべての事業者を対象に1年間の措置
また、売上税額の計算の特例だけでなく、仕入税額の計算の特例も平成29年4月1日からの1年間に限り導入されることになった(図表3参照)。中小事業者だけでなく、大規模事業者も適用を受けることが可能だ。
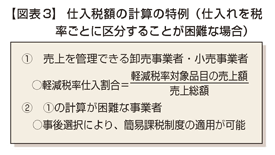
簡易課税の適用を受けない卸売業・小売業を対象に、仕入を税率ごとに区分することが困難な事業者については、課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲渡等の割合を用いて、当該期間の仕入税額を簡便に計算することを認めている。加えて、同計算によっても困難な事業者に関しては、事後選択であっても簡易課税制度の適用を認めている。
インボイス制度導入で免税事業者に迫られる課税事業者への選択の可否
以上がインボイス制度導入までの経過措置だが、平成33年4月1日以降は「適格請求書発行事業者登録制度」を創設。原則として、仕入側は「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書」(仮称)又は「適格簡易請求書」(仮称)を保存しなければ仕入税額控除が認められなくなる(本誌622号10頁参照)。
この「適格請求書発行事業者」とは、適格請求書を交付することのできる事業者として登録を受けた者。登録は平成31年4月1日から申請が受け付けられることになり、登録を受けた事業者の氏名又は名称及び登録番号等は国税庁のホームページに公表される予定だ。登録番号に関しては、新たに付番されるもので、法人番号とは異なるものとなっている。なお、免税事業者制度は存続するものの、課税事業者でなければ適格請求書発行事業者になれないことになる。
インボイス制度導入後は、「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となる。「適格請求書」等とは、請求書、納品書のことであり、登録番号等が記載された書類である。偽りの「適格請求書」等を発行した場合には罰則が適用される。また、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業等の不特定多数かつ多数の社に課税資産の譲渡等を行う一定の事業を行う場合には、「適格請求書」に代えて「適格簡易請求書」を交付することができることとした。「適格請求書」と比べて一部記載事項が簡略化されている(図表4参照)。
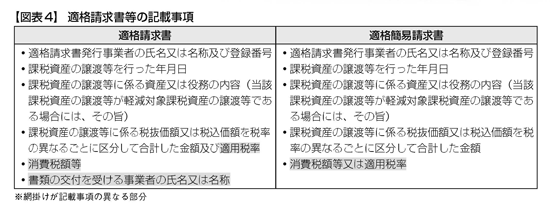
この「適格請求書」等は、課税事業者のみが発行できる仕組みとなっているため、免税事業者からの課税仕入れについては仕入税額控除ができなくなる。ただし、約513万事業者といわれる免税事業者に配慮し、インボイス導入から6年間は一定の経過措置が設けられることになった。具体的には、インボイス制度導入後、3年間(平成33年4月1日から平成36年3月31日)は仕入税額相当額の80%、その後の3年間(平成36年4月1日から平成39年3月31日)は同50%の控除が認められる。しかし、仕入側からすると、同じ価格であれば課税事業者から購入した方がより多くの仕入税額控除ができるため、BtoB取引を主にする免税事業者を中心に取引対象から除外される可能性が高くなる。
このため、免税事業者においては、取引から除外されるか等の業務への影響を分析し、課税選択の要否を検討する必要に迫られることになる。納付税額の計算方法や日々の記帳業務、価格の見直し、会計ソフト等の導入など、事務負担やコストを考慮しながら課税事業者となるか検討することになろう。
納付税額の計算方法については、売上税額、仕入税額の計算は、「適格請求書」等に記載されたすべての消費税額を集計する「積上げ計算」のほか、適用税率ごとの取引総額に110分の10、108分の8を乗じて計算する「割戻し計算」を行うことも可能だ。ただし、益税防止の観点から売上税額を「積上げ計算」する場合は、仕入税額も「積上げ計算」でなければならない。
現行制度とインボイス制度の違いは?
軽減税率導入後の事業者の経理処理
消費税の軽減税率制度が平成29年4月1日から導入されることが決まった。これに併せて、平成33年4月1日より「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)も益税防止の観点から導入されることになる。インボイス制度導入後は、一定の経過措置はあるものの、免税事業者からの課税仕入れについては仕入税額控除ができないことになるため、その影響は大きい。また、軽減税率制度の対象範囲が「飲食料品」(食品表示法に規定する食品)となったことで多くの事業者にも影響を及ぼすことになった。軽減税率制度導入後、事業者の経理はどうなっていくのか、与党税制協議会の内容も踏まえてレポートする(図表1参照)。
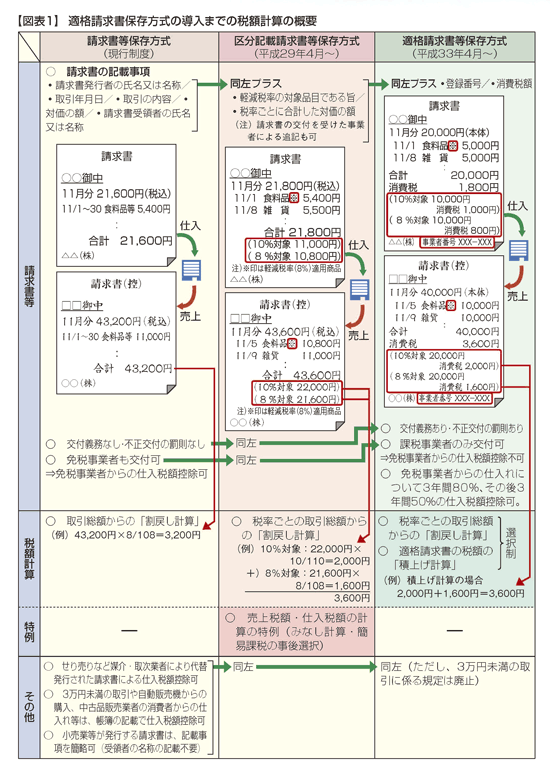
簡易な税額計算、現行制度との違いは記載事項
平成28年度税制改正大綱が12月16日に決定されたが、最後まで調整が続けられたのが消費税の軽減税率制度だ。平成29年4月1日から軽減税率制度が導入されるが、事業者の事務負担などを考慮し、インボイス制度は平成33年4月1日からの導入となり、4年間の経過措置として簡素な経理方法が設けられることになった(本誌621号4頁参照)。これが「区分記載請求書等保存方式」であり、事業者の記帳事務やシステム改修に大きな負担が生じないよう、現行の税額計算の方法を維持。税込価格を割り戻す方法(例えば、売上108円×8/108)も現状通りとなる。また、請求書等の発行義務や請求書等の写しの保存義務を課さないほか、罰則も行わない点は現行制度のままとなっている。
現行制度から変更されたのは、請求書等への記載事項だ。具体的には、課税仕入れが軽減税率対象品目に係るものである場合には、「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」及び「税率の異なるごとに合計した対価の額」を記載することになる。これまでは単一税率のため不要であったものだ。ただし、登録番号などの記載は求められておらず、必要最小限の記載事項となっている。
売上税額の計算の特例、中小事業者は4年間適用が可能
ただし、前述の「区分記載請求書等保存方式」によっても、売上を税率ごとに区分することが困難な事業者を対象として3つの特例計算方法を用意することになった。具体的には、①卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等に占める軽減対象課税資産の譲渡等にのみ要するものの割合を用いる、②通常の事業を行う連続する10営業日の課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲渡等の割合、③軽減対象課税資産の譲渡等の割合を50%のいずれかを用いて、当該期間の売上税額を簡便に計算することを認めている(図表2参照)。
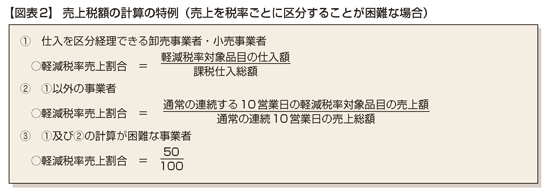
簡易課税制度と同様、2期前の課税売上高が5,000万円以下の事業者については、平成29年4月1日から平成33年3月31日までの4年間が対象となる。当初は、基準期間の課税売上高5,000万円超の事業者は対象外であったが、軽減税率の対象品目が拡大したことから、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間に限り特例計算を適用することが可能になった(本誌623号80頁参照)。
仕入税額の計算の特例はすべての事業者を対象に1年間の措置
また、売上税額の計算の特例だけでなく、仕入税額の計算の特例も平成29年4月1日からの1年間に限り導入されることになった(図表3参照)。中小事業者だけでなく、大規模事業者も適用を受けることが可能だ。
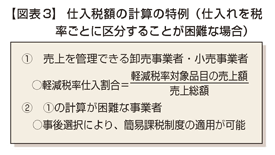
簡易課税の適用を受けない卸売業・小売業を対象に、仕入を税率ごとに区分することが困難な事業者については、課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲渡等の割合を用いて、当該期間の仕入税額を簡便に計算することを認めている。加えて、同計算によっても困難な事業者に関しては、事後選択であっても簡易課税制度の適用を認めている。
インボイス制度導入で免税事業者に迫られる課税事業者への選択の可否
以上がインボイス制度導入までの経過措置だが、平成33年4月1日以降は「適格請求書発行事業者登録制度」を創設。原則として、仕入側は「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書」(仮称)又は「適格簡易請求書」(仮称)を保存しなければ仕入税額控除が認められなくなる(本誌622号10頁参照)。
この「適格請求書発行事業者」とは、適格請求書を交付することのできる事業者として登録を受けた者。登録は平成31年4月1日から申請が受け付けられることになり、登録を受けた事業者の氏名又は名称及び登録番号等は国税庁のホームページに公表される予定だ。登録番号に関しては、新たに付番されるもので、法人番号とは異なるものとなっている。なお、免税事業者制度は存続するものの、課税事業者でなければ適格請求書発行事業者になれないことになる。
インボイス制度導入後は、「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となる。「適格請求書」等とは、請求書、納品書のことであり、登録番号等が記載された書類である。偽りの「適格請求書」等を発行した場合には罰則が適用される。また、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業等の不特定多数かつ多数の社に課税資産の譲渡等を行う一定の事業を行う場合には、「適格請求書」に代えて「適格簡易請求書」を交付することができることとした。「適格請求書」と比べて一部記載事項が簡略化されている(図表4参照)。
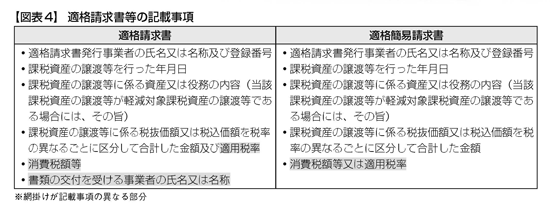
この「適格請求書」等は、課税事業者のみが発行できる仕組みとなっているため、免税事業者からの課税仕入れについては仕入税額控除ができなくなる。ただし、約513万事業者といわれる免税事業者に配慮し、インボイス導入から6年間は一定の経過措置が設けられることになった。具体的には、インボイス制度導入後、3年間(平成33年4月1日から平成36年3月31日)は仕入税額相当額の80%、その後の3年間(平成36年4月1日から平成39年3月31日)は同50%の控除が認められる。しかし、仕入側からすると、同じ価格であれば課税事業者から購入した方がより多くの仕入税額控除ができるため、BtoB取引を主にする免税事業者を中心に取引対象から除外される可能性が高くなる。
このため、免税事業者においては、取引から除外されるか等の業務への影響を分析し、課税選択の要否を検討する必要に迫られることになる。納付税額の計算方法や日々の記帳業務、価格の見直し、会計ソフト等の導入など、事務負担やコストを考慮しながら課税事業者となるか検討することになろう。
納付税額の計算方法については、売上税額、仕入税額の計算は、「適格請求書」等に記載されたすべての消費税額を集計する「積上げ計算」のほか、適用税率ごとの取引総額に110分の10、108分の8を乗じて計算する「割戻し計算」を行うことも可能だ。ただし、益税防止の観点から売上税額を「積上げ計算」する場合は、仕入税額も「積上げ計算」でなければならない。
| コラム | 軽減税率導入に伴い事業者が対応すべきことは? |
| 軽減税率導入に伴い事業者(顧客)から請求書(領収書)の発行を求められることがあるため、日々の業務において適切な商品管理を行うとともに、個々の商品の適用税率を把握しておく必要がある。仕入れの際には、納品書に記載された各品目の適用税率が正しいかを確認し、確認した適用税率を価格ラベルに記載したり、適用税率確認用の早見表や簡易なシステムなどを作成しておくことが考えられる。販売の際にも「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」及び「税率の異なるごとに合計した対価の額」を記載した請求書を発行することになる。 納税事務に関しては、売上税額の計算の特例なども手当てされており、事務負担が軽減されているが、基本的には軽減税率が適用される1年間の取引金額及び標準税率が適用される1年間の取引金額を区分して計算する必要がある。 | |
| 軽減税率制度の概要
税制抜本改革法第7条に基づく消費税率引上げに伴う低所得者対策として、平成29年4月に、以下のとおり、軽減税率制度を導入する。 ○軽減税率の対象品目 ・飲食料品(飲食店営業等を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供を除く) ※飲食料品は、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除くものとする) ・週2回以上発行される新聞の購読料 ○軽減税率 8%(国分:6.24%、地方分:1.76%) 標準税率 10%(国分:7.8%、地方分:2.2%) ○適格請求書等保存方式の導入 ・平成33年4月から、適格請求書等保存方式を導入する。 ・登録を受けた課税事業者が交付する適格請求書及び帳簿の保存を、仕入税額控除の要件とする。 ※適格請求書の記載事項は、発行者の氏名又は名称及び登録番号、取引年月日、取引の内容(軽減税率対象である旨の記載を含む)、税率ごとに合計した対価の額及び適用税率、消費税額等、交付を受ける事業者の氏名又は名称とする。 ・税額計算の方法は、適格請求書の税額の積上げ計算と、取引総額からの割戻し計算の選択制とする。 (適格請求書等保存方式導入までの経過措置) ・現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に対応するための措置を講ずる。具体的には、請求書等の記載事項に、①軽減税率の対象品目である旨と、②税率ごとに合計した対価の額、を加える(区分記載請求書等保存方式)。 なお、上記①・②については、区分記載請求書の交付を受けた事業者が、事実に基づき追記することを認める。 ・売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者に対し、売上税額又は仕入税額の計算の特例を設ける。 (適格請求書等保存方式導入後の経過措置) ・適格請求書等保存方式の導入後6年間、免税事業者からの仕入れについて、一定割合の仕入税額控除を認める。 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























