解説記事2016年09月12日 【税理士のための相続法講座】 遺産の管理(2016年9月12日号・№658)
税理士のための相続法講座
第19回
遺産の管理
弁護士 間瀬まゆ子
1 遺産の評価について ここまで、個別の遺産について触れてきました。一般的な実務書等では、ここで「相続財産の評価」を一テーマとして採り上げることが多いと思いますが、遺産の評価は、税理士の方が法曹関係者よりも得意とする分野であること、各相続財産に関する説明の中で若干の説明を付したことから、本連載では割愛します。
ただ、遺産分割の場面では、相続開始時ではなく分割時における遺産評価に基づいて分割を行っていること、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分の算定に際しては評価の基準時が相続開始時であること(民法903条1項、904条の2第1項参照)のみ付言しておきます(そのため、不動産の鑑定を依頼する際に、相続開始時と鑑定時点の2時点の評価を求めることもあります。)。
2 遺産の管理 さて、前置きが長くなりましたが、今回のテーマは相続財産の管理です。
複数の相続人がいる場合、相続が発生してから遺産分割により具体的な帰属先が決まるまでの間、遺産は相続人らの共有財産となります。そのため、管理をどうするかの問題が生じます。
まず、相続開始後相続人が相続の承認または放棄をするまでの間は、自己の「固有財産におけるのと同一の注意」をもって遺産を管理すれば足りる(すなわち善管注意義務までは負わない)ことになっています(民法918条1項)。
一方、相続の承認後、遺産分割が終了するまでの間の遺産の管理に関しては、民法上特別な規定は存在せず、通常の共有に関する規定に従うことになります。
したがって、保存行為(修繕や納税等)は各相続人が単独でできるものの、管理行為(賃料の取立て等)は各相続人の相続分による多数決によって決し、処分行為は相続人全員の同意により行うべきこととなります(民法249条、251条、252条)。
そのほか、株式を共同相続することがありますが、この場合、会社の同意がない限りは、権利行使者一人を定めて会社に通知することが必要です(会社法106条)。その際、権利行使者は、持分割合の過半数をもって決することになります。
そして、これらの管理にかかった費用は、「相続財産に関する費用」として相続財産の負担となります(民法885条)。
上記のとおり共有に関する規定に従うとはいっても、遺産分割に至るまで時間を要する場合もあります。そのような場合に、相続人全員の合意により、特定の者に遺産の管理を委託することがあります(通常の委任の規定に従います)。
また、一部の相続人が費消してしまう恐れがあるような場合、審判前の保全処分として、遺産管理者の選任を家庭裁判所に申し立てることができます(なお、「審判前」の保全処分といっても、家事事件手続法の元では、審判に移行する前の調停の段階でも、保全処分の申立てができることになっています(200条1項)。また、保全処分には、遺産管理者の選任以外に、仮差押えや仮処分もあります。)。
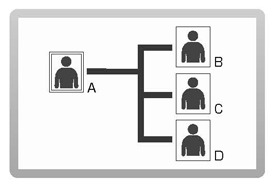
この場合、CとDの持分を合わせると、持分割合の過半数を超えています。しかし、Bも自らの持分1/3に基づいて共有物である自宅不動産を使用収益する権限を有しており、その権限に基づいて占有しているため、C及びDが当然にBに対して明渡しを請求することはできないと解されています(最一小判昭和41年5月19日民集20巻5号947頁)。
更に、Bが自己の持分が1/3に過ぎないにもかかわらず、自宅不動産全体を占有している点をとらえて、C及びDが、自らの持分各1/3に基づき、賃料相当の不当利得の返還をBに求められるかも問題になります。
しかし、この点に関し、最高裁は、被相続人と同居の相続人との間で、被相続人死亡後も、遺産分割で建物の所有関係が確定するまでの間は、引き続き建物を無償で使用させるという使用貸借契約が成立していたと推認して、不当利得の問題は生じないとしました(最三小判平成8年12月17日民集50巻10号2778頁)。
上記の事例でも、BがAと長年同居しAの世話をしていたということですから、Aの生前に、AとBとの間で、自宅建物を、遺産分割で所有関係が確定するまではBに無償で使用させるとの合意があったと認定されることも十分考えられます。
その場合、CとDが不当利得としてBに賃料相当分の支払を求めることは難しくなります。
3 配偶者の居住権(民法改正中間試案より) 2に記載したとおり、他の相続人らによる明渡請求や賃料相当額の返還請求が認められない場合があるとしても、遺産である不動産に住み続けている相続人の地位はやはり不安定です。
遺言を残しておくことで防止できる部分もありますが、まだまだ遺言を残す被相続人は限定的です。特に、残された配偶者の居住権の保護の必要性は以前から言われていたところです。
そのため、「配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮等の観点」から現在行われている民法相続編改正に向けた審議の中で、配偶者の居住権を保護するための方策の導入も検討されています。
具体的に中間試案で示されたのは、短期居住権と長期居住権の2つです。
(1)短期居住権 短期居住権は、遺産分割が行われるべき場合に、相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた配偶者に、遺産分割により当該建物の帰属が確定されるまでの間、引き続きその建物を無償で使用することができる権利を与えるものです。
その他、遺言または死因贈与により配偶者以外の者が当該建物を取得したときも、配偶者が一定期間(例えば6か月)無償で建物を使用することができるようにするとの提案もなされています。
(2)長期居住権 もう一つの長期居住権は、今回のテーマである遺産の管理とは関係しませんが、配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間、配偶者にその建物の使用を認めることを内容とする法定の権利を新設しようというものです。
長期居住権の評価方法等、税務的にも気になるところがありますが、これが実現すれば、「配偶者に住まわせた後に長女に取得させたい」というような「後継ぎ遺贈」を気軽に実現できるようになるかもしれません。
第19回
遺産の管理
弁護士 間瀬まゆ子
1 遺産の評価について ここまで、個別の遺産について触れてきました。一般的な実務書等では、ここで「相続財産の評価」を一テーマとして採り上げることが多いと思いますが、遺産の評価は、税理士の方が法曹関係者よりも得意とする分野であること、各相続財産に関する説明の中で若干の説明を付したことから、本連載では割愛します。
ただ、遺産分割の場面では、相続開始時ではなく分割時における遺産評価に基づいて分割を行っていること、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分の算定に際しては評価の基準時が相続開始時であること(民法903条1項、904条の2第1項参照)のみ付言しておきます(そのため、不動産の鑑定を依頼する際に、相続開始時と鑑定時点の2時点の評価を求めることもあります。)。
2 遺産の管理 さて、前置きが長くなりましたが、今回のテーマは相続財産の管理です。
複数の相続人がいる場合、相続が発生してから遺産分割により具体的な帰属先が決まるまでの間、遺産は相続人らの共有財産となります。そのため、管理をどうするかの問題が生じます。
まず、相続開始後相続人が相続の承認または放棄をするまでの間は、自己の「固有財産におけるのと同一の注意」をもって遺産を管理すれば足りる(すなわち善管注意義務までは負わない)ことになっています(民法918条1項)。
一方、相続の承認後、遺産分割が終了するまでの間の遺産の管理に関しては、民法上特別な規定は存在せず、通常の共有に関する規定に従うことになります。
したがって、保存行為(修繕や納税等)は各相続人が単独でできるものの、管理行為(賃料の取立て等)は各相続人の相続分による多数決によって決し、処分行為は相続人全員の同意により行うべきこととなります(民法249条、251条、252条)。
そのほか、株式を共同相続することがありますが、この場合、会社の同意がない限りは、権利行使者一人を定めて会社に通知することが必要です(会社法106条)。その際、権利行使者は、持分割合の過半数をもって決することになります。
そして、これらの管理にかかった費用は、「相続財産に関する費用」として相続財産の負担となります(民法885条)。
上記のとおり共有に関する規定に従うとはいっても、遺産分割に至るまで時間を要する場合もあります。そのような場合に、相続人全員の合意により、特定の者に遺産の管理を委託することがあります(通常の委任の規定に従います)。
また、一部の相続人が費消してしまう恐れがあるような場合、審判前の保全処分として、遺産管理者の選任を家庭裁判所に申し立てることができます(なお、「審判前」の保全処分といっても、家事事件手続法の元では、審判に移行する前の調停の段階でも、保全処分の申立てができることになっています(200条1項)。また、保全処分には、遺産管理者の選任以外に、仮差押えや仮処分もあります。)。
| Aが亡くなった。相続人は3人の子。Aと同居し、Aの身の回りの世話を長年していた子Bは、相続開始後も、Aの自宅に住み続けている。子C及びDは、Bを出て行かせるか、それが難しいのならば、自分たちの賃料相当分をBに支払わせたいと思っている。 |
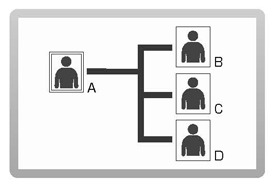
この場合、CとDの持分を合わせると、持分割合の過半数を超えています。しかし、Bも自らの持分1/3に基づいて共有物である自宅不動産を使用収益する権限を有しており、その権限に基づいて占有しているため、C及びDが当然にBに対して明渡しを請求することはできないと解されています(最一小判昭和41年5月19日民集20巻5号947頁)。
更に、Bが自己の持分が1/3に過ぎないにもかかわらず、自宅不動産全体を占有している点をとらえて、C及びDが、自らの持分各1/3に基づき、賃料相当の不当利得の返還をBに求められるかも問題になります。
しかし、この点に関し、最高裁は、被相続人と同居の相続人との間で、被相続人死亡後も、遺産分割で建物の所有関係が確定するまでの間は、引き続き建物を無償で使用させるという使用貸借契約が成立していたと推認して、不当利得の問題は生じないとしました(最三小判平成8年12月17日民集50巻10号2778頁)。
上記の事例でも、BがAと長年同居しAの世話をしていたということですから、Aの生前に、AとBとの間で、自宅建物を、遺産分割で所有関係が確定するまではBに無償で使用させるとの合意があったと認定されることも十分考えられます。
その場合、CとDが不当利得としてBに賃料相当分の支払を求めることは難しくなります。
3 配偶者の居住権(民法改正中間試案より) 2に記載したとおり、他の相続人らによる明渡請求や賃料相当額の返還請求が認められない場合があるとしても、遺産である不動産に住み続けている相続人の地位はやはり不安定です。
遺言を残しておくことで防止できる部分もありますが、まだまだ遺言を残す被相続人は限定的です。特に、残された配偶者の居住権の保護の必要性は以前から言われていたところです。
そのため、「配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮等の観点」から現在行われている民法相続編改正に向けた審議の中で、配偶者の居住権を保護するための方策の導入も検討されています。
具体的に中間試案で示されたのは、短期居住権と長期居住権の2つです。
(1)短期居住権 短期居住権は、遺産分割が行われるべき場合に、相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた配偶者に、遺産分割により当該建物の帰属が確定されるまでの間、引き続きその建物を無償で使用することができる権利を与えるものです。
その他、遺言または死因贈与により配偶者以外の者が当該建物を取得したときも、配偶者が一定期間(例えば6か月)無償で建物を使用することができるようにするとの提案もなされています。
(2)長期居住権 もう一つの長期居住権は、今回のテーマである遺産の管理とは関係しませんが、配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間、配偶者にその建物の使用を認めることを内容とする法定の権利を新設しようというものです。
長期居住権の評価方法等、税務的にも気になるところがありますが、これが実現すれば、「配偶者に住まわせた後に長女に取得させたい」というような「後継ぎ遺贈」を気軽に実現できるようになるかもしれません。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















