資料2017年05月22日 【重要資料】 「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)(2017年5月22日号・№691)
重要資料
「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
平成29年4月27日付課評2-12ほか2課共同「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)及び平成29年4月27日付課評2-14ほか2課共同「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について』の一部改正について」(法令解釈通達)により、森林の立木の評価及び取引相場のない株式等の評価について所要の改正を行ったところであるが、そのあらましは別添のとおりであるので、参考のため送付する。
別添
1 森林の主要樹種の立木の評価
1 従来の取扱い (1)木材市場へ出すと有価となり始める立木の樹齢を切替樹齢(m年)とし、杉は39年、ひのきは32年と定めている。
(2)標準伐期は主要林業地帯ごとに定め、杉が50年から60年、ひのきが60年から65年の間で標準伐期を定めている。
(3)標準伐期を超え標準伐期の2倍の樹齢までの立木の価額は、標準伐期の標準価額を基とし、その樹齢に応ずる年2%の利率による複利終価の額を基として定めている。
(4)評価通達の別表2「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」では、「1 樹齢1年以下の森林の立木の標準価額表」、「2 樹齢1年を超えm年未満の森林の立木の標準価額を計算する場合の『C』の金額表」、「3 樹齢1年を超えm年未満の森林の立木の標準価額を計算する場合の『補助金相当額』の金額表」、「4 樹齢1年を超えm年未満の森林の立木の標準価額を計算する場合の『標準伐期の標準価額』の金額表」、「5 樹齢m年の森林の立木の標準価額表」及び「6 標準伐期にある森林の立木の標準価額表」を定めている。
2 通達改正の概要
近年の林業を取り巻く環境の変化を踏まえ、切替樹齢、標準伐期及び植林費等の実態を調べるなどして、立木評価の一層の適正化を図った。
(1)切替樹齢 切替樹齢(m年)について、市場価逆算価格を基に算定し、杉は37年、ひのきは33年に改めた。
(2)標準伐期
木材の需給状況等により、全国的に標準伐期が長期化している実態を踏まえ、杉及びひのきの標準伐期を後ろ倒しした。
(3)適用利率
標準伐期を超え標準伐期の2倍の樹齢までの立木の評価に適用する利率について、売買実例を基に算定し、年1.5%に改めた。
(4)別表2の各種金額
植林費、育林費及び補助金等の実態を調べるなどして、別表2(「6 標準伐期にある森林の立木の標準価額表」を除く。)の杉及びひのきの各種金額を改めた。
2 森林の主要樹種以外の立木の評価
1 従来の取扱い 森林の主要樹種を杉、ひのき、松、くぬぎ及び雑木とし、その立木の価額は、国税局長の定める標準価額に、その森林について地味級(地味の肥せき)、立木度(立木の密度)及び地利級(立木の搬出の便否)に応じてそれぞれ別に定める割合を連乗して求めた金額に、その森林の地積を乗じて計算した金額によって評価することとしている。
また、「森林の主要樹種以外の立木」の価額についても、主要樹種の立木の価額と同様の方法により評価することとしている。
2 通達改正の概要 松、くぬぎ及び雑木の価額については、近年の林業を取り巻く環境の変化により、価額の個別性が強い樹種となってきている実態を踏まえ、標準価額を定めることはせずに、その個別性を課税時期の評価額に適正に反映させることとし、「森林の主要樹種以外の立木」に改め、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとした。
また、松、くぬぎ及び雑木以外の「森林の主要樹種以外の立木」の価額についても、同様の方法により評価することとした。
3 取引相場のない株式等の評価(類似業種比準方式の見直し)
1 従来の取扱い
取引相場のない株式等を評価する際の類似業種比準方式は、評価会社の事業内容と類似する業種目の上場会社の平均株価等を基として、次の算式により評価する方式である。
この算式における類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3か月の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価によることができることとしていた。
また、類似業種の1株当たりの配当金額、利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)(以下これらを併せて「類似業種の比準要素」という。)については、評価通達183((評価会社の1株当たりの配当金額等の計算))の定めに準じて、法人税等の数値に基づき算出することとしていた。
2 通達改正の概要
(1)類似業種の株価
従来から、類似業種の株価については、類似業種比準価額の計算において、上場会社の株価の急激な変動による影響を緩和する趣旨から、一定の選択肢を設けていたところであるが、最近の株価の動向を踏まえると、株価の急激な変動を平準化するには、2年程度必要と考えられること及び現行においても課税時期が12月の場合には、前年平均株価の計算上、前年の1月までの株価を考慮しており、実質的に2年間の株価を考慮していることから、課税時期の属する月以前2年間の平均株価を選択可能とした。
(注)類似業種の株価については、1株当たりの資本金等の額(法人税法((定義))第2条16号に規定する「資本金等の額」をいう。以下同じ。)を50円として計算した金額によることとしていたが、次の(2)「類似業種の比準要素の計算」と同様に、1株当たりの資本金の額等)(「資本金の額及び資本剰余金の額の合計額から自己株式の額を控除した金額」をいう。以下同じ。)を50円として計算した金額によることとした。
(2)類似業種の比準要素の計算 上場会社については、連結決算に係る財務情報を公表することが原則義務付けられており、投資判断に当たりその情報も重視されて株価の形成要素となっていると考えられることから、より適切な時価を算出するため、類似業種の比準要素の数値について、連結決算を反映させることとした。
この場合、上場会社は、原則として監査義務が課されており、利益計算の恣意性は排除されていることを考慮し、類似業種の比準要素については、財務諸表の数値を基に計算することとした上で、連結決算を行っている場合には、その数値を反映させたものとすることとした。
具体的には、類似業種の1株当たりの利益金額については、市場において当期純利益が株価の分析対象とされていること及び課税所得金額が税引前当期純利益に基づき計算されていることとのバランスから、税引前当期純利益(連結決算を行っている場合には税金等調整前当期純利益)を基に計算することとした。
また、類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)(以下「簿価純資産価額」という。)については、企業会計上の純資産が資産と負債の差額に基づく概念であることを踏まえ、財務諸表における資産と負債の差額である純資産の部の合計額を基に計算することとした。
(注1)類似業種の比準要素の数値の算出に当たっては、配当金額等を発行済株式数で除した1株当たりの金額に基づき計算している。この発行済株式数は、1株当たりの資本金等の額が50円以外の場合には1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数により計算することとしていたところ、類似業種の比準要素について連結決算を反映させるため、財務諸表に基づく数値とすることとのバランスから、1株当たりの資本金の額等が50円以外の場合には、1株当たりの資本金の額等の金額を50円とした場合の発行済株式数に基づき計算することとした。
(注2)非上場会社である評価会社には、原則として、上場会社のような監査義務は課されておらず、利益計算の恣意性を排除し、評価会社の株式を同一の算定基準により評価することが合理的であることに鑑み、納税者利便の観点から、評価会社の1株当たりの配当金額、利益金額及び簿価純資産価額については、従来どおり法人税等の数値に基づき計算することに留意する。
(3)配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重
類似業種比準方式における3つの比準要素である配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重は、平成12年の評価通達改正以前においては、株価形成に与える影響度が等しいものとして取り扱っていたが、平成12年の評価通達の改正時に、上場会社のデータに基づき検証作業等を行ったところ、これらの要素の比重を1:3:1とした場合が最も適正に株価の算定がなされると認められたことから、この比重により計算することとしたものである。
今般、平成12年の評価通達の改正時と同様に、上場会社のデータに基づき、個別の上場会社について、これらの要素の比重をどのようにすると最も当該上場会社の株価に近似する評価額を導くか、それぞれの要素の比重を変えて検証作業を行った。
その結果、1:1:1という比重が最も実際の株価と評価額との乖離が少なく、適正に「時価」が算出されると認められたことから、これを踏まえて類似業種比準方式の算式を改正した。
以上の評価通達の改正により、類似業種比準方式の算式は以下のとおりとなった。
3 類似業種比準方式の見直しに伴う改正
類似業種比準方式における算式の改正に伴い、株式保有特定会社の株式の評価におけるS1の金額を計算する場合の算式及び医療法人の出資の評価における算式について、それぞれ同様に改正した。
4 取引相場のない株式等の評価(会社規模の判定基準の見直し等)
1 従来の取扱い
取引相場のない株式等の発行会社の規模は、大は上場会社に匹敵するものから、小は個人企業と変わらないものまで様々であり、これらの会社の株式を、会社の規模と関係なく同一の評価方法により評価することは適当ではないことから、①上場会社に匹敵するような大規模な会社を大会社、②個人企業と変わらない規模の会社を小会社、③これらの会社の中間の規模の会社を中会社に区分して、それぞれに適した評価方式により評価することとしている。
この会社規模については、総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)(以下「総資産価額」という。)、従業員数及び直前期末以前1年間における取引金額(以下これらを併せて「総資産価額等」という。)に応じて、判定することとしている。
2 通達改正の概要 会社規模の判定基準について、法人企業統計調査(財務省)等に基づき、以下のとおり改正した。
(1)大会社
大会社は、従来から上場会社に匹敵するような規模の会社と区分しており、法人企業統計調査に基づき、上場審査基準に相当する総資産価額等を算出することとしている。
ところで、国内証券市場については、マザーズ、JASDAQ等の新興市場が創設され、更に、近年、新興市場を含む金融商品取引所が順次再編されており、上場審査基準も見直しが行われ、上場会社の実態にも変化が生じている。
そこで、近年の上場会社の実態に合わせて、現在の上場審査基準を基に規模区分の金額等の基準を見直すこととした。具体的には、代表的な株式市場である東京証券取引所第一部等の上場審査基準のみならず、新興市場の上場審査基準についても加味した上で、法人企業統計調査に基づき総資産価額等を算出した。
(2)中会社
イ Lの割合が0.9の会社
中会社は大会社と小会社の中間の規模の会社であり、とりわけLの割合が0.9の会社(以下「中会社(大)」という。)は、大会社に準ずる会社であって、上場を企図すればすぐに上場できる規模の会社と考えられることから、新興市場に上場する会社と同視し得るものとの考え方の下、新興市場の上場審査基準を基に、総資産価額等を算出した。
ロ Lの割合が0.75の会社
現行通達における取扱いと同様に、中会社(大)の基準のほぼ50%(総資産価額及び取引金額は中会社(大)の50%、従業員数はその60%)に相当する総資産価額等を算出した。
3 大会社の判定基準の見直しに伴う改正
大会社の判定基準に係る総資産価額が改正されたことに伴い、土地保有特定会社の判定基準のうち、総資産価額について改正した。
4 明細書通達の改正
「類似業種比準方式の見直し」及び「会社規模区分の判定基準の見直し」により、明細書通達における次の欄について改正した。
① 「第1表の2 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書(続)」における「3 会社規模(Lの割合)の判定」中の「判定基準」欄
② 「第2表 特定の評価会社の判定の明細書」における「3 土地保有特定会社」中の「小会社」欄
③ 「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」における「3 類似業種比準価額の計算」中の「1株(50円)当たりの比準価額の計算」欄
④ 「第7表 株式保有特定会社の株式の価額の計算明細書」における「1 S1の金額(類似業種比準価額の修正計算)」中の「1株(50円)当たりの比準価額の計算」欄
(参考)会社規模の判定基準
※アンダーラインを付した部分が改正部分である。
| 資産評価企画官情報 資産課税課情報 | 第3号 第10号 | 平成29年4月28日 | 国税庁 資産評価企画官 資産課税課 |
「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)
平成29年4月27日付課評2-12ほか2課共同「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)及び平成29年4月27日付課評2-14ほか2課共同「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について』の一部改正について」(法令解釈通達)により、森林の立木の評価及び取引相場のない株式等の評価について所要の改正を行ったところであるが、そのあらましは別添のとおりであるので、参考のため送付する。
別添
1 森林の主要樹種の立木の評価
| 立木評価の一層の適正化を図る観点から、森林の主要樹種の立木の評価方法の一部を次のとおり改正した。 1 木材市場へ出すと有価となり始める立木の樹齢である切替樹齢の年数を改めた。 2 標準伐期を後ろ倒しした。 3 標準伐期を超え標準伐期の2倍の樹齢までの立木の評価に適用する利率を改めた。 4 評価通達の別表2「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」における各種金額を改めた。 (評価通達115、116、120、別表2=改正) |
1 従来の取扱い (1)木材市場へ出すと有価となり始める立木の樹齢を切替樹齢(m年)とし、杉は39年、ひのきは32年と定めている。
(2)標準伐期は主要林業地帯ごとに定め、杉が50年から60年、ひのきが60年から65年の間で標準伐期を定めている。
(3)標準伐期を超え標準伐期の2倍の樹齢までの立木の価額は、標準伐期の標準価額を基とし、その樹齢に応ずる年2%の利率による複利終価の額を基として定めている。
(4)評価通達の別表2「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」では、「1 樹齢1年以下の森林の立木の標準価額表」、「2 樹齢1年を超えm年未満の森林の立木の標準価額を計算する場合の『C』の金額表」、「3 樹齢1年を超えm年未満の森林の立木の標準価額を計算する場合の『補助金相当額』の金額表」、「4 樹齢1年を超えm年未満の森林の立木の標準価額を計算する場合の『標準伐期の標準価額』の金額表」、「5 樹齢m年の森林の立木の標準価額表」及び「6 標準伐期にある森林の立木の標準価額表」を定めている。
2 通達改正の概要
近年の林業を取り巻く環境の変化を踏まえ、切替樹齢、標準伐期及び植林費等の実態を調べるなどして、立木評価の一層の適正化を図った。
(1)切替樹齢 切替樹齢(m年)について、市場価逆算価格を基に算定し、杉は37年、ひのきは33年に改めた。
(2)標準伐期
木材の需給状況等により、全国的に標準伐期が長期化している実態を踏まえ、杉及びひのきの標準伐期を後ろ倒しした。
(3)適用利率
標準伐期を超え標準伐期の2倍の樹齢までの立木の評価に適用する利率について、売買実例を基に算定し、年1.5%に改めた。
(4)別表2の各種金額
植林費、育林費及び補助金等の実態を調べるなどして、別表2(「6 標準伐期にある森林の立木の標準価額表」を除く。)の杉及びひのきの各種金額を改めた。
2 森林の主要樹種以外の立木の評価
| 立木評価の一層の適正化を図る観点から、松、くぬぎ及び雑木を「森林の主要樹種以外の立木」に改めることとした。 また、「森林の主要樹種以外の立木」の価額については、標準価額を基として評価することとしていたが、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとした。 (評価通達113、117、118、119=改正) |
1 従来の取扱い 森林の主要樹種を杉、ひのき、松、くぬぎ及び雑木とし、その立木の価額は、国税局長の定める標準価額に、その森林について地味級(地味の肥せき)、立木度(立木の密度)及び地利級(立木の搬出の便否)に応じてそれぞれ別に定める割合を連乗して求めた金額に、その森林の地積を乗じて計算した金額によって評価することとしている。
また、「森林の主要樹種以外の立木」の価額についても、主要樹種の立木の価額と同様の方法により評価することとしている。
2 通達改正の概要 松、くぬぎ及び雑木の価額については、近年の林業を取り巻く環境の変化により、価額の個別性が強い樹種となってきている実態を踏まえ、標準価額を定めることはせずに、その個別性を課税時期の評価額に適正に反映させることとし、「森林の主要樹種以外の立木」に改め、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとした。
また、松、くぬぎ及び雑木以外の「森林の主要樹種以外の立木」の価額についても、同様の方法により評価することとした。
3 取引相場のない株式等の評価(類似業種比準方式の見直し)
| 取引相場のない株式等を評価する際の類似業種比準方式の算式について、次のとおり改正した。 1 類似業種の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える。 2 類似業種の配当金額、利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)について、連結決算を反映させたものとする。 3 配当金額、利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)の比重について、1:1:1とする。 (評価通達180、182、183-2、189-3、194-2、明細書通達=改正) |
1 従来の取扱い
取引相場のない株式等を評価する際の類似業種比準方式は、評価会社の事業内容と類似する業種目の上場会社の平均株価等を基として、次の算式により評価する方式である。
(改正前の算式) 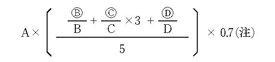 「A」=類似業種の株価 「B」=類似業種の1株当たりの配当金額 「C」=類似業種の1株当たりの利益金額 「D」=類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額) 「  」=評価会社の1株当たりの配当金額 」=評価会社の1株当たりの配当金額 「  」=評価会社の1株当たりの利益金額 」=評価会社の1株当たりの利益金額 「  」=評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額) 」=評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額) (注)0.7は、中会社の場合は「0.6」、小会社の場合は「0.5」 |
この算式における類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3か月の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価によることができることとしていた。
また、類似業種の1株当たりの配当金額、利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)(以下これらを併せて「類似業種の比準要素」という。)については、評価通達183((評価会社の1株当たりの配当金額等の計算))の定めに準じて、法人税等の数値に基づき算出することとしていた。
2 通達改正の概要
(1)類似業種の株価
従来から、類似業種の株価については、類似業種比準価額の計算において、上場会社の株価の急激な変動による影響を緩和する趣旨から、一定の選択肢を設けていたところであるが、最近の株価の動向を踏まえると、株価の急激な変動を平準化するには、2年程度必要と考えられること及び現行においても課税時期が12月の場合には、前年平均株価の計算上、前年の1月までの株価を考慮しており、実質的に2年間の株価を考慮していることから、課税時期の属する月以前2年間の平均株価を選択可能とした。
(注)類似業種の株価については、1株当たりの資本金等の額(法人税法((定義))第2条16号に規定する「資本金等の額」をいう。以下同じ。)を50円として計算した金額によることとしていたが、次の(2)「類似業種の比準要素の計算」と同様に、1株当たりの資本金の額等)(「資本金の額及び資本剰余金の額の合計額から自己株式の額を控除した金額」をいう。以下同じ。)を50円として計算した金額によることとした。
(2)類似業種の比準要素の計算 上場会社については、連結決算に係る財務情報を公表することが原則義務付けられており、投資判断に当たりその情報も重視されて株価の形成要素となっていると考えられることから、より適切な時価を算出するため、類似業種の比準要素の数値について、連結決算を反映させることとした。
この場合、上場会社は、原則として監査義務が課されており、利益計算の恣意性は排除されていることを考慮し、類似業種の比準要素については、財務諸表の数値を基に計算することとした上で、連結決算を行っている場合には、その数値を反映させたものとすることとした。
具体的には、類似業種の1株当たりの利益金額については、市場において当期純利益が株価の分析対象とされていること及び課税所得金額が税引前当期純利益に基づき計算されていることとのバランスから、税引前当期純利益(連結決算を行っている場合には税金等調整前当期純利益)を基に計算することとした。
また、類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)(以下「簿価純資産価額」という。)については、企業会計上の純資産が資産と負債の差額に基づく概念であることを踏まえ、財務諸表における資産と負債の差額である純資産の部の合計額を基に計算することとした。
(注1)類似業種の比準要素の数値の算出に当たっては、配当金額等を発行済株式数で除した1株当たりの金額に基づき計算している。この発行済株式数は、1株当たりの資本金等の額が50円以外の場合には1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済株式数により計算することとしていたところ、類似業種の比準要素について連結決算を反映させるため、財務諸表に基づく数値とすることとのバランスから、1株当たりの資本金の額等が50円以外の場合には、1株当たりの資本金の額等の金額を50円とした場合の発行済株式数に基づき計算することとした。
(注2)非上場会社である評価会社には、原則として、上場会社のような監査義務は課されておらず、利益計算の恣意性を排除し、評価会社の株式を同一の算定基準により評価することが合理的であることに鑑み、納税者利便の観点から、評価会社の1株当たりの配当金額、利益金額及び簿価純資産価額については、従来どおり法人税等の数値に基づき計算することに留意する。
(3)配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重
類似業種比準方式における3つの比準要素である配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重は、平成12年の評価通達改正以前においては、株価形成に与える影響度が等しいものとして取り扱っていたが、平成12年の評価通達の改正時に、上場会社のデータに基づき検証作業等を行ったところ、これらの要素の比重を1:3:1とした場合が最も適正に株価の算定がなされると認められたことから、この比重により計算することとしたものである。
今般、平成12年の評価通達の改正時と同様に、上場会社のデータに基づき、個別の上場会社について、これらの要素の比重をどのようにすると最も当該上場会社の株価に近似する評価額を導くか、それぞれの要素の比重を変えて検証作業を行った。
その結果、1:1:1という比重が最も実際の株価と評価額との乖離が少なく、適正に「時価」が算出されると認められたことから、これを踏まえて類似業種比準方式の算式を改正した。
以上の評価通達の改正により、類似業種比準方式の算式は以下のとおりとなった。
(改正後の算式)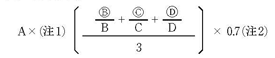 (注1)課税時期以前3か月の各月の平均株価のうち最も低い株価による。ただし、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価又は課税時期以前2年間の平均株価を採用することができる。 (注2)0.7は、中会社の場合は「0.6」、小会社の場合は「0.5」 |
3 類似業種比準方式の見直しに伴う改正
類似業種比準方式における算式の改正に伴い、株式保有特定会社の株式の評価におけるS1の金額を計算する場合の算式及び医療法人の出資の評価における算式について、それぞれ同様に改正した。
4 取引相場のない株式等の評価(会社規模の判定基準の見直し等)
| 取引相場のない株式等を評価する際の会社規模の判定基準における大会社及び中会社の総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)、従業員数及び直前期末以前1年間における取引金額について、近年の上場会社の実態に合わせて改正した。 (評価通達178、179、189、明細書通達=改正) |
1 従来の取扱い
取引相場のない株式等の発行会社の規模は、大は上場会社に匹敵するものから、小は個人企業と変わらないものまで様々であり、これらの会社の株式を、会社の規模と関係なく同一の評価方法により評価することは適当ではないことから、①上場会社に匹敵するような大規模な会社を大会社、②個人企業と変わらない規模の会社を小会社、③これらの会社の中間の規模の会社を中会社に区分して、それぞれに適した評価方式により評価することとしている。
この会社規模については、総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)(以下「総資産価額」という。)、従業員数及び直前期末以前1年間における取引金額(以下これらを併せて「総資産価額等」という。)に応じて、判定することとしている。
2 通達改正の概要 会社規模の判定基準について、法人企業統計調査(財務省)等に基づき、以下のとおり改正した。
(1)大会社
大会社は、従来から上場会社に匹敵するような規模の会社と区分しており、法人企業統計調査に基づき、上場審査基準に相当する総資産価額等を算出することとしている。
ところで、国内証券市場については、マザーズ、JASDAQ等の新興市場が創設され、更に、近年、新興市場を含む金融商品取引所が順次再編されており、上場審査基準も見直しが行われ、上場会社の実態にも変化が生じている。
そこで、近年の上場会社の実態に合わせて、現在の上場審査基準を基に規模区分の金額等の基準を見直すこととした。具体的には、代表的な株式市場である東京証券取引所第一部等の上場審査基準のみならず、新興市場の上場審査基準についても加味した上で、法人企業統計調査に基づき総資産価額等を算出した。
(2)中会社
イ Lの割合が0.9の会社
中会社は大会社と小会社の中間の規模の会社であり、とりわけLの割合が0.9の会社(以下「中会社(大)」という。)は、大会社に準ずる会社であって、上場を企図すればすぐに上場できる規模の会社と考えられることから、新興市場に上場する会社と同視し得るものとの考え方の下、新興市場の上場審査基準を基に、総資産価額等を算出した。
ロ Lの割合が0.75の会社
現行通達における取扱いと同様に、中会社(大)の基準のほぼ50%(総資産価額及び取引金額は中会社(大)の50%、従業員数はその60%)に相当する総資産価額等を算出した。
3 大会社の判定基準の見直しに伴う改正
大会社の判定基準に係る総資産価額が改正されたことに伴い、土地保有特定会社の判定基準のうち、総資産価額について改正した。
4 明細書通達の改正
「類似業種比準方式の見直し」及び「会社規模区分の判定基準の見直し」により、明細書通達における次の欄について改正した。
① 「第1表の2 評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書(続)」における「3 会社規模(Lの割合)の判定」中の「判定基準」欄
② 「第2表 特定の評価会社の判定の明細書」における「3 土地保有特定会社」中の「小会社」欄
③ 「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」における「3 類似業種比準価額の計算」中の「1株(50円)当たりの比準価額の計算」欄
④ 「第7表 株式保有特定会社の株式の価額の計算明細書」における「1 S1の金額(類似業種比準価額の修正計算)」中の「1株(50円)当たりの比準価額の計算」欄
(参考)会社規模の判定基準
※アンダーラインを付した部分が改正部分である。
| 改正後 | 改正前 |
| 1 従業員数が70人以上の会社は大会社とする。 2 従業員数が70人未満の会社は次による。 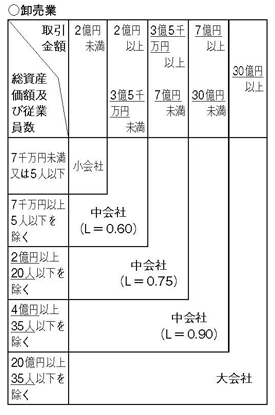 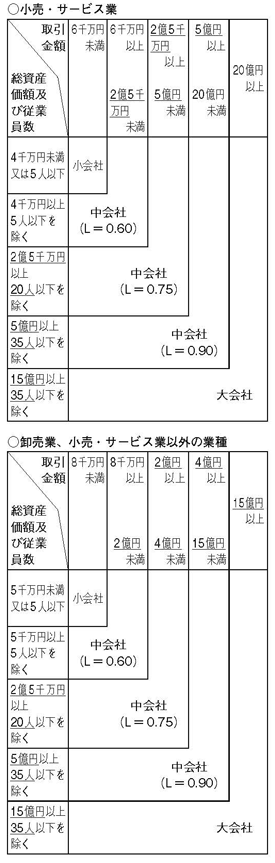 | 1 従業員数が100人以上の会社は大会社とする。 2 従業員数が100人未満の会社は次による。 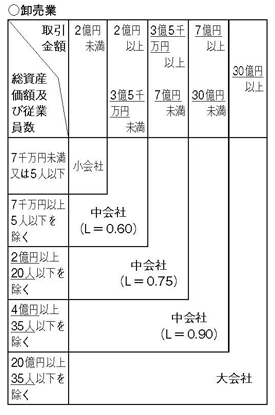 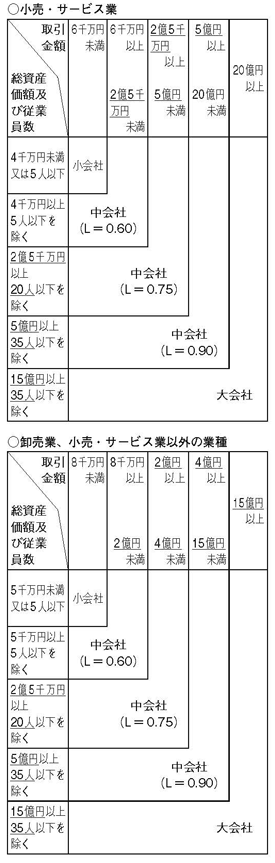 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















