解説記事2017年09月11日 【実務解説】 平成29年度税制改正がM&Aに与える影響(2017年9月11日号・№706)
実務解説
平成29年度税制改正がM&Aに与える影響
公認会計士・税理士 佐藤信祐
Ⅰ はじめに
平成29年度税制改正により、分割型分割における支配関係継続要件が見直され、支配株主による分割承継法人に対する支配が継続することは要求されるものの、分割法人に対する支配が継続することは要求されなくなった(法人税法施行令4の3⑥二イ、ハ(1)、⑦二)。さらに、100%子会社が親会社に対して分割型分割を行う場合には、移転した資産に対する親会社による支配が継続していることから、支配関係継続要件が要求されないことになった(同令4の3⑥一イ)。
本改正の影響は、M&A、子会社整理、事業再生、事業承継など多岐に及ぶと思われるが、本稿では、オーナー企業に対するM&Aに焦点を当てて解説を行いたい。
Ⅱ オーナー企業に対するM&Aの特徴
1 従来の議論 本稿で、オーナー企業に対するM&Aに焦点を当てた理由は、平成29年度税制改正の影響が大きいと思われるからである。なぜなら、オーナー企業に対するM&Aの手法として、事業譲渡や会社分割により事業を譲渡するのではなく、オーナー企業の株式を譲渡した方が有利であると言われているからである(脚注1)。その理由として、①被買収会社(オーナー企業)が保有している資産に含み益があっても、当該含み益が実現しないことから、被買収会社において法人税、住民税及び事業税の負担が発生しない、②被買収会社の株主(オーナー)において生じる所得が配当所得ではなく、譲渡所得であることから、所得税及び住民税の税率が安い(脚注2)、③役員退職慰労金を支給し、被買収会社で役員退職慰労金を損金の額に算入させることにより、法人税、住民税及び事業税の負担を軽減できる、ことが挙げられる。
2 株式譲渡方式は本当に有利なのか しかし、最近の実務では、これらの有利性についての疑問が指摘され始めている。まず、①資産の含み益が実現しないというメリットであるが、例えば、被買収会社が保有している土地の帳簿価額が500百万円であり、時価が3,000百万円であるとしよう。土地そのものを譲渡するのではなく、被買収会社の株式を譲渡した場合には、被買収会社の株主において株式譲渡益が生じるものの、被買収会社において土地譲渡益は生じない。しかし、買収会社からすれば、将来において、被買収会社の土地を5,000百万円で譲渡した場合に、土地譲渡益が2,000百万円でなく、4,500百万円になるというデメリットがある。
すなわち、①のメリットは短期的な視点に基づくものであり、長期的には何らメリットがないと言わざるを得ない。そのため、買収会社が上場会社である場合には、連結財務諸表上、被買収会社の保有する資産を時価で認識したうえで、税効果会計の適用による繰延税金負債を認識する必要があることから、将来の転売における税負担を理由としたディスカウントを要求してくることがある。そして、買収会社がファンドである場合であっても、将来の転売における税負担を考慮することが多いため、同様のディスカウントを要求してくることがある。その結果、①のメリットが期待できるとすれば、買い手が非上場会社であり、かつ、将来の転売が予定されていない場合のみであると考えられる。この場合には、非上場会社の支配株主における相続税評価額の計算上、土地の帳簿価額と相続税評価額との差額に対する「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」を認識することができるという副次的な効果が期待できる(財産評価基本通達186-2)。
次に、②被買収会社の株主において譲渡所得として分類できる、③役員退職慰労金により節税をすることができるというメリットであるが、そもそも被買収会社の株主において所得を発生させる必要があるのかという問題がある。なぜなら、一般的に、相続税評価額の計算上、預金よりも、非上場株式の方が評価額を引き下げやすいからである(脚注3)。すなわち、被買収会社の株主ではなく、被買収会社に譲渡代金が入金される方法(事業譲渡、会社分割など)の方が相続税対策の観点からは有利性が高いということになる。
被買収会社の株主において所得を発生させる必要がないのであれば、配当所得の方が有利なのか、譲渡所得の方が有利なのかという議論は生じない。そのため、事業を譲渡するのではなく、被買収会社の株式を譲渡した方が有利であるかどうかは、事業を譲渡した場合に、被買収会社において生じる事業譲渡益と、被買収会社の株式を譲渡した場合に、被買収会社の株主において生じる株式譲渡益を比較することにより判定すべきである。具体的には、次頁の事例を参照されたい。

現行法上、居住者(被買収会社の株主)が株式を譲渡した場合には、株式譲渡益(譲渡所得)に対して、20.315%(所得税率15.315%、住民税率5%)の税負担が生じる(脚注4)。すなわち、次頁の事例では、株式譲渡益が1,300百万円となり、それに対する譲渡所得税が264百万円となる。これに対し、被買収会社が事業を譲渡した場合には、事業譲渡益に対して、約30%の法人税、住民税及び事業税が生じる(脚注5)。すなわち、上記の事案では、事業譲渡益が600百万円となり、それに対する税負担が180百万円となる。
このように、実効税率だけを考えると、被買収会社の株主において生じる譲渡所得の方が税率が安いように思えるが、事業を譲渡する場合と株式を譲渡する場合とで譲渡原価が異なることから、どちらが有利なのかは事案によって異なる。この点については、法人税の実効税率が引き下げられたことから、より顕著になってきたということが言える。
そのため、そもそも被買収会社の株主において所得を発生させる必要がないということになると、株式譲渡方式が有利であるという論拠はかなり疑わしいということになる。さらに、最近では、中堅企業だけでなく、零細企業もM&Aの対象になるようになってきた。一般的に、零細企業の決算の信用性は低く、デューデリジェンスのコストをかけるよりは、事業譲受方式を採用すべきであることも少なくない(脚注6)。
後述するように、平成29年度税制改正により、適格分割型分割を利用したM&A手法が用いられることが予想されるが、上記のような議論があるということも踏まえてストラクチャーの検討をする必要があると考えられる。
Ⅲ 分割型分割を利用したM&A手法
1 平成29年度税制改正 平成29年度税制改正前であっても、被買収会社のすべての事業を買収するのではなく、一部の事業のみを買収したいというニーズが存在していた。この場合には、買収会社が用意した受皿会社に対して、事業譲渡又は会社分割により事業を移転する手法が多かった。しかし、前述のように、オーナー企業に対するM&Aでは、事業譲渡や会社分割よりも、株式譲渡の方が有利であると言われていたため、被買収会社の株主が受皿会社を設立し、当該受皿会社に対してM&Aの対象にならない事業を事業譲渡又は会社分割により移転させた後に、M&Aの対象になる事業だけになった被買収会社の株式を譲渡するという方法が採用されていた(図1参照)。
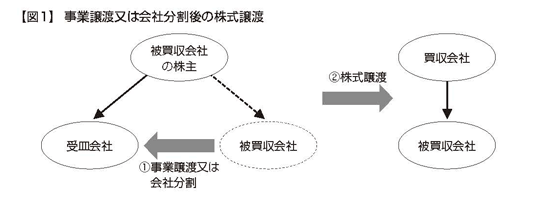
このようなニーズは、不動産M&Aの事案で多かったように思われる。不動産を購入する場合に比べ、不動産会社を購入する場合には、不動産を取得したことに伴う不動産取得税及び登録免許税の負担が生じないという効果も期待できるからである。
さらに、M&Aの対象となる事業だけでなく、M&Aの対象にならない事業にも多額の含み益がある場合には、両方の含み益を実現させない方法が検討されていた。そして、両方の含み益も実現させない手法として、適格分割型分割により、被買収会社のグループ会社に対して、M&Aの対象にならない事業を移転させたうえで、M&Aの対象となる事業のみになった被買収会社株式を譲渡するという方法が用いられていた(図2参照)。
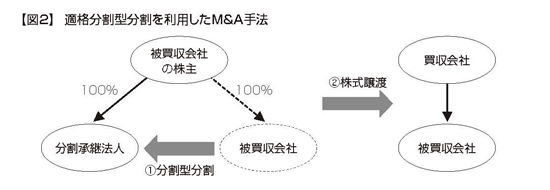
前述のように、平成29年度税制改正により、支配関係継続要件を満たすためには、支配株主による分割承継法人に対する支配関係が継続することが要求されるものの、分割法人に対する支配関係が継続することは要求されなくなったため、上記の手法については、容易に税制適格要件を満たすことが可能になった。
平成29年度税制改正では、スピンオフ税制やスクイーズアウト税制が取り上げられることが多いが、オーナー企業のM&Aに従事する専門家の中では、支配関係継続要件の見直しに対する注目度が高く、オーナー企業のM&Aの実務を変えかねないとも言われている。
2 分割型分割を利用したM&A手法の留意点
(1)株式譲渡損益の計算 適格分割型分割を利用したM&A手法を行う際に留意が必要なのは、分割法人(被買収会社)の株主が分割法人株式を譲渡していることから、株式譲渡損益は生じてしまうという点である。そして、適格分割型分割を行った場合には、以下の金額について、分割法人株式の帳簿価額から分割承継法人株式の帳簿価額に付け替えられる(法人税法施行令119①六、所得税法施行令113①)。
【分割承継法人株式に付け替えるべき金額(脚注7)】
このように、適格分割型分割を利用したM&A手法では、適格分割型分割を行った後の分割法人株式の帳簿価額を把握することが重要になる。
(2)譲渡対価の調整方法 さらに、適格分割型分割を利用したM&A手法を行う際には、分割法人に残る資産及び負債を調整することにより、分割法人株式の時価と帳簿価額を調整することができるという点に留意が必要である。
具体的には、譲渡の対象となる不動産の時価が1,000百万円であり、預かり保証金等の負債が300百万円であり、分割前の分割法人において500百万円の有利子負債があると仮定する。この場合に、分割承継法人にすべての有利子負債を移転するのであれば、分割法人株式の譲渡代金は700百万円となる。これに対し、分割法人にすべての有利子負債を残すのであれば、分割法人株式の譲渡代金は200百万円となる。逆に、分割法人株式の時価を増やしたいのであれば、余剰資金を分割承継法人に移転させるのではなく、分割法人に残せば良いということになる(脚注8)。
このように、分割法人株式の時価を容易に調整することが可能である。実務上は、分割法人の株主に多額の金銭を支払いたいのであれば、分割法人株式の時価を増やせばよいし、分割法人の株主に金銭を支払う必要がないのであれば、分割法人株式の時価を減らせばよい。分割法人の株主で生じる譲渡所得は、分割法人株式の譲渡代金から帳簿価額を控除して計算することから、譲渡代金が小さくなれば、譲渡所得は小さくなりやすいという傾向もある。
さらに、上記の事例では、分割承継法人にすべての有利子負債を移転した場合に比べ、分割法人にすべての有利子負債を残した場合には、分割法人株式の譲渡代金が500百万円減少してしまうが、分割承継法人の時価純資産価額が500百万円増加するという違いが生じる。すなわち、分割法人の株主が譲渡代金を受け取るのではなく、有利子負債の減少により、実質的に、分割承継法人が譲渡代金を受け取ったのに近い状態が生じる。前述のように、分割法人の株主が預金を保有しているよりは、分割承継法人が預金を保有している方が、相続税評価額が安くなりやすいということを考えると、分割法人に有利子負債を残すことにより分割法人株式の譲渡代金を低く抑えた方が有利であるということが言える。
もちろん、このタイミングで、分割法人の株主が譲渡代金の一部を収受したいというニーズもあることから、分割法人株式の譲渡代金を0円ではなく、100百万円にするということも考えられる。この点についても、分割承継法人に移転する預金や有利子負債を調整することにより、ある程度の操作は可能になる。
3 役員退職慰労金の支給
前述のように、役員退職慰労金を支給することにより、被買収会社で節税をすることができることから、オーナー企業に対するM&Aでは、役員退職慰労金を支給してから、被買収会社の株式を譲渡するという手法が一般的である。例えば、被買収会社株式の時価が1,000百万円である場合には、300百万円の役員退職慰労金を支給することにより(脚注9)、700百万円で株式を譲渡する方法が用いられている。
適格分割型分割を利用したM&A手法を行う場合であっても、分割法人株式を譲渡した後に分割法人の役員を退任することから、役員退職慰労金を支給することは可能である。前述の事案では、譲渡の対象となる不動産の時価が1,000百万円であり、預かり保証金等の負債が300百万円であり、分割前の分割法人において500百万円の有利子負債があった。もし、役員退職慰労金の支給額を200百万円とした場合において、分割法人にすべての有利子負債を残すのであれば、分割法人が保有する資産の時価と負債の時価が一致するため、分割法人株式の譲渡代金を0円まで引き下げることが可能になる。その結果、分割法人の株主において譲渡所得を発生させないことが可能になる。
このような役員退職慰労金の支給は、M&Aのタイミングで行われることが多い。例えば、10月1日に分割法人株式を譲渡し、9月30日時点で役員を退任する場合において、役員退職慰労金を支払うためには、分割法人(被買収会社)が資金調達を行う必要がある。実務上、買収会社から分割法人に対する貸付けにより、そのための資金調達を行うことが多いと思われるが(脚注10)、役員退職慰労金の支給により、分割法人株式の時価が引き下げられていることから、買収会社にとっても不都合はないと思われる。
なお、適格分割型分割を利用したM&A手法では、M&Aの対象にならない資産及び負債がすべて分割承継法人に移転していることが望ましい。しかしながら、分割の日の属する事業年度開始の日から分割の日の前日までにおいて生じる法人税、住民税及び事業税を確定させることは難しい。これに対し、役員退職慰労金を支給した場合には、分割の日の属する事業年度において多額の損金が生じることから、多くの場合において課税所得は生じない。その結果、住民税均等割のみを考慮すれば良いということになり(脚注11)、買収会社と被買収会社との間で争いが生じにくいということが言える。
Ⅳ ノンコア事業の切り離し
このように、平成29年度税制改正により、適格分割型分割を利用したM&A手法が用いられることが多いと思われる。そして、最も典型的なケースとして、不動産M&Aが考えられるが、ノンコア事業を切り離す際にも同様の手法を用いることができる。
ただし、M&A市場を見てみると、後継者の不在によりすべての事業をM&Aの対象にすることは多いものの、一部の事業をM&Aの対象にすることはそれほど多くはないように思われる。40代の創業者であれば、M&Aに対する理解があるものの、60代、70代が創業者である場合には、なかなか一部の事業のみをM&Aの対象にすることに対して、心理的な抵抗が強いように感じられる。
しかし、ノンコア事業の存在により不効率な経営が行われているオーナー企業が存在するのも事実であり、世代交代の中で、ノンコア事業を対象としたM&Aが行われる可能性は十分にあると考えられる。その際には、本稿で解説した適格分割型分割を利用したM&A手法が用いられることも考えられる。
Ⅴ むすび
本稿では、平成29年度税制改正による支配関係継続要件の見直しがM&Aに与える影響について解説を行った。気づかれた読者も多いと思われるが、実務上、M&Aを行った後の相続税対策を考慮したうえでM&Aのストラクチャーを検討している事案は、それほど多くはないという問題がある。
平成29年度税制改正により整備された適格分割型分割により一部の事業を譲渡する手法は、M&Aを行った後に、被買収会社側に何かしらの事業が残ることを前提とした手法である。すなわち、M&Aを行った後に残った事業に対する相続税対策を考えざるを得ない手法であることから、今まで検討されていたM&A手法の問題点が無視できないものとなる。
本稿が、皆さまのお役に立つことができれば幸いである。
脚注
1 詳細については、佐藤信祐『税務コストをへらす組織再編のストラクチャー選択』31-37頁(中央経済社、平成29年)を参照されたい。
2 事業譲渡や会社分割により事業を譲渡した場合には、被買収会社に譲渡代金が入金されることから、被買収会社の株主が譲渡代金を受け取る場合には、受取配当金や清算分配金の形で受け取る必要がある。この場合には、所得税法上、配当所得として処理されることになる。
3 これは、類似業種比準方式、折衷方式を採用することにより、時価純資産価額よりも安い評価にすることができるからである。
4 譲渡所得に対する税率は20%(所得税15%、住民税5%)であるが、復興税制により、平成25年から平成49年までの所得税額に対して2.1%の「復興特別所得税」が課されているため、実質的な最高税率は20.315%となる。
5 会社規模、所在地、留保金課税の有無などによって異なるが、本稿では、単純化のために30%とする。
6 詳細については、佐藤前掲(注1)39-48頁を参照されたい。
7 実際には、上記のB/C(分割移転割合)を小数点第3位未満の端数を切り上げて計算するなど、細かな計算規定がなされているが、本稿では詳細な解説は省略する。
8 極端なことを言えば、分割法人株式の譲渡代金を0円にすることができる。例えば、分割前に、金融機関から200百万円を借り入れたうえで、分割型分割により分割承継法人に200百万円の預金を移転させた場合には、分割法人における預かり保証金等の負債が300百万円、有利子負債が700百万円となり、不動産の時価に等しくなるため、分割法人株式の時価が0円となる。
9 法人税法上、役員退職慰労金のうち、不相当に高額なものについては、損金の額に算入することができない(法人税法34②)。そのため、適正な範囲で役員退職慰労金を支給する必要があるが、適正な役員退職慰労金の金額がいくらなのかという点については、実務上、功績倍率法により計算しているケースが多い。
10 代替的な手法として、金融機関から分割法人が借入れを行って、買収会社が連帯保証を行う方法も考えられる。
11 むろん、固定資産税や事業所税などの税金もあるが、法人税、住民税及び事業税に比べて金額を確定させることは容易であろう。
平成29年度税制改正がM&Aに与える影響
公認会計士・税理士 佐藤信祐
Ⅰ はじめに
平成29年度税制改正により、分割型分割における支配関係継続要件が見直され、支配株主による分割承継法人に対する支配が継続することは要求されるものの、分割法人に対する支配が継続することは要求されなくなった(法人税法施行令4の3⑥二イ、ハ(1)、⑦二)。さらに、100%子会社が親会社に対して分割型分割を行う場合には、移転した資産に対する親会社による支配が継続していることから、支配関係継続要件が要求されないことになった(同令4の3⑥一イ)。
本改正の影響は、M&A、子会社整理、事業再生、事業承継など多岐に及ぶと思われるが、本稿では、オーナー企業に対するM&Aに焦点を当てて解説を行いたい。
Ⅱ オーナー企業に対するM&Aの特徴
1 従来の議論 本稿で、オーナー企業に対するM&Aに焦点を当てた理由は、平成29年度税制改正の影響が大きいと思われるからである。なぜなら、オーナー企業に対するM&Aの手法として、事業譲渡や会社分割により事業を譲渡するのではなく、オーナー企業の株式を譲渡した方が有利であると言われているからである(脚注1)。その理由として、①被買収会社(オーナー企業)が保有している資産に含み益があっても、当該含み益が実現しないことから、被買収会社において法人税、住民税及び事業税の負担が発生しない、②被買収会社の株主(オーナー)において生じる所得が配当所得ではなく、譲渡所得であることから、所得税及び住民税の税率が安い(脚注2)、③役員退職慰労金を支給し、被買収会社で役員退職慰労金を損金の額に算入させることにより、法人税、住民税及び事業税の負担を軽減できる、ことが挙げられる。
2 株式譲渡方式は本当に有利なのか しかし、最近の実務では、これらの有利性についての疑問が指摘され始めている。まず、①資産の含み益が実現しないというメリットであるが、例えば、被買収会社が保有している土地の帳簿価額が500百万円であり、時価が3,000百万円であるとしよう。土地そのものを譲渡するのではなく、被買収会社の株式を譲渡した場合には、被買収会社の株主において株式譲渡益が生じるものの、被買収会社において土地譲渡益は生じない。しかし、買収会社からすれば、将来において、被買収会社の土地を5,000百万円で譲渡した場合に、土地譲渡益が2,000百万円でなく、4,500百万円になるというデメリットがある。
すなわち、①のメリットは短期的な視点に基づくものであり、長期的には何らメリットがないと言わざるを得ない。そのため、買収会社が上場会社である場合には、連結財務諸表上、被買収会社の保有する資産を時価で認識したうえで、税効果会計の適用による繰延税金負債を認識する必要があることから、将来の転売における税負担を理由としたディスカウントを要求してくることがある。そして、買収会社がファンドである場合であっても、将来の転売における税負担を考慮することが多いため、同様のディスカウントを要求してくることがある。その結果、①のメリットが期待できるとすれば、買い手が非上場会社であり、かつ、将来の転売が予定されていない場合のみであると考えられる。この場合には、非上場会社の支配株主における相続税評価額の計算上、土地の帳簿価額と相続税評価額との差額に対する「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」を認識することができるという副次的な効果が期待できる(財産評価基本通達186-2)。
次に、②被買収会社の株主において譲渡所得として分類できる、③役員退職慰労金により節税をすることができるというメリットであるが、そもそも被買収会社の株主において所得を発生させる必要があるのかという問題がある。なぜなら、一般的に、相続税評価額の計算上、預金よりも、非上場株式の方が評価額を引き下げやすいからである(脚注3)。すなわち、被買収会社の株主ではなく、被買収会社に譲渡代金が入金される方法(事業譲渡、会社分割など)の方が相続税対策の観点からは有利性が高いということになる。
被買収会社の株主において所得を発生させる必要がないのであれば、配当所得の方が有利なのか、譲渡所得の方が有利なのかという議論は生じない。そのため、事業を譲渡するのではなく、被買収会社の株式を譲渡した方が有利であるかどうかは、事業を譲渡した場合に、被買収会社において生じる事業譲渡益と、被買収会社の株式を譲渡した場合に、被買収会社の株主において生じる株式譲渡益を比較することにより判定すべきである。具体的には、次頁の事例を参照されたい。

現行法上、居住者(被買収会社の株主)が株式を譲渡した場合には、株式譲渡益(譲渡所得)に対して、20.315%(所得税率15.315%、住民税率5%)の税負担が生じる(脚注4)。すなわち、次頁の事例では、株式譲渡益が1,300百万円となり、それに対する譲渡所得税が264百万円となる。これに対し、被買収会社が事業を譲渡した場合には、事業譲渡益に対して、約30%の法人税、住民税及び事業税が生じる(脚注5)。すなわち、上記の事案では、事業譲渡益が600百万円となり、それに対する税負担が180百万円となる。
このように、実効税率だけを考えると、被買収会社の株主において生じる譲渡所得の方が税率が安いように思えるが、事業を譲渡する場合と株式を譲渡する場合とで譲渡原価が異なることから、どちらが有利なのかは事案によって異なる。この点については、法人税の実効税率が引き下げられたことから、より顕著になってきたということが言える。
そのため、そもそも被買収会社の株主において所得を発生させる必要がないということになると、株式譲渡方式が有利であるという論拠はかなり疑わしいということになる。さらに、最近では、中堅企業だけでなく、零細企業もM&Aの対象になるようになってきた。一般的に、零細企業の決算の信用性は低く、デューデリジェンスのコストをかけるよりは、事業譲受方式を採用すべきであることも少なくない(脚注6)。
後述するように、平成29年度税制改正により、適格分割型分割を利用したM&A手法が用いられることが予想されるが、上記のような議論があるということも踏まえてストラクチャーの検討をする必要があると考えられる。
Ⅲ 分割型分割を利用したM&A手法
1 平成29年度税制改正 平成29年度税制改正前であっても、被買収会社のすべての事業を買収するのではなく、一部の事業のみを買収したいというニーズが存在していた。この場合には、買収会社が用意した受皿会社に対して、事業譲渡又は会社分割により事業を移転する手法が多かった。しかし、前述のように、オーナー企業に対するM&Aでは、事業譲渡や会社分割よりも、株式譲渡の方が有利であると言われていたため、被買収会社の株主が受皿会社を設立し、当該受皿会社に対してM&Aの対象にならない事業を事業譲渡又は会社分割により移転させた後に、M&Aの対象になる事業だけになった被買収会社の株式を譲渡するという方法が採用されていた(図1参照)。
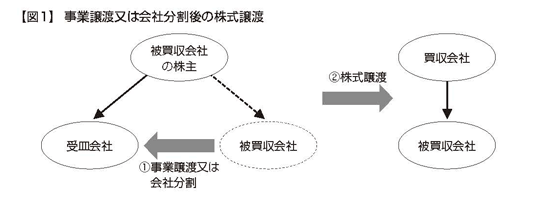
このようなニーズは、不動産M&Aの事案で多かったように思われる。不動産を購入する場合に比べ、不動産会社を購入する場合には、不動産を取得したことに伴う不動産取得税及び登録免許税の負担が生じないという効果も期待できるからである。
さらに、M&Aの対象となる事業だけでなく、M&Aの対象にならない事業にも多額の含み益がある場合には、両方の含み益を実現させない方法が検討されていた。そして、両方の含み益も実現させない手法として、適格分割型分割により、被買収会社のグループ会社に対して、M&Aの対象にならない事業を移転させたうえで、M&Aの対象となる事業のみになった被買収会社株式を譲渡するという方法が用いられていた(図2参照)。
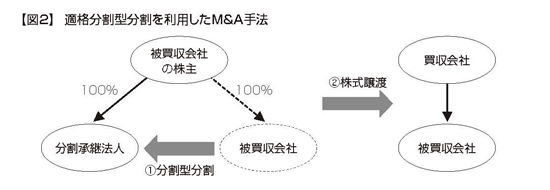
前述のように、平成29年度税制改正により、支配関係継続要件を満たすためには、支配株主による分割承継法人に対する支配関係が継続することが要求されるものの、分割法人に対する支配関係が継続することは要求されなくなったため、上記の手法については、容易に税制適格要件を満たすことが可能になった。
平成29年度税制改正では、スピンオフ税制やスクイーズアウト税制が取り上げられることが多いが、オーナー企業のM&Aに従事する専門家の中では、支配関係継続要件の見直しに対する注目度が高く、オーナー企業のM&Aの実務を変えかねないとも言われている。
2 分割型分割を利用したM&A手法の留意点
(1)株式譲渡損益の計算 適格分割型分割を利用したM&A手法を行う際に留意が必要なのは、分割法人(被買収会社)の株主が分割法人株式を譲渡していることから、株式譲渡損益は生じてしまうという点である。そして、適格分割型分割を行った場合には、以下の金額について、分割法人株式の帳簿価額から分割承継法人株式の帳簿価額に付け替えられる(法人税法施行令119①六、所得税法施行令113①)。
【分割承継法人株式に付け替えるべき金額(脚注7)】
 A=分割法人株式の分割型分割の直前の帳簿価額 B=分割法人の分割型分割の直前の移転純資産の簿価純資産価額 C=分割法人の前期期末時の簿価純資産価額 |
(2)譲渡対価の調整方法 さらに、適格分割型分割を利用したM&A手法を行う際には、分割法人に残る資産及び負債を調整することにより、分割法人株式の時価と帳簿価額を調整することができるという点に留意が必要である。
具体的には、譲渡の対象となる不動産の時価が1,000百万円であり、預かり保証金等の負債が300百万円であり、分割前の分割法人において500百万円の有利子負債があると仮定する。この場合に、分割承継法人にすべての有利子負債を移転するのであれば、分割法人株式の譲渡代金は700百万円となる。これに対し、分割法人にすべての有利子負債を残すのであれば、分割法人株式の譲渡代金は200百万円となる。逆に、分割法人株式の時価を増やしたいのであれば、余剰資金を分割承継法人に移転させるのではなく、分割法人に残せば良いということになる(脚注8)。
このように、分割法人株式の時価を容易に調整することが可能である。実務上は、分割法人の株主に多額の金銭を支払いたいのであれば、分割法人株式の時価を増やせばよいし、分割法人の株主に金銭を支払う必要がないのであれば、分割法人株式の時価を減らせばよい。分割法人の株主で生じる譲渡所得は、分割法人株式の譲渡代金から帳簿価額を控除して計算することから、譲渡代金が小さくなれば、譲渡所得は小さくなりやすいという傾向もある。
さらに、上記の事例では、分割承継法人にすべての有利子負債を移転した場合に比べ、分割法人にすべての有利子負債を残した場合には、分割法人株式の譲渡代金が500百万円減少してしまうが、分割承継法人の時価純資産価額が500百万円増加するという違いが生じる。すなわち、分割法人の株主が譲渡代金を受け取るのではなく、有利子負債の減少により、実質的に、分割承継法人が譲渡代金を受け取ったのに近い状態が生じる。前述のように、分割法人の株主が預金を保有しているよりは、分割承継法人が預金を保有している方が、相続税評価額が安くなりやすいということを考えると、分割法人に有利子負債を残すことにより分割法人株式の譲渡代金を低く抑えた方が有利であるということが言える。
もちろん、このタイミングで、分割法人の株主が譲渡代金の一部を収受したいというニーズもあることから、分割法人株式の譲渡代金を0円ではなく、100百万円にするということも考えられる。この点についても、分割承継法人に移転する預金や有利子負債を調整することにより、ある程度の操作は可能になる。
3 役員退職慰労金の支給
前述のように、役員退職慰労金を支給することにより、被買収会社で節税をすることができることから、オーナー企業に対するM&Aでは、役員退職慰労金を支給してから、被買収会社の株式を譲渡するという手法が一般的である。例えば、被買収会社株式の時価が1,000百万円である場合には、300百万円の役員退職慰労金を支給することにより(脚注9)、700百万円で株式を譲渡する方法が用いられている。
適格分割型分割を利用したM&A手法を行う場合であっても、分割法人株式を譲渡した後に分割法人の役員を退任することから、役員退職慰労金を支給することは可能である。前述の事案では、譲渡の対象となる不動産の時価が1,000百万円であり、預かり保証金等の負債が300百万円であり、分割前の分割法人において500百万円の有利子負債があった。もし、役員退職慰労金の支給額を200百万円とした場合において、分割法人にすべての有利子負債を残すのであれば、分割法人が保有する資産の時価と負債の時価が一致するため、分割法人株式の譲渡代金を0円まで引き下げることが可能になる。その結果、分割法人の株主において譲渡所得を発生させないことが可能になる。
このような役員退職慰労金の支給は、M&Aのタイミングで行われることが多い。例えば、10月1日に分割法人株式を譲渡し、9月30日時点で役員を退任する場合において、役員退職慰労金を支払うためには、分割法人(被買収会社)が資金調達を行う必要がある。実務上、買収会社から分割法人に対する貸付けにより、そのための資金調達を行うことが多いと思われるが(脚注10)、役員退職慰労金の支給により、分割法人株式の時価が引き下げられていることから、買収会社にとっても不都合はないと思われる。
なお、適格分割型分割を利用したM&A手法では、M&Aの対象にならない資産及び負債がすべて分割承継法人に移転していることが望ましい。しかしながら、分割の日の属する事業年度開始の日から分割の日の前日までにおいて生じる法人税、住民税及び事業税を確定させることは難しい。これに対し、役員退職慰労金を支給した場合には、分割の日の属する事業年度において多額の損金が生じることから、多くの場合において課税所得は生じない。その結果、住民税均等割のみを考慮すれば良いということになり(脚注11)、買収会社と被買収会社との間で争いが生じにくいということが言える。
Ⅳ ノンコア事業の切り離し
このように、平成29年度税制改正により、適格分割型分割を利用したM&A手法が用いられることが多いと思われる。そして、最も典型的なケースとして、不動産M&Aが考えられるが、ノンコア事業を切り離す際にも同様の手法を用いることができる。
ただし、M&A市場を見てみると、後継者の不在によりすべての事業をM&Aの対象にすることは多いものの、一部の事業をM&Aの対象にすることはそれほど多くはないように思われる。40代の創業者であれば、M&Aに対する理解があるものの、60代、70代が創業者である場合には、なかなか一部の事業のみをM&Aの対象にすることに対して、心理的な抵抗が強いように感じられる。
しかし、ノンコア事業の存在により不効率な経営が行われているオーナー企業が存在するのも事実であり、世代交代の中で、ノンコア事業を対象としたM&Aが行われる可能性は十分にあると考えられる。その際には、本稿で解説した適格分割型分割を利用したM&A手法が用いられることも考えられる。
Ⅴ むすび
本稿では、平成29年度税制改正による支配関係継続要件の見直しがM&Aに与える影響について解説を行った。気づかれた読者も多いと思われるが、実務上、M&Aを行った後の相続税対策を考慮したうえでM&Aのストラクチャーを検討している事案は、それほど多くはないという問題がある。
平成29年度税制改正により整備された適格分割型分割により一部の事業を譲渡する手法は、M&Aを行った後に、被買収会社側に何かしらの事業が残ることを前提とした手法である。すなわち、M&Aを行った後に残った事業に対する相続税対策を考えざるを得ない手法であることから、今まで検討されていたM&A手法の問題点が無視できないものとなる。
本稿が、皆さまのお役に立つことができれば幸いである。
脚注
1 詳細については、佐藤信祐『税務コストをへらす組織再編のストラクチャー選択』31-37頁(中央経済社、平成29年)を参照されたい。
2 事業譲渡や会社分割により事業を譲渡した場合には、被買収会社に譲渡代金が入金されることから、被買収会社の株主が譲渡代金を受け取る場合には、受取配当金や清算分配金の形で受け取る必要がある。この場合には、所得税法上、配当所得として処理されることになる。
3 これは、類似業種比準方式、折衷方式を採用することにより、時価純資産価額よりも安い評価にすることができるからである。
4 譲渡所得に対する税率は20%(所得税15%、住民税5%)であるが、復興税制により、平成25年から平成49年までの所得税額に対して2.1%の「復興特別所得税」が課されているため、実質的な最高税率は20.315%となる。
5 会社規模、所在地、留保金課税の有無などによって異なるが、本稿では、単純化のために30%とする。
6 詳細については、佐藤前掲(注1)39-48頁を参照されたい。
7 実際には、上記のB/C(分割移転割合)を小数点第3位未満の端数を切り上げて計算するなど、細かな計算規定がなされているが、本稿では詳細な解説は省略する。
8 極端なことを言えば、分割法人株式の譲渡代金を0円にすることができる。例えば、分割前に、金融機関から200百万円を借り入れたうえで、分割型分割により分割承継法人に200百万円の預金を移転させた場合には、分割法人における預かり保証金等の負債が300百万円、有利子負債が700百万円となり、不動産の時価に等しくなるため、分割法人株式の時価が0円となる。
9 法人税法上、役員退職慰労金のうち、不相当に高額なものについては、損金の額に算入することができない(法人税法34②)。そのため、適正な範囲で役員退職慰労金を支給する必要があるが、適正な役員退職慰労金の金額がいくらなのかという点については、実務上、功績倍率法により計算しているケースが多い。
10 代替的な手法として、金融機関から分割法人が借入れを行って、買収会社が連帯保証を行う方法も考えられる。
11 むろん、固定資産税や事業所税などの税金もあるが、法人税、住民税及び事業税に比べて金額を確定させることは容易であろう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















