解説記事2018年03月19日 【ニュース特集】 疑似ストックオプションを巡る税賠訴訟で税理士側が敗訴(2018年3月19日号・№731)
ニュース特集
権利行使時に課税は発生せず、給与所得とした税理士に賠償命令
疑似ストックオプションを巡る税賠訴訟で税理士側が敗訴
疑似ストックオプションの課税関係をめぐる税賠訴訟で、納税者の申告を受任した税理士が敗訴する判決が下された(東京地裁平成29年10月30日判決・民事第13部)。東京地裁の河合芳光裁判長は、疑似ストックオプションの権利行使時には課税は発生しないと判断。納税者による権利行使時に給与所得として申告した税理士の善管注意義務違反を認めたうえで、税理士に3,600万円の損害賠償を命じた。敗訴した税理士が控訴を提起したことから本地裁判決は確定したものではない。ただ、ストックオプションやリストリクテッドストックユニットなど役員報酬が多様化するなか、確定申告を受任した税理士にとって、その課税関係などを詳細に検討する必要があることを浮き彫りにした判決といえそうだ。
ストックオプション制度解禁前に多くの企業が“疑似SO”を利用
疑似ストックオプション(ワラント方式)は、会社が第三者に対して分離型新株引受権付社債を発行し、その第三者から分離された新株引受権を買い戻してその取締役等にその新株引受権を付与するものである。平成9年の商法改正前はストックオプション制度の利用が特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成7年改正)の認定会社等に限られていたことから、ストックオプションと同様の効果を生むスキームとして利用されていた。もっとも、平成9年の商法改正によるストックオプション制度(新株引受権等)の解禁により疑似ストックオプションは大きな意味をなさなくなっていたものの、その後も活用されるケースもみられた。
今回紹介する税賠訴訟は、疑似ストックオプションの課税関係をめぐり、納税者の破産管財人が納税者の確定申告を受任した税理士に対して過大納付に係る損害賠償(3,600万円)を請求した事件である(図表1参照)。
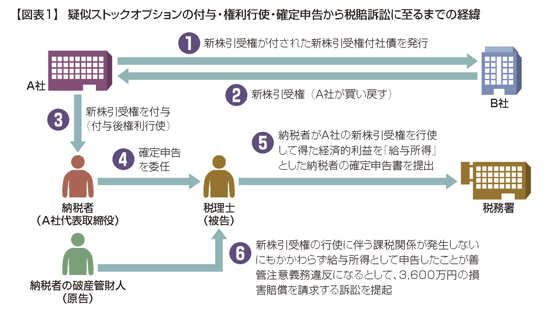
事実関係をみると、納税者が代表取締役を務めるA社(非上場会社)は平成12年7月、B社に対して分離型新株引受権付社債を発行し、新株引受権部分(以下「本件新株引受権」)のみをB社から買い戻したうえで、代表取締役である納税者に対してその本件新株引受権を交付した。納税者は、平成15年と平成16年に本件新株引受権を行使(以下、行使された新株引受権を「本件行使権利」)してA社の株式を取得した。
納税者は、平成15年分及び平成16年分の所得税の確定申告手続きを被告である税理士に委任した。これを受け税理士は、納税者がA社の本件新株引受権を行使して得た経済的利益を給与所得とする確定申告書を提出した。
その後、納税者は平成26年2月に破産手続開始の決定を受けた。納税者の破産管財人に選任された原告は、被告である税理士は納税者からの委任を受けて行った平成15年分及び平成16年分の確定申告において、本件新株引受権の行使に伴う課税関係が発生しないにもかかわらず、給与所得として申告したことが税理士の善管注意義務違反になるとして、債務不履行に基づく損害賠償請求として、損害額の一部である3,600万円を請求する税賠訴訟を提起した。
権利行使時に課税が発生するか否か 本件で問題の1つとなったのは、株式を取得する権利について一定の条件の下、権利行使時に課税する旨を定めた所得税法施行令84条(平成18年改正前のもの。次頁の図表2参照)の適用があるか否かという点である。
【図表2】「所得税法施行令84条(株式等を取得する権利の価額)」(平成18年改正前のもの)
(編注)疑似ストックオプション(分離型新株引受権付社債に付された新株引受権)は所得税法施行令84条1号から3号までに掲げる権利に当たらないことから、1号から3号は省略している。
原告である納税者の破産管財人は、疑似ストックオプションである本件行使権利の行使には所得税法施行令84条の適用はない旨などを主張した。一方で、被告である税理士は、本件行使権利の行使には所得税法施行令84条の適用があり、その権利行使時に給与所得課税がされる旨などを主張した。また、税理士は、時間的制約の中で速やかに申告をする必要があった旨などを指摘し、相応の過失相殺がされるべきであるなどと主張した。
地裁、疑似SOの権利行使時課税は発生しないと判断
東京地裁はまず、所得税法施行令84条が一定の場合に権利取得時ではなく権利行使時に課税することとしたのは、ストックオプションの場合は取得する権利には一般的に譲渡性がなく、権利の付与時には経済的利益を観念することが困難であるとの理由によるものと考えられると指摘。そして疑似ストックオプションについて地裁は、発行法人から新株引受権を取得しているものの第三者に発行した新株引受権を発行法人が買い戻したものであるから、その権利には本来的には譲渡性があり、市場における経済価値を有していたため、取締役等が取得した権利の行使につき制約があるかどうかに関わらず、その付与時に経済的利益を観念することができるから、所得税法施行令84条の適用を認める合理性がなく、同条の適用の基礎がないと考えられると指摘した。さらに地裁は、疑似ストックオプションの権利行使時に課税関係が生じない旨の見解を示した文献(税務大学校の論文等)が複数存在する一方で、これと異なる見解を示した文献等は見当たらない旨などを指摘した。
以上の点を踏まえ地裁は、調査嘱託により示された国税庁の見解(図表3参照)について、同見解は所得税法施行令84条柱書の「発行法人から次の各号に掲げる権利を与えられた場合」の該当性について述べただけであって、疑似ストックオプションに同条の適用の余地があることを肯定したものと見ることには疑問があるとした。また、地裁は、平成18年改正前の所得税法施行令84条4号(有利な発行価額により新株……を取得する権利)は疑似ストックオプションにも形式的には該当する余地がないとはいえないとする一方で、同条4号は元来会社が新株を発行する場合に付与する新株の引受権を対象とした規定とみるべきであって、分離型新株引受権付社債に付された新株引受権が対象となる疑似ストックオプションの性質からすれば、疑似ストックオプションは同号に該当しないと考えるのが相当であるとした。
【図表3】国税庁の見解(裁判所による調査嘱託の結果)
(編注・判決文から抜粋)
そのうえで地裁は、本件新株引受権に係る本件行使権利についても、権利行使時に課税がされないという判断を示した。
給与所得とした税理士の義務違反を認める そして地裁は、税理士の善管注意義務の判断基準(図表4参照)を示したうえで、被告である税理士に善管注意義務違反があるか否かを検討。地裁は、被告である税理士について①平成16年申告書の資料として摘要欄に「新株引受権付社債」と記載された調書を添付していること、②所得内訳に「ワラント行使」や「新株引受権等行使」と記載していたこと、③申告当時、疑似ストックオプションという言葉を知らなかったものの、会社が新株引受権付社債を発行し、その新株引受権を買い戻して役員に付与するものがあることを知っており、その場合に権利行使時に課税がされないことが記載された文献があることを知っていたと思うと述べていることなどの諸事情を踏まえると、本件行使権利について権利行使時に課税関係が発生しないことを容易に認識することができたと推認することができると認定。この点を踏まえ地裁は、被告である税理士は権利行使時の課税関係を検討し、必要であれば更に資料の提供を指示して課税の対象となる法律関係を確認した上で、適正な税務申告を行うべき義務に違反したと判断した。また、過失相殺の有無について地裁は、適正な税務申告がされるように追加の資料提出を求めて課税の対象となる法律関係を確認することは税務の専門家としての基本的な責務であって、時間的制約があるからといってこれを怠ったことによる責任を減じさせるものとなるということはできないなどと指摘し、過失相殺をすることが相当であるということはできないとした。
【図表4】税理士の善管注意義務について地裁が示した判断基準
(編注・判決文から抜粋)
以上の点などを踏まえ地裁は、被告である税理士が本件行使権利の行使に伴う経済的利益を給与所得として申告したことで納税者は約2億円の損害を被ったと認めたうえで、原告である納税者の破産管財人が求めた3,600万円の損害賠償を税理士に対して命じる判決を下した。
なお、地裁判決で敗訴した税理士は控訴を提起している。本誌取材によると、控訴審では、疑似ストックオプションに係る本件行使権利が平成18年改正前の所得税法施行令84条4号(有利な発行価額により新株……を取得する権利)に該当するか否かなどが改めて争われるもようだ。
権利行使時に課税は発生せず、給与所得とした税理士に賠償命令
疑似ストックオプションを巡る税賠訴訟で税理士側が敗訴
疑似ストックオプションの課税関係をめぐる税賠訴訟で、納税者の申告を受任した税理士が敗訴する判決が下された(東京地裁平成29年10月30日判決・民事第13部)。東京地裁の河合芳光裁判長は、疑似ストックオプションの権利行使時には課税は発生しないと判断。納税者による権利行使時に給与所得として申告した税理士の善管注意義務違反を認めたうえで、税理士に3,600万円の損害賠償を命じた。敗訴した税理士が控訴を提起したことから本地裁判決は確定したものではない。ただ、ストックオプションやリストリクテッドストックユニットなど役員報酬が多様化するなか、確定申告を受任した税理士にとって、その課税関係などを詳細に検討する必要があることを浮き彫りにした判決といえそうだ。
ストックオプション制度解禁前に多くの企業が“疑似SO”を利用
疑似ストックオプション(ワラント方式)は、会社が第三者に対して分離型新株引受権付社債を発行し、その第三者から分離された新株引受権を買い戻してその取締役等にその新株引受権を付与するものである。平成9年の商法改正前はストックオプション制度の利用が特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成7年改正)の認定会社等に限られていたことから、ストックオプションと同様の効果を生むスキームとして利用されていた。もっとも、平成9年の商法改正によるストックオプション制度(新株引受権等)の解禁により疑似ストックオプションは大きな意味をなさなくなっていたものの、その後も活用されるケースもみられた。
今回紹介する税賠訴訟は、疑似ストックオプションの課税関係をめぐり、納税者の破産管財人が納税者の確定申告を受任した税理士に対して過大納付に係る損害賠償(3,600万円)を請求した事件である(図表1参照)。
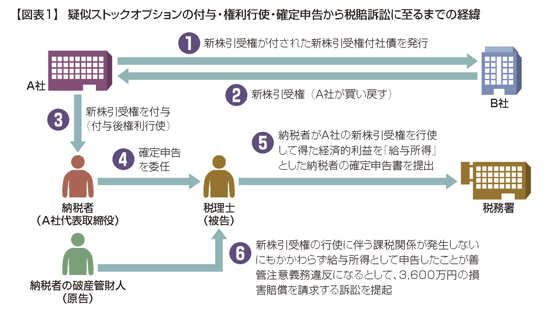
事実関係をみると、納税者が代表取締役を務めるA社(非上場会社)は平成12年7月、B社に対して分離型新株引受権付社債を発行し、新株引受権部分(以下「本件新株引受権」)のみをB社から買い戻したうえで、代表取締役である納税者に対してその本件新株引受権を交付した。納税者は、平成15年と平成16年に本件新株引受権を行使(以下、行使された新株引受権を「本件行使権利」)してA社の株式を取得した。
納税者は、平成15年分及び平成16年分の所得税の確定申告手続きを被告である税理士に委任した。これを受け税理士は、納税者がA社の本件新株引受権を行使して得た経済的利益を給与所得とする確定申告書を提出した。
その後、納税者は平成26年2月に破産手続開始の決定を受けた。納税者の破産管財人に選任された原告は、被告である税理士は納税者からの委任を受けて行った平成15年分及び平成16年分の確定申告において、本件新株引受権の行使に伴う課税関係が発生しないにもかかわらず、給与所得として申告したことが税理士の善管注意義務違反になるとして、債務不履行に基づく損害賠償請求として、損害額の一部である3,600万円を請求する税賠訴訟を提起した。
権利行使時に課税が発生するか否か 本件で問題の1つとなったのは、株式を取得する権利について一定の条件の下、権利行使時に課税する旨を定めた所得税法施行令84条(平成18年改正前のもの。次頁の図表2参照)の適用があるか否かという点である。
【図表2】「所得税法施行令84条(株式等を取得する権利の価額)」(平成18年改正前のもの)
| 発行法人から次の各号に掲げる権利を与えられた場合(……省略……)における当該権利に係る法第36条第2項(収入金額)の価額は、当該権利の行使により取得した株式(これに準ずるものを含む。)のその行使の日(第四号に掲げる権利にあっては、当該権利に基づく払込みに係る期日)における価額から次の各号に掲げる権利の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額による。 一~三(省略) 四 有利な発行価額により新株(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)を取得する権利(前2号に掲げるものを除く。) 当該権利の行使に係る新株の発行価額 |
原告である納税者の破産管財人は、疑似ストックオプションである本件行使権利の行使には所得税法施行令84条の適用はない旨などを主張した。一方で、被告である税理士は、本件行使権利の行使には所得税法施行令84条の適用があり、その権利行使時に給与所得課税がされる旨などを主張した。また、税理士は、時間的制約の中で速やかに申告をする必要があった旨などを指摘し、相応の過失相殺がされるべきであるなどと主張した。
地裁、疑似SOの権利行使時課税は発生しないと判断
東京地裁はまず、所得税法施行令84条が一定の場合に権利取得時ではなく権利行使時に課税することとしたのは、ストックオプションの場合は取得する権利には一般的に譲渡性がなく、権利の付与時には経済的利益を観念することが困難であるとの理由によるものと考えられると指摘。そして疑似ストックオプションについて地裁は、発行法人から新株引受権を取得しているものの第三者に発行した新株引受権を発行法人が買い戻したものであるから、その権利には本来的には譲渡性があり、市場における経済価値を有していたため、取締役等が取得した権利の行使につき制約があるかどうかに関わらず、その付与時に経済的利益を観念することができるから、所得税法施行令84条の適用を認める合理性がなく、同条の適用の基礎がないと考えられると指摘した。さらに地裁は、疑似ストックオプションの権利行使時に課税関係が生じない旨の見解を示した文献(税務大学校の論文等)が複数存在する一方で、これと異なる見解を示した文献等は見当たらない旨などを指摘した。
以上の点を踏まえ地裁は、調査嘱託により示された国税庁の見解(図表3参照)について、同見解は所得税法施行令84条柱書の「発行法人から次の各号に掲げる権利を与えられた場合」の該当性について述べただけであって、疑似ストックオプションに同条の適用の余地があることを肯定したものと見ることには疑問があるとした。また、地裁は、平成18年改正前の所得税法施行令84条4号(有利な発行価額により新株……を取得する権利)は疑似ストックオプションにも形式的には該当する余地がないとはいえないとする一方で、同条4号は元来会社が新株を発行する場合に付与する新株の引受権を対象とした規定とみるべきであって、分離型新株引受権付社債に付された新株引受権が対象となる疑似ストックオプションの性質からすれば、疑似ストックオプションは同号に該当しないと考えるのが相当であるとした。
【図表3】国税庁の見解(裁判所による調査嘱託の結果)
| 国税庁個人課税課は、平成28年5月9日、国内の非上場株式会社の代表取締役が、同社の無担保新株引受権付社債の新株引受権を取得し、その後、平成15年7月1日から平成16年5月31日までの間に同新株引受権を行使し同社の株式を取得した場合において、同取締役につき、同社が第三者に平成12年7月に同社債を発行した後、当該第三者が同取締役に対して同新株引受権を譲渡したときは、所得税法施行令84条柱書の「発行法人から次の各号に掲げる権利を与えられた場合」に該当しないものの、同社が、第三者に同月に同社債を発行した後、当該第三者から同新株引受権を取得して、同取締役に対して同新株引受権を譲渡したときには、同条柱書の「発行法人から次の各号に掲げる権利を与えられた場合」に該当する旨の見解を有している(調査嘱託の結果)。 |
そのうえで地裁は、本件新株引受権に係る本件行使権利についても、権利行使時に課税がされないという判断を示した。
給与所得とした税理士の義務違反を認める そして地裁は、税理士の善管注意義務の判断基準(図表4参照)を示したうえで、被告である税理士に善管注意義務違反があるか否かを検討。地裁は、被告である税理士について①平成16年申告書の資料として摘要欄に「新株引受権付社債」と記載された調書を添付していること、②所得内訳に「ワラント行使」や「新株引受権等行使」と記載していたこと、③申告当時、疑似ストックオプションという言葉を知らなかったものの、会社が新株引受権付社債を発行し、その新株引受権を買い戻して役員に付与するものがあることを知っており、その場合に権利行使時に課税がされないことが記載された文献があることを知っていたと思うと述べていることなどの諸事情を踏まえると、本件行使権利について権利行使時に課税関係が発生しないことを容易に認識することができたと推認することができると認定。この点を踏まえ地裁は、被告である税理士は権利行使時の課税関係を検討し、必要であれば更に資料の提供を指示して課税の対象となる法律関係を確認した上で、適正な税務申告を行うべき義務に違反したと判断した。また、過失相殺の有無について地裁は、適正な税務申告がされるように追加の資料提出を求めて課税の対象となる法律関係を確認することは税務の専門家としての基本的な責務であって、時間的制約があるからといってこれを怠ったことによる責任を減じさせるものとなるということはできないなどと指摘し、過失相殺をすることが相当であるということはできないとした。
【図表4】税理士の善管注意義務について地裁が示した判断基準
| 税務申告の代理の委任を受けた税理士は、税務申告をするに際して、委任者から提供された資料が不十分であるため、これに依拠して申告をすると適正な税務申告がされないおそれがあるときは、委任者に対して追加の資料の提供を指示し、課税の対象となる法律関係を確認した上で、適正な税務申告を行う義務を負うものというべきである。 |
以上の点などを踏まえ地裁は、被告である税理士が本件行使権利の行使に伴う経済的利益を給与所得として申告したことで納税者は約2億円の損害を被ったと認めたうえで、原告である納税者の破産管財人が求めた3,600万円の損害賠償を税理士に対して命じる判決を下した。
なお、地裁判決で敗訴した税理士は控訴を提起している。本誌取材によると、控訴審では、疑似ストックオプションに係る本件行使権利が平成18年改正前の所得税法施行令84条4号(有利な発行価額により新株……を取得する権利)に該当するか否かなどが改めて争われるもようだ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























