解説記事2018年03月19日 【法令解説】 企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正(2018年3月19日号・№731)
法令解説
企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正
金融庁総務企画局企業開示課開示企画調整官 大谷 潤
金融庁総務企画局企業開示課課長補佐 上利悟史
金融庁総務企画局企業開示課課長補佐 堀内 隼
金融庁総務企画局企業開示課係長 岡村健史
Ⅰ はじめに
平成30年1月26日、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(平成30年内閣府令第3号)が公布され、同日から施行された。
これは、平成28年4月18日に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告(以下「DWG報告」という。)における提言を踏まえ、企業と投資者との建設的な対話をより充実・促進させていく観点から、非財務情報の開示充実や開示内容の共通化・合理化を図るものである。
本稿では、改正内容について、パブリックコメントに対する金融庁の考え方なども踏まえて解説する。また、今回の改正の中には、金融庁が法務省とともに、平成29年12月28日に公表した「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」(以下「共通化に向けた対応」という。)の関連部分が含まれているため、これについても併せて紹介する。なお、本稿において、意見にわたる部分については、筆者らの個人的見解であることをあらかじめ申し添えておく。
Ⅱ 改正の概要
DWG報告等の提言を踏まえた改正
(1)非財務情報の開示充実(「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に係る記載の統合と対話に資する内容の充実)
① 背 景 改正前の有価証券報告書では、企業の経営成績等に関し、
(ⅰ)「業績等の概要」として、業績及びキャッシュ・フローの状況について分析的に記載すること、
(ⅱ)「生産、受注及び販売の状況」として、生産、受注及び販売の実績等を記載すること、
(ⅲ)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」(Management Discussion and Analysis。以下「MD&A」という。)として、経営成績に重要な影響を与える要因についての分析など、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況に関する分析・検討内容を記載することが求められていた。これらの項目は、その時々の必要性に応じて追加してきたものだが、現在の開示の状況を見ると、各項目に同じ内容を記載している例が多く見られるなど、内容が重複している部分があるとの意見や、我が国の企業の「MD&A」は、ひな型的な開示となっており付加価値に乏しいとの意見がある。
DWG報告では、こうした意見も踏まえ、内容が重複している部分の合理化を図りつつ、これらの項目で本来意図されていた開示をより充実させ、より体系立った分かりやすい開示を行うことで対話に資するよう、手当てを行うことが適当であるとされた。
② 改正内容 (ⅰ)概要
DWG報告の提言を踏まえ、「業績等の概要」及び「生産、受注及び販売の状況」を「MD&A」に統合し、記載内容の整理を行った。改正後の「MD&A」の項目では、経営成績等の状況(生産、受注及び販売の状況を含む。)の概要及び経営者の視点による当該経営成績等の状況に関する分析・検討内容を記載することとした(表1)。
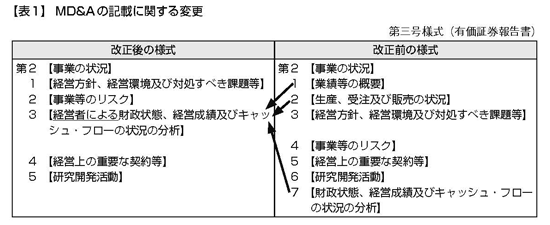
なお、MD&Aの記載に当たって、企業の開示内容が投資者にとってより分かりやすくなるのであれば、改正前の「業績等の概要」、「生産、受注及び販売の状況」及び「MD&A」に相当する内容を一体的に記載することや、別々に記載することのどちらも可能である。
併せて、本改正では、経営成績等の状況の分析・検討の記載を充実させる観点から、
(ア)経営成績等の状況について、事業全体及びセグメント別に、例えば、経営成績に重要な影響を与える要因など、経営者の視点による認識及び分析
(イ)経営者が経営方針・経営戦略等の中長期的な目標に照らして経営成績等をどのように分析・評価しているか
(ウ)資本の財源及び資金の流動性に係る情報
について記載を求めることとした。
「資本の財源及び資金の流動性に係る情報」は投資者が投資判断を行う上で重要な情報であることから、これまでも、分析・検討内容の例として示していたが、現在の開示の状況については、単にキャッシュ・フロー計算書の要約を文章化した記載にとどまり、本来求められる開示が行われていない例が多いとの指摘がある。このため、MD&Aで本来求められる開示内容をより充実させる観点から、記載を求めることとした。記載に当たっては、改正の趣旨を踏まえ、単にキャッシュ・フロー計算書の要約を文章化したものを記載するだけではなく、企業の経営内容に即して、例えば、重要な資本的支出の予定及びその資金の調達源は何であるかなどについて、具体的に記載することが期待される。
(ⅱ)経営者の視点
MD&Aに記載されるべき経営成績等の状況に関する十分な分析・検討は、経営者の視点からなされるべきものであるとの考え方の下、改正前においても、企業の責任者である「提出会社の代表者」による分析・検討内容の記載を求めてきた。しかしながら、現在の開示の状況については、経営者の視点による分析・検討が欠けている例が多いとの指摘があり、DWG報告において、事業全体及びセグメント別の経営成績等に重要な影響を与えた要因について「経営者の視点」による認識と分析などを記載することとされた。これを受けて、MD&Aの記載内容の明確化の観点から、規定を「提出会社の代表者」から「経営者の視点」に変更している。
MD&Aでは、事業の状況等に関して投資者が適正な判断を行うことができるよう、経営者の視点による経営成績等の状況に関する十分な分析・検討内容が記載されることが期待されている。本改正は、MD&Aで本来求められている開示内容をより充実させるとともに、結果的に同様の記載となっている項目の統合を図ることによって、企業と投資者との対話に資する、より体系立った分かりやすい開示の実現を目指して行ったものである。MD&Aの記載に当たっては、こうした趣旨を踏まえ、経営者が早期に関与することなどにより、経営成績等のうち、何を評価し、何を問題視しているかなどについて、投資者により分かりやすい開示を行うことが考えられる。
(ⅲ)その他
四半期報告書及び半期報告書におけるMD&A(半期報告書の場合は「業績等の概要」)では、これまで、前年同四半期連結累計期間(半期報告書の場合は前年同期。以下、この(ⅲ)において同じ。)との比較・分析を記載することを求めてきたが、前年同四半期との比較よりも、当該事業年度の経営状況の方が投資者にとってより重要な情報となる場合もあると考えられる。このため、本改正では、経営戦略等を定めている場合で、当該経営戦略等との比較が前年同四半期連結累計期間との比較よりも、投資者の理解を深めると判断した場合には、前年同四半期連結累計期間との比較・分析に代えて、自社の経営戦略等と比較・分析して記載することを可能とした。
(2)新株予約権等の記載の合理化
① 背 景 有価証券報告書の「新株予約権等の状況」、「ライツプランの内容」及び「ストックオプション制度の内容」は、いずれも株式の希釈化の可能性を明らかにするための開示項目であるが、
・「ライツプランの内容」は買収防衛策として発行された新株予約権であること
・「ストックオプション制度の内容」は役職員の報酬として発行された新株予約権であること
を、それぞれ投資者に明確にするために、「新株予約権等の状況」と一部記載内容が重複する部分が生じることも念頭に置いた上で、別個に記載する欄が設けられていた。
この点について、DWG報告では、「各制度の定着状況等を踏まえると、現時点においては、別個の欄とせずとも投資者が当該有価証券の性質等を誤認するおそれは小さくなったと考えられるため、これらの各欄を統合し、ライツプラン及びストックオプション制度の内容を記載することで開示項目を合理化することが適当である。」と提言された。
また、共通化に向けた対応においても、①有価証券報告書について、「新株予約権等の状況」、「ライツプランの内容」及び「ストックオプション制度の内容」の項目を統合し、かつ、ストックオプションについては、財務諸表注記への集約を可能とする企業内容等の開示に関する内閣府令(以下、「開示府令」という。)の改正を行う、②有価証券報告書における記載時点について、事業年度末から変更がない場合には、その旨を記載することにより提出日の前月末の記載を省略可能とする開示府令の改正を行う、③開示府令の様式の表を撤廃し、一覧表形式で記載することを可能とする開示府令の改正を行うとされている。
② 改正内容 (ⅰ)有価証券報告書及び有価証券届出書の様式改正(脚注1)
DWG報告の提言等を踏まえ、有価証券報告書等の「株式等の状況」欄のうち、改正前の「新株予約権等の状況」以外の箇所における「ライツプランの内容」及び「ストックオプション制度の内容」の記載欄を撤廃し、「新株予約権等の状況」に「①ストックオプション制度の内容」、「②ライツプランの内容」及び「③その他の新株予約権等の状況」を集約して記載できるようにした(表2)。また、改正前の様式の表を撤廃することで、企業の判断により新株予約権の過去発行分を一覧表形式で記載することを可能とした。なお、それぞれの新株予約権の行使期間や行使の条件など、投資者保護上必要なものとして改正前に求めていた各事項については、引き続き記載を要する。
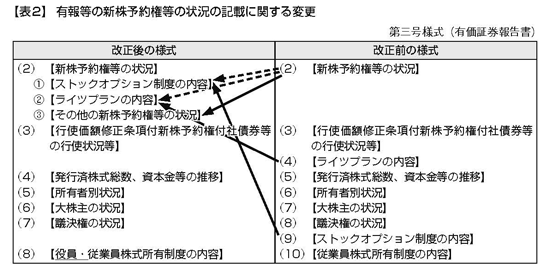
また、「新株予約権等の状況」については、投資判断に必要な最新の情報を投資者に提供する観点から、事業年度末及び有価証券報告書提出日の前月末現在の記載を求めているが、有価証券報告書提出日の前月末現在の情報については、事業年度末の情報から変更がない場合には、変更ない旨の記載のみでよいこととした。これは、事業年度末から変更がない場合には記載が重複するとの指摘を踏まえ、企業負担にも配慮したものである。
併せて、「ストックオプション制度の内容」については、財務諸表注記(日本基準)においてもその内容を記載することとされていることから、「ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項の全部又は一部を「第5経理の状況」のストック・オプションに係る注記に記載している場合には、「ストックオプション制度の内容」に、その旨を記載することにより、当該注記において記載した事項の記載の省略を可能とした(表3)。
【表3】「ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項の全部を「第5 経理の状況」の注記事項(ストック・オプション等関係)に記載している場合の記載例
(ⅱ)四半期報告書及び半期報告書の様式改正(脚注2)
四半期報告書及び半期報告書においては、改正前は、「新株予約権等の状況」、「ライツプランの内容」の項目が設けられていた。本改正により、これらの項目を「新株予約権等の状況」に統合した上で、「①ストックオプション制度の内容」、「②その他の新株予約権等の状況」に分けて記載を求めることとした(表4)。改正前の「ライツプランの内容」は、「②その他の新株予約権等の状況」に含めて記載することとなる。
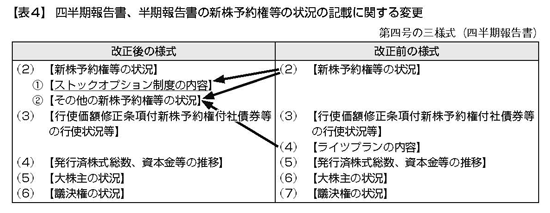 (3)大株主の状況に係る記載の共通化
(3)大株主の状況に係る記載の共通化
① 背 景 DWG報告では、企業と株主・投資者との建設的な対話を充実させていく観点から、事業報告・計算書類と有価証券報告書について、同種の開示項目及び内容となっているものについては記載を共通化できるようにすることが提言された。具体的には、「事業報告の「上位10名の株主の状況」では、所有割合の算定の基礎となる発行済株式について、大株主の議決権に着目して自己株式を控除しているのに対し、有価証券報告書の「大株主の状況」では、流通市場への情報提供等の観点から自己株式を控除していない。しかしながら、自己株式の数に係る情報は「議決権の状況」等でも開示されていることを考慮すると、有価証券報告書における「大株主の状況」においても、発行済株式から自己株式を控除することで事業報告との共通化を図ることが適当である。」とされた。
また、共通化に向けた対応においても、株式の所有割合について、有価証券報告書でも、発行済株式総数から自己株式数を控除して算定することとする開示府令の改正を行うとされた。
② 改正内容 上記の提言等を踏まえ、有価証券報告書等の「大株主の状況」の記載内容を改正(脚注3)し、事業報告と同様に、自己株式を控除した発行済株式の総数を基礎として、大株主の株式所有割合を算定することとし、両者の記載内容を共通化した。
(4)株主総会日程の柔軟化のための開示の見直し
① 背 景 会社法上、株主が基準日から3ヶ月以内に行使する権利に限り、基準日を定めることができるとされていることから、例えば3月決算の会社が7月に株主総会を開催する場合、議決権行使基準日を4月以降(決算日より遅い日)とする必要がある。一方で、有価証券報告書及び事業報告では、事業年度末における「大株主の状況」を記載することとされている。このため、3月決算の会社が7月に株主総会を開催する場合、議決権行使基準日における株主の確定とは別に、大株主の状況等を開示書類に記載するために事業年度末における株主を確定しなければならず、企業の事務負担が増加するおそれがある。
DWG報告では、上場会社は、株主との建設的な対話の促進や、そのための正確な情報提供等の観点を考慮して、株主総会関連の日程を適切に設定すべきであり、上場会社のこうした取組みを後押しする観点から、株主総会に係る開示の日程・手続について自由度を向上させることが必要であるとされ、株主総会日程の柔軟化を図るため、例えば3月決算の会社が株主総会を7月に開催する場合に支障となり得る開示書類の記載を見直すことが提言された。
② 改正内容 DWG報告の提言を踏まえ、議決権行使基準日を決算日以外の日とする企業の事務負担が増加しないようにする観点から、有価証券報告書における「大株主の状況」の記載時点を、事業年度末から原則として議決権行使基準日へ変更した(脚注4)。併せて、有価証券報告書の「大株主の状況」と同様に、株主名簿に依拠して記載される「所有者別状況」及び「議決権の状況」についても、記載時点を事業年度末から原則として議決権行使基準日へ変更した。
(5)適 用 これらの開示府令の改正は、平成30年1月26日に公布、施行されている。なお、改正後の規定は、平成30年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書及び当該事業年度に係る有価証券報告書から適用される。また、半期報告書、四半期報告書については、平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類から適用される。
Ⅲ 有価証券報告書と事業報告等の記載内容の共通化や一体化を容易とするための対応
我が国の年度の企業開示の実務では、株主総会前に会社法に基づく事業報告・計算書類が提供され、株主総会後に金融商品取引法に基づく有価証券報告書が開示されている。このような開示は、
・株主・債権者への情報提供や株主総会に係る適正手続の確保(会社法開示)
・株主・投資者への十分な情報開示の確保(金融商品取引法開示)
という要請を満たすべく、企業の実務も踏まえて構築され、定着してきたものである。
諸外国では、決算期末から株主総会開催日までの期間が日本の場合よりも長く、我が国の金融商品取引法と会社法がそれぞれ要請する開示内容に相当する内容を記載した「一つの書類」を作成し、株主総会前に開示している例が見られる。我が国においても、制度上、金融商品取引法と会社法の両方の要請を満たす「一つの書類」を開示することは可能となっている(脚注5)。しかしながら、実務では、決算期末から株主総会開催日までの期間が諸外国に比べて短いこともあり(脚注6)、「一つの書類」による開示に向けた動きは見られず、また、開示書類の記載例の相違等から記載内容の共通化を行いにくいとの指摘も見られた。
昨年12月28日、金融庁は法務省とともに、投資者と企業との建設的な対話をより促進する観点から、有価証券報告書と事業報告・計算書類の記載内容の共通化や一体化をより容易とするための環境整備の一環として、共通化に向けた対応を公表している。この共通化に向けた対応に掲げた項目のうち法令改正を要するものについては、前述のとおり、今般、改正を行っている。また、その他の項目(従業員の状況、主要な設備の状況、役員の状況、監査報酬の内容等)については、財務会計基準機構の協力を得ながら、今後、有価証券報告書の作成要領において共通の記載が可能であることなどが明確化される予定である。
有価証券報告書と事業報告・計算書類の記載内容の共通化や一体化を行おうとする企業におかれては、これらの取組みも参考にしながら、十分かつ正確、適時な開示を行うことで、投資者との建設的な対話が一層促進されるよう検討いただきたい。
脚注
1 有価証券届出書については、第二号様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式及び第二号の七様式を、有価証券報告書については、第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式を改正。
2 四半期報告書については、第四号の三様式を、半期報告書については、第五号様式及び第五号の二様式を改正。
3 有価証券届出書については、第二号様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式及び第二号の七様式を、有価証券報告書については、第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式を、四半期報告書については、第四号の三様式を、半期報告書については、第五号様式及び第五号の二様式を、親会社等状況報告書については、第五号の四様式を改正。
4 事業報告については、法務省において、「上位10名の株主の状況」の記載時点を議決権行使基準日とすることができるよう会社法施行規則の改正を実施予定。
5 有価証券報告書は、開示府令で一定の様式が定められているが、定められた各記載項目に関連した事項を追加で記載することができるとされている(開示府令第三号様式記載上の注意(1)a)。したがって、事業報告・計算書類に記載することが求められているが、有価証券報告書では必ずしも記載が明示的には求められていない事項についても、有価証券報告書の関連する記載箇所に記載することで、記載内容の共通化や「一つの書類」を作成・開示することは可能だと考えられる。なお、会社法では書類の名称の定めはないため、必ずしも「事業報告」などの名称を示す必要はないと考えられる。
6 なお、多くの企業は議決権行使基準日を決算日に設定しているため、決算日から3ヵ月以内に(3月決算会社であれば6月末までに)株主総会を開催する必要があるが、議決権行使基準日は定款変更により変更することが可能である。実際に、昨年の株主総会において、株主との建設的な対話の促進を理由として議決権行使基準日を変更した企業も見られている。
企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正
金融庁総務企画局企業開示課開示企画調整官 大谷 潤
金融庁総務企画局企業開示課課長補佐 上利悟史
金融庁総務企画局企業開示課課長補佐 堀内 隼
金融庁総務企画局企業開示課係長 岡村健史
Ⅰ はじめに
平成30年1月26日、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(平成30年内閣府令第3号)が公布され、同日から施行された。
これは、平成28年4月18日に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告(以下「DWG報告」という。)における提言を踏まえ、企業と投資者との建設的な対話をより充実・促進させていく観点から、非財務情報の開示充実や開示内容の共通化・合理化を図るものである。
本稿では、改正内容について、パブリックコメントに対する金融庁の考え方なども踏まえて解説する。また、今回の改正の中には、金融庁が法務省とともに、平成29年12月28日に公表した「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について」(以下「共通化に向けた対応」という。)の関連部分が含まれているため、これについても併せて紹介する。なお、本稿において、意見にわたる部分については、筆者らの個人的見解であることをあらかじめ申し添えておく。
Ⅱ 改正の概要
DWG報告等の提言を踏まえた改正
(1)非財務情報の開示充実(「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に係る記載の統合と対話に資する内容の充実)
① 背 景 改正前の有価証券報告書では、企業の経営成績等に関し、
(ⅰ)「業績等の概要」として、業績及びキャッシュ・フローの状況について分析的に記載すること、
(ⅱ)「生産、受注及び販売の状況」として、生産、受注及び販売の実績等を記載すること、
(ⅲ)「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」(Management Discussion and Analysis。以下「MD&A」という。)として、経営成績に重要な影響を与える要因についての分析など、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況に関する分析・検討内容を記載することが求められていた。これらの項目は、その時々の必要性に応じて追加してきたものだが、現在の開示の状況を見ると、各項目に同じ内容を記載している例が多く見られるなど、内容が重複している部分があるとの意見や、我が国の企業の「MD&A」は、ひな型的な開示となっており付加価値に乏しいとの意見がある。
DWG報告では、こうした意見も踏まえ、内容が重複している部分の合理化を図りつつ、これらの項目で本来意図されていた開示をより充実させ、より体系立った分かりやすい開示を行うことで対話に資するよう、手当てを行うことが適当であるとされた。
② 改正内容 (ⅰ)概要
DWG報告の提言を踏まえ、「業績等の概要」及び「生産、受注及び販売の状況」を「MD&A」に統合し、記載内容の整理を行った。改正後の「MD&A」の項目では、経営成績等の状況(生産、受注及び販売の状況を含む。)の概要及び経営者の視点による当該経営成績等の状況に関する分析・検討内容を記載することとした(表1)。
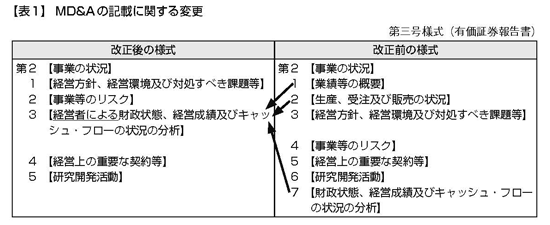
なお、MD&Aの記載に当たって、企業の開示内容が投資者にとってより分かりやすくなるのであれば、改正前の「業績等の概要」、「生産、受注及び販売の状況」及び「MD&A」に相当する内容を一体的に記載することや、別々に記載することのどちらも可能である。
併せて、本改正では、経営成績等の状況の分析・検討の記載を充実させる観点から、
(ア)経営成績等の状況について、事業全体及びセグメント別に、例えば、経営成績に重要な影響を与える要因など、経営者の視点による認識及び分析
(イ)経営者が経営方針・経営戦略等の中長期的な目標に照らして経営成績等をどのように分析・評価しているか
(ウ)資本の財源及び資金の流動性に係る情報
について記載を求めることとした。
「資本の財源及び資金の流動性に係る情報」は投資者が投資判断を行う上で重要な情報であることから、これまでも、分析・検討内容の例として示していたが、現在の開示の状況については、単にキャッシュ・フロー計算書の要約を文章化した記載にとどまり、本来求められる開示が行われていない例が多いとの指摘がある。このため、MD&Aで本来求められる開示内容をより充実させる観点から、記載を求めることとした。記載に当たっては、改正の趣旨を踏まえ、単にキャッシュ・フロー計算書の要約を文章化したものを記載するだけではなく、企業の経営内容に即して、例えば、重要な資本的支出の予定及びその資金の調達源は何であるかなどについて、具体的に記載することが期待される。
(ⅱ)経営者の視点
MD&Aに記載されるべき経営成績等の状況に関する十分な分析・検討は、経営者の視点からなされるべきものであるとの考え方の下、改正前においても、企業の責任者である「提出会社の代表者」による分析・検討内容の記載を求めてきた。しかしながら、現在の開示の状況については、経営者の視点による分析・検討が欠けている例が多いとの指摘があり、DWG報告において、事業全体及びセグメント別の経営成績等に重要な影響を与えた要因について「経営者の視点」による認識と分析などを記載することとされた。これを受けて、MD&Aの記載内容の明確化の観点から、規定を「提出会社の代表者」から「経営者の視点」に変更している。
MD&Aでは、事業の状況等に関して投資者が適正な判断を行うことができるよう、経営者の視点による経営成績等の状況に関する十分な分析・検討内容が記載されることが期待されている。本改正は、MD&Aで本来求められている開示内容をより充実させるとともに、結果的に同様の記載となっている項目の統合を図ることによって、企業と投資者との対話に資する、より体系立った分かりやすい開示の実現を目指して行ったものである。MD&Aの記載に当たっては、こうした趣旨を踏まえ、経営者が早期に関与することなどにより、経営成績等のうち、何を評価し、何を問題視しているかなどについて、投資者により分かりやすい開示を行うことが考えられる。
(ⅲ)その他
四半期報告書及び半期報告書におけるMD&A(半期報告書の場合は「業績等の概要」)では、これまで、前年同四半期連結累計期間(半期報告書の場合は前年同期。以下、この(ⅲ)において同じ。)との比較・分析を記載することを求めてきたが、前年同四半期との比較よりも、当該事業年度の経営状況の方が投資者にとってより重要な情報となる場合もあると考えられる。このため、本改正では、経営戦略等を定めている場合で、当該経営戦略等との比較が前年同四半期連結累計期間との比較よりも、投資者の理解を深めると判断した場合には、前年同四半期連結累計期間との比較・分析に代えて、自社の経営戦略等と比較・分析して記載することを可能とした。
(2)新株予約権等の記載の合理化
① 背 景 有価証券報告書の「新株予約権等の状況」、「ライツプランの内容」及び「ストックオプション制度の内容」は、いずれも株式の希釈化の可能性を明らかにするための開示項目であるが、
・「ライツプランの内容」は買収防衛策として発行された新株予約権であること
・「ストックオプション制度の内容」は役職員の報酬として発行された新株予約権であること
を、それぞれ投資者に明確にするために、「新株予約権等の状況」と一部記載内容が重複する部分が生じることも念頭に置いた上で、別個に記載する欄が設けられていた。
この点について、DWG報告では、「各制度の定着状況等を踏まえると、現時点においては、別個の欄とせずとも投資者が当該有価証券の性質等を誤認するおそれは小さくなったと考えられるため、これらの各欄を統合し、ライツプラン及びストックオプション制度の内容を記載することで開示項目を合理化することが適当である。」と提言された。
また、共通化に向けた対応においても、①有価証券報告書について、「新株予約権等の状況」、「ライツプランの内容」及び「ストックオプション制度の内容」の項目を統合し、かつ、ストックオプションについては、財務諸表注記への集約を可能とする企業内容等の開示に関する内閣府令(以下、「開示府令」という。)の改正を行う、②有価証券報告書における記載時点について、事業年度末から変更がない場合には、その旨を記載することにより提出日の前月末の記載を省略可能とする開示府令の改正を行う、③開示府令の様式の表を撤廃し、一覧表形式で記載することを可能とする開示府令の改正を行うとされている。
② 改正内容 (ⅰ)有価証券報告書及び有価証券届出書の様式改正(脚注1)
DWG報告の提言等を踏まえ、有価証券報告書等の「株式等の状況」欄のうち、改正前の「新株予約権等の状況」以外の箇所における「ライツプランの内容」及び「ストックオプション制度の内容」の記載欄を撤廃し、「新株予約権等の状況」に「①ストックオプション制度の内容」、「②ライツプランの内容」及び「③その他の新株予約権等の状況」を集約して記載できるようにした(表2)。また、改正前の様式の表を撤廃することで、企業の判断により新株予約権の過去発行分を一覧表形式で記載することを可能とした。なお、それぞれの新株予約権の行使期間や行使の条件など、投資者保護上必要なものとして改正前に求めていた各事項については、引き続き記載を要する。
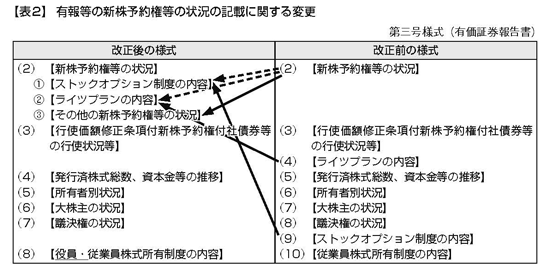
また、「新株予約権等の状況」については、投資判断に必要な最新の情報を投資者に提供する観点から、事業年度末及び有価証券報告書提出日の前月末現在の記載を求めているが、有価証券報告書提出日の前月末現在の情報については、事業年度末の情報から変更がない場合には、変更ない旨の記載のみでよいこととした。これは、事業年度末から変更がない場合には記載が重複するとの指摘を踏まえ、企業負担にも配慮したものである。
併せて、「ストックオプション制度の内容」については、財務諸表注記(日本基準)においてもその内容を記載することとされていることから、「ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項の全部又は一部を「第5経理の状況」のストック・オプションに係る注記に記載している場合には、「ストックオプション制度の内容」に、その旨を記載することにより、当該注記において記載した事項の記載の省略を可能とした(表3)。
【表3】「ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項の全部を「第5 経理の状況」の注記事項(ストック・オプション等関係)に記載している場合の記載例
| ①【ストックオプション制度の内容】 ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載している。 |
(ⅱ)四半期報告書及び半期報告書の様式改正(脚注2)
四半期報告書及び半期報告書においては、改正前は、「新株予約権等の状況」、「ライツプランの内容」の項目が設けられていた。本改正により、これらの項目を「新株予約権等の状況」に統合した上で、「①ストックオプション制度の内容」、「②その他の新株予約権等の状況」に分けて記載を求めることとした(表4)。改正前の「ライツプランの内容」は、「②その他の新株予約権等の状況」に含めて記載することとなる。
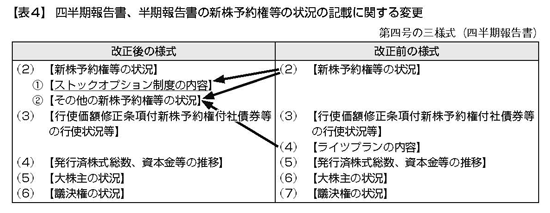 (3)大株主の状況に係る記載の共通化
(3)大株主の状況に係る記載の共通化① 背 景 DWG報告では、企業と株主・投資者との建設的な対話を充実させていく観点から、事業報告・計算書類と有価証券報告書について、同種の開示項目及び内容となっているものについては記載を共通化できるようにすることが提言された。具体的には、「事業報告の「上位10名の株主の状況」では、所有割合の算定の基礎となる発行済株式について、大株主の議決権に着目して自己株式を控除しているのに対し、有価証券報告書の「大株主の状況」では、流通市場への情報提供等の観点から自己株式を控除していない。しかしながら、自己株式の数に係る情報は「議決権の状況」等でも開示されていることを考慮すると、有価証券報告書における「大株主の状況」においても、発行済株式から自己株式を控除することで事業報告との共通化を図ることが適当である。」とされた。
また、共通化に向けた対応においても、株式の所有割合について、有価証券報告書でも、発行済株式総数から自己株式数を控除して算定することとする開示府令の改正を行うとされた。
② 改正内容 上記の提言等を踏まえ、有価証券報告書等の「大株主の状況」の記載内容を改正(脚注3)し、事業報告と同様に、自己株式を控除した発行済株式の総数を基礎として、大株主の株式所有割合を算定することとし、両者の記載内容を共通化した。
(4)株主総会日程の柔軟化のための開示の見直し
① 背 景 会社法上、株主が基準日から3ヶ月以内に行使する権利に限り、基準日を定めることができるとされていることから、例えば3月決算の会社が7月に株主総会を開催する場合、議決権行使基準日を4月以降(決算日より遅い日)とする必要がある。一方で、有価証券報告書及び事業報告では、事業年度末における「大株主の状況」を記載することとされている。このため、3月決算の会社が7月に株主総会を開催する場合、議決権行使基準日における株主の確定とは別に、大株主の状況等を開示書類に記載するために事業年度末における株主を確定しなければならず、企業の事務負担が増加するおそれがある。
DWG報告では、上場会社は、株主との建設的な対話の促進や、そのための正確な情報提供等の観点を考慮して、株主総会関連の日程を適切に設定すべきであり、上場会社のこうした取組みを後押しする観点から、株主総会に係る開示の日程・手続について自由度を向上させることが必要であるとされ、株主総会日程の柔軟化を図るため、例えば3月決算の会社が株主総会を7月に開催する場合に支障となり得る開示書類の記載を見直すことが提言された。
② 改正内容 DWG報告の提言を踏まえ、議決権行使基準日を決算日以外の日とする企業の事務負担が増加しないようにする観点から、有価証券報告書における「大株主の状況」の記載時点を、事業年度末から原則として議決権行使基準日へ変更した(脚注4)。併せて、有価証券報告書の「大株主の状況」と同様に、株主名簿に依拠して記載される「所有者別状況」及び「議決権の状況」についても、記載時点を事業年度末から原則として議決権行使基準日へ変更した。
(5)適 用 これらの開示府令の改正は、平成30年1月26日に公布、施行されている。なお、改正後の規定は、平成30年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書及び当該事業年度に係る有価証券報告書から適用される。また、半期報告書、四半期報告書については、平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類から適用される。
Ⅲ 有価証券報告書と事業報告等の記載内容の共通化や一体化を容易とするための対応
我が国の年度の企業開示の実務では、株主総会前に会社法に基づく事業報告・計算書類が提供され、株主総会後に金融商品取引法に基づく有価証券報告書が開示されている。このような開示は、
・株主・債権者への情報提供や株主総会に係る適正手続の確保(会社法開示)
・株主・投資者への十分な情報開示の確保(金融商品取引法開示)
という要請を満たすべく、企業の実務も踏まえて構築され、定着してきたものである。
諸外国では、決算期末から株主総会開催日までの期間が日本の場合よりも長く、我が国の金融商品取引法と会社法がそれぞれ要請する開示内容に相当する内容を記載した「一つの書類」を作成し、株主総会前に開示している例が見られる。我が国においても、制度上、金融商品取引法と会社法の両方の要請を満たす「一つの書類」を開示することは可能となっている(脚注5)。しかしながら、実務では、決算期末から株主総会開催日までの期間が諸外国に比べて短いこともあり(脚注6)、「一つの書類」による開示に向けた動きは見られず、また、開示書類の記載例の相違等から記載内容の共通化を行いにくいとの指摘も見られた。
昨年12月28日、金融庁は法務省とともに、投資者と企業との建設的な対話をより促進する観点から、有価証券報告書と事業報告・計算書類の記載内容の共通化や一体化をより容易とするための環境整備の一環として、共通化に向けた対応を公表している。この共通化に向けた対応に掲げた項目のうち法令改正を要するものについては、前述のとおり、今般、改正を行っている。また、その他の項目(従業員の状況、主要な設備の状況、役員の状況、監査報酬の内容等)については、財務会計基準機構の協力を得ながら、今後、有価証券報告書の作成要領において共通の記載が可能であることなどが明確化される予定である。
有価証券報告書と事業報告・計算書類の記載内容の共通化や一体化を行おうとする企業におかれては、これらの取組みも参考にしながら、十分かつ正確、適時な開示を行うことで、投資者との建設的な対話が一層促進されるよう検討いただきたい。
脚注
1 有価証券届出書については、第二号様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式及び第二号の七様式を、有価証券報告書については、第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式を改正。
2 四半期報告書については、第四号の三様式を、半期報告書については、第五号様式及び第五号の二様式を改正。
3 有価証券届出書については、第二号様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式及び第二号の七様式を、有価証券報告書については、第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式を、四半期報告書については、第四号の三様式を、半期報告書については、第五号様式及び第五号の二様式を、親会社等状況報告書については、第五号の四様式を改正。
4 事業報告については、法務省において、「上位10名の株主の状況」の記載時点を議決権行使基準日とすることができるよう会社法施行規則の改正を実施予定。
5 有価証券報告書は、開示府令で一定の様式が定められているが、定められた各記載項目に関連した事項を追加で記載することができるとされている(開示府令第三号様式記載上の注意(1)a)。したがって、事業報告・計算書類に記載することが求められているが、有価証券報告書では必ずしも記載が明示的には求められていない事項についても、有価証券報告書の関連する記載箇所に記載することで、記載内容の共通化や「一つの書類」を作成・開示することは可能だと考えられる。なお、会社法では書類の名称の定めはないため、必ずしも「事業報告」などの名称を示す必要はないと考えられる。
6 なお、多くの企業は議決権行使基準日を決算日に設定しているため、決算日から3ヵ月以内に(3月決算会社であれば6月末までに)株主総会を開催する必要があるが、議決権行使基準日は定款変更により変更することが可能である。実際に、昨年の株主総会において、株主との建設的な対話の促進を理由として議決権行使基準日を変更した企業も見られている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























