解説記事2018年04月02日 【税務マエストロ】 恒久的施設(PE)に関する改正(2018年4月2日号・№733)
税務マエストロ
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座
今週のマエストロ&テーマ
恒久的施設(PE)に関する改正
#210 品川克己
PwC税理士法人
略歴 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究。97年より00年までOECD租税委員会に主任行政官として出向(在フランス)し、「OECD移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財務省を辞職し現職。
次回のテーマ
#211
非課税(9)
税理士 熊王征秀 消費税率引上げ、それに伴う課税の適正化など、消費税法の改正が続く。消費税マエストロが実務ポイントを解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
ta@lotus21.co.jp
マエストロの解説 2018年度(平成30年度)の税制改正では、恒久的施設(PE:Permanent Establishment)の定義等が大きく改正される。これは、日本企業の健全な海外展開を支えることにより海外の成長を国内に取り込むとともに、国際的な脱税や租税回避に対してより効果的に対応していくという基本スタンスに沿った改正と位置付けられている。特に、BEPSプロジェクトの合意事項の着実な実施を通じた国際協調の推進の観点から、BEPSプロジェクトの合意事項が盛り込まれたBEPS防止措置実施条約やOECDモデル租税条約を踏まえたもので、具体的には「恒久的施設認定の人為的回避に対応」する改正といえる。
1 BEPSプロジェクトにおける問題提起と勧告
(1)主要な論点 恒久的施設(PE)とは、事業を行う一定の場所(支店等)であり、租税条約上、自国の企業が相手国内で事業を行う場合、相手国内にその企業のPEがなければ、相手国はその企業の事業利得に課税できない(「PEなければ課税なし」)とされている。そのため、人為的にPEに該当しないような方法で事業を営み、相手国内での課税を不当にさける行為をいかに防止するかについて議論が行われた。その結果、①代理人PEの要件に該当しない販売委託契約の利用、②PEと認定されない活動のみを行うことによるPE認定の人為的な回避に対処するため、モデル条約のPEの定義の修正が勧告されたものである。
(2)最終報告書の内容
① 代理人PE回避への対応 現行モデル条約では、「企業(本人)の名で契約を締結する」者は代理人PEとなる(代理人業を通常業務とする者(独立代理人)を除く)。そこで、①代理人の名で契約を締結する、②契約締結に至る実質的な活動を代理人が行い、契約の締結は本人が行う、③関連企業を独立代理人とすることで、PE認定が回避されるという問題が指摘され、これらを回避するため次の対策が勧告された。
イ)契約者名基準に加え、契約類型基準(企業(本人)の物品の販売契約等)によって代理人PEを認定する。
ロ)PEと認定される代理人の活動に、「契約の締結につながる主要な役割を果たすこと」を追加する。
ハ)専ら関連企業のためにのみ業務を行う者を、独立代理人の定義から除外する。
② 準備的・補助的活動の見直し 現行のモデル条約では、商品の引渡しや購入のみを行う場所等は、その活動が企業の本質的活動である場合でもPEと認定されないため、こうした場合には事業利得に対するPE所在地国の課税権が不当に損なわれることになると指摘された。こうした事態に対応するため、次のような対策が勧告された。
いかなる活動も準備的・補助的活動でない場合はPE認定の例外としないこととし、かつ、各場所が相互に補完的な活動を行う場合は、各場所を一体の場所とみなしてPE認定を行うこととする。また、別の対策方法として、特定の活動(商品の引渡し等)についてのみ、準備的・補助的活動でない場合にPE認定の例外としないとすることにより対応する。
2 代理人PEの定義の拡大
(1)現行規定 現行法人税法及び所得税法では、次のように、外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者(「独立代理人」を除く)が「代理人PE」とされている。
(ア)外国法人のために、その事業に関し契約(その外国法人が資産を購入するための契約を除く)を締結する権限を有し、かつ、これを継続的に又は反復して行使する者(その外国法人の事業と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づきその外国法人のために当該契約の締結に係る業務を行う者を除く)
(イ)外国法人のために、顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
(ウ)専ら又は主として一の外国法人(その外国法人の主要な株主等その他その外国法人と特殊の関係のある者を含む)のために、継続的に又は反復して、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者
また、その代理人が、その事業に係る業務(代理人としての業務)を、上記の外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該者は、「独立代理人」として「代理人PE」から除かれている。
(2)改正概要 代理人PEの範囲に、「国内において非居住者または外国法人のために、その事業に関し反復して契約を締結し、又は一定の契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者で、これらの契約が非居住者等の資産の所有権の移転等に関する契約である場合における当該者」が追加される。代理人PEは、外国法人の名で契約締結等を行うことが一つの要件であり、代理人の名で契約を行えば代理人PEに該当しないとの解釈もあった。そこで改正案は、追加的に、「契約者名」にとらわれず「契約」そのものに着目して「代理人PE」をとらえることとなる。
この改正により、いわゆるコミッショネア契約(販売委託契約)の受託者(コミッショネア)は代理人PEに該当する可能性がある。コミッショネア契約とは、外国法人(委託者企業)の売買契約等について、代理人が当該企業に代わって契約等を締結するものであるが、その際、契約の締結に当たっては代理人(受託者)の名で契約する販売委託契約である。委託者の名でなく受託者の名で契約を締結することにより、代理人PEの認定を人為的に回避しているといわれていた(図1参照)。
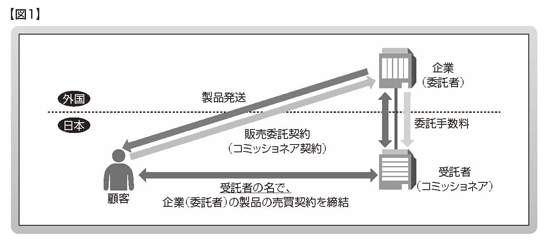
また、独立代理人の範囲から、専ら又は主として一又は二以上の自己と密接に関連する者に代わって行動する者が除外される。この「密接に関連する者」とは、その個人または法人との間に直接・間接の持分割合50%超の関係その他の支配・被支配の関係にある者が該当する。
3 準備的・補助的活動の範囲の見直し
(1)現行規定 現行法人税法及び所得税法では、次のように、資産の購入、資産の保管、準備的・補助的活動を行う場合にはPEに認定されないこととされている。
(ア)外国法人がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所
(イ)外国法人がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所
(ウ)外国法人が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他その事業の遂行にとつて補助的な機能を有する事業上の活動を行うためにのみ使用する一定の場所
(2)改正概要 現行法上、上記準備的・補助的活動等特定の活動を行うことのみを目的として使用する事業を行う一定の場所等はPEに含まれないが、改正案では、その活動が非居住者等の事業の遂行にとって準備的又は補助的な機能を有する場合に限ることとされる。したがって、資産の保管のための倉庫であっても、その倉庫が準備的又は補助的な役割ではなく、事業全体の中で重要な機能を果たす場合にはPEと認定されることとなる。なお、そのようなケースでは、事業の重要な機能が果たされているのであれば、それはそもそも単なる倉庫でないため、現行規定でもPE認定することが可能とも考えられる。
今回の改正の目的は、次の図2のような昨今のネット通販を対象としていると考えられる。つまり、ネット通販事業に従事する外国法人が、日本国内に相当数の従業員が勤務する巨大倉庫を保有し、この倉庫を通じて行われる製品の保管・引渡しの活動が、企業の製品販売事業の本質的な部分を構成する場合には、明確にPEを有することとなろう。
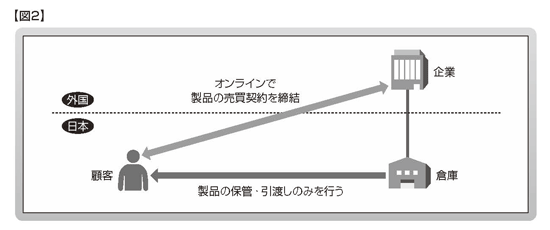
また、事業を行う一定の場所を有する非居住者等と密接に関連する者が当該一定の場所等において事業活動を行う等の場合において、当該一定の場所等がその者のPEを構成する等の一定の要件に該当するとき(当該事業活動が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る)は、上記の取扱いは当該一定の場所については適用されない。
4 租税条約との調整 日本が締結した租税条約上、国内法のPEの定義と異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける非居住者等については、その条約上のPEを国内法上のPEとするように改正される。PEの範囲については租税条約が優先することとなる。
なお、租税条約は個別に改正する必要があるが、BEPS防止措置実施条約(マルチ条約)が適用され、修正点が合致する国との間では、個別の租税条約の改正を待たずとも結果的にPEの定義が修正されることとなる。
記事に関連するお問い合わせ先 記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
今週のマエストロ&テーマ
恒久的施設(PE)に関する改正
#210 品川克己
PwC税理士法人
略歴 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事。96年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究。97年より00年までOECD租税委員会に主任行政官として出向(在フランス)し、「OECD移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」の改定、及び関連会議の運営に従事。01年9月財務省を辞職し現職。
次回のテーマ
#211
非課税(9)
税理士 熊王征秀 消費税率引上げ、それに伴う課税の適正化など、消費税法の改正が続く。消費税マエストロが実務ポイントを解説する。
※取り上げて欲しいテーマを編集部にお寄せください。
ta@lotus21.co.jp
マエストロの解説 2018年度(平成30年度)の税制改正では、恒久的施設(PE:Permanent Establishment)の定義等が大きく改正される。これは、日本企業の健全な海外展開を支えることにより海外の成長を国内に取り込むとともに、国際的な脱税や租税回避に対してより効果的に対応していくという基本スタンスに沿った改正と位置付けられている。特に、BEPSプロジェクトの合意事項の着実な実施を通じた国際協調の推進の観点から、BEPSプロジェクトの合意事項が盛り込まれたBEPS防止措置実施条約やOECDモデル租税条約を踏まえたもので、具体的には「恒久的施設認定の人為的回避に対応」する改正といえる。
1 BEPSプロジェクトにおける問題提起と勧告
(1)主要な論点 恒久的施設(PE)とは、事業を行う一定の場所(支店等)であり、租税条約上、自国の企業が相手国内で事業を行う場合、相手国内にその企業のPEがなければ、相手国はその企業の事業利得に課税できない(「PEなければ課税なし」)とされている。そのため、人為的にPEに該当しないような方法で事業を営み、相手国内での課税を不当にさける行為をいかに防止するかについて議論が行われた。その結果、①代理人PEの要件に該当しない販売委託契約の利用、②PEと認定されない活動のみを行うことによるPE認定の人為的な回避に対処するため、モデル条約のPEの定義の修正が勧告されたものである。
(2)最終報告書の内容
① 代理人PE回避への対応 現行モデル条約では、「企業(本人)の名で契約を締結する」者は代理人PEとなる(代理人業を通常業務とする者(独立代理人)を除く)。そこで、①代理人の名で契約を締結する、②契約締結に至る実質的な活動を代理人が行い、契約の締結は本人が行う、③関連企業を独立代理人とすることで、PE認定が回避されるという問題が指摘され、これらを回避するため次の対策が勧告された。
イ)契約者名基準に加え、契約類型基準(企業(本人)の物品の販売契約等)によって代理人PEを認定する。
ロ)PEと認定される代理人の活動に、「契約の締結につながる主要な役割を果たすこと」を追加する。
ハ)専ら関連企業のためにのみ業務を行う者を、独立代理人の定義から除外する。
② 準備的・補助的活動の見直し 現行のモデル条約では、商品の引渡しや購入のみを行う場所等は、その活動が企業の本質的活動である場合でもPEと認定されないため、こうした場合には事業利得に対するPE所在地国の課税権が不当に損なわれることになると指摘された。こうした事態に対応するため、次のような対策が勧告された。
いかなる活動も準備的・補助的活動でない場合はPE認定の例外としないこととし、かつ、各場所が相互に補完的な活動を行う場合は、各場所を一体の場所とみなしてPE認定を行うこととする。また、別の対策方法として、特定の活動(商品の引渡し等)についてのみ、準備的・補助的活動でない場合にPE認定の例外としないとすることにより対応する。
2 代理人PEの定義の拡大
(1)現行規定 現行法人税法及び所得税法では、次のように、外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者(「独立代理人」を除く)が「代理人PE」とされている。
(ア)外国法人のために、その事業に関し契約(その外国法人が資産を購入するための契約を除く)を締結する権限を有し、かつ、これを継続的に又は反復して行使する者(その外国法人の事業と同一又は類似の事業を営み、かつ、その事業の性質上欠くことができない必要に基づきその外国法人のために当該契約の締結に係る業務を行う者を除く)
(イ)外国法人のために、顧客の通常の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、当該資産を顧客の要求に応じて引き渡す者
(ウ)専ら又は主として一の外国法人(その外国法人の主要な株主等その他その外国法人と特殊の関係のある者を含む)のために、継続的に又は反復して、その事業に関し契約を締結するための注文の取得、協議その他の行為のうちの重要な部分をする者
また、その代理人が、その事業に係る業務(代理人としての業務)を、上記の外国法人に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合における当該者は、「独立代理人」として「代理人PE」から除かれている。
(2)改正概要 代理人PEの範囲に、「国内において非居住者または外国法人のために、その事業に関し反復して契約を締結し、又は一定の契約の締結のために反復して主要な役割を果たす者で、これらの契約が非居住者等の資産の所有権の移転等に関する契約である場合における当該者」が追加される。代理人PEは、外国法人の名で契約締結等を行うことが一つの要件であり、代理人の名で契約を行えば代理人PEに該当しないとの解釈もあった。そこで改正案は、追加的に、「契約者名」にとらわれず「契約」そのものに着目して「代理人PE」をとらえることとなる。
この改正により、いわゆるコミッショネア契約(販売委託契約)の受託者(コミッショネア)は代理人PEに該当する可能性がある。コミッショネア契約とは、外国法人(委託者企業)の売買契約等について、代理人が当該企業に代わって契約等を締結するものであるが、その際、契約の締結に当たっては代理人(受託者)の名で契約する販売委託契約である。委託者の名でなく受託者の名で契約を締結することにより、代理人PEの認定を人為的に回避しているといわれていた(図1参照)。
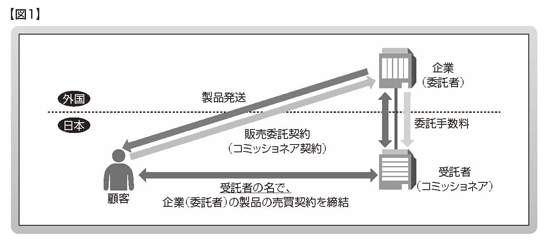
また、独立代理人の範囲から、専ら又は主として一又は二以上の自己と密接に関連する者に代わって行動する者が除外される。この「密接に関連する者」とは、その個人または法人との間に直接・間接の持分割合50%超の関係その他の支配・被支配の関係にある者が該当する。
| 【参考】OECDモデル条約5条5項及び6項の改正 |
| 現行の代理人PEの要件 | 改正後の代理人PEの要件 |
| 企業のために相手国内で行動する者は、以下の要件を満たす場合に代理人PEとされる。 | 企業のために相手国内で行動する者は、以下の要件を満たす場合に代理人PEとされる。 |
| 1.企業の名において締結される契約であること。 | 1.次のいずれかの契約であること ①企業の名において締結される契約であること ②企業の物品の販売に関する契約であること ③企業による役務提供に関する契約であること |
| 2.代理人が契約を締結すること。 | 2.次のいずれかの行為を行うこと ①代理人が契約を締結すること ②代理人が契約の締結に繋がる主要な役割を担うこと |
| 3.ただし、代理人業を通常業務として行う者(独立代理人)は、代理人PEとされない。 | 3.ただし、代理人業を通常業務として行う者(独立代理人)は、代理人PEとされない(ただし、専ら関連企業のためにのみ代理人業を行う者を除く)。 |
3 準備的・補助的活動の範囲の見直し
(1)現行規定 現行法人税法及び所得税法では、次のように、資産の購入、資産の保管、準備的・補助的活動を行う場合にはPEに認定されないこととされている。
(ア)外国法人がその資産を購入する業務のためにのみ使用する一定の場所
(イ)外国法人がその資産を保管するためにのみ使用する一定の場所
(ウ)外国法人が広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究その他その事業の遂行にとつて補助的な機能を有する事業上の活動を行うためにのみ使用する一定の場所
(2)改正概要 現行法上、上記準備的・補助的活動等特定の活動を行うことのみを目的として使用する事業を行う一定の場所等はPEに含まれないが、改正案では、その活動が非居住者等の事業の遂行にとって準備的又は補助的な機能を有する場合に限ることとされる。したがって、資産の保管のための倉庫であっても、その倉庫が準備的又は補助的な役割ではなく、事業全体の中で重要な機能を果たす場合にはPEと認定されることとなる。なお、そのようなケースでは、事業の重要な機能が果たされているのであれば、それはそもそも単なる倉庫でないため、現行規定でもPE認定することが可能とも考えられる。
今回の改正の目的は、次の図2のような昨今のネット通販を対象としていると考えられる。つまり、ネット通販事業に従事する外国法人が、日本国内に相当数の従業員が勤務する巨大倉庫を保有し、この倉庫を通じて行われる製品の保管・引渡しの活動が、企業の製品販売事業の本質的な部分を構成する場合には、明確にPEを有することとなろう。
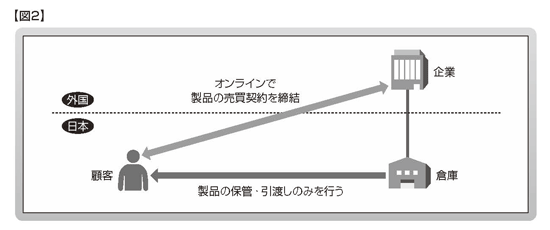
また、事業を行う一定の場所を有する非居住者等と密接に関連する者が当該一定の場所等において事業活動を行う等の場合において、当該一定の場所等がその者のPEを構成する等の一定の要件に該当するとき(当該事業活動が一体的な業務の一部として補完的な機能を果たすときに限る)は、上記の取扱いは当該一定の場所については適用されない。
| 【参考】OECDモデル条約5条4項(PEに含まれないもの)改正 |
| 現行の規定 | 改正後の規定 |
| 4 次の活動を行う場合は「恒久的施設」に当たらない。 (a)物品等の保管・展示・引渡しのためにのみ施設を使用 (b)企業の在庫を保管・展示・引渡しのためにのみ保有 (c)企業の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有 (d)企業のために物品等を購入し、又は情報収集のみを目的として、一定の場所を保有 (e)企業のためにその他の準備的又は補助的な性格の活動を行うことのみを目的として、一定の場所を保有 (f)(a)から(e)までの活動を組み合わせた活動のみを目的として、一定の場所を保有。ただし、その組合せによる活動の全体が準備的又は補助的な性格のものである場合に限る。 | 4 次の活動を行う場合は「恒久的施設」に当たらない。 ただし、その(a)から(e)の活動((f)の場合には、その組合せによる活動の全体)が準備的又は補助的な性格のものである場合に限る。 (a)物品等の保管・展示・引渡しのためにのみ施設を使用 (b)企業の在庫を保管・展示・引渡しのためにのみ保有 (c)企業の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有 (d)企業のために物品等を購入し、又は情報収集のみを目的として、一定の場所を保有 (e)企業のためにその他の活動を行うことのみを目的として、一定の場所を保有 (f)(a)から(e)までの活動を組み合わせた活動のみを目的として、一定の場所を保有 【上記改正の代替案】 現行の規定から「引渡し(a)(b)」「物品等の購入(d)」、「情報収集(d)」を削除し、これからの活動は、(e)の規定により、準備的・補助的活動である場合にのみPEの例外とする。 |
4 租税条約との調整 日本が締結した租税条約上、国内法のPEの定義と異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける非居住者等については、その条約上のPEを国内法上のPEとするように改正される。PEの範囲については租税条約が優先することとなる。
なお、租税条約は個別に改正する必要があるが、BEPS防止措置実施条約(マルチ条約)が適用され、修正点が合致する国との間では、個別の租税条約の改正を待たずとも結果的にPEの定義が修正されることとなる。
記事に関連するお問い合わせ先 記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
TEL:03-5281-0020 FAX:03-5281-0030 e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























