資料2018年09月17日 【重要資料】 スピンオフに関するQ&A(経済産業省)(2018年9月17日号・№755)
重要資料
スピンオフに関するQ&A(経済産業省)
(編注:経済産業省『「スピンオフ」の活用に関する手引』から抜粋)
(一般)
税法上の「スピンオフ」に該当するものは、次の二つです。
① 分割型分割……自社内の特定の事業部門を分割により別法人に移転させ、同時に設立時に交付を受けるその法人の株式の全てを自社の株主に交付する方法(※適格組織再編に該当するためには単独新設分割であることが必要)
② 株式分配……自社の完全子法人の発行済株式の全部を自社の株主に全て分配する方法(※外国法人である完全子法人の場合も想定されます)
※ 上記のほか、①と②の中間形態として、「新設分社型分割又は新設現物出資+(一定期間経過後の)株式分配」という方式によるスピンオフも考えられます。
※ 以降のQ&Aでは、税法上のスピンオフに該当する分割型分割と株式分配を指して、「スピンオフ」と呼んでいます。
① 分割型分割の場合
会社法に基づき、株主総会決議など、会社分割及び剰余金の配当の手続を行うことが必要です。特に、適格組織再編に該当するスピンオフは、「株式のみ按分交付要件」を満たすために、金銭分配請求権のない現物配当であり、剰余金の配当に係る株主総会特別決議が必要となります(会社法第309条第2項第10号)。また、分配可能額規制など、剰余金配当に係る規制の一部は適用されない(会社法第812条)、債権者保護手続(会社法第810条)が必要となる、スピンオフしようとする会社の株主に株式買取請求権が認められる(会社法第806条)といった特徴があります。ただし、簡易新設分割に該当する場合には、新設分割計画の承認の株主総会決議は不要で(会社法第805条)、新設分割会社の株主には新設分割の差止請求権はなく(会社法第805条の2ただし書)反対株主の買取請求権は認められません(会社法第806条第1項第2号)。
なお、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律に基づく手続、許認可等に関する手続等、関係法令に基づく手続を行うことも必要です。
② 株式分配の場合
会社法に基づき、株主総会決議など、剰余金の配当の手続を行うことが必要です。特に、金銭分配請求権のない現物配当については、剰余金の配当に係る株主総会特別決議が必要となります(会社法第309条第2項第10号)。また、株式分配を行うに足りる分配可能額があることを確認することが必要(※)、債権者保護手続が不要、スピンオフしようとする会社の株主の株式買取請求権は認められていないといった特徴があります。
なお、許認可等に関する手続等、関係法令に基づく手続が必要となる場合があります。
(※)現物配当を行う会社の会計処理について定めている「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会)第10項では、分割型分割、株式分配いずれの場合も、帳簿価額をもって処理することとされており、分配可能額の確認においても、子会社株式の価額は帳簿価額をもって計算することになると考えられます。
スピンオフ元の会社が上場会社等の場合の有価証券届出書や目論見書の作成の要否については、以下のとおりとなります。
① 分割型分割の場合
金融商品取引法では、上場会社等が一定の組織再編を行う場合について、有価証券の募集に当たるとして、有価証券届出書の提出を求めており、分割型分割のスピンオフについては、原則、スピンオフされた会社が有価証券届出書の提出を行うことが必要となります(この場合の目論見書の作成は不要です(金融商品取引法第4条第1項、第13条第1項))。なお、届出書提出日においてスピンオフされた会社が設立されていないため、実務的には、スピンオフ元の会社が提出することが考えられます。
② 株式分配の場合
金銭分配請求権がない株式分配は、スピンオフされた会社の株式の交付が有価証券の募集や売出しに該当しないため、有価証券届出書の提出や目論見書の作成は不要です。
ただし、スピンオフされた会社が上場する時には、スピンオフされた会社が、遅滞なく有価証券報告書を提出することが必要となります。なお、上場しない場合であっても、株主が1,000人以上となった場合には、事業年度末までに有価証券報告書を提出することが必要です。
※ 平成30年3月に公表した本手引きに誤りがあったため、①の目論見書に係る記載(下線部)について修正しています(平成30年4月)。
法令に基づく関係省庁の承認が得られないときに組織再編の効力が生じない旨の規定を合併契約書に記載することが行われていますが、これと同様に、新設分割計画において、登記すべき日(会社法第924条参照)までに上場承認が得られないことを条件に新設分割を中止する旨を定めた場合には、株主総会の承認を要せずに新設分割を中止することが可能となります。最高裁判例でも、株主総会の決議の効力の発生を条件に係らしめることについて、「法律の規定、趣旨または条理に反しない限り、原則として許される」(最高裁昭和37年3月8日第1小法廷判決)とされています。
可能です。なお、スピンオフされる子会社が外国会社である場合には、東京証券取引所に外国株として上場する、または外国の証券取引所に上場するということも考えられます。
1933年米国証券法では、非米国企業が合併などのM&A取引に伴い米国株主に証券を発行する場合には、FormF-4と呼ばれる様式による登録届出書を米国証券取引委員会(SEC)に提出することが要求されており、規則802では、①対象会社の米国株主の保有比率が10%以下であること、②米国株主に平等な取扱いがなされること、③一定の情報開示(FormCBやFormF-Xの提出など)がなされること、という要件を満たしている場合には、このFormF-4の提出義務が適用除外されることとされています。
スピンオフの場合の上記提出義務の適用については、子会社のスピンオフの場合を念頭に米国証券取引委員会の職員が見解を出しており(StaffLegalBulletinNo.4,1997年9月16日)、これによると、以下の5条件を満たす場合には、提出が不要であるという見解となっています。(仮訳)
① 親会社の株主がスピンオフされた会社の株式に対して対価を支払わないこと
② 親会社の株主に按分交付されるスピンオフであること
③ 親会社が株主と証券市場に対してスピンオフと子会社についての適切な情報を提供すること
④ 親会社がスピンオフについて正当な業務目的を有していること
⑤ 親会社が制限付証券をスピンオフする場合には、親会社はこれらの証券を最低2年間保有していること
通常は、分割型分割や株式分配に関する会社法に基づく手続や関係法令に基づく手続と、独立する会社の上場審査の手続を並行して実施することが想定されます。想定されるスケジュールの例は21~22ページをご覧ください(編注:省略)。
取得価額の計算式における分母(元会社の簿価純資産価額。Q30参照)は税務上の簿価を基礎として計算するため、通常は、法人税の申告をした後で、スピンオフを行うことになると考えられます(仮に決算期末から法人税の申告までの間にスピンオフを行おうとする場合には、法人税の申告に先立って純資産額を確定させておくことが必要となります)。
会社法上は、剰余金の配当としてスピンオフされた会社の株式の交付がなされますが、一般に、配当の権利を受ける株主に関する基準日については、会社が一定の日を定めることができることとされています(会社法第124条)。
上場会社のスピンオフによる剰余金の配当については、分割型分割と株式分配のいずれの場合も、スピンオフの効力発生日の前日を基準日とすると、この場合、効力発生日の前日(権利確定日)の振替口座簿に登録されている株主が、スピンオフされた法人の株式の割り当てを受けることができます。振替口座簿への登録には時間がかかりますので、株式分割に係る「権利落ち」の場合と同様に、割り当てを受ける権利を取得するためには、権利確定日の3営業日前(権利付最終日)までに、スピンオフを行う法人の株式を取得している必要があります。
スピンオフを行うことにより、株主には新たにスピンオフされた会社の株式を割り当てることになるため、株主や証券会社に対する通知が必要です。
株主への通知については、会社法上は、新設分割によるスピンオフをしようとする株式会社は、新設分割をする旨などについて、株主総会から2週間以内に株主に対して通知や公告をする必要があります(会社法第806条第3項、第4項)。
また、法人税法施行令等において、分割型分割や株式分配を行った場合には、株主に対し、分割等の割合(Q30参照)の値を通知しなければならないこととされています(法人株主については法人税法施行令第119条の8第2項、第119条の8の2第2項参照。個人株主については所得税法施行令参照)。加えて、租税特別措置法施行令において、その分割型分割や株式分配を行う法人の株式が特定口座で保管されている場合には、その法人は、その特定口座が開設されている証券会社に対し、その株式の取得価額及びその分割型分割や株式分配により取得した株式の取得価額の計算に必要な情報(分割割合等)を通知しなければならないこととされています(租税特別措置法施行令第25条の10の2第26項)。
上記の証券会社への通知については、予めスピンオフを行う上場会社が所定の情報を保振のウェブサイト(「Target保振サイト」)に掲載することで、証券会社に自動で情報が通知される仕組みが構築されています。スピンオフを行う上場会社は、これを利用して、分割割合等の内容について速やかに通知を行ってください(変更・修正があった場合の変更・修正も含め、効力発生日の2週間前までに行う必要があります)。詳しくは、日本証券業協会と全国株懇連合会により定められている「会社が株主に交付する金銭等に係る情報提供に関する事務取扱要領」(平成29年8月25日公表)をご参照ください。
なお、上記通知の期日を考慮して、分割契約において合意された対価に見合うよう、日々変動する営業債権・債務などの承継対象範囲を調整する等、実務上の工夫を行うことが考えられます。
スピンオフを行う株式会社の上場株式を特定口座やNISA口座に保管している場合、スピンオフによって新たに独立して上場する株式会社の株式もその特定口座やNISA口座において保管されることになります。
(上場)
会社法や税法において、スピンオフをした場合の上場は必須ではありません。ただし、上場会社がスピンオフを行おうとする場合、スピンオフされた会社が非上場であると、株式の流動性が乏しくなるため、株主の株式売却の機会を確保するために、通常は上場を前提とするものが多くなると考えられます。
証券取引所による上場審査を受け、上場承認を受けることができれば可能です。
なお、上場の準備に当たっては、あらかじめ余裕を持って証券会社、監査法人、証券取引所等とご相談ください。
株式市場において、投資家の需要状況に基づき、形成されることが原則だと考えられますが、スピンオフされた会社の上場後の価格形成については、証券取引所にご相談ください。
東証の上場規則では、通常の新規上場申請と同様の手続が必要となりますが、スピンオフの効力発生日と同日の上場を目指す場合など早期上場のため、新設分割によって設立される会社の上場申請について以下の特例が設けられています。
① 元の会社(分割会社)が上場会社であれば、新設会社の設立前であっても、会社分割に係る株主総会の決議後に限り、当該元の会社が申請者となって上場申請をすることが可能であり(有価証券上場規程第201条第2項)、また、それ以前であっても、予備申請を行い、実質的に審査を進めることが可能です。
② 市場第一部及び第二部の上場審査基準では、「3年前より前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること」(事業継続年数要件)とされていますが(有価証券上場規程第205条第1項第4号)、分割型分割の場合については、新設会社の設立前の元の会社での事業年数を加算して事業継続年数を算出することができるものとされています(有価証券上場規程施行規則第212条第4項第3号)。
③ 新設会社の設立前の期間に係る財務書類については、「部門財務情報の作成基準」に基づきプロフォルマを準備のうえ、「会社分割により承継される事業に係る財務計算に関する書類に対する意見表明に係る基準」に基づき監査意見を得ることで対応可能とされています(有価証券上場規程施行規則別添4)。
テクニカル上場制度は、経済的な実態が変わらないものの、法人格が変わってしまう場合を念頭に、上場契約の承継を認めて継続上場を図る制度です。したがって、上場会社がスピンオフした会社に主要な事業を承継し上場契約を承継させる(上場会社は上場廃止となる)場合にのみ利用可能です。
会社法上は、新株発行のための手続が必要となります(注)。また、金融商品取引法上は、公募を行う際の開示規制が適用されます。
(注)加えて、スピンオフをする会社の株主総会の決議に際しては、新株発行に関する事項を株主に対して開示することが望ましいものと考えられます。
株式分配によるスピンオフの場合には、これら必要な手続を行えば、スピンオフされた会社の上場とともに新株の発行を行うことができると考えられます。
他方、分割型分割の場合、事前に会社が存在していないため、取締役会決議など新株発行に必要な手続を行うことが困難と考えられます。
なお、税制上は、「他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと」や「スピンオフ元の会社がすべての株式を分配すること」が適格株式分配の要件となっています。
有価証券届出書の提出に際し、過去2年間分(公認会計士又は監査法人の監査が必要)の財務諸表が求められています(Q15③に記載の上場審査において必要とされる財務諸表については提出が必要です)。
なお、海外の開示規制に基づき、監査済の財務諸表の必要性についてもご確認ください。
(税務)
分割型分割により行う場合、株式分配により行う場合、それぞれの主な要件は以下の通りです。
① 適格分割型分割(※法人税法第2条第12号の11ニ、法人税法施行令第4条の3第9項)※単独新設分割であることが必要。
非支配要件……分割法人が分割の直前に他の者による支配関係がない法人であり、かつ、分割承継法人が分割後に他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと
株式のみ按分交付要件……分割により分割法人が交付を受ける分割承継法人の株式の全てが分割法人の株主に交付されるもので、分割法人の株主の持株数に応じて分割承継法人の株式のみが交付されること
主要資産等移転要件……分割事業に係る主要な資産・負債が分割承継法人に移転すること
従業者引継要件……分割事業に係る80%以上の従業者が分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれること
事業継続要件……分割事業が分割承継法人において分割後も引き続き行われることが見込まれること
役員引継要件……役員又は分割事業に従事している重要な使用人のいずれかが分割承継法人の特定役員となることが見込まれること
② 適格株式分配(※法人税法第2条第12号の15の3、法人税法施行令第4条の3第16項)
非支配要件……現物分配法人が分配の直前に他の者による支配関係がない法人であり、かつ完全子法人が株式分配後に他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと
株式のみ按分交付要件……完全子法人株式の全てが移転するもので、分配法人の株主の持株数に応じて完全子法人の株式のみが交付されること
従業者継続要件……80%以上の従業者が完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれること
事業継続要件……完全子法人の主要な事業が完全子法人において、株式分配後も引き続き行われることが見込まれること
役員継続要件……特定役員の全てが株式分配に伴い退任するものでないこと
単独新設分社型分割の適格要件の一つに完全支配関係の継続の見込みがあります。この要件について、単独新設分社型分割後に適格株式分配を行うことが見込まれる場合には当該単独新設分社型分割の時から当該適格株式分配の直前の時まで完全支配関係の継続が見込まれればよいこととされています(法人税法施行令第4条の3第6項第1号ハ)。これは、単独新設分社型分割に代えて単独新設現物出資により完全子会社を設立した場合も同様の取扱いとなります(法人税法施行令第4条の3第13項第1号ロ)。
また、完全支配関係のある法人との間で分社型吸収分割等を行った後に適格株式分配を行うことが見込まれる場合にも、当該分社型分割等の時から当該適格株式分配の直前の時まで完全支配関係の継続が見込まれればよいこととされています(法人税法施行令第4条の3第6項第1号イ等)。
このため、特定の事業をスピンオフする場合において、まず事業部門を分社型分割あるいは現物出資することで完全子会社を設立し、又は完全支配関係にある法人同士の事業を統合した上で、一定期間経過後に株式分配を行うことも可能です。
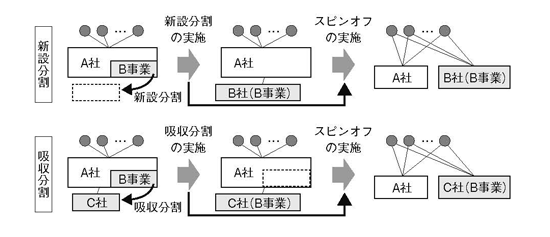
合併、吸収分割等の組織再編(完全支配関係内の組織再編を除きます。)が適格組織再編になるためには、従業者引継要件及び事業継続要件の充足が組織再編時に見込まれることが必要です。そのため、独立する会社に自社内の部門と他の完全子会社を統合するため、合併等の組織再編を行う場合、その時点で将来のスピンオフが予定されていると、これらの要件を満たさず非適格となると考えられます。
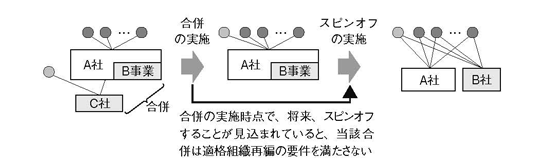
税制上、既存株主の継続保有は適格組織再編の要件とされていません。
他の者による支配関係がない法人が行うスピンオフが今回の税制改正の対象です。
50%超100%未満の株式を保有する株主が存在する法人等、他の者による支配関係がある法人では、改正前と同様、分割型分割ではグループ内再編として課税繰延べの対象となる場合がありますが、株式分配では課税繰延べの対象となりません。
スピンオフされた法人が、スピンオフ後、他の法人の支配を受けることになったとしても、スピンオフの時点で他の法人に支配されることが見込まれていなければ、組織再編税制の適格要件の判定には影響を及ぼしません。
スピンオフではスピンオフした会社(分割法人又は現物分配法人)の株主の所有する株式数に応じてスピンオフされた会社(分割承継法人又は完全子法人)の株式のみが交付されることが必要です。このため、一部の株主のみにスピンオフされた会社の株式を交付する場合や、株式に代えて金銭を交付する場合についてはこの要件を満たしません(法人税法第2条第12号の11、第12号の15の3)。
なお、交付する株数に端数が生ずる場合に、その端数に相当する金銭を交付することは認められています(法人税法施行令第139条の3の2第2項、第3項)。
ストックオプションは効力発生日までに行使されない限り、完全子会社であるかどうかの判定において保有株式として考慮されません。
税制の適格要件としては、完全子会社が複数の種類の株式を発行している場合、ある種類の株式は交付しなくていいといった考慮はなされていません。このため、適格要件を満たすためには、完全子会社が発行しているすべての種類の株式をスピンオフした会社(分割法人又は現物分配法人)の株主に按分交付する必要があります。
分割型分割では、役員又は分割事業に係る業務に従事している重要な使用人の1名以上が分割承継法人の特定役員となることが見込まれること(法人税法施行令第4条の3第9項第2号)が要件です。
また、株式分配では、特定役員の全てが株式分配に伴い退任するものでないこと、言い換えると、株式分配後も1名以上が特定役員であることが見込まれること(法人税法施行令第4条の3第16項第2号)が要件です。特定役員全員が残ることは要件とされていません。
なお、特定役員が株式分配に伴い全て退任し、新経営陣が新たに特定役員として選任され、従前の特定役員は本部長等の役職(法人の経営に従事していない)で従業員として在籍するとしても、特定役員でないため、この要件を満たさないことになります。
※ 特定役員とは、社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者(法人税法施行令第4条の3第4項第2号)。
一部の株式を持ち続けるケースなど、適格要件をさないスキームとしては、35~36ページ(編注:下記(参考)を参照)のようなものがあります。
(参考)適格要件を満たさないスピンオフのスキームの例
例1:一部の株式を持ち続けるケース B社株式の全部を分配することが求められるため、右図の場合は適格とならない。
※ A社がB社株を株主に分配せず、他者に売却した場合も、この例と同様に適格とならない。
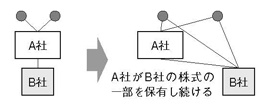
例2:完全支配関係にない子会社のスピンオフ 100%所有関係がある子会社株式(B社株式)の全部を分配することが求められるため、右図の場合は適格とならない。
※ スピンオフに先立って、A社はB社株式の全部を保有している必要がある。
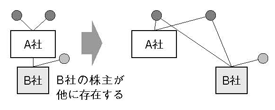
例3:子会社株式を非按分で分配するスピンオフ 株式の持株数に応じた株式の分配が求められるため、右図の場合は適格とならない。
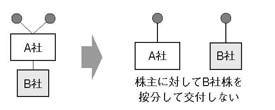
(備考)上記はいずれも株式分配によるスピンオフのケースであるが、分割型分割によるスピンオフの場合も同様。
例4:スピンオフされた会社の買収が見込まれているケース スピンオフ実施後、B社が継続して他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないことが求められるため、下図の場合は適格とならない。
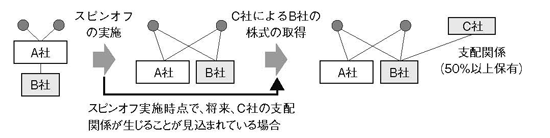
※ スピンオフ実施後においてB社の新株発行等による株式取得を第三者が行うことをスピンオフ実施時に計画していることも想定し得る。この場合、当該株式取得の結果としてB社に支配株主が生じない限り、上記のスピンオフの実施の場面において、「他の者による支配関係」に係る要件に反することにはならない。
※ なお、A社が、スピンオフを行った後で、B社が他の法人の支配を受けることになったとしても、スピンオフの時点で他の法人に支配されることが見込まれていなければ、組織再編税制の適格要件の判定には影響を及ぼさない。
スピンオフの際の分割法人又は現物分配法人の株主における分割法人又は現物分配法人の株式の譲渡については、株式のみ按分交付要件を満たしていれば、譲渡損益を計上せずに帳簿価額を付け替えることとされており(法人税法第61条の2第4項、第8項)、その付け替える金額は、分割型分割の場合、株式分配の場合、それぞれについて、以下の計算式で計算することとされています(法人税法施行令第119条の3第12項、第14項、第119条の4第1項)。
分割法人株式の帳簿価額=(B)-(A)
現物分配法人株式の帳簿価額=(B)-(A)
剰余金の分配可能額の範囲内であれば、スピンオフしようとする完全子会社の資本金を減少して生み出した資本剰余金を原資として株式分配を行うことが可能です。
税務上は、適格株式分配の場合には、現物分配法人の適格株式分配の直前のその適格株式分配によりその株主等に交付した完全子法人株式の帳簿価額に相当する金額を、資本金等の額から減算し、利益積立金額は減算しないこととされており、分配原資の違いにより税務上の取扱に変わりありません(法人税法施行令第8条第1項第16号、第9条第1項第8号)。
以下の場合を除き、居住者の株主と同様の取扱いとなります。
① 事業譲渡類似の株式に該当する場合
譲渡益に対して課税されます(所得税法施行令第281条第1項第4号ロ、第7項第2号)。
② 内国法人である株式分配法人の外国子法人株式のみが非居住者の株主の持株数に応じて交付される場合
譲渡益(国内源泉所得に該当するものに限る)に対して課税されます(租税特別措置法第37条の14の3第3項、第8項)。ただし、恒久的施設においてスピンオフを行う法人の株式を管理する場合は対象外です(租税特別措置法第37条の14の3第5項)。
※ 株主である非居住者が居住する国によっては、租税条約により取扱いが異なる場合があります。
(会計)
【単独新設分割型分割の場合】
単独新設分割型分割は、①会社分割(分社型分割)と、②これにより受け取った新設分割設立会社の株式の分配、という2つの取引と考えられます。
① 会社分割(分社型分割)の会計処理
分割会社が会社分割により取得する新設分割設立会社株式の取得原価は、移転事業に係る株主資本相当額に基づいて算定するため、当該会社分割により移転損益は生じません。
② 株式の分配の会計処理
分割会社は、受け取った新設分割設立会社の株式の取得原価により株主資本を変動させます。なお、変動させる株主資本の内訳は、取締役会等の会社の意思決定機関において定められた額となります。
(事業分離等に関する会計基準第63項
企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第263項、第233項、第226項
自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針第10項)
【完全子会社の株式分配の場合】 配当の効力発生日における配当財産の適正な帳簿価額をもって、その他資本剰余金又はその他利益剰余金(繰越利益剰余金)を減額させます。
(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針第10項)
【単独新設分割型分割の場合】
受け取る新設分割設立会社の株式と、これまで保有していた分割会社の株式とが実質的に引き換えられたものとみなして会計処理します。
投資が継続しているとみなされる場合には交換損益を認識せず、新設分割設立会社の株式の取得原価は、分割直前の分割会社株式の適正な帳簿価額のうち、合理的に按分する方法によって算定した引き換えられたものとみなされる部分の価額とします。合理的に按分する方法には、(1)関連する時価の比率で按分する方法、(2)時価総額の比率で按分する方法、(3)関連する帳簿価額の比率で按分する方法、が考えられます。
例えば(3)の方法では、分割された移転事業に係る株主資本相当額の適正な帳簿価額と分割直前の分割会社の株主資本の適正な帳簿価額との比率により、分割会社株式の適正な帳簿価額を按分することとなります。
(事業分離等に関する会計基準第49項、第50項、第141項
企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第294項、第295項)
【完全子会社の株式分配の場合】 交換等の一般的な会計処理の考え方に準じて、これまで保有していた株式が実質的に引き換えられたものとみなして会計処理します。
投資が継続しているとみなされる場合には交換損益を認識せず、スピンオフ元会社の完全子会社の株式の取得原価は、分配を受ける直前のスピンオフ元会社株式の適正な帳簿価額のうち、合理的に按分する方法によって算定した引き換えられたものとみなされる部分の価額とします。合理的に按分する方法には、【単独新設分割型分割の場合】と同様の方法が考えられます。
(事業分離等に関する会計基準第52項、第143項
企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第297項)
【単独新設分割型分割の場合】
単独新設分割会社が分割会社から受け入れる資産及び負債は、分割期日の前日に付された分割会社における適正な帳簿価額により計上します。
増加すべき株主資本については、移転事業に係る評価・換算差額等を引き継ぐとともに、移転事業に係る株主資本相当額は払込資本(資本金又は資本剰余金)として計上します。増加すべき払込資本の内訳項目(資本金、資本準備金又はその他資本剰余金)は会社法の規定に基づき決定します。
ただし、受け入れた資産及び負債の対価として新設分割設立会社の株式のみを交付している場合には、分割会社で計上されていた株主資本の内訳を適切に配分した額をもって計上することができ、この場合、株主資本の内訳の配分額は分割会社が減少させた株主資本の内訳の額と一致させます。
(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第264項、第234項)
【完全子会社の株式分配の場合】 完全子会社であった会社の株主に変更が生じるのみで、当該会社における会計処理は不要です。
スピンオフに関するQ&A(経済産業省)
(編注:経済産業省『「スピンオフ」の活用に関する手引』から抜粋)
(一般)
| Q1.どのような行為が税法上の「スピンオフ」に該当するのでしょうか。 |
① 分割型分割……自社内の特定の事業部門を分割により別法人に移転させ、同時に設立時に交付を受けるその法人の株式の全てを自社の株主に交付する方法(※適格組織再編に該当するためには単独新設分割であることが必要)
② 株式分配……自社の完全子法人の発行済株式の全部を自社の株主に全て分配する方法(※外国法人である完全子法人の場合も想定されます)
※ 上記のほか、①と②の中間形態として、「新設分社型分割又は新設現物出資+(一定期間経過後の)株式分配」という方式によるスピンオフも考えられます。
※ 以降のQ&Aでは、税法上のスピンオフに該当する分割型分割と株式分配を指して、「スピンオフ」と呼んでいます。
| Q2.スピンオフを行う場合、会社法等との関係でどのような手続が必要ですか。 |
会社法に基づき、株主総会決議など、会社分割及び剰余金の配当の手続を行うことが必要です。特に、適格組織再編に該当するスピンオフは、「株式のみ按分交付要件」を満たすために、金銭分配請求権のない現物配当であり、剰余金の配当に係る株主総会特別決議が必要となります(会社法第309条第2項第10号)。また、分配可能額規制など、剰余金配当に係る規制の一部は適用されない(会社法第812条)、債権者保護手続(会社法第810条)が必要となる、スピンオフしようとする会社の株主に株式買取請求権が認められる(会社法第806条)といった特徴があります。ただし、簡易新設分割に該当する場合には、新設分割計画の承認の株主総会決議は不要で(会社法第805条)、新設分割会社の株主には新設分割の差止請求権はなく(会社法第805条の2ただし書)反対株主の買取請求権は認められません(会社法第806条第1項第2号)。
なお、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律に基づく手続、許認可等に関する手続等、関係法令に基づく手続を行うことも必要です。
② 株式分配の場合
会社法に基づき、株主総会決議など、剰余金の配当の手続を行うことが必要です。特に、金銭分配請求権のない現物配当については、剰余金の配当に係る株主総会特別決議が必要となります(会社法第309条第2項第10号)。また、株式分配を行うに足りる分配可能額があることを確認することが必要(※)、債権者保護手続が不要、スピンオフしようとする会社の株主の株式買取請求権は認められていないといった特徴があります。
なお、許認可等に関する手続等、関係法令に基づく手続が必要となる場合があります。
(※)現物配当を行う会社の会計処理について定めている「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会)第10項では、分割型分割、株式分配いずれの場合も、帳簿価額をもって処理することとされており、分配可能額の確認においても、子会社株式の価額は帳簿価額をもって計算することになると考えられます。
| Q3.スピンオフを行う場合、金融商品取引法との関係でどのような手続が必要ですか。 |
① 分割型分割の場合
金融商品取引法では、上場会社等が一定の組織再編を行う場合について、有価証券の募集に当たるとして、有価証券届出書の提出を求めており、分割型分割のスピンオフについては、原則、スピンオフされた会社が有価証券届出書の提出を行うことが必要となります(この場合の目論見書の作成は不要です(金融商品取引法第4条第1項、第13条第1項))。なお、届出書提出日においてスピンオフされた会社が設立されていないため、実務的には、スピンオフ元の会社が提出することが考えられます。
② 株式分配の場合
金銭分配請求権がない株式分配は、スピンオフされた会社の株式の交付が有価証券の募集や売出しに該当しないため、有価証券届出書の提出や目論見書の作成は不要です。
ただし、スピンオフされた会社が上場する時には、スピンオフされた会社が、遅滞なく有価証券報告書を提出することが必要となります。なお、上場しない場合であっても、株主が1,000人以上となった場合には、事業年度末までに有価証券報告書を提出することが必要です。
※ 平成30年3月に公表した本手引きに誤りがあったため、①の目論見書に係る記載(下線部)について修正しています(平成30年4月)。
| Q4.上場承認が得られることを条件として、会社分割等に関する株主総会決議を行うことはできますか。 |
| Q5.外国会社である完全子会社をスピンオフすることはできますか。 |
| Q6.米国証券法の開示義務(F-4提出義務)については、どのようなルールとなっていますか。 |
スピンオフの場合の上記提出義務の適用については、子会社のスピンオフの場合を念頭に米国証券取引委員会の職員が見解を出しており(StaffLegalBulletinNo.4,1997年9月16日)、これによると、以下の5条件を満たす場合には、提出が不要であるという見解となっています。(仮訳)
① 親会社の株主がスピンオフされた会社の株式に対して対価を支払わないこと
② 親会社の株主に按分交付されるスピンオフであること
③ 親会社が株主と証券市場に対してスピンオフと子会社についての適切な情報を提供すること
④ 親会社がスピンオフについて正当な業務目的を有していること
⑤ 親会社が制限付証券をスピンオフする場合には、親会社はこれらの証券を最低2年間保有していること
| Q7.スピンオフの一般的なスケジュールはどのようになりますか。 |
| Q8.取得価額の計算との関係で、スピンオフの実施日についての実務上の制約はありますか。 |
| Q9.スピンオフされた会社の株式の交付を受けることができるのは、いつの時点の株主ですか。 |
上場会社のスピンオフによる剰余金の配当については、分割型分割と株式分配のいずれの場合も、スピンオフの効力発生日の前日を基準日とすると、この場合、効力発生日の前日(権利確定日)の振替口座簿に登録されている株主が、スピンオフされた法人の株式の割り当てを受けることができます。振替口座簿への登録には時間がかかりますので、株式分割に係る「権利落ち」の場合と同様に、割り当てを受ける権利を取得するためには、権利確定日の3営業日前(権利付最終日)までに、スピンオフを行う法人の株式を取得している必要があります。
| Q10.スピンオフを行おうとする際に、株主や証券会社への通知を行う必要はありますか。 |
株主への通知については、会社法上は、新設分割によるスピンオフをしようとする株式会社は、新設分割をする旨などについて、株主総会から2週間以内に株主に対して通知や公告をする必要があります(会社法第806条第3項、第4項)。
また、法人税法施行令等において、分割型分割や株式分配を行った場合には、株主に対し、分割等の割合(Q30参照)の値を通知しなければならないこととされています(法人株主については法人税法施行令第119条の8第2項、第119条の8の2第2項参照。個人株主については所得税法施行令参照)。加えて、租税特別措置法施行令において、その分割型分割や株式分配を行う法人の株式が特定口座で保管されている場合には、その法人は、その特定口座が開設されている証券会社に対し、その株式の取得価額及びその分割型分割や株式分配により取得した株式の取得価額の計算に必要な情報(分割割合等)を通知しなければならないこととされています(租税特別措置法施行令第25条の10の2第26項)。
上記の証券会社への通知については、予めスピンオフを行う上場会社が所定の情報を保振のウェブサイト(「Target保振サイト」)に掲載することで、証券会社に自動で情報が通知される仕組みが構築されています。スピンオフを行う上場会社は、これを利用して、分割割合等の内容について速やかに通知を行ってください(変更・修正があった場合の変更・修正も含め、効力発生日の2週間前までに行う必要があります)。詳しくは、日本証券業協会と全国株懇連合会により定められている「会社が株主に交付する金銭等に係る情報提供に関する事務取扱要領」(平成29年8月25日公表)をご参照ください。
なお、上記通知の期日を考慮して、分割契約において合意された対価に見合うよう、日々変動する営業債権・債務などの承継対象範囲を調整する等、実務上の工夫を行うことが考えられます。
| Q11.上場会社のスピンオフにおいて、特定口座やNISA口座にその上場会社の株式を保管している場合、独立して上場する株式会社の株式はどのように取り扱われますか。 |
(上場)
| Q12.スピンオフを行う際には、スピンオフされた会社の上場が必須ですか。 |
| Q13.スピンオフ実施日に独立する会社が上場することはできますか。 |
なお、上場の準備に当たっては、あらかじめ余裕を持って証券会社、監査法人、証券取引所等とご相談ください。
| Q14.スピンオフされた会社の上場後の最初の株価はどのように形成されますか。 |
| Q15.スピンオフした会社を上場しようとする際には、どのような手続となりますか。 |
① 元の会社(分割会社)が上場会社であれば、新設会社の設立前であっても、会社分割に係る株主総会の決議後に限り、当該元の会社が申請者となって上場申請をすることが可能であり(有価証券上場規程第201条第2項)、また、それ以前であっても、予備申請を行い、実質的に審査を進めることが可能です。
② 市場第一部及び第二部の上場審査基準では、「3年前より前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること」(事業継続年数要件)とされていますが(有価証券上場規程第205条第1項第4号)、分割型分割の場合については、新設会社の設立前の元の会社での事業年数を加算して事業継続年数を算出することができるものとされています(有価証券上場規程施行規則第212条第4項第3号)。
③ 新設会社の設立前の期間に係る財務書類については、「部門財務情報の作成基準」に基づきプロフォルマを準備のうえ、「会社分割により承継される事業に係る財務計算に関する書類に対する意見表明に係る基準」に基づき監査意見を得ることで対応可能とされています(有価証券上場規程施行規則別添4)。
| Q16.スピンオフした会社はテクニカル上場として新規上場することはできないのでしょうか。 |
| Q17.株式分配によるスピンオフと同日に、スピンオフされた会社を上場するとともに、新株の発行により資金調達を行うことはできますか。 |
(注)加えて、スピンオフをする会社の株主総会の決議に際しては、新株発行に関する事項を株主に対して開示することが望ましいものと考えられます。
株式分配によるスピンオフの場合には、これら必要な手続を行えば、スピンオフされた会社の上場とともに新株の発行を行うことができると考えられます。
他方、分割型分割の場合、事前に会社が存在していないため、取締役会決議など新株発行に必要な手続を行うことが困難と考えられます。
なお、税制上は、「他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと」や「スピンオフ元の会社がすべての株式を分配すること」が適格株式分配の要件となっています。
| Q18.株式分配によるスピンオフと併せて新株発行をする際に、スピンオフされる会社の監査済み財務諸表はどこまで必要でしょうか。 |
なお、海外の開示規制に基づき、監査済の財務諸表の必要性についてもご確認ください。
(税務)
| Q19.スピンオフが適格組織再編に該当するための要件はどのようなものですか。 |
① 適格分割型分割(※法人税法第2条第12号の11ニ、法人税法施行令第4条の3第9項)※単独新設分割であることが必要。
非支配要件……分割法人が分割の直前に他の者による支配関係がない法人であり、かつ、分割承継法人が分割後に他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと
株式のみ按分交付要件……分割により分割法人が交付を受ける分割承継法人の株式の全てが分割法人の株主に交付されるもので、分割法人の株主の持株数に応じて分割承継法人の株式のみが交付されること
主要資産等移転要件……分割事業に係る主要な資産・負債が分割承継法人に移転すること
従業者引継要件……分割事業に係る80%以上の従業者が分割後に分割承継法人の業務に従事することが見込まれること
事業継続要件……分割事業が分割承継法人において分割後も引き続き行われることが見込まれること
役員引継要件……役員又は分割事業に従事している重要な使用人のいずれかが分割承継法人の特定役員となることが見込まれること
② 適格株式分配(※法人税法第2条第12号の15の3、法人税法施行令第4条の3第16項)
非支配要件……現物分配法人が分配の直前に他の者による支配関係がない法人であり、かつ完全子法人が株式分配後に他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと
株式のみ按分交付要件……完全子法人株式の全てが移転するもので、分配法人の株主の持株数に応じて完全子法人の株式のみが交付されること
従業者継続要件……80%以上の従業者が完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれること
事業継続要件……完全子法人の主要な事業が完全子法人において、株式分配後も引き続き行われることが見込まれること
役員継続要件……特定役員の全てが株式分配に伴い退任するものでないこと
| Q20.特定の事業をスピンオフする場合、上場会社としての体制を整えるなどのため、まず単独新設分社型分割により完全子会社を設立し、一定期間経過後に適格株式分配を行った場合の単独新設分社型分割は適格組織再編に該当しますか。 |
また、完全支配関係のある法人との間で分社型吸収分割等を行った後に適格株式分配を行うことが見込まれる場合にも、当該分社型分割等の時から当該適格株式分配の直前の時まで完全支配関係の継続が見込まれればよいこととされています(法人税法施行令第4条の3第6項第1号イ等)。
このため、特定の事業をスピンオフする場合において、まず事業部門を分社型分割あるいは現物出資することで完全子会社を設立し、又は完全支配関係にある法人同士の事業を統合した上で、一定期間経過後に株式分配を行うことも可能です。
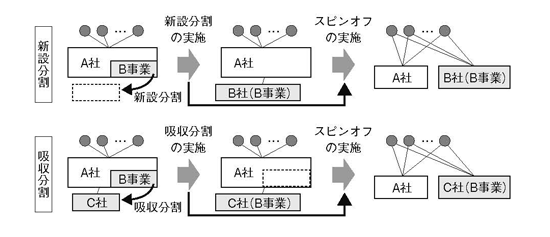
| Q21.スピンオフを行う前に、独立する会社に自社内の部門や他の完全子会社を統合するための組織再編(合併等)を行った場合、その組織再編は適格組織再編となりますか。 |
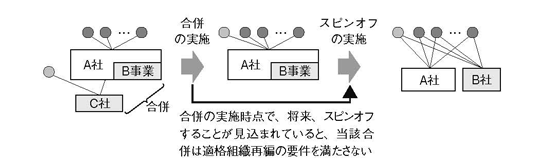
| Q22.スピンオフ実施後、既存株主(分割法人又は現物分配法人の株主)がスピンオフされた会社(分割承継法人又は完全子法人)の株式を継続的に保有することが必要ですか。 |
| Q23.発行済株式の50%超100%未満の株式を保有する株主が存在する法人がスピンオフを行う場合も適格組織再編に該当しますか。 |
50%超100%未満の株式を保有する株主が存在する法人等、他の者による支配関係がある法人では、改正前と同様、分割型分割ではグループ内再編として課税繰延べの対象となる場合がありますが、株式分配では課税繰延べの対象となりません。
| Q24.スピンオフされた法人が、スピンオフ実施後に他法人に買収された場合、税制上の扱いに影響が生じますか。 |
| Q25.対価に関する「株式のみ按分交付要件」を満たす上での注意点は何ですか。 |
なお、交付する株数に端数が生ずる場合に、その端数に相当する金銭を交付することは認められています(法人税法施行令第139条の3の2第2項、第3項)。
| Q26.株式分配でスピンオフしようとする際における、完全子会社であるかどうかの判定では、第三者(完全子会社の従業員など)が保有しているストックオプションも考慮されますか。 |
| Q27.適格要件を満たすためには、完全子会社が発行している種類株についても、「株式のみ按分交付要件」を満たす必要がありますか。 |
| Q28.役員引継要件(役員継続要件)とはどのような要件ですか。 |
また、株式分配では、特定役員の全てが株式分配に伴い退任するものでないこと、言い換えると、株式分配後も1名以上が特定役員であることが見込まれること(法人税法施行令第4条の3第16項第2号)が要件です。特定役員全員が残ることは要件とされていません。
なお、特定役員が株式分配に伴い全て退任し、新経営陣が新たに特定役員として選任され、従前の特定役員は本部長等の役職(法人の経営に従事していない)で従業員として在籍するとしても、特定役員でないため、この要件を満たさないことになります。
※ 特定役員とは、社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者(法人税法施行令第4条の3第4項第2号)。
| Q29.スピンオフされた会社の株式を、スピンオフした会社が一部保有しつづけると適格要件を満たさないと聞きました。どのような場合に適格要件を満たさないか、教えてください。 |
(参考)適格要件を満たさないスピンオフのスキームの例
例1:一部の株式を持ち続けるケース B社株式の全部を分配することが求められるため、右図の場合は適格とならない。
※ A社がB社株を株主に分配せず、他者に売却した場合も、この例と同様に適格とならない。
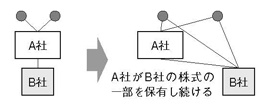
例2:完全支配関係にない子会社のスピンオフ 100%所有関係がある子会社株式(B社株式)の全部を分配することが求められるため、右図の場合は適格とならない。
※ スピンオフに先立って、A社はB社株式の全部を保有している必要がある。
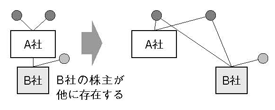
例3:子会社株式を非按分で分配するスピンオフ 株式の持株数に応じた株式の分配が求められるため、右図の場合は適格とならない。
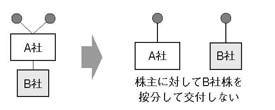
(備考)上記はいずれも株式分配によるスピンオフのケースであるが、分割型分割によるスピンオフの場合も同様。
例4:スピンオフされた会社の買収が見込まれているケース スピンオフ実施後、B社が継続して他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないことが求められるため、下図の場合は適格とならない。
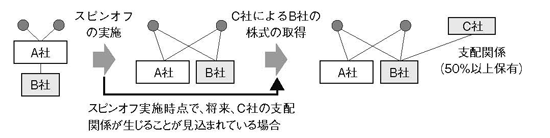
※ スピンオフ実施後においてB社の新株発行等による株式取得を第三者が行うことをスピンオフ実施時に計画していることも想定し得る。この場合、当該株式取得の結果としてB社に支配株主が生じない限り、上記のスピンオフの実施の場面において、「他の者による支配関係」に係る要件に反することにはならない。
※ なお、A社が、スピンオフを行った後で、B社が他の法人の支配を受けることになったとしても、スピンオフの時点で他の法人に支配されることが見込まれていなければ、組織再編税制の適格要件の判定には影響を及ぼさない。
| Q30.スピンオフの際の分割法人又は現物分配法人(親法人)の株式の帳簿価額はどう計算しますか。 |
分割承継法人の株式の帳簿価額の計算式(法人税法第61条の2第24項、法人税法施行令第119条第1項第6号)
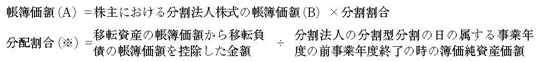 (※)法人税法施行令第23条第1項第2号、同令第119条の8第1項 |
分割法人株式の帳簿価額=(B)-(A)
株式分配に係る完全子法人の株式の帳簿価額の計算式(法人税法第61条の2第24項、法人税法施行令第119条第1項第6号)
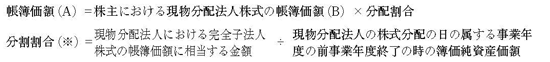 (※)法人税法施行令第23条第1項第3号、同令第119条の8の2第1項 (参考)「現物分配法人」とは、現物分配によりその有する資産の移転を行った法人であり、株式分配によるスピンオフの際のいわゆる「親法人」である。 |
現物分配法人株式の帳簿価額=(B)-(A)
| Q31.適格株式分配の分配原資の違いにより税務上の取扱いはどう変わりますか。 |
税務上は、適格株式分配の場合には、現物分配法人の適格株式分配の直前のその適格株式分配によりその株主等に交付した完全子法人株式の帳簿価額に相当する金額を、資本金等の額から減算し、利益積立金額は減算しないこととされており、分配原資の違いにより税務上の取扱に変わりありません(法人税法施行令第8条第1項第16号、第9条第1項第8号)。
| Q32.スピンオフに際し株主に交付される対価が株式のみである場合、居住者の株主(分割法人又は現物分配法人の株主)における分割法人又は現物分配法人の株式の譲渡は、簿価譲渡となりますが、非居住者の株主について取扱いが異なる点はありますか。 |
① 事業譲渡類似の株式に該当する場合
譲渡益に対して課税されます(所得税法施行令第281条第1項第4号ロ、第7項第2号)。
② 内国法人である株式分配法人の外国子法人株式のみが非居住者の株主の持株数に応じて交付される場合
譲渡益(国内源泉所得に該当するものに限る)に対して課税されます(租税特別措置法第37条の14の3第3項、第8項)。ただし、恒久的施設においてスピンオフを行う法人の株式を管理する場合は対象外です(租税特別措置法第37条の14の3第5項)。
※ 株主である非居住者が居住する国によっては、租税条約により取扱いが異なる場合があります。
(会計)
| Q33.スピンオフ元の会社の会計処理については、どのように行えば良いか。 |
① 会社分割(分社型分割)の会計処理
分割会社が会社分割により取得する新設分割設立会社株式の取得原価は、移転事業に係る株主資本相当額に基づいて算定するため、当該会社分割により移転損益は生じません。
② 株式の分配の会計処理
分割会社は、受け取った新設分割設立会社の株式の取得原価により株主資本を変動させます。なお、変動させる株主資本の内訳は、取締役会等の会社の意思決定機関において定められた額となります。
(事業分離等に関する会計基準第63項
企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第263項、第233項、第226項
自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針第10項)
【完全子会社の株式分配の場合】 配当の効力発生日における配当財産の適正な帳簿価額をもって、その他資本剰余金又はその他利益剰余金(繰越利益剰余金)を減額させます。
(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針第10項)
| Q34.スピンオフ元の会社の法人株主の会計処理については、どのように行えば良いか。 |
投資が継続しているとみなされる場合には交換損益を認識せず、新設分割設立会社の株式の取得原価は、分割直前の分割会社株式の適正な帳簿価額のうち、合理的に按分する方法によって算定した引き換えられたものとみなされる部分の価額とします。合理的に按分する方法には、(1)関連する時価の比率で按分する方法、(2)時価総額の比率で按分する方法、(3)関連する帳簿価額の比率で按分する方法、が考えられます。
例えば(3)の方法では、分割された移転事業に係る株主資本相当額の適正な帳簿価額と分割直前の分割会社の株主資本の適正な帳簿価額との比率により、分割会社株式の適正な帳簿価額を按分することとなります。
(事業分離等に関する会計基準第49項、第50項、第141項
企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第294項、第295項)
【完全子会社の株式分配の場合】 交換等の一般的な会計処理の考え方に準じて、これまで保有していた株式が実質的に引き換えられたものとみなして会計処理します。
投資が継続しているとみなされる場合には交換損益を認識せず、スピンオフ元会社の完全子会社の株式の取得原価は、分配を受ける直前のスピンオフ元会社株式の適正な帳簿価額のうち、合理的に按分する方法によって算定した引き換えられたものとみなされる部分の価額とします。合理的に按分する方法には、【単独新設分割型分割の場合】と同様の方法が考えられます。
(事業分離等に関する会計基準第52項、第143項
企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第297項)
| Q35.スピンオフされた会社の会計処理については、どのように行えば良いか。 |
増加すべき株主資本については、移転事業に係る評価・換算差額等を引き継ぐとともに、移転事業に係る株主資本相当額は払込資本(資本金又は資本剰余金)として計上します。増加すべき払込資本の内訳項目(資本金、資本準備金又はその他資本剰余金)は会社法の規定に基づき決定します。
ただし、受け入れた資産及び負債の対価として新設分割設立会社の株式のみを交付している場合には、分割会社で計上されていた株主資本の内訳を適切に配分した額をもって計上することができ、この場合、株主資本の内訳の配分額は分割会社が減少させた株主資本の内訳の額と一致させます。
(企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針第264項、第234項)
【完全子会社の株式分配の場合】 完全子会社であった会社の株主に変更が生じるのみで、当該会社における会計処理は不要です。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















