解説記事2018年11月05日 【税制改正解説】 贈与税の納税猶予における相続時精算課税のメリットとデメリット(2018年11月5日号・№762)
税制改正解説
贈与税の納税猶予における相続時精算課税のメリットとデメリット
税理士 竹内陽一
公認会計士 長谷川敏也
公認会計士 有田賢臣
Ⅰ 平成29年度改正により相続時精算課税制度との併用が可能に
平成29年度税制改正により、贈与税の納税猶予制度と相続時精算課税制度の併用が可能になった。特例事業承継税制でも同様に併用が可能である(措法70の7②五ロ、70の7の5②八ロ)。
この平成29年度改正では、相続時精算課税制度との併用を禁止していた改正前租税特別措置法70条の7第3項が削除され、調整規定として租税特別措置法70条の7第13項に、9号と10号が設置されるに留まっている。調整規定の内容は、2世代連続贈与においての第1贈与者死亡時と第2贈与者死亡時において、相続税法21条の14から21条の16までの規定(相続時精算課税制度によるみなし相続)は適用しないというシンプルなものであった。
そして贈与税の納税猶予が期限確定した際に、暦年課税制度を選択している場合の贈与税額(下記事例における贈与税の実効税率は約51.5%)に比べて、相続時精算課税制度を選択している場合の相続税額(下記事例における相続税の実効税率は30.6%)が小さくなるので、期限確定の場合は相続時精算課税を贈与税の納税猶予制度と併用したほうが確かに有利である。
【事例】 贈与税の納税猶予が期限確定した場合、特例経営承継受贈者(後継者)に高額な税負担が生じる恐れがあるため、相続時精算課税制度との併用が可能となり、期限確定時の贈与税負担額は(評価額-2,500万円)×20%相当額(利子税別途)のみとされた。
以下の通り、相続時精算課税制度を選択すれば、贈与税の納税猶予制度を適用した場合のリスクが大幅に軽減されることになり(実質的に利子税のみがリスクとなる)、贈与者死亡時の相続税額は、暦年課税制度による贈与税額より少額となる。
① 事業承継税制を適用せずに相続が開始された場合の相続税総額
贈与時と相続時の自社株式の評価額は同額とする。
相続財産=自社株式2億円+預貯金1億円=3億円……
② 贈与税の納税猶予制度を適用し、その後期限確定した場合
贈与税の納税猶予制度を適用していたところ、適用対象株式の全てについて期限が確定した場合、暦年課税制度を選択した場合と相続時精算課税制度を選択した場合の納税額を比較をすると図1の通りである。
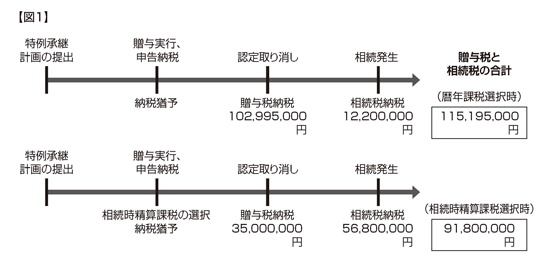
このように、贈与時と相続時の評価額を同額とした場合、事業承継税制を適用しない場合の相続税額91,800,000円と、贈与税の納税猶予制度と相続時精算課税制度を併用し、その後期限が確定した場合の納税額の総額91,800,000円は一致することになり、期限が確定した場合に暦年課税制度により算出された過大な贈与税額を払わなければならないリスクが回避できるようになった。
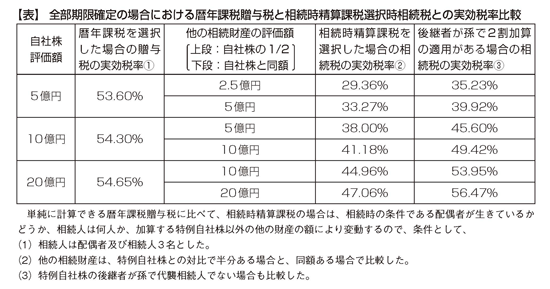
Ⅱ 相続時精算課税制度と贈与税の納税猶予制度の共通点
この両制度は、これらの制度を適用して贈与した財産を贈与者の死亡時に贈与時の時価で相続したものとみなして相続税が計算されるという点で極めて類似している。
なお、贈与税の納税猶予制度は政策税制であるので、贈与後の不幸な事態について救済規定を設けており、相続時精算課税制度にはない次の特徴がある。第一は株価の下落に対応した猶予税額の減免規定であり、第二は受贈者(子)が先代経営者(親)より先に亡くなった場合に猶予税額の全額を免除するという割り切った規定である。
Ⅲ 贈与税の納税猶予制度適用時における相続時精算課税と暦年課税の違い
1 株価の下落に伴う新減免特例 納税猶予適用対象株式を譲渡することにより、納税猶予の期限が確定した際に、業績悪化により株価が下落している場合には、減免措置により譲渡時の株価で納税猶予額が再計算され、当初納税猶予額と再計算納税猶予額の差額は免除となる。
納税猶予の期限が確定した場合、暦年課税制度を選択している場合には、この減免された贈与税額を納付することにより課税関係は確定し、租税特別措置法70条の7の3が適用されること(贈与財産が相続税の課税対象となること)はない。すなわち、租税特別措置法70条の7の3においては、1項本文において、「その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第三項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合及びその死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合を除く。」とされている。
一方、相続時精算課税制度を選択している場合には、上記Ⅰのとおり、相続税法21条の14から21条の16までの適用において、株価の下落に伴う減免規定と同様の規定(贈与時の時価を譲渡時の時価に置き換える調整規定)が平成29年度改正において創設されなかった。
平成29年度税制改正の解説を逆読みすれば、減免規定が適用されるケース(株式の譲渡により納税猶予の期限が確定するケース)においては、事業承継税制のレールから外れて、相続時精算課税制度だけ適用している状態に復帰することになる。
そうすると、贈与者の死亡時には、贈与財産が贈与時の時価で相続財産に加算され、「課せられた贈与税」が控除されるので、免除された贈与税額を含めて控除されることになるようだ(相続税法21条の15③、21条の16④、相基通21の15-3、21の16-1)。
平成30年度税制改正の解説p604によれば(図2を参照)、新減免特例の効果として暦年課税制度を選択した場合の解説がなされており、当初の贈与税額150(300×50%とする)が減免されて、60を納付することにより課税関係は終了することになる(みなし相続課税はない)。
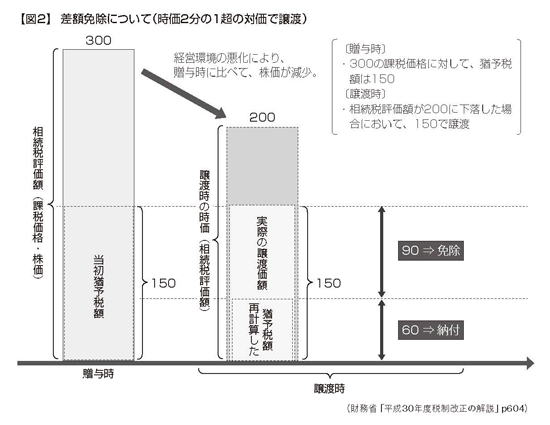
一方、相続時精算課税制度を選択した場合は、贈与税の当初納税猶予額は60(300×20%とする)であり、減免によって再計算猶予税額30(150×20%とする)を納付し、30が減免される。しかし、贈与者の相続時には、300で相続財産に加算されるとともに、控除される贈与税額は、免除された30と期限確定納付の30の合計60が控除されることになる。みなし相続課税を受けるという点で暦年課税を選択した場合よりも不利になるものの、免除された贈与税も含めて相続税から控除できるという点で、新減免の効果は一定程度あることになる。
2 受贈者が贈与者より先に死亡した場合 贈与者より先に受贈者が死亡した場合、納税猶予された贈与税は免除される。
暦年課税制度を選択している場合には、このような不幸な事態に、受贈者の相続人に対して受贈者が保有していた自社株式についての相続税課税が開始されるのみである。贈与者の死亡時には贈与財産(当該自社株式)が相続税の課税対象となることはないので1世代飛ばしの効果がフルに享受できる。
一方、相続時精算課税を選択している場合においては、上記の新減免特例と同様に、調整規定が創設されていないので、受贈者の相続人に対して受贈者が保有していた自社株式についての相続税課税が開始されるが、その後の贈与者の死亡時には、相続税法21条の17(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)が働き、贈与財産(当該自社株式)が相続税の課税対象となる。そして、この相続税計算においては、上記Ⅲ1のとおり、当初に課せられた贈与税の全額が控除できるようだ。
このみなし相続財産に係る相続税は、死亡した受贈者の相続人がその法定相続分割合で負担し、課せられた贈与税を控除した差額を納付することとなるようだ(相続税法21条の17③、国税通則法5条②)。
なお、上記1、2において、相続税法33条の2において還付となる場合において、この免除された税額の取扱いについては、定かではない。
3 両制度の相違点 このように、贈与税の納税猶予において、暦年課税制度と相続時精算課税制度は、贈与後の不幸な事態への対応に、大きな違いがある。
贈与税の納税猶予においては、株価が下落した場合と、親より子供が先に死んだ場合に、免除という救済規定がある。相続時精算課税は、これらの場合にこれらの事情を考慮しない制度となっている。相続時精算課税制度と贈与税の納税猶予制度を併用した場合において、平成29年度改正において2世代連続贈与に係る重複課税の排除以外は調整規定が設けられなかったことが要因である。
この点は課税当局に照会したが、やはり相続時精算課税との調整規定がないとのことだった。
従って、相続時精算課税制度と贈与税の納税猶予制度を併用した場合は、次の2点で明らかに暦年課税制度と贈与税の納税猶予制度を併用した場合より不利だと言えるが、その程度は個々の計算事例によることになり、有利不利の度合いは直ちには計算できない。
① 株価の下落による新減免措置の適用により贈与税の減免を受けた場合、いったん減免されるのは相続時精算課税制度の贈与税であり、贈与者の死亡時には相続税法21条の14から21条の16までにより、贈与時の時価で相続財産に加算され、同時に免除額を含めて課せられた贈与税が控除されることになる。
② 贈与者より前に受贈者が死亡した場合、免除されるのは相続時精算課税による贈与税であって、贈与者の死亡時には、相続税法21条の17により、受贈者(相続時精算課税適用者)が有していた納税に係る権利及び義務を受贈者の相続人が承継し、贈与時の時価でみなし相続され、かつ、課せられた贈与税額が、その相続税より控除されることになる。
上記の場合の、暦年課税と相続時精算課税選択の有利不利は個別の計算をみないと直ちに判定できない事態になっている。その意味で、今後の税制改正要望に期待したい。
Ⅳ 相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利・義務の承継【事例】
【事例】(後継者先死亡)
相続時精算課税適用者の相続人(妻、孫)は、その相続時精算課税適用者(後継者)が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する(相続税法21条の17)。
この場合、相続時精算課税適用者の相続人が2人以上いる場合の各相続人が承継する相続時精算課税の適用に伴う権利義務の割合は、民法第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続分・指定相続分)に規定する相続分により(国税通則法5条②、相基通21の17-2)、相続人は、その超える価額を限度として、他の相続人が前二項の規定により承継する国税を納付する責めに任ずる。
相続時精算課税適用者(後継者)が死亡した後にその特定贈与者(父)が死亡した場合には、相続時精算課税適用者の相続人(妻、孫)が、その相続時精算課税適用者に代わって、特定贈与者の死亡に係る相続税の申告をすることとなるが、その申告をするまでは、納付すべき税額が算出されるか、あるいは還付を受けることができる税額が算出されるかが明らかでないことから、相続時精算課税適用者の死亡に係る相続税額の計算においては、この相続時精算課税の適用に伴う納税に係る義務は、当該相続時精算課税適用者の死亡に係る相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象とはならない。
この事例では、父が死亡した場合の相続税の負担額は前頁下表の通り。

(基礎控除は、法定相続人が孫1名なので、3,600万円。税額按分の割合は、本来財産0.4:みなし財産0.6)
先に亡くなった後継者の配偶者と故長男の子(孫)は、後に亡くなった亡き父(長男)の相続税を上記の通り法定相続分で負担することになる(国税通則法5条②③)。本件で亡き長男に係る相続税は、亡き長男の相続において債務控除できない。
相続時精算課税制度を利用して贈与した場合、相続時精算課税適用者が先に亡くなった時には贈与した部分が持ち戻されて、亡き父の本来財産と亡き長男に係るみなし相続財産で相続税を計算し、みなし財産に係る相続税を負担しなければならない。相続時精算課税適用者の相続人が2人分(特定贈与者固有分と亡き長男に係るみなし財産について)の相続税を負担しなければならなくなる。
但し、贈与税の納税猶予の制度上免除された贈与税は、その免除がなかったものとして、相続税より控除できる。
なお暦年課税を選択した場合は、3億円の贈与税は157,995千円であるが、全額が納税猶予となり、かつ贈与者より先に受贈者が死亡した場合は免除される。
このように、相続時精算課税は贈与税の納税猶予において暦年課税より不利な場合がある。
その有利不利の度合いは、個別性が強いので一概に言えないが、贈与税の納税猶予の適用を受ける場合は、慎重な選択をすすめたい。
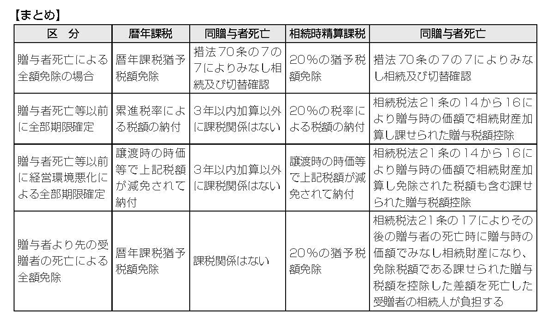
贈与税の納税猶予における相続時精算課税のメリットとデメリット
税理士 竹内陽一
公認会計士 長谷川敏也
公認会計士 有田賢臣
Ⅰ 平成29年度改正により相続時精算課税制度との併用が可能に
平成29年度税制改正により、贈与税の納税猶予制度と相続時精算課税制度の併用が可能になった。特例事業承継税制でも同様に併用が可能である(措法70の7②五ロ、70の7の5②八ロ)。
この平成29年度改正では、相続時精算課税制度との併用を禁止していた改正前租税特別措置法70条の7第3項が削除され、調整規定として租税特別措置法70条の7第13項に、9号と10号が設置されるに留まっている。調整規定の内容は、2世代連続贈与においての第1贈与者死亡時と第2贈与者死亡時において、相続税法21条の14から21条の16までの規定(相続時精算課税制度によるみなし相続)は適用しないというシンプルなものであった。
そして贈与税の納税猶予が期限確定した際に、暦年課税制度を選択している場合の贈与税額(下記事例における贈与税の実効税率は約51.5%)に比べて、相続時精算課税制度を選択している場合の相続税額(下記事例における相続税の実効税率は30.6%)が小さくなるので、期限確定の場合は相続時精算課税を贈与税の納税猶予制度と併用したほうが確かに有利である。
【事例】 贈与税の納税猶予が期限確定した場合、特例経営承継受贈者(後継者)に高額な税負担が生じる恐れがあるため、相続時精算課税制度との併用が可能となり、期限確定時の贈与税負担額は(評価額-2,500万円)×20%相当額(利子税別途)のみとされた。
以下の通り、相続時精算課税制度を選択すれば、贈与税の納税猶予制度を適用した場合のリスクが大幅に軽減されることになり(実質的に利子税のみがリスクとなる)、贈与者死亡時の相続税額は、暦年課税制度による贈与税額より少額となる。
| 完全議決権株式総数 1,000株 一株当たり評価額 300,000円/株 株価総額 3億円 先代経営者は株式全体の三分の二(2億円)を保有している。 相続人は後継者1名であり、先代経営者の資産は自社株式以外に預貯金1億円のみ。 |
贈与時と相続時の自社株式の評価額は同額とする。
相続財産=自社株式2億円+預貯金1億円=3億円……
| 相続税91,800,000円 |
贈与税の納税猶予制度を適用していたところ、適用対象株式の全てについて期限が確定した場合、暦年課税制度を選択した場合と相続時精算課税制度を選択した場合の納税額を比較をすると図1の通りである。
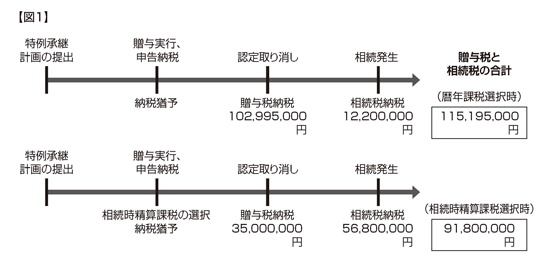
このように、贈与時と相続時の評価額を同額とした場合、事業承継税制を適用しない場合の相続税額91,800,000円と、贈与税の納税猶予制度と相続時精算課税制度を併用し、その後期限が確定した場合の納税額の総額91,800,000円は一致することになり、期限が確定した場合に暦年課税制度により算出された過大な贈与税額を払わなければならないリスクが回避できるようになった。
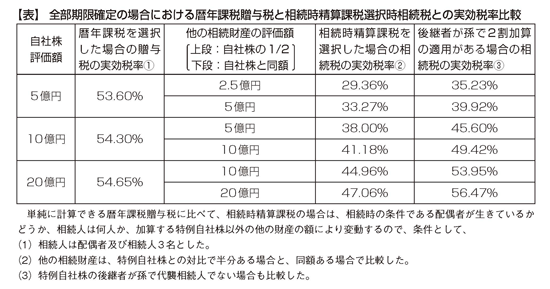
Ⅱ 相続時精算課税制度と贈与税の納税猶予制度の共通点
この両制度は、これらの制度を適用して贈与した財産を贈与者の死亡時に贈与時の時価で相続したものとみなして相続税が計算されるという点で極めて類似している。
なお、贈与税の納税猶予制度は政策税制であるので、贈与後の不幸な事態について救済規定を設けており、相続時精算課税制度にはない次の特徴がある。第一は株価の下落に対応した猶予税額の減免規定であり、第二は受贈者(子)が先代経営者(親)より先に亡くなった場合に猶予税額の全額を免除するという割り切った規定である。
Ⅲ 贈与税の納税猶予制度適用時における相続時精算課税と暦年課税の違い
1 株価の下落に伴う新減免特例 納税猶予適用対象株式を譲渡することにより、納税猶予の期限が確定した際に、業績悪化により株価が下落している場合には、減免措置により譲渡時の株価で納税猶予額が再計算され、当初納税猶予額と再計算納税猶予額の差額は免除となる。
納税猶予の期限が確定した場合、暦年課税制度を選択している場合には、この減免された贈与税額を納付することにより課税関係は確定し、租税特別措置法70条の7の3が適用されること(贈与財産が相続税の課税対象となること)はない。すなわち、租税特別措置法70条の7の3においては、1項本文において、「その死亡の日前に猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同条第三項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定した場合及びその死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合を除く。」とされている。
一方、相続時精算課税制度を選択している場合には、上記Ⅰのとおり、相続税法21条の14から21条の16までの適用において、株価の下落に伴う減免規定と同様の規定(贈与時の時価を譲渡時の時価に置き換える調整規定)が平成29年度改正において創設されなかった。
平成29年度税制改正の解説を逆読みすれば、減免規定が適用されるケース(株式の譲渡により納税猶予の期限が確定するケース)においては、事業承継税制のレールから外れて、相続時精算課税制度だけ適用している状態に復帰することになる。
そうすると、贈与者の死亡時には、贈与財産が贈与時の時価で相続財産に加算され、「課せられた贈与税」が控除されるので、免除された贈与税額を含めて控除されることになるようだ(相続税法21条の15③、21条の16④、相基通21の15-3、21の16-1)。
平成30年度税制改正の解説p604によれば(図2を参照)、新減免特例の効果として暦年課税制度を選択した場合の解説がなされており、当初の贈与税額150(300×50%とする)が減免されて、60を納付することにより課税関係は終了することになる(みなし相続課税はない)。
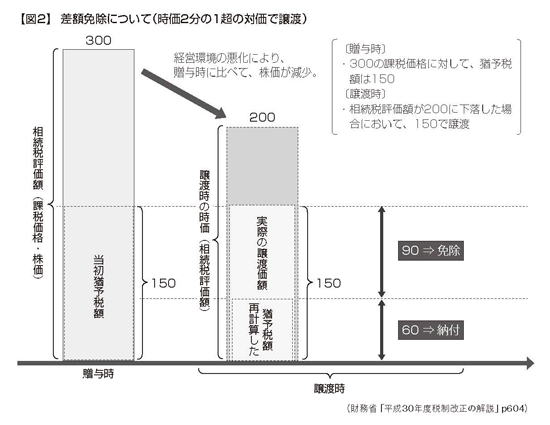
一方、相続時精算課税制度を選択した場合は、贈与税の当初納税猶予額は60(300×20%とする)であり、減免によって再計算猶予税額30(150×20%とする)を納付し、30が減免される。しかし、贈与者の相続時には、300で相続財産に加算されるとともに、控除される贈与税額は、免除された30と期限確定納付の30の合計60が控除されることになる。みなし相続課税を受けるという点で暦年課税を選択した場合よりも不利になるものの、免除された贈与税も含めて相続税から控除できるという点で、新減免の効果は一定程度あることになる。
2 受贈者が贈与者より先に死亡した場合 贈与者より先に受贈者が死亡した場合、納税猶予された贈与税は免除される。
暦年課税制度を選択している場合には、このような不幸な事態に、受贈者の相続人に対して受贈者が保有していた自社株式についての相続税課税が開始されるのみである。贈与者の死亡時には贈与財産(当該自社株式)が相続税の課税対象となることはないので1世代飛ばしの効果がフルに享受できる。
一方、相続時精算課税を選択している場合においては、上記の新減免特例と同様に、調整規定が創設されていないので、受贈者の相続人に対して受贈者が保有していた自社株式についての相続税課税が開始されるが、その後の贈与者の死亡時には、相続税法21条の17(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)が働き、贈与財産(当該自社株式)が相続税の課税対象となる。そして、この相続税計算においては、上記Ⅲ1のとおり、当初に課せられた贈与税の全額が控除できるようだ。
このみなし相続財産に係る相続税は、死亡した受贈者の相続人がその法定相続分割合で負担し、課せられた贈与税を控除した差額を納付することとなるようだ(相続税法21条の17③、国税通則法5条②)。
なお、上記1、2において、相続税法33条の2において還付となる場合において、この免除された税額の取扱いについては、定かではない。
3 両制度の相違点 このように、贈与税の納税猶予において、暦年課税制度と相続時精算課税制度は、贈与後の不幸な事態への対応に、大きな違いがある。
贈与税の納税猶予においては、株価が下落した場合と、親より子供が先に死んだ場合に、免除という救済規定がある。相続時精算課税は、これらの場合にこれらの事情を考慮しない制度となっている。相続時精算課税制度と贈与税の納税猶予制度を併用した場合において、平成29年度改正において2世代連続贈与に係る重複課税の排除以外は調整規定が設けられなかったことが要因である。
この点は課税当局に照会したが、やはり相続時精算課税との調整規定がないとのことだった。
従って、相続時精算課税制度と贈与税の納税猶予制度を併用した場合は、次の2点で明らかに暦年課税制度と贈与税の納税猶予制度を併用した場合より不利だと言えるが、その程度は個々の計算事例によることになり、有利不利の度合いは直ちには計算できない。
① 株価の下落による新減免措置の適用により贈与税の減免を受けた場合、いったん減免されるのは相続時精算課税制度の贈与税であり、贈与者の死亡時には相続税法21条の14から21条の16までにより、贈与時の時価で相続財産に加算され、同時に免除額を含めて課せられた贈与税が控除されることになる。
② 贈与者より前に受贈者が死亡した場合、免除されるのは相続時精算課税による贈与税であって、贈与者の死亡時には、相続税法21条の17により、受贈者(相続時精算課税適用者)が有していた納税に係る権利及び義務を受贈者の相続人が承継し、贈与時の時価でみなし相続され、かつ、課せられた贈与税額が、その相続税より控除されることになる。
上記の場合の、暦年課税と相続時精算課税選択の有利不利は個別の計算をみないと直ちに判定できない事態になっている。その意味で、今後の税制改正要望に期待したい。
| (相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等) 第二十一条の十七 特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該相続時精算課税適用者が有していたこの節の規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。ただし、当該相続人のうちに当該特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者は、当該納税に係る権利又は義務については、これを承継しない。 |
Ⅳ 相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利・義務の承継【事例】
【事例】(後継者先死亡)
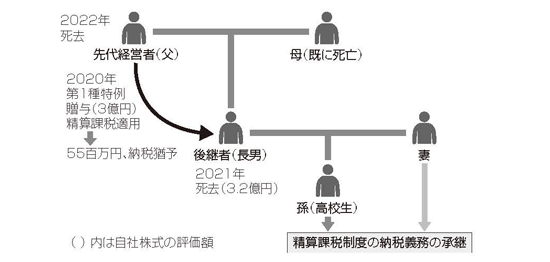
|
相続時精算課税適用者の相続人(妻、孫)は、その相続時精算課税適用者(後継者)が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する(相続税法21条の17)。
この場合、相続時精算課税適用者の相続人が2人以上いる場合の各相続人が承継する相続時精算課税の適用に伴う権利義務の割合は、民法第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続分・指定相続分)に規定する相続分により(国税通則法5条②、相基通21の17-2)、相続人は、その超える価額を限度として、他の相続人が前二項の規定により承継する国税を納付する責めに任ずる。
相続時精算課税適用者(後継者)が死亡した後にその特定贈与者(父)が死亡した場合には、相続時精算課税適用者の相続人(妻、孫)が、その相続時精算課税適用者に代わって、特定贈与者の死亡に係る相続税の申告をすることとなるが、その申告をするまでは、納付すべき税額が算出されるか、あるいは還付を受けることができる税額が算出されるかが明らかでないことから、相続時精算課税適用者の死亡に係る相続税額の計算においては、この相続時精算課税の適用に伴う納税に係る義務は、当該相続時精算課税適用者の死亡に係る相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象とはならない。
この事例では、父が死亡した場合の相続税の負担額は前頁下表の通り。

(基礎控除は、法定相続人が孫1名なので、3,600万円。税額按分の割合は、本来財産0.4:みなし財産0.6)
先に亡くなった後継者の配偶者と故長男の子(孫)は、後に亡くなった亡き父(長男)の相続税を上記の通り法定相続分で負担することになる(国税通則法5条②③)。本件で亡き長男に係る相続税は、亡き長男の相続において債務控除できない。
相続時精算課税制度を利用して贈与した場合、相続時精算課税適用者が先に亡くなった時には贈与した部分が持ち戻されて、亡き父の本来財産と亡き長男に係るみなし相続財産で相続税を計算し、みなし財産に係る相続税を負担しなければならない。相続時精算課税適用者の相続人が2人分(特定贈与者固有分と亡き長男に係るみなし財産について)の相続税を負担しなければならなくなる。
但し、贈与税の納税猶予の制度上免除された贈与税は、その免除がなかったものとして、相続税より控除できる。
なお暦年課税を選択した場合は、3億円の贈与税は157,995千円であるが、全額が納税猶予となり、かつ贈与者より先に受贈者が死亡した場合は免除される。
このように、相続時精算課税は贈与税の納税猶予において暦年課税より不利な場合がある。
その有利不利の度合いは、個別性が強いので一概に言えないが、贈与税の納税猶予の適用を受ける場合は、慎重な選択をすすめたい。
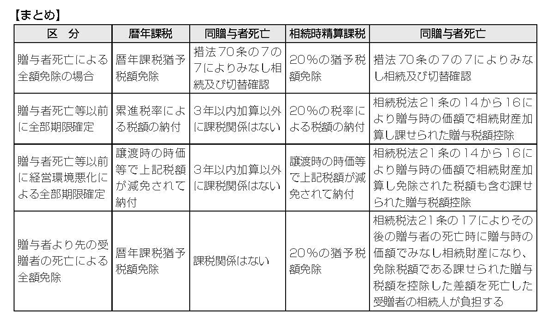
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















