解説記事2019年01月28日 【税制改正解説】 平成31年度税制改正について(2019年1月28日号・№772)
税制改正解説
平成31年度税制改正について
一般社団法人日本経済団体連合会 経済基盤本部 神谷智彦
はじめに
平成31年度税制改正では、消費税率の引き上げに伴う需要平準化対策の観点から、自動車関係諸税・住宅税制の見直しが行われるとともに、研究開発税制の改組・拡充や地方法人課税、中小企業税制、役員給与制度の見直し、国際課税などについて重要な改正がなされた。以下、主要な改正点について整理したい。
なお、本記事の内容は、現在公表されている平成31年度与党税制改正大綱や各省庁の税制改正に関する解説資料、政府税制調査会資料等に基づいて作成している。各省庁の資料等の作成・公表に感謝するとともに、今後の法案の策定・審議により、内容に変更が生じうることにご留意いただきたい。また、内容については、すべて筆者個人の見解であり、組織を代表したものではない。
Ⅰ 消費税率の引き上げに伴う需要平準化対策
2019年における税制の最も大きなテーマは、消費税率の引き上げである。2019年10月の消費税率の8%から10%への引き上げについては、前回の5%から8%への引き上げの際に、需要の反動減が大きく生じたことを踏まえ、政府として、需要平準化のための対策を行うことを2018年の前半ごろから検討していた。「経済財政運営と改革の基本方針2018(以下、骨太の方針2018)」(2018年6月15日閣議決定)において、「2019年10月1日における消費税率の引上げに向けては、消費税率引上げによる駆け込み需要・反動減といった経済の振れをコントロールし、需要変動の平準化、ひいては景気変動の安定化に万全を期す」ことが明記され、具体的な方策として、消費税率引上げ分の使い道の見直し、軽減税率制度の実施、転嫁対策の徹底に加え、商店街の活性化、中小企業・小規模事業者のIT・決済端末の導入やポイント制・キャッシュレス決済の普及・促進や自動車や住宅などの購入支援に係る措置を検討するとされていた。
平成31年度税制改正では、これらの骨太の方針の記述を踏まえ、自動車関係諸税や住宅税制について幅広い見直し・制度の拡充が行われた。
(1)自動車関係諸税 自動車関係諸税については、消費税率10%への引上げにあわせて、自動車の保有に係る税負担を恒久的に引き下げるとともに、環境性能割について、時限的な軽減措置を設ける。
具体的には、保有に係る税である自動車税について、創設後約70年で初めて恒久減税を行うこととなった。引き下げ幅は1,000円~4,500円となる。なお、消費税率の引き上げに伴う需要平準化という観点から、引き下げの対象となる車は消費税率引き上げ後に、新車新規登録を受けたものに限られる(引き下げ幅について、図1参照)。
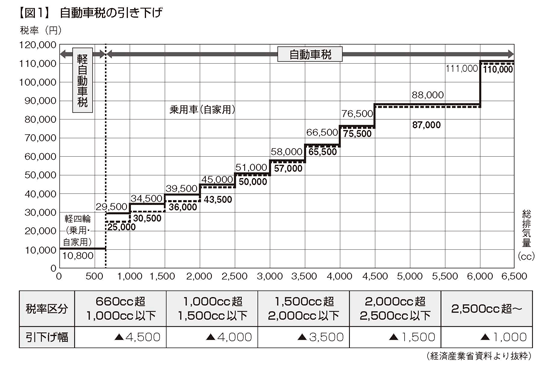
他方、これらの税収減に対応するために、エコカー減税の見直し、グリーン化特例の重点化、環境性能割の見直しにより財源を確保することとなった。
エコカー減税については、2020年基準+30%達成車~2020年基準+10%達成車について、2019年以降、軽減の割合を見直すこととする。現行でエコカー減税により自動車取得税を80%~40%軽減されている車については、2019年4月1日から9月30日にかけて50%~25%にまで軽減の幅が縮小されることになる。なお、エコカー減税の制度は2019年9月末で廃止となる。また、自動車重量税については、現在75%~50%軽減されている車について、50%~25%にまで軽減の幅を縮小する。
自動車取得税に代わって導入される自動車税の環境性能割の税率については、表1のとおり燃費性能に関する要件を引き上げることとした。
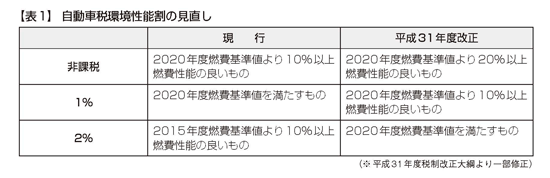
もっとも、2019年10月1日から1年間の間に取得した自家用乗用車に係る環境性能割については、税率1%分を軽減する特例措置が講じられる。このため、普通自動車では、消費税率引き上げ後1年間は環境性能割の引き上げの影響は生じないこととなる。また、軽自動車では、上記の環境性能割の引き上げは行われない一方、2019年10月1日から1年間の間に取得した自家用乗用車に係る環境性能割については、税率1%の軽減措置が講じられることとなる。
グリーン化特例については、2021年3月末まで現行制度が単純延長されるが、2021年4月以降は、適用対象が電気自動車等(電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車、クリーンディーゼル車)に限定される。
これらの自動車関係諸税の見直しの全体像は図2のとおりである。
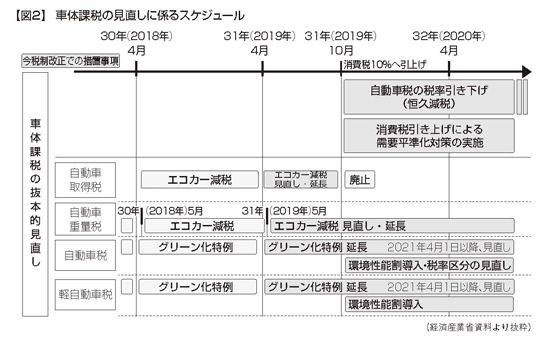
なお、自動車関係諸税については、中長期的な検討の方向性が、大綱の検討事項に以下のとおり示されている。
昨年末には、自動車課税の抜本的な見直しの方向性として、走行距離に応じた課税に移行する等の報道等も一部でなされていたが、走行距離を適正に把握することが可能なのかという技術的な問題等もある。このため、大綱では、特に走行距離課税という方向は示さずに、「中長期的な視点に立って検討を行う」としている。
(2)住宅関係諸税 住宅に関する税制措置についても、需要変動の平準化のため、措置が講じられた。消費税率が10%となる住宅の取得に関し、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例(住宅ローン減税)を3年間延長することとした。この延長は単純延長ではなく、当該年度における控除の限度額は、イ)住宅借入金等の年末残高×1%と、ロ)建物購入金額(消費税額分を除く)×2%÷3のいずれか少ない金額となる。なお、一般住宅の住宅借入金等の年末残高及び建物購入金額(消費税額分を除く)の限度額は4,000万円、認定住宅等のそれぞれの限度は5,000万円である。この住宅ローン減税の特例は2019年10月1日から2020年12月31日までの間に、対象の住宅を本人の居住の用に供した場合について適用する。
(3)その他、消費税率の引き上げに伴う予算措置等 上記の自動車・住宅に関する税制措置の他、需要変動の平準化に対応する観点から様々な予算措置が講じられる見込みである。具体的には、低所得者及び子育て世帯(0歳児~2歳児)向けのプレミアム付商品券の発行・販売(使用は、2019年10月から2020年3月まで)や中小・小規模事業者に対するキャッシュレス決済手段を用いた場合のポイント還元支援(2019年10月から2020年6月まで)、マイナンバーを活用した自治体ポイントの付与(2020年7月以降)、住宅に係るすまい給付金の拡充(対象となる所得階層を収入目安510万円以下から775万円以下に拡充し、給付額も最大30万円から50万円に引上げ(2019年10月から2021年12月末まで))、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事・介護負担の軽減に資する新築・リフォームに対し、様々な商品等と交換できるポイントを発行する次世代住宅ポイント制度(2019年10月から2020年3月末まで)等の措置を行うこととしている。
これらの消費税率の引き上げに伴う対策のパッケージの全体像は前頁の表2のとおりである。
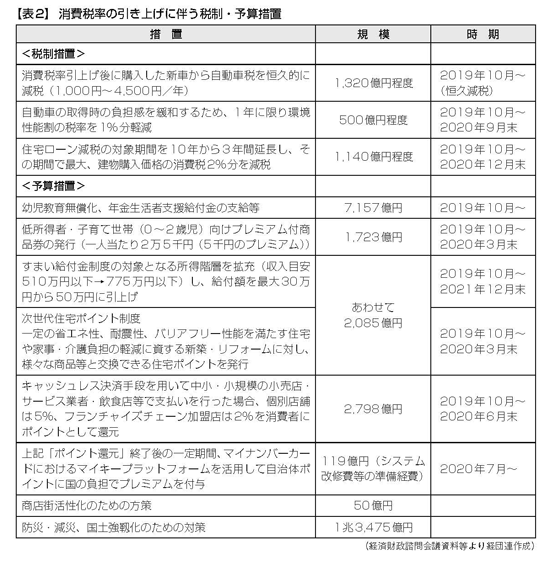
Ⅱ 法人課税
1.研究開発税制の改組・拡充 研究開発税制については、研究開発投資の増加インセンティブを強化する観点から見直しが行われた。研究開発税制の見直しのポイントは以下の表3のとおりである。
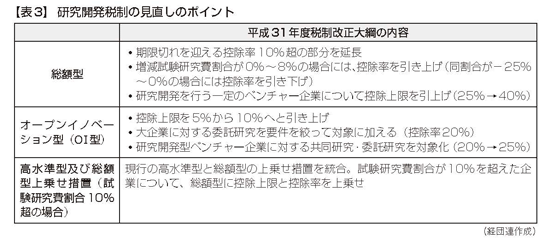
(1)総額型 研究開発税制の総額型については平成29年度税制改正により、増加型が取り込まれ、試験研究費の増減(増減試験研究費割合)に対応して、控除率が増減する制度となっていた。この点、平成31年度税制改正大綱では、「骨太の方針2018」及び「未来投資戦略2018」(2018年6月15日閣議決定)で掲げられている「2020年度までに、官民合わせた研究開発投資をGDP比4パーセント以上にする」という目標を達成すべく、目標から逆算した研究開発費が年8%増となる水準を基点として、より試験研究費の増加インセンティブを強化する観点から、控除率の増減に係るグラフの傾きを大きくすることとした。グラフの概要は図3のとおりである。なお、控除率10%超の場合については、2年間の適用期限が設けられている。
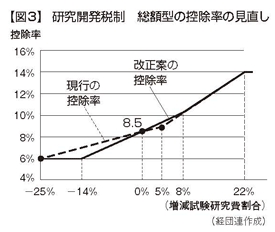
増減試験研究費割合と控除率の計算は上記の表4の式により求められることになる。
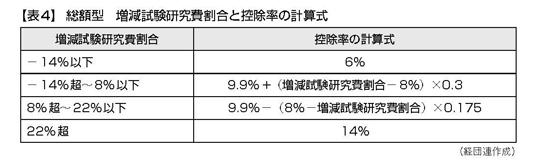
上記の改正により、総額型では控除上限(調整前法人税額の25%)に達していない企業においては、増減試験研究費割合が増減なし~8%増加している場合は減税となる一方、-25%~増減なしの場合は、税負担が増えることとなる。
また、「研究開発を行う一定のベンチャー企業」については、総額型の控除上限が40%となる。「研究開発を行う一定のベンチャー企業」とは、「設立後10年以内の法人のうち、当期において翌期繰越欠損金額を有するもの(大企業の子会社等を除く)」とされている。この「研究開発を行う一定のベンチャー企業」が中小企業の場合、基本的に翌期繰越欠損金額は全額控除できることから、活用が想定されるのは、資本金1億円超の大法人に成長したベンチャー企業となる。
(2)オープンイノベーション型(OI型) オープンイノベーション型(特別試験研究費の額に係る税額控除制度)についても今般の税制改正で拡充されることとなった。OI型の控除上限を現行の法人税額の5%から10%へと引き上げるとともに、対象を大きく拡充することとした(図4参照)。対象については、これまで認められていなかった大企業に対する委託試験研究について、a)民法上の委任契約によって委託される委託試験研究で、b)委託法人の基礎研究又は応用研究にかかる試験研究であること、もしくは、受託者の知的財産権等を利用した試験研究であること、c)委任契約等においてb)の事項が定められていることという要件のもと、大企業に対する委託試験研究を認めることとなった。
「研究開発型のベンチャー企業」との共同研究及び「研究開発型のベンチャー企業」への委託研究については、税額控除率を25%とするかたちで認めることとした。対象となる「研究開発型のベンチャー企業」は、前述の総額型における「研究開発を行う一定のベンチャー企業」とは要件が異なっており、「産業競争力強化法の新事業開拓事業者でその発行する株式の全部又は一部が同法の認定ベンチャーファンドの組合財産であるものその他これに準ずるものをいう」とされ、基本的にベンチャーファンドの投資対象となる新興企業(大企業子会社や上場企業を除く)が対象となる見込みである。なお、「研究開発型のベンチャー企業」への委託研究については、大企業に対する委託研究と同様に、前述のa)~c)の要件を満たすことが必要となる。
また、大学との共同研究に係るOI型の適用に関しては、これまでも、リサーチ・アドミニストレーターなどの研究開発のプロジェクトマネジメント業務等を担う者の人件費を対象とすることが否定されてきたわけではないが、今回の税制改正大綱において、それらリサーチ・アドミニストレーターの人件費についても、OI型の適用対象となることが明示されている。
(3)高水準型・総額型上乗せ措置 高水準型及び試験研究費割合が10%超の場合の総額型の上乗せ措置についても、見直しが行われることとなった。平成29年度税制改正により、高水準型に加えて、試験研究費割合が10%超の場合の総額型の上乗せ措置が創設され、試験研究費割合が10%超の場合の措置が並存する状況となっていた。今般の平成31年度税制改正では、この両方の措置を基本的に総額型の上乗せ措置に一本化し、制度を拡充することとした。具体的には、現行の総額型の上乗せ措置の控除上限の上乗せ措置(控除上限を「25%+(試験研究費割合-10%)×2」とする)を引き続き維持したうえで、新たに控除率を上乗せする。上乗せされた控除率は、「通常の総額型の控除率+((試験研究費割合-10%)×0.5)×通常の総額型の控除率」となる。なお、「試験研究費割合-10%」は10%が上限となる。
従来の試験研究費割合が10%超の場合の総額型の上乗せ措置では、控除上限の引き上げという措置のみであったため、総額型の控除上限に達していない場合には、控除上限の引き上げによるメリットが生じていなかった。今般の見直しにより、控除率を引き上げるという措置が整備され、これらの総額型の控除上限に達していない場合であっても、メリットが生じることとなった。
(4)中小企業に係る研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制) 中小企業に対する研究開発税制についても大企業と同じように、総額型やOI型の見直しに対応するかたちで増減試験研究費割合が8%となるところがグラフの傾きの起点となるよう見直しがなされることとなった(図5参照)。
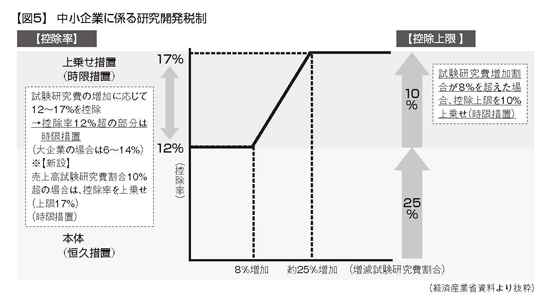
以上が平成31年度税制改正の研究開発税制の見直しの概要となる。
イノベーションにつながる研究開発をより一層促進していくためには、研究開発税制の存在が引き続き重要となる。近年、AIやビッグデータ、IoTなどの技術が進展し、社会全体に組み込まれている。このようなデジタル革新と多様な人々の想像・創造力の融合によって社会の課題を解決し、価値を創造する社会を、「Society5.0」として、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く第5段階の新たな「創造社会」として位置づけている。今後の研究開発税制のあり方を考えるうえでも、このような流れを踏まえ、「Society 5.0」の実現に資するかたちで引き続き制度を検討することが求められる。
オープンイノベーション型については今般、控除上限が拡充されたが、大学などと共同研究を進めるうえで、書面に記載すべき項目などの手続に関する要件がネックとなって、活用が十分に進んでいないという側面もある。拡充された控除上限を十分に活かすためにも、引き続き検討を進めることが必要となるだろう。また、Society 5.0を支えるITサービス等の開発・活用を進める観点から、平成29年度税制改正で整備されたサービス開発に関する研究開発税制についても、より幅広い産業や様々な局面で活用しやすくなるよう要件の見直しを検討していくことが重要と考える。
2.中小企業関係税制等 中小企業の関係では、研究開発税制に加えて、いくつかの税制措置が講じられることとなった。
(1)個人版事業承継税制の創設 平成30年度税制改正では、法人に係る事業承継税制について大きく拡充する措置が講じられたが、平成31年度税制改正では、個人版の事業承継税制を創設することとした(図6参照)。
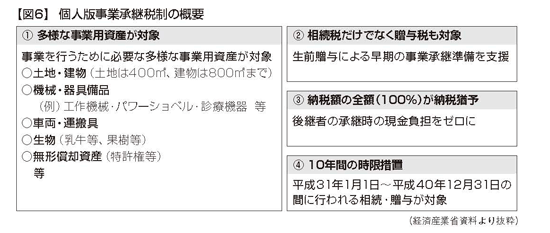
個人版の事業承継税制では、10年間に限って、土地・建物や器具・備品など、様々な事業用資産に関する相続税・贈与税を100%納税猶予する措置を設ける。なお、この制度を活用するためには、①経営承継円滑化法に基づく認定とともに、②2019年度から5年以内に、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が示された承継計画を作成し、都道府県に提出する必要がある。また、この制度については、現行の事業用小規模宅地特例との選択により適用することとなる。
(2) 中小企業に係る投資促進税制等 中小企業者等に係る軽減税率の特例、中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制については、適用期限が2年延長される。商業・サービス業・農林水産業活性化税制については、売上高又は営業利益が年間で2%以上の向上する見込みがあるという要件が追加されることとなった。
また、中小企業の事前防災の対策を促進する観点から、事業継続力強化計画(仮称)の認定を受けた中小企業が、対象となる防災・減災設備を取得した場合には、20%の特別償却ができる措置を創設することとした(図7参照)。
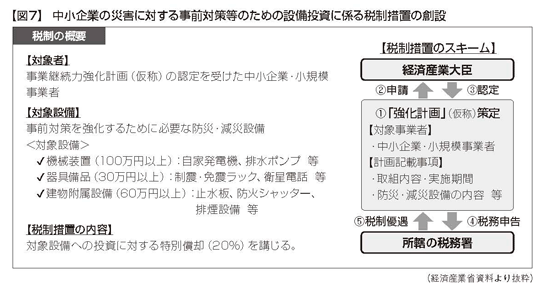
地域未来投資促進税制に関しては、制度を2年間延長するとともに、直近の事業年度の付加価値増加率が8%を超える場合には、対象設備に係る投資について50%の特別償却(現行:40%)もしくは、5%の税額控除(現行:4%)を認めることとした。
3.役員給与税制・組織再編税制の見直し
(1)役員給与税制の見直し 役員報酬制度については、平成29年度税制改正で業績連動給与の算定指標の範囲拡大など拡充が行われた。一方で、支給にかかる適正手続要件に関しては、とりわけ、指名委員会等設置会社における報酬委員会について、「業務執行役員又はその業務執行役員と一定の特殊の関係のある者がその委員になっているものを除く」とされていることから、報酬委員会の構成員が一人でも業務執行役員又はその業務執行役員と一定の特殊の関係のある者(以下、業務執行役員等)である場合には、業績連動報酬の損金算入を行うことができなくなっていた。
このため、平成31年度税制改正では、業績連動報酬制度の見直しがなされることとなった。大綱では、「報酬委員会等を設置する法人の業務執行役員が報酬委員会等の委員でないこととの要件を除外する」としており、報酬委員会の構成員が業務執行役員等であるかどうかにより外形的に判断する要件は見直されることになる。一方で、「業務執行役員が自己の業績連動給与の決定等に係る決議に参加していないこととの要件を加える」、及び「報酬委員会等の委員の過半数が独立社外役員であること及び委員である独立社外役員の全てが業績連動給与の決定に賛成している」という2つの要件を満たすことが必要とされた。業績連動給与に係る決議の内容に着目し、独立社外役員がその内容をチェックして決定するという昨今のコーポレートガバナンスの流れを踏まえた見直しと評価できる。
他方、監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社については、役員給与の損金算入要件について、要件を絞ることで適正化がなされた。現行の規定で、監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社にかかる役員給与に関し、①報酬諮問委員会に対する諮問を経た手続の他、②株主総会における決議や、③監査役の過半数が適正であると認められる旨を記載した書面を提出した場合における取締役会の決定(監査役会設置会社の場合)及び監査等委員である取締役の過半数が当該決議に賛成している場合における取締役会の決定(監査等委員会設置会社の場合)があった場合においても、業績連動報酬の損金算入が認められている。この点、コーポレートガバナンスコード改訂版で監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社においても、「独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置する」ことが推奨されていることを踏まえ、監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社においても、報酬諮問委員会等を通じた役員報酬の決定の適正化を担保すべく、①の報酬諮問委員会の手続について、上記の指名委員会等設置会社の報酬委員会の場合の手続と同様の要件となるよう改正するとともに、③の適正と認められる書面の提出による手続については、廃止することとした(図8参照)。このため、③の書面による手続をとっている企業にあたっては、手続の見直しが必要となる。
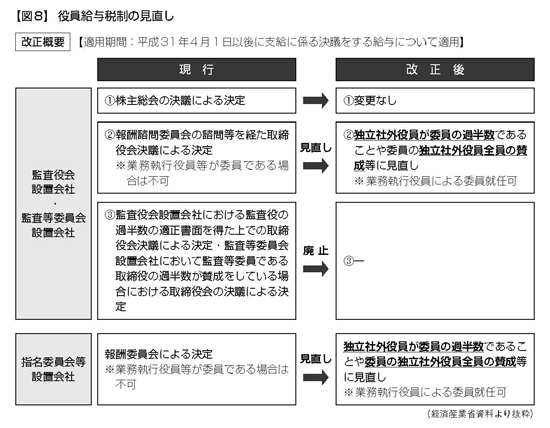
(2)組織再編税制の見直し 組織再編税制に関しては、親会社が子会社を完全子会社化した後に行う逆さ合併について、逆さ合併を続けて行うことが見込まれている場合には、適格組織再編の対象とする。また、親会社の株式を対価とした組織再編について、現状では、直接の親会社の株式を対価とする場合のみが、適格組織再編とされているが、間接保有の完全親会社の株式を組織再編の対価として交付する場合についても適格組織再編の対象とするよう見直しを行う。
Ⅲ 地方税
1.地方法人課税の偏在是正 地方法人課税の見直しについては、平成30年度与党税制改正大綱において「特に偏在度の高い地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置について、消費税率10%段階において地方法人特別税・譲与税が廃止され法人事業税に復元されること等も踏まえて検討し、平成31年度税制改正において結論を得る」とされていた。
この大綱の記載を踏まえ、総務省地方財政審議会において「地方法人課税に関する検討会(座長:堀場勇夫青山学院大学名誉教授)」が設置され、7回の会合を経て、2018年11月に報告書が公表された。報告書の中では、新しい制度を設計する際には、①法人事業税を対象とすること、②具体的な方策については、譲与税化により実効性のある偏在是正措置とすることができる場合には、譲与税化を基本として考えること、③十分な偏在是正効果を得られない場合には、交付税原資化も視野に入れて検討すること、④譲与税化の場合、偏在是正という趣旨・目的に沿って、譲与基準を「人口」とすることを基本とすること等としていた。
平成31年度税制改正では、この報告書の内容も踏まえ、地方法人課税について、地方における法人関係税収の偏在を是正する観点から見直しがなされた。現在の地方法人課税の税収は付加価値の総計である県内総生産の分布状況と比較して、大都市部に集中していることから、この偏在を是正すべく、特別法人事業税(仮称)及び特別法人事業税(仮称)という新たな税制措置を創設することとした。制度の概要は以下のとおりである。
特別法人事業税(仮称) 消費税率10%段階において復元後の法人事業税(所得割・収入割)の一部(法人事業税の約3割)を分離し、特別法人事業税(仮称)(国税)とする。
課税標準:法人事業税(所得割・収入割)の税額(標準税率分)
賦課徴収:都道府県(法人事業税と併せて実施)
適用期日:2019年10月1日以後に開始する事業年度から適用
特別法人事業譲与税(仮称)
譲与額:特別法人事業税(仮称)の税収(全額)を都道府県に譲与
譲与基準等:「人口」を譲与基準とし、不交付団体に譲与制限の仕組み(25%までを上限として保障)を設ける
譲与開始時期:2020年度
2.ふるさと納税制度の見直し ふるさと納税制度について、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような地方自治体に対しては、ふるさと納税の対象外にすることができるよう、制度の見直しを行うこととした。
具体的には、総務大臣は、地方財政審議会の意見を聴いた上で、寄附金の募集を適正に実施し、①返礼品の返礼割合は3割以下、かつ、②返礼品を地場産品とする自治体のみをふるさと納税の控除の対象となる自治体として指定できることとした。
Ⅳ 国際課税
平成29年度与党税制改正大綱及び平成30年度与党税制改正大綱で中長期的に取り組むべき事項とされたOECD/G20のBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトの残された課題(所得相応性基準、過大支払利子税制、義務的情報開示)のうち、過大支払利子税制及び所得相応性基準について、平成31年度税制改正で見直しがなされた。また、外国子会社合算税制(CFC税制)についても、米国税制改正等を踏まえ、ペーパーカンパニーの要件等が見直されることとなった。
1.過大支払利子税制の見直し 現行の過大支払利子税制については、関連者への純支払利子等の額のうち調整所得金額の一定割合(50%)を超える部分の金額につき当期の損金の額に算入しないこととする制度である(※関連者とは、直接・間接の持分割合50%以上又は実質支配・被支配関係にある者)。もっとも、現行の過大支払利子税制では、利子等の受領者側でわが国の法人税の課税所得に算入されるもの等を除くとされているため、国内の関連者・非関連者との取引における支払利子は対象外とされている。また、ベースとなる調整所得金額についても受取配当益金不算入額が含まれている。
この点、BEPS行動4の最終報告書では、①BEPSの勧告では損金不算入となる利子の範囲が国外関連者に対する利子のみならず、国外の非関連者及び国内の関連者・非関連者に対する利子についても対象となること、②固定比率の水準が異なること(BEPS行動4ではEBITDAの10%~30%とされている)、③過大支払利子税制の調整所得金額に対応する税務上のEBITDAについて、受取配当益金不算入額が含まれないこととされていた。
このBEPS行動4の考え方をそのまま採用した場合、国外の非関連者及び国内の関連者・非関連者に対する利子についても対象となることから、国内の銀行からの借入の利子も対象となり、借入の縮小による金融市場の弱体化につながりうること、また、税務上のEBITDAについて、受取配当益金不算入額が含まれないことから、海外からの受取配当が多い業種や単体納税の持株会社などでは、多大な損金不算入額が生じるおそれがあった。
このため、今回の大綱では、全ての利子を対象とするのではなく、主に国内の非関連者及び関連者については対象外とするかたちで見直しを行うこととした。具体的には、借入等に関する利子等について、①支払利子等を受ける側において、受け取った利子が日本の課税所得に含まれる支払利子、②一定の公共法人に対する支払利子、③一定の債券現先取引等に係る支払利子の額は、対象となる支払利子から除かれることとなった。また、債券に関する利子等についても、(a)支払いの際に源泉徴収が行われる、又は債券利子を受ける側において、受け取った債券利子が日本の課税所得に含まれる場合の債券の支払利子の額、もしくは、(b)国内で発行された債券について、特定債券利子等の額の95%に相当する金額・国外で発行された債券について、特定債券利子等の額の25%に相当する金額のうち、(a)(b)のいずれかを控除できるとしている。(b)については、債券の場合、保有者の属性を特定することが容易ではないため、その点に配慮したものと考えられる。ベースとなる調整所得金額については現行と異なり、受取配当益金不算入額が除外されている。また、損金不算入額については、現行の調整所得金額の50%から、調整所得金額の20%と要件がかなり厳しくなっている。BEPSプロジェクトの最終報告書において、EBITDAの10%~30%という水準を決定する際には、他の要件とのバランスを踏まえて決定することが求められていた。20%となった背景には、欧米などでは、全ての利子を対象としてEBITDAの30%を基準として設定している国が多いため、それらの国の制度設計を踏まえたものと思われる。なお、この過大支払利子税制には適用免除基準が設けられており、対象となる純支払利子の額が2,000万円以下(現行:1,000万円以下)となる場合には、制度を適用しない。この過大支払利子税制の見直しは、2020年度4月以降に開始する事業年度から適用することとなる。
2.移転価格税制における所得相応性基準の導入 移転価格税制において、開発途上の無形資産を譲渡した場合、類似の取引が無い等の理由により、独立企業間価格を算定することは容易ではない。このため、開発途上だが今後多額の利益を生みそうな無形資産などについて、十分にその価値が生じていない段階で低課税国等へ移転し、租税回避を図ることが可能となっていた。このようなスキームを防止するため、BEPS行動8では、評価困難な無形資産(HTVI:Hard-to-Value Intangibles)について、税務当局が事後の実現値に基づき当初の譲渡価格を調整することを認めるアプローチ(所得相応性基準・HTVIアプローチ)を導入することを勧告している(図9参照)。
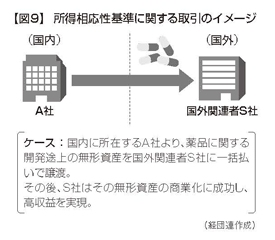
このOECDの勧告を踏まえ、今般、日本でも、所得相応性基準及び所得相応性基準を適用する際に前提となるディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)を導入することとした。
第一に、独立企業間価格の算定方法として、比較対象取引が特定できない無形資産取引等に対し、DCF法を認めることとした。また、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類の提出がない場合の推定課税の価格算定方法としても、DCF法により算定した金額を認めることとする。
第二に、「特定無形資産」に係る取引に関し、独立企業間価格の算定の基礎となる予測と結果が20%を超える範囲で相違した場合に、最適な価格算定方法により算定した金額を独立企業間価格とみなして更正等を行うことができるとする所得相応性基準を導入するとしている。
上記の「特定無形資産」とは、①独自性があり、重要な価値を有するもの、②予測収益の額を基礎として独立企業間価格を算定するもの、③独立企業間価格の算定の基礎となる予測が不確実であると認められるものという3つの要件を全て満たすものとしている。
所得相応性基準については、適用免除要件も定められている。一定期間内に、①(a)特定無形資産取引に係る独立企業間価格の算定の基礎となる予測の詳細を記載した書類、及び(b)当該予測と結果が相違する原因となった事由が災害その他これに類するものであり取引時においてその発生を予測することが困難であったこと、又は取引において当該事由の発生の可能性を適切に勘案して独立企業間価格を算定していたことを証する書類、もしくは、②特定無形資産の使用により生じる非関連者収入が、5年の間に予測収益等の額と実際収益等の額の相違が20%を超えていないことを証する書類を提出すれば、所得相応性基準は適用されないこととなる。
なお、このDCF法及び所得相応性基準の導入とあわせて、移転価格税制に係る法人税の更正期間及び更正の請求期間等を現行の6年から7年に延長することとなる。この更正期間等の延長は、DCF法及び所得相応性基準にかかるものに限られず、移転価格税制に係る内容全てに及ぶため、注意が必要である。
移転価格税制の見直しは、2020年度4月以降に開始する事業年度分の法人税及び2021年度以降の所得税について適用する。
所得相応性基準については、後知恵課税にあたるとして、経済界などから制度の導入を慎重に検討すべきという声が出されていた。今後、法令・通達・Q&Aなどで、どのような場合に所得相応性基準の発動が検討されるのか等、事業者の事務負担の軽減の観点も踏まえつつ、詳細なガイダンスを示すことが重要となるだろう。
3.外国子会社合算税制におけるペーパーカンパニーの要件等の見直し 外国子会社合算税制は平成29年度税制改正で、外国子会社の経済実体・所得の内容に即して、実体がない受動的所得は合算対象とする一方、実体ある事業からの所得については、外国子会社の税負担率に関わらず合算対象外とする方向で抜本的な見直しがなされた。この見直しのなかで、特に、租税回避のおそれが強い、①事業所等の固定施設を持たず、かつ、その本店所在地国において事業の管理、支配、運営を自ら行っていない会社(ペーパーカンパニー)、②総資産の額に対する受動的所得の合計額の割合が30%を超える企業で、総資産の額に対する金融資産等の割合が50%を超える会社(事実上のキャッシュボックス)、③租税に関する情報の交換に非協力的な国(ブラックリスト国)に所在する会社という3つの類型を特定外国関係会社として会社単位の合算課税の対象とした。平成31年度税制改正大綱では、この中で主にペーパーカンパニーの範囲が見直しの対象となった。
2017年12月に、米国におけるトランプ政権下での税制改革(「Tax Cut and Jobs Act 2017」)により連邦法人税率が35%から21%に引き下げられた。これにより、米国に所在する実態のない子会社が日本のCFC税制により、ペーパーカンパニー等にあたるとして合算課税の対象となるおそれが生じることとなった。
このため、平成31年度税制改正大綱では、米国等において実態あるビジネスを行っているかどうかという観点及び租税回避に資する類型を除外するという観点から、「イ 持株会社である一定の外国関係会社」、「ロ 不動産保有に係る一定の外国関係会社」、「ハ 資源開発等プロジェクトに係る一定の外国関係会社」という3つの類型について合算課税の対象外とすることとした。
「イ 持株会社である一定の外国関係会社」の類型については、主に米国等で、日本法人が構成員課税の事業体を有している場合に、米国から日本法人に対して直接課税が及ぶことを避けるために、米国で申告納税を行うために設立するブロッカーコーポレーションや倒産隔離の目的、他から出資を受ける場合に設置される中間持株会社が念頭に置かれている。「ロ 不動産保有に係る一定の外国関係会社」に関しては、米国などでは、不動産の保有を目的とした会社等を設けるなどして、不動産の流動性を高める取引慣行があり、この不動産の保有に係る会社については実態がないことが多く、ペーパーカンパニーとみなされる可能性があった。このため、この不動産保有に係る一定の外国関係会社についても、合算課税の対象外とすることとした。あわせて、「ハ 資源開発等プロジェクトに係る一定の外国関係会社」についても、共同出資等により中間持株会社を設置することに対応するとともに、資源開発という特性から事業規模が大きくなり、個々の企業の出資比率等は小さくなる一方、資金調達手段も多様化することが通常となることから、資金提供などの一定の関係もカバーするかたちで、合算課税の対象外とすることとした。
それぞれの類型の詳細な要件は以下の表5のとおりとなる。
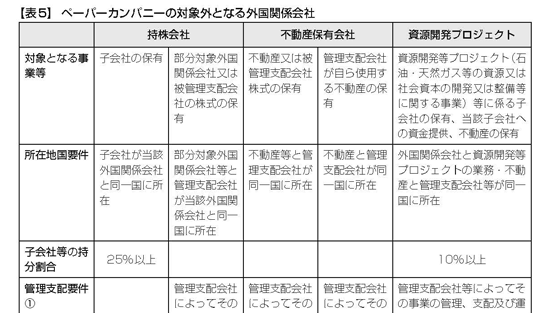
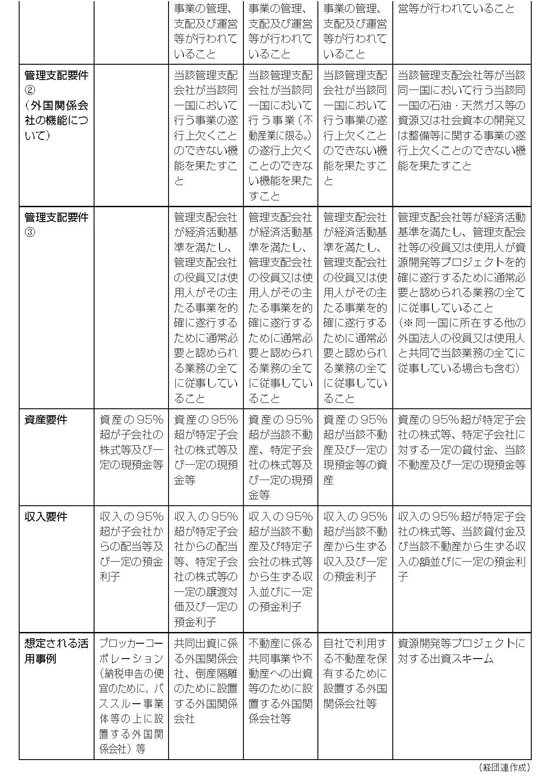
Ⅴ その他、主要項目等
1.情報照会手続の整備 情報照会手続の整備については、2018年に政府税制調査会において具体的に検討がなされている。政府税制調査会において「納税環境整備に関する専門家会合(座長:岡村忠生京都大学教授)」が設置され、仮想通貨取引、シェアリングエコノミー、金地金取引を取り上げて、税務当局による必要な情報の取得の観点から検討を行っている。この中では、「仮想通貨取引やシェアリングエコノミーについては、……既存の枠組みでは、高額・悪質な無申告者等を特定することも困難」、「仲介者(仮想通貨交換業者、プラットフォーム事業者等)が、個々の納税者の取引に係る情報を一定程度保有しているという特徴があることから、当該仲介者に対して法定調書の提出を求めることについて検討してはどうか」、「高額・悪質な無申告者等に対応するため特に必要な場合に限って、事業者が通常保有する情報の範囲内で照会を行うということも考えられる」などの指摘もなされていた。
今回の平成31年度税制改正大綱は、これらの問題意識を踏まえたものと考えられる。第一に、任意の協力要請について法制化し、調査に係る権限を明確化して、事業者の協力を得やすくするとしている。
第二に、仮想通貨取引や宿泊サービスの提供などのシェアリングエコノミーに関する特定取引等に関与し、その取引に係る課税標準等が年間1,000万円を超える者(特定取引者)を対象として、限定的な場合において(①特定取引者の国税について、更正決定すべきこととなる相当程度の可能性があり、かつ、②この報告の求めによらなければ、特定取引者を特定することが困難である場合)、事業者に対してその氏名(名称)、住所(居所)、個人番号(法人番号)に限って報告を求めることができる旨の規定を整備する。なお、拒否・虚偽報告については罰則が設けられる。
Ⅵ 2019年度以降の税制改正の議論の見通し
所得課税の関係では、大綱の検討事項にあるとおり、年金課税について、「世代間及び世代内の公平性の確保や、老後を保障する公的年金、公的年金を補完する企業年金を始めとした各種年金制度間のバランス、貯蓄・投資商品に対する課税との関連、給与課税等とのバランス等に留意するとともに、平成30年度税制改正の公的年金等控除の見直しの考え方や年金制度改革の方向性も踏まえつつ、拠出・運用・給付を通じて課税のあり方を総合的に検討する」としている。
政府税制調査会でもこの点は議論されている。2015年11月にとりまとめられた「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理」では、個人の働き方やライフコースによって、受けられる税制上の支援の大きさが異なっていることから、「個人の働き方やライフコースに影響されない公平な制度の構築を念頭に、幅広く検討」すること、「その際、拠出・運用・給付の各段階を通じた体系的な課税のあり方について、公平な税負担の確保や、高齢化の進展、貯蓄率の低下等の構造変化を踏まえて検討」すること、「給与・退職一時金・年金給付の間の税負担のバランスについて、働き方やライフコースの多様化を踏まえて検討」するというとりまとめがなされている。
政府税制調査会では、次頁の図10のとおり、老後を保障する各種年金制度や貯蓄・投資商品に関する資料が提出されているが、今後、これらの制度について、政府税制調査会等でさらに議論が行われる可能性がある。
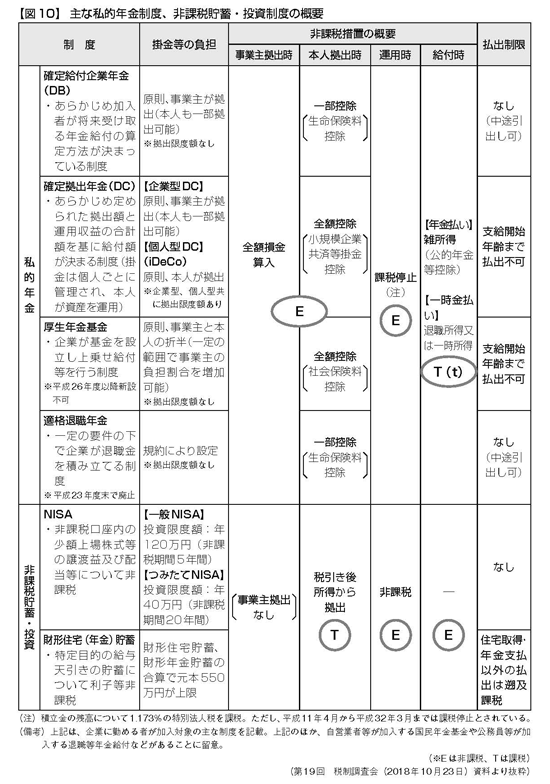
法人課税においては、連結納税制度について見直しが検討される可能性がある。現在、政府税制調査会において、「連結納税制度に関する専門家会合(座長:田近栄治成城大学経済学部特任教授)」が設置されており、連結納税制度を取り巻く状況の変化を踏まえた現状の課題や必要な見直しについて議論することとされている。2018年11月17日に開催された第1回会合の財務省提出資料では、「検討に当たっての視点」として、「完全支配関係にある企業グループ内における損益通算を可能とする基本的な枠組みは維持しつつ、制度の簡素化や中立性・公平性の観点から……検討を行う」としており、事務負担の軽減を図る観点から、「連結グループを一つの納税単位とする現行の制度の在り方(申告・納付の方法)や、連結固有のグループ調整計算の要否、修正や更正の場合の企業や課税庁の事務負担の軽減等について検討する」ことが示されている。連結納税を現在適用している企業及び今後適用を予定・検討している企業については、今後、専門家会合における議論の状況によっては、実務に影響が生じる可能性がある。
国際課税の分野では、2019年は電子経済への課税のあり方に関する議論が本格化する見込みである。2018年3月に公表されたOECDの電子経済に対する課税に関する中間報告書「Tax Challenges Arising from Digitalisation-Interim Report 2018」では、今後の検討の方向性として、①デジタル企業のみを対象として課税を考える案、②デジタル化は社会全体を変えるものであり、国際課税の枠組み全体を議論すべきとする案、③見直しは時期尚早とする案という3つの考え方が示されていたが、最近の海外メディア等の報道によれば、アメリカが②の考え方を取りつつあり、デジタル化に止まらず、国際課税全体の枠組みも含めて、検討を行う方向性を打ち出しつつある。源泉地国における課税を広く認めるなどの方向性で検討が進めば、デジタル化と直接関係しないと考えている日本企業にとっても、新興国等の市場国における課税リスクが増大する可能性がある。2019年は日本がG20の議長国となるため、日本がこの議論を主導する役割を担うことになる。国際的な議論の動向も留意すべきである。
この他、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する更なる対応について、平成31年度与党税制改正大綱の検討事項で「更なる税制上の対応の要否等について、平成32年度税制改正において検討し、結論を得る」として整理されている。
また、現在、電気供給業及び大手のガス供給業については、収入金額による外形標準課税が行われている。両業界については、すでに小売の全面自由化が実施されており、また、電気供給業については2020年に法的分離が予定されている。このため、収入金額による課税から、付加価値割及び資本金等の額による外形標準課税へと移行していくことが検討対象となるだろう。
平成31年度税制改正について
一般社団法人日本経済団体連合会 経済基盤本部 神谷智彦
はじめに
平成31年度税制改正では、消費税率の引き上げに伴う需要平準化対策の観点から、自動車関係諸税・住宅税制の見直しが行われるとともに、研究開発税制の改組・拡充や地方法人課税、中小企業税制、役員給与制度の見直し、国際課税などについて重要な改正がなされた。以下、主要な改正点について整理したい。
なお、本記事の内容は、現在公表されている平成31年度与党税制改正大綱や各省庁の税制改正に関する解説資料、政府税制調査会資料等に基づいて作成している。各省庁の資料等の作成・公表に感謝するとともに、今後の法案の策定・審議により、内容に変更が生じうることにご留意いただきたい。また、内容については、すべて筆者個人の見解であり、組織を代表したものではない。
Ⅰ 消費税率の引き上げに伴う需要平準化対策
2019年における税制の最も大きなテーマは、消費税率の引き上げである。2019年10月の消費税率の8%から10%への引き上げについては、前回の5%から8%への引き上げの際に、需要の反動減が大きく生じたことを踏まえ、政府として、需要平準化のための対策を行うことを2018年の前半ごろから検討していた。「経済財政運営と改革の基本方針2018(以下、骨太の方針2018)」(2018年6月15日閣議決定)において、「2019年10月1日における消費税率の引上げに向けては、消費税率引上げによる駆け込み需要・反動減といった経済の振れをコントロールし、需要変動の平準化、ひいては景気変動の安定化に万全を期す」ことが明記され、具体的な方策として、消費税率引上げ分の使い道の見直し、軽減税率制度の実施、転嫁対策の徹底に加え、商店街の活性化、中小企業・小規模事業者のIT・決済端末の導入やポイント制・キャッシュレス決済の普及・促進や自動車や住宅などの購入支援に係る措置を検討するとされていた。
平成31年度税制改正では、これらの骨太の方針の記述を踏まえ、自動車関係諸税や住宅税制について幅広い見直し・制度の拡充が行われた。
(1)自動車関係諸税 自動車関係諸税については、消費税率10%への引上げにあわせて、自動車の保有に係る税負担を恒久的に引き下げるとともに、環境性能割について、時限的な軽減措置を設ける。
具体的には、保有に係る税である自動車税について、創設後約70年で初めて恒久減税を行うこととなった。引き下げ幅は1,000円~4,500円となる。なお、消費税率の引き上げに伴う需要平準化という観点から、引き下げの対象となる車は消費税率引き上げ後に、新車新規登録を受けたものに限られる(引き下げ幅について、図1参照)。
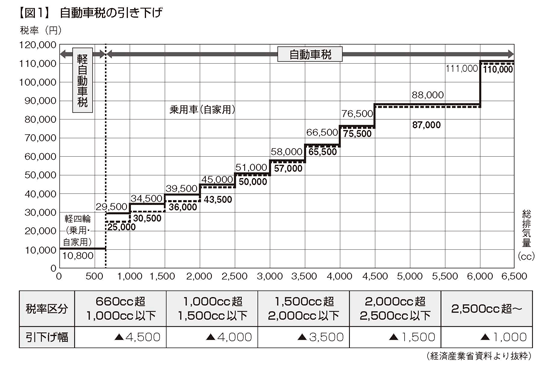
他方、これらの税収減に対応するために、エコカー減税の見直し、グリーン化特例の重点化、環境性能割の見直しにより財源を確保することとなった。
エコカー減税については、2020年基準+30%達成車~2020年基準+10%達成車について、2019年以降、軽減の割合を見直すこととする。現行でエコカー減税により自動車取得税を80%~40%軽減されている車については、2019年4月1日から9月30日にかけて50%~25%にまで軽減の幅が縮小されることになる。なお、エコカー減税の制度は2019年9月末で廃止となる。また、自動車重量税については、現在75%~50%軽減されている車について、50%~25%にまで軽減の幅を縮小する。
自動車取得税に代わって導入される自動車税の環境性能割の税率については、表1のとおり燃費性能に関する要件を引き上げることとした。
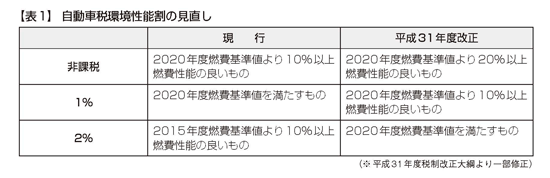
もっとも、2019年10月1日から1年間の間に取得した自家用乗用車に係る環境性能割については、税率1%分を軽減する特例措置が講じられる。このため、普通自動車では、消費税率引き上げ後1年間は環境性能割の引き上げの影響は生じないこととなる。また、軽自動車では、上記の環境性能割の引き上げは行われない一方、2019年10月1日から1年間の間に取得した自家用乗用車に係る環境性能割については、税率1%の軽減措置が講じられることとなる。
グリーン化特例については、2021年3月末まで現行制度が単純延長されるが、2021年4月以降は、適用対象が電気自動車等(電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車、クリーンディーゼル車)に限定される。
これらの自動車関係諸税の見直しの全体像は図2のとおりである。
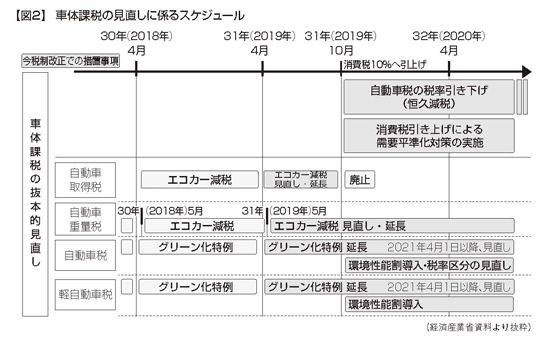
なお、自動車関係諸税については、中長期的な検討の方向性が、大綱の検討事項に以下のとおり示されている。
| 自動車関係諸税については、技術革新や保有から利用への変化等の自動車を取り巻く環境変化の動向、環境負荷の低減に対する要請の高まり等を踏まえつつ、国・地方を通じた財源を安定的に確保していくことを前提に、その課税のあり方について、中長期的な視点に立って検討を行う。 |
(2)住宅関係諸税 住宅に関する税制措置についても、需要変動の平準化のため、措置が講じられた。消費税率が10%となる住宅の取得に関し、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例(住宅ローン減税)を3年間延長することとした。この延長は単純延長ではなく、当該年度における控除の限度額は、イ)住宅借入金等の年末残高×1%と、ロ)建物購入金額(消費税額分を除く)×2%÷3のいずれか少ない金額となる。なお、一般住宅の住宅借入金等の年末残高及び建物購入金額(消費税額分を除く)の限度額は4,000万円、認定住宅等のそれぞれの限度は5,000万円である。この住宅ローン減税の特例は2019年10月1日から2020年12月31日までの間に、対象の住宅を本人の居住の用に供した場合について適用する。
(3)その他、消費税率の引き上げに伴う予算措置等 上記の自動車・住宅に関する税制措置の他、需要変動の平準化に対応する観点から様々な予算措置が講じられる見込みである。具体的には、低所得者及び子育て世帯(0歳児~2歳児)向けのプレミアム付商品券の発行・販売(使用は、2019年10月から2020年3月まで)や中小・小規模事業者に対するキャッシュレス決済手段を用いた場合のポイント還元支援(2019年10月から2020年6月まで)、マイナンバーを活用した自治体ポイントの付与(2020年7月以降)、住宅に係るすまい給付金の拡充(対象となる所得階層を収入目安510万円以下から775万円以下に拡充し、給付額も最大30万円から50万円に引上げ(2019年10月から2021年12月末まで))、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事・介護負担の軽減に資する新築・リフォームに対し、様々な商品等と交換できるポイントを発行する次世代住宅ポイント制度(2019年10月から2020年3月末まで)等の措置を行うこととしている。
これらの消費税率の引き上げに伴う対策のパッケージの全体像は前頁の表2のとおりである。
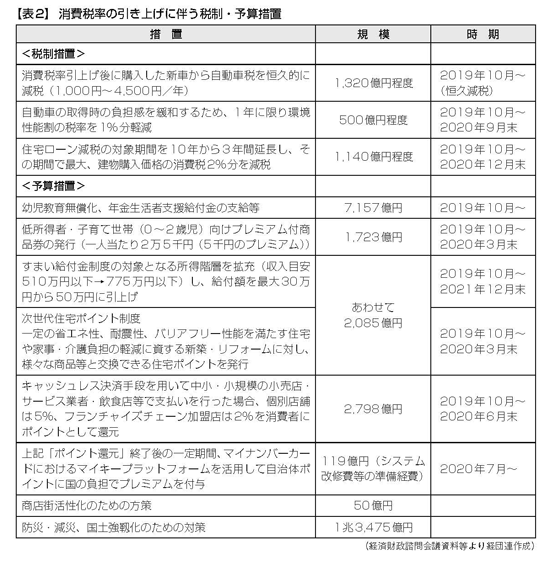
Ⅱ 法人課税
1.研究開発税制の改組・拡充 研究開発税制については、研究開発投資の増加インセンティブを強化する観点から見直しが行われた。研究開発税制の見直しのポイントは以下の表3のとおりである。
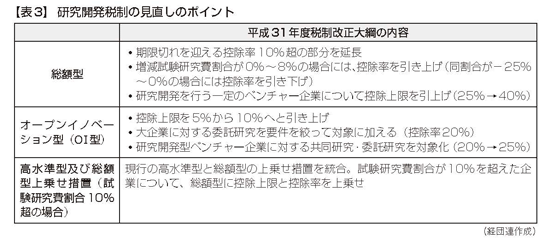
(1)総額型 研究開発税制の総額型については平成29年度税制改正により、増加型が取り込まれ、試験研究費の増減(増減試験研究費割合)に対応して、控除率が増減する制度となっていた。この点、平成31年度税制改正大綱では、「骨太の方針2018」及び「未来投資戦略2018」(2018年6月15日閣議決定)で掲げられている「2020年度までに、官民合わせた研究開発投資をGDP比4パーセント以上にする」という目標を達成すべく、目標から逆算した研究開発費が年8%増となる水準を基点として、より試験研究費の増加インセンティブを強化する観点から、控除率の増減に係るグラフの傾きを大きくすることとした。グラフの概要は図3のとおりである。なお、控除率10%超の場合については、2年間の適用期限が設けられている。
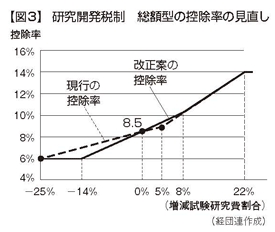
増減試験研究費割合と控除率の計算は上記の表4の式により求められることになる。
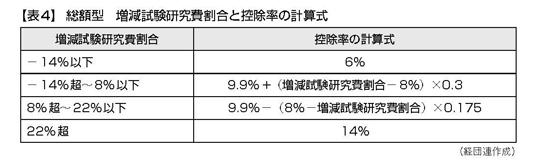
上記の改正により、総額型では控除上限(調整前法人税額の25%)に達していない企業においては、増減試験研究費割合が増減なし~8%増加している場合は減税となる一方、-25%~増減なしの場合は、税負担が増えることとなる。
また、「研究開発を行う一定のベンチャー企業」については、総額型の控除上限が40%となる。「研究開発を行う一定のベンチャー企業」とは、「設立後10年以内の法人のうち、当期において翌期繰越欠損金額を有するもの(大企業の子会社等を除く)」とされている。この「研究開発を行う一定のベンチャー企業」が中小企業の場合、基本的に翌期繰越欠損金額は全額控除できることから、活用が想定されるのは、資本金1億円超の大法人に成長したベンチャー企業となる。
(2)オープンイノベーション型(OI型) オープンイノベーション型(特別試験研究費の額に係る税額控除制度)についても今般の税制改正で拡充されることとなった。OI型の控除上限を現行の法人税額の5%から10%へと引き上げるとともに、対象を大きく拡充することとした(図4参照)。対象については、これまで認められていなかった大企業に対する委託試験研究について、a)民法上の委任契約によって委託される委託試験研究で、b)委託法人の基礎研究又は応用研究にかかる試験研究であること、もしくは、受託者の知的財産権等を利用した試験研究であること、c)委任契約等においてb)の事項が定められていることという要件のもと、大企業に対する委託試験研究を認めることとなった。
「研究開発型のベンチャー企業」との共同研究及び「研究開発型のベンチャー企業」への委託研究については、税額控除率を25%とするかたちで認めることとした。対象となる「研究開発型のベンチャー企業」は、前述の総額型における「研究開発を行う一定のベンチャー企業」とは要件が異なっており、「産業競争力強化法の新事業開拓事業者でその発行する株式の全部又は一部が同法の認定ベンチャーファンドの組合財産であるものその他これに準ずるものをいう」とされ、基本的にベンチャーファンドの投資対象となる新興企業(大企業子会社や上場企業を除く)が対象となる見込みである。なお、「研究開発型のベンチャー企業」への委託研究については、大企業に対する委託研究と同様に、前述のa)~c)の要件を満たすことが必要となる。
また、大学との共同研究に係るOI型の適用に関しては、これまでも、リサーチ・アドミニストレーターなどの研究開発のプロジェクトマネジメント業務等を担う者の人件費を対象とすることが否定されてきたわけではないが、今回の税制改正大綱において、それらリサーチ・アドミニストレーターの人件費についても、OI型の適用対象となることが明示されている。
(3)高水準型・総額型上乗せ措置 高水準型及び試験研究費割合が10%超の場合の総額型の上乗せ措置についても、見直しが行われることとなった。平成29年度税制改正により、高水準型に加えて、試験研究費割合が10%超の場合の総額型の上乗せ措置が創設され、試験研究費割合が10%超の場合の措置が並存する状況となっていた。今般の平成31年度税制改正では、この両方の措置を基本的に総額型の上乗せ措置に一本化し、制度を拡充することとした。具体的には、現行の総額型の上乗せ措置の控除上限の上乗せ措置(控除上限を「25%+(試験研究費割合-10%)×2」とする)を引き続き維持したうえで、新たに控除率を上乗せする。上乗せされた控除率は、「通常の総額型の控除率+((試験研究費割合-10%)×0.5)×通常の総額型の控除率」となる。なお、「試験研究費割合-10%」は10%が上限となる。
従来の試験研究費割合が10%超の場合の総額型の上乗せ措置では、控除上限の引き上げという措置のみであったため、総額型の控除上限に達していない場合には、控除上限の引き上げによるメリットが生じていなかった。今般の見直しにより、控除率を引き上げるという措置が整備され、これらの総額型の控除上限に達していない場合であっても、メリットが生じることとなった。
(4)中小企業に係る研究開発税制(中小企業技術基盤強化税制) 中小企業に対する研究開発税制についても大企業と同じように、総額型やOI型の見直しに対応するかたちで増減試験研究費割合が8%となるところがグラフの傾きの起点となるよう見直しがなされることとなった(図5参照)。
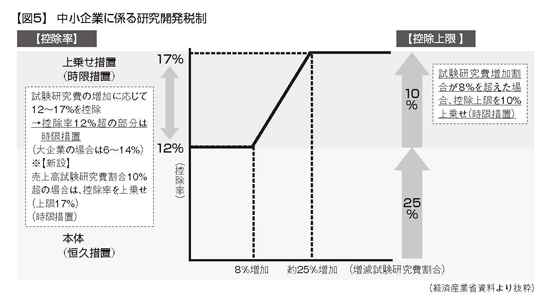
以上が平成31年度税制改正の研究開発税制の見直しの概要となる。
イノベーションにつながる研究開発をより一層促進していくためには、研究開発税制の存在が引き続き重要となる。近年、AIやビッグデータ、IoTなどの技術が進展し、社会全体に組み込まれている。このようなデジタル革新と多様な人々の想像・創造力の融合によって社会の課題を解決し、価値を創造する社会を、「Society5.0」として、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く第5段階の新たな「創造社会」として位置づけている。今後の研究開発税制のあり方を考えるうえでも、このような流れを踏まえ、「Society 5.0」の実現に資するかたちで引き続き制度を検討することが求められる。
オープンイノベーション型については今般、控除上限が拡充されたが、大学などと共同研究を進めるうえで、書面に記載すべき項目などの手続に関する要件がネックとなって、活用が十分に進んでいないという側面もある。拡充された控除上限を十分に活かすためにも、引き続き検討を進めることが必要となるだろう。また、Society 5.0を支えるITサービス等の開発・活用を進める観点から、平成29年度税制改正で整備されたサービス開発に関する研究開発税制についても、より幅広い産業や様々な局面で活用しやすくなるよう要件の見直しを検討していくことが重要と考える。
2.中小企業関係税制等 中小企業の関係では、研究開発税制に加えて、いくつかの税制措置が講じられることとなった。
(1)個人版事業承継税制の創設 平成30年度税制改正では、法人に係る事業承継税制について大きく拡充する措置が講じられたが、平成31年度税制改正では、個人版の事業承継税制を創設することとした(図6参照)。
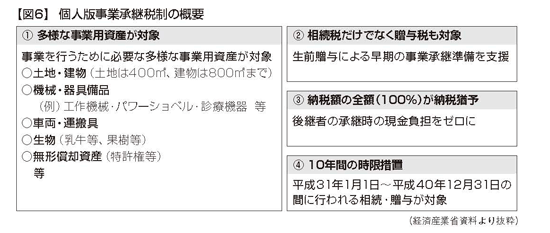
個人版の事業承継税制では、10年間に限って、土地・建物や器具・備品など、様々な事業用資産に関する相続税・贈与税を100%納税猶予する措置を設ける。なお、この制度を活用するためには、①経営承継円滑化法に基づく認定とともに、②2019年度から5年以内に、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が示された承継計画を作成し、都道府県に提出する必要がある。また、この制度については、現行の事業用小規模宅地特例との選択により適用することとなる。
(2) 中小企業に係る投資促進税制等 中小企業者等に係る軽減税率の特例、中小企業投資促進税制、中小企業経営強化税制については、適用期限が2年延長される。商業・サービス業・農林水産業活性化税制については、売上高又は営業利益が年間で2%以上の向上する見込みがあるという要件が追加されることとなった。
また、中小企業の事前防災の対策を促進する観点から、事業継続力強化計画(仮称)の認定を受けた中小企業が、対象となる防災・減災設備を取得した場合には、20%の特別償却ができる措置を創設することとした(図7参照)。
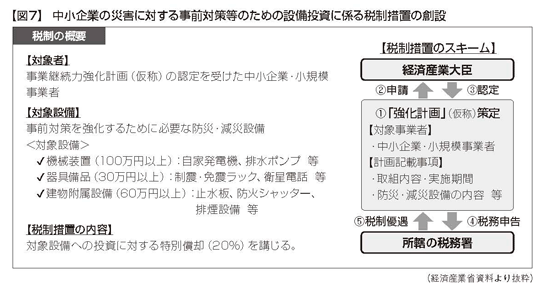
地域未来投資促進税制に関しては、制度を2年間延長するとともに、直近の事業年度の付加価値増加率が8%を超える場合には、対象設備に係る投資について50%の特別償却(現行:40%)もしくは、5%の税額控除(現行:4%)を認めることとした。
3.役員給与税制・組織再編税制の見直し
(1)役員給与税制の見直し 役員報酬制度については、平成29年度税制改正で業績連動給与の算定指標の範囲拡大など拡充が行われた。一方で、支給にかかる適正手続要件に関しては、とりわけ、指名委員会等設置会社における報酬委員会について、「業務執行役員又はその業務執行役員と一定の特殊の関係のある者がその委員になっているものを除く」とされていることから、報酬委員会の構成員が一人でも業務執行役員又はその業務執行役員と一定の特殊の関係のある者(以下、業務執行役員等)である場合には、業績連動報酬の損金算入を行うことができなくなっていた。
このため、平成31年度税制改正では、業績連動報酬制度の見直しがなされることとなった。大綱では、「報酬委員会等を設置する法人の業務執行役員が報酬委員会等の委員でないこととの要件を除外する」としており、報酬委員会の構成員が業務執行役員等であるかどうかにより外形的に判断する要件は見直されることになる。一方で、「業務執行役員が自己の業績連動給与の決定等に係る決議に参加していないこととの要件を加える」、及び「報酬委員会等の委員の過半数が独立社外役員であること及び委員である独立社外役員の全てが業績連動給与の決定に賛成している」という2つの要件を満たすことが必要とされた。業績連動給与に係る決議の内容に着目し、独立社外役員がその内容をチェックして決定するという昨今のコーポレートガバナンスの流れを踏まえた見直しと評価できる。
他方、監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社については、役員給与の損金算入要件について、要件を絞ることで適正化がなされた。現行の規定で、監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社にかかる役員給与に関し、①報酬諮問委員会に対する諮問を経た手続の他、②株主総会における決議や、③監査役の過半数が適正であると認められる旨を記載した書面を提出した場合における取締役会の決定(監査役会設置会社の場合)及び監査等委員である取締役の過半数が当該決議に賛成している場合における取締役会の決定(監査等委員会設置会社の場合)があった場合においても、業績連動報酬の損金算入が認められている。この点、コーポレートガバナンスコード改訂版で監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社においても、「独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置する」ことが推奨されていることを踏まえ、監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社においても、報酬諮問委員会等を通じた役員報酬の決定の適正化を担保すべく、①の報酬諮問委員会の手続について、上記の指名委員会等設置会社の報酬委員会の場合の手続と同様の要件となるよう改正するとともに、③の適正と認められる書面の提出による手続については、廃止することとした(図8参照)。このため、③の書面による手続をとっている企業にあたっては、手続の見直しが必要となる。
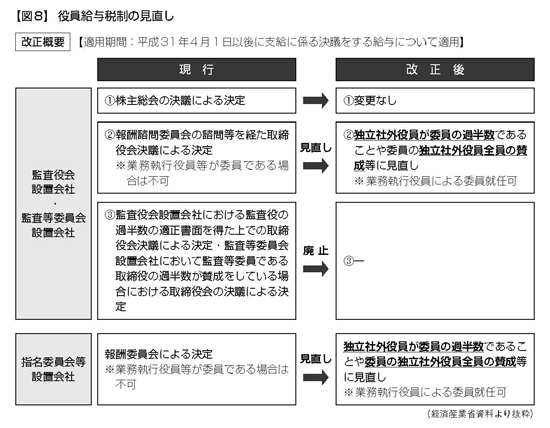
(2)組織再編税制の見直し 組織再編税制に関しては、親会社が子会社を完全子会社化した後に行う逆さ合併について、逆さ合併を続けて行うことが見込まれている場合には、適格組織再編の対象とする。また、親会社の株式を対価とした組織再編について、現状では、直接の親会社の株式を対価とする場合のみが、適格組織再編とされているが、間接保有の完全親会社の株式を組織再編の対価として交付する場合についても適格組織再編の対象とするよう見直しを行う。
Ⅲ 地方税
1.地方法人課税の偏在是正 地方法人課税の見直しについては、平成30年度与党税制改正大綱において「特に偏在度の高い地方法人課税における税源の偏在を是正する新たな措置について、消費税率10%段階において地方法人特別税・譲与税が廃止され法人事業税に復元されること等も踏まえて検討し、平成31年度税制改正において結論を得る」とされていた。
この大綱の記載を踏まえ、総務省地方財政審議会において「地方法人課税に関する検討会(座長:堀場勇夫青山学院大学名誉教授)」が設置され、7回の会合を経て、2018年11月に報告書が公表された。報告書の中では、新しい制度を設計する際には、①法人事業税を対象とすること、②具体的な方策については、譲与税化により実効性のある偏在是正措置とすることができる場合には、譲与税化を基本として考えること、③十分な偏在是正効果を得られない場合には、交付税原資化も視野に入れて検討すること、④譲与税化の場合、偏在是正という趣旨・目的に沿って、譲与基準を「人口」とすることを基本とすること等としていた。
平成31年度税制改正では、この報告書の内容も踏まえ、地方法人課税について、地方における法人関係税収の偏在を是正する観点から見直しがなされた。現在の地方法人課税の税収は付加価値の総計である県内総生産の分布状況と比較して、大都市部に集中していることから、この偏在を是正すべく、特別法人事業税(仮称)及び特別法人事業税(仮称)という新たな税制措置を創設することとした。制度の概要は以下のとおりである。
特別法人事業税(仮称) 消費税率10%段階において復元後の法人事業税(所得割・収入割)の一部(法人事業税の約3割)を分離し、特別法人事業税(仮称)(国税)とする。
課税標準:法人事業税(所得割・収入割)の税額(標準税率分)
賦課徴収:都道府県(法人事業税と併せて実施)
適用期日:2019年10月1日以後に開始する事業年度から適用
特別法人事業譲与税(仮称)
譲与額:特別法人事業税(仮称)の税収(全額)を都道府県に譲与
譲与基準等:「人口」を譲与基準とし、不交付団体に譲与制限の仕組み(25%までを上限として保障)を設ける
譲与開始時期:2020年度
2.ふるさと納税制度の見直し ふるさと納税制度について、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような地方自治体に対しては、ふるさと納税の対象外にすることができるよう、制度の見直しを行うこととした。
具体的には、総務大臣は、地方財政審議会の意見を聴いた上で、寄附金の募集を適正に実施し、①返礼品の返礼割合は3割以下、かつ、②返礼品を地場産品とする自治体のみをふるさと納税の控除の対象となる自治体として指定できることとした。
Ⅳ 国際課税
平成29年度与党税制改正大綱及び平成30年度与党税制改正大綱で中長期的に取り組むべき事項とされたOECD/G20のBEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトの残された課題(所得相応性基準、過大支払利子税制、義務的情報開示)のうち、過大支払利子税制及び所得相応性基準について、平成31年度税制改正で見直しがなされた。また、外国子会社合算税制(CFC税制)についても、米国税制改正等を踏まえ、ペーパーカンパニーの要件等が見直されることとなった。
1.過大支払利子税制の見直し 現行の過大支払利子税制については、関連者への純支払利子等の額のうち調整所得金額の一定割合(50%)を超える部分の金額につき当期の損金の額に算入しないこととする制度である(※関連者とは、直接・間接の持分割合50%以上又は実質支配・被支配関係にある者)。もっとも、現行の過大支払利子税制では、利子等の受領者側でわが国の法人税の課税所得に算入されるもの等を除くとされているため、国内の関連者・非関連者との取引における支払利子は対象外とされている。また、ベースとなる調整所得金額についても受取配当益金不算入額が含まれている。
この点、BEPS行動4の最終報告書では、①BEPSの勧告では損金不算入となる利子の範囲が国外関連者に対する利子のみならず、国外の非関連者及び国内の関連者・非関連者に対する利子についても対象となること、②固定比率の水準が異なること(BEPS行動4ではEBITDAの10%~30%とされている)、③過大支払利子税制の調整所得金額に対応する税務上のEBITDAについて、受取配当益金不算入額が含まれないこととされていた。
このBEPS行動4の考え方をそのまま採用した場合、国外の非関連者及び国内の関連者・非関連者に対する利子についても対象となることから、国内の銀行からの借入の利子も対象となり、借入の縮小による金融市場の弱体化につながりうること、また、税務上のEBITDAについて、受取配当益金不算入額が含まれないことから、海外からの受取配当が多い業種や単体納税の持株会社などでは、多大な損金不算入額が生じるおそれがあった。
このため、今回の大綱では、全ての利子を対象とするのではなく、主に国内の非関連者及び関連者については対象外とするかたちで見直しを行うこととした。具体的には、借入等に関する利子等について、①支払利子等を受ける側において、受け取った利子が日本の課税所得に含まれる支払利子、②一定の公共法人に対する支払利子、③一定の債券現先取引等に係る支払利子の額は、対象となる支払利子から除かれることとなった。また、債券に関する利子等についても、(a)支払いの際に源泉徴収が行われる、又は債券利子を受ける側において、受け取った債券利子が日本の課税所得に含まれる場合の債券の支払利子の額、もしくは、(b)国内で発行された債券について、特定債券利子等の額の95%に相当する金額・国外で発行された債券について、特定債券利子等の額の25%に相当する金額のうち、(a)(b)のいずれかを控除できるとしている。(b)については、債券の場合、保有者の属性を特定することが容易ではないため、その点に配慮したものと考えられる。ベースとなる調整所得金額については現行と異なり、受取配当益金不算入額が除外されている。また、損金不算入額については、現行の調整所得金額の50%から、調整所得金額の20%と要件がかなり厳しくなっている。BEPSプロジェクトの最終報告書において、EBITDAの10%~30%という水準を決定する際には、他の要件とのバランスを踏まえて決定することが求められていた。20%となった背景には、欧米などでは、全ての利子を対象としてEBITDAの30%を基準として設定している国が多いため、それらの国の制度設計を踏まえたものと思われる。なお、この過大支払利子税制には適用免除基準が設けられており、対象となる純支払利子の額が2,000万円以下(現行:1,000万円以下)となる場合には、制度を適用しない。この過大支払利子税制の見直しは、2020年度4月以降に開始する事業年度から適用することとなる。
2.移転価格税制における所得相応性基準の導入 移転価格税制において、開発途上の無形資産を譲渡した場合、類似の取引が無い等の理由により、独立企業間価格を算定することは容易ではない。このため、開発途上だが今後多額の利益を生みそうな無形資産などについて、十分にその価値が生じていない段階で低課税国等へ移転し、租税回避を図ることが可能となっていた。このようなスキームを防止するため、BEPS行動8では、評価困難な無形資産(HTVI:Hard-to-Value Intangibles)について、税務当局が事後の実現値に基づき当初の譲渡価格を調整することを認めるアプローチ(所得相応性基準・HTVIアプローチ)を導入することを勧告している(図9参照)。
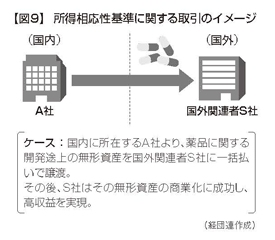
このOECDの勧告を踏まえ、今般、日本でも、所得相応性基準及び所得相応性基準を適用する際に前提となるディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)を導入することとした。
第一に、独立企業間価格の算定方法として、比較対象取引が特定できない無形資産取引等に対し、DCF法を認めることとした。また、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類の提出がない場合の推定課税の価格算定方法としても、DCF法により算定した金額を認めることとする。
第二に、「特定無形資産」に係る取引に関し、独立企業間価格の算定の基礎となる予測と結果が20%を超える範囲で相違した場合に、最適な価格算定方法により算定した金額を独立企業間価格とみなして更正等を行うことができるとする所得相応性基準を導入するとしている。
上記の「特定無形資産」とは、①独自性があり、重要な価値を有するもの、②予測収益の額を基礎として独立企業間価格を算定するもの、③独立企業間価格の算定の基礎となる予測が不確実であると認められるものという3つの要件を全て満たすものとしている。
所得相応性基準については、適用免除要件も定められている。一定期間内に、①(a)特定無形資産取引に係る独立企業間価格の算定の基礎となる予測の詳細を記載した書類、及び(b)当該予測と結果が相違する原因となった事由が災害その他これに類するものであり取引時においてその発生を予測することが困難であったこと、又は取引において当該事由の発生の可能性を適切に勘案して独立企業間価格を算定していたことを証する書類、もしくは、②特定無形資産の使用により生じる非関連者収入が、5年の間に予測収益等の額と実際収益等の額の相違が20%を超えていないことを証する書類を提出すれば、所得相応性基準は適用されないこととなる。
なお、このDCF法及び所得相応性基準の導入とあわせて、移転価格税制に係る法人税の更正期間及び更正の請求期間等を現行の6年から7年に延長することとなる。この更正期間等の延長は、DCF法及び所得相応性基準にかかるものに限られず、移転価格税制に係る内容全てに及ぶため、注意が必要である。
移転価格税制の見直しは、2020年度4月以降に開始する事業年度分の法人税及び2021年度以降の所得税について適用する。
所得相応性基準については、後知恵課税にあたるとして、経済界などから制度の導入を慎重に検討すべきという声が出されていた。今後、法令・通達・Q&Aなどで、どのような場合に所得相応性基準の発動が検討されるのか等、事業者の事務負担の軽減の観点も踏まえつつ、詳細なガイダンスを示すことが重要となるだろう。
3.外国子会社合算税制におけるペーパーカンパニーの要件等の見直し 外国子会社合算税制は平成29年度税制改正で、外国子会社の経済実体・所得の内容に即して、実体がない受動的所得は合算対象とする一方、実体ある事業からの所得については、外国子会社の税負担率に関わらず合算対象外とする方向で抜本的な見直しがなされた。この見直しのなかで、特に、租税回避のおそれが強い、①事業所等の固定施設を持たず、かつ、その本店所在地国において事業の管理、支配、運営を自ら行っていない会社(ペーパーカンパニー)、②総資産の額に対する受動的所得の合計額の割合が30%を超える企業で、総資産の額に対する金融資産等の割合が50%を超える会社(事実上のキャッシュボックス)、③租税に関する情報の交換に非協力的な国(ブラックリスト国)に所在する会社という3つの類型を特定外国関係会社として会社単位の合算課税の対象とした。平成31年度税制改正大綱では、この中で主にペーパーカンパニーの範囲が見直しの対象となった。
2017年12月に、米国におけるトランプ政権下での税制改革(「Tax Cut and Jobs Act 2017」)により連邦法人税率が35%から21%に引き下げられた。これにより、米国に所在する実態のない子会社が日本のCFC税制により、ペーパーカンパニー等にあたるとして合算課税の対象となるおそれが生じることとなった。
このため、平成31年度税制改正大綱では、米国等において実態あるビジネスを行っているかどうかという観点及び租税回避に資する類型を除外するという観点から、「イ 持株会社である一定の外国関係会社」、「ロ 不動産保有に係る一定の外国関係会社」、「ハ 資源開発等プロジェクトに係る一定の外国関係会社」という3つの類型について合算課税の対象外とすることとした。
「イ 持株会社である一定の外国関係会社」の類型については、主に米国等で、日本法人が構成員課税の事業体を有している場合に、米国から日本法人に対して直接課税が及ぶことを避けるために、米国で申告納税を行うために設立するブロッカーコーポレーションや倒産隔離の目的、他から出資を受ける場合に設置される中間持株会社が念頭に置かれている。「ロ 不動産保有に係る一定の外国関係会社」に関しては、米国などでは、不動産の保有を目的とした会社等を設けるなどして、不動産の流動性を高める取引慣行があり、この不動産の保有に係る会社については実態がないことが多く、ペーパーカンパニーとみなされる可能性があった。このため、この不動産保有に係る一定の外国関係会社についても、合算課税の対象外とすることとした。あわせて、「ハ 資源開発等プロジェクトに係る一定の外国関係会社」についても、共同出資等により中間持株会社を設置することに対応するとともに、資源開発という特性から事業規模が大きくなり、個々の企業の出資比率等は小さくなる一方、資金調達手段も多様化することが通常となることから、資金提供などの一定の関係もカバーするかたちで、合算課税の対象外とすることとした。
それぞれの類型の詳細な要件は以下の表5のとおりとなる。
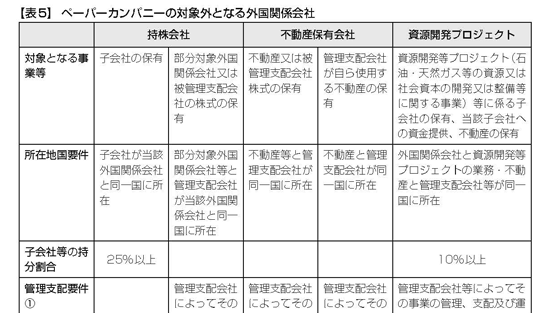
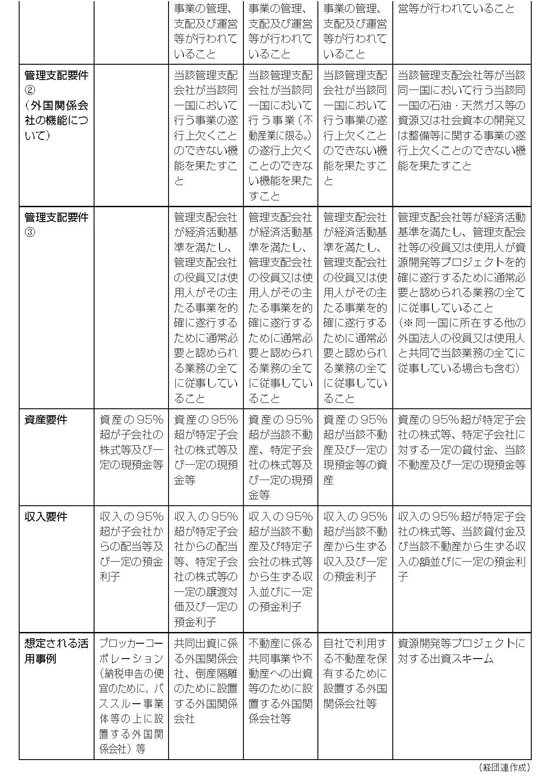
Ⅴ その他、主要項目等
1.情報照会手続の整備 情報照会手続の整備については、2018年に政府税制調査会において具体的に検討がなされている。政府税制調査会において「納税環境整備に関する専門家会合(座長:岡村忠生京都大学教授)」が設置され、仮想通貨取引、シェアリングエコノミー、金地金取引を取り上げて、税務当局による必要な情報の取得の観点から検討を行っている。この中では、「仮想通貨取引やシェアリングエコノミーについては、……既存の枠組みでは、高額・悪質な無申告者等を特定することも困難」、「仲介者(仮想通貨交換業者、プラットフォーム事業者等)が、個々の納税者の取引に係る情報を一定程度保有しているという特徴があることから、当該仲介者に対して法定調書の提出を求めることについて検討してはどうか」、「高額・悪質な無申告者等に対応するため特に必要な場合に限って、事業者が通常保有する情報の範囲内で照会を行うということも考えられる」などの指摘もなされていた。
今回の平成31年度税制改正大綱は、これらの問題意識を踏まえたものと考えられる。第一に、任意の協力要請について法制化し、調査に係る権限を明確化して、事業者の協力を得やすくするとしている。
第二に、仮想通貨取引や宿泊サービスの提供などのシェアリングエコノミーに関する特定取引等に関与し、その取引に係る課税標準等が年間1,000万円を超える者(特定取引者)を対象として、限定的な場合において(①特定取引者の国税について、更正決定すべきこととなる相当程度の可能性があり、かつ、②この報告の求めによらなければ、特定取引者を特定することが困難である場合)、事業者に対してその氏名(名称)、住所(居所)、個人番号(法人番号)に限って報告を求めることができる旨の規定を整備する。なお、拒否・虚偽報告については罰則が設けられる。
Ⅵ 2019年度以降の税制改正の議論の見通し
所得課税の関係では、大綱の検討事項にあるとおり、年金課税について、「世代間及び世代内の公平性の確保や、老後を保障する公的年金、公的年金を補完する企業年金を始めとした各種年金制度間のバランス、貯蓄・投資商品に対する課税との関連、給与課税等とのバランス等に留意するとともに、平成30年度税制改正の公的年金等控除の見直しの考え方や年金制度改革の方向性も踏まえつつ、拠出・運用・給付を通じて課税のあり方を総合的に検討する」としている。
政府税制調査会でもこの点は議論されている。2015年11月にとりまとめられた「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する論点整理」では、個人の働き方やライフコースによって、受けられる税制上の支援の大きさが異なっていることから、「個人の働き方やライフコースに影響されない公平な制度の構築を念頭に、幅広く検討」すること、「その際、拠出・運用・給付の各段階を通じた体系的な課税のあり方について、公平な税負担の確保や、高齢化の進展、貯蓄率の低下等の構造変化を踏まえて検討」すること、「給与・退職一時金・年金給付の間の税負担のバランスについて、働き方やライフコースの多様化を踏まえて検討」するというとりまとめがなされている。
政府税制調査会では、次頁の図10のとおり、老後を保障する各種年金制度や貯蓄・投資商品に関する資料が提出されているが、今後、これらの制度について、政府税制調査会等でさらに議論が行われる可能性がある。
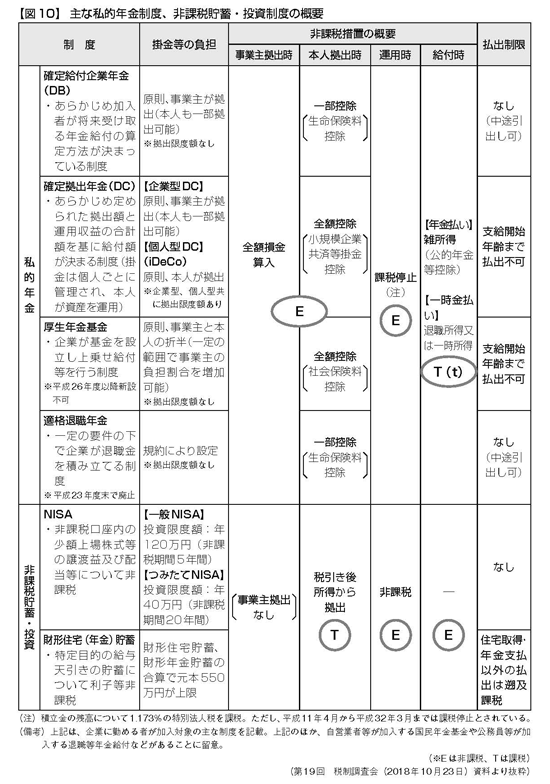
法人課税においては、連結納税制度について見直しが検討される可能性がある。現在、政府税制調査会において、「連結納税制度に関する専門家会合(座長:田近栄治成城大学経済学部特任教授)」が設置されており、連結納税制度を取り巻く状況の変化を踏まえた現状の課題や必要な見直しについて議論することとされている。2018年11月17日に開催された第1回会合の財務省提出資料では、「検討に当たっての視点」として、「完全支配関係にある企業グループ内における損益通算を可能とする基本的な枠組みは維持しつつ、制度の簡素化や中立性・公平性の観点から……検討を行う」としており、事務負担の軽減を図る観点から、「連結グループを一つの納税単位とする現行の制度の在り方(申告・納付の方法)や、連結固有のグループ調整計算の要否、修正や更正の場合の企業や課税庁の事務負担の軽減等について検討する」ことが示されている。連結納税を現在適用している企業及び今後適用を予定・検討している企業については、今後、専門家会合における議論の状況によっては、実務に影響が生じる可能性がある。
国際課税の分野では、2019年は電子経済への課税のあり方に関する議論が本格化する見込みである。2018年3月に公表されたOECDの電子経済に対する課税に関する中間報告書「Tax Challenges Arising from Digitalisation-Interim Report 2018」では、今後の検討の方向性として、①デジタル企業のみを対象として課税を考える案、②デジタル化は社会全体を変えるものであり、国際課税の枠組み全体を議論すべきとする案、③見直しは時期尚早とする案という3つの考え方が示されていたが、最近の海外メディア等の報道によれば、アメリカが②の考え方を取りつつあり、デジタル化に止まらず、国際課税全体の枠組みも含めて、検討を行う方向性を打ち出しつつある。源泉地国における課税を広く認めるなどの方向性で検討が進めば、デジタル化と直接関係しないと考えている日本企業にとっても、新興国等の市場国における課税リスクが増大する可能性がある。2019年は日本がG20の議長国となるため、日本がこの議論を主導する役割を担うことになる。国際的な議論の動向も留意すべきである。
この他、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する更なる対応について、平成31年度与党税制改正大綱の検討事項で「更なる税制上の対応の要否等について、平成32年度税制改正において検討し、結論を得る」として整理されている。
また、現在、電気供給業及び大手のガス供給業については、収入金額による外形標準課税が行われている。両業界については、すでに小売の全面自由化が実施されており、また、電気供給業については2020年に法的分離が予定されている。このため、収入金額による課税から、付加価値割及び資本金等の額による外形標準課税へと移行していくことが検討対象となるだろう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















