解説記事2019年01月28日 【SCOPE】 事業用資産に係る納税猶予は機械装置等を買い換えても継続(2019年1月28日号・№772)
譲渡はNGも除却はOK
事業用資産に係る納税猶予は機械装置等を買い換えても継続
平成31年度税制改正では、個人版事業承継税制が創設される。認定相続人が平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保を条件に、認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対する相続税の納税を猶予するもの。特定事業用資産とは土地・建物のほか、機械・器具備品など減価償却資産も対象となる。
ここで問題となるのは、納税猶予期間内に減価償却資産の耐用年数が満了あるいは壊れるなどして、除却したり同様の減価償却資産を買い換える場合、納税猶予期限の確定事由となり、納税猶予が認められなくなるのかといった点だ。本誌の取材によれば、機械装置等の減価償却資産を除却しても納税猶予期間は継続することが分かった。また、同様の機械装置等を買い換えた場合にも納税猶予期間は継続することになる。なお、この点については耐用年数が満了する前に買い換えたとしても同様の取扱いとなる。また、建物や土地を買い換えたケースも同様だ。
事業用資産(土地、建物、減価償却資産)を買い換えてもOK
平成31年度税制改正で創設される予定の新たな個人事業者を対象とした事業承継税制は、10年間の時限措置で既存の事業用小規模宅地特例との選択適用とするもの。法人の事業承継税制と同じく、承継計画(認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画で、平成31年4月1日から平成36年3月31日までに都道府県に提出されたもの)を作成して中小企業経営承継円滑化法の認定を受ける仕組みである。
対象となる特定事業用資産とは、事業用土地及び建物のほか、建物以外の減価償却資産で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものとされる。機械・器具備品(工作機械・パワーショベル・診療機器等)、車両・運搬具、生物(乳牛等、果樹等)、無形償却資産(特許権等)が対象となる。
買換えは納税猶予期限の確定事由か不明 ここで問題となるのは、納税猶予期間内に上記の減価償却資産の耐用年数が満了した場合だ。認定相続人が死亡あるいは次の後継者へ特定事業用資産を贈与する期間に比べて減価償却資産の耐用年数は明らかに短い。
例えば、農業用設備の耐用年数は「5年」であり、事業を継続していくには減価償却資産を譲渡し、同様のものを買い換えることも必要になってこよう。しかし、猶予税額が免除されるのは、「認定相続人が死亡時まで、特定事業用資産を保有し、事業を継続した場合」などとされているため(表参照)、減価償却資産を除却又は譲渡して買い換えた場合、納税猶予期間が継続するかどうか、平成31年度税制改正大綱からは明らかではない。
【表】猶予税額の全額免除
売却価額未満で買い換えた場合は差額を納付 本誌が取材したところによれば、耐用年数に関係なく、納税猶予期間内に減価償却資産を除却したとしても、その減価償却資産に係る相続税等は猶予されることになることが分かった。
また、減価償却資産を100で売却し、同様の減価償却資産を100以上の価額で買い換えた場合には全額が納税猶予される。農地等の贈与税・相続税の納税猶予制度に係る買換え特例等と同様といってよさそうだ。ただし、100で売却した減価償却資産について、80で買い換えた場合には、差額の「20」相当の猶予税額は納付する必要がある。
なお、この点は減価償却資産にかかわらず、土地や建物についても同様の取扱いとなる。
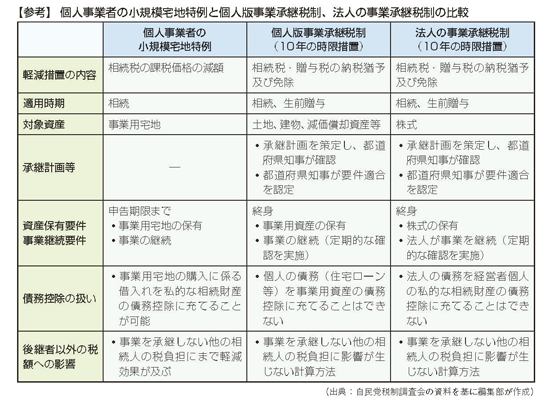
事業用資産に係る納税猶予は機械装置等を買い換えても継続
平成31年度税制改正では、個人版事業承継税制が創設される。認定相続人が平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保を条件に、認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対する相続税の納税を猶予するもの。特定事業用資産とは土地・建物のほか、機械・器具備品など減価償却資産も対象となる。
ここで問題となるのは、納税猶予期間内に減価償却資産の耐用年数が満了あるいは壊れるなどして、除却したり同様の減価償却資産を買い換える場合、納税猶予期限の確定事由となり、納税猶予が認められなくなるのかといった点だ。本誌の取材によれば、機械装置等の減価償却資産を除却しても納税猶予期間は継続することが分かった。また、同様の機械装置等を買い換えた場合にも納税猶予期間は継続することになる。なお、この点については耐用年数が満了する前に買い換えたとしても同様の取扱いとなる。また、建物や土地を買い換えたケースも同様だ。
事業用資産(土地、建物、減価償却資産)を買い換えてもOK
平成31年度税制改正で創設される予定の新たな個人事業者を対象とした事業承継税制は、10年間の時限措置で既存の事業用小規模宅地特例との選択適用とするもの。法人の事業承継税制と同じく、承継計画(認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画で、平成31年4月1日から平成36年3月31日までに都道府県に提出されたもの)を作成して中小企業経営承継円滑化法の認定を受ける仕組みである。
対象となる特定事業用資産とは、事業用土地及び建物のほか、建物以外の減価償却資産で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものとされる。機械・器具備品(工作機械・パワーショベル・診療機器等)、車両・運搬具、生物(乳牛等、果樹等)、無形償却資産(特許権等)が対象となる。
買換えは納税猶予期限の確定事由か不明 ここで問題となるのは、納税猶予期間内に上記の減価償却資産の耐用年数が満了した場合だ。認定相続人が死亡あるいは次の後継者へ特定事業用資産を贈与する期間に比べて減価償却資産の耐用年数は明らかに短い。
例えば、農業用設備の耐用年数は「5年」であり、事業を継続していくには減価償却資産を譲渡し、同様のものを買い換えることも必要になってこよう。しかし、猶予税額が免除されるのは、「認定相続人が死亡時まで、特定事業用資産を保有し、事業を継続した場合」などとされているため(表参照)、減価償却資産を除却又は譲渡して買い換えた場合、納税猶予期間が継続するかどうか、平成31年度税制改正大綱からは明らかではない。
【表】猶予税額の全額免除
| 次の場合には、猶予税額の全額を免除する。 (イ)認定相続人が、その死亡の時まで、特定事業用資産を保有し、事業を継続した場合 (ロ)認定相続人が一定の身体障害等に該当した場合 (ハ)認定相続人について破産手続開始の決定があった場合 (ニ)相続税の申告期限から5年経過後に、次の後継者へ特定事業用資産を贈与し、その後継者がその特定事業用資産について贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合 |
売却価額未満で買い換えた場合は差額を納付 本誌が取材したところによれば、耐用年数に関係なく、納税猶予期間内に減価償却資産を除却したとしても、その減価償却資産に係る相続税等は猶予されることになることが分かった。
また、減価償却資産を100で売却し、同様の減価償却資産を100以上の価額で買い換えた場合には全額が納税猶予される。農地等の贈与税・相続税の納税猶予制度に係る買換え特例等と同様といってよさそうだ。ただし、100で売却した減価償却資産について、80で買い換えた場合には、差額の「20」相当の猶予税額は納付する必要がある。
なお、この点は減価償却資産にかかわらず、土地や建物についても同様の取扱いとなる。
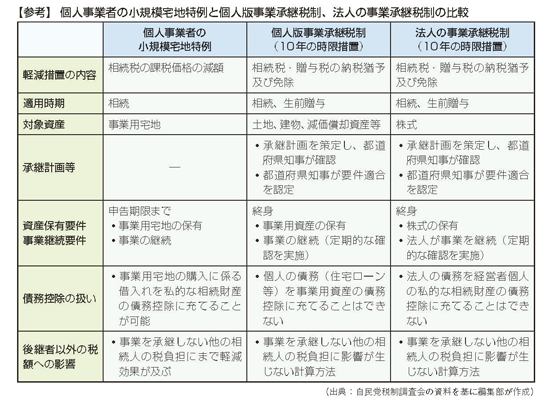
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























