解説記事2019年02月11日 【税理士のための相続法講座】 遺言(18)-遺言の内容(10)特別受益の持戻しの免除(2019年2月11日号・№774)
税理士のための相続法講座
第44回
遺言(18)-遺言の内容(10)
特別受益の持戻しの免除
弁護士 間瀬まゆ子
1 特別受益の持戻し免除の意思表示 相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に多額の贈与を受けたりした者がいた場合に、民法は、当該受益を相続分の前渡しとみてこれを相続財産に加算して(持ち戻して)相続分を算定することにしています(903条1項)。しかし、被相続人が意思表示によって特別受益者の受益分の持戻しを免除していた場合には、持戻し計算はなされないことになります(同条3項)。
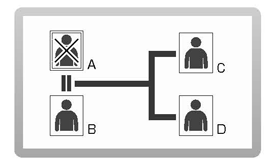
この事例で、AがBへの贈与につき持戻しの免除の意思表示をしていなければ、1,000万円の特別受益が持ち戻されますので、Bは(4,000万円+1,000万円)×法定相続分1/2-1,000万円の1,500万円しか取得できないところ、免除の意思表示があれば、4,000万×1/2の2,000万円の遺産を取得できることになります。
特別受益の持戻しの免除の意思表示については方式の定めはなく、黙示でもよいと解されています(ただし、遺贈については、遺言によらなければならないとする説もあります。)。
特別受益があったかは、遺産分割協議の中で非常に揉めやすいポイントの一つですが、特別受益の持戻しの免除の意思表示があったか否かも、また対立が生じやすいところです。なぜなら、特別受益の持戻しやその免除につき、周知が進んでいるとは言い難く、被相続人が持戻しを免除する旨の意思表示を書面等で残す場合は稀で、問題となるのは通常、黙示の意思表示があったかという点になるからです。そして、黙示の意思表示があったか否かは、様々な事情(評価根拠事実と評価障害事実)から判断されることになりますので、双方が自己に有利な事実を次々出してきて、紛争が混迷を深めることになってしまうのです。
そこで、紛争化が懸念されるようなケースについて、持戻しを免除したい(特別受益者が遺産分割により得られる財産を減らしたくない)との希望が遺言者にあるならば、その旨遺言に明示しておくのが肝要です。実際、遺言者の持戻し免除の意思表示が記載されている公正証書遺言は増えてきているそうです(恐らく、公証人がそのようなアドバイスをしているためでしょう。)。
ただ、遺言で全ての遺産の取得者を決めておけば、遺産分割の余地はありませんので、そもそも特別受益の問題も生じません。例えば、先ほどの例で、4,000万円の預貯金を誰に取得させるか、Aが遺言で定めていた場合です(ただし、4,000万円全額をBに遺贈したりすると、CとDの遺留分の問題は残ります。)。そのような場合は、当然、特別受益の持戻しの免除の意思表示を行う必要もありません。わざわざ遺言書を作るならば、持戻しを免除するか否かの判断をする以前に、全ての遺産についての帰属を定め、遺産分割を不要にして、相続人同士が対立し得る場面を減らしておく方が賢明と思います。
なお、持戻し免除の意思表示は贈与と同時に行う必要はなく、相続開始時までに行えば足ります。
2 持戻し免除の意思表示の推定 相続法改正により、婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地(配偶者居住権を含む。)について遺贈または贈与をしたときは、持戻しの免除の意思表示があったものと推定する(新民法903条4項)との規定が設けられることになりました。施行は本年7月1日です。
ただ、配偶者への自宅不動産の贈与のように、配偶者の老後の生活を支えるための贈与は、従来から持戻しの免除の意思表示が認定されやすい例の一つと言われてきました。ですから、推定規定ができることによるインパクトは、さほど大きくないかもしれません。加えて、新法は、持戻し免除の意思表示を「推定」するに過ぎません。立法の趣旨からして、推定は容易に覆ることはないようにも思いますが、反証は許されますので、紛争を完全に防げるわけではありません。
したがって、配偶者への自宅の贈与についても、他の場合と同様、特別受益の持戻しを免除したいなら、遺言で明示の意思表示をしておくのが確実です。
なお、配偶者居住権も含め、「配偶者の保護」を図る改正であることが広く報道されたため、過度な期待を持ってしまう当事者が出てきています。相続開始後、早い段階で相続人に接する専門家が冷静な判断を促すことが、無用な紛争を防ぐために非常に重要な意味を持つと感じています。
3 遺留分との関係 被相続人が特別受益の持戻しの免除の意思表示を行ったとしても、当該特別受益者が他の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分権利者の減殺請求(新法では遺留分侵害額請求)により、侵害の限度で効力を失うと解されています。つまり、遺留分との関係では、持戻しの免除の意思表示は無力なのです(遺言でできる遺留分対策については、本誌766号の記事を参照ください。)。
なお、新法の下では、上記とは逆に、生前贈与が特別受益として持ち戻されるのにもかかわらず、遺留分算定の基礎財産には入れられない場面が生じます。相続人への贈与が、相続開始前の10年間にされたものに限り遺留分算定の基礎財産に算入されることになったため(新法1044条3項)(※)、問題となる特別受益たる生前贈与が10年より前になされたものである場合に、上記のような場面が生じることになるのです。
そのため、特別受益と遺留分の関係は、より複雑になったように思います。この点を含め、遺留分については、別稿で再度採り上げる予定です。
※これに対し、遺留分権利者が侵害された遺留分の額を算定する際に控除される財産には、遺留分権利者の特別受益が含まれるところ、この特別受益については期間の制限がありません。つまり、相続人Aと相続人Bに対し、相続開始の11年前にそれぞれ被相続人から贈与がなされた事例で、BがAに対し遺留分侵害額請求をする場合に、遺留分の計算の過程で、Aへの贈与は加算されないのに、Bへの贈与は減算対象にされることになります。Bの側の不満は高まりそうです。
第44回
遺言(18)-遺言の内容(10)
特別受益の持戻しの免除
弁護士 間瀬まゆ子
1 特別受益の持戻し免除の意思表示 相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に多額の贈与を受けたりした者がいた場合に、民法は、当該受益を相続分の前渡しとみてこれを相続財産に加算して(持ち戻して)相続分を算定することにしています(903条1項)。しかし、被相続人が意思表示によって特別受益者の受益分の持戻しを免除していた場合には、持戻し計算はなされないことになります(同条3項)。
| Aが亡くなった。相続人は、配偶者B、子CとDの3人。相続財産は4,000万円の預貯金のみ。Aは生前、Bに1,000万円の金銭を贈与していた。 |
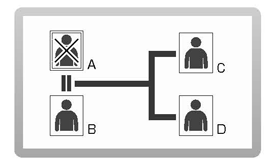
この事例で、AがBへの贈与につき持戻しの免除の意思表示をしていなければ、1,000万円の特別受益が持ち戻されますので、Bは(4,000万円+1,000万円)×法定相続分1/2-1,000万円の1,500万円しか取得できないところ、免除の意思表示があれば、4,000万×1/2の2,000万円の遺産を取得できることになります。
特別受益の持戻しの免除の意思表示については方式の定めはなく、黙示でもよいと解されています(ただし、遺贈については、遺言によらなければならないとする説もあります。)。
特別受益があったかは、遺産分割協議の中で非常に揉めやすいポイントの一つですが、特別受益の持戻しの免除の意思表示があったか否かも、また対立が生じやすいところです。なぜなら、特別受益の持戻しやその免除につき、周知が進んでいるとは言い難く、被相続人が持戻しを免除する旨の意思表示を書面等で残す場合は稀で、問題となるのは通常、黙示の意思表示があったかという点になるからです。そして、黙示の意思表示があったか否かは、様々な事情(評価根拠事実と評価障害事実)から判断されることになりますので、双方が自己に有利な事実を次々出してきて、紛争が混迷を深めることになってしまうのです。
そこで、紛争化が懸念されるようなケースについて、持戻しを免除したい(特別受益者が遺産分割により得られる財産を減らしたくない)との希望が遺言者にあるならば、その旨遺言に明示しておくのが肝要です。実際、遺言者の持戻し免除の意思表示が記載されている公正証書遺言は増えてきているそうです(恐らく、公証人がそのようなアドバイスをしているためでしょう。)。
ただ、遺言で全ての遺産の取得者を決めておけば、遺産分割の余地はありませんので、そもそも特別受益の問題も生じません。例えば、先ほどの例で、4,000万円の預貯金を誰に取得させるか、Aが遺言で定めていた場合です(ただし、4,000万円全額をBに遺贈したりすると、CとDの遺留分の問題は残ります。)。そのような場合は、当然、特別受益の持戻しの免除の意思表示を行う必要もありません。わざわざ遺言書を作るならば、持戻しを免除するか否かの判断をする以前に、全ての遺産についての帰属を定め、遺産分割を不要にして、相続人同士が対立し得る場面を減らしておく方が賢明と思います。
なお、持戻し免除の意思表示は贈与と同時に行う必要はなく、相続開始時までに行えば足ります。
2 持戻し免除の意思表示の推定 相続法改正により、婚姻期間が20年以上である夫婦の一方が他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地(配偶者居住権を含む。)について遺贈または贈与をしたときは、持戻しの免除の意思表示があったものと推定する(新民法903条4項)との規定が設けられることになりました。施行は本年7月1日です。
ただ、配偶者への自宅不動産の贈与のように、配偶者の老後の生活を支えるための贈与は、従来から持戻しの免除の意思表示が認定されやすい例の一つと言われてきました。ですから、推定規定ができることによるインパクトは、さほど大きくないかもしれません。加えて、新法は、持戻し免除の意思表示を「推定」するに過ぎません。立法の趣旨からして、推定は容易に覆ることはないようにも思いますが、反証は許されますので、紛争を完全に防げるわけではありません。
したがって、配偶者への自宅の贈与についても、他の場合と同様、特別受益の持戻しを免除したいなら、遺言で明示の意思表示をしておくのが確実です。
なお、配偶者居住権も含め、「配偶者の保護」を図る改正であることが広く報道されたため、過度な期待を持ってしまう当事者が出てきています。相続開始後、早い段階で相続人に接する専門家が冷静な判断を促すことが、無用な紛争を防ぐために非常に重要な意味を持つと感じています。
3 遺留分との関係 被相続人が特別受益の持戻しの免除の意思表示を行ったとしても、当該特別受益者が他の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分権利者の減殺請求(新法では遺留分侵害額請求)により、侵害の限度で効力を失うと解されています。つまり、遺留分との関係では、持戻しの免除の意思表示は無力なのです(遺言でできる遺留分対策については、本誌766号の記事を参照ください。)。
なお、新法の下では、上記とは逆に、生前贈与が特別受益として持ち戻されるのにもかかわらず、遺留分算定の基礎財産には入れられない場面が生じます。相続人への贈与が、相続開始前の10年間にされたものに限り遺留分算定の基礎財産に算入されることになったため(新法1044条3項)(※)、問題となる特別受益たる生前贈与が10年より前になされたものである場合に、上記のような場面が生じることになるのです。
そのため、特別受益と遺留分の関係は、より複雑になったように思います。この点を含め、遺留分については、別稿で再度採り上げる予定です。
※これに対し、遺留分権利者が侵害された遺留分の額を算定する際に控除される財産には、遺留分権利者の特別受益が含まれるところ、この特別受益については期間の制限がありません。つまり、相続人Aと相続人Bに対し、相続開始の11年前にそれぞれ被相続人から贈与がなされた事例で、BがAに対し遺留分侵害額請求をする場合に、遺留分の計算の過程で、Aへの贈与は加算されないのに、Bへの贈与は減算対象にされることになります。Bの側の不満は高まりそうです。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















