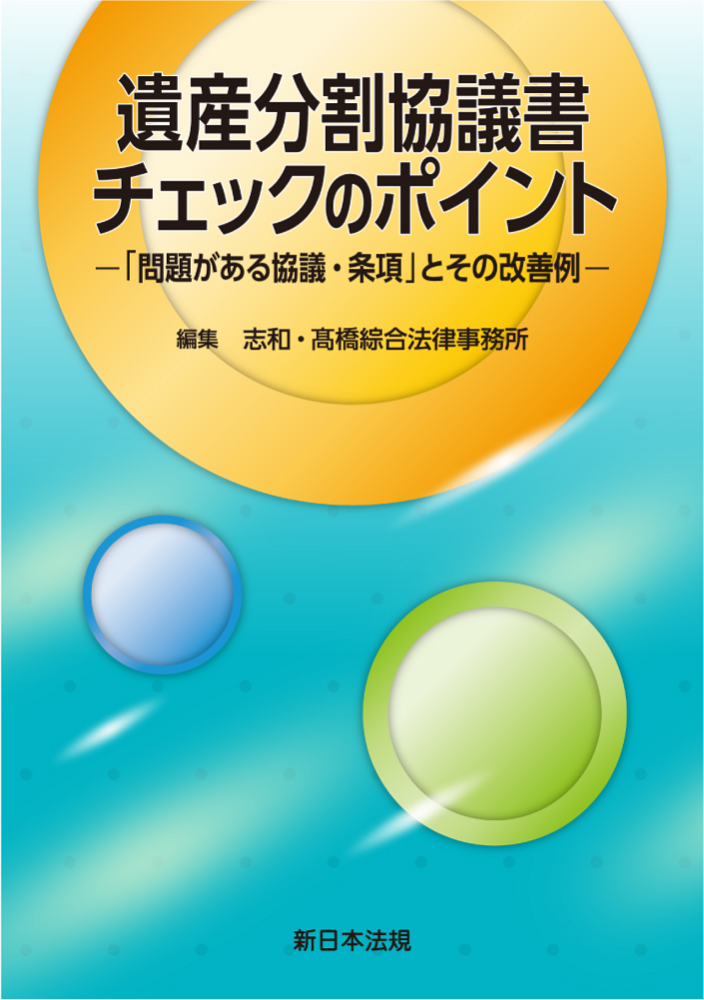税務ニュース2007年06月04日 取得価額の5%に到達した資産は総合償却から切離し5年均等償却可(2007年6月4日号・№213) 新制度下でも、法基通7-7-4等の考え方を踏襲
取得価額の5%に到達した資産は総合償却から切離し5年均等償却可
新制度下でも、法基通7-7-4等の考え方を踏襲
総合償却を行っている複数の減価償却資産のうち、取得価額の5%に到達した資産については、到達の翌事業年度から、その資産のみ単独で5年均等償却の対象にできることが本誌取材で確認された。
この点、一部には、「総合償却資産全体」の償却額の累計額が、総合償却資産を構成するすべての資産の取得価額の合計額の95%に到達しない限り均等償却は開始できないとの誤解があるので注意したい。
「総合償却資産=一の資産」は誤解 19年度税制改正で導入された新減価償却制度では、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で残りの帳簿価額を均等償却することとされている。
そこで、総合償却を行っている資産の1つが取得価額の5%に到達した場合、当該資産を総合償却から切り離して、単独で5年均等償却を適用してよいのかどうかという疑問が生じる。
この点について、総合償却では総合償却資産全体を「一の資産」と考えるため、「総合償却資産全体」の償却累計額が、総合償却資産を構成する全資産の取得価額の合計額の95%に到達しない限り、5年均等償却は開始できないとの誤解があるようだ。
しかし、耐用年数通達をみると、そもそも総合償却資産とは、「……当該資産に属する個々の資産の全部につき、その償却の基礎となる価額を個々の資産の全部を総合して定められた耐用年数により償却することとされているもの」と定義されているように(耐用年数通達1-5-8、カッコ書き)、複数の資産に対し総合的に1つの「耐用年数」を適用するのがその趣旨であり、複数の資産を「一の資産」として扱うものとは違う。
また、法人税法基本通達7-7-4では、「……総合償却資産の償却費の額をこれに含まれる個々の資産に配賦し、当該個々の資産の帳簿価額が明らかにされている場合において、その帳簿価額が個々の資産の取得価額の5%相当額に達したときは、当該個々の資産はじ後減価償却の対象とならないのであるから、その取得価額及び帳簿価額は、当該総合償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額及び帳簿価額から除くものとする」と規定している。同通達は旧減価償却制度を前提としているが、総合償却資産を構成する個々の資産を切り離すことができるという考え方は新制度下においても変わることはないと考えられる。
結論として、総合償却を行っている複数の減価償却資産のうち取得価額の5%に到達した資産については、5%に到達した事業年度の翌事業年度から、その資産のみを単独で5年均等償却の対象としてよいことになる。
新制度下でも、法基通7-7-4等の考え方を踏襲
総合償却を行っている複数の減価償却資産のうち、取得価額の5%に到達した資産については、到達の翌事業年度から、その資産のみ単独で5年均等償却の対象にできることが本誌取材で確認された。
この点、一部には、「総合償却資産全体」の償却額の累計額が、総合償却資産を構成するすべての資産の取得価額の合計額の95%に到達しない限り均等償却は開始できないとの誤解があるので注意したい。
「総合償却資産=一の資産」は誤解 19年度税制改正で導入された新減価償却制度では、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で残りの帳簿価額を均等償却することとされている。
そこで、総合償却を行っている資産の1つが取得価額の5%に到達した場合、当該資産を総合償却から切り離して、単独で5年均等償却を適用してよいのかどうかという疑問が生じる。
この点について、総合償却では総合償却資産全体を「一の資産」と考えるため、「総合償却資産全体」の償却累計額が、総合償却資産を構成する全資産の取得価額の合計額の95%に到達しない限り、5年均等償却は開始できないとの誤解があるようだ。
しかし、耐用年数通達をみると、そもそも総合償却資産とは、「……当該資産に属する個々の資産の全部につき、その償却の基礎となる価額を個々の資産の全部を総合して定められた耐用年数により償却することとされているもの」と定義されているように(耐用年数通達1-5-8、カッコ書き)、複数の資産に対し総合的に1つの「耐用年数」を適用するのがその趣旨であり、複数の資産を「一の資産」として扱うものとは違う。
また、法人税法基本通達7-7-4では、「……総合償却資産の償却費の額をこれに含まれる個々の資産に配賦し、当該個々の資産の帳簿価額が明らかにされている場合において、その帳簿価額が個々の資産の取得価額の5%相当額に達したときは、当該個々の資産はじ後減価償却の対象とならないのであるから、その取得価額及び帳簿価額は、当該総合償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額及び帳簿価額から除くものとする」と規定している。同通達は旧減価償却制度を前提としているが、総合償却資産を構成する個々の資産を切り離すことができるという考え方は新制度下においても変わることはないと考えられる。
結論として、総合償却を行っている複数の減価償却資産のうち取得価額の5%に到達した資産については、5%に到達した事業年度の翌事業年度から、その資産のみを単独で5年均等償却の対象としてよいことになる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.