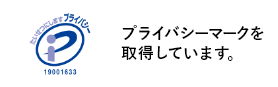税務ニュース2011年06月06日 資本剰余金と利益剰余金からの配当、株主総会議案順で充当順決定は不可(2011年6月6日号・№405) 配当原資の割当方法はすでに18年度改正でルール化
資本剰余金と利益剰余金からの配当、株主総会議案順で充当順決定は不可
配当原資の割当方法はすでに18年度改正でルール化
法人が資本剰余金と利益剰余金を同時に減少させて剰余金の配当を行うケースがあるが、この場合において、株主総会の決議上の議案の順番をもって、議案の号数の早い方の剰余金から先に配当原資に充てられたとして、それを前提に株主への税務処理を適用しようと考える向きもあるようだ。
しかし、配当原資の割当方法は18年度税制改正でルール化されており、どちらを原資とするのかを法人が任意に決めることは税務上認められないので留意したい。
どちらを原資にするかで株主の課税関係に違い 税務上、剰余金の配当の原資を資本剰余金とするのか利益剰余金とするのかが問題となるのは、どちらを原資とするかによって株主の課税関係が変わってくるからだ。
具体的には、利益剰余金を配当原資とする場合には「受取配当」となる一方(法法23①一、所法24①)、資本剰余金を配当原資とする場合には、資本金等の額と利益積立金額の割合に応じ、当該配当総額のうち①資本金等の額に対応する部分については、その金額のうち株主の保有割合に相当する金額を株式の譲渡対価として譲渡損益課税が行われ(法法61の2⑰、措法37の10③三)、②利益積立金に対応する部分はみなし配当となり(法法24①三、所法25①三)、受取配当として処理される。
株主が個人の場合、配当の全額が総合課税を受けるか、その一部が譲渡損益課税を受けるかによっては税負担に違いが生じ得ることとなり、株主が法人の場合には、受取配当の益金不算入規定の適用対象の範囲が異なり、やはり税負担が変わってくる。
このように、配当原資の違いによって株主の税負担が変わると課税上の弊害が生じかねないことから、平成18年度税制改正では、資本剰余金と利益剰余金の双方を同時に減少して剰余金の配当を行う場合には、まず資本剰余金の減少額の範囲内で資本金等の額を減少させ、交付した金銭等のうち「減少資本金等の額を超える部分の金額」を利益積立金額の減少額(株主にとっては受取配当の額)とするとの整理が行われている(法法24①、法令8①十九)。
一部には、株主総会の決議上、議案の号数の順番が早い方から先に剰余金の配当原資に充てられたとして、それを前提に株主への税務処理を適用しようとするケースがあるようだ(たとえば第2号議案を「利益剰余金を原資とする剰余金の配当」、第3号議案を「資本剰余金を原資とする剰余金の配当」とする)。しかし、上記のとおり、配当原資の割当方法は18年度税制改正でルール化されており、どちらを原資とするのかを法人が任意に決めることは税務上認められないので留意したい。
配当原資の割当方法はすでに18年度改正でルール化
法人が資本剰余金と利益剰余金を同時に減少させて剰余金の配当を行うケースがあるが、この場合において、株主総会の決議上の議案の順番をもって、議案の号数の早い方の剰余金から先に配当原資に充てられたとして、それを前提に株主への税務処理を適用しようと考える向きもあるようだ。
しかし、配当原資の割当方法は18年度税制改正でルール化されており、どちらを原資とするのかを法人が任意に決めることは税務上認められないので留意したい。
どちらを原資にするかで株主の課税関係に違い 税務上、剰余金の配当の原資を資本剰余金とするのか利益剰余金とするのかが問題となるのは、どちらを原資とするかによって株主の課税関係が変わってくるからだ。
具体的には、利益剰余金を配当原資とする場合には「受取配当」となる一方(法法23①一、所法24①)、資本剰余金を配当原資とする場合には、資本金等の額と利益積立金額の割合に応じ、当該配当総額のうち①資本金等の額に対応する部分については、その金額のうち株主の保有割合に相当する金額を株式の譲渡対価として譲渡損益課税が行われ(法法61の2⑰、措法37の10③三)、②利益積立金に対応する部分はみなし配当となり(法法24①三、所法25①三)、受取配当として処理される。
株主が個人の場合、配当の全額が総合課税を受けるか、その一部が譲渡損益課税を受けるかによっては税負担に違いが生じ得ることとなり、株主が法人の場合には、受取配当の益金不算入規定の適用対象の範囲が異なり、やはり税負担が変わってくる。
このように、配当原資の違いによって株主の税負担が変わると課税上の弊害が生じかねないことから、平成18年度税制改正では、資本剰余金と利益剰余金の双方を同時に減少して剰余金の配当を行う場合には、まず資本剰余金の減少額の範囲内で資本金等の額を減少させ、交付した金銭等のうち「減少資本金等の額を超える部分の金額」を利益積立金額の減少額(株主にとっては受取配当の額)とするとの整理が行われている(法法24①、法令8①十九)。
一部には、株主総会の決議上、議案の号数の順番が早い方から先に剰余金の配当原資に充てられたとして、それを前提に株主への税務処理を適用しようとするケースがあるようだ(たとえば第2号議案を「利益剰余金を原資とする剰余金の配当」、第3号議案を「資本剰余金を原資とする剰余金の配当」とする)。しかし、上記のとおり、配当原資の割当方法は18年度税制改正でルール化されており、どちらを原資とするのかを法人が任意に決めることは税務上認められないので留意したい。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -