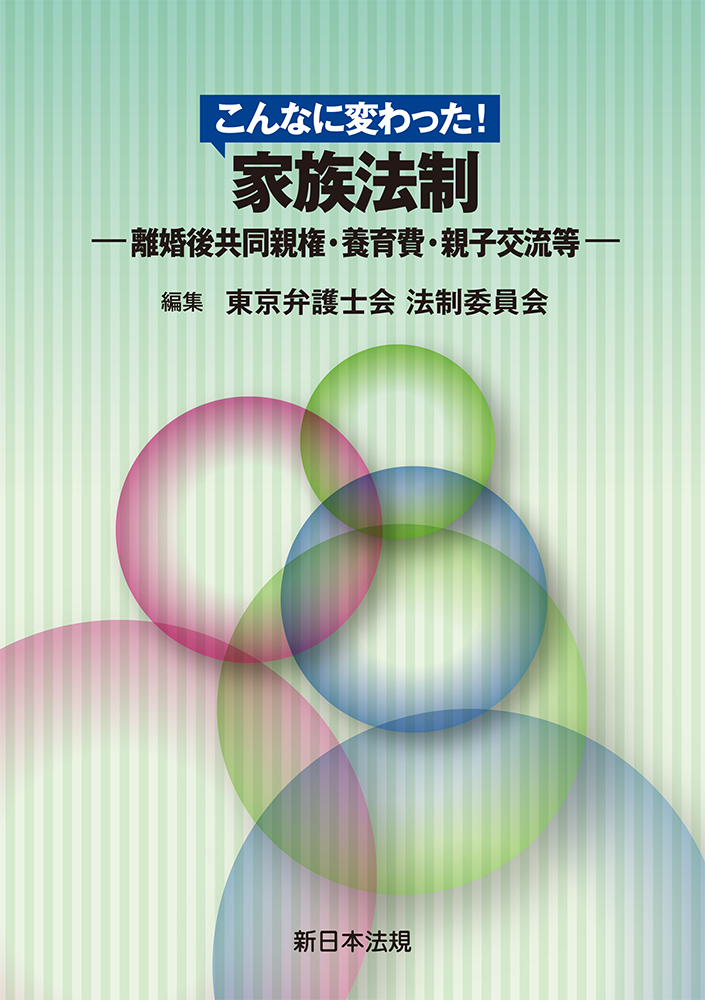会社法ニュース2003年09月15日 株券不発行制度と電子公告制度とは?(2003年9月1日号・№033) ニュース特集 次に予定されている商法改正の概要を探る
ニュース特集
次に予定されている商法改正の概要を探る
株券不発行制度と電子公告制度とは?
7月に改正(本誌8月4日号(No.30)参照)されたばかりの商法ですが、更なる次の改正が控えていることをご存知ですか。次の改正として予定されているのは株券不発行制度と電子公告制度。今年の3月に法制審議会会社法部会は「株券不発行制度及び電子公告制度の導入に関する要綱中間試案」を公表し、広く意見を募りました。改正案は早ければ今年中に国会に提出される予定です。今回の特集では、その概要を探ってみました。
株券不発行制度
次の改正において、会社は定款で株券を発行しない旨の定めをすることができる旨改正が予定されています。
現行法では、株券の交付が株式譲渡の要件とされており(205条1項)、株主名簿の記載は会社に対する対抗要件とされています。
改正により、定款を変更することで株券不発行制度の採用が可能になります。株券不発行制度を採用した会社(以下「株券廃止会社」)の株式を譲渡する場合、交付する株券がないので、譲渡人と譲受人の意思表示のみで株式の譲渡ができます。譲渡人と譲受人が共同して名義書換を請求し、譲受人の名義に書き換えられることで会社だけでなく第三者に対しての対抗要件が備わることとなります(現行法の有限会社と同様の対抗要件となります(有限会社法20条))。もちろん、株券不発行制度を採用しない会社では従来どおり株券の移転により株式を譲渡します(なお、後述の株式振替制度利用会社の株式は「振替」によって移転します)。
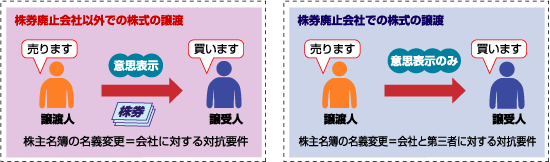
なお、現行法の株券不所持制度(226条の2第1項)は、株主から請求があればいつでも株券を発行しなければならない点において、株券不発行制度と決定的に異なります。
株式振替制度
また、株式振替制度も導入されます。これは、株式振替制度利用会社の株式(振替株式)に関する権利の帰属については、振替機関または口座管理機関が作成する振替口座簿の記載により決せられるというもの。すなわち、振替株式は「振替」によって移転することとなります。改正案では公開会社は、一斉に株券廃止会社かつ株式振替制度利用会社に移行することを予定しています。具体的には、公開会社は、新改正商法施行後5年以内の政令で定める日(一斉移行日)において、株券を発行しない旨の定めをする定款変更決議をなし、かつ、株式振替制度利用会社になったものとみなされる予定です。
その他の付随する改正
その他、次のような改正も予定されています。
・株式の譲渡につき取締役会の承認が必要な譲渡制限会社は、株主の請求がない限り、株券の発行が不要。
・株主名簿の閉鎖の制度(224条の3第1項)が廃止され、基準日制度に一本化。
・新株の発行において、新株引受人が株主となる日(280条の9第1項)を「払込期日の翌日」から「払込期日」とする(これにより「新株式払込金」という科目名がなくなります。これにつきましては本誌8月11日号(No.31)の42ページの「ことばのコンビニ」を参照してください)。
・株券廃止会社は新株予約権証券を発行することができなくなります(既発行の新株予約権証券の効力に影響はありません)。
電子公告制度
株式会社の公告は、現在の官報・日刊新聞紙(以下、日刊紙)に掲げる方法に加えて、インターネットを利用する方法により行うこともできるように改正が検討されています。官報自体も紙媒体の官報に加えて電子官報が発行される計画もあり、紙情報が電子情報へ置き換わるのは時代の趨勢といえます。
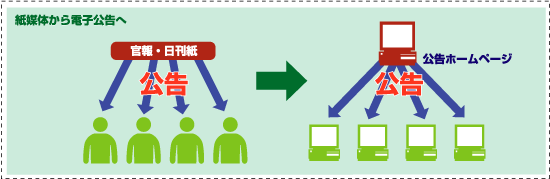
官報・日刊紙の公告は一回掲載されればOKですが、インターネットの場合「一回掲載」という概念になじまないことから、次のような「公告の期間」というのが重要となります。
この期間中に連続して掲載する必要があります。そして、本当に連続して掲載していたかどうかにつき調査機関が調査することを予定しています。具体的には調査機関が公告期間中に断続的にサーバー故障等による不掲載やハッカー侵入等による改ざん等の有無を調査します。調査機関が調査を行ったすべての日時において当該公告の内容が公告ホームページに掲載されていた旨記載のある調査機関発行の調査結果通知書が、登記申請の際に添付される「公告をしたことを証する書面」となる予定です。
調査機関に調査の申請がされた電子公告のURLは法務省が開設するリンク集のホームページにリンクされます。リンク集のホームページは個々の会社の公告ホームページに個別にアクセスしなければ公告の存否・内容を確認しえないという電子公告の欠点を補完するものとなります。
なお、調査機関は法務大臣の登録により営業可能となるため、様々な団体の参入が予想されます。
貸借対照表等の電磁的公示の制度との関係は?
貸借対照表等の電磁的公示の制度(283条5項)は、電子公告を公告の方法としない会社において引き続き認められる方針です。なお、貸借対照表等の電子公告は現行の貸借対照表等の電磁的公示の制度と同様、全文の掲載が要求される点に注意が必要です。
その他の付随する改正
その他、合併や減資等における債権者保護手続につき、官報公告に加えて、日刊紙による公告又は電子公告も行った場合には、債権者に対する個別催告は不要といった改正も予定されています。
A:官報公告と日刊紙による公告の併用で、債権者に対する個別催告の省略可
B:公告併用でも債権者に対する個別催告の省略不可(なお、374条の4第1項但書あり)
C:官報公告に加えて、日刊紙による公告又は電子公告も行った場合には、債権者に対する個別催告は省略可
D:官報公告に加えて、日刊紙による公告又は電子公告も行った場合には、不法行為によって生じた債権を有する者以外の債権者に対しては個別催告を省略可(不法行為によって生じた権利を有する者には個別催告が必要)
次に予定されている商法改正の概要を探る
株券不発行制度と電子公告制度とは?
7月に改正(本誌8月4日号(No.30)参照)されたばかりの商法ですが、更なる次の改正が控えていることをご存知ですか。次の改正として予定されているのは株券不発行制度と電子公告制度。今年の3月に法制審議会会社法部会は「株券不発行制度及び電子公告制度の導入に関する要綱中間試案」を公表し、広く意見を募りました。改正案は早ければ今年中に国会に提出される予定です。今回の特集では、その概要を探ってみました。
株券不発行制度
次の改正において、会社は定款で株券を発行しない旨の定めをすることができる旨改正が予定されています。
現行法では、株券の交付が株式譲渡の要件とされており(205条1項)、株主名簿の記載は会社に対する対抗要件とされています。
改正により、定款を変更することで株券不発行制度の採用が可能になります。株券不発行制度を採用した会社(以下「株券廃止会社」)の株式を譲渡する場合、交付する株券がないので、譲渡人と譲受人の意思表示のみで株式の譲渡ができます。譲渡人と譲受人が共同して名義書換を請求し、譲受人の名義に書き換えられることで会社だけでなく第三者に対しての対抗要件が備わることとなります(現行法の有限会社と同様の対抗要件となります(有限会社法20条))。もちろん、株券不発行制度を採用しない会社では従来どおり株券の移転により株式を譲渡します(なお、後述の株式振替制度利用会社の株式は「振替」によって移転します)。
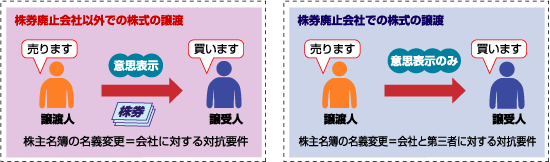
なお、現行法の株券不所持制度(226条の2第1項)は、株主から請求があればいつでも株券を発行しなければならない点において、株券不発行制度と決定的に異なります。
株式振替制度
また、株式振替制度も導入されます。これは、株式振替制度利用会社の株式(振替株式)に関する権利の帰属については、振替機関または口座管理機関が作成する振替口座簿の記載により決せられるというもの。すなわち、振替株式は「振替」によって移転することとなります。改正案では公開会社は、一斉に株券廃止会社かつ株式振替制度利用会社に移行することを予定しています。具体的には、公開会社は、新改正商法施行後5年以内の政令で定める日(一斉移行日)において、株券を発行しない旨の定めをする定款変更決議をなし、かつ、株式振替制度利用会社になったものとみなされる予定です。
その他の付随する改正
その他、次のような改正も予定されています。
・株式の譲渡につき取締役会の承認が必要な譲渡制限会社は、株主の請求がない限り、株券の発行が不要。
・株主名簿の閉鎖の制度(224条の3第1項)が廃止され、基準日制度に一本化。
・新株の発行において、新株引受人が株主となる日(280条の9第1項)を「払込期日の翌日」から「払込期日」とする(これにより「新株式払込金」という科目名がなくなります。これにつきましては本誌8月11日号(No.31)の42ページの「ことばのコンビニ」を参照してください)。
・株券廃止会社は新株予約権証券を発行することができなくなります(既発行の新株予約権証券の効力に影響はありません)。
電子公告制度
株式会社の公告は、現在の官報・日刊新聞紙(以下、日刊紙)に掲げる方法に加えて、インターネットを利用する方法により行うこともできるように改正が検討されています。官報自体も紙媒体の官報に加えて電子官報が発行される計画もあり、紙情報が電子情報へ置き換わるのは時代の趨勢といえます。
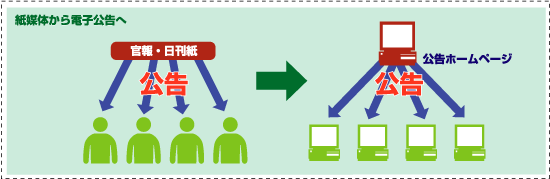
官報・日刊紙の公告は一回掲載されればOKですが、インターネットの場合「一回掲載」という概念になじまないことから、次のような「公告の期間」というのが重要となります。
| ・債権者保護手続における公告のように、その期間中については異議の申出等の行為をすることができるとされている公告については、当該期間 ・決算公告(B/S。大会社はB/S・P/L)は5年間 ・基準日や割当日の公告のように一定の日の2週間前や3週間前に公告をしなければならないとされているものは、当該一定の日までの期間 ・その他の公告については1ヶ月間 |
この期間中に連続して掲載する必要があります。そして、本当に連続して掲載していたかどうかにつき調査機関が調査することを予定しています。具体的には調査機関が公告期間中に断続的にサーバー故障等による不掲載やハッカー侵入等による改ざん等の有無を調査します。調査機関が調査を行ったすべての日時において当該公告の内容が公告ホームページに掲載されていた旨記載のある調査機関発行の調査結果通知書が、登記申請の際に添付される「公告をしたことを証する書面」となる予定です。
調査機関に調査の申請がされた電子公告のURLは法務省が開設するリンク集のホームページにリンクされます。リンク集のホームページは個々の会社の公告ホームページに個別にアクセスしなければ公告の存否・内容を確認しえないという電子公告の欠点を補完するものとなります。
なお、調査機関は法務大臣の登録により営業可能となるため、様々な団体の参入が予想されます。
電子公告の流れ(予定)
|
貸借対照表等の電磁的公示の制度との関係は?
貸借対照表等の電磁的公示の制度(283条5項)は、電子公告を公告の方法としない会社において引き続き認められる方針です。なお、貸借対照表等の電子公告は現行の貸借対照表等の電磁的公示の制度と同様、全文の掲載が要求される点に注意が必要です。
| 電子公告を公告の方法とした会社 | | ||
| 電磁的公示の制度採用会社 | 官報・日刊紙に決算公告を掲げる会社 | ||
| 全文or要旨? | 要旨の掲載でOK | ||
その他の付随する改正
その他、合併や減資等における債権者保護手続につき、官報公告に加えて、日刊紙による公告又は電子公告も行った場合には、債権者に対する個別催告は不要といった改正も予定されています。
| 債権者保護手続の局面 | | | |
| 合併 | | | |
| 会社分割 | 承継会社がする債権者保護手続 | | |
| 分割会社がする債権者保護手続 | | | |
| 資本金・法定準備金の減少 | | | |
| 清算 | | | |
A:官報公告と日刊紙による公告の併用で、債権者に対する個別催告の省略可
B:公告併用でも債権者に対する個別催告の省略不可(なお、374条の4第1項但書あり)
C:官報公告に加えて、日刊紙による公告又は電子公告も行った場合には、債権者に対する個別催告は省略可
D:官報公告に加えて、日刊紙による公告又は電子公告も行った場合には、不法行為によって生じた債権を有する者以外の債権者に対しては個別催告を省略可(不法行為によって生じた権利を有する者には個別催告が必要)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.