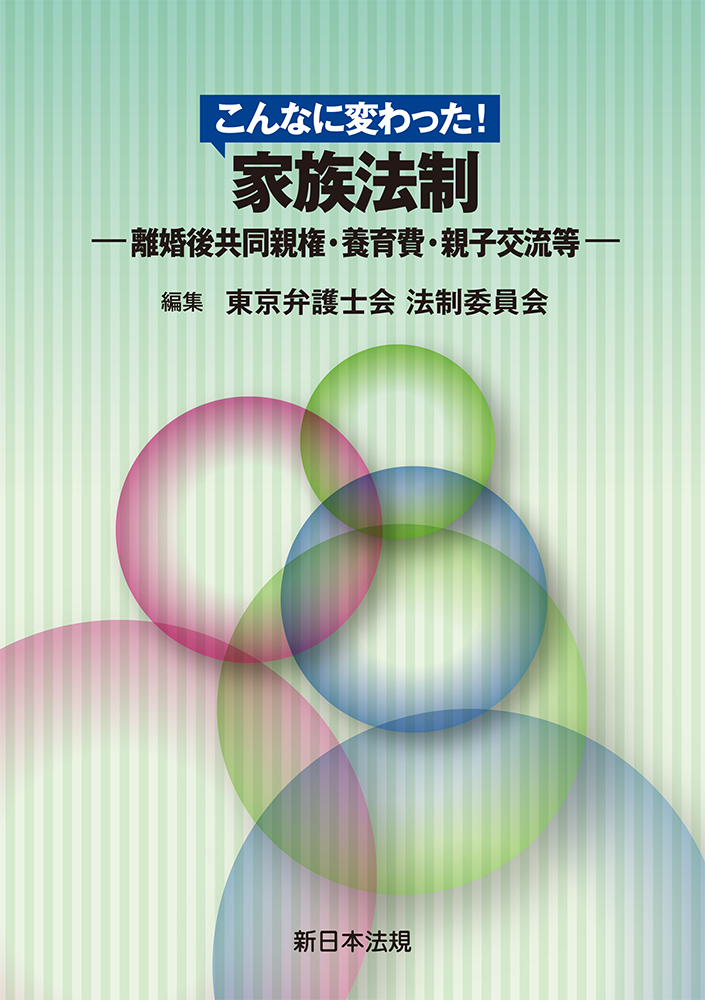会社法ニュース2003年10月20日 9月25日より施行!(2003年10月20日号・№039) ニュース特集 新商法・新商法施行規則あわせて理解
ニュース特集
9月25日より施行!
新商法・新商法施行規則あわせて理解
改正商法(H15法律第132号)及び改正商法施行規則(H15法務省令第68号)は9月25日から施行されています。商法改正を特集した8月4日号(No.030)の時点では商法施行規則は改正されていませんでしたので、今回の特集では、商法と商法施行規則をあわせて改正点をみていくことにします。
なお、条文については以下のページ等もあわせて参照してください。
改正商法:8月4日号(No.030)4ページ以降
改正商法施行規則:e-hokiの会員登録を済ませた後、9月22日のWeb記事「改正商法施行規則を全文掲載!」をご覧下さい→http://www.e-hoki.com/ta/ta.php
改正点1 定款授権に基づく取締役会決議による自己株式取得が可能に!!
公開会社に限り、定款授権に基づく取締役会決議による自己株式取得が可能となりました。
point 1 公開会社にのみ影響がある改正です。
商法211条ノ3第1項2号に「第210条第9項本文ニ規定スル方法」とありますが、これは「市場ニ於テスル取引又ハ(中略)公開買付けノ方法」(商法210条9項)を意味します。非公開会社の場合どちらの方法にもよることができません。そこで、本改正は非公開会社には影響のない改正といえます。
point 2 従来の株主総会決議による取得枠とあわせて設定できます。
定款授権をした会社が、取締役会決議ではなく株主総会決議により自己株式の取得枠を設定(商法210条1項)することは当然可能ですし、株主総会決議の枠以上に自己株式の取得が必要となれば、その分につき取締役会決議により取得することもできます。
ただ、取締役会の決議で取得した場合は、定時総会の終結後に自己株式の買受が必要となった理由を次期の定時総会で報告する必要があります(商法211条ノ3第4項)。これは、本来的な姿としては株主総会で取得枠を決議すべきであるという考え方が背景にあるといえます。
point 3 営業報告書の記載内容が変わりました。
商法211条ノ3第4項に対応して、商法施行規則103条1項9号の規定が整備されました。
改正点2 中間配当財源の見直し
中間配当限度額の計算がよりきめ細かいものとなりました。
point 1 期中に取崩した法定準備金を財源に中間配当ができるようになりました。
法定準備金の取崩(減少)を行った期において当該取崩額(商法289条2項各号に定める額を除く)を財源に中間配当を実施することが可能となりました(商法293ノ5第3項5号。なお、減資により生じた剰余金も同様→同6号)。それは取崩した法定準備金を配当にまわせるタイミングが早まったことを意味します。すなわち、5月19日号(No.019)の特集「法定準備金の取崩に際しての法務・会計・税務処理の注意点(発行会社側編―上)」(5ページ)では、
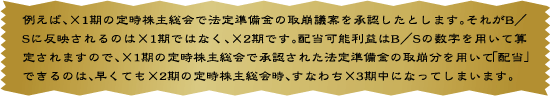
とありますが、今回の改正により中間配当より前に債権者保護手続が完了していれば、取り崩した法定準備金を財源に中間配当を実施することが可能となりました。
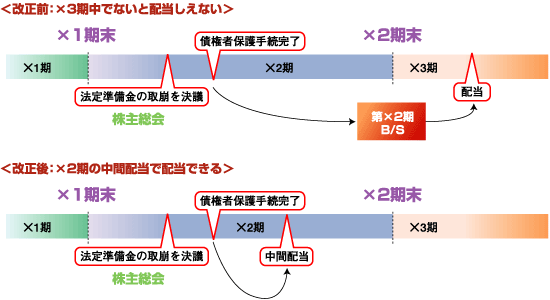
point 2 中間配当限度額の計算にあたり、「控除」の対象となる項目が増えました。
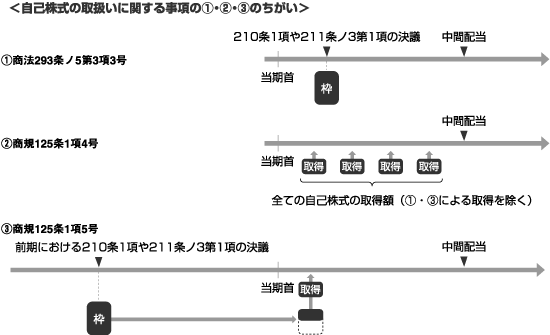
point 3 中間配当限度額の計算にあたり、従来は「控除」額だけでしたが、改正により「加算」額も加わりました。
改正点3 ストック・オプションに係る記載事項の改正
営業報告書において「特に有利な条件で発行した新株予約権」(いわゆるストック・オプション)に係る記載事項が改正されました(商規103条2項)。これは、商法改正を受けて商法施行規則が改正された訳ではなく、単に商法改正とタイミングをあわせて、商法施行規則の整備が図られたものです。
point 1 ストック・オプションに関して個別開示が必要な対象が狭まりました。
特に有利な条件で発行された新株予約権の割当を受けた子会社(*1)の取締役(*2)または監査役(*3)について、改正前は全員の氏名の個別開示が必要でした。これについては煩雑である等の批判があり、実務上の要請を受け、商法施行規則が改正されることとなりました。改正により、計算書類作成会社・子会社の使用人と併せて上位10名以内の者(商規103条2項3号イ)及び計算書類作成会社の取締役等のうち割当株式数が最も少ない者以上の割当てを受けた者(商規103条2項3号ロ)の氏名を開示すれば足りることとなりました。
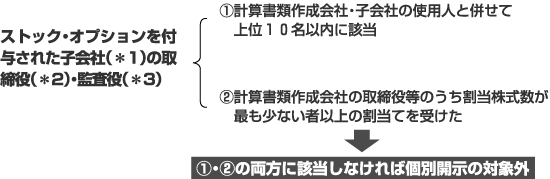
point 2 ストック・オプションに関して類型毎の開示が必要となりました。
計算書類作成会社の使用人、子会社(*1)の取締役(*2)、監査役(*3)、使用人の類型に該当するものについては、その類型毎に付与の総数等の記載が新たに必要となります(商規103条2項4号)。Aさんに何株、Bさんに何株といった個別開示と異なり、計算書類作成会社の使用人というカテゴリーに対して総計で何株、子会社の取締役というカテゴリーに対して総計で何株といった開示になります。これにより、個別開示とは異なった視点から株主が判断することが可能となります。
*1 連結特例規定適用会社については、計算書類作成会社の親会社以外の関係会社を指します。
*2 委員会等設置会社においては執行役が含まれるとともに、監査委員である取締役は除かれます(*3参照)。
*3 委員会等設置会社においては監査委員会を組織する取締役(監査委員)も含みます。
9月25日より施行!
新商法・新商法施行規則あわせて理解
改正商法(H15法律第132号)及び改正商法施行規則(H15法務省令第68号)は9月25日から施行されています。商法改正を特集した8月4日号(No.030)の時点では商法施行規則は改正されていませんでしたので、今回の特集では、商法と商法施行規則をあわせて改正点をみていくことにします。
なお、条文については以下のページ等もあわせて参照してください。
改正商法:8月4日号(No.030)4ページ以降
改正商法施行規則:e-hokiの会員登録を済ませた後、9月22日のWeb記事「改正商法施行規則を全文掲載!」をご覧下さい→http://www.e-hoki.com/ta/ta.php
改正点1 定款授権に基づく取締役会決議による自己株式取得が可能に!!
公開会社に限り、定款授権に基づく取締役会決議による自己株式取得が可能となりました。
| 参 考 条 文 ・ 要 約 ・ | 商法211条ノ3 1項 会社は次の場合に取締役会の決議で自己株式を買受けることができる。 2号 取締役会の決議で自己株式を買受ける旨の定款の定がある場合において210条9項本文に規定する方法により自己株式を買受けるとき 4項 1項2号の決議により自己株式を買受けた場合には①その決議前に終結した最後に招集された定時総会の終結後に買受けた自己株式の買受を必要とした理由、②その株式の種類、数及び取得価額の総額を1項2号の決議による買受後最初に招集される定時総会において報告しなければならない。 |
point 1 公開会社にのみ影響がある改正です。
商法211条ノ3第1項2号に「第210条第9項本文ニ規定スル方法」とありますが、これは「市場ニ於テスル取引又ハ(中略)公開買付けノ方法」(商法210条9項)を意味します。非公開会社の場合どちらの方法にもよることができません。そこで、本改正は非公開会社には影響のない改正といえます。
point 2 従来の株主総会決議による取得枠とあわせて設定できます。
定款授権をした会社が、取締役会決議ではなく株主総会決議により自己株式の取得枠を設定(商法210条1項)することは当然可能ですし、株主総会決議の枠以上に自己株式の取得が必要となれば、その分につき取締役会決議により取得することもできます。
ただ、取締役会の決議で取得した場合は、定時総会の終結後に自己株式の買受が必要となった理由を次期の定時総会で報告する必要があります(商法211条ノ3第4項)。これは、本来的な姿としては株主総会で取得枠を決議すべきであるという考え方が背景にあるといえます。
point 3 営業報告書の記載内容が変わりました。
商法211条ノ3第4項に対応して、商法施行規則103条1項9号の規定が整備されました。
改正点2 中間配当財源の見直し
中間配当限度額の計算がよりきめ細かいものとなりました。
| 参 考 条 文 商 法 2 9 3 条 ノ 5 ・ 要 約 ・ |
|
point 1 期中に取崩した法定準備金を財源に中間配当ができるようになりました。
法定準備金の取崩(減少)を行った期において当該取崩額(商法289条2項各号に定める額を除く)を財源に中間配当を実施することが可能となりました(商法293ノ5第3項5号。なお、減資により生じた剰余金も同様→同6号)。それは取崩した法定準備金を配当にまわせるタイミングが早まったことを意味します。すなわち、5月19日号(No.019)の特集「法定準備金の取崩に際しての法務・会計・税務処理の注意点(発行会社側編―上)」(5ページ)では、
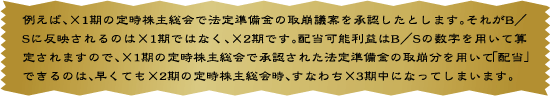
とありますが、今回の改正により中間配当より前に債権者保護手続が完了していれば、取り崩した法定準備金を財源に中間配当を実施することが可能となりました。
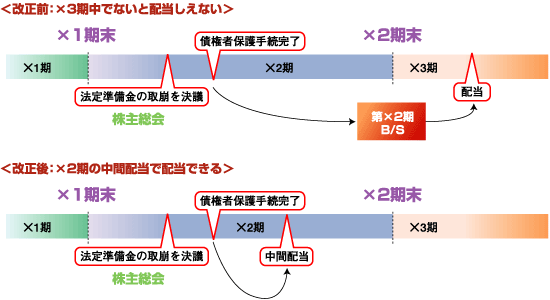
point 2 中間配当限度額の計算にあたり、「控除」の対象となる項目が増えました。
| 自己株式の取扱いに関する事項 (①・②・③のちがいについては次ページ参照) |
| ①定時総会決議による自己株式取得の枠(商法210条1項)に加えて、定款授権に基づく取締役会決議による枠(商法211条ノ3第1項)が控除されることになりました(商法293条ノ5第3項3号)。 ②改正前は財源規制の係る特定の取得に限定されていましたが、改正により期中に取得したすべての自己株式(定時総会決議及び定款授権に基づく取締役会決議に基づいて買い受けたものを除く)の取得額が新たに控除されることとなりました(商規125条1項4号)。 ③改正前は、商法210条1項・211条ノ3第1項の規定による取得に関しては、当期に決議がされた取得枠のみが控除の対象とされていましたが、新たに前期中の決議に基づき当期に取得した額も控除されることとなりました(商規125条1項5号)。 |
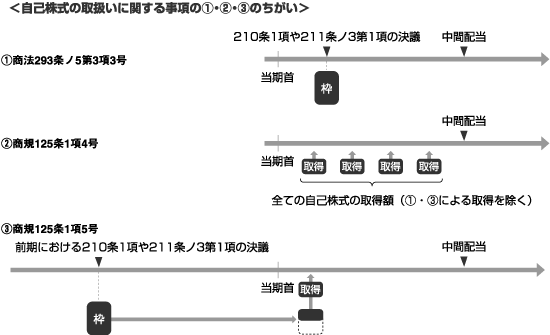
| 期中の人的分割に伴う変動に関する事項 |
| 人的分割に際して減少する純資産額が新たに控除されることとなりました(商規125条1項6号)。 |
point 3 中間配当限度額の計算にあたり、従来は「控除」額だけでしたが、改正により「加算」額も加わりました。
| 期中に生じた資本・法定準備金の取崩(減少)による剰余金の増加額に関する事項 |
| 期中に資本・法定準備金の取崩(減少)により剰余金が増加した場合、当該増加額は中間配当限度額の計算にあたり加算されることとなりました(商法293条ノ5第3項5号・6号)。なお、商法289条2項各号並びに商法375条1項各号に定める額は除かれることに注意が必要です(もっとも欠損てん補については次項参照)。 |
| 欠損てん補に充てた額に関する事項 |
| 期中に法定準備金又は資本の使用又は減少により資本の欠損のてん補をした場合、それに充てた額が加算されることとなりました(商規125条2項1号)。 |
<法定準備金の取崩し目的と中間配当限度額の計算>
|
<資本の取崩目的と中間配当限度額の計算>
|
| 期中の組織再編行為による配当限度額の変動に関する事項 |
| 合併又は分割により、消滅会社又は分割会社から承継した留保利益の額が加算されることとなりました(商規125条2項2号・3号)。なお、その際に増加した利益準備金の額については加算額に含めない点に注意が必要です。 |
改正点3 ストック・オプションに係る記載事項の改正
営業報告書において「特に有利な条件で発行した新株予約権」(いわゆるストック・オプション)に係る記載事項が改正されました(商規103条2項)。これは、商法改正を受けて商法施行規則が改正された訳ではなく、単に商法改正とタイミングをあわせて、商法施行規則の整備が図られたものです。
point 1 ストック・オプションに関して個別開示が必要な対象が狭まりました。
特に有利な条件で発行された新株予約権の割当を受けた子会社(*1)の取締役(*2)または監査役(*3)について、改正前は全員の氏名の個別開示が必要でした。これについては煩雑である等の批判があり、実務上の要請を受け、商法施行規則が改正されることとなりました。改正により、計算書類作成会社・子会社の使用人と併せて上位10名以内の者(商規103条2項3号イ)及び計算書類作成会社の取締役等のうち割当株式数が最も少ない者以上の割当てを受けた者(商規103条2項3号ロ)の氏名を開示すれば足りることとなりました。
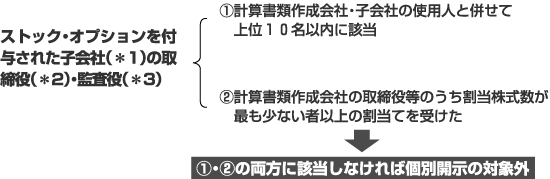
point 2 ストック・オプションに関して類型毎の開示が必要となりました。
計算書類作成会社の使用人、子会社(*1)の取締役(*2)、監査役(*3)、使用人の類型に該当するものについては、その類型毎に付与の総数等の記載が新たに必要となります(商規103条2項4号)。Aさんに何株、Bさんに何株といった個別開示と異なり、計算書類作成会社の使用人というカテゴリーに対して総計で何株、子会社の取締役というカテゴリーに対して総計で何株といった開示になります。これにより、個別開示とは異なった視点から株主が判断することが可能となります。
*1 連結特例規定適用会社については、計算書類作成会社の親会社以外の関係会社を指します。
*2 委員会等設置会社においては執行役が含まれるとともに、監査委員である取締役は除かれます(*3参照)。
*3 委員会等設置会社においては監査委員会を組織する取締役(監査委員)も含みます。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.